
「闇の奥」" Heart of Darkness "J.コンラッド(改訂)~映画「地獄の黙示録」
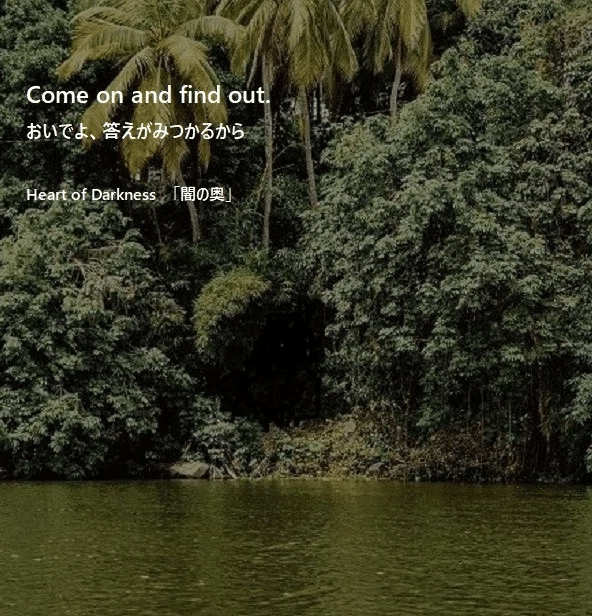
ジョセフ・コンラッド(1857 - 1924)
今回は「モダニズム文学」の簡単な説明と、その先駆の一例として、コンラッド作「闇の奥」を取り上げます。
また、同小説から翻案された映画「地獄の黙示録 "Apocalypse Now"」にも、最後に少し触れておきます。
Apocalypse Now「地獄の黙示録」 監督・脚本 F.F.コッポラ(1979アメリカ)
自分で選んだ悪夢には忠実にあれ。その声は告げていた。
おれは単身、カーツという幽霊と渉り合ってみたかった。
「読みづらさ」で名を残す奇書
「闇の奥」は、ポーランド出身のイギリス作家ジョセフ・コンラッドによる中編小説です。
この作品は、今日でも、「英語で書かれた名作ランキング」上位の常連であり、英語圏の教科書で最も多く使われている作品の一つともされています。
我が国では夏目漱石が傾倒したとされ、いくつかの評論を残しています。
「文学史に残る名作」と評される当作品なのですが、「読みづらさ」においてもたいへん有名です。
原作は文庫版で200ページ程度なのですが、第一章からあまりに混沌としているため、ここで挫折してしまうケースが多いのではないでしょうか。
日本では映画版「地獄の黙示録」がよく知られていますが、こちらも原作同様にきわめて難解な作品です。
その不可解さ故か、「闇の奥」は「謎の書」として今日でも多く語られ、様々な解釈や評論が行われ続けています。

モダニズム文学の先駆
「闇の奥」の作風は、従来の写実主義小説とは全く異なったものでした。
「私の仕事は...書かれた言葉の力によって、読者にものごとを聞かせ 、感じさせることなのです。それはとりわけ、読者にものごとを見させることなのです」
(この序文は、後年にヘミングウェイが賛辞を送ったことで知られています)
ここでの「ものごと」は、文脈から「真理」と置きかえることができるでしょう。
つまり、彼の宣言をざっくりまとめれば、「材料を提示しますので、解釈はそちらで自由に(能動的に)行ってください」ということでしょうか。
彼が世に出た19世紀末は、「分かりやすい写実主義小説」が限界を迎え始めていた時代でした。
この世界や人間を表現するには、従来のリアリズムでは表せない領域があるものとされ、新しい文学的手法が台頭してきたのでした。
これが後に、「世界に対する信頼」を崩壊させた第一次大戦前後に起きた、「モダニズム」と呼ばれる芸術全般における新しい思潮に結実したのでした。
その代表的な作家としては、ジョイス、ウルフ、エリオット、プルーストなどが挙げられます。また、ヘミングウェイら「喪失の世代」の作家たちもここに含めることができます。
コンラッドは、この「モダニズム」文学の先駆といえる作家でした。
世に出された「タイミング」も、この作品の文学史上における重要性が高く評価されている要因と言えるかも知れません。
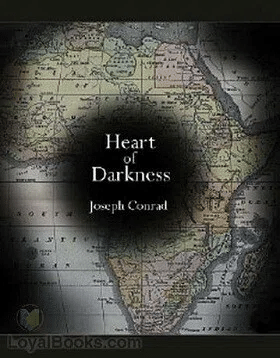
このように、「闇の奥」は従来の写実小説を解体再構築したような作品であるため、読解にはたいへん難儀します。
しかし、この作品には他で味わうことのできない独特の魔力があります。
あくまでも個人的なアプローチではありますが、以下にてこの作品を楽しむためのヒントの提案を試みてみます。
あらすじ
<概要>
主人公は「船乗りマーロウ」、その若い頃の体験が語られます。
舞台は19世紀終盤。
ヨーロッパの列強が植民地政策のもと、権勢を争っていた時代です。
マーロウはポーランドから英国に亡命し、職を求めていました。
そして彼は、ある商社に採用されます。
その商社から派遣された「カーツ」という社員が、コンゴの奥地で大変な量の象牙の獲得で能力を発揮し、出世の道をたどっていました。
象牙は、現地の人々から半ば略奪したものでした。そしてカーツは現地人にあがめられ、彼らを従えて「神の座」に君臨しています。
マーロウの任務とは、重病を患ったカーツを連れ戻すことでした。
長旅の末に対面したカーツは、発狂寸前の状態にありました。
何がカーツを狂わせたのか?彼が奥地で対峙した得体のしれないものとは?
そして、最期に彼が遺したダイング・メッセージ「地獄だ!地獄だ!」は何を告げようとしていたのか?
表層にある展開としては、この「カーツ救出劇」というシンプルなものです。
ただ、取り扱われている根本のテーマとしては「人種差別」や「文明批判」だけではなく、より深く観念的に、
・世界の(人間の)「闇」の「奥の奥」をつき詰めると、そこには何があるのか?
・カーツを狂気に陥れた「それ」とは何なのか?
というものが本流となっていると言えるでしょう。

なぜ読みにくいのか?
「読みにくさ」に戻りますが、この作品を難解にさせている最大の理由は以下にあるのではないでしょうか。
そもそも、根本的な課題が「闇の奥に何があるのか?」としたとき、それを「分かりやすく」描くことなど困難なのでは?
この作品の読解を難しくさせている理由は、他にもいくつかあります。
以後の他の作家たちによるモダニズム作品の多くに見られる要素が多々あるため、挙げておきます。
・語り手のマーロウが、だらだらと話している設定であり、それが体系立てたものでないため、思いつきや飛躍が多い
・そのマーロウが「たまたま耳にした話」や人づてに聞いた話の断片等が多
い
つまり、コラージュのようなかたちで出来事や考えが提示されているのです。また、以下も挙げられます。
・マーロウ自身、自分におきたことを含め、状況が理解できていない~特に肝心なカーツの身に起きたことが具体的に(マーロウに)伝えられていない。
・マーロウ自身、嘘つきのきらいがある。(実際、話の最後で大きな「嘘」をつく)
また、著者は、序盤で自ら宣言しています。
マーロウにとっては、一つの話の意味は核のように話の内側に納まっているのではなく、その外側、つまり、白熱光が生み出す陽炎のように、そう、時おり月の光に妖しく照らされて見えてくる朦朧した月の暈(かさ)にも似た、物語を包む雰囲気のなかにこそあった。
さらに第一章で以下のようにほぼ「ギブアップ」すらしています。
いや、無理だ。自分の存在の忘れ難いその時に覚えた生の感覚というものを、他人に伝えるのは不可能なんだよ。・・私たちは、夢の中で生きるように、孤独なんだよ。
つまり、この作品はまとまりのよい話ではなく、「得体の知れないもの」の謎解きとして読者に提示されているのです。
ですので、作中のヒントをもとに読者がそれぞれの印象・視点から「答」を考える。そんな作品ではないかと思われます。

道具立てとヒント(例・第一章)
内容をすっきりと整理しながら説明できるような小説ではないので、まずは第一章を例にとってヒントとなりそうな材料を挙げておきます。
この作品の「難関」とされる第一章は、約 70ページの長さです。
この章は、いきなり描写が重く、マーロウの独白も支離滅裂な感があるため、読むのをやめたくなります。
その上、この先を読み解くための象徴となる小道具やヒントが伏線として多く登場するのも、読みにくさの要因となっています。「後で読み返せばOK」ぐらいで先に進むのがよいかと思われます。
(第一章)
テームズ河に停泊する船の上で、仲間たち相手のマーロウの昔話が始まります。
その話とは…
幼いころからコンゴ奥地への探検に憧れていたマーロウは、成人になってからその夢を果たすべく、ベルギーの商社より蒸気船の船長の職を得ます。
コンゴの奥地に駐在するエリート社員「カーツ」が病気であるため、彼を連れ戻すということがマーロウの任務でした。
雇用主との面談のため、マーロウはベルギーのブリュッセルにある本社に赴きます。

以下はややランダムになりますが、第一章における作品解釈の上での「ヒント」と思われるところを一部拾ってみます。
・西洋文明の側の道具立てや描写は、概ね「死」や「空っぽ」のイメージで
覆われています。
例えば「骨」
~象牙・・ドミノ駒、ピアノなど
~本社での面接場面。採用検査として、なぜか頭蓋骨の測定が行われる
他にも何かの暗示のような部分
~本社建物を「白い墓」と表している、
~フロアの入口には、編み物をする二人の老婆が座っている。
・叔母の口利きがあったため、マーロウは難なく採用されるものの、それは 格差社会の底辺に属する危険な任務でした。
赤痢やマラリアに罹患するのは日常的なことでした。また、前任者は現地人ともめて殺されてしまったというのです。その後釜としてマーロウが採用されたのでした。
ポーランドからの移民だったマーロウには、当時他にありつけそうな仕事がなかったのでした。
カーツもまた、低い身分からエリートへ成りあがった者でした。
マーロウはどこか西洋文明を鼻で笑っている感があります。
「語りながらのポーズが東洋の座禅を想起させる」、というところも、どこか暗示的です。
そして彼の説明は、終始歯切れが悪く、分かりづらいまま続きます。
・・・そうなんだ、およそ、すぱっと割り切れるような体験ではなかった。それでも、ある種の光を投げかけてくれるように思えたのさ。
マーロウの話は、カーツのことへと移行しながら、先へ進みます。

"Wilderness"~圧倒的な力の源
奥地へ進むにつれて、マーロウが徐々に、密林の魔性に魅入られれていくようすが多く描かれていきます・・・カーツに同化してゆくように。
この作品では、"Wilderness" という言葉が再三使われます。
意味としては荒野、荒地、未開地、密林などですが、ここでは「自然の、圧倒的な力の源」と解釈できるでしょう
この小説を理解する上でのキーワードとも言える"Wilderness"への言及と描写がなされてる箇所をいくつか挙げておきます。
よじれたマングローブの木々は、無力な絶望の果てに身もだえしながらわれわれに襲いかかってくるかに見えた。
そしてその外側では、この狭小な開拓地を囲む寡黙な大密林が、悪か真理か、打ち克ちがたい偉大な存在としてこちらを圧倒してくるんだ。
照りつける陽光に歓喜はなかった。この生命の静寂は安らぎとは似ても似つかぬものだった。おれは、その神秘な静寂がおれの猿芝居をじっと見守っているのを、しばしば感じていた。
森は仮面のように動かず・・・監獄の閉ざされた扉のように重々しいばかりで・・・秘密を内包しながらも、何かを辛抱強く期待して、牢固たる沈黙を守っているかのようだった。
このように、"Wilderness" が作中、ひんぱんに描写されます。
その「自然の、圧倒的な力の源」とはどのようなものなのか、、、
・・・それは一面おぞましいことでもある。と同時に、それは魅惑的でもあって、その魅惑が彼に働きかけてくる。おぞましいものの魅惑・・・

What were we who had strayed in here? Could we handle that dumb thing, or would it handle us? I felt how big, how confoundedly big, was that thing that couldn’t talk, and perhaps was deaf as well. What was in there? I could see a little ivory coming out from there, and I had heard Mr. Kurtz was in there.
こんなところにまぎれこんできたおれたちは、いったい何者なのか?この物言わぬ大自然を、おれたちは手馴づけることができるのか、それとも逆に手馴づけられてしまうのか。物言わぬ、そしておそらくは耳も聞こえぬ、この深淵なるもののとてつもない巨大さを、おれは感じていた。そこにはいったい何があるのか。そこからは象牙が運び出され、またカーツなる男がそこにいるという。
以上は、あくまでも筆者の勝手な解釈です。読者によっては、この作品から全く別の釣果が得られるかも知れません。
例えば、ニーチェの「超人」思想とカーツを関連づける見方も面白いかも知れません。
彼の場合は、あの最後の一歩を踏み出して境界線を踏み越えたのに対し、おれは踏ん切りがつかずに足を引っ込めることを許された。おそらく、すべての違いはそこにあるのだろう。おそらく、すべての叡智、すべての真実、すべての誠実さは、見えない世界への敷居をおれたちが踏み越える、あの、ほんの一瞬に凝縮されるのだろう。
どの抜粋をご覧いただいても分かるように、大変に抽象的な描写が多いので、やはりとっつきにくい作品ではあります。
しかし、人と世界の「闇の奥」はどうなっているのか、
その奥の奥に魅せられてしまい、あげくに狂ってしまったカーツが見てしまったものは何だったのか・・・
読後、脳裏に深い謎が残り、いつまでも消えない作品です。

ジョセフ・コンラッド(1857- 1924~英国、小説家)
ベルディチェフ(ポーランド)生まれ。
4歳の時、父の流刑で北ロシアに行く。7歳で母を11歳で父を失い、16歳の時マルセイユに行き船員となり、1886年英国に帰化する。各国の船に乗り航海しながら小説を書き始める。’94年健康を損ね船員生活をやめ創作に専念する。’95年「オールメイアの阿房宮」を出版し、’97年「ナーシサスの黒人」で批評家に認められ、1912年「運命」で作家的成功を収める。人間心理の底流に迫る倫理的作家であり、20世紀英国小説の開拓者である。
参考・映画「地獄の黙示録」について
”Apocalypse Now”「地獄の黙示録」(1979 アメリカ)
サーフィン好きなヘリ部隊隊長の指揮により、「快適にサーフィンをするため」だけに河口一帯をナパーム弾で焼き払うなど、空疎な戦闘がリアルに描かれています。
設定は、原作から約70年を隔てた1969年東西冷戦~ベトナム戦争に置き換えられており、スペクタクル化はされているものの、根本的なところは原作に忠実につくられていると感じます。
ただ個人的には、原作と比べて西洋文明側の「闇」に描写の重きが置かれているように思いました。

Planet Earth
いいなと思ったら応援しよう!

