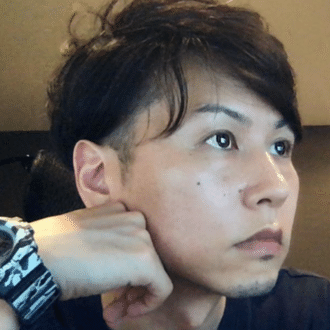人事の原理原則をまなぶ - 報酬とインセンティブ
こんにちは! メルカリのHR部門でマネージャーをしている@_tweeeety_です。
ぼくは、Software Engineer / Engineering Managerがキャリアの大半だったところから、人事へ興味をもちHRへジョブチェンジをしました。そのため人事経験が浅いです。(「なぜ人事へ興味を持ったの?」という話しはここでは割愛します。気になったら直接きいてください)
そこで、人事の原理原則を学ぶために「Every HR Academy」という講座を受講しました。このnoteでは、今年のふりかえりも兼ねて本講座を通しての人事領域に対する自分なりの学びや備忘録をまとめます。
このnoteのテーマは「報酬とインセンティブ」です。
また、本記事はジンジニア アドベントカレンダー 21日目の記事になります。
前回は「人事の原理原則をまなぶ - 人材開発とキャリアマネジメント」でした。
(参考: 2023年 ジンジニア アドベントカレンダー)
はじめに
Every HR Academyは全8回の講座で、内6回がテーマのあるInput & Discussionの形式になっています。
- Day1: これからのHR
- Day2: 採用&選抜
- Day3: パフォーマンスマネジメントと評価
- Day4: ピープル・アナリティクス
- Day5: 人材開発・キャリアマネジメント
- Day6: 報酬制度・インセンティブ(←このnote)
- Day7: 特別公演
- Day8: アサインメント発表会 & Find your why
このnoteは各dayごとに連載予定です。1dayごとに「内容」「学び」「学びを活かすには?」を書いて自分への備忘録noteにしていきます。講座が気になる方への参考にもなれば幸いです。また、文末には各回のリンクも貼る予定です。
では本題へ。
内容サマリ
6回目の講座は「報酬とインセンティブ」でした。
セクションは以下の3つ。
Day6 アジェンダ:
- 1. 人事制度と報酬制度
- 2. 報酬制度の原則
- 3. インセンティブの原則
「人事制度と報酬制度」は、報酬の種類や報酬に対する考え方についてのセクションでした。手当や福利厚生などについても触れるセクションでした。「報酬制度の原則」では、報酬制度のポリシーをはじめとする「報酬制度の作り方」などを扱いました。「インセンティブの原則」では、インセンティブが従業員をモチベートする原理原則について学びました。「妥当な報酬」ということで、もちろん報酬が低くて良いことはないのですが、確実・高すぎも良いわけではないという点が意外な学びでした。
学び
講義内で個人的に気になった学びと備忘録です。(講義の3セクションから気になった点だけ抜き出してるので順不同です)
定期的にふりかえりたい学び:
- 1. 「報酬とは何か」「報酬はどんなものがあるのか」
- 2. 報酬制度の作り方 - Pay for performance
- 3. インセンティブの成功と失敗
学び1. 「報酬とは何か」「報酬はどんなものがあるのか」
「報酬」と聞いて、会社員であれば思い浮かぶのは賃金だと思います。魅力的な報酬であれば従業員を組織に惹きつけて定着させることができます。確定申告をする方であれば税法の面で「収入」を考えたことはあると思います。いくつかの側面がある「報酬」ですが、このセクションのおかげで人事の側面から「報酬」を考えなおす良い機会になりました。
まず、ひろく「報酬」を調べてみました。おもに3つに分かれるそうです。
「報酬」の意味は文脈によって異なる:
① 人事制度上の報酬:
報酬は「労働の対価」とみなす
② 社会保険上の報酬:
社会保険料を計算するためのもの
③ 所得税上の報酬:
雇用契約の有無で「給与所得」と「報酬」に区別
参考: 日本の人事部 > 報酬
会社員や確定申告の側面で触れてきた方は②や③のイメージがメインだったのではないでしょうか。このnoteでは①の「人事制度上の報酬」のほうにフォーカスします。「人事制度上の報酬」は、別名「総合的報酬(トータル・リワード/Total Reward)」ということもあるようです。「総合的報酬(トータル・リワード/Total Reward)」で調べた内容を図にしてまとめてみます。図で表すとこんな感じでしょうか。

この図は以下のwebを参考にさせて頂きました。
社員をモチベートすると報酬という意味だと確かにお金だけではありません。「やりがい」「自己実現感」などは仕事だから得られることも多いと思います。
こういったことをまた違う視点で分類された方がいらっしゃいます。サイバーエージェント曽山さんです。曽山さん提唱の金銭/非金銭報酬 x 安心/挑戦のマトリックスを参考につくられた図があり、これも「報酬とはどんなものがあるか」の参考になりました。引用させていただきます。

報酬・インセンティブまわりは永遠に深ぼれそうなテーマですね。
学び2. 報酬制度を作るときのポイント
ここでは報酬制度をつくるときに意識するポイントで気になったものを2つほど取り上げます。まずは報酬制度を作るプロセスの一連はこんな感じというものをサラっと流します。

この画像は以下のサイトを参考に作成しました。
プロセスに記載した「point」2つが触れたい箇所です。
「point」1つめは、報酬を決めるときに大事な「報酬ポリシー」です。報酬を決めるといっても、単に基本給額を決める、テーブルを決めるというのはもっとずっと後の話しです。人事制度全般に言えることですが「ポリシー」を定めること、いわば、どうでありたいかを言語化することが重要です。「報酬ポリシー」は「何に対して報酬を与えるのか?」を明確に定義することといえます。そのポリシーに対して報酬や手当を決めていくことになります。
たとえば、メルカリでは「ダウンサイドリスクを会社がサポートする」という方針があります。メルカリ内のいくつかの制度はこの方針に則って設定されています。
また、もう少し外観の大枠でいえば「年功序列型」「成果型」という考え方もあります。会社として、何にお金を支払うかのポリシーやこういった大枠を決めることで報酬を決定していきます。大枠に関しては次の参考サイトや貼った表をご参照ください。


「point」2つめは、報酬水準にかかわる「公平性」です。公平性には「内的公平性」と「外的公平性」があります。

「内的公平性」は、社内の職種や部門間の公平性です。特徴としては、相対評価(どんな職種が利益を生んでいるかなど)から報酬を決めることになり「その職種への期待」というメッセージにもなります。
対して「外的公平性」は、ご想像の通りだと思いますが、マーケットとの相対評価です。これは「他社がその仕事にいくら支払っているか?」を参考に報酬を決めることです。メッセージとしては「採用に勝ちたい」「辞めないでほしい」といった感じになります。
noteを書くにあたって「報酬制度」をwebで調べていたのですが情報量が半端ないです。評価・報酬制度まわりは人事のコアといわれる所以がわかります。よくもわるくも従業員の心にも生活にも影響をあたえる機能なだけに、さまざまな原則、理論、知識、ノウハウが必要なことがわかりました。機会があったら担当してみたいHR機能の1つです。
学び3. インセンティブの成功と失敗
気になった最後のポイントは「報酬」のなかでも「インセンティブ」です。講義中に「あるとちょっと頑張れるインセンティブはなにか」という問いがありました。数人とディスカッションしましたが「金銭」のほかには「はたらきやすさ」「一緒にはたらく人」「経験やスキル」「承認欲求」などさまざまでした。
インセンティブの原理原則はありつつも、ここではどんなときにインセンティブが「成功するか(従業員がモチベートされるか」「失敗するか」という点が面白かったので触れて終わりにしたいと思います。
インセンティブが成功するとき(モチベートされるとき):
- パフォーマンスや成果と偶発的な関係性(オペラント条件付け、スキナー箱)
- 行動 -> 報酬という時系列がある(ソーンダイクの問題箱)
- 個人の努力が成果に結びついている
- 現実的な目標と妥当な報酬(too muchもtoo lessもやる気なくす)
- 行動のタイミングに紐づいて報酬がもらえる(今日やれば明日もらえる。「10年後です」はダメ)
「オペラント条件付け、スキナー箱」「ソーンダイクの問題箱」については参考サイトをご参照ください。
インセンティブが失敗するとき:
- 実行能力の欠如(測定不可能ことのインセンティブ)
- 成果のコントロール欠如
- 努力<>パフォーマンス<>結果が関連しない
- パフォーマンス測定が不正確
- 報酬が妥当でない(too muchな負担、too lessな報酬)
- パフォーマンスが異なっても、報酬が変わらない
「行動してパフォーマンスが出たことへ払われる仕組みだと良い」というのはわかりますが、従業員の納得感をえながら設計・運用するのはやっぱり難しそうです。だからこそ、先人の知恵(原理原則)やポリシーという軸が重要になる、というのは納得です。
学びを活かすには?
報酬制度とインセンティブに関しては、金銭的報酬であれば評価・報酬まわりチーム以外で活かすことはなかなか難しそうですが、非金銭的報酬であれば他の人事制度や組織の役職者としても応用できることはありそうです。
たとえば「やりがい」「面白さ」といった「仕事内容」や、「人間関係」「はたらきやすさ」といった「労働環境」であれば提供できるものもあるのではないでしょうか。
人事でも現場側でも「最高のパフォーマンスのため」に「人事的な報酬」がつくれれば、結果として自分のモチベーション向上にも繋がるのでこれを機になにか考えていきたいと思いました。
おわりに
報酬制度とインセンティブは、人事機能のなかでもとりわけ深さ?(難しさ?)を感じる会でした。また、この機能が会社ではたらくことを回している心臓部といっても過言ではないでしょう。しかし、単に従業員のいち個人として過ごしていると評価や報酬に不満を持つこともあるかもしれません。が、こういった難題を扱っているチームがあることを知ると、どんな結果にせよもうすこし違った見方で捉えることもできそうです。
ということで、あらためて今後も人事の学習をつづけていこうと思いました。(なんとか締めた感…)
■ 連載について
このnoteは連載です。12/18から数日にかけて一連をリンクしていきますので良かったら読んでみてくださいませ。
■ 謝辞
このnoteを書くにあたり、内容や画像の引用については事前にEvery HR Academyさまの許可を頂いております。快く許可をくださった主催の松澤さん、ありがとうございます。人事の原理原則が体系的に学べる数少ない講座です。気になる方は、受講を検討してみてはいかがでしょうか!
いいなと思ったら応援しよう!