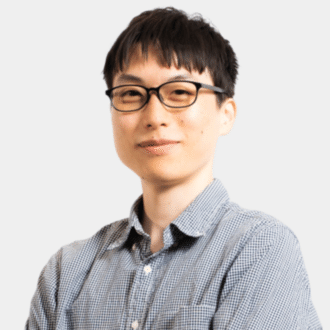「同一労働」と判定するのはとても難しいのです。
「同一労働同一賃金」という発想について、ふと考えた。
詳細な知識のないままに印象論で語っているところもあるかもしれないが、とりあえず考えたことを書いておこうと思う。
この発想が生まれたのはおそらく、正規・非正規間や男女間での労働格差を是正するためだろう。
その契約形態や男女の性差によって賃金差別を受けるのは不当であり、同一の労働を行った労働者には、同一の賃金が支払われるべきだ、とする考え方だと現状の私は理解している。
このことについては私も同意し、言わんとする理想な状態には共感しつつも、これを実現するのは結構難しそうだなぁと思ってしまう。
というのも、そもそも「同一労働」とは一体何を意味しているのだろう?
産業革命が起こった18世紀の半ばにおいて、労働者の多くは工場労働における単純作業に従事していた。
そこで各労働者が行っていた労働はほとんど同一のものだっただろう。
その意味で「同一労働」は成立していたと考えられる。
ところが、現代社会においてはそのように均質に、同一に扱えるような労働はかなり少なくなってきているような気がする(もちろん業界によると思う)。
工場労働のような世界ではまだ上記の説明も可能かもしれないが、そうではない領域の労働について、どのように「同一労働」を規定すればいいのか、私には知識がないからわからない。
加えて、そもそも全ての人間はそれぞれ異なる性質を持っており、共同で何か1つの仕事をやり遂げる場合には、彼らがそれぞれ異なる作業を分業して行った方が、集団としてより良い成果を出せるはずだ。
そのように考えると、この現代社会において「同一労働」を元に賃金を決定するのはとても難しいことなのではないか、と思うのである。
いいなと思ったら応援しよう!