
占領下の抵抗 / 志賀直哉のエッセイ『国語問題』をめぐって
はじめに
志賀直哉の随筆はどれも面白い。その中には「フランス語を日本の国語にする」と主張した『国語問題』 [1]も含まれています。これがなんともいい。含蓄に富む文章です。
「フランス語を日本の国語にする」とだけ聞いた時と『国語問題』を通読した後とでは、印象は全く違います。そこには志賀直哉独特のアイロニーがある (ⅰ)。
しかしこれは単なる皮肉(cynicism)ではありません。志賀はフランス語を日本の国語にする事を本気で考えていたと思います。
それは11年後に座談会(『志賀氏を囲んでの芸術夜話』 [2])で、あれは本気だったと改めて強調していることからも窺われます。
『国語問題』は敗戦後まもない1946年
今ほど厳しい時代を日本はかつて経験したことがない。いろいろな問題が怒濤のように後から後から寄せてくる。茫然自失の虚脱状態になるのも無理はない。
というような時に、戦前・戦中に飛び交った生硬な言葉への反省から国語の改革の研究会が出来、志賀もその発起人となるという背景のもとで書かれています。
志賀直哉はその中で
「日本の国語が如何に不完全」であるかを「四〇年近い自身の文筆生活」で痛感し
その改革の必要を感じながらも国語の改革に対しては悲観的であるとし
六〇年前に森有礼が英語を国語に採用しようとした事をこの戦中、度々想起した。
と言い、その事の先見性を説きながら、いっそのこと
「世界中で一番いい言語、美しい言語」を日本の国語にする方が日本語を改革するよりも「確実であり、徹底的であり、懸命である」とし
それにはフランス語がふさわしいというのです。
このように纏めてしまうと、自国文化を卑下し、西欧文化を無闇に美化するような愚かな考えに映るだろうと思います。
しかし前述したように、私にはとても含蓄のあるものに思え、初めて読んだ時、密かに興奮したのを覚えています。
この随筆は簡潔で、行間をどう読むかで印象が異なってくると思うので、なかなか実証的に語るのは難しいのですが、私がこれをどのように捉えたのか思い起こし、後に得た知見も交えながら以下に詳しく論じてみます。 [1]
志賀の主張の背景と意義
まず敗戦を受け入れた日本は連合国総司令部(G H Q)の統治下に入りました。
これは連合国と云いながら、実質はアメリカの支配でした。その事はこの随筆が書かれた時には既に明白でした。だから本気で西欧の言語を国語とするのであれば、G H Q の力を借りながら英語を選択するのがもっとも近道で、実現の可能性が高かった事は明らかです。
しかも志賀は
英語を国語に採用しようとした
森有礼の主張を引いて論じているのですから、ますます英語とするのが順当です。
なのに「もっともいい」とか「美しい」とか言ってフランス語を選択するのは何ともおかしい。
このことが志賀は本気ではなく、ただ皮肉を言っただけだとする見解に一定の根拠を与えています。しかし私はそうは思いません。
確かにそこには志賀独特のアイロニーがあります。
ですが同時にアメリカの支配に対する痛烈な批判と抵抗があると、私は思うのです。 [1]
敗戦後の日本で英語が国語となるということは、アメリカにその気があれば十分に可能だったのではないかと思います。戦争に敗れて他国の支配を受けるとはそういう事です。
とはいえ、アメリカは国語の改革は進めつつも、そこにおいて英語を導入する意思はなかったようです。
「国語ローマ字化の研究 改訂版ー占領下日本の国内的・国際的要因こ解明ー」 [3]の中で茅島篤は、アメリカ側に英語重視の考えがなかったかを丹念に調査し
アメリカでは占領前には英語教育を重視しようとした戦略局の考えもあったが、連合国の占領下「ポツダム宣言」に沿った改革のもと、それを強く推進することもなかった。連合国として方針を出すこともなく、日本側に大きく委ねていた。
[3]
と結論づけています。
ポツダム宣言に基づき間接統治を前提としたG H Q には、国語の変革については慎重な姿勢があったようです。アメリカによる国語の英語化は差し迫ったものではなかった。(xiii)
しかし同著に即して書くと
日本の降伏文書調印式の翌日の1945年9月3日にG H Q は
自治体の名称、駅や主要道路標識は
英語ヲ以テ掲ゲラレルコトヲ確保スルモノトス。名称ノ英語ヘノ転記ハ、修正『ヘボン』式(ローマ字)二依ルベシ
[3]
との指令を早くも出しています。
そして日本語のローマ字化への動きも始まります。同月30日に来日した国語ローマ字化の中心人物 R・Kホールは、同年11月10日に文部省教科書局の有村光次郎に国字ローマ字化を示唆、同月12日にホールは国語改革担当官に任命され、それに同調するかのように、同日読売報知新聞には社説「漢字を廃止せよ」(「ローマ字採用論」)が出ています。
そして1946年3月30日にG H Q 最高司令官・ダグラス・マッカーサーに提出された米国対日教育使節団の報告書には
漢字の全廃と
ある種のローマ字表現形式を一般に普及させること
[3]
が提言されています。(xxvii)
これら日本語のローマ字化の動きは英語の公用語化と表裏一体に見えます。
使節団報告書の中にはローマ字化の利点として
・諸外国の文学研究をも容易にするであろう
・国際理解を深めることにじゅうぶん役立つであろう
・知識と思想の伝播に、国境を超えて、おおきく貢献することになるだろう
[3]
とあります。これらの利点は英語の導入についての方が、さらによく当てはまると思います。
街に英語の表示が並び、英語を話すアメリカ人が闊歩する中で進められるローマ字化の動きを見て、当時の日本国民の中に国語が英語になる事を本気で危惧した人々がいたとしてもおかしくありません。
特に国語の改革を唱えたような知識人層の多くはそう考えたのではないかと思います。(xx)
国語の改革を唱えることは、一見するとそれまでの日本社会・文化を否定し、新しい社会・文化の創造を目指しているかのようですが、そこにはアメリカの支配を受け入れながらも、ぎりぎりのところで英語の公用語化を塞ぎ、日本語と日本文化を守る抵抗運動という側面があったのではないかと思います。(xxx)
ローマ字化と結びつく事によって分かり難くなっていますが、漢字廃止論は賀茂真淵の漢字批判(『國意考』 [4])や本居宣長の漢文の否定(『玉勝間』 [5])に淵源する国学的理想と云う側面があり、ナショナリズムが基にあります。
国語改革派の運動はこのナショナリズムと通底していたと、私は見ています。
これは全面的ローマ字化もしくはカナ文字化を主張した論者(土岐善麿など)から、最終的には漢字の制限・簡略化を目指した論者(山本有三など)までに共通したものだったのではないかと思います(ⅱ) 。
志賀直哉の主張はこういったナショナリズムとは異質です。しかしやはり抵抗の一つだと思います。
敗戦が迫り来る中で、敗戦国が外国語を国語として受け入れることは避けられないと志賀は真剣に考えたのだと思います。
それが
六〇年前に森有礼が英語を国語に採用しようとした事をこの戦中、度々想起した。
という事の意味だと思います。(xxxiii)
薩英戦争で英国に完膚なきまでに敗れた薩摩の森有礼を、志賀が自身と重ねたとしても不思議はありません。
志賀にはもはや外国語が日本の国語になる事は避けられないものと映った。それが国語の改革に悲観的になった理由の一つです。
もちろんそれだけが理由ではないのですが(後述します)、志賀にとって米国支配下での国語の改革が、絵空事に思えたとしても納得がいきます。
そうであれば国語の改革(そこには漢字の廃止とローマ字化も視野に入る)という不徹底な事をするより、広域で使われている国際語たるフランス語を導入する事で英語に対抗した方が良いと、志賀は考えたのだと思います。
「世界中で一番いい言語、美しい言語」はフランス語だなどと言うのも、暗に英語は「世界中で一番いい言語、美しい言語」ではないと言っているのだと思います。そう考えると実に辛辣な主張です。
しかも
森有礼の時代には実現困難であったろうが、いまならば実現できない事ではない。
というのは、G H Q の支配下であればそれが可能だという意味にも取れる。それを英語ではなくフランス語でやれという訳です。なんとも痛烈です 。が、それは殆ど実現する可能性のない事に思えます。志賀もおそらくそう思ったでしょう。
しかし形式的なものであっても連合国にはフランスが含まれていました。
幕末、アメリカが先んじて日本の最恵国としての条約を結んだ後に、イギリスとフランスがアメリカよりも有利な条約を日本と結ぶ事を画策したように、今回もフランスが動いてくれないかと、その少ない可能性にかける思いも志賀にはあったのだと思います。
そのような機縁が少しでも見えれば、自分の作家としての名声を利用して、国語改革の研究会の発起人として出来うる限りの力を注ぐ覚悟が志賀にはあったのだと思います。それが、11年後に座談会 (『志賀氏を囲んでの芸術夜話』 [2])で、あれは本気だったと語ったことの真意だと思います(ⅲ) 。
そして『国語問題』を、本気でありかつ可能性の薄いことも心得た人の文章として読むと、辛辣であるとともに、とてもユーモラスにも思えてきます。
例えば検閲される事を前提で、検閲官の気持ちで志賀のこの文章を読むとどうでしょうか。(当時の日本の出版物が G H Q の検閲を受けていた事は江藤淳が『閉ざされた言語空間』 [6]で詳しく追っていますが、当時の作家にとっては自明のことであったと思われます。)
改めて論旨を簡単に追ってみます。
① 日本は今混乱しているが、それでも国語の問題は重要である。
② 日本の国語ほど不便で不完全なものはない。40年近い分筆活動でそれを痛いほど感じてきた。
③ かといって仮名書きとかローマ字書きが普及しないのは致命的な欠陥があるとしか思えない。
④ 60年前に森有礼が英語を国語に採用しようとした事を度々思い起こした。
⑤ 英語を国語に採用していたら、多くの利益があっただろう。
⑥ 国語の改革には悲観的である。
⑦ いっそのこと思い切って世界中で一番いい言語、美しい言語を採用してはどうか?
⑧ それにはフランス語がいいと思う。
⑦まで読み進んだ時、これは「英語を採用すべき」と来るのだと検閲官は思ったに違いありません。それが次に⑧と来る。
しかもその後で、フランス語をよく分かっているわけではないが、フランス語が一番良さそうな気がするなどとはぐらかす。
検閲官は苦笑いするしかなかった事でしょう。論旨の流れをこのように組んだのは、志賀の悪戯だろうと思います。 [1](xxiv)
国語の不完全性と外国語導入をめぐって
しかし、それにしても疑問は残ります。それはなぜ
日本の国語が不完全であると四十年も日本語で文筆活動を行なった末に思った。
のか?という事です。
アメリカへの対抗としてフランス語の採用を主張するだけなら、フランス語が世界中で一番いい、美しい言語だと述べるだけでも良いし、その主張を補完するために日本語の不完全さを唱えるにしても、ただそう述べるだけで十分だと思います。
日本語は不完全だという主張はこれ以前にもあり(森有礼もその一人)、志賀がそれを主張すれば、暗にそれらの考えに同意したと捉えられるだけで特に説明はいらない。
志賀直哉の長年にわたる文筆活動も自明のことで、簡潔な文章を得意とする志賀がわざわざ「日本の国語が如何に不完全か」ということを「四〇年も日本語で文筆活動を行なった末に」痛感したとしつこく述べているのはとても大袈裟だと思います [1]。
そして作家らしくよく纏まった『国語問題』と比べ、昭和22年と23年の対談ではもっと言いたい放題です。
「文章の構成だけでも、フランス語にするといふことはどうかね。」
と言い放ったり
「不完全極まる国語だと思います。哲学なんかの言葉も分からないから読む気がしない。出てくる言葉の意味がわからない。」
と憤ったりしています。
両対談は論旨がはっきりしない部分もあり、全てをそのまま受け取って良いのか分かりませんが、しかし日本語に不満があることは強く伝わってきます。
やはり志賀は、日本の国語が不完全であると本気で考えていたのでしょう。
ここで重要なのは、志賀が『国語問題』のなかで不完全だと言っているのが、終始「日本の国語」であるという事です。おそらくこれは日本語全般のことではないのだと思います(ⅳ) 。
日本語を母語とする志賀は、文筆活動を行う中で、母国語としての日本の国語に限界を感じていたのだと思います。 [1]
遡れば明治以降の国語(標準語)(xxxv)は、西洋列強の脅威の下にその影響を内面化し、改革された日本語です。
明治の国語国字改良時には
欧米語採用論や「ローマ字論、カナ論、新字論など」さまざまな事が議論され、それは日清戦争後に「文字改良論」「仮名遣改訂、文体改良、言文一致、標準語、方言の問題」の議論へと移っていきました。
これは戦後に議論された項目をほぼ網羅しています。
これらの議論は標準語の制定を望む国家の後押しの下に行われました。
それと同時に様々な作家が言文一致体を作品の中で試していきます。(xxxvi)
すでに多くの言文一致体が試され、国語国字の改良の議論がなりを潜めた明治末年に創作を始めた志賀の文体は、それまでの言文一致体を踏まえてさらに磨き上げた一つの完成品であると云った趣があります。
菊池寛はその簡潔な文体に率直に驚き、賛美の言葉を寄せています。(『志賀直哉氏の作品』 [8])
さて、標準語(国語)は、単純化できない部分もありますが、それでも基本的には志賀の育った東京の山手の言葉を元にしています。そして山手の言葉は標準語の元となっただけに、反作用として標準語化の影響を強く受けたと云います。(『東京語−その成立と展開』田中章夫 [9])
志賀は当時の日本において、標準語(国語)に近い言葉を話し考えることができた数少ない一群に属していたと云っていいと思います。15年間暮らした奈良でも娘たちが奈良弁を話すなか、志賀は東京弁で通したそうです。(『志賀直哉』阿川弘之 [10])
これは移り住んだ関西を愛し、『卍』 [11]のような関西の口語の小説を書いた谷崎潤一郎とは随分と違っています。このように標準語(国語)に近い言葉で育ち、その言葉を意識的に守り通した事と志賀の鋭敏な言文一致体は、おそらく無縁ではないでしょう。
志賀が最初に日本語への違和感を示したとされる『五月蝿』 [12](昭和20年11月)では
「五月の蝿と書いてうるさいと読ますんでせう。考えるとインチキなもんだね」
と言う息子の言葉を挙げ、その他にもこまごまとした日本語の不合理な点を挙げています [12]。
しかし簡潔な言文一致体を完成した志賀のような作家が、今更このような事で日本語を不完全というのはおかしい。国語改革の議論をきっかけに『五月蝿』の中に出てくるような事にも、より目が行くようになった事は確かでしょう。ですが『国語問題』で具体的な話を避けた志賀が感じた日本語の不完全さは、もっと根本的なことだったのではないでしょうか。
志賀がどこまでそれを意識的に分析できていたかは分かりませんが、志賀は日本の国語に息苦しさを感じていたのではないか。
それは一つには日本語の多様性によると思います。当時、志賀の育った東京の山手でも多くの人はどこかしらの方言が混ざる。志賀の両親も東京の出身ではありません。志賀を育んだ言葉も本当は「東京の山手の言葉」と簡単には括れません。(『志賀直哉』阿川弘之[10])志賀は奈良や尾道(広島)にも暮らし、方言の多様性はよく分かって思いた筈です。それらの表現を包括的に取り込める言葉などはありません。これは今よりも志賀の時代にはより顕著でした。
しかも志賀の時代、古語の文学・和歌の伝統・漢詩の素養なども根強くありました。ますます出来たばかりの標準語(国語)では対応が難しくなります。
さらに国語には明治以降、多くの西欧の言葉が短期間に取り入れられています。これらの言葉はたとえ学術的な言葉であっても、原語の中では母語と結びつく豊富なイメージをも持ちますが、日本語の中ではそうはいきません。しかもそのような言葉の多くは漢字で表記されます。
漢字の表記は、漢語(中国語)の中では広いイメージのつながりを持つとしても、日本語にとってはもともと外国語で、疎遠なものでした。過去に漢語を日本語に取り入れた経験は、明治の西欧語受容と類似性があり、漢語受容の時の手法を真似て、西欧の言葉を漢字表記に翻訳して日本語に取り入れた訳です。それは日本の国語を豊かにしつつも、原語が持つイメージを切れ切れにしてしまった。
このような外来語の受容という意味でも、標準語は改革された言語でした。
このように諸方言や伝統との乖離と外来語の導入が急激であったことが、日本の国語を不完全なものにしてしまった。これは日本語の改革の結果です。
これはある意味避けられなかった事ですが、その不完全さを一番に感じていたのは、長年にわたって言文一致体の完成に尽くした志賀直哉のような人ではないかと思います。
そんな改革された日本語をさらに改革することに、志賀はどうしても賛成できなかったのだと思います。(これが国語の改革に悲観的だった二つ目の理由です。)
やれることはやって来たという自負もあったかもしれませんし、単に疲れてしまったのかもしれません。諸方言に取り囲まれ、文学者として古典にも触れつつ、東京の言葉を守りながら外来語溢れる国語で文学を書く事に。
分からないでもありません。言葉は本来国策としてではなく、自然に混じり合い変化するものです。その中から純粋な日本語を抽出するような志賀の作業は、無理のあることだったのかもしれません。(xxix)
ではフランス語を導入すれば日本の国語は完全なものになるのでしょうか?
世界中で一番いい言語、美しい言語
はフランス語であるという表現から、志賀がそう思っていたと考える向きもあるでしょう。しかし上述したように、この表現は米国の支配と英語の導入に対抗するためのものであって、本気でそのように思っていた訳ではないと思います。
志賀は『国語問題』の中で
「フランス語を具体的にわかっている訳ではない」がさまざまな理由から「フランス語が一番良さそうな気がする」と
なんとも無責任な事を言っています 。
こういった発言を真正面から捉えるべきではないでしょう。これも志賀独特のアイロニーなのだと思います。
博識な志賀は、おそらくフランス語について論じるだけの知識は十分に持っていた。しかし志賀の主張は、そのような知識とはなんら関係がないので、わざと無責任な事を言ったのだと思います。
なぜならフランス語を日本に導入すべきなのはその良さや美しさにあるのではなく、英語に対抗できる国際語であることにのみあるからです(ⅴ) 。
ではフランス語を日本に導入したらどうなると志賀は考えていたのでしょうか?
志賀は言います。60年前に森有礼のいう通りに英語を日本に導入していたなら
古い国語を知らず、外国語の意識なしに英語を話し、英文を書いていたろう。英語辞書にない日本語独特の言葉も沢山出来ていたろうし、万葉集も源氏物語もその言葉によって今より遥か多くの人々に読まれていたろうという事ことまでが考えられる。
こうして生まれる日本語の語彙と表現を取り入れた西欧語は、外来語を取り入れた日本の国語とは逆向きの混成言語であり、完全なものとはとても云えません。
国際的に広がった言語がさまざまな語彙を取り入れ豊かになったり、多くの人が使いやすいように変化したりすることが仮にあったとしても、それは完全なものになるという訳ではないでしょう。
国際語が発達する過程は終わりがなく、それは常に揺れ動く不完全なものであるという宿命を負っています。それはエスペラントのような人工国際語であっても変わりません。
現代言語学の祖ソシュールの『一般言語学講義』では
言語は、あるいは音を、あるいは意味をおそう・ありとあらゆる作因の影響下に, 変遷・いや進化することになる.この進化は宿命的である.それに逆らった言語の例は一つもない.ある時間の終わりには, 必ず目立ったずれが認められるのである
と記述された後、人工言語について
この原理は人工語についてさえ実証されるにちがいない.それほどそれは真である. それを案出したものは, それが世に行なわれぬうちは, それを意のまのままに扱う事ができる;しかしそれが使命を果たし, 万人のものとなるや, 統制が効かなくなる. エスペラントはこの試みである;もしそれが成功したとして, 宿命的法則を免れるであろうか?第一期を過ぎれば, この言語とて必ずや記号的生活に入るに違いない;それは反省的創造の法則とは似ても似つかぬものによって,伝承されるであろう; そうなってはもう引き返すよしもない.子々孫々がそのまま受けとるべき万代不易の言語を制作すると豪語する人間は, あひるの卵をかえしたにわとりのたぐいである:かれの案出した言語は,全ての言語を押しやる潮流に, いやおうなしに引きさらわれるであろう
と書かれています。
これはどんなエスペラント批判よりも根本的な批判であり、言語の本質を物語っています。完全な言語という観念が、そもそも誤謬なのです。(xxii)
エスペラントの熱烈な支持者であった白樺派の盟友・武者小路実篤や有島生馬を通して、志賀はエスペラントについても知悉していたと思われます。
ザメンホフが様々な言語の比較と分析から生み出したエスペラントは国際的な言語の実態についての知識と不可分のものです。外国語を日本に導入した場合についての志賀の考察は、世界の植民地における外国語の導入とその現状についての知識に基づいているのだと思います。しかし志賀はフランス語について語った時と同様、その知識を披瀝する事はしません。
ただ
朝鮮語を日本語に切り替えた時はどうしたのだろう。
と匂わせるだけです(ⅶ) 。
外国語が公的に導入された地域で、現地の母語が必ずしも完全に葬り去られるわけではありません。それは併存しつつ混成もする。そのような場合に母語は外国語の抑圧の下で、アイデンティティの拠り所として強化される可能性も考えられます。(ⅷ)
日本語を更に人工的に改革してより不完全なものにしてしまうよりも、日本語を取り入れた新たなフランス語と母語として強化された日本語という二重構造の方が志賀にはまだ良いように思えたのだと思います。(ⅸ) (xxxiv)
『国語問題』を
日本人の血を信頼し、(中略)この問題を純粋に未来の日本ために考えなくてはならぬ。
と志賀は締めくくっています(ⅹ) 。
しかしこのようなことは日本ではかつて起きた事がない事態です。外国の圧力に対し日本が国語や文化の改革のみで済んで来たことは、実に稀な事です。その事がさまざまな歪みを生んできたとしても、とても恵まれた環境です。(xxxvii)
志賀の考えは、植民地諸国の現状を外から眺めた身勝手な発想であると云わざるを得ません。その点で志賀の考えは、やはり愚かなものであると思います。
志賀直哉の眼差(芥川龍之介との比較)
ただもう一つ論じておきたい事があります。それは日本文化に対する志賀の認識についてです。それは志賀自身の内部へ向けられた眼差でもあり、それが志賀をこれまで述べてきた考えへと導いたと思うからです。それは随筆ではなく、本業の小説の中にのみ現れています。
志賀の短編『濁った頭』 [14](1911年)は
「精神的にも肉体的にも延び延びとした子供」だった若者が、キリスト教に入信した事により体を動かす事に興味を失って徐々に鬱屈して行き、最後は駆け落ちした相手を殺して「癲狂院」(精神病院)に2年入っていた
そんな人物の語りです。主人公・津田は長年、キリスト教の「肉慾の禁止」による自身の「性欲の圧迫」について悩んでいます。それ自体はありふれた事です。しかし彼の悩み方は異様です。
「肉慾の禁止」を「うつつ攻めの拷問」と云い、「独りでする恥ずかしい行」を止めようと「ナイフを腿に突たてようと」し「マッチを擦って腿へのせた事も二三度ではない」と云います。自分を「特別に強い肉慾を持って生まれた不具の人間」ではないかと考えたりもします。
そして、ここで語られる肉慾には、のちに駆け落ちするお夏と最初に関係を結ぶときに
女との関係では曾つて、こうした事はなかったけれども、基督教に接する以前に男同士の恋で度々経験した事だった。
と言っている事から分かるように同性愛(xix)が含まれています。しかもかなり早い時期に男同士でそう云う関係を結ぶ事がわりと普通だった事を伺わせます。そんな津田は成り行きのままにお夏と駆け落ちし、まるで何かに取り憑かれたかのようにお夏を殺してしまいます。
ここには現在の多くの日本人には想像するのが難しい失われた日本人の心性が、残酷な形で表れていると思います。
自身もキリスト教へ入信した経験のある志賀が、キリスト教(西欧文化)と日本文化との邂逅をこのような破綻した人物に託して描いた事は重要です。そこには芥川龍之介が『神神の微笑』 [15](1922年)の中で示したような日本の文化と歴史への信頼がありません。
『神神の微笑』の中では、日本の精霊と思しき老人が宣教師オルガンティノにこう語っています。
「泥烏須自身も、この国の土人に変わるでしょう。支那や印度も変わったのです。西洋も変わらなければなりません。」
日本は外来の文化を変容して何でも日本文化の中に取り入れてしまうという訳です。これは何を取り入れても日本の同一性は保たれ揺らぐ事はないという一種の楽観論を必然的に孕んでいます。
このような認識は、それを肯定的に捉えるにせよ否定的に見るにせよ、その後も日本で繰り返されます。(山本七平など)(xxviii) ( xxxi)
しかし詳しくは触れませんが、芥川がここで描いたものは非常に細緻であり、他を寄せ付けません。しかも芥川は、4年前の代表作『蜘蛛の糸』 [16](1918年)で、その認識をすでに作品として実践していました。
『蜘蛛の糸』は、外国が舞台であるにも関わらず、一見すると日本の古典に基づいているような印象を受けます。
今では、ドイツ系アメリカ人の作家ポール・ケーラスの『因果の小車』 [17](鈴木大拙訳)所収の『蜘蛛の糸』が元であると考えられているようです(Wikipedia 2021.1.19. 蜘蛛の糸)。題名も同じですし、登場人物の名前も犍陀多と同じなので、おそらくそうなのでしょう。
しかし、蜘蛛の糸を葱に、釈迦を守り神の天使に置き換えると、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』 [18]に出てくるロシアの民話『一本の葱』とも内容はほとんど同じです。そして芥川の『蜘蛛の糸』の大まかなフレームは、ケールラスの『蜘蛛の糸』よりもむしろ『一本の葱』の方に似ているように思います。
ケーラスの『蜘蛛の糸』では
犍陀多の話は僧の説話中に出てくる挿話で、犍陀多の物語のあとも僧の説話が続きます。そしてその挿話の中では犍陀多自身が仏に救いを求め、我執のために失敗して奈落の底に落ちています。
それに対し芥川の『蜘蛛の糸』は
散策をしている御釈迦様から話が始まり、御釈迦様が犍陀多をたまたま目に留め、犍陀多が虫を助けたことを思い出して救いの手を差し伸べます。犍陀多の結末は同じですが、最後は御釈迦様が去っていく極楽の情景までが描かれています。
これは『一本の葱』の前後の枠組み
主人公が苦しんでいるのを見ていた守り神の天使みずからが救う理由を見出し、失敗の後には天使が泣きながら去っていく
というその外形を借りて変化させたもののように、私には思えます。
おそらくどちらの話も、芥川は知っていたのでしょう。もしかしたら他にも幾つかの話を参考にしているのかもしれません。
このように外国の話を入れ子にして取り入れながら、新しい日本の古典として違和感のない作品をつくった芥川の手腕は見事です。
芥川に、彼が生まれる以前の日本人が、外国の文化や思想をどのように受け取ったかという問題を検証しようとする一貫した意思があったように思われる。
と述べています。
おそらく晩年の『河童』 [19](1927年)に至るまで、彼の作品の多くは、外来文化の日本化の実践だったのではないかと思います(ⅺ) 。
そもそも芥川にとっては、日本語で小説を執筆すること自体が、外来文化(novel[小説])の日本化の実践だったのでしょう。
志賀は
外国の文化をとりいれ巧みに日本化する能力は日本民族の一つの特性であつて、天平文化の昔より、この事なくして今日の日本文化は考へられない。
と述べており、似た認識を持っていたようにも見えます。
しかし、芥川より9年早い1883年(明治16年)の生まれで、黒船来航の年に生まれた父を持ち、日清戦争〔1894年(明治27年)〕の時に11歳、日露戦争〔1904年(明治37年)〕直前に二十歳を迎え、混乱と動乱の連続であった頃の明治人気質を、まだ色濃く残していた志賀には、物事はそう簡単に割り切れるものではなかった。
西欧列強の力を背景とする西欧文化の受容と軋轢。その裏にある酷な現実を、志賀は見ていました(ⅻ) 。そのようなものは、芥川の初期の作品からは抜け落ちています。
『蜘蛛の糸』の7年前(『神神の微笑』の11年前)に書かれた『濁った頭』(1911年)は期せずして、芥川への批判になっていると思います。
そのような志賀が、外国の作品を元に作ったのが『クローディアスの日記』 [14](1912年)です。
この作品はシェイクスピアの『ハムレット』 [21]の中で、王子ハムレットに復讐される叔父クラウディアスの日記という体裁を取っています。『ハムレット』は
父王を毒殺して王位に就き、母を妃とした叔父に復讐する物語
なのですが
志賀の作品では
クローディアスは、ハムレットの母に思いを寄せていたのは事実だが、決して自分の兄(先王)を毒殺などはしていないと仕切りに述べています。クローディアスは、この誤解を解こうと必死なのですが、彼の中には一片のやましさがあります。それは、夢の中で兄(先王)を殺した記憶によるものです。
これが自分の夢の中であれば
柄谷行人が『日本近代文学の起源』[64]の中で云うように
ありふれている。
しかし彼は
うなされながら眠る兄の枕元で、兄の夢の中で兄を殺す自分を、確かに実感するのです。
これはなんとも
驚くべき「殺人」
です。このような例を他に聞いた事がありません。
そしてこの小説は、太宰治の『新ハムレット』 [22]のようなふざけたところは微塵もなく、西欧(デンマーク)の物語として真に迫って来ます。これは芥川の『蜘蛛の糸』が日本の物語として違和感がないのと、好対象を成しています。
しかしここで描かれたクローディアスの心性は
志賀が
あの小説のクローディアスの心理からいへば全く自分自身です。
と言っているように、日本人(志賀自身)のものを元にしています。
それを西欧にまで敷衍して、普遍化した。この作品が書かれた頃までは、西欧も日本とそれほど違わなかったと、志賀は考えたのだと思います。
そしてこの小説でも志賀は、現実を割り切れない複雑なものとして描いています。クローディアスを弁明したかのようなこの作品を通して見ると、復讐心に燃える若きハムレットは、新王クローディアスに残る古い心性と、あたかも内通しているかのように思えて来ます。原作の父王の幽霊は、その媒介者の役割を果たしているように見えます。
『ハムレット』の作者シェイクスピアが生きたのは、ルネサンスと宗教改革があり、社会が大きく揺れ動いた時代です。この混乱を経て、さらに市民革命と云う動乱を抜け、長い年月をかけて西欧は近代化を体現していきます。その過程は欧州でも一様ではなく、それぞれの地域がそれを受け止め内面化していきました。長い歩みを経た為に見えにくくなっているとしても、多くの西欧諸国においても、それは非西欧諸国の近代化と同じく、文化を変形しつつ受容する過程でした。
実際にシェイクスピアの祖国イギリスでは、1543年に独自の英国国教会の成立とそこでの改革をきっかけに、大陸よりプロテスタントの運動が急速に流入し、紆余曲折を経て、その後の清教徒(ピューリタン)の運動、更には清教徒革命(1642〜1649年)という動乱へと繋がっていきます (参考:『物語 イギリスの歴史』上・下 [23])。
『ハムレット』の舞台デンマークでも、ドイツから伝わったプロテスタントのルター派が席巻します。(Wikipedia.2021.1.19. デンマークの歴史、 デンマーク=ノルウェーの宗教改革)。
『クローディアスの日記』を読むと、ハムレットとクローディアスの悲劇は、そのような外来文化の受容に伴う軋轢の象徴のように思えてきます。
芥川がアジアの辺縁としての日本を舞台にしたのと、『ハムレット』と『クラウディアスの日記』の舞台が、欧州の辺縁デンマークであるのは、興味深い符合です。シェイクスピアが当時の教養であったラテン語ではなく、当時の一地方言語であった英語で劇を書いたということも、とても示唆的だと思います(xiii) 。
『クローディアスの日記』も期せずして、日本の独自性を体現した芥川の作品への回答になっていると思います。
この志賀の二作品で描かれた心性は、現代人の多くから見れば異様に写るのではないかと思います。
それは丸山眞男なら、悪しき日本の封建遺制・前近代制と呼ぶかもしれない。日本の古い心性を再評価したように見える吉本隆明の『共同幻想論』 [24]にも、このようなものは含まれないと思います。
赤松啓介の『夜這いの民俗学』 [25]で描かれたようなものは再評価されても、これは無理だと思います。
大方の理解を超えているだけでなく、そもそも日本の内部をいくら精密に調べても、こういったものはおそらく出てこない。それは外部から来た異質なもの(キリスト教)との先鋭化した葛藤を通して、小説という形でこそ露呈して来たものだと思います。
近代化へと向かう社会で、このような本源的ともいえる心性を保つことには、困難が伴います。それは時に悲惨な結末を呼びよせます。『濁った頭』の主人公が、精神を病んで殺人を犯し、クローディアスが甥に殺されたように。
志賀自身も、キリスト教を受容し、棄教する中で、危機に直面したのではないかと思います(xiv) 。しかし志賀は破綻する事はありませんでした。そして自身の古い心性を、完全に失うこともなかったのだと思います。
志賀自身のこのような経験は、芥川とは違ったオプティミズムを志賀にもたらし、それが日本の国語をフランス語にしても良いという認識に繋がっていったのだと思います。
つまり、日本の国語をフランス語にすれば、多くの困難を伴い、多くの悲惨な結末を呼び寄せるだろう。しかしそれでも良い。それを乗り越える者は(自分のように)きっとある。そしてそこにこそ、日本人の心性は生き残るのだ、という訳です。
それが
日本人の血を信頼し
という言葉にもつながっているのだと思います。(xxxii)
志賀が失わなかった、このような本源的心性は、国学のそれとは、ずれています。
それは志賀が作品に描いた心性が歪んだ形で表れているからと云うだけでなく、そもそも本居宣長 (参考: [26]) の「もののあはれ」や「やまとこころ」のように名付けられるものではないからです。名付けてしまうと、その瞬間に違うものになってしまう、そんなものだと思います。
志賀の認識は、本居宣長を
日本魂と云うも、偏よる時には、漢籍意にひとし
と痛烈に批判した上田秋成に近いかも知れません。
迷信を嫌い、神仏に手を合わせることのなかった(『志賀直哉』阿川弘之 [10])という志賀の描いた心性は
「狐」を信じるということは、もちろん儒学の合理主義的な秩序の枠内におさまり切らぬものの存在を認めることである。
と論じた、上田秋成のいう「狐(狐憑)」 [29]のようなものに思えます。それは実証的に語れるものではなく、だからこそ志賀はそれを作品として描いた。
そのような心性は、志賀がシェイクスピアの作品を題に取り、上田秋成が中国の古典を元に物語を描いたように(『雨月物語』) [30]、決して日本固有のものでなく、普遍的なものです。
しかし西欧科学文明の広がりの元では、どこでも滅びゆく運命にあります。
『濁った頭』に連なる志賀の作品について、芥川は述べています。
神秘が、古の希臘の神々のやうに、森からも海からも遂におはれて、人々の心裡のうちに、隠れたのは、今更らここに云う迄もない。−神秘を解こうとした作家は、日本にも、少なくない。しかし、彼等の多くは笑ふ可き「怪談」を繰り返すか、さもなければ、幼稚なカテゴリイの中に徘徊するか、その二途を出ずにゐたのである。翻つて、「濁った頭」にはじまる作品のseriesを見ると、ここに描かれた神秘は、いづれも殆直下に、常人の世界に迫つて来る神秘である。「濁った頭」の末節に於て、津田のみた林間の幻影の如きは、明に「怪談」を離れた神品であつた。
まことに見事な分析です。(xviii)
しかし芥川はこのように志賀の作品を理解できても、それを自身では描けなかった。
最晩年の『点鬼簿』 [32]『歯車』 [33]『或阿呆の一生』 [34]などは「人々の心裡のうちに、隠れた」神秘を描こうとした芥川なりの足掻きのなのかもしれませんが、志賀の作品の不気味さには及びません。『歯車』の主人公がどんなに怪しい影に誘われるようであっても、そこには自我のようなものが感じられ、その自我が混乱しているように読めます。それは断片的な『或阿呆の一生』でもそうです。
『点鬼簿』で
人物を必ず「狐の顔」に描く「狂人」の母
について述べ、その母と亡くなった姉が混じり合った姿で自分を見守っていると感じ
それを
何かの機会に実存の世界へも面かげを見せる超自然の力の仕業であろうか?
と語る芥川に、それほど奇異な印象は受けません。それは同様の経験がなくとも、想像の範囲内です。
それに対して、志賀の一連の作品の主人公には、自我のようなものがおよそ感じられません。ただ何かに取り憑かれ、強いられている切迫感があるだけです。それが「常人に迫つてくる神秘」を感じさせるのだと思います。(xxxviii)
初期中期のものは芥川君の一面で、晩年のものは他のより眞實な一面であつたと思ふ。傷ましいことではあるが、私は此面のものをもつと見せて貰ひたかつた。
と自殺した作家の全集の推薦文に平然と書く志賀の率直さは異様です。
それに比して芥川は、あくまでも、客観的・歴史的分析に片足を残したままで、彼の作品もその日本文化史の理論の実践としての枠を、超える事はなかったと思います。
志賀直哉と三島由紀夫
さて、フランス語(国際語)を強制的に導入して、あとは自然に任せるというのは、それがかえって日本語と日本人の心性を強化する可能性があるとしても、なんとも乱暴な方法です。しかし、国語の改革によって日本語を守った日本で、その後、志賀が描いたような心性が、急激に失われていった事は確かです。
それは三島由紀夫が『文化防衛論』 [35]を書いた頃(初出1968年)には、確実性を帯びていました。
三島の
「文化というものは、ほんとうにどんな弱い女よりもか弱く、どんなに破れやすい布よりも破れやすい。もう手にそうっと持っていなければならん。」
という認識と志賀のオプティミズムは相補的なものだと思います。
大正時代に活躍した志賀は、三島がどう考えようとも、三島が批判した
大正教養主義
とは無縁です。(xv)
自衛隊駐屯地での自決という三島の壮絶な死と志賀の二作品に現れた悲劇とは底流で通じていると、私は感じます。
志賀が「フランス語を日本の国語にする」事を本気で考えていて、それでも日本文化は生き残ると考えていたことと
三島が
「文化概念たる天皇」「文化の全体性の統括者としての天皇」によって、「左右の全体主義に対抗」して
文化を防衛しようと本気で考えていたこととは、うらはらで、捩れながら繋がっているように思えます。
前述したように、志賀は『国語問題』で
吾々は日本人の血を信頼し
て考えなくてはいけないと言い
『メートル法廃止運動についての返事』でも
メートル法採用によつて國風の確立に不安を感ずるが如きは日本民族の血液を冒涜するものである。
と言っていて、とても民族主義的で不思議な一面があります。
また天皇については
「天子様のご意志を無視し、少数の馬鹿者がこんな戦争を起す事のできる天皇制」には反対でも「天子様と国民との古い関係をこの際捨て去つて了う事は淋しい」
と言っています。
何やら三島と通じるものを感じます。(xxi)
しかし元来皇室に関心のなかった志賀が、こういう風に考えるようになったのは、二・二六事件に際して、断固とした決断をした天皇への尊敬心からだと、阿川弘之は述べています。(『志賀直哉』 [10])
一方、三島は二・二六事件を元に『英霊の声』『憂国』『十日の菊』3作品 [38]を書きました。一見すると三島は、二・二六事件を起こした陸軍将校たちの側に立っているように見えます。しかし、この3作品は、それぞれが全く違う観点から、違う調子で描かれていて、単純ではありません。
とにかく二・二六事件が、この2人の作家に大きな痕跡を残したことだけは確かです。
そして三島には、志賀が『特攻隊再教育』[12]の中で気に掛けている
「新しい生活の焦点を自身の力で見出」せない特攻隊員
という様相があります。
「死に対する淡々たる心境」を持った故に「恐らく彼等には今日の世相を軽佻浮薄、無節操なものと考え、白眼視してゐるのではないかと思う。」
という特攻隊員に対する志賀の言葉は、戦後社会への嫌悪感を露わにした、その後の三島の姿を彷彿とさせます。
志賀の闘いも三島のそれも、どちらも敗北を覚悟した上での、ぎりぎりのものでした。
三島の『文化防衛論』初出の翌年、三島自決の前年に書かれた志賀の『ナイルの水の一滴』 [39]は、自身が敗北した後も生き続けた志賀からの三島へ向けた言葉のように、私には読めてしまいます。
長くはないので、全文を下記に引用します。
人間が出来て、何千万年になるか知らないが、その間に数えきれない人間が生れ、生き、死んでいった。私もその一人として生れ、生きているのだが、例えていえば悠々流れるナイルの水の一滴のようなもので、その一滴は後にも前にもこの私だけで、何万年溯っても私はいず、何万年経っても再び生まれては来ないのだ。しかもなおその私は依然として大河の水の一滴に過ぎない。それで差支えないのだ。
志賀を三島と結ぶ観点から捉えると、芥川の認識は対極にあります。しかしそれは志賀と三島を結ぶ線上からそう見えるのであって、三人の立場は、ちょうど三角形の頂点のような関係にあります。(図1)
第二次世界大戦後の6年8ヶ月弱を除いて他国に支配されるという事がなく、外国の影響が文化的なものに留まって来た日本の歴史が、芥川に代表される「日本は何でも取り入れて日本化する」というポジティブな視点を可能にし、それがあってこそ、志賀や三島のような大胆な主張がありうるのだと思います。
そういう意味では、3者は補完的であると云えます。
その中で芥川の立場は、私に本居宣長を想起させます。宣長の「もののあはれ」や「やまとこころ」も、本来はポジティブに名付けられるようなものではないと思うからです。宣長も本当は、上田秋成のいう「狐」が跋扈する世を生きていた筈です (xvi) 。芥川も、彼が描いた以上に、その理知を超えた「神秘」の中を生きていた。
芥川の頃よりも、更に「神秘」が「心裡」と「怪談」の中に閉じ込められた現在の日本においても、本当の「狐」は「心裡」と「怪談」の狭間にいるのだと思います。それは神秘主義が、繰り返し復活してくる基になっていると思います。(図2)
しかし神秘主義は「心裡」と「怪談」を補完するものでしかありません。本当の姿は志賀のように、異質なものとの軋轢の中に垣間見えるだけだと思います。(xxvi)

志賀直哉と有島武郎の多様性
志賀直哉は、白樺派の作家ばかりではなく多くの作家と交流がありました。三島が敬愛した谷崎潤一郎とは懇意でしたし、プロレタリア文学の小林多喜二は、自身の小説について志賀に批評を求め、志賀は手紙で答えています。
官憲に監視される身であった小林は
目立たないやうに呉服屋の番頭みたやうななりをして
奈良に志賀を訪ねています。
志賀というと私小説という枠組みで切り取られ、わりと単一の視点で描かれた小説ばかりであると捉えられがちですが、志賀の柔軟性を考えると、その小説の多くは長大な物語の断片として捉えられるべきではないかと思います。
その視野には『クローディアスの日記』で描かれたように、日本以外の場所も含まれます。と云ってもそれはフランスの作家ゾラの代表作「居酒屋」と「ナナ」を含む長編の連作ルーゴン=マッカール叢書とは違い、ほとんどが短編で、内容に統一のテーマや関連は見られません。
志賀の作品群を叢書として捉えるとしても、それは日本の詩歌の伝統に基づいているという感じがします。一つ一つの詩歌は短くとも、句集や歌集を読み通した時に一つのまとまりを確かに感じる、そういった手応えに近いのではないかと思います(xvii) 。
それでも志賀の作品をそのような多様なものの交錯として捉えると
有島武郎の
実生活の波乱に乏しい、孤独な道を踏んできた私の衷に、思いもかけず、多数の個性を発見した時、私は眼を見張って驚かずにはいられなかったではないか。私が眼を据えて憚りなく自己を見つめれば見つめるほど、大きな真実な人間生活の諸相が現れ出た。私の内部に充満して私の表現を待ち望んでいるこの不思議な世界。
という感性と志賀のそれとが近づいて見えます。
白樺派で志賀より5つ年長の有島は志賀と同様、キリスト教との軋轢を先鋭化させた数少ない作家の一人でした。
とはいえ、有島と志賀の作品は異質です。断片を繋ぎ合わせたような志賀の長編『暗夜行路』 [41]に比べて、有島の『或る女』 [42] [43]と『カインの末裔』 [44]は作中人物がどんどん勝手に動き出していくような大胆な作品です。それを書きかつ『惜しみなく愛は奪う』のような哲学書と呼べるものまで書いた有島の多彩さは、志賀にはないものです。
有島には前述した志賀・三島・芥川の補完的な関係を揺るがす湧き上がる力のようなものを感じます。(xxv)
1923年(大正12年)に45歳で縊死した有島がもし生きていたら、戦後の国語と日本文化についての議論も違った展開があったかもしれません。
最後に
志賀直哉を中心に据えると、かつての日本と日本の作家の諸相が浮き上がって来ます。稀有な資質を持った志賀は、多様で豊かな作家達の中で、その連関の結節点のような位置にいたのだと思います。志賀を批判した太宰治(『如是我聞』 [45])や織田作之助(『可能性の文学』)のような作家も、反発という形で同じ環の中にいたと云えます。
そんな日本文学の要の位置にいた志賀の『国語問題』を単なる愚かな暴言と捉えるべきではありません。むしろ日本の社会を読み解く上での貴重なテキストの1つとして捉え直して行くべきであると思います。拙論はその1つの試みです。
* 本論の引用と要約には、一部今日から見れば不適切な表現がありますが、作品が書かれた時代背景を表しているもので、引用として不可欠な部分であると考え、そのままの表現で記載しました。どうぞご理解をお願い致します。
改訂歴
2022.1.25.本文と注に一部訂正加筆、2022.1.27.引用文献追加
2022.5.21. 本文と注に一部訂正加筆・引用文献追加
2022.6.7. 注ⅺに加筆
2022.7.12.本文若干の訂正・改訂歴項目に追加・注xviii追加
2023.4.13.注 xixを追加。
2023.4.26.本文に江藤淳「近代以前」からの引用文を加筆。
2023.12.16.注xxを追加
2023.12.17.注xvに後半部、柄谷行人の書籍からの引用を用いた箇所を追加
注xxiを追加
2023.12.30. 注xxiiを追加
2023.12.31.注xiiiを追加
2024.1.3.注xxivを追加
2024.1.4.注xxvを追加
2024.1.4.注xxviを追加
2024.1.5注viに「ソシュール一般言語学講義 コンスタンタンのノート」(東京大学出版会)からの引用を追加
2024.1.6.注xxviiを追加とそれに伴う若干の訂正(書籍の表記方法など)
2024.1.11.注xxviiiを追加
2024.1.16.注xxixとxxxとxxxiとxxxiiを追加
2024.1.17.注xxxiiiを追加
2024.1.20.注xxxivを追加
2024.1.21.注xxxivに*2を追加→削除
2024.2.4.注xxxv〜xxxviiを追加
2024.2.12.注xxxviiiを追加。注xiに加筆、またもとの注xiにあった文章の一部を本文中に挿入。(柄谷行人の『日本精神分析』[48]からの引用を含む)
2024.2.17.注xxxvに追記。
2024.10.12.脱字訂正。段落「最後に」に織田作之助『可能性の文学』を追加。
2025.1.5.注xvとxxiに加筆。
今までのところ本論の大意に変更はありません。
注 [本文中の(i)〜(xxxviii)からも見れます]
ⅰ イロニーもしくはアイロニー(英:irony, 独: Ironie, 仏: ironie)は、皮肉と訳されますが、本意は「表面的な立ち振る舞いによって本質を隠すこと、無知の状態を演じること」(Wikipedia 2021.1.19.アイロニー)であり、反語、逆説などの意味も含み、ほのめかすという語感もあります。また、ソクラテスが真理を探求する為に用いた、知っていることを知らぬふりをして議論をする「哲学的イロニー」はヘーゲル、キルケゴールに批判的に取り上げられたのをはじめ、現代に至るまで多くの哲学者に取り上げられた(ポール・ド・マンの「アイロニーの概念」 [53]など)長い歴史があり、それらによる豊富なイメージの広がりを持ちます。
ⅱ 例えば日本語の全面的ローマ字化を主張した土岐善麿はG H Qのローマ字化の動きを歓迎し、『國語と國字問題』 [49]を書きましたが、その冒頭を
太安萬侶が古事記をつくつたとき、(中略)いろいろと苦辛をかさねて、遂に、その漢字にとくべつな日本語的用法を考えだした。
と云うところから始めています。そして日本語の
ことばを音としてつたえることは、なかなかむずかしかった。
とし、カナ文字の発明から、前島密の漢字廃止論、南部義籌と西周のローマ字論へと必然の流れであるかのように描いて、ローマ字を日本語の歴史の中に正統に位置付けようとしています。これは日本語のローマ字化を正当化する試みなのはもちろんですが、同時にナショナリスティックなものだと思います。前島・南部・西の三人の目的が、日本の国力を高め、日本の独立を守ることにあったのはその論旨より明らかです。特に南部については、明白に国粋主義的であることを、土岐も認めています [49]。
ただそれが西によって、真に開明的なものになったというG H Qが喜びそうな論述になっています。土岐はこの著書の中に、米国対日教育使節団の報告書の国語改革に関する箇所を全て載せて
消しておしつけがましい指圖はしない。指圖どころか、實に親切な、ていねいなことばづかいで、その決定を日本人にまかせている。
と賛辞を送っています。しかしこれは賛辞であると同時に、今後も変わらず “指図せずに日本人に任せるように” という牽制の意味もあったのではないかと思います。
土岐の国語のローマ字化を正当化しようとする歴史の中に、賀茂真淵と本居宣長への言及がないのが気になる所ではあります。もしかすると、国学を取り上げることが、国粋主義を警戒するG H Qの意向に沿わないと判断したのかもしれません。
ⅲ 志賀はこの座談会で、アルファベットが、26字であることの利点を強調しています。それであれば尚の事、英語で構わない筈です。ローマ字については、長年の普及運動があったにも関わらず広まらないのは
致命的欠点があるのではないか
と、志賀は否定的ですが、英語については述べていません。
さらに志賀は
「たとえば尺貫法をメートル法に直したために、ずッと子供達の算術が進んだといふからね。」
とメートル法をアルファベットに類比させています。
この類比は、『国語問題』と谷崎潤一郎との対談(『文藝放談』 [2])でも述べられていて、一貫しています。メートル法がフランスによって生み出され、広まった事を考えれば、そのようなフランスの国際性(アメリカに対抗できる力)を念頭に置いているのだと思います。
フランスは、ドイツ占領時には、分割統治の一角を占めましたが、日本の分割統治が画策された時には、そこから外れています。
そこまでの事実は知らなくとも、フランスを日本の占領政策に強く導き入れることは、ポツダム会談とポツダム宣言に関わったアメリカ・イギリス・ソ連・中国とは違う軸を持ち込むことであったろうことは、想像できたのではないかと思います。
しかし、11年後の座談会で、このような事を強調しても仕方がない事は確かです。
これは、辰野隆に
「『いつそフランス語にしちやえばいい』という冗談まじりの意見を出しましたね。」
と言われて、思わず出た発言だと思われます。
「あれはみんな、僕が何か思ひつきでさう云つたと思われているんだが、さうぢやないんだよ」
と話し始め、26字の利点のくだりの後
「といつても今はもう駄目だが、戦後なら」
と残念そうに言っています。
ⅳ 対談(『内村鑑三その他』 [2])では
「日本語が不自由な言葉だということは」
という表現も見られますが、その後でやはり国語と言っていて、主意はやはり国語なのだと思います。
ⅴ これが志賀独特のアイロニーである事は私には疑い得ないのですが、多くの論者は、志賀の主張を真正面から捉えるばかりなので不思議です。
それは
無茶苦茶な議論で、馬鹿につける薬はないとどなりたくなる
という丸谷才一から
内容については(フランス語で語ったとしても)支離滅裂だろうとしながらも
真面目に扱う必要のある、近代の日本人の国語観を典型的に示した重要な論文
とする鈴木孝夫
敗戦といふ衝撃によつて生じた一時的な精神麻痺の悪戯とは言え、些か度が過ぎている。
と切り捨てる『國語問題論争史』 [61] [60]の土屋道雄・福田恆存
このような主張をする志賀を「小説の神様」とした人々への苛立ちを露わにする大野晋(『日本語練習帳』 [56])まで、志賀の豪胆さに比べると、皆とても小心な生真面目さを示しています。
私の知る限りでは、蓮實重彦の
「制度」としての「日本語」と国家としての「日本」とに対する苛立ちに捉えられ、その「制度」が「制度」として機能しえない理想郷を「フランス語」として思い描いてみたまでのことだ。
と云う言葉のみが、一面で芯をついています。
蓮實の云う「『制度』としての『日本語』と国家としての『日本』とに対する苛立ち」は、確かに志賀に内在していたと思います。
しかし、敗戦直後のこの時期に、なぜ志賀があえてこのような発言をしたのかを、それだけで説明するのは無理があります。
そこには G H Q による支配下という状況を鑑みる事が必要だと思います。
そしてその場合、加藤三重子が『志賀直哉の「国語問題」の政治学』 [58]で示唆しているように、アメリカに対する密かな反発から、フランス語を選んだと云うよりも、より積極的な抵抗として志賀は選択したのだと、私は考えます。
*追記: 2022.2.25
加藤三重子の他に、当時の状況を鑑みた論考として
終戦後直後の特別な状況の中で執筆されている
ことを強調した甲斐睦郎の『終戦後直後の国語国字問題』[66] があります。まともに志賀の『国語問題』を扱ったものとして大変貴重なものですが、私は拙論を書いた当初、この著書の事を愚かにも知らなかった。
読み通してみて大いに参考になったが、拙論に大きな変更を加える必要は感じなかった。
ただ一つだけ重要な指摘があった。それは志賀が対談『浅春放談』[2]の中で
「主格なしで文章の書ける国語というものは言葉としては非常に不完全なものだと思ふ。」
と日本語について言っている事です。
このような事を志賀の考える国語批判の中心とするなら、日本語そのものを否定したと取られても仕方がない。
志賀はこの後
「突飛なやうだけれども、言葉は日本の言葉を、名詞でもなんでも使つていいが、文章の構成だけでも、フランス語にするといふことはどうかね」
と言っています。これをどう理解したら良いか。
これは似通った主張をした対談『内村鑑三その他』の
「皆に対手にされないことを承知で、云つてゐるのです。」
という志賀の言葉から押して、『国語問題』がまともに相手にされないことに苛立った放言という側面が強いように、私は思います。
志賀にも混乱した部分があったのかもしれませんが、この発言だけで「主格なしで文章の書ける国語」である事が志賀の国語批判の主題の1つであるとは、私には思えない。
日本語が「主格なしで文章の書ける国語」である事は自明のことであり、志賀のような老練な作家が今更このような事を強調してみせるのは、その後の「突飛な」意見へ繋げるための方便ではないかと思います。
ⅵ ソシュールの『一般言語学講義』は、ソシュールの講義そのものではなく、学生の講義ノートから再構成したもので、その後のさまざまな資料の発見により、新たな研究が進んでいます。
しかしソシュールの手稿や新たな学生の講義ノートがジュネーブ公共大学図書館で収集され始めたのは1954年の事であり、ここでは志賀が『国語問題』を書く前に見聞きした可能性を考え、一般言語学講義初版のものを選びました。
様々な資料をもとにした各著書から、本文で引用したものと完全に同じ箇所を取り出すのは難しいですが、類似性のある記述の一例を上げると
「ソシュール一般言語学講義 コンスタンタンのノート」(東京大学出版会)では下記のように記されています。
どのような言語であれ、そもそも言語としての条件を満たすならば、シニフィアンからシニフィエへの関係全体を刻々と変化させる諸要因から身を守るには、弱い存在です。関係が完全にそのまま保たれている例はありません。これは連続性の原理からすぐに得られる補題です。記号の恣意性に含まれる自由の原理との関係では、連続性は自由を剥奪するだけでなく、法律にもとづいて言語を構築したとしても、次の日には人々(共同体)がその関係を変化させてしまっているでしょう。人々のあいだに流通しない限り、言語を統制することは可能ですが、言語がその機能を満たすならばなら、関係は変化します。歴史が示す例にもとづくならば、少なくとも、このことは避け難いと結論するかことができます。
エスペラントは、人工的な言語の試みとして成功したかに見えますが、社会に広まるにつれて、この避けがたい法則に従うでしょうか?
エスペラント語を用いているのは小さなまとまった共同体ではなく、あちこちに散らばったグループです。そこに属する人々は、自分たちのしていることを完全に意識しており、この言語を自然言語として学んだわけではありません。
記号システム(文字表記のシステム。パーリ語を考えてみましょう)や、聴覚障害者の言語でも、同様にむやみに関係が変化します。次のことは一般記号学の事実でしょう: 時間の連続性は時間上の変化と関係する。
引用文献: 「ソシュール 一般言語学講義 コンスタンタンのノート」
2007.3.27.初版、2008.3.18.第2刷
著者: フェルナンド・ド・ソシュール
訳者: 影浦峡・田中久美子
発行所: 財団法人 東京大学出版会
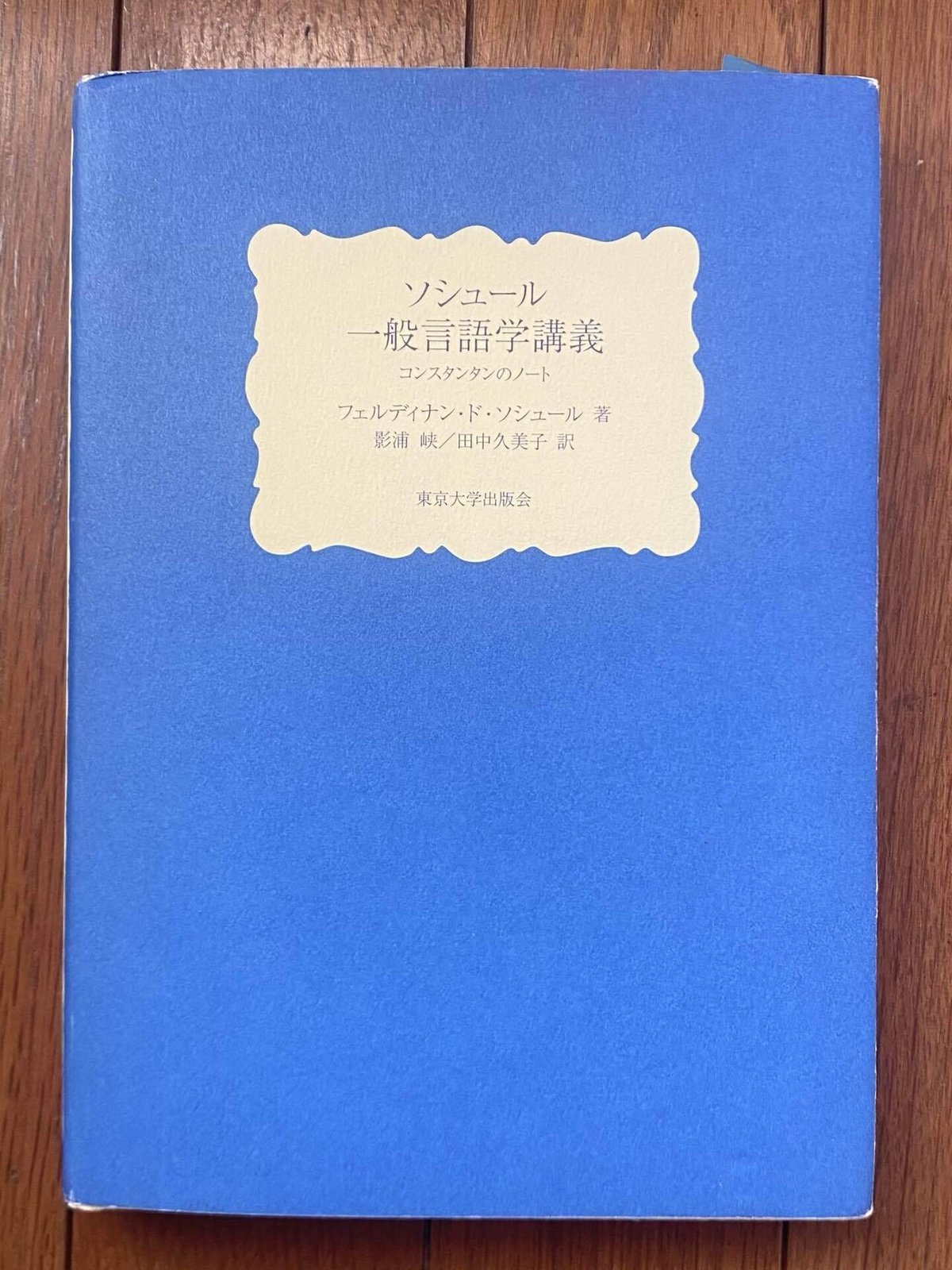
ⅶ この発言について、
志賀の帝国主義・植民地主義意識を露呈してしまった。
ものと加藤三重子は述べています。(『志賀直哉の「国語問題」の政治学』 [58])
加藤三重子も取り上げているこの前段で志賀は
国語の切換について、技術的な面のことは私にはよく分からないが、それほどの困難はないと思つている。教員の養成が出来た時には小学生から、それに切換ればいいと思う。
とぶっきらぼうに述べているので、そう取られても仕方はありません。しかしこれも志賀のアイロニーなのであって、むしろ「台湾や朝鮮で、日本も日本語を公用語として強制したではないか、今更なにを驚くのだ」という事を含意しているのだと、私は思います。技術的なことは分からないのに、困難はないと思うなどと云うのも、反語的表現であると私には取れます。しかし後述したように、外国語の強制に対する無理解が志賀にあることも確かです。
ⅷ アイデンティティの拠り所としての母語の可能性について、例えば『言語学と植民地主義−ことば喰い小論−』[54]のルイ=ジャン・カルヴェの
自分の言語を話すことは一種の抵抗行為となる。大多数の植民地原住民にとって社会体制が理解不可能であるのと同様、大多数の植民地支配者にとっては彼らの言語は理解不能だからである。そしてこの抵抗は、形式的独立を隠れ蓑に新植民地主義がことば喰いを継続するとき、言うまでもなく継続されるのである。
という力強い言葉を思い起こす事ができます。
しかしこれは実際に植民地化され、外国語を強制された人々の必死の抵抗の姿であり、日本のようにそのような強制が起こらなかった国の想像の中で可能性として考えられるようなものとはやはり違います。
それはガンジーの自伝にある次のような言葉と相まってこそ、意味を持つものであることを忘れてはならないでしょう。
祝いの言葉を言われ、また、総督主催の会議でヒンドニスター語を話したのはわたしが最初だったことを知って、わたしの民族的自負心は傷つけられた。わたしは肩身の狭い思いをした。自国の言葉が、自国に関係することのために自国で開かれる会議で使用禁止になるとは。またその席上、わたしのような一介の心定まらない者によって、演説が自国の言葉、ヒンドニスター語で行われたということが慶賀に価するとは、なんという悲劇であろう。このような出来事からみても、私たちがいかに低劣な状態に落ちこんでいたかを思い知らされる。
ⅸ 加藤三重子は『志賀直哉の「国語問題」の政治学』 [58]の中で志賀が自分は日本語を使い続けると対談(『文芸放談』 [2])で言っていることをもって、志賀がフランス語/日本語の二層構造を想定しているではなかと論じています。私の場合の二重構造は『国語問題』で志賀が終始「日本の国語」を問題としていることから、志賀が母語としての日本語の使用を全否定したわけではないと推論したに過ぎません。
外国語と母語が併存した実例としてはフィリピンが考えられます。
フィリピンにおける教授語としての英語の導入と母語との関連と歴史については岡田泰平著『「恩恵の論理」と植民地−アメリカ植民地期の教育とその遺制−』が詳しい。 [52]
ⅹ こうした文脈での「日本人の血を信頼し」という言葉は、仮に日本語が完全に滅んでも、それでも日本人の血があれば、というふうにも読め、一種の恐ろしさも感じます。
しかし対談では
「『言葉は日本語の言葉を、名詞でも何でも使つていいが、文章の構成だけでもフランス語にする』といふことはどうかね」
と言っていて、より積極的な混淆言語を想定しているようにも読め、
志賀がどのようなものを想定していたのか、はっきりしません。
名詞などはそのままでいいから日本語の仕組みを思ひ切って合理的に変える必要がある
というような発言は、フランス語の構造が日本語よりも合理的であると理解していたようにも取れます。志賀自身の考えにも混乱したところがあり、そこにはフランス語の構造が日本語よりも合理的であるというような、西欧中心主義的な考えも若干混じり合っていたのかもしれません。
しかしこの対談では
「皆に対手にされないことを承知で、云つてゐるのです。」
と言っていて、『国語問題』がまともに相手にされないことに苛立った放言という側面もあるように思います。
ⅺ 柄谷行人は『日本精神分析』の中で、『神神の微笑』[15]を取り上げて、日本の文化受容の歴史について、詳細な分析と考察をしています。 [48]
その上で柄谷行人は、キリシタンの弾圧と背教を描いた「おぎん」という芥川の作品に触れながら、
キリシタンを滅ぼしたのは、「造り変える力」などではない。端的に、暴力なのです。なぜ芥川は、そんな自明の理を無視しようとしたのでしょうか。
と問いかけています。
そして
大正時代は、西洋列強の下で、近代国家として自己確立するために懸命であった日本人が、日露戦争後そうした軍事的経済的緊張から解放され、また、自ら列強の中に入ったという誇りから、日本の文化的独自性をいいはじめたじきです。しかし、それは日露戦争までの日本人のように、世界を規定している普遍的な「力」を忘れるということです。
と述べ、更に
大正時代の日本社会が忘れてのは、「満州の戦場」だけではありません。大正時代の社会は日韓併合と大逆事件の後に成立したのですが、この二つの出来事が、この二つの出来事がこの時代の言説にまったく出てこないのです。大正デモクラシーと呼ばれた時代は、実際は、そのような暴力を隠すことにおいて形成されています。
と大正時代を規定した上で
しかし少なくとも芥川は、暴力が根底に存することを強く意識していました。彼が文化的な「造り変える力」を強調したのは、むしろそのためです。
と述べています。
柄谷行人のこの論に則するならば、芥川龍之介は志賀直哉とは違った意味で、暴力を感受していたのかもしれない。
ⅻ 明治政府は、当初キリスト教を弾圧しました。しかし西欧列強の圧力により、信教の自由を認めます。キリスト教(プロテスタント)が日本で広まるのは、明治20年頃からで、信者の中心は、かつての幕臣の師弟であったといいます。(『日本近代文学の出発』平岡敏夫 [50])
志賀直哉の師・内村鑑三もその一人です。明治維新という暴力と西欧列強の強大な軍事力の狭間で、キリスト教は足場を失った者たち(幕臣の師弟)の拠り所になった。
ナイジェリアの作家チアヌ・アチェべが『崩れゆく絆』の後半で描いたキリスト教の二重性
ある人々にとってはキリスト教が新たな可能性と解放の契機をもたらした。しかし同時に、キリスト教は植民地支配の論理と結びついき、社会が独自に変革し刷新していく能力と機会を、暴力的に、そして永久に奪い去ってしまうことになった
粟飯文子[59]
と部分的には似た構図が日本にもあったのかもしれません。
しかし、日本で最初にキリスト教に救いを求めたのは、アチェべが描いたような
共同体で抑圧を受けてきた者たち
粟飯文子[59]
よりも、かつての支配層(幕臣)の師弟でした。そして日本は植民地化されることはなかった。
社会が独自に変革し刷新していく能力と機会を、暴力的に、そして永久に奪い去
粟飯文子[59]
られるという過酷な状況は、日本にはなかった。キリスト教の広がりは限定的でした。信者からも棄教する者が続出します。キリスト教を堅持し続けた内村鑑三とその教えとの葛藤を先鋭化させた志賀直哉のような人は、どちらも日本では稀でした。その志賀の特異性が、独特の考察を可能にしたと云えます。
尚、日本人とキリスト教の関係については、柄谷行人が『日本近代文学の起源』[64]の「告白という制度」で詳しく論考を加えている。志賀の『濁った頭』に連なる作品群についても、そこで触れられている。この点での拙論の発想は、多く柄谷氏の考察に触発されたものである。
xiii ハムレットは、北欧の伝説が元となったと云われ、それはシェイクスピアがハムレットを書いたとされる1600年前後を遥かに遡ります(『ハムレット』(福田恆存訳)所収「解題」福田恆存 [21])。しかし、志賀は、シェイクスピアが自分の時代の混乱を託した物語として、ハムレットを読んだのだと思います。
xiv 志賀の『内村鑑三先生の憶い出 [39]』を読むと、『濁った頭』の内容の一部は、志賀自身の経験に基づいている事がわかります。
xv 三島由紀夫は
高等学生の千編一律の教養体系、西田幾多郎の『善の研究』、和辻哲郎の『風土』『倫理学』、阿部次郎の『三太郎の日記』などの必読書に縛られた知的コンフォーミティが我慢ならなかった。現在にいたるまで私には根強い知識人嫌悪があるが、その根はおそらくこういう少年期のヘソ曲りに源しているに違いない。
と言っている。
『濁った頭』や『クローディアスの日記』のような異様な作品を書いた志賀が、このような「知識人」に該当するとは、私には思えません。
『行動学入門』[68]所収の「革命哲学としての陽明学」の中で三島が大正教養主義に触れた箇所で、武者小路実篤と志賀直哉を並べているのはは不当なことに思えます。武者小路と志賀は共に白樺派を代表する人物ではありますが、全く資質の異なる作家であると思います。
ただ、柄谷行人が「双系性をめぐって」の中で
大正期に、志賀や西田がいわば基層的なものに向かったのは、それ自体、明治的近代のなかにおいてであり、また、西洋という強迫的な「他者」から一時的に解放されたという状況なしには、ありえないのです。
と述べている通り、志賀の作品もまた大正という時代を反映しているとはいえるのかもしれない。
そして、柄谷行人が
西田も志賀もある意味で、「明治」的な人で、ある強さを持っています。しかし、大正以後の人にとっては、こうしたものが日本独自のものとして自明化されていきました。
と述べているように、大正教養主義の元祖の1人である西田幾多郎にも、三島の云う
知的コンフォーミティ
とは異質な側面があったのかもしれない。
このような
大正教養主義
の
知的コーンフォーミティ
とは異質な側面が志賀直哉にある事に、三島由紀夫は気が付かなかったのだろうか?
おそらくそんな事はあるまい。
三島由紀夫は学習院の4年先輩の美術評論家・徳大寺公英との対談の中で
2人が通った当時までの
「学習院には教養主義に対する侮蔑があってね」
「その三つ子の魂百までってのは今でも残ってるね。
僕は大学の先生ってのさ大っ嫌いだしね。それからそのインテリゲンチャってのも嫌いでしょ。その体質は二十何年経ったって全然治らないね。」
と自分の
「教養主義に対する侮蔑」
の源泉の1つに学習院がある事を述べている。
しかし時期は違えど志賀直哉と白樺派の作家たちも学習院に在籍していたのである。
同対談で三島由紀夫は
「白樺があんまりに学習院を代表しちゃったから、反感を感じたんだな」
と言っている。
三島由紀夫が白樺派に対して、同じ学習院であっても、距離を感じていた事も事実のようではある。
それでも白樺派の作家たちも、同じような学習院の反教養主義を身近に感じていたものと思われる。
人道主義的思想家という側面が段々と大きくなっていった武者小路実篤と違い、志賀直哉は晩年に至るまで、教養主義とは無縁であったように、私には思われる。
また、この対談の中で三島由紀夫と徳大寺公英は、当時の学習院がいかに暴力に溢れていたかを繰り返し話題にし、そしてそれが学習院の学生の封建的家庭環境から来ている事を述べ、そういった環境が白樺派の文学にも影響を与えている事を指摘している。
志賀直哉の小説「和解」で描かれた親子の確執は、その典型例であろう。
それは具体的には
「お家騒動からね。家ん中で誰が殿様方で誰が奥方方だとかね。(中略)
それから、家ん中に腹違いの兄弟がいっぱいいるとかね。
それから、まぁ、財産争いとかね。
そんな事がどこの家だってない家はないよ。
そんな中で揉みに揉まれて、お父さんは嫌でも威厳を持って、完全な父権性社会だから」
と云った家庭である。
三島由紀夫と志賀直哉に時に現れる暴力性は、学習院とその師弟の家庭という共通の地盤があるように思われる。
以上のようなことからも、三島由紀夫の志賀直哉に対する態度について考える時には、安直に捉えずに、少し留保がいるように思われる。
三島由紀夫は1966年の安部公房との対談で
「ただ僕が伝統などと言うのは、やはり一種の敵本主義でそういうことを言うのだ。」
と言っている。
そして
「志賀直哉氏のは立派ない文学だが、ああいうふつなものだけが日本語の特質であって、もっとデコラティヴな西鶴以来の、ああいう連想作用の豊富な、メタファーの豊富な文学はだね、ぜんぜん、つまり日本文学の美しいものではないというふうな考え、それでずいぶんひどい目にあってる作家が、どれだけいるかわからないよ。泉鏡花だろうが、岡本かの子だろうが、だれだろが」
と言い
「僕がいまだにくやしくて覚えているのは、小学校のとき綴り方を書いて、そのころはみんな志賀直哉が最高のお手本だよ。小学生に志賀直哉を読ませてもしようがないのだけれどもね。あれに少しでも似ていない文章は、もう悪い文章で、形容詞が一つあってもいけないのだ。つまり、ああいうふうなものが最高だと。そうして、ああいう写生文なり、写実的なね、非常に象徴の域にまで入った写実が最高だという考えね。」
と小学生の時の思い出を語っている。
三島由紀夫の志賀直哉に対する態度は、このような現状に対して対抗する為のもので
三島が
「一種の敵本主義」
というように戦略的なものであろう。
『文章読本』の中で
日本語のいかに堪能な西洋人でも、森鴎外や志賀直哉の文章がわかりにくいのは、それがきわめて微妙な味、水に似た味わいをもっているからにほかなりません。
と敬愛した森鴎外と並べるかたちで、三島由紀夫は志賀直哉の名前を上げています。志賀直哉を高く評価していた事がうかがえます。
三島由紀夫は『蘭陵王』(新潮社)所収の「日本への信条」(1967年)のなかで
戦後、日本語をフランス語に変えよう、などと言った文学者があったとは、驚くにたえたことである。
と述べている。これは志賀直哉の「国語問題」の事であろうが、多弁な三島にしては、なんとも簡潔な言葉である。
三島由紀夫は同『蘭陵王』所収の「「変革の思想」とは」(1970年1月)の中で、井上清の『全人民的激動の予震』という文章を批判するという文脈の中ではありますが(この井上清の文章を私は読んでいないのですが)
学生の勇気の証明を黙秘権に置くのは、論理的矛盾である。なぜなら、死を賭けるべき黙秘を、「黙秘権」として基本的人権と接着せしめた法体系こそ、思想の相対化によって柔構造社会を成立せしめた張本人であり、その権利を利用することは、すでにそのような法体系を容認することでこそあれ、何ら勇気の証明にはならぬからである。
と述べている。
これを書いた年の11月25日に三島由紀夫は割腹自殺を遂げている。
三島由紀夫は、多くを語ったが、時に簡潔すぎるほど簡潔にしか語らない事がある。
志賀直哉の「国語問題」について、また注 xxi で取り上げた坂口安吾についてもそうである。
三島由紀夫は
死を賭け
て黙秘を守ったのかもしれない。
その黙秘された心のうちを想像するのには、困難が伴うが、三島由紀夫が言葉少なに語った中にこそ、重要なものが隠れていると思えてならない。
引用文献・音声:
①三島由紀夫, 『古典文学読本』[46]中央公論新社,初版発行 2016.11.25. 、再版発行 2020.5.25. うち「日本の古典と私」初出: 1968.1.1.他「山形新聞」
②『〈戦前〉の思考』柄谷行人
1994.2.1.第1刷
1994年4.10.第4刷
発行所: 株式会社 文藝春秋
③ 決定版三島由紀夫全集41 音声
発行2004.9.10.
著者: 三島由紀夫
発行所: 株式会社新潮社
「青春を語る」は昭和44年11月12日に、東京・有楽町の日活ホテルのレストランで行われた。
④ 『文学者とは何か』
2024.12.10.初版発行
著者: 安部公房 三島由紀夫 大江健三郎
発行所: 中央公論社
「二十世紀の文学」初出1966.2.「文芸」
⑤ 『文章読本』ー 新装版
1973.8.10.初版発行
2020.3.25.改版発行
2024.1.30.改版3刷発行
著者:三島由紀夫
発行所: 中央公論社
⑥ 『蘭陵王』ー 三島由紀夫 1967.1〜1970.11
1971.5.1.印刷 1971.5.6.発行
著者: 三島由紀夫
発行所: 株式会社新潮社
「日本への信条」初出:1967.1.1.「共同通信」
「「変革の思想」とは」初出:1970.1.20.〜22.『読売新聞』
xvi この狐が跋扈する世は、あるいは柄谷行人が『反文学論』[65] の第6章「法について」で富岡多惠子の小説『坂の上の闇』[67]に言及した箇所で
宣長もまたこのような「闇」に触れていたといってもよいだろう。また、そういう「闇」をぬいて、宣長を読むことはできない。
と述べた時の「闇」に触れる世と云えるかもしれない。
xvii 志賀の短編の作風は様々ですが、それぞれのフレームは異なっても、正岡子規と高浜虚子に始まる近代俳句と写生文に、どれも近いように思います。
これは、江藤淳が『リアリズムの源流』 [51]の中で分析したように、近代日本のリアリズムの源流の一つが写生文に基づいていて
志賀が虚子と
地下水にようにリアリズムへの志向が共通していた。
とするなら、当然のことと云えます。
菊池寛が
氏のリアリズムは、文壇における自然派系統の老少幾多の作家のリアリズムとは、似ても似つかぬように自分に思われる。
と指摘しているのも、志賀が、国木田独歩に端を発する日本の自然主義派(島崎藤村・田山花袋など)のリアリズムとは別の、写生文の流れを汲んでいる故であろうと思います。
そして、芥川龍之介が『文芸的な、あまりに文芸的な』の中で、
あらゆる小説中、もっとも詩に近い小説である。しかも散文詩などと呼ばれるものよりも遥かに小説に近いものである。
と云った「『話』らしい話のない小説」の代表格として志賀をあげているのは、もっともなことだと思います。
xviii 芥川龍之介はここで、ハインリッヒ・ハイネの「流刑の神々・精霊物語」を念頭に置いているものと思われます。
「流刑の神々・精霊物語」ハインリッヒ・ハイネ小澤俊夫訳
岩波書店 1980.2.28.第1刷発行、2019.5.24.第16刷発行
原典: GÖTTER IM EXIL 1853
ELEMENTARGEISTER 1935-36
Heinrich Heine

xix 志賀直哉の「濁った頭」の中で述べられた同性愛は現代のものとはだいぶ違っているように感じられます。それはまるで異性愛へと向かう一段階であるかのように読めます。
三橋順子は著書『歴史の中の多様な「性」ー日本とアジア 変幻するセクシュアリティ』の中で
前近代の日本人が男色体験を一種の通過儀礼と認識していた
ー日本とアジア 変幻するセクシュアリティ』三橋順子
ことを指摘しています。
それはこの小説の主人公のように、女色へと容易に結びつくものだった。
三橋順子によれば
日本の前近代の男色文化の最大の特性は年齢階梯制という仕組みにあ
ー日本とアジア 変幻するセクシュアリティ』三橋順子
り、同著を元に僕なりに要約すると、それは
性愛行為において、受動的役割を担っていた年少者が、成長して年長者としての能動的役割を担うようになることによって、受動から能動へと役割を変えながら、伝えられていくものだった。
明治以降こうした男色文化は抑圧されるが、男子校文化の中で、根強く残っていたことをこの本は様々な事例を元に指摘しています。
志賀直哉との関連では、里見弴が「志賀君との交友録」『銀語録』相模書房(1938年)の中で志賀へと向けた言葉を紹介しています。
志賀直哉が、このような男色文化が色濃く残る社会で、この小説を書いたのだということが、この本を読むと良くわかります。
同著で三橋は前近代の日本では
男性同士の性愛は「男色」として概念化されていたが、それは成人した男性と元服前の少年の関係が主で、成人男性同士の性愛を中心とする「男性同性愛」とはかなり異なる。男色は文化的、環境的なら要素が強く影響していて後天的かつ可変的である。それに対して「同性愛は先天的かつ不変的とされている。「男色」と「男性同性愛」は似て非なるものだ。そこらへんをしっかり認識してほしい。
ー日本とアジア 変幻するセクシュアリティ』三橋順子
と述べています。重要な指摘です。
志賀直哉の「濁つた頭」で述べられた男性同士の性愛もおそらく男色の流れを汲むもと思われるので、男性同性愛とするよりは男色とする方が正しいのかもしれない。
引用文献:
『歴史の中の多様な「性」ー日本とアジア 変幻するセクシュアリティ』三橋順子
2022.7.14.第1刷発行
岩波書店

xx 「戦後日本の国語教育 二松學舎に学んだ沖山光の軌跡」に戦後の昭和
二二年四月から二四年三月まで使用された最後の国定教科書(第六期)「みんないいこ」読本
の編集責任者、
文部省教科書局第一課の国語担当で児童文学者の石森延男
の次のような言葉が紹介されています。
「無条件降伏日本、まさに日本語そのものが、消えてしまうかもしれないと思った。国語科などという教科は、果たして存続するのだろうか。当の責任者であるわたしにすら不明であった。局長でも、大臣とても予想はしかねたであろう。それほど混沌としていたさ中に、国語教科書の編集は、なみたいていのわざではなかった。」
敗戦国日本の知識人層の心情をよく表している言葉ではないかと思います。
同著の P94 注7 に上記の発言の引用元が記されています。下記の通りです。
石森延男「敗戦直後の国語教育」、現代国語教育論集成編集委員会『現代国語教育論集成 石森延男」一九九二、明治図書、三一二頁(初出は『教育科学国語教育』一九六六・二、明治図書)。
引用文献: 「戦後日本の国語教育 二松學舎に学んだ沖山光の軌跡」
2018年3月31日 初版第1刷発行
編者 沖山光研究会 発行者 村松泰子
発行所 東京学芸大学出版社
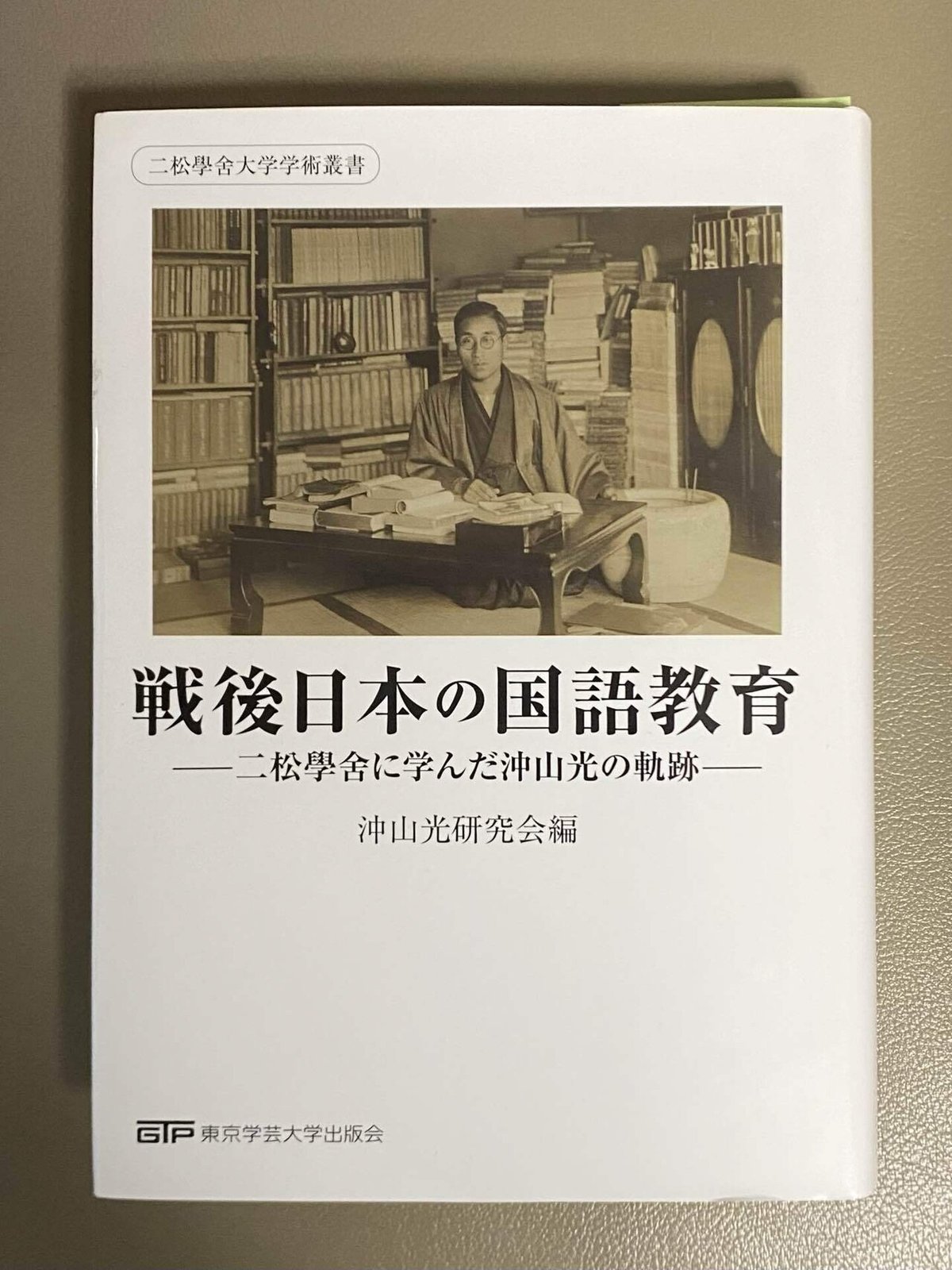
xxi 三島由紀夫を志賀直哉と結ぶ線で理解しようとする時、その補助となるのは坂口安吾ではないかと思います。
三島は戦後の無頼派と呼ばれた作家達の中で、太宰治よりも坂口安吾を高く評価していました。
坂口安吾全集の推薦文で三島は
何たる悪い世相だ。太宰治がもてはやされて、坂口安吾が忘れられるとは、石が浮かんで、木の葉が沈むようなものだ。
と述べた後、
坂口安吾は、何もかも洞察してゐた。底の底まで見透かしてゐた
と述べています。
坂口安吾は何をどのように洞察し見透かしたのだろうか?
有名な「堕落論」の中で坂口安吾は述べています。
元来日本人は最も憎悪心の少い又永続しない国民であり、昨日の敵は今日の友という楽天性が実際の偽らぬ心情であろう。昨日の敵と妥協否肝胆相照すのは日常茶飯事であり、仇敵なるが故に一そう肝胆相照らし、忽ち二君に仕えたがるし、昨日の敵にも仕えたがる。生きて捕虜の恥を受けるべからず、というが、こういう規定がないと日本人を戦闘にかりたてるのは不可能なので、我々は規約に従順であるが、我々の偽らぬ心情は規約と逆なものである。
だからこそ
古の武人は武士道によって自らの又部下達の弱点を抑える必要があった。
のであり、その必要によって生まれた武士道は
人性や本能に対する禁止条項である為に非人間的反人性的なものであるが、その人性や本能に対する洞察の結果である点に於ては全く人間的なものである。
これが三島由紀夫が拘った武士道に関する坂口安吾の既定だとすると、
もう一つの三島の思想の鍵である天皇についてはどうだろうか?
「天皇陛下にさゝぐる言葉」の中で坂口安吾は述べています。
天皇が我々と同じ混雑の電車で出勤する、それをふと国民が気がついて、サアサア、天皇、どうぞおかけ下さい、と席をすゝめる。これだけの自然の尊敬が持続すればそれでよい。
私とても、銀座の散歩の人波の中に、もし天皇とすれ違う時があるなら、私はオジギなどはしないであろうけれども、道はゆずってあげるであろう。天皇家というものが、人間として、日本人から受ける尊敬は、それが限度であり、又、この尊敬の限度が、元来、尊敬というものゝ全ての限度ではないか。
このような武士道と天皇に関する坂口安吾の洞察を三島由紀夫は受け入れていたのだろうか?
受け入れていたと考えると、三島の武士道と天皇に関する発言と思想も、だいぶ違って響いて来ます。
それは志賀直哉の
「天子様のご意志を無視し、少数の馬鹿者がこんな戦争を起す事のできる天皇制」には反対でも「天子様と国民との古い関係をこの際捨て去つて了う事は淋しい」
と云う朴訥な認識とも更に近づいて感じられて来ます。
とはいえ、坂口安吾の豪放な言葉には、志賀直哉の素朴さとは異質なものがありますし、
三島由紀夫の認識も、素朴なものにとどまっていたわけではありません。
1968年の石原慎太郎との対談で三島由紀夫は
「つまり日本をね、日本以外の国から、何が日本かということを弁別する最終的なメルクマールとして、天皇しかないんだよ。はっきりしていることだ。ぼくはね、それ以外にはあまり日本的なものというのを信じないな。そういう意味では天皇しかないんだ。」
と言い切り
「日本の国から外へ、天皇を信じさせようとするのは、僕は無理だと思うし、大東亜共栄圏なんていう考えは持たないね。日本を外国から弁別するメルクマール、日本人を他国人から弁別するのはメルクマールというのは天皇しかない。他をいくらさがしてもないんだ。いろいろ考えてみたんだが。」
と繰り返した後
「ぼくは、日本文化の特殊性というものをずい分長く考えてきた。ほとんどそれは、非常に特殊なもんであるけれども、結局普遍的なものになりうることが、文化というものの一つの宿命みたいなものだよ。それは文化の長所であるとはいえないが、普遍的になりうることが文化の宿命なんだ。しかし一方、文化の中核には絶対に普遍化されぬものがあるはずだ。その中で絶対に普遍化されないものというのは、天皇みたいなものしかないんだ。
お能なんか解りにくいというけれども、僕はお能の中にあるロジックは、西洋人にも絶対解るものだと信じいる。」
と述べています。
これは志賀直哉の朴訥な認識とは、随分と遠く隔たっています。
そして、このような考察に三島由紀夫を向かわせた契機も、坂口安吾にあるのではないかと、私は思います。
前述の石原慎太郎との対談で三島由紀夫は
「日本人というのは、権力というものの構造を抽象的なものと考えないね。どうも、自分の権力意志を具体的なものにぶつけて、はね返ってきた手ごたえが自分の権力だという感じを持つんです。野球の球を壁にぶつけて、はね返ってきてはじめて、わが手に握ったんだと思うでしょう。それと同じで、天皇というのは、そういう生きた壁なんですよ。あれに一度ぶつけないと、権力というものは、絶対になりたたない。日本人というのは、なにか、ああいうクッションというか、そういうものにぶつけてみないと、全くわからない。そのクッションというものが抽象的なものであってはいけないんですよ。どうしても」
と述べています。
これは坂口安吾が『堕落論』の中で述べている。
藤原氏や将軍家にとって何がために天皇制が必要であったか。何が故に彼等自身が最高の主権を握らなかったか。
それは彼等が自ら主権を握るよりも、天皇制が都合がよかったからで、彼らは自分自身が天下に号令するよりも、天皇に号令させ、自分がまっさきにその号令に服従してみせることによって号令が更によく行きわたることを心得ていた。その天皇の号令とは天皇自身の意志ではなく、実は彼等の号令であり、彼等は自分の欲するところを天皇の名に於て行い、自分が先ずまっさきにその号令に服してみせる、自分が天皇に服す範を人民に押しつけることによって、自分の号令を押しつけるのである。 自分自らを神と称し絶対の尊厳を人民に要求することは不可能だ。だが、自分が天皇にぬかずくことによって天皇を神たらしめ、それを人民に押しつけることは可能なのである。そこで彼等は天皇の擁立を自分勝手にやりながら、天皇の前にぬかずき、自分がぬかずくことによって天皇の尊厳を人民に強要し、その尊厳を利用して号令していた。 それは遠い歴史の藤原氏や武家のみの物語ではないのだ。
という言葉と殆ど同じ事について述べているように思えます。
日本歴史と文化・武士道・天皇について、明確に自身の見解を示し
坂口安吾は、何もかも洞察してゐた。底の底まで見透かしてゐた
とまで三島由紀夫に言わしめた坂口安吾。
最終的な三島由紀夫の認識は、坂口安吾のものとはだいぶ異なるものを含むとしても、それは坂口安吾の洞察を一度は受け入れた上でのものであったのだろうと思います。
坂口安吾の認識から、更に自分の論を進めた三島由紀夫ですが
1969年の東大全共闘との対話の中では
「こんな事を言うとね、あげ足をとられるから言いたくないのだけれどもね、ひとつ個人的な感想を聞いてください。というのはだね、ぼくらはつまり戦争中に生まれた人間でね、こういうところに陛下が立ってて、まぁ坐っておられたが、3時間全然微動だにしない姿を見ている。
とにかく3時間、木像のごとく全然微動もしない、卒業式で。そういう天皇から私は時計をもらった。そういう個人的な恩顧があるんだな。こんな事言いたくないよ、俺は。言いたくないけれどもだね、人間の一人の個人的な歴史の中で、そういう事はあるんだ。そしてそういう事はどうしても否定できないんだ、俺ん中でね。それはとても立派だった、その時の天皇は。」
豊島圭介監督『三島由紀夫vs東大全共闘〜50年目の真実〜』[37]
という個人的な回顧を述べています。
これは志賀直哉の
「天子様と国民との古い関係をこの際捨て去つて了う事は淋しい」
という素朴な言葉を再び思い起こさせます。
そして志賀直哉と三島由紀夫が時期は違っても共に学習院に在籍していたことを想起させます。
しかし同時にこの発言には奇異な印象を私は受けます。
この東大全共闘との討論が行われた時点で、三島由紀夫は既にこのような個人的な感慨とは異質な地点にいたように思われるからです。
先に取り上げた石原慎太郎との対談での発言からも、その事は明らかです。
そのような三島由紀夫がなぜ今更
あげ足をとられるから言いたくないのだけれども
と断りつつも
天皇から私は時計をもらった
という個人的感懐を敢えて述べたのだろうか?
そこには何か意図があるのだろうか?
それとも文化的・歴史的な考察・見解とは別に、このような素朴な敬愛の念も、隠しきれぬほどに強く持ち続けていたのだろうか?
「三島さん、これからの日本の天皇だけど天皇はもう少し国民と話をすべきじゃあないですか。(後略)」
という石原慎太郎の問いかけに
三島由紀夫は
「ぼくは全然そう思わないね。
つまり日本が、小さいコミュニティーであり、そういう中では多少そういう可能性はあったかも知れない。だけど今、一億の国民に伝達するのは、いろんなマスコミュニケーションでもって伝達しているでしょう。
天皇というものは伝達から断絶しなけりゃあならないですよ。ぼくは伝達に天皇が阿諛するというか、伝達というものに天皇が負けたならば、天皇制はなくなるとも思っている。」
と言い
「どうしても伝達できないところを一つ作っておかなきゃあならないね。今日本人は、つまりどんなことも伝達できるという妄想をもってるよ。(中略)
陛下というものは、絶対にそういう伝達の仕方から断絶しなきゃならないと思う。」
と述べています。
このような考えは
志賀直哉の素朴さとはもちろん
坂口安吾の
天皇が我々と同じ混雑の電車で出勤する、それをふと国民が気がついて、サアサア、天皇、どうぞおかけ下さい、と席をすゝめる。これだけの自然の尊敬が持続すればそれでよい。
という発想とも、全く異質なものであるように思います。
何か天皇に対して冷淡なようにさえ、私は感じます。
志賀直哉・坂口安吾・三島由紀夫の3人をこのように簡単に比較しただけでも、興味深い論点が浮かび上がってきます。
三島由紀夫の思想についは多く論じられて来たが、この2人との比較は、管見の限りでは殆ど見受けない。
特に三島由紀夫が
坂口安吾は、何もかも洞察してゐた。底の底まで見透かしてゐた
とまでいう坂口安吾との比較は、三島由紀夫を論じる際には必須ではないかとすら、私は思うのだけれども。
引用文献・映画:
① 決定版三島由紀夫全集34
著者 三島由紀夫
発行 2003.9.10. 2刷2012.10.5.
発行所 株式会社新潮社
所収 無題(「坂口安吾全集」推薦文)
〈初出〉坂口安吾全集 内容見本・冬樹社・昭和42年11月
〈初刊〉三島由紀夫全集33・新潮社・昭和51年1月
②「堕落論」青空文庫
2006年1月11日作成 2012年5月19日修正
著者: 坂口安吾
底本:「坂口安吾全集14」ちくま文庫、筑摩書房1990(平成2)年6月26日第1刷発行
底本の親本:「堕落論」銀座出版社 1947(昭和22)年6月25日発行
初出:「新潮 第四十三巻第四号」1946(昭和21)年4月1日発行
③「天皇陛下にさゝぐる言葉」
青空文庫 2007年2月18日作成
著者: 坂口安吾
底本:「坂口安吾全集 06」筑摩書房 1998(平成10)年7月20日初版第1刷発行
底本の親本:「風報 第二巻第一号」
1948(昭和23)年1月5日発行
初出:「風報 第二巻第一号」1948(昭和23)年1月5日発行
④志賀直哉, 志賀直哉全集 第七巻, 岩波書店, 1999.6.7. [12]
「天皇制」1946.4.1.「婦人公論」]
⑤『三島由紀夫 石原慎太郎 全体話』
2020.7.25.初版発行
著者: 三島由紀夫 石原慎太郎
発行所: 中央公論社
引用した「天皇と現代日本の風土」は、初出『論争ジャーナル』昭和43年2月号 底本:『中央公論特別編集 三島由紀夫と戦後』
⑥監督 豊島圭介, 『三島由紀夫vs東大全共闘〜50年目の真実〜』[37]
1969.5.13.東京駒場キャンパスでの三島由紀夫と全共闘学生の討論会のドキュメンタリー, 2020.3.20.
xxii 人工言語エスペラントの創案者ザメンホフは、エスペラントを完璧なものと思っていた訳ではなく、それが変化していく事を全面的に否定してはいません。しかしザメンホフが認める変化はとても限定的です。
エスペラントの改造案による混乱とエスペラント運動の分裂の危機のあと、以前の著作から編纂された「エスペラントの基礎」への序文(1905年)のなかでザメンホフは
国際語の順調な前進のためには
明確に規定され、何人にも不可侵の、ぜったいに変更を許さない言語の基礎の存在が必要であると述べています。
「国際共通語の思想 エスペラント創始者ザメンホフ論説集」
そしてその上で
エスペラントが確実に存続し使用され、個々の気まぐれや議論に左右されないことを保証する日が来たら、そのときには各国政府の合意の下に選出される権威ある委員会が、この言語の基礎に要望のある変更を必要あれば最終的におこなってもよい。
「国際共通語の思想 エスペラント創始者ザメンホフ論説集」
とその基礎への変更の可能性を、限定的にだけ認めています。
そしてエスペラントについて
基礎は厳重に不可侵であるが、たえず内容を充実させるだけでなく、たえず改良し完成へ向かう可能性がじゅうぶんにあるのだ。基礎が不可侵ということは「そのような完成の過程が、恣意的で内輪揉めによる破滅のもとになる破壊や変更や、これまでの文献を無価値にしてしまうような改変に頼るのではなく、混乱も危険もない自然の道にしたがっておこなわれていく」ための保証となっているのである。
「国際共通語の思想 エスペラント創始者ザメンホフ論説集」
と述べています。
しかし「自然の道」にしたがったときに、その変化が言語の基礎にまで及ばないという保証はないのではないだろうか?拙論で引用したソシュールの指摘はその事を示しているように私には思われる。
引用文献: 「国際共通語の思想 エスペラント創始者ザメンホフ論説集」L.L.ザメンホフ[著・述]水野義明[編集・訳]
1997年6月10日第1刷発行
著者: Lazaro Ludviko Zamenhof
訳者: 水野義明
発行所:株式会社 新泉社

参考文献:: 「ザメンホフ |世界共通語《エスペラントを創った医師の物語」
2005年1月24日 第1刷
著者: 小林司
発行所: 株式会社 原書房
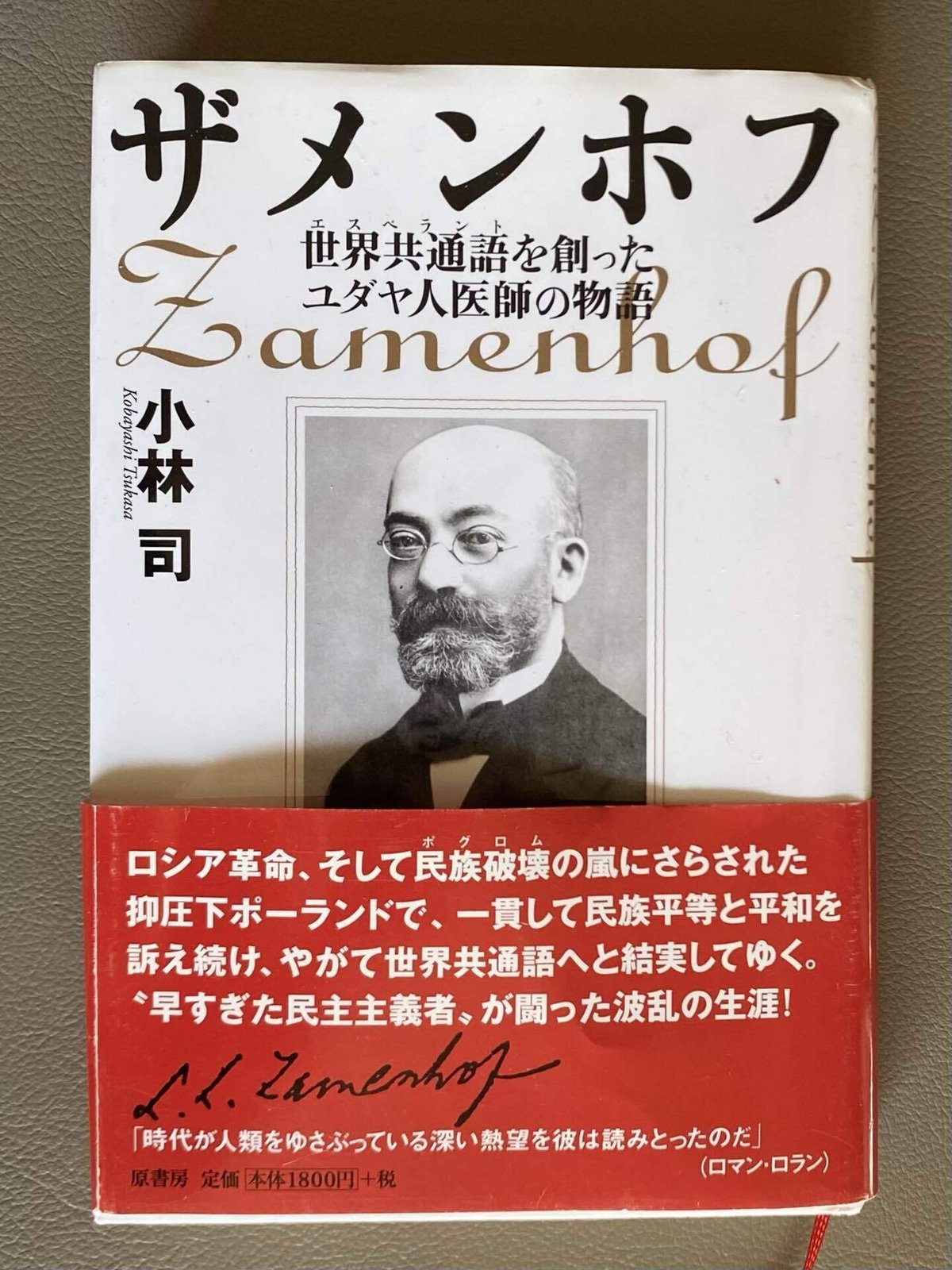
xiii 日本の降伏文書調印以後にGHQにより占領された地域においては、ポツダム宣言に基づく間接統治が大枠では決まっていたとはいえ、占領初期には混乱もあり、1945年9月2日に示され、日本側のGHQとの折衝もあり、公表される事なく終わった布告第一号の中には
第五条「軍事管理期間中ニ英語ヲ以ッテ一切ノ目的ニ使用セラルル公用語トス」
と云うような文言も確かにあった
これは
「本官ハ連合国最高司令官トシテ賦与セラレタル権限ニ基キ、茲ニ日本国全領域竝其ノ住民ニ対シ軍事管理ヲ設定シ、左ノ占領条件ヲ布告ス」
と始まり
第一条で
「行政、司法及立法ノ三権ヲ含ム日本帝国政府ノ一切ノ機能ハ、爾今本官ノ権力下ニ行使セラルルモノトス」
としているように
一時的にせよ間接統治ではなく、GHQによる直接的な軍政を敷く事を前提としており、その事に主眼がある。
第五条はそれに付随するもので、拙論で取り上げた「外国語が日本の国語になる」と云うこととは少し意味合いが異なるし、すぐ取り下げたところから見ても、本文中でも論じたように、英語を日本の公用語にすると云うような政策が実施された可能性は殆どなかったものと思われる。
とはいえ、もしこの布告が実際に出されていたら、日本国内に大きな混乱をもたらしていたであろう事は想像に難くない。
引用文献: GHQ
1983年6月20日第1刷発行
著者: 竹前栄治
発行所: 株式会社 岩波書店

xxiv 作家の津原泰水氏は2018.12.6.にTwitter(現X)上で
僕がそれなりにGHQ通なのは回し者だからではなく、戦後巻き起こった「日本の公用語・正式表記」論議を調べた経験から。GHQ民間情報教育局(CIE)の人類学者ペルゼルは、日本の民主化の遅れの原因を読み書き能力に求め、表記のローマ字化を主張したが、識字率調査の結果を知り断念。100%に近かった。
と述べた後
同時期、志賀直哉は随筆「国語問題」で「日本は思ひ切って世界中で一番いい言語、一番美しい言語をとって」としてフランス語の公用化を推した。僕はこれを、他国語を積極的に受け容れれば、日本語が禁じられはしまいと予測しての、一種の囮作戦だったのではと考えている。志賀は仏語を話せなかった。
とコメントしています。
前半部分はともかく、後半部の志賀直哉の「国語問題」に関する考えは、拙論と同じではないが、それを一つの作戦として捉えているという点で、類似した方向性がある。
拙論を書くにあたっては、その動機として、志賀の「国語問題」について、それを作戦として捉える見方が全く見受けられない事に対する違和感が強くあった。
津原泰水氏の発言を知らなかった事は全く私の不覚の致すところです。
本日(2024.1.3.)この発言を見つけた時、私は嬉しくなり、後先考えずに、あわててコメントを返してしまった。しかし、津原泰水が2022.10.2.に亡くなっている事をすぐに知った。
ご冥福をお祈り致します。
津原泰水氏Twitter(現X)
https://x.com/tsuharayasumi?s=21
戦後のローマ字化政策の流れについては注xxviiに引用を元にまとめました。
xxv 柄谷行人は「階級について」の中で
自我あるいは意識は、中間階級(これを中産階級と呼ばないのは、中間性を強調したいからだ)の意識であって、この階級は支配階級による禁止を逆に積極的に内面化する。
と述べた後、有島武郎について
彼にとって、書くことはこの「中間にある」意識を転倒することであり、日常の有島とは似ても似つかぬ凶暴な官能的な世界を実現することである。
と述べ、志賀直哉については
おそらく、志賀直哉だけが彼らのような「意識」から自由であり、いわば「無意識」の作家だった。だが、志賀もまた内村鑑三の門下に属した時期がある。
とし、志賀と有島について
したがって、この二人の棄教者が、白樺派のなかでアウトサイダーだったことは偶然ではない。
と2人の親近性を示唆しつつも
後段で有島武郎について
おそらく有島は最も深刻にキリスト教に内面を喰い破られた人間であり、それを転倒することこそが「書く」ことに結実していった唯一の作家だといってさしつかえない。
と有島の特異性を強調している。
これはとても納得のいく分析であると思う。
引用文献: 新版 夏目漱石集成
2017.11.16.第1刷発行
著者: 柄谷行人
発行所: 株式会社 岩波書店
引用した本著所収の「階級について」の初出は「文体」1977年秋創刊号

xxvi 芥川龍之介の云う
人々の心裡のうちに、隠れた
神秘を描こうとすると、大体において、それを誘き出すか(怪談)、分析するか(心理学)の主に2つの方法に収束していくように思う。
それは芥川が述べたように
笑ふ可き「怪談」を繰り返すか、さもなければ、幼稚なカテゴリイの中に徘徊するか
のどちらかか、その混合になりがちである。
優れた作品でも、この2つの方法を避ける事は難しい。それは近年の作品を見てもわかる。
吾峠呼世晴の「鬼滅の刃」や諫山創の「進撃の巨人」のような優れたヒット作が、怪談と多様な心理学的・精神医学的カテゴリー(*1)との混淆である事は、一見して明らかであるように、私には思われる。
両作品は、驚くほどさまざまな学術的知識の宝庫でもある。
それは私に泉鏡花の「高野聖」や芥川龍之介の「河童」を想起させる。
これらは全て
笑ふ可き「怪談」
とか
幼稚なカテゴリイの中に徘徊
といって片付けられるようなものではなく、たいへん優秀な作品であるし、エンターテイメントとして楽しめる。
しかしそのようなものからはこぼれ落ちてしまう神秘を、芥川が志賀直哉の「濁った頭」にはじまる一連の作品から感じ取ったこともまた真理であると思われる。
改めて、本文中に引用した芥川の言葉を載せておきます。
神秘が、古の希臘の神々のやうに、森からも海からも遂におはれて、人々の心裡のうちに、隠れたのは、今更らここに云う迄もない。−神秘を解こうとした作家は、日本にも、少なくない。しかし、彼等の多くは笑ふ可き「怪談」を繰り返すか、さもなければ、幼稚なカテゴリイの中に徘徊するか、その二途を出ずにゐたのである。翻つて、「濁った頭」にはじまる作品のseriesを見ると、ここに描かれた神秘は、いづれも殆直下に、常人の世界に迫つて来る神秘である。「濁った頭」の末節に於て、津田のみた林間の幻影の如きは、明に「怪談」を離れた神品であつた。
(*1 )ここで芥川の言葉と関連させて用いた心理学的・精神医学的カテゴリーとは、現在疾病等の診断基準で用いられているカテゴリー(分類)だけではなく、歴史期的に変遷してきた多様な分類を意味する。それは典型的事象として語られてきたあらゆるものを含む。人の内面を描こうとした時、こうしたカテゴリーから一切無縁である事はもはや困難であると思われる。
引用文献: 芥川龍之介, 芥川龍之介未定稿集, 葛巻義敏編: 岩波書店, 1976.6.30.第四刷、1968.2.13.第一刷発行.
[原典:1914年〜15年]
xxvii 本文中にも上げた茅島篤「国語ローマ字化の研究 改訂版ー占領下日本の国内的・国際的要因こ解明ー」では綿密な調査と検討を経て
最終章では
アメリカ側からみたローマ字化の主張根拠
として
(一)軍事占領下の検閲に役にたつ、(二)国語表記の複雑さ、(三)国語(殊に漢字)の学習負担、(四)日本人の再教育・日本の民主化の一環、(五)日本人の識字率に対する疑問、(六)国語に内在する軍国主義的・国家主義的性質、(七)文字の大衆化、(八)国際社会への参加・国際理解への助長、(九)知識と思想の国境を超えた伝播、(一〇)音声表記でも立派な文学は可能、(一一)文字機械利用上の利便性、つまり経済性、(一二)文字数が少なく、短音文字で表記に都合がよい
など多様な論拠が
有機的につながって
いたこと
また
CI&Eと使節団の間、および占領前と占領後では視点も異なり、当然異論もあった
ことを述べ、その複雑さを明示し(CI&Eは民間情報教育局。使節団はアメリカ教育使節団)
後段でローマ字化へのアメリカ側の動向をまとめています。
CI&E教育課では、占領当初、(略)ロバート・K・ホール海軍大尉を中心に、国字ローマ字化にむけて、精力的な調査が行われた。(略)一方使節団も、国語の簡易化、つまり漢字制限やかなづかいの改革は過渡期のものにすぎないとみた。CI&Eでの国字ローマ字化問題は、使節団が帰国後の約一カ月半後に持たれた同局での特別会議で、承認されず一応終止符を打つことになった。けれどもCI&Eでは、その後も国語改革担当部署を占領後半まで設置し、国語簡易化顧問にハルパーン、ペルゼル(両人とも個人的にはローマ字論者)をおき、国語審議会の会議に出席するなどして、国語改革自体には関心を示し続けた。そして四八年には、CI&Eは日本側を指導する形で、使節団が残していった実証的研究の宿題ともいえる「読み書き能力調査」を実施した。しかしこれは結果的に、日本の識字率の高さを証明するものとなり、極く一部の人々の漢字の運命の憂慮は杞憂となった。
そして
ローマ字化が実現しなかった背景としては、まず国民内部の盛り上がりの欠如にあるが、日本占領が公式には連合国による間接統治で、米国側、占領軍上層部にその確たる意思がなかったことが挙げられる。
としています。
拙論では志賀直哉がエッセイ「国語問題」を書いた占領初期の国語ローマ字化政策についてのみ簡単にしか触れなかったが、実際にローマ字化の政策がどのような論拠でどのように進んでいったのかは、拙論とも無関係とはいえず、重要な問題であると感じたため、長文を引用させていただきました。(更に詳しくは引用文献に精細に述べられています。)
この引用をする必要性に気が付いたのは、はーぼさんの記事↓でのコメントのやり取りがあったおかげでした。私の不躾なコメントに真摯に答えてくださったはーぼさんに感謝します。
引用文献: 茅島篤, 『国語ローマ字化の研究 改訂版 ー占領下日本の国内的・国際的要因の解明ー』, 風間書房, 2009.3.31.改訂版第1刷発行(2000.3.15.初版第1刷発行).
xxviii 日本は外来文化を日本化して受容するという芥川龍之介等の視点は、間違いであるとは勿論言えない。
それは仏教の伝来や明治期の西洋文化の受容といったことばかりではなく、私の生きた時代にも多く当てはまる。
レベッカとマドンナ
例えばブレイク後の第1期レベッカのNOKKOの衣装には、シンディ・ローパーを思わせるものと混ざり合いつつも、キャバレーのダンサー・ストリッパーあるいは娼婦の服装を私に連想させるものが幾つかある。映画「フラッシュダンス」("Flashdance"1983年公開)を知る彼女が、その事を意識していなかったとは、私には思えない。(*1)
これは悪い事とはいえない。社会から蔑視されてきた人々のファッションや言葉をあえて使って、表社会で隠されていたものを表舞台に上げる。そういった事こそ、アーティストの真骨頂ともいえる。しかし例えばマドンナの「Like A Virgin 」のMVの衣装も、私に同様のことを連想させるが、そこでは前半の歌詞が、その人物の存在あり方を強く暗示している。だからこそ、Like A Virginという言葉も生きてくる。
Like A Virgin / Madonna
それは私に、ある不思議な客に惹かれていく女郎を描いた山本周五郎の短編小説「夜の辛夷」(*i)を連想させる。独特のリアリティが底にある。(*2)
対して、レベッカの歌詞の多様な比喩は、どれも全く空想的なものであり、何ら具体性を感じさせない。マドンナの歌に常にあるラディカルさは、レベッカにはない。それは変容し無害化されている。(*3)
SPEEDとTLC
他の例をあげれば、TLCに憧れたというSPEEDがある。1stアルバム『Ooooooohhh... On the TLC Tip』の時のTLCはTeenagerを思わせる子供っぽい格好をしている。しかし彼女らは既に20才を過ぎており、幼さを演じているのである。(*4)
1stアルバム所収
What About Your Friends / TLC
Ain't 2 Proud 2 Beg / TLC
そんな中、メンバーの1人 Left Eye は左目にコンドームで作った眼帯をしている。そのような格好で彼女らは Safe Sexを訴えた。
TLC talking about safe sex
そのようなラディカルさは、デビュー当時本当に子供だったSPEEDのメンバーには求められる訳もない。SPEEDのデビュー曲「Body & Soul」は、初期のTLCを連想させるところがあるが、TLCのラディカルさはSPEEDにおいてやはり変容し無害化されている。(*5)
Body & Soul / SPEED
「Body & Soul」がリリースされたのは、1996.8.5.で、既にTLCの2ndアルバム『CrazySexyCool』(1994.11.15.)が出た後である。SPEEDのデビューアルバム『Starting Over』とセカンドアルバム『RISE』の曲とファッションの中には、より大人っぽいスタイル、『CrazySexyCool』の頃のTLCを思わせるものもある。しかし『CrazySexyCool』のエッセンスとメッセージは尚のこと、当時のSPEEDのメンバーには表現するのが難しかったのではないかと思う。実際に大人だったTLCのメンバーに比べて、それは背伸びをした子供の表現であった。
1stアルバム『Starting Over』所収Steady / SPEED
2ndアルバム『RISE』所収White Love / SPEED
『CrazySexyCool』所収Waterfalls / TLC
『CrazySexyCool』所収Creep / TLC
レベッカとSPEEDの魅力の先に
レベッカとSPEEDの音楽とパフォーマンスはどちらも大変優れていて、抗えない魅力がある。(それは鎌倉仏教のような日本化された仏教が魅力的なのと軌を一にする。)以後に与えた影響も大きい。
Raspberry Dream / Rebcca
NOKKOのパフォーマンスは圧巻である
Wake Me Up! /SPEED
今観ても清新である
しかしそのことが返って、彼女らに影響を与えた海外の音楽家の真の姿を見えにくくし、本来あった歌の力を無効化しているように思う。上述したような外来文化の日本化の現象は一長一短である。このような文化受容の形は、異文化の受け入れを容易にし、日本の同一性を揺るがすような軋轢を生み出さない。それはただのファッションとして、NOKKOとSPEEDの特異で実力ある個性を彩なしているのである。
それは日本の現実を反映していると同時に、覆い隠してもいる。
それらは例えば八木澤高明の「黄金町マリア 横浜黄金町 路上の娼婦たち」(*ii)にあるような日本の性の現実を誘き出すものには、決して繋がる事はなかった。
※上述の論はレベッカ及びNOKKOとSPEEDを日本の異文化受容の一例として見るという一つの試みであって、レベッカ及びNOKKOとSPEEDを貶めようとする意図は何らありません。
*1〜6[注(引用文献、参考文献・音楽・映画含む)]
(*1)「Nokko This Town, New Yorkフォト&エッセイ」の中で、ダンス・スクールの光景を
その光景ってさ、あの映画〈フラッシュ・ダンス〉の一場面に出てきたと思わない?
と語っている。
映画「フラッシュダンス」("Flashdance"1983年公開)の主人公はキャバレーでセクシーなダンスを踊りながらダンスの練習に励んでいて、ストリップ・クラブへの出演の勧誘を受けている。彼女はキャバレーでのショーの為にたくさんの衣装を揃えている。
また1980年代頃のニューヨークの娼婦のアイコニックでステレオタイプな姿は、映画「大逆転」(("Trading Places" 1983年公開)や「プリティ・ウーマン」("Pretty Women "1990年公開)に良く現れている。
映画「Trading Places」邦題「大逆転」1シーン
映画「Pretty Women」1シーン
引用文献: 「NOKKO THIS TOWN, NEW YORKフォト&エッセイ」発行日:1986年6月10日発行所: 株式会社シンコー・ミュージック

(*2)「 Like A Virgin」の歌詞も多くのレベッカ曲の歌詞も、何かを仄めかしているだけで、はっりした事は述べられてはいない。それでいて、両者の喚起するイメージは全くちがう。レベッカのファンシーさと違って、「Like A Virgin」は現実へと繋がる強度を持っている。マドンナの2ndアルバム『True Blue』収録曲「Papa Don't Preach」でのリアルな表現を見れば、マドンナの目指していた方向性がよく分かる。これは同アルバムの「La Isla Bonita」などにも共通するものと見るべきだし、 1stアルバムから一貫したものと考えるべきであると思う。
「Papa Don't Preach」
「La Isla Bonita」
マドンナは常にアメリカのラディカルな良心であり続けたて来た思う。
『Like a Prayer』所収 Like A prayer / Madonna
Madonnaインタビュー(日本語字幕付き)
なお中で触れた山本周五郎の「夜の辛夷」は、小学館文庫 「新編傑作3 夜の辛夷」山本周五郎 竹添敦子編 2010年10月11日 初版第一刷発行 発行所 株式会社 小学館 に収録されています。初出は、〈週刊朝日別冊〉(1955年4月、時代小説特集号)です。
(*3)NOKKOがマドンナの影響を強く受けていた事は明らかである。「Rockin,On Japan Mar.1992 Vol.58」のインタビューでNOKKOはそれまでの活動を振り返る中で
そうした人生の決断を経て、ノッコ自身の具体的な方法論はどう生まれてきたのか、と。
問われ
「バンドで?『私マドンナみたいになりたい』っていう短絡的な(笑)、そっくりな"ラブ・イズ・キャッシュ"ーもう汚点だわ私、一生の(笑)。でも、そういうのもどうでもよかったんだよね。何か知んないけれど演れさえすれば」
と答え
少し後で
「だってやっぱりパクリのフレーズ沢山あったしさあ。だけど何て言うのかな、そうした原曲の威力を取り除いても凄くパワフルな物がでも感じられたのね。だから私はこっちの方がノレたし」
と言い
だから、マドンナ演りたくなったから素直にマドンナやってみた、みたいな。
と問われ
「そう。でもアルバムがそればっかりだと、自分の一部分しかないからーバレエで言ったら1幕があって2幕があったみたいな、いろいろな場面があっていろんな衣装があったという世界を、全部一人で演りたかったのね。」
と答えている。大変興味深い。
このインタビューの発言からも、レベッカは海外文化の日本化の一例として上げるのにふさわしいと思える。
特に
「そうした原曲の威力を取り除いても凄くパワフルな物がでも感じられたのね。だから私はこっちの方がノレたし」
と言う発言はとても意味深い。
そしてNOKKOかバレエのステージを意識していたとすると、多様な衣装を着こなすのも納得がいく。
彼女は様々な人物を演じようとしていたのかもしれない。
引用文献: 「Rockin,On Japan Mar.1992 Vol.58」月刊ロッキング・オン・ジャパン3月号 第6巻3号通巻58号 平成元年2月20日第三種郵便物認可
平成4年3月16日発行(毎月1回16日発行)
発行=株式会社 ロッキング・オン

(*4) TLCは、2ndアルバム『CrazySexyCool』(1994年)で既に「幼さを演じる」路線から脱却している。当然のことであろう。しかし、彼女らは、女性アーティストに求められるステレオタイプな女らしさに一貫して抗い続けた事も確かである。(時にはドレスアップする事もあるとしても)
『FanMail』所収 No Scrubs / TLC
初期のスタイルは、その流れの始まりである。それは幼なさといっても、少女らしさではなく、少年ぽさである。
(*5)JUNON (ジュノン) 1997年 9月号のインタビューでSPEEDの上原多香子は
「私たちは高い目標を持ってるんですよ。TLCみたいになりたいっていう目標。アルバムのジャケット写真を撮った時、カメラの横でTLCのビデオを流してたんです。だからみんな、見つめた目が真剣になってる。目標を持ってやってるっていうのはすごくパワーになりますよね。」
と語っている。
この初々しいポジティブな姿勢は素晴らしい。私が行った分析は、決してこういったSPEEDの良さを何ら否定するものではありません。
引用文献: JUNON (ジュノン) 1997年 9月号
発行: 主婦と生活社 月刊(毎月23日)
文献(*i)(*ii)
(*i)小学館文庫 「新編傑作3 夜の辛夷」山本周五郎 竹添敦子編 2010年10月11日 初版第一刷発 発行所 株式会社 小学館 所収短編「夜の辛夷」の初出は〈週刊朝日別冊〉(1955年4月、時代小説特集号)です。

(*ii)「黄金町マリア 横浜黄金町 路上の娼婦たち」2006.11.8.初版第一刷発行著者 八木澤高明発行所 ミリオン出版株式会社

xxix 「病床にて」の中で徳田秋声は
何が一番親しみがあるかと言えば、それはおそらく漢文で、次が英語 ー 日本語は不幸にして最も希薄な感じしか与えないのことは、私のその時分のの教育がさうであつたためもあるでせうが、実際に考えてみると、日本語にはこれと云って懐かしい何にもがないことは争えない事実です。
と言っている。
「あらくれ」[1915年(大正4年]のような当時の日本を代表する言文一致体の小説を書いた徳田秋声のこのような発言は、当時の多くの人にとって、国語(標準語)・言文一致体がいかに困難なものであったのかをうかがわせる。
大杉重男は「森有礼の弔鐘 ー 『小説家の起源』補遺」の中では、上述した徳田秋声の発言を他の発言と合わせながら
国語が英語になったとしても、秋声は実践的には困るかもしれないが、心情的にはまったく痛みを感じないだろう。
とし
この秋声の日本語に対する冷淡な態度は、第二次大戦後に志賀直哉がフランス語を国語にするべきだと述べた事が、決して志賀個人の夢想ではなかった事を示している。
と志賀と並べて論じている。
しかし志賀よりも10年以上早い明治4年(1872年)生まれで、金沢で幼少期を過ごした秋声と、当時の日本で例外的に標準語に近い言葉を話していたと思われる東京の山手で育った志賀とを同列に論じて良いものだろうか?
それは拙論の中で論じたように、志賀を育んだ言葉にも多様な要素があり、東京の山手の言葉と単純に括れないとしても、なお志賀と秋声の間の懸隔は決して小さくはなかったのではないかと思われる。
柄谷行人は「文学について」のなかで
「言文一致」は、けっして「言」を「文」にすることではなく、あらたな「文」の創出にほかならなかった。
さらに重要なことは、「言文一致」が「言」そのものの創出でもあったということである。
と述べた後で
このことは、「標準語」と「方言」の区別において、端的に示される。いうまでもなく、「標準語」は、明治の制度が中央集権的に確立されたことを言語的なレベルで示すものである。標準語は音声言語においてある。それまで、現在の意味での方言なるものはなかった。どの地域の人間も書くときは共通の書き方をしたのであり、音声言語における「標準」などはなかったのである。だが「言文一致」において、「言」そのものの標準化が強いられる。地方の人間にとって、「言文一致」は、「言」の習得をしか意味していない。
と述べている。
徳田秋声にとって標準語・言文一致体は、このような
「言」の習得
であったであろう。
そのような要素は、志賀直哉にとってももちろん皆無ではないが、拙論で論じたように他地方に住んでも東京の下町の言葉を守り続け、言文一致体をさらに研ぎ澄ませていった志賀の感じた国語(日本語の標準化)に対する困難は、徳田秋声の感じたものとは、相当に異質なものだったのではないかと思われる。
正宗白鳥の例を上げながら
明治の知識人にとって、自分たち自身が開発し創造してきた言文一致文は、英語の文章と取り替え可能なものであり、決して自明の前提ではなかった。
と論じ
「母国語」というもののフィクション性
を云い
志賀の言葉が示しているのは、今ここで日本語を使っていることの根源的偶然性である。
とする大杉重男の議論は一面の真理ではあるかもしれないが、それは先に述べた志賀と秋声の違いと、志賀の発言が戦後まもないGHQの占領下に発せられたことの意味合いを無視したものであり、行き届いた議論であるとは言えない。
大杉が述べているように
「国語」という概念そのものが、明治において「学校」と同じく制度的に人工的に構築された
のは確かであろう。
しかしそのようなにして生まれた国語は、それが定着すれば、多くの人にとって自然なものに感じられるだろう。それを自然なものとして捉える目から見れば、徳田秋声の発言は奇異なものに映るだろう。
志賀直哉の感性は、国語を人工的なもの感じる徳田秋声のような人と自然なものと感じる人との中間に位置するように、私には思われる。
引用文献:①「徳田秋聲全集」第20巻(随筆・評論Ⅱ 大正4年〜大正14年) 2001.1.18.初版発行
著者 徳田秋聲
発行所: 株式会社 八木書店
引用した本書所収の「病床にて」の初出は大正9年4月1日「新潮」
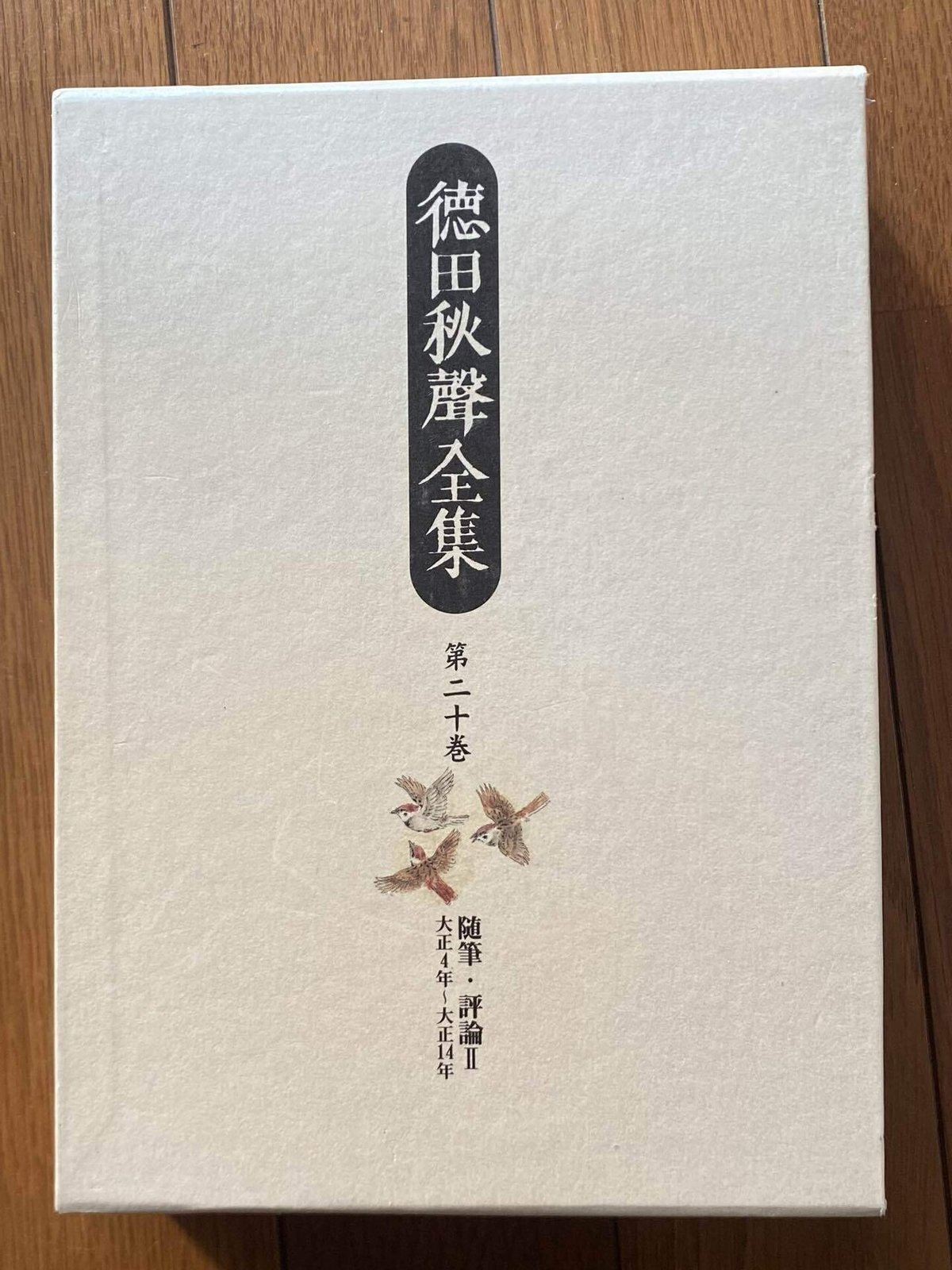
②「重力01」初版第一刷発行 2002年2月28日
発行者: 「重力」編集会議
発行元:株式会社 青山出版社
P234. 大杉重雄「森有礼の弔鐘 ー 『小説家の起源』補遺
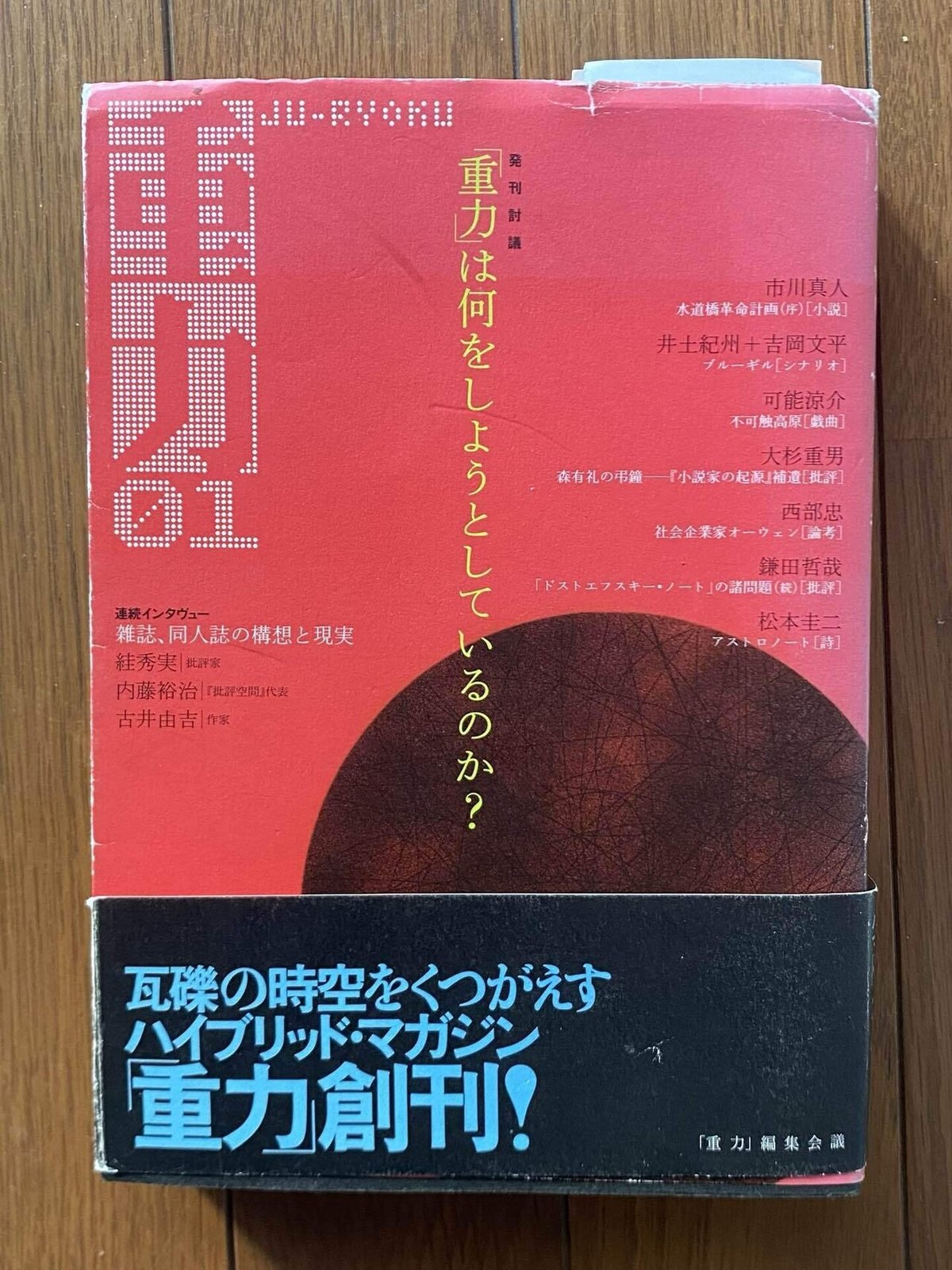
③ 新版 夏目漱石集成
2017.11.16.第1刷発行
著者: 柄谷行人
発行所: 株式会社 岩波書店
引用した本著所収の「文学について」の初出は「國文學」1978年5月号

xxx 石森延男と共に、戦後最後の国定国語教科書の作成に携わった沖山光は「占領下における魂の雄たけび」の中で
終戦と共に石森先生を残してあと数人の国語の監修官はすべて追放処分。
国語教育は、思想育成につながることは、進駐軍の検討ずみのことである。だからこそヒューマニストの石森先生だけが追放の処置から除かれている。
これからの教科書で育っていく青少年の日本人としての自負は、国語教科書によって培われていく。このことは、何よりも進駐軍当局が知りぬいている。だからこそ、国語の監修官をねこそぎにしたのである。
と当時の状況を述べた後
全知全能を傾けて、日本の子どもたちに、日本のことばを通して、日本人としての心情を培っていかなければならない。何としてもこの焼土から立ち上がってもらわなければならない。
とその意気込みを語っている。
その後も
町行く進駐軍の兵士たちにガムをねだるような子どもたちに、何としても日本人としての自負を芽生えさせてやらなければならない。
焼土の中に芽生えた草のように、咲き出た一輪の花のように、根強く生きるのだ。自分のことばを失ってはいけない。明るいきれいな日本語。これを忘れてはいけない。
と力強い言葉が続く。
その上で後段では占領軍の民間情報局との難しい交渉について触れた後
世人は、占領によって、すべてのものがアメリカの押しつけであると言う人もあるが、ここに私が取りあげた一シーンをもってしても、アメリカは決して押しつけてきたのではない。お互いに良識ある文化人として、誠意をもって接し合ったのである。まことに文化の闘いである。こちらが善戦善処すれば、相手もまた然りである。あとに何のしこりも残さない。
と述べている。
ここにはGHQと対峙した良識ある日本の知識人層の姿勢と心持ちがよく現れている。
引用文献: 石森延男国語教育選集第二巻
昭和53年(1978年)9月10日発行
著者: 石森延男
発行所: 光村図書出版株式会社
引用個所は【解説】「占領下における魂の雄たけび」沖山光

xxxi 日本の西洋文化受容については、データを用いながら分析を加えた小坂井敏晶の「異文化受容のパラドックス」(1996年)という優れた論考がある。この著書の核となる視点は、「社会心理学講義」小坂井敏晶(2013年)の中でも繰り返し取り上げられている。
中国文化がいかに日本独自のものに変わっているかということについては、中国から日本に移り住んだ際に感じた疑問を起点に、中国と日本の文化を比較検討した彭丹の「中国と茶碗と日本と」(2012年)が示唆に富んでいる。
文献
①「異文化受容のパラドックス」
1996年10月25日 第1刷発行
著者: 小坂井敏晶
発行所: 朝日新聞社

②「社会心理学講義 〈閉ざされた社会〉と〈開かれた社会〉」
2016年7月15日 初版発行
著者: 小坂井敏晶(こざかい・としあき)
発行所 株式会社 筑摩書房
③「中国と茶碗と日本と」
2012年9月5日 初版 第一刷発行
著者: 彭丹
発行所: 株式会社 小学館

xxxii 大杉重男は志賀直哉の「国語問題」について
志賀の言説の中で真に批判に値する部分があるとすれば、それはこの国語として採用された英語ないしフランス語が日本化され得ることへの自信である。それは「吾々は日本人の血を信頼し」という「日本人の血」への信頼とつながっている
としている。
しかし志賀は、英語やフランス語が日本に導入された場合、さまざまな植民地で現実に起きている言語の混淆が、日本でも起きるであろう事を述べているのに過ぎない。それをよりポジティブに捉えようとしているところがあるとしても。
拙論でも論じたように、志賀の「日本人の血」への信頼は、もっと大きなもの、言語の強制に伴うあらゆる困難に対して向けられているだと私は思う。
「重力01」初版第一刷発行 2002年2月28日
発行者: 「重力」編集会議
発行元:株式会社 青山出版社
P234. 大杉重雄「森有礼の弔鐘 ー 『小説家の起源』補遺

xxxiii イ・ヨンスクは『「国語」という思想 近代日本の言語認識』の中で森有礼が日本の国語として採用を主張した英語が現実に使われている英語そのままではなく
簡易英語(simplified English)
と呼ばれるものだった事を指摘しています。
同書によると
森は、英語には「正書法に語源あるいは発音にもとづいた法則、規則、秩序が欠けていること、大量の不規則動詞があること」が「英語の日本への導入」を困難にしていると考えた。そこで森は、「日本国民の使用のために英語からすべての不規則性を取り除くことを提案する」にいたる。たとえば、動詞活用ではsaw/seenやspoke/spokenのような不規則変化を廃止して、seed, speakedとすること、また、正書法に関しては綴りと発音を一致させるために、thoughではなくthoと、boughではなくbowと書くことを森は提案している。
という。
このような簡易英語の発想は、拙論でも触れた人工国際言語エスペラントに近いと言えるかもしれない。
引用文献: 『「国語」という思想』
1996年12月18日 第1刷発行
2002年9月5日 第11刷発行
著者: イ・ヨンスク
発行所: 株式会社 岩波書店
引用した個所の内容は、本書の注によれば、「森有礼全集 第1巻」からの引用に基づく。森のアメリカの言語学者ホイットニー宛書簡より。

xxxiv イ・ヨンスクは『「ことば」という幻影』の中で
志賀直哉は従来の「国語改革」の試みがきわめて「不徹底な改革」「中途半端な改革」であると考えていた。志賀によれば、ローマ字運動や仮名文字運動がいっこうに成功しないのは、日本語に「致命的な欠陥」があるからである。
明治以来の日本では、いわゆる「国語国字問題」が大きな論争の的となってきた。改革派は、表音式仮名づかい、漢字廃止、言文一致などをつねに主張してきたが、そのつど「国語の伝統」を信奉する保守派の反撃にあって、「国語改革」の芽はつみとられてきた。結局のところ騒々しい論争のあとにはなにも残らなかった。志賀はこうした近代日本語の歴史にいらだったのである。
とし
そして志賀にあるのは
日本語への絶望感であり、「徹底的な」改革を望む断固たる決意のほうである。
と述べている。
しかし
騒々しい論争
の後、多様な作家達の試作によって何とか形になった言文一致体を、志賀は一度は受け入れて、それを研ぎ澄ませていったのである。
その上で志賀が国語に持った
いらだち
の強さは、言文一致体を完成へと導こうとした者ゆえの苦悩だといえる。
そのような志賀にとって、戦後の政策として改めて国語の改革を議論することは、もう一度
騒々しい論争
へと逆戻りすることでしかない。そのような事が受け入れ難いのは当然として
果たしてどのような
徹底的な改革
が歴史上行われていたら、志賀は満足できたというのであろうか?
おそらくどのような言語のどのような改革でも、志賀の感じた
いらだち
は言語の標準化において不可避であるように思われる。
「国語問題」で志賀か主張したフランス語の導入は
確かに
徹底的な改革
ではあるだろうが、フランス語も一つの言語に過ぎない以上、それはある意味で人工的な改革の放棄である。
イは志賀がフランス語を日本の国語とする理由として
フランスは文化の進んだ国であり、小説を読んで見ても何か日本人と通ずるものがあると思われる
という志賀の言葉を引用しているが、これはあまりに恣意的な引用である。
この言葉の前に志賀は
外国語に不案内な私はフランス語採用を自信を以っていうほど、具体的にわかっているわけではない
と断っているのだから。志賀の言葉はアイロニックなものであり、フランス語を選んだのは拙論で論じたように、戦術的なものであろう。
そして志賀は少なくともこのエッセイにおいて、母語としての日本語と日本の国語(標準語)を混同するような事はしていない。
志賀が問題としているのは一貫して日本の国語である。
志賀の論を
日本語廃止論
と断ずるのは早計である。
それはここでイ・ヨンスクが志賀と並べて論じている北一輝とは全く違う。
北が否定しているのは、明らかに日本語全般である。
それは日本語の
組織根底
にまで及んでいるのだから。
人工語エスペラントの導入よって、日本語だけでなく
劣惡ナル者ガ亡ビテ優秀ナル者ガ殘存スル自然淘汰律ハ日本語ト國際語ノ存亡ヲ決スル如ク、百年ヲ出デズシテ日本領土内ノ歐洲各國語、支那、印度、朝鮮語ハ亦當然ニ國際語ノタメニ亡ブベシ
(前段で北は國際語にエスペラントとルビを振っている。ここでの国際語はエスペラントを意味する。) (*1)
という北の姿勢は志賀とは根本的に異質であり、似て非なるものである。
それはイがしたように
志賀直哉と北一輝が思う存分表現してしまった「日本語への絶望」
と並置して論じられるようなものではない。(*2)
北が優れたものとして推奨するエスペラントを志賀が支持したとは思えない。
同じ白樺派の武者小路実篤や有島生馬のような熱心なエスペランティストと交流のあった志賀である。エスペラントを推奨するならば、はっきりとそう述べたであろう。
志賀の
仮名書きとか、ローマ字書きとか、そういう運動は大分前からあるが、なかなかものにならない。殊にローマ字運動は知名の人々が随分熱心にそれを続けているにもかかわらず、どうしても普及しないのはやはりそれに致命的な欠陥があるのではないかと思われる。
と云う言葉を素直に受け取るならば
志賀は
イが云うように
ローマ字運動や仮名文字運動がいっこうに成功しないのは、日本語に「致命的な欠陥」があるから
と考えたのではなく
そのような人工的な改革そのものに
致命的な欠陥
があると考えたのだと思う。
人工語エスペラントなら尚更である。
志賀は
「国語問題」の時点では
徹底的な改革を望んだ
どころではなく、あらゆる人工的改革を拒否しているように、私には思われる。
志賀が望んだのは、どうせ不徹底なものに終わらざるを得ない
騒々しい論争
と人工的な改革ではなく、戦術的に導入さへた国際語としてのフランス語と母語としての日本語の自然な混淆であったと、私には思われる。
その意味ではイが 『「国語」という思想』の中で指摘した人工的に改革された
簡易英語(simplified English)
を提案した森有礼とも、志賀の考えは異質であると云えるだろう。(森の簡易英語については注xxxiiiへ)
(*1)エスペラントの創始者ザメンホフは、
国際語そのものは、民族語の力を弱めないばかりか、その反対に民族語をますます強化し反映させる事は確かだ。
といっている。エスペラントを推奨しながら、北一輝の主張はザメンホフの考えとも全く異質である。
(*2)志賀直哉と北一輝はどちらも、1883年(明治16年)の生まれですが、東京の山手で育った志賀と新潟の佐渡で育った北とでは、日本の言語について、おのずと別様の感覚があったのではないかと想像できます。
志賀が「国語問題」を出したのは63才の時、北が「日本改造法案大綱 」を著したのは38才の時でした。
北は1937年(昭和12年) 二・二六事件の理論的指導者の内の一人とされ、死刑判決を受けた。58歳没。志賀が「国語問題」を出した1946年(昭和21年)まで生きる事はかなわなかった。
引用書籍:『「ことば」という幻影――近代日本の言語イデオロギー』〔電子書籍版〕
2013年9月15日発行
著者:イ・ヨンスク
発行所:株式会社明石書店
電子書籍版の元本:
『「ことば」という幻影――近代日本の言語イデオロギー』2009年2月7日初版第1刷発行
日本改造法案大綱
著者: 北一輝
青空文庫
2012年10月12日作成
底本:「北一輝著作集 Ⅱ」みすず書房 1959(昭和34)年7月10日第1刷発行 1972(昭和47)年8月30日第9刷発行
初出:「日本改造法案大綱」改造社 1923(大正12)年5月9日発行
『「国語」という思想』
1996年12月18日 第1刷発行
2002年9月5日 第11刷発行
著者: イ・ヨンスク
発行所: 株式会社 岩波書店
志賀直哉, 志賀直哉全集 第七巻「国語問題」, 岩波書店, 1999.6.7.
[「国語問題」初出: 1946.4.1.「改造」第27巻第4号]「志賀直哉随筆集」高橋英夫編 [39](岩波書店)(1995.10.16.第1刷発行、2021.1.15.第9刷発行)にも所収:
⑤「国際共通語の思想 エスペラント創始者ザメンホフ論説集」L.L.ザメンホフ[著・述]水野義明[編集・訳]1997年6月10日第1刷発行著者: Lazaro Ludviko Zamenhof訳者: 水野義明発行所:株式会社 新泉者引用した「国際語の思想の本質と将来」は1900年に出されたもの。
xxxv 標準語と共通語
ここで標準語という言葉を用いたのは、標準語という言葉が飛び交った時代の事を想起しながら読んでほしいからです。
現在では標準語に代わって、共通語という言葉が多く使われている。
実際に日本全国で通じる言葉がある以上、それを共通語と呼ぶのは理解できる。
ただ
共通語を大辞林で引くと
②一国のどこででも、互いの思想や感情を伝え合うことのできる言語。わが国では東京語(特にその山の手言葉)がこれにあたる。全国共通語。
とあった後に〔 〕
〔共通語は標準語という用語を避けて用いるようになった語。標準語は全国に共通して用いられるとともに的に整備された規範性の強いものであり、共通語は自然に存在して全国に用いられるものとして区別する考え方による〕
と書かれている。これには違和感を覚える。
現在使われている共通語が
人為的に整備された規範性
によって作られた側面がある事は否定出来ない。
先の文言に沿うと、標準語を共通語と言い直す事は、そういった歴史的事実を隠蔽しかねないのではないかと危惧する。
それは共通語を
自然に存在して全国に用いられる
当然のものとして、受け入れさせる装置として作用している可能性はないだろうか?
もし現在の共通語が標準語に比べ
人為的に整備された規範性が弱まって感じられるのだとしたら、それは過去に強力な人為的な整備がなされた故であろう。
過去の事実について論じる場合は別として、標準語という理念的言葉を殊更に復活させる必要はないし、共通語という言葉を使う事は避けられないとしても、上記のような可能性を念頭に置いて使う必要があるだろうと思う。
追記(2024.2.17):
富岡多惠子との対談の中で、柄谷行人は母語と母国語を区別した上で
もう一つ大事なのは、母語と母国語の他に共通語があるということですね。大阪弁も多様であってね。各地から人が来ていたわけですからね。富岡さんも佐々木幹郎との対談で何度も言われてたけど、たとえば近松、西鶴は共通語で書いていたということ。しかし、あれがむしろ大阪弁でしょう。武智鐵ニが言うように、当時全国で通用したのは、問屋語である。それは江戸時代や経済・交通から見たら当たり前で、それが自然に形成された共通語なんですよ。
富岡多惠子との対談「漫才とナショナリズム」
その言葉をしゃべらないと、交易はできませんからね。武士の言葉というのも、参勤交代で江戸に出てきた武士が互いにまったく通じないので、謡曲や漢文をもとにして共通語を作ったわけですね。しかし、実際の経済になると、大阪の商人が中心だから、問屋語が全国の共通語になっていた。近松、西鶴もそれによっている。だから、今の大阪の人が、大阪弁を自慢するのはバカげている。あれは河内弁にすぎない。大体がふだんは母語でしゃべっていて、交通・コミュニケーションにおいては共通語でしゃべるというのは、これは世界中全部そうなんですよ。
富岡多惠子との対談「漫才とナショナリズム」
と語っている。
ここで述べられているような共通語についてであれば、先に述べた大辞林の〔 〕中の文言とも、とくに大きな齟齬はないだろう。
(柄谷行人は兵庫県尼崎市市、富岡多惠子は大阪府大阪市出身)
引用文献: スーパー大辞林 3.0
編者:松村 明(まつむら あきら)
三省堂編修所 三省堂 2006-2008
Version 4.2.4 (R62)
Copyright © 2008 MONOKAKIDO Co. Ltd.
Tokyo, Japan
All rights reserved.
柄谷行人発言集 対話篇
発行日:2020年11月12日第一刷発行
著者: 柄谷行人
発行所: 株式会社読者人
引用した富岡多惠子との対談「漫才とナショナリズム」
のは1991年6月5日、初出:『すばる』1991年8月号
xxxvi 国語・標準語・言文一致
国語・標準語・言文一致体は、もちろん同じものではないが、この論考の中で、これらを厳密に分けて論じることをしなかった。
日本の近代国家が成立する過程で、これらは相俟って進んだ。それらを厳密に区別して定義することは可能だろうが、そうした時、国語・標準語・言文一致といった言葉が飛び交った時代のダイナミックさは失われてしまうように思います。
Wikipediaの標準語(2024.2.3)では
明治中期から昭和前期にかけて、主に東京山の手の教養層が使用する言葉(山の手言葉)を基に標準語を整備しようという試みが推進された(そのうち最も代表的で革新的だったのは小学校における国語教科書である)。これに文壇の言文一致運動が大きな影響を与えて、「標準語」と呼ばれる言語の基礎が築かれた。
とある。
国語・標準語・言文一致が相俟って進んだ様子がこの短い文からも分かる。
言文一致の代表的論客の一人だった山田美妙は「言文一致論概略」の中で
「若し我々が今日の俗語を此儘
文章に用ゐるなら日本国中で通ぜぬことがあるだろう。」
という想定した言文一致への反論に対して、
小生に限ツては小生が主唱する言文一致を造るに於ては決してどの言葉でも構はず用ゐるが善いとは言ひません。じつに大阪の「さかい」や奥州の「なす」や又は長崎の「ばツてん」などは、其実古語に基づいて居るにせよ、普通の言葉とは言へますまい。又薩摩や隠岐や安房の俗語など、是も古文の変ツた物とは言へ、普通の語法とは言へますまい。普通の言葉とは言はれぬもの、又は普通の語法とは言はれぬ物を構はず文章に用ゐるなら、如何にも不通の害は有りましやう。若し左様為ないなら其様な事は有りますまい。それには普通の言葉を見出し、普通の語法を探出し、それを用いる事さへ出来れば最早十分のことでしやう。
とし
今東京語の性質を精密に吟味してみると実に此言葉ばかりが前の注文に合ふ様です。事実から文を見ても東京語が通ぜぬ度は薩州語や奥州語が通ぜぬ度よりは軽いです。何処でも此東京語が不十分ながらも通用せぬ処は殆ど無い程です。
と述べています。
ここには方言への蔑視と東京語の優位性の意識、俗語に対する普通の言葉・語法という標準語に通ずる志向性が見られる様に思います。
また明治後の日本の国語学の祖ともいえる上田万年は「標準語に就きて」の中で標準語について
一国内に話され居る言語中にて、殊に一地方一部の人々にのみかぎり用ゐらるゝ、所謂方言なるほど者とは事かはり、全国内至る処、凡その場所に通じて大抵の人々に理解せらるべき効力をゆうするものを云ふ。猶一層簡単にいへば、標準語とは一国内に模範として用ゐらるゝ言語をいふ。
と標準語を定義して
後段では
現今の東京語が他日其名誉を享有すべき資格を供ふる者なりと確信す。たゞし、東京後といへば或る一部の人は、直に東京の「ベランメー」言葉の様に思ふけれども、決してさにあらず、予の云う東京語とは、教育ある東京人の話すことばと云う義なり。
言っています。
山田美妙の主張との類似性は明らかだと思います。
そして上田万年にとって標準語は文学や文章と切り離せないものです。
上田は外国の状況について
如何にしてチョーサー、シエークスピヤ等の言語が、英国の標準語となりしか。如何にしてルーテル、ゲーテ等の言語が、独逸帝国の標準語とまで発達し来たりしか。而してコルネーユ、モリエール等の言語、ダンテ、ボツカショ等の言語が、数百年来かの大勢力を有せる羅甸の旧標準語を排斥して、仏に以に皆発生を為すの止むを得ざりしを見る時は、所謂時世に伴う理想の変遷が、如何に言語の中心と文学の中心とを動かすのに力あるかに驚かざるを得ず。
と述べ、日本について
文学者が此感化力に富む東京語を使用して、其大傑作を著はさゞるも、亦遺憾なる一事なりとす。予はある言文一致崇拝者の如く、何もかも俗語に憑拠して、其奴隷となり了り、却つて文学者の尊ふべき、気品という者を悉皆抛棄するが如き形跡あるは、決してほむべき事ならずと信ず。しかれども、此親しき言語の文章法単語法を基礎として、而して其美術上の妙意妙案を此上に仕組みなば、其時には唯に標準語制定上の一大補助を得るのみならず、又一種独特の美文学此間に生ぜずとせんや。
と述べています。
これも
言文一致を造るに於ては決してどの言葉でも構はず用ゐるが善いとは言ひません。
と云う山田美妙と軌を一にしています。
そして、多くの文学者が東京語を元にした言文一致体の作品を書いて行ったことは、歴史が示す通りです。
このような国語・標準語・言文一致の関係について詳しく論じたものに、イ・ヨンスク『「国語」という思想』という優れた著書があります。
引用文献: ①『山田美妙集 第九巻』(全12巻)
2014年5月31日 初版発行
編者: 『山田美妙集』編集委員会
発行所: 株式会社 臨川書店
「言文一致論概略」初出:1888年(明治21年)2月25日発行「学海之指針」第八号及び3月25日発行第九号
②『国語のため』東洋文庫808
2011年4月25日 初版第1刷発行
著者: 上田万年
校注者: 安田敏朗
発行所:株式会社 平凡社
参考文献:『「国語」という思想』
1996年12月18日 第1刷発行
2002年9月5日 第11刷発行
著者: イ・ヨンスク
発行所: 株式会社 岩波書店
xxxvii 国語学・民族学・文学
国語は多義的な言葉である。とはいえ志賀直哉がフランス語にすると言った時の国語が日本の共通語もしくは公用語としての国語である事は疑い得ないだろう。ここでフランス語に置き換えられる事を求められている日本の国語は、言文一致と標準化が進み、ある程度の成功を収めた結果として出来たものである。
時枝誠記は「国語学史」の中で国語を
日本語的性格を持った言語を意味するものと考えたい。換言すれば国語はすなわち日本語のことである。
と敷衍させている。
このような考えを広げていくと、日琉同祖論や日鮮同祖論に見られるようにどんどんとその領域を拡大していきそうでもあるが
時枝は
朝鮮語、アイヌ語、台湾語のごときは国語学の対象として考えることは出来ない。
としている。
これは京城帝国大学で教鞭をとった時枝の実感から来るのかもしれない。
共通語としての国語は、こうした異なった言語を母語に持つ人々に対しても公用語とされたことを忘れてはならないだろう。
朝鮮語については、志賀直哉も「国語問題」で
朝鮮語を日本語に切り替えた時はどうしたのだろう。
と簡単にではあるが触れている。
これは拙論中でも述べ、注viiでも朝鮮や台湾についての、志賀のアイロニックな態度として極々簡単にではあるが触れた。
時枝から国語学の埒外とされたアイヌ語は、日本の民俗学・文学に絡みついている。
日本の民俗学の嚆矢、柳田國男の「遠野物語」[1910年(明治43年)]では
遠野郷のトーはもとアイヌ語の湖という語より出でたるなるべし、ナイもアイヌ語なり。
タッソベもアイヌ語なるべし。岩手郡玉山村にも同じ大字あり。
上郷村大字来内、ライナイもアイヌ語にてライは死のことナイは沢なり、水の静かなるよりの名か。
とアイヌ語を語源とする地名が沢山出てくるし
また文中に
オシラサマという神あり。この神の像もまた同じようにして造り設け、これも正月の十五日に里人集まりてこれを祭る。
とあった後
オシラサマは双神なり。アイヌの中にもこの神あること『蝦夷風俗彙聞』に見ゆ。
との記載もある。
また北海道を舞台とした有島武郎の「カインの末裔」[1917年(大正6年)]では冒頭部で
蝦夷富士といわれるマッカリヌプリの麓に続く胆振の大草原を、日本海から内浦湾に吹きぬける西風が、打ち寄せる紆濤のように跡から跡から吹き払っていった。寒い風だ。見上げると八合目まで雪になったマッカリヌプリは少し頭を前にこごめて風に歯向いながら黙ったまま突立っていた。
とアイヌ語の山名が出てくる。
私はこれらを最初に読んだ時、どきりとした。
それらはアイヌについて直截に語られたものではないが、少なくとも過去に、そこでアイヌの人々が暮らしていたことを明確に現している。それではこれらが書かれた当時はどうだったのか?
それは語られぬだけに、語られた物語・小説に纏わりついているように、私には思われる。
そのように思ってから読見直すと、言文一致小説の嚆矢の一つ、国木田独歩の北海道を描いた「空知川の岸辺」[1902年(明治35年)]にアイヌを思わせるものが何も出てこないのは、何か異様な感じがして来る。
空知太というアイヌ語が語源と思われる地名も、流暢な言葉の中に埋もれて、何も感じさせない。
社会が何処にある、人間の誇り顔に伝唱する「歴史」が何処にある。此場所に於て、此時に於て、人はたゞ「生存」其者の、自然の一呼吸の中に托されてをることを感ずるばかりである。
と平然と語る国木田の小説には、有島武郎や柳田國男が記した残酷な物語・小説とは別種の残酷さが底に横たわっているように思われる。
なお日本語を母語としない人々に対する日本の言語政策については『言語帝国主義とは何か』所収の「日本の言語帝国主義」【アイヌ、琉球から台湾まで】小熊英二と「帝国日本の言語編制」【植民地期朝鮮・「満州」・「大東亜共栄圏」】安田敏朗が包括的でかつ分かりやすい。
引用文献: ①『国語学史』 〔電子書籍版〕 2021年7月21日発行
著者:時枝誠記
発行所:株式会社 岩波書店
定本: 「国語学史」2017年10月17日 第一刷発行 岩波文庫
昭和15年(1940年)12月発行『国語学史』岩波書店、が底本の元本と思われる。
②志賀直哉, 志賀直哉全集 第七巻「国語問題」岩波書店, 1999.6.7.
[「国語問題」初出: 1946.4.1.「改造」第27巻第4号]「志賀直哉随筆集」高橋英夫編 [39](岩波書店)(1995.10.16.第1刷発行、2021.1.15.第9刷発行)にも所収
③「遠野物語」柳田國男
青空文庫 2012年12月16日作成
2022年3月9日修正
底本:「遠野物語・山の人生」岩波文庫、岩波書店 1976(昭和51)年4月16日第1刷発行 2007(平成19)年10月4日第47刷改版発行 2010(平成22)年3月5日第50刷発行
初出:「遠野物語」柳田國男
1910(明治43)年6月14日発行
④「カインの末裔」有島武郎
青空文庫
2000年3月4日公開
2005年9月24日修正作成
底本:「カインの末裔 クララの出家」岩波文庫、岩波書店
1940(昭和15)年9月10日第1刷発行 1980(昭和55)年5月16日第25刷改版発行 1990(平成2)年4月15日第35刷発行
底本の親本:「有島武郎著作集 第三輯」新潮社 1918(大正7)年2月刊
初出:「新小説」 1917(大正6)年7月号
⑤「空知川の岸辺」国木田独歩
(明治三十五年十一月─十二月)
青空文庫
2000年6月27日公開2006年3月18日修正
底本:「現代日本文學大系 11
國木田獨歩・田山花袋集」筑摩書房
1970(昭和45)年3月15日初版第1刷発行 1973(昭和48)年9月1日初版第4刷発行
参考文献: 『言語帝国主義とは何か』
2000年9月30日 初版第1刷発行
2006年11月30日 初版第4刷発行
編者: 三浦信孝 粕谷啓介
発行所: 株式会社 藤原書店
xxxviii 主観・自我・身体性〈柄谷行人・メルロー=ポンティ・志賀直哉〉
柄谷行人は『日本近代文学の起源』[64]の中で、志賀直哉の「濁つた頭」から引用しなら、志賀について
彼にとって、「主体」たることは暴力的な抑圧だったのだ。他の連中が「意識」から出発したのに対して、彼にとって「意識」とはせいぜい「濁つた頭」にすぎなかった。
「近代文学」が、一つの主体・主観・意識から出発したとすれば、志賀はそのこと自体の転倒性に反撥したのである。「一つの主観」を疑うところからはじめたのだ。
と述べています。
また同著の中で、柄谷は、拙論でも取り上げた志賀直哉の「クローディアスの日記」に出て来る
兄の夢の中で兄を殺
すという
驚くべき「殺人」
を引用し、さらにメルロ=ポンティ『眼と精神』(滝浦静雄・木田元訳)所収「幼児の対人関係」に出て来る
ヴァロンがシャルロッテ・ビューラーの著者から借りてきた
というある
小さな女の子の話
を「クローディアスの日記」の夢と関連付ける為に引用しています。
それは
彼女はその家の女中ともう一人の女の子のそばに坐りながら、何か不安そうな様子をしているうちに、やがて不意に隣の女の子に平手打ちを食わせ、そしてその理由を聞かれたとき、意地悪で自分をたたいたのはあの子だから、と答えました。その子のひじょうに真剣な様子からすると、でっち上げの嘘を言っているとは思われません。
という内容で、メルロ=ポンティはこういった例などから
幼児自身の人格は同時に他人の人格なのであって、この二つの人格の無差別こそが転嫁を可能にするわけです。こうした人格の無差別は、幼児の意識構造の全体を前提とするものです。
と結論づけています。
このメルロ=ポンティの帰結を引用しながら
柄谷行人は志賀直哉について
おそらく志賀が幼児的だとか原始人とかいわれる理由はここにある。しかし、重要なのは、志賀が、私は私であり他者は他者であるという区別に先立ってあるような身体性を感受していたことである。
と述べています。
メルロ=ポンティは先の論の中で
幼児は三歳頃になりますと、これまでみた癒合的社会性の段階のときとは違って、自分の身体ばかりか思考をさえ他人のものだと思うようなことはやめます。彼は自分を、〈状況〉そのものと混同したり、また自分に負わされることもありある〈役割〉そのものと混同したりすることがなくなります。彼は自分固有の視点やパースペクティヴというものを採用するわけです。いや、彼には、状況や役柄がどれほどの多様性をもっていようとも、自分はそうしたさまざまの状況やさまざまの役柄を超えた〈或る何者か〉だということがわかってきます。
と云い
幼児が最初そこに埋没していた直接与件としての〈感覚的光景〉と、今後自分の考えで選んだ方向に経験を再編成したり再配分したりするような〈主観〉というものとが、二つに分かれなければなりません。
と三歳頃に主観が現われ出て来る事を示し
そしてそうなると
幼児には他人の眼ざしが邪魔になり、他人が彼の方を見ると、彼の注意は果たすべき課題からそらされて、その課題を遂行しつつある自分自身の表象に向けられてしまうといった風になるのです。
と述べています。
しかしその上でメルロは
自我、つまり「私」というものが、他人から見た私によって二重化されずに本当の意味で現れて来ることは、三歳児においてはありえません。
と述べ、三歳児において見られる現象は
もっと後で起こって来るような意味での〈羞恥心〉、つまり〈裸であることの恥ずかしさ〉(それは五・六歳頃にしか現れません)が問題なのではなく、また叱られるこわさも問題ではないからです。
としています。
柄谷行人が述べたように
志賀が、私は私であり他者は他者であるという区別に先立ってあるような身体性を感受していたことである。
とするなら、それはメルロ=ポンティに即すれば3歳頃に現れる主観以前のものであり、5、6歳頃に芽生える自我からは更に距離の或る感覚です。
メルロ=ポンティの考察を元に柄谷行人に即して考えれば、私が志賀の「濁つた頭」、「クローディアスの日記」を含む一連の作品から自我を感じられなかったのは、当然のことと云えるのかもしれません。
「幼児の対人関係」の後段でメルロ=ポンティは
おそらく癒合的社会性は、三歳とともに清算されてしまうものではないでしょう。かの他人との不可分の状態、さまざまの状況内部で他人と自己とが互いに侵食し合い、互いに混同されている状況、同一主体が多くの役柄に顔を出すといったことは、成人の生活にもまだ見られます。三歳の危機は、癒合性を抹殺するというよりは、むしろそれを遠くに押しやるだけのことなのです。
と論じています。
このような
成人の生活にもまだ見られる
癒合的社会性
を志賀の一連の作品は捉えていると云えるのかもしれません。
引用文献: ①『日本近代文学の起源』[64]
著者: 柄谷行人
1988年6月10日第1刷発行
2006年3月1日第35刷発行
発行所: 株式会社 講談社
引用は本書の中のⅢ「告白という制度」(初出季刊芸術1979年冬号)より
②『眼と精神』
著者: M. メルロ=ポンティ
滝浦静雄・木田元共訳
1966年11月30日 第1刷発行
2022年4月15日 第36刷発行
発行所: 株式会社 みすず書房
引用は本書所収「幼児の対人関係」(1950〜51年にかけてパリ大学文学部で行われた幼児心理学の講義録)より
引用文献・映画と参考文献(本文中の[1]〜[68]からも見れます)
[1] 志賀直哉, 志賀直哉全集 第七巻「国語問題」(書籍は[12]と同じですが、引用数が多いため別枠としました。, 岩波書店, 1999.6.7.
[「国語問題」初出: 1946.4.1.「改造」第27巻第4号]「志賀直哉随筆集」高橋英夫編 [39](岩波書店)(1995.10.16.第1刷発行、2021.1.15.第9刷発行)にも所収:

[2] 志賀直哉, 『夕陽』, 櫻井書店, 1960.9.15.
[初出:「文芸放談」1946.9月「朝日評論」
「浅春清談」1947.1月「サンデー毎日」
「内村鑑三その他」1948.1月「文芸」
「志賀氏を囲んでの芸術夜話」1957.1月「随筆サンデー」]

[3] 茅島篤, 『国語ローマ字化の研究』(改訂版), 風間書房, 2009.3.31.改訂版第1刷発行(2000.3.15.初版第1刷発行).

[4] 賀茂真淵, 國意考(現代語訳)電子版, 原著1804年: いざなみ文庫, 2019.10月. [原著1764〜1769]
[5] 本居宣長, 『玉勝間』上: 岩波書店, 2008.4.4.第20刷発行(第1刷1934.6.15). 下: 1970.5.10.第9刷発行(第1刷1934年) [原著1795〜1817]

[6] 江藤淳, 『閉ざされた言語空間』, 2019.10.5.第15刷(1994.1.10.第1版)
[底本 1989.8月、初出:1982.2月号〜1987.2月号「諸君!」(6回に分け掲載): 文藝春秋]

[7] 時枝誠記, 『国語学史』(電子書籍版), 岩波書店, 20021.7.21.
[底本:「国語学史」2017.10.17.第1刷発行
底本の親本:「国語学史」岩波書店1966.5月第14版、初版1940.12月]
[8] 菊池寛, 『志賀直哉氏の作品』, 青空文庫, 2005.1.6.
[底本:「半自叙伝」講談社学術文庫1987.7.10.第1刷発行、原典: 1918.11月]
[9] 田中章夫, 『東京語ーその成立と展開』, 明治書院, 1983.11.30.

[10] 阿川弘之, 志賀直哉, 底本1994.7月岩波書店: 新潮社, 1997.8.1.

[11] 谷崎潤一郎, 『卍』, 新潮社, 2010.5.15.107刷改版、1951.12.10.発行.
[ 初出1928〜1930年『改造』]

[12] 志賀直哉, 志賀直哉全集 第七巻, 岩波書店, 1999.6.7.
[初出:「五月蝿」1945.12.1.「文藝春秋」、「特攻隊の再教育」1945.12.16.「朝日新聞」、「天皇制」1946.4.1.「婦人公論」]

[13] ソシュール , 『一般言語学講義』, 小林英夫訳: 岩波書店, 1972.12.22.改訂版第1刷発行(1940.3.1第1刷発行)

[14] 志賀直哉, 『和解・濁った頭 ほか十三編』(電子書籍), 2019.11.1
[底本:1972.2月講談社文庫、原典:「濁った頭」1911年、「クローディアスの日記」1912年]
[15] 芥川龍之介, 「神神の微笑」, 青空文庫, 1998.12.19.公開、2004.3.10.修正.
[底本:「芥川龍之介全集」ちくま文庫(筑摩書房)1987.1.27.第1刷発行、1993.12.25.第6刷発行
底本の親本:「筑摩全集類聚版芥川龍之介全集」筑摩書房1971.3月〜11月、原典1921.12月]
[16] 芥川龍之介, 「蜘蛛の糸」, 青空文庫, 1997.11.10公開、2011.1.28.修正.
[底本:「芥川龍之介全集2」ちくま文庫(筑摩書房)1986.10.28.第1刷発行、1996.7.15.第11刷発行
親本:筑摩全集類聚版芥川龍之介全集1971.3月〜11月、原典1918.4.16]
[17] ポール・ケーラス , 因果の小車(Kindle版 電子書籍), 鈴木大拙訳、温古堂文庫, 2021.4.27.
[底本「因果の小車」長谷川商店1898年、原典1894年]
[18] ドストエフスキー, カラマーゾフの兄弟 完全版(電子書籍), 米川正夫訳 上妻純一郎編集 2019.4.16.第3版(初版2017.12.26).
[原著1880年: 古典教養文庫]
[19] 芥川龍之介, 「河童」, 青空文庫, 1999.1.24.公開、2012.3.20.修正.
[底本:「河童・或阿呆の一生」旺文社文庫(旺文社)1966.10.20.初版発行、1984年重版発行
初出:1927.3.1.「改造」]
[20] 志賀直哉, 志賀直哉全集 第八巻, 岩波書店, 1974.6.5.
[初出:「『クローディアスの日記』に就いてー舟木重雄君にー」1913.4.1「奇蹟」
「『芥川龍之介全集』推薦」1934.10月
「『定本小林多喜二全集』」推薦1968.1月
「メートル法廃止運動に就いての返事」1938.6月]


[21] シェイクスピア, ハムレット(電子書籍版), 福田恆存訳 新潮社, 2016.1.29. 「解題」福田恆存
[底本2013.6月発行第95刷、初版1967年、原作1601年頃]
[22] 太宰治, 『新ハムレット』, 青空文庫, 2003.1.27.作成.
[底本『新ハムレット』新潮社1974.3.30.発行、1995.1.30.30刷改版、1998.7.20.33刷。
原典:1941.7月.文藝春秋社]
[23] 君塚直隆, 『物語 イギリスの歴史』(電子書籍版), 底本:2019.6.10.上(7版)下(6版): 中央公論新社, 2019.8.1.
[24] 吉本隆明, 『共同幻想論』, 河出書房新社, 1981.4.3.39版発行(1968.12.5. 初版発行)

[25] 赤松敬介, 『夜這いの民俗学・夜這いの性愛学』(電子書籍), 筑摩書房, 2014.10.31.
[底本:2004.6月ちくま学芸文庫、うち『夜這いの民俗学』は1994.7.15.明石書店刊行]
[26] 「もののあはれ」をめぐる本居宣長の考えについては、この本が分かりやすく参考になった。
本居宣長, 新潮日本古典集成(新装版)『本居宣長集』, 日野龍夫校註
大和心は宣長の六十一歳自画自賛像に賛として書かれた「しき嶋のやまとこころを人とはば朝日ににほふ山さくら花」が有名である。: 新潮社, 2018.9.30.

[27] 上田秋成, 上田秋成全集 第1巻 国学篇所収「呵刈葭」, 中央公論社, 1990.11.25.
[参考比較:日本の名著 21 本居宣長所収「呵刈葭 」現代語訳 中央公論社 1970.5.10]
[原典1786年]


[28] 江藤淳, 『近代以前』, 文藝春秋, 2013.10.20
[底本『近代以前』(1985年、小社刊)]

[29] 上田秋成, 胆大小心録, 重友毅校訂岩波文庫, 1989.3.17.第3版発行(初版1938.10.15)
[ 原典1808年]

[30] 上田秋成, 雨月物語(改訂 現代語訳付き), 鵜月洋訳註: KADOKAWA, 2013.12.15.[原典:1768年〜1776年 ]
[31] 芥川龍之介, 芥川龍之介未定稿集, 葛巻義敏編: 岩波書店, 1976.6.30.第四刷、1968.2.13.第一刷発行.
[原典:1914年〜15年]

[32] 芥川龍之介, 『点鬼簿』, 青空文庫, 1998.10.5.公開、2016.2.25.修正.
[底本「昭和文学全集 第1巻」小学館1987.5.1.初版第1刷発行
底本の親本「芥川龍之介全集 第8巻」岩波書店1978.3.22.発行
初出「改造 第8巻11号」1926.10.1]
[33] 芥川龍之介, 「歯車」, 青空文庫、2009.3.24.
[底本:「河童・或る阿呆の一生」新潮文庫(新潮社)1968.12.15.発行、1987.11.5.41刷、原典1927年, 2009.3.24.]
[34] 芥川龍之介, 「或阿呆の一生」, 青空文庫, 1998.4.23.公開、2005.12.2.修正.
[底本:「現代日本文学体系43芥川龍之介集」筑摩書房1968.8.25.初版第1刷発行、原典:1927.6月遺稿]
[35] 三島由紀夫, 『文化防衛論』(文庫版)筑摩書房, 2021.7.10.第10刷発行、2006.7.10.第1刷発行.
[初出「文化防衛論」中央公論 昭和43年(1968年)7月号]

[36] 三島由紀夫, 三島由紀夫対談集『源泉の感情』2006.2.20.河出書房新社
[底本:1970.10 月、初出:「文武両道と死の哲学」福田恆存との対談 1967.11月「論争ジャーナル」]

[37] 監督 豊島圭介, 『三島由紀夫vs東大全共闘〜50年目の真実〜』, 1969.5.13.東京駒場キャンパスでの三島由紀夫と全共闘学生の討論会のドキュメンタリー, 2020.3.20.公開.
[38] 三島由紀夫, オリジナル版『英霊の声』, 河出書房新書, 2020.4.30. 9刷発行、2005.10.20. 初版発行. [底本『英霊の声』1966年、初出:「英霊の声」1966.6月『文藝』、「憂国」1960.冬季号『小説中央公論』、「十日の菊」1961.12月『文學界』]

[39] 志賀直哉高橋英夫編, 志賀直哉随筆集, 岩波書店, 1995.10.16.第1刷発行、2021.1.15.第9刷発行.
[初出: 「内村鑑三先生の憶い出」1941.3.1「婦人公論」、「ナイルの水の一滴」1969.2.23.「朝日新聞」]

[40] 有島武郎, 「惜しみなく愛は奪う」, 青空文庫, 2003.7.28.作成、2012.8.8.修正.
[底本:「惜しみなく愛は奪う」新潮文庫(新潮社)1955.1.25発行、1968.12.20.25版改版、1974.8.30.34刷
初出:「有島武郎著作集 第1輯」叢文閣1920.6月]
[41] 志賀直哉, 『暗夜行路』, 新潮社, 1990.3.15.発行、2004.3.5.31刷.
[原典:1921.1月〜1937.4月「改造」]

[42] 有島武郎, 「或る女 前編」青空文庫, 1999.10.17.公開、2013.1.8.修正
[底本:「或る女 前編」岩波文庫(岩波書店)1950.5.5.第1刷発行、1968.6.16.第27刷改版発行、1998.11.16.第42刷発行
初出:1911.1月〜1913.3月「白樺」]
[43] 有島武郎, 「或る女 後編」, 青空文庫, 2000.3.1.公開、2013.1.8.修正.
[底本:「或る女 後編」岩波文庫(岩波書店)1950.9.5.第1刷発行、1968.8.16.第23刷改版発行、1998.11.16.第37刷発行
初出:叢文閣「有島武郎著作集」(前編と合わせて)]
[44] 有島武郎, 「カインの末裔」, 青空文庫, 2000.3.4.公開、2005.9.24.修正.
[ 底本:「カインの末裔 クララの出家」岩波文庫(岩波書店)1940.9.10.第1刷発行、1980.5.16.第25刷改版発行、1990.4.15.第35版発行
底本の親本:「有島武郎著作集 第三輯」新潮社1918.2月刊行
初出:1917年7月号「新小説」]
[45] 太宰治, 『如是我聞』(電子書籍)2000.10.14.公開、2004.3.4.修正, 青空文庫.
[底本『もの思う葦』新潮社 1980.9.25.発行、1998.7.20.第38刷発行。原典1948.11.10.新潮社]
[46] 三島由紀夫, 『古典文学読本』中央公論新社,初版発行 2016.11.25. 、再版発行 2020.5.25. うち「日本の古典と私」初出: 1968.1.1.他「山形新聞」

[47] ガンジー, 「ガンジー自伝」, 蠟山芳郎訳: 中央公論社, 1992.12.15. 8版 (1983.6.10初版).
[初出: 1925年〜1929年]

[48] 柄谷行人, 日本精神分析, 文藝春秋, 2002.7.30.
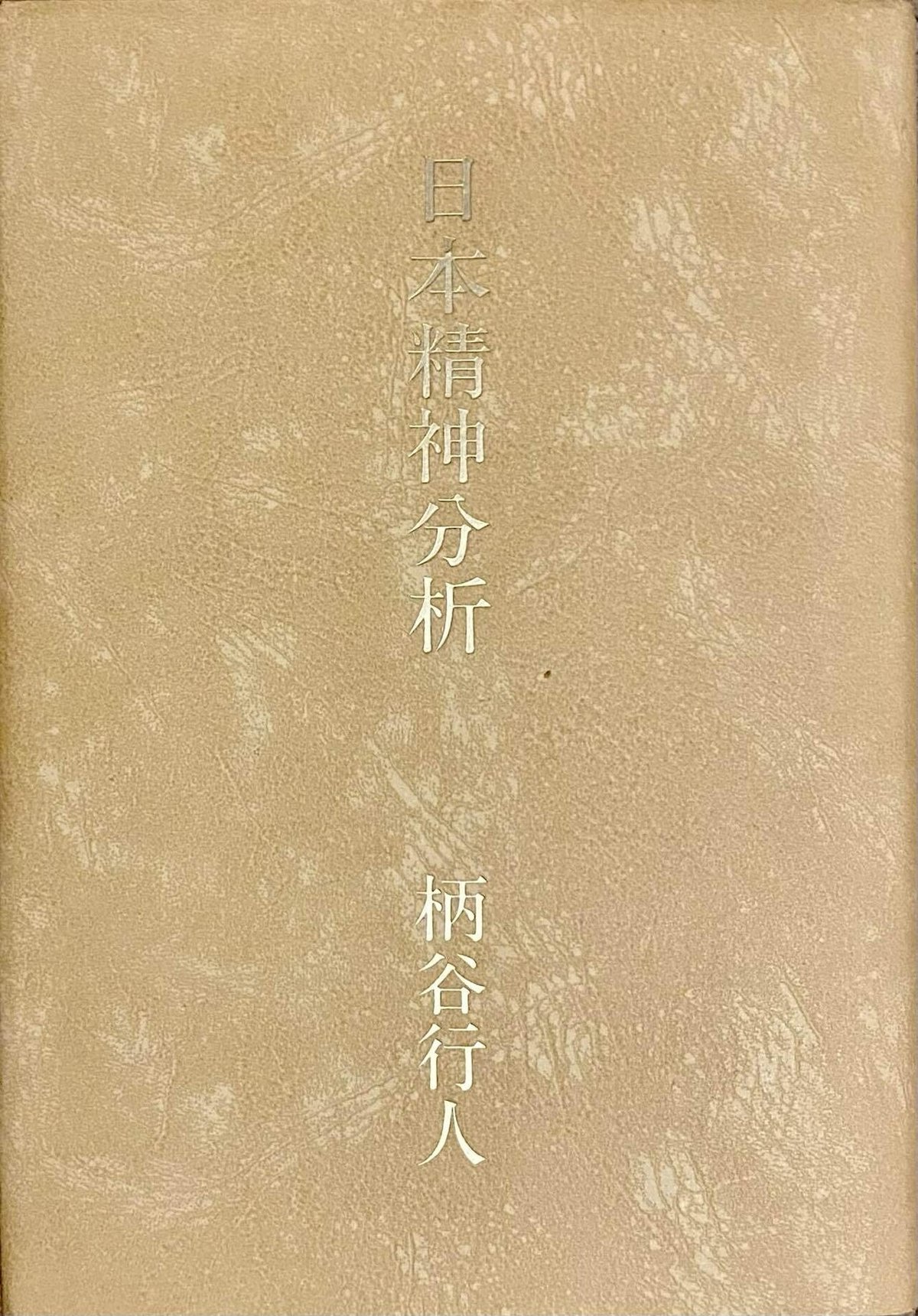
[49] 土岐善麿, 『國語と國字問題』, 春秋社, 1947.2.20.


[50] 平岡敏夫, 『日本近代文学の出発』塙書房,1992.9.10. [底本 1973年紀伊国屋書店]

[51] 江藤淳, 『リアリズムの源流』, 河出書房新社, 1989.4.20.発行.
うち「リアリズムの源流ー写生文と他社の問題」初出1971.10月号「新潮」]

[52] 岡田泰平, 『「恩恵の論理」と植民地ーアメリカ植民地期の教育とその遺制』, 法政大学出版局, 2014.9.30.

[53] ポール・ド・マン, 美学イデオロギー, 平凡社, 2013.12.10.
[底本2005.1月平凡社、「アイロニーの概念」
原典:1977.4.4.オハイオ州立大学での講演をもとに校訂]
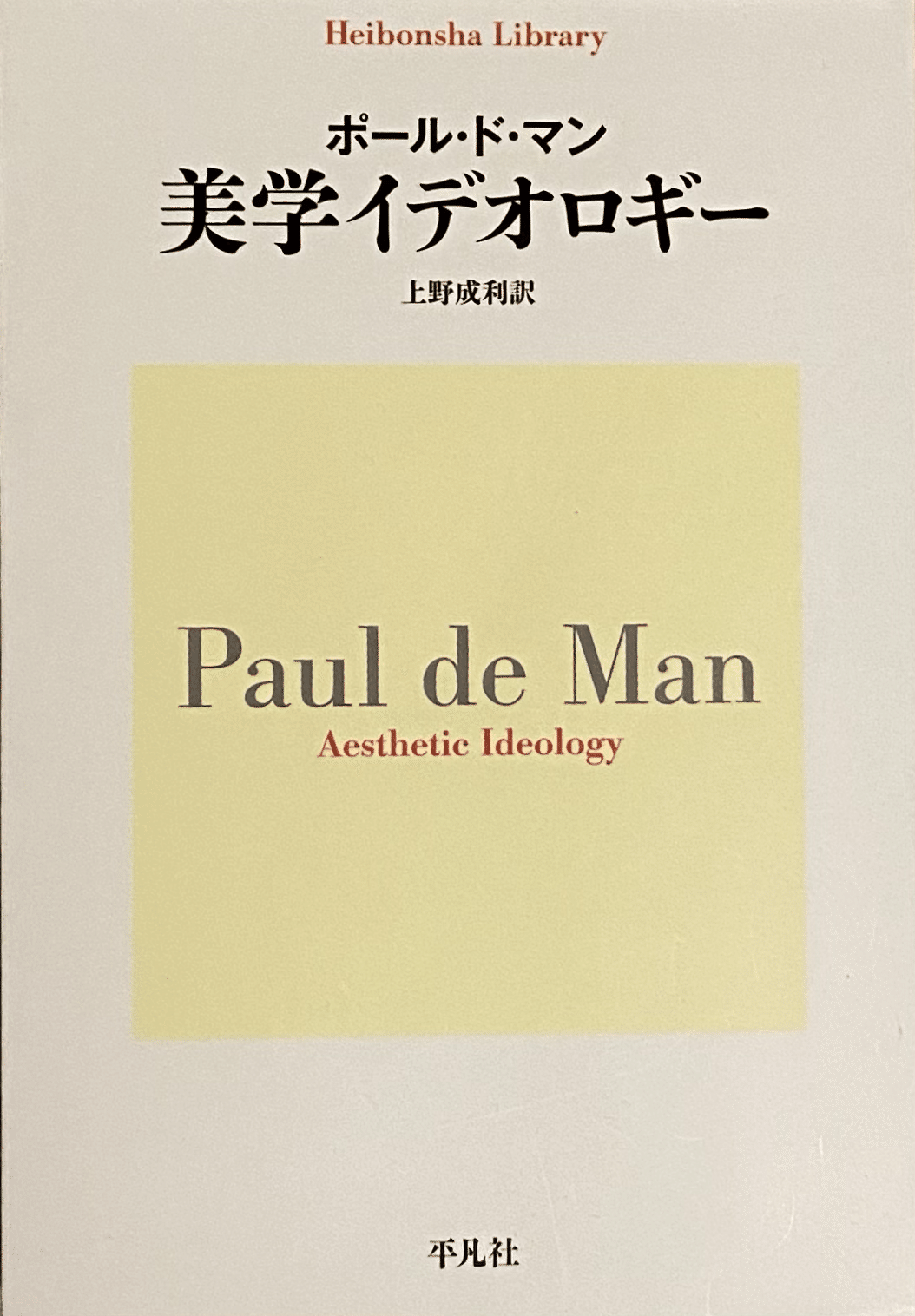
[54] ルイ=ジャン・カルヴェ, 『言語学と植民地主義ーことば喰い小論ー』, 砂野幸稔訳: 三元社, 2006.7.20
[原著:1998、2002、初出:1974.1月]
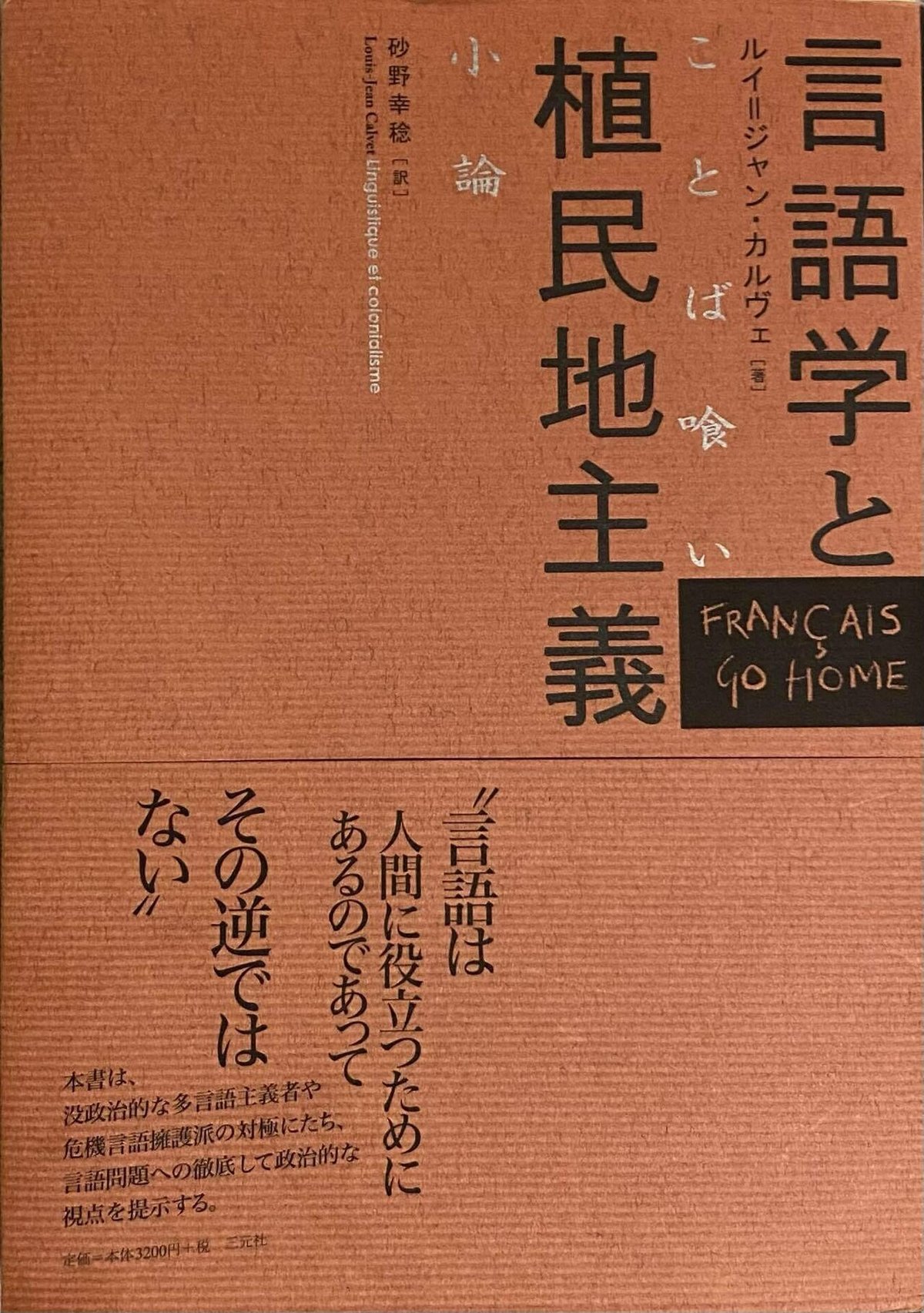
[55] 蓮實重彦, 『反=日本語論』, 筑摩書房, 2019.4.20.第3版発行(初版2009.7.10)
[底本 1977年筑摩書房]

[56] 大野晋, 『日本語練習帳』(電子書籍版), 岩波書店, 2004.12.10.
[ 底本1999年日本語練習帳]
[57] 鈴木孝夫, 『閉ざされた言語・日本語の世界』(増補改訂版)(電子書籍)新潮社 2017.8.11.
[定本:『閉ざされた言語・日本語の世界』(新潮選書)(1975.3月)を増補改訂(新潮社)した初版第1刷 (2017.2月)]
[58] 加藤三重子, 城西大学大学院研究科、論文『志賀直哉の「国語問題」の政治学』, 成城国文学.15号, p29〜P39、1999.3.
今回は拙論との対比として、簡単に触れただけですが、私が知る範囲でまともに志賀の「国語問題」を取り上げた数少ない論の1つです。この論文と自分の考えを比較検討することなくして、私の拙論は完成することはなかったと思います。感謝するとともに、敬意を感じます。
加藤三重子さんの志賀直哉についてのもう一つの論文「志賀直哉『灰色の月』のポリティクス」もたいへんな力作です。驚きます。
「志賀直哉『灰色の月』のポリティクス」成城国文学18号、p100〜P116、2002.3月
[59] アチェべ, 『崩れゆく絆』, 粟飯文子訳、光文電子書店, 2015.6.19. 「解説 チアヌ・アチェべとアフリカの文学」粟飯原文子
[原著1958年]
チアヌ・アチェべの小説『崩れゆく絆』を、今回は植民地とキリスト教の関係についての参照例として挙げたが、この小説でそれが描かれるのは、後半の最後部であり、話の殆どは、植民地化される前のナイジェリアのイボ人の社会にさかれています。とても興味深く、優れた小説です。
ひらげエレキテルさんが Youtubeで『崩れゆく絆』について語っています。ネタバレの感はありますが、とても興味深い内容です。↓
[60] 福田恆存, 『國語問題論争史』, 編輯者 土屋道雄、[61]は土谷道雄による増補版: 新潮社, 1962.12.25.

[61] 土屋道雄, 『國語問題論争史』玉川大学出版部, 2005.1.10. ,福田恆存「國語問題論争史」(新潮社) [60]の編輯者・土屋道夫による増補版:

[62] 芥川龍之介, 「文芸的、余りに文芸的な」, 青空文庫, 1999.2.2.公開、2004.3.16.修正.
[底本:「現代日本文学体系 43 芥川龍之介集」筑摩書房1968.8.25. 、原典:1927.2月〜7月]
[63] 丸谷才一, 『日本語のために』新潮社, 1974.8.30.、17版1975.10.10.
引用部分は『完本 日本語のために』新潮社(2011.3.1.)には収録されなかった「当節言葉づかい」の後半にあります。

[64] 柄谷行人、『日本近代文学の起源』講談社、1988.6.10.第一刷発行、2006.3.1.第35刷発行
[底本:1980.8月、「告白という制度」初出「季刊藝術」1979年冬号
[65] 柄谷行人、『反文学論』冬樹社 1979.4.25.初版第1刷発行、1984.2.25.第4版発行 [「法について」初出:1978.6]

[66] 甲斐睦郎、『終戦後直後の国語国字問題』明治書院、2011.3.30.

[67] 富岡多惠子、『新家族ー富岡多惠子自選短編集ー』學藝書林1990.2.25.初版発行、1992.10.5.2版発行
[初出:「坂の上の闇」1978.7月号「群像」(講談社、1980年刊『芻狗』所収)

[68]三島由紀夫、『行動学入門』文藝春秋社1974.10.25.第一刷、2021.2.25.第45刷、三島由紀夫による後書きは1970年に書かれている。各エッセイの初出はそれ以前。)
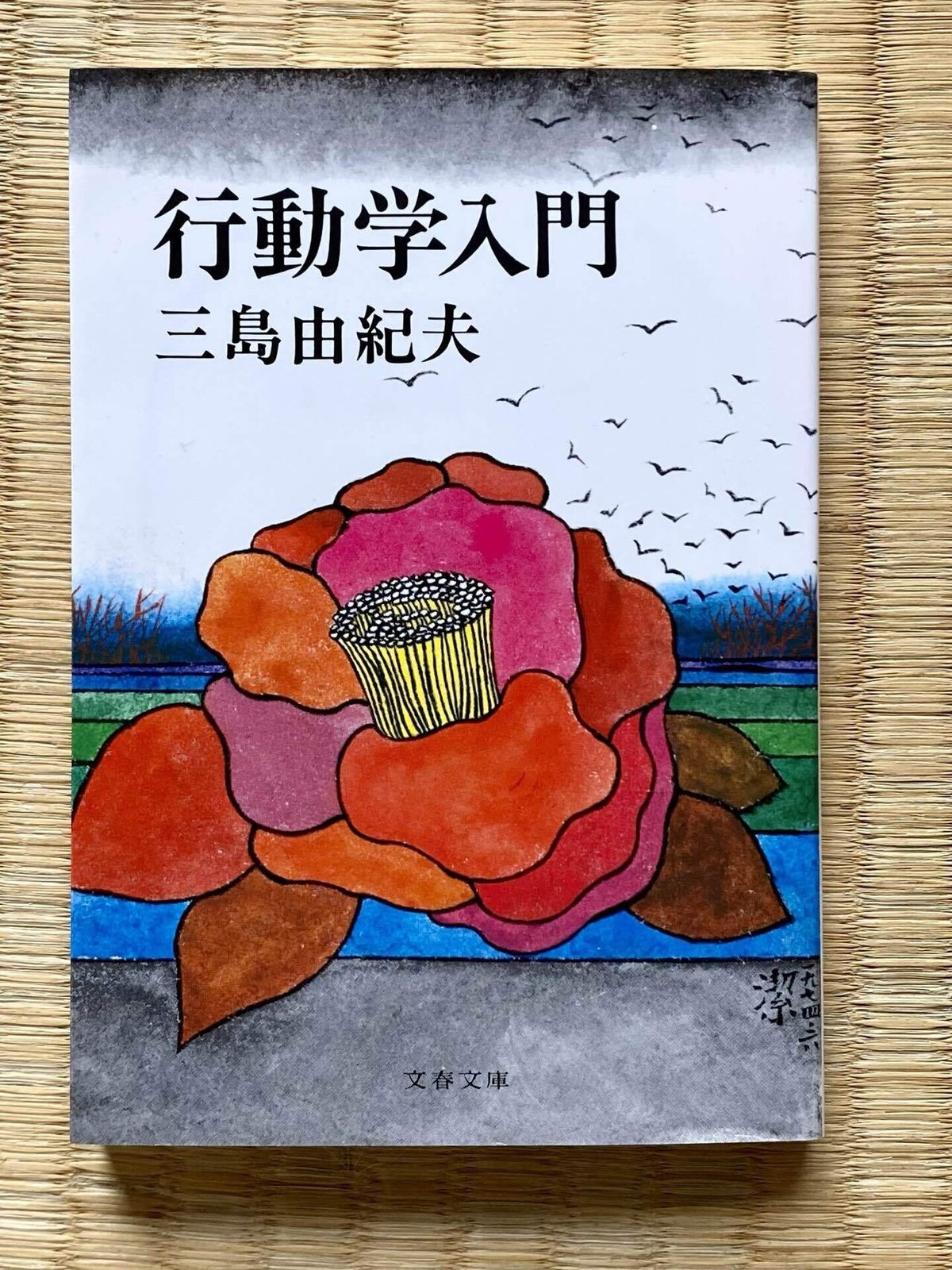
これまでの論文とエッセイ
自己紹介の代わりに
自身の作品 (詩・短歌・俳句・夢)
