
スタートアップSaaS企業の急成長を阻害する「THE MODEL」の3つの罠。
株式会社セールスのタクミ
代表取締役の佐藤匠です。
いつもnoteを読んでいただきありがとうございます!
今回は、「THE MODEL」によって
発生するスタートアップSaaS企業の弊害について書いていきます。
結論から言うとスタートアップSaaS企業
にTHE MODELは適していません。
今日は具体的に何が罠であるのか
どう対策すべきかを弊社の
ご支援事例を元に解説をしていきます。
ぜひ、リツイートにて
ご感想をお伺いできますと嬉しいです。
スタートアップSaaS企業様向けに
— 佐藤匠┃株式会社セールスのタクミ スタートアップ特化のエンプラ立ち上げ支援 (@takumi_startup) August 17, 2023
「THE MODELをぶっこわ〜す👊」
という約1万字のnoteを明日リリースしようと
思うのですが関係各所で炎上しないか心配です。
このツイートに応援のいいねが
5いいね集まったら無料公開しようと思います。
集まらなかったら限定の有料noteにします。
結構気合を入れて書いたので、長いです!
最後まで読んでいただければ、
多くのスタートアップ組織で起こりがちな
THE MODEL導入の失敗を防げます。
改めておさらいです。
「THE MODEL」とは、米国で生まれた
営業の分業体制の運営を体系化したものです。
日本で「THE MODEL」が広がったのは、セールスフォース・ドットコム日本支社福田康隆氏が、著書「THE MODEL」の出版とともに営業の分業体制を名付けたことに由来します。
https://www.salesforce.com/jp/resources/articles/sales/the-model/
実は、弊社もSalesforceのプロフェッショナルプランを導入していますし、お客様に導入支援をさせていただいているので、タイトルにも入れたような「THE MODEL」を取り入れるべきではない!
という内容を書くことに少し勇気が必要でした。
もちろん、セールスフォース・ドットコム社を批判する意図は一切ありませんし、同社のプロダクトと営業の方は素晴らしい方ばかりです。
これは一人の管理者、ユーザーとして普段から
製品を使っていて率直に感じています。
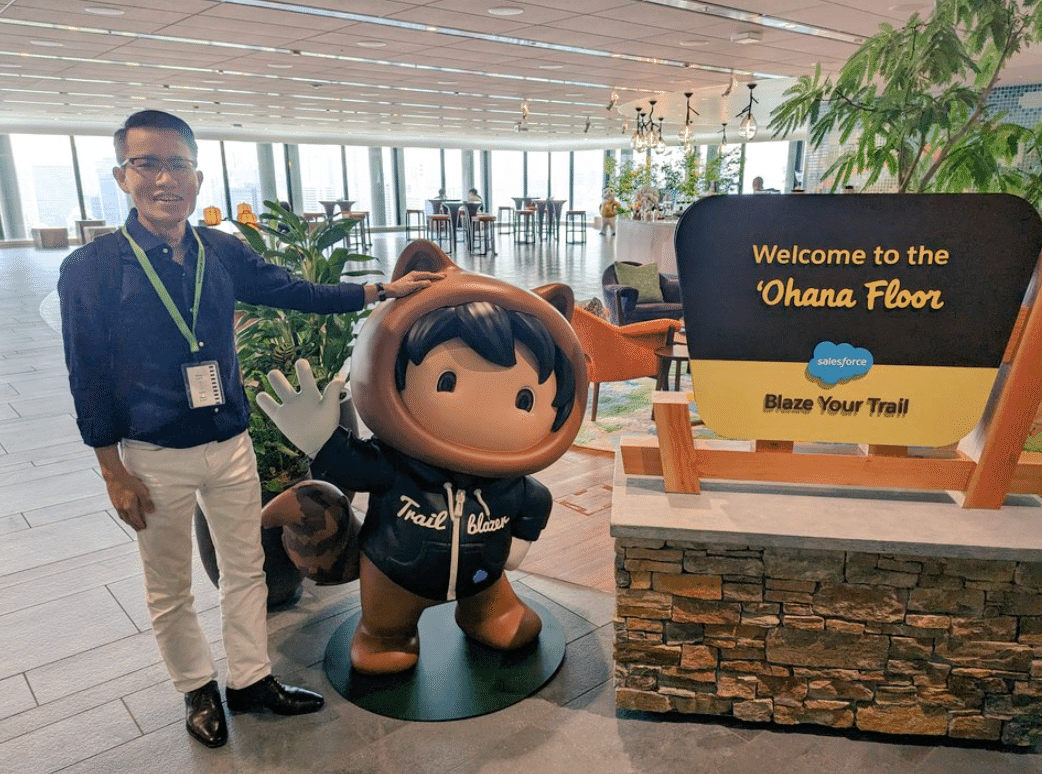
色々とサポートいただいております。
ゴルフも一緒に行かせていただきました。
しかしながら、こと、
スタートアップSaaS企業においては、
「THE MODEL」を取り入れる上での注意点や弊害をよく理解しないまま表面的な運用を行っている企業があまりにも多く、その先には悲劇しかありません。
この「THE MODEL」はその成り立ちからもわかるように、売上100億円以上、顧客が数1,000社以上のようなエンタープライズ企業向けのモデルであり、従業員1名~10名のスタートアップ企業には適していないと感じます。
ここからは、これまでアーリーステージのSaaSに30社以上の営業組織立ち上げ、コンサルティングのご支援をし、現場で酸いも甘いも経験してきた経験も踏まえて、なぜスタートアップSaaS企業がいきなり「THE MODEL」を取り入れるべきではないと感じたのか?
失敗してしまう企業の代表的な
アクションを3つあげます。
早速参ります。
1、マーケティングとセールスの分離はマーケット選定の遅延に繋がる。
営業が悪い!マーケが悪い!
これはもううんざりですよね。
マーケティングとセールスは
必ず統括できる人材を配置しましょう。
大企業だとマーケティングとセールスが別々の部門であるケースが殆どです。リード自体はマーケティングチームが取ってきて、商談対応は営業がするケースが一般的です。
ただ、スタートアップ組織の場合こういった運用では売上の増加につながりません。圧倒的に改善スピードが足りないのと顧客解像度が低いのが原因です。
スタートアップ事業においては、朝令暮改の如くサイクルを回していく必要があります。例えば、ターゲットの業界、規模、解決する課題感、従業員数など目まぐるしくPDCAを回しながら市場を捉えていく必要があります。
結局はいかに商談化しても受注につながる商談が取れなければマーケティングの価値はゼロなのです。反面、いかにターゲットリストが取れたとしても営業が適切に提案・クロージングできなければ売り上げに繋がることはありません。
よく営業とマーケが対立するのはお互いが他責思考で、売上の上がらない原因が相手にあると考えることが原因です。もちろんこれは水掛論になるばかりです。スタートアップ組織においては特にスピード感の早いセグメントの変更が求められるため、そもそも情報を伝達するコストを考えると遅すぎて話になりません。
マーケとセールスを統括できるCMO的な存在がいなければこの問題は組織の対立へと繋がります。

ターゲット市場を決める人材は必ず、独裁である必要があります。
また、ここで重要なのが営業力が確かにある人間が統率を取ることが重要です。いかに市場のリードが取れて、たくさんの商談のパスが上がってきてもゴールを決めるストライカーが決められなければチームは負けます。
どのようなゴールであれば決められるかは
最終的なシューターが最も知っています。
であればシューターがパスを定義した方が
いいコースにパスが来るに決まってます。
例えば、
ご支援に入らせていただく中で実際にあった事例。
自分からするとSDRからの受注率30%は余程のことがない限りは切らないので、これは完全にストライカーの能力不足と判断し、営業プロセスの改善と営業研修の実施を行いました。結果的にSDRの受注率は30%を安定して推移し、更に出稿金額を増加させました。

仮に弱いストライカーがこの状況を見てマーケのアクションを切った場合
・SDR以外のリードソースを開拓した方がいいかもしれない。
・マーケのリード供給の質が悪いのかもしれない。
という発想になってしまい、
結果的に本質的な営業改善ができないままとりあえず展示会に出よう。
とりあえずインサイドセールス代行にお願いしよう
という表面的な逃げの意思決定に染まっていくのです。
このnoteを読んでいる方に1つ基準として持っていただきたいのですが、
・SDR(資料請求)からの商談化率が30%、受注率が30%を切っているようなSaaS組織は他の施策の何をやっても絶対に伸びません。断言します。
圧倒的に営業力不足です。
マーケとか施策系何やってもまだROIが合わないです。展示会もまだ出ないでください。
イメージで言うと自分のことを好きと言ってくれている女の子と
さえ付き合えない男性が、道端でナンパをして彼女を作るようなものです。

実際ほとんどの企業様がこの水準に達していないケースが多いとは思いますが、逃げずにまずはSDRの転換率の改善から行っていきましょう。ここがしっかりと取れるようになって来れば難易度の高いリードソースの展開にチャレンジしても良いと思います。
この辺りはプロダクト要因や、市場要因もありますが、
投資家のデューデリを完了しているような企業様であれば
マーケ戦略(営業含む)に課題があります。
上記の話を踏まえて、ストライカー不在の組織でマーケティング施策を頑張ったとしても穴の空いたバケツになってしまうので、まずはクロージングをしっかりと30%の水準で決められる人材の確保に努めましょう。
弊社のご支援では未経験営業からエンタープライズ営業ゴリゴリ未経験の学生インターンを即戦力化した事例など多数あるので
低コストでも内製化することは可能です。

そしてマーケティング責任者に関しては必ず、営業のクロージング経験を持った人間をアサインするようにしましょう。結局ここの受注率が3倍変わったら、3倍の許容CPAまで広告出稿ができるようになるので、圧倒的に商談獲得効率が変わります。マーケティングは営業業務の1つです。
もちろん広告のLPを作る、広告出稿の設定をするなどはまだ専門的な業務なのでマーケターの力を借りたり、外注したりする必要がありますが、ターゲットセグメントを決める。許容CPAを定義する。
それぞれのリードソースごとの転換率を計測して、ROASを算出する。
SaaS営業であれば当たり前に意識するようにしましょう。
取り急ぎ、営業の強いCMO人材の採用は圧倒的な改善のスピード感と無駄のない広告投資を実現することに繋がります。1,000万円以上で採用しても簡単にペイすることができます。ここの方針を決める人間に投資できないのに、マーケティング施策に投資してペイするわけがないです。採用できない場合は匠コンサルがサポートしますので、ぜひお問合せください。
2、セールスとカスタマーサクセスの分離は顧客解像度の低下に繋がる。
これが一番ありがちなのではないでしょうか?
私の見解としては、ARR1億円、または従業員10名までは営業とカスタマーサクセスが分離すべきではありません。大体のSaaSのMRRが5万円なので、ARR1億円というのはMRR830万円、契約社数でいうと166社になります。しかし実際はエンタープライズ企業でうわぶれるのが一般的なため、
エンタープライズ企業の単価が5倍の25万円
全体の契約社数の10%がエンタープライズ企業だとします。
この数値は弊社の支援実績としてもかなり実値に近いです。
整理するとこんな感じです。
===
ARR:1億円
MRR:830万円
SMB受注数:76社=380万円
エンタープライズ受注数:18社=450万円
===
こうなると全体の受注者数はたったの94社になります。
全て単価5万円で考えた時は166社だったので、43.3%も顧客数は減ったのに
金額は変わっていませんね。エンタープライズ営業はだからこそ価値が高いのです。
話はそれますが、私がこれまで30社以上のSaaS企業様をご支援してきた結論から申し上げると、エンタープライズ企業とSMB企業の対応コストは、あまり変わりません。むしろSMB企業の方が対応コストが高い場合も多くありました。
===
例
・個人経営の企業などによって過剰なクレームが発生する。
・選定する人のリテラシーが低いケースだとオンボーディングコストが大きくかかる
===
エンタープライズ営業がいて、しっかりと大企業からの単価の高い受注ができる組織は営業もカスタマーサクセスも全員が幸せになる構造にあります。
先ほどの企業数をベースに大体1人あたりどのくらいの社数を対応できるのかを考えてみましょう。
弊社のご支援ではカスタマーサクセスの立ち上げも同時に行っております。CSフェーズとしては導入期、活用期、展開期に分かれます。
細かい説明は別のnoteをまとめます。
一旦下記を参考にしていただければと思います。

これまでカスタマーサクセスの立ち上げコンサルを行なってきて
大体の企業様の属性としては
===
展開期は全体の5%、
活用期が80%、
導入期が10%、
不明が5%(ちゃんと運用してる場合は無い)
という属性配分になります。
===
予想以上に展開期からのアップセルというのは発生しずらいです。
これも別のnoteで書きますが、アップセルには2つの方向性があって
1つは、アカウント数が増える。もう1つは追加の機能を使うになるのですが、後者はスタートアッププロダクトだと殆ど難しいと思います。30社の中で1社だけ代表の方がGoogle出身でえげつないエンジニアリング力を持っている企業様だけはアカウント増加以外のアップセルもありましたが、基本的には前者のアップセルが組織の総合力を加味するとスタートアップには現実的です。アカウント増加以外のアップセルは無いものと思った方がスタートアップにおいては現実的です。

次にカスタマーサクセスの
それぞれにかかる対応コストを考えてみましょう。
===
展開期:提案資料作成、商談、見積もり、契約関連(1社10時間)
活用期:利用状況のモニタリング(1社10分)
導入期:オンボーディング、アンケート(1社2~3時間)
不明:状況確認の架電、メール(1社30分)
===
時間数は圧倒的に展開期が多いです。
展開期は完全に通常の営業プロセスに近いので、
単純なフィールドセールス業務になります。
先ほど計算した企業分布に照らし合わせると
ARR1億時点でのカスタマーサクセスの時間配分は下記のようになります。
===
ARR:1億円
MRR:830万円
SMB受注数:76社=380万円
エンタープライズ受注数:18社=450万円
展開期は全体の5%=5社(50時間)
活用期が80%=75社(12.5時間)
導入期が10%=10社(12.5時間)
不明が5=5社(3時間)
合計で78時間です。
===
ちなみに結構多めに見積もってます。
導入期のお客様でオンボーディングが不要の方や活用期の顧客も全て見るわけではなかったりするので、ARR1億円のカスタマーサクセスに必要な時間数を考えてもせいぜい80時間です。
1人あたりの労働時間が120時間としても、
たったの0.66人月で賄えてしまいます。
だから私は思うのです。
ARR1億もいっていない会社がMAツール以外のCSツールなどを入れているのを見ると、全部に架電した方が早いし、安いぞ!と思ってしまいます。
まあその辺りは各社の拘りがあるので私の意見です。
そういうところで実はARR1億円までは
営業とCSを1人で兼務することも可能なんです。
だから私はARR1億円なんて1人で余裕と言いますが、
これは結構ガチで言ってます。
ということである程度、
カスタマーサクセスの工数がそこまでかからないんだということが分かっていただいた上で、何故営業とカスタマーサクセスを分けない方が良いかを説明していきます。大きく3つあります。

1、引き継ぎコスト、ミスが発生する。
これは当たり前ですが、営業が受注した内容をCSに伝達するコストが発生します。最近では、Rimo voiceやamp talkやAI leadなど便利な議事録ツールも増えたため、URLで共有する企業も増えています。
しかし当然ですが、その動画を見る時間、顧客の課題をキャッチアップする時間、特別な営業の握りを理解する時間、改めて顧客と関係値を築く時間が発生します。
私の数々の経験からすると1受注に最低30分、多いと3時間位は引き継ぎコストがかかります。つまり、月に30件受注したとすると、30時間〜50時間位は引き継ぎコストにかかってしまいます。これは引き継ぎがなければそもそも発生しなかった時間になり、完全に無駄です。
大体の企業様が営業工数を空けたいから引き継いでると思うのですが、前述した通り、対してかからないCS工数の為に引き継ぎコストを支払っているので、実は全体を俯瞰すると本末転倒な構造になります。
また、実はCSの専任対応した場合と、営業がそのまま請け負った場合の顧客満足度でいくともちろんですが、後者の方が圧倒的に高まります。
私は月に1度銀座の美容院にいくのですが、そこはシャンプーからカット、顔剃り、ブローまで全て同じ人が担当してくれます。これは無駄なく、全体のイメージを分かった上で各所でのサービスが受けられるので満足度も高いです。一方で安い美容室だと、シャンプー・ブロー、顔剃りは若手の新人が私たちが担当します。満足度の違いは言わずもがなかと思います。

追加で、私の経験上必ず引き継ぎミスが発生します。
スタートアップ企業でSFA、CRMをしっかりと運用できている会社は見たことないので必ず大事な引き継ぎ情報が抜け漏れたり、プライシングの変更などが発生して、旧プライシングで提案してたのに新プライシングで出してました。等のエラー等が発生します。これは顧客解約リスクを一気に高めることに繋がりますし、顧客体験としては最悪です。もちろん社内としても営業とCSの対立構造に繋がり、人材のリテンションも下がる可能性に繋がります。
私たちが、THE MODELにしているのは実は完全に会社側の都合なのです。
全体最適をしたいがため、採用単価を下げたいがためにTHE MODELを導入しているのです。本来であれば、顧客担当性にした方がいいに決まっています。THE MODELで効率化を優先した結果、責任の分断と、顧客体験の悪化に繋がっているのは否定できないと思います。
特に組織文化が未熟なスタートアップではそれがより大きく影響するように思います。
2、圧倒的に顧客解像度が低くなる。
弊社ではプロダクトの機能の用件定義などのPMのご支援もやらせていただいております。営業、CS、PMの全てを体験すると面白いのが、営業の場面で要望いただく機能とCSのタイミングでいただく機能というのは全く別のものになります。
例えば、営業の時には目に見えるようなBIの機能が欲しいという要望が多かったのが、CSになると実際に運用してみた結果、権限設定の機能が圧倒的に必要であるというケースがありました。
なぜ、こういった違いが発生するのかというと企業側も使っていく中でリテラシーが変化していくからと考えています。使う前に抱いていたイメージと実際の使用後のイメージではプロダクトに対する要望が変わるのは当たり前です。
しかし、プロダクトのゴールはLTVを最大化することなのです。
SaaSの重要KPIとして、もちろんARPA、受注率などありますが、
1番はLTVです。本当にこれにつきます。LTVを分解するとMRR✖︎利用期間
になりますが、利用期間を満たすにはCS、利用顧客からのフィードバックが最も重要になると考えます。不満の溜まったままプロダクトを使い続ける人はいません。
しかし、こういった要望や導入後のイメージを分かってない営業のする提案というのは非常に刹那的でありCSを経験している営業と比較すると全く相手になりません。導入後のイメージや課題感やデメリットなどのマイナスの部分や良く導入でつまづく所も商談時に説明してもらった時の安心感てありますよね?
こういった顧客の声を聞いている営業はどんどん受注率が上がりますし、プロダクトへのフィードバックも受注するためではなく、LTVを伸ばすための意見になっていきます。営業とCSが別れてしまうと、営業の機能要望はこれ、CSの機能要望はこれと貴重なエンジニアリングコストに無駄が発生してしまいます。
顧客解像度を会社として高めることは、受注率の向上、LTVを重視した無駄の無いプロダクトロードマップの引き直しなど多くのメリットがあります。こういったチャンスを潰してまで、本来必要のない引き継ぎコストをかけてまでたかが1人で対応できるカスタマーサクセス業務を集約させるって本当に意味があるのでしょうか?

補足ですが、実は私が新卒で入った会社は完全にTHE MODEL型でした。
私は顧客志向が強い営業だったため、無理な営業握りというのは少なかったですが、中には受注して案件をCSにぶん投げる営業などもいました。
自分が対応、サポートすることは無いから受注して終わり。という意識が発生するのだと思います。THE MODELは、KPIと同時に責任も分断させてしまいます。倫理観が高いメンバーのみであれば発生しないとは思いますが、採用基準も安定しないスタートアップ組織では、責任放棄や、責任転換が起きるリスクが高いと私はこれまでの経験から感じます。
3、単純に顧客体験が悪く、LTVの低下に繋がる。競争優位性を失う。
私がとあるスタートアップSaaS企業を支援した時の話です。
私は営業部長であり、カスタマーサクセスも全て対応していました。
あるA社という有名な業界大手エンタープライズ企業の商談を担当しました。もちろん受注しました。MRRベースで300万弱です。
実はこのSaaSは既に市場でコモディティ化していました。
しかし他社の2倍のプライシングで受注できました。
なぜか?カスタマーサクセスまで全て私が担当したからです。
通常のSaaSではありえませんが、
営業で受注してそのままオンボーディング、
活用支援、そしてアップセルまで1人で実行しました。
もっというと1人で全ての店舗にセットアップに回りました。
都内で10店舗はありましたが、全て導入の支援と挨拶に回りました。
ここまでされて断れる担当者は多くはないと思います。
カスタマーサクセスは圧倒的な営業差別化になります。
想像してみていただきたいのですが、あなたが風邪で病院に行って
お医者さんが受付から診察から、会計までやってくれたらびっくりしませんか?
THE MODELって例えるならお医者さんが一番分かりやすいと思うんですよね。看護師がヒアリングをして、医師が診察する。まさにISとFSとCSみたいな関係性ですよね。全てのプロセスを1人の担当が対応してくれるという過程自体がその企業の価値になります。

私はよくエンタープライズ企業と大きな受注を決まるときはプロセスストーリーを大切にします。あのとき、こんな資料を作って、議論して、サポートしてもらって、上申したけど上司に反対されて、どうにか議論して導入までいく。これはまさに物語なのです。物語には圧倒的な力があります。どれだけプロダクトが強くても、このプロセスストーリーを顧客と作れる場合は競合他社に勝てるのです。
平たく言うと、〇〇さんだから発注したよ。みたいなことになりますが、
それを意図的に再現性を持たせることを意識しています。簡単な話で言うと顧客接触時間、頻度が長ければ長いほどプロセスストーリーが築かれていきます。なので、担当を変えることはこのプロセスストーリーの醸成を阻害する要因になるため、LTVの最大化を考えると全くもっておすすめしません。
担当者を変えることはこのプロセスストーリーの受注効果をかなり下げてしまう要因になるので、手札の少ないスタートアップにおいては営業がそのままCSを担ってアップセルまで持っていくことを強くお勧めします。
特にスーパーエンタープライズ企業の場合は、
THE MODELを会社で導入したとしても営業担当がそのままアカウントを引き継いで一定の期間までサポートをすることを強く推奨します。
これはスタートアップに限らず再現性があります。
補足
ラスト3ついきましょう。
ここまで読んでいただいたあなたの意見もぜひTweetで聞かせてください。
もしこのnoteが20件以上リツイートが回れば
続編の「SaaSプロダクトで最速で1億円を目指す匠MODELの全貌」を執筆しようと思います。
3、過剰なKPI管理は時間の無駄。ARR1億までに注力すべきKPIはこの3つ。
基本的に大きなアクションの改善につながるKPI指標というのは絞られてます。
逆に言えばアクションの改善に繋げられないKPIに関しては追うだけ無駄になります。KPIを追うだけ追って何も改善のアクションを切れなければ工数を追うコストだけ掛かってしまうのでむしろ追わない方が良いです。
リソースの限られているスタートアップ企業に関しては如何に大きなKPIの改善指標を明確にして、アクションが改善できるかに注力するべきです。
弊社のコンサルティングの基本方針として、
インパクトの無い改善施策は全て後回しにします。

THE MODELのメリットとして、KPI管理が複雑にできます。
これによって各セグメントでの最適化が実装しやすくなります。
一方で30社も支援をしていると大抵つまづくようなKPIの指標に関しては共通してきます。一方で絶対にここは死守しないといけないKPIも明確になってきます。
今日はここだけは絶対に管理してほしいというKPIを上げていきます。
これは私が現場に入ってARR1億円達成のコンサルティングを
行なってきた中でもはやこれしかみてなかったという
リアルな3つになります。
最重要指標
1: NEW MRR
→結論いくら、バケツの穴から水が漏れてもゲリラ豪雨が降り続ければ溢れます。NEW MRRさえ稼げる組織になればいくら解約されようが、関係ないです。むしろNEW MRRが毎月着実に伸ばせない企業はどうしても伸びません。
ちなみにこれはExpansion MRRは含みません。完全に新規顧客からの獲得MRRになります。組織が新規開拓を絶やさない文化を作るのは一朝一夕にはなりません。これは文化です。強い企業は必ず新規からMRRを作ることができます。
2: CHRUN MRR
→重要なのは解約MRRです。解約率とか、解約数はどうでもいいです。
MRR1万円のSMB企業が10社失注したとしても、MRR25万円のエンタープライズ企業の解約を防ぐ方が重要です。大手企業がIRで出しているようなCHURN RATE 0.5%みたいなのは圧倒的にSMBの受注企業数が多いからです。毎月多くて10社程度のスタートアップにおいては、1社解約したら10%、2社で20%です。スタートアップ初期はそもそもターゲットセグメントが目まぐるしく変わります。受注はできるけど、LTVは伸びない業界などプロダクトとマーケットの相性は明確に存在します。
だんだんと自社プロダクトのLTVが高く、かつリードタイムも短く、SOMが広いマーケットが見つかります。それまでは無理に受注をしたり、本当はマーケット外なのにゴリっと受注してしまうこともあります。解約率を気にしていたらどうしようもないです。とにかく大きいアカウントを落とさないように貴重なリソースはエンプラCSに集約することをお勧めします。
こういったことを加味するとやはり、単価の低いSMBマーケットをSLGでかつCS人員も割いて事業運営をするのは明確に死の谷を越えれないと感覚的にも分かりますね。
正直私が、コンサルティングをする上で意識しているのは上の2つだけです。
これさえ、目標値を立てて、しっかりと運営していければ勝手にARRは伸びていきます。私がご支援に入ってから2,3ヶ月は大体膿が出ます。
CHRUN MRR>NEW MRRの構造になります。
それはこれまで適切なオンボーディングフローや、営業フローができていなかったせいで全く状況不明の既存顧客が顕になるからです。
しかし、3ヶ月もすればCSとSALESとマーケ整備が最低限整い
NEW MRR>CHRUN MRRの構造になります。
こうなれば後は、如何に各リードソースの転換率を最大化していくかと
リードソースを増やすだけの簡単な作業になります。
だからARR1億円なんて余裕なのです。
3: ARPA
→結局は単価が命です。単価が低いSaaSが待つ未来は地獄です。営業しても営業しても儲からない。CSをしたら赤字になるのでサポートができない。エンタープライズ企業に売ろうがSMBに売ろうが単価が変わらないので、エンタープライズ向けの営業戦略を組めない。広告のCPAも上げられないのキーワード競争に負ける。行き着く先は完全な蟻地獄です。
単価が上がるとこんないいことがあります。
・まずはリスティングのキーワード単価が挙げられて、流入が増えます。
・流入が増えると対応する優先順位がつけられるので予算の多い企業には潤沢な営業提案を実施することができます。
・受注数は少なくなっても単価が高いので問題ありません。
・受注した後はしっかりとカスタマーサクセスを行うことができるので顧客満足度も高くLTVも伸びやすく、解約率も低くなります。
・従業員の残業時間は減り、SMB企業のクレーム対応の必要も少なくなります。
実はSaaSはプライシングが命なのです。私はプライシングコンサルティングを最も得意としています。最も高い単価で、かつ受注率には最大限影響しない最高のプライシングを作ることができます。私の実績平均として、最低2倍〜最大で4倍ほどプライシングを上げた実績があります。
プライシングに関しての重要性はこちらで解説しております。
もちろんこういった支援企業は楽々ARR1億円を達成しています。
プライシングは本当に難しいです。私は、これまでの数十社での経験と
綿密な競合調査、営業メンバーの戦闘力、プロダクト力を総合的に加味して最適なプライシングを提供しています。なので普通の人には難しいかもしれませんが、ポイントだけお伝えします。
1、必ずエンタープライズ向けにプライシングを設計してください。
→最低単価は5万円のプランにしてください。
2、SMBの方も購買できるプライシングである必要があります。
→受注の8割は結局SMBになります。SMB企業でもギリギリ買える
プライシングにすることによってマーケットが一気に増えます。
3、とにかくシンプルにしてください。
→人数制限がある、機能が細かく変わるなど
検討の障害、リードタイムの増加になる要因は
全て排除してください。
ARPAを上げるにはプライシングを変える以外にもマーケットを変えるの方法がありますが、正直プライシングを変えるほど楽にARPAをあげられる方法はないです。私がコンサルで入らせていただく中で感じることは、殆どの企業様が安すぎます。エンタープライズ企業のお財布からすれば、正直100万以下は一緒という感覚をまずは持っていただくと良いと思います。
エンタープライズ営業に関する記事はこちらです。
ということで、私の提案としてはこうです。
■マーケ・セールス・カスタマーサクセスは
1人の独裁者がスピード感を持って判断をしていくべき。
■セールス・カスタマーサクセスに関しては分断をしないで担当性にする。
(tier規模での振り分けがお勧め。)
■細かいKPI管理よりもとにかく新規受注がしっかりとできる組織をまずは作っていく。
■従業員が10名、ARR1億円を突破したタイミングでTHE MODELを取り入れていく。
これらを管理するには、Salesforce、hubspot無しには難易度が高いので
そういった管理ツールとしてはぜSFA・CRMをご検討いただけると良いと思います。
今回はスタートアップSaaS企業においては
「THE MODEL」を否定する形にはなってしまいましたが、
組織が10名を超えてきたり、ARRが1億円を超えてくるような状況になれば
もちろん「THE MODEL」が段々と全体最適であってくると思います。
私はとにかくプロダクトを高く売って、
最短で粗利を積むことにしか興味がない人間です。
30社以上のSaaSを支援してきた中であらゆるケースを見てきて、
経営者の方と並走させてきていただいた中で1年以内の
最短最速でARR1億円を達成させることに成功しています。
ぜひ、1人でも多くのSaaS経営者の方が
最短・最小の投資でインパクトのある事業を作れることを祈っております。
ぜひTwitterで感想や拡散をいただけると非常に嬉しいです。
もし何か力になれることがあればお気軽にご相談ください。
大人気の佐藤コンサルのご予約もぜひ承っております。
お気軽にご相談くださいませ。
9/17 現在有料チケットが全て売り切れておりまして、
次回の相談募集は11月を予定しております。
11月に再販するので、ご希望の方は事前予約承ります。
#チケミー
— 佐藤匠┃株式会社セールスのタクミ SaaSスタートアップ専門の営業コンサル (@takumi_startup) September 15, 2023
10枚完売しました!
私を信頼して投資して下さった
9社の代表様は責任をもって
アドバイザリーいたします。
ようこそ匠ファミリーへ。
私は必ずバリューを出します。
これをもちまして、
【9月・10月】
全ての新規法人様の
ご相談を停止と致します。
またの機会にお会いしましょう。 https://t.co/Qw3jibKIg7
Twitterのフォローやいいねも全て見ております。
いつも応援してくださる匠パートナーの皆様、
ありがとうございます!
ぜひご感想を投稿いただけますと嬉しいです。
人気の記事
いいなと思ったら応援しよう!

