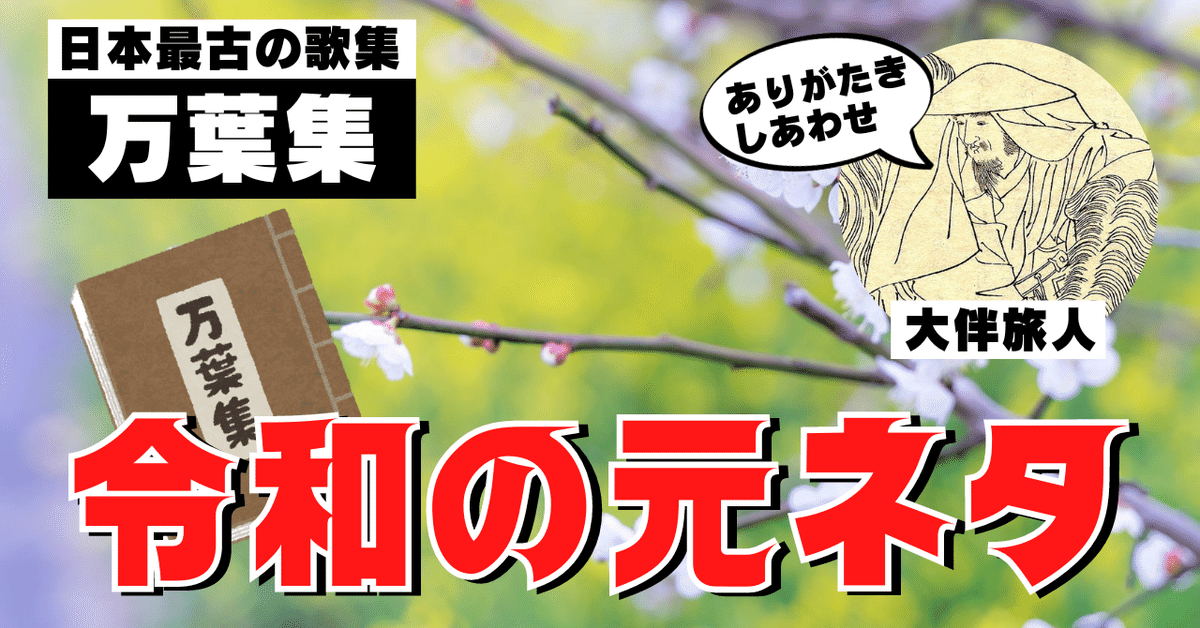
【万葉集】令和の元ネタとなった日本最古の歌集を4つの時期に分けて見てみた【大伴旅人】
どーも、たかしーのです。
今回は、日本最古の歌集『万葉集』について、書いていきたいと思います!
「万葉集」基本情報
現存する日本最古の歌集
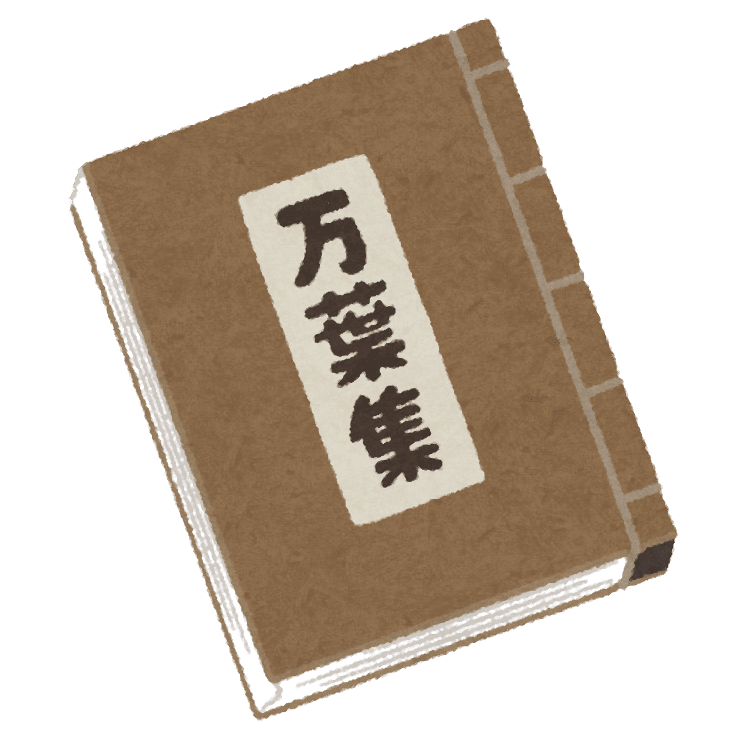
『 万葉集』は、現存する日本最古の歌集で、7世紀後半から8世紀後半にかけて編纂がされました。成立したのは、奈良時代末期とみられています。※奈良時代=710~784年までの74年間。
『万葉集』の名前の意味は、「万葉」の解釈で諸説あり、
「万葉」を”多くの言葉”と解釈して、多くの言葉や歌を集めたもの
「万葉」を”長い世代”と解釈して、末永く語り継がれるべき歌集
といった意味が込められているのでは?と考えられています。
ボリュームは全20巻あり、その中に約4500首の歌が収録されています。
日本最古の歌集ということもあり、後世に続く文学作品や勅撰和歌集に多大な影響を与えました。
詠み人は天皇から一般庶民まで身分関係なく収録されている
『万葉集』は、天皇から一般庶民までと、登場する作者の身分的階層が幅広い特徴を持っています。また、作者別で書いた歌の数をランキングにすると、上位5名はご覧の通りとなります。
1位 作者不詳 約2,000首
2位 大伴家持 約470首
3位 柿本人麻呂 約90首
4位 坂上郎女 約85首
5位 山上憶良 約80首
なんと『万葉集』の半分弱を、名もない人々による歌が占めています。中でも巻十四に収録された歌(約230首)に限っては、全てが作者不詳となっています。
ちなみに、2位の大伴家持の歌がなぜ圧倒的に多いのかについては、のちほど説明することにします。
このように、身分や知名度に関係なく、当時の人々の思いが決まった文字数の言葉でまとめれていることから、近年では”古代のツイッターまとめ”として例えられたりもします。(今となっては、Xまとめですが…)
収録された歌のテーマは「雑歌」「相聞」「挽歌」
『万葉集』は編纂にあたっては、いくつかのテーマが設定されていたと考えられており、同じ内容を持つ歌がまとめて収録されています。
『万葉集』の代表的なテーマは、次のとおりです。
雑歌(ぞうか):宮廷などの公式行事で読まれた歌
相聞(そうもん):男女が詠み合う恋愛の歌
挽歌(ばんか):死者を悼み悲しみを表現する歌
また、万葉集の歌体は、短歌・長歌・ 旋頭歌の3種に区別されています。
短歌(ぞうか):五・七・五・七・七の五句からなる歌
長歌(ちょうか):五・七を長く続け、最後を五・七・七という形式で結ぶ歌
旋頭歌(せどうか):五・七・七・五・七・七の六句からなる歌 ※頭句を再び旋(めぐ)らす歌、であるため、そう呼ばれる
『万葉集』4500首の歌のうち、ほとんどを短歌が占めています。長歌は260首くらいあります。
内容はすべて漢字で書かれている

※元暦校本・・・平安時代に書写された『万葉集』の古写本のひとつ
『万葉集』が書かれた当時は、まだかな文字がありませんでした。そのため、全文が漢字で書かれていますが、その使い方はとてもユニークです。
のちに「万葉仮名」と呼ばれる表記法が用いられており、漢字の意味に関係なく、音訓の読みだけを現在のカタカナ、ひらがなのようにして、使われています。
4つの時期で見る「万葉集」
『万葉集』が書かれた時代は、大きく分けて4つの時期に分類することができます。今回は、この4つの時期(第一期~第四期)に沿って、詠まれた歌などを中心に描いていきます。
※なお、今回の内容は、NHKの番組「100分 de 名著」の「万葉集」回に登場された佐佐木幸綱先生(国文学者・歌人)の見解を参考に、まとめさせていただきました。
第一期:舒明天皇即位~壬申の乱(629年~672年)
【時代背景】
・645年:乙巳の変により、中大兄皇子が蘇我入鹿を暗殺。
・658年:謀反の疑いにより、中大兄皇子が有間皇子を処刑。
・663年:白村江の戦いで、倭国は唐・新羅連合軍に敗北。
『万葉集』は、雄略天皇(第21代)によるナンパの歌から始まります。(えっ!)ちなみに、雄略天皇が在位していた期間は、457年~479年ごろと推定されているため、この時代に生きた人ではないのですが、次のような歌が『万葉集』の冒頭に載っています。

(万葉仮名)
籠毛與 美籠母乳 布久思毛與 美夫君志持 此岳尓 菜採須兒
家吉閑名 告紗根 虚見津 山跡乃國者 押奈戸手 吾許曽居
師吉名倍手 吾己曽座 我許背齒 告目 家呼毛名雄母
(万葉仮名→漢字・ひらがな)
籠(こ)もよ み籠持ち 掘串もよ み掘串持ち この岳に 菜摘ます兒
家聞かな 告らさね そらみつ大和の国は おしなべて我こそ居(を)れ
しきなべて 我こそ座せ 我にこそは告らめ 家をも名をも
(現代語訳)
美しい籠やヘラを持って、この丘で菜をお摘みのお嬢さん、
君はどこの家のお嬢さんなのか教えてくれないか。大和の全てを私が治めているのだ。
私こそ教えよう、家柄も名も。
この歌は、文字だけ読むと天皇が若い娘に求婚している歌のように見えますが、その真意は豊作を祈る一種の農耕儀礼を表現した歌であると考えられています。つまり、絶対的権力者である天皇が自ら農業を営む娘子に求婚することで、今年の豊作を祈願するといった意味が込められているわけです。
また、ナンパと捉えてしまうと、『万葉集』を通じて、雄略天皇の単なる黒歴史が文字として末永く残ってしまっているとも捉えがちですが、この歌が豊作を祈念した歌ということであるとするならば、これは言霊を信じて文字として残したとも受け取ることができるのです。
言霊とは、言葉に内在する不思議な力のことで、古代日本では言葉の「言(コト)」と実際に起きる「事(コト)」は同じであるとして、信じられてきました。今でも受験生に対して「すべる」や「おちる」など言ってはいけないといったことを言う人がいますが、これは現在にも言霊信仰が色濃く残っている証とも言えます。
すなわち、この歌を冒頭に持ってきた理由としては、天皇が詠んだ歌であることもありますが、言霊を信じて、毎年の五穀豊穣を願って冒頭に持ってきたとも考えられるのです。
同じような歌で、額田王が詠んだ歌があります。
(万葉仮名→漢字・ひらがな)
熟田津(にきたつ)に 船乗りせむと 月待てば 潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな
(現代語訳)
熟田津で船出をしようとして月の出を待っていると、潮も満ちてきた。さあ、今こそ漕ぎ出そう。
額田王は、斉明天皇(第37代)に仕えた歌人であり、この歌も斉明天皇になり変わって詠んだ歌とされています。
この歌が詠まれたのは、白村江の戦い(663年に勃発)の前であり、中大兄皇子(後の天智天皇)の軍が、唐・ 新羅の連合軍と戦う 百済を援護するために、 飛鳥(現在の奈良県)から北九州へ向かう途中、伊予(現在の愛媛県)の熟田津という土地に立ち寄った際に詠まれたと考えられています。
この歌も言霊の一種であり、ただ単に、波の様子を謳ったのではなく、白村江の戦いへの戦勝祈願が込められています。
他にも、魂を鎮める歌として、以下のような歌が詠まれています。
『万葉集』には、謀反の疑いを着せられ、処刑された有間皇子の歌も収録しています。
(万葉仮名→漢字・ひらがな)
磐代の 浜松が枝を 引き結び まさきくあらば また帰り見む
(現在語訳)
岩代の松の枝に願い事を書いた紙を結び、運が良ければ帰りに見ることができよう。

ちなみに、この歌を詠んだ後に、有間皇子は処刑され、実際には松の枝に結んだ紙を見る事はなかったのですが、後世の歌人がこのような歌を残しています。
(万葉仮名→漢字・ひらがな)
磐代の 野中に立てる 結び松 心も解けず 古思ほゆ
(現在語訳)
岩代の野の中に立つ結び松よ、いつまでも枝を解かぬように私の心の悲しみも解けず、昔の事が思われてならない。
(万葉仮名→漢字・ひらがな)
後見むと 君が結べる 磐代の 小松がうれを またも見むかも
(現在語訳)
後で見ようと皇子が結んだ岩代の小松の梢(こずえ)を私も見ることになるでしょうか。
どちらも、有間皇子が詠んだ松が歌に登場していることがわかります。
これは、歌の中に松を詠むことで、有間皇子を想い、魂を鎮めるためであったと考えられています。
第二期:壬申の乱~平城遷都(672年~710年)
【時代背景】
・672年:天智天皇が崩御/壬申の乱が勃発
・673年:天武天皇が即位
・690年:天武天皇の皇后であった 鸕野讚良が持統天皇として即位
・694年:飛鳥浄御原宮から藤原京に遷都
672年、天智天皇がなくなったことで、天皇家の後継者争いである壬申の乱が勃発しました。これにより、勝利した天智天皇の弟・大海人皇子が天武天皇(第40代)として即位します。

天武天皇は、天皇を中心とした中央集権国家を目指した人物で、のちの日本の政治基盤となる律令制の導入に向けた制度改革を進めたり、天皇家の正統性をアピールするため、国史(『古事記』『日本書紀』)の編纂を命じたりもしました。
また、即位中に成し遂げることはできませんでしたが、新しい都(藤原京)の造営にも、天武天皇は取り組んでいました。
↓『古事記』の内容については、こちらをどうぞ。
そんな偉大な天皇を称える歌が、この時期の『万葉集』ではいくつも詠まれています。
(万葉仮名→漢字・ひらがな)
大君は 神にしませば 赤駒の はらばふ田居(たゐ)を 都となしつ
(現在語訳)
天皇は神でいらっしゃるので、赤駒が腹ばう田を、都としてお造りになった。
(万葉仮名→漢字・ひらがな)
大君は 神にしませば 水鳥の すだく水沼(みぬま)を、都となしつ
(現在語訳)
天皇は神でいらっしゃるので、水鳥(みづとり)が群がり集まる水沼を、都としてお造りになった。
(万葉仮名→漢字・ひらがな)
大君は 神にしませば 天雲の 雷の上に 廬(いほら)せるかも
(現在語訳)
天皇は神でいらっしゃるので、天雲の雷の上に仮のやどりをしておられることよ。
端的にいうと、天皇、神ってる!という歌が収録されています。
例えば、1つ目の歌では「馬の脚が沈み込むような深い田んぼを整地して都にしてしまった」といった人間では実現不可能と思えることを、「天皇は神でいらっしゃるので」に続けて詠んでいるといった内容になります。
また、この時期になると、そのときのニーズにあった歌を詠むプロ歌人が登場するようになりました。
その一人が、柿本人麻呂です。

柿本人麻呂は、持統天皇と吉野(現在の奈良県ほぼ中央)に出かけた際に、このような歌を詠んでいます。
(万葉仮名→漢字・ひらがな)
やすみしし 我が大君 神ながら 神さびせすと
吉野川 たぎつ河内に 高殿を 高知りまして 登り立ち
国見をせせば たたなはる 青垣山
やまつみの 奉る御調(みつき)と
春へには 花かざし持ち 秋立てば 黄葉(もみじ)かざせり
行き沿ふ 川の神も 大御食(おおみけ)に 仕へ奉ると
上つ瀬に 鵜川を立ち 下つ瀬に 小網(さで)さし渡す
山川も 依りて仕ふる 神の御代かも
(現在語訳)
わが天皇が神として ご意志のままに神らしく お振舞いになるために
吉野の川の急流の谷間に 立派な高殿をお建てになって登り立ち
国見なさると 幾重にも連なる山の峰々は
山の神がこれですと差し出す貢ぎ物として
春には花を髪に挿し 秋になると色づいた紅葉を飾り立てている
離宮に流れ沿う川の神も帝にお食事をさし上げようと
上流の瀬で鵜飼いして 下流では網で魚をすくい獲る
山や川の神までが従い仕えるありさまは 神の帝の御代である
実は、この歌の中には、プロ歌人らしいテクニックが、豊富に盛り込まれています。
テクニック① 枕詞で天皇の偉大さを強調させる
まず、歌の冒頭で「やすみしし」という言葉が使われています。これは後に続く「我が大君」を引き立てるための枕詞であり、柿本人麻呂は、よく自身の歌の中で枕詞を駆使して、歌を詠んでいました。
この「やすみしし」は「八隅知し」とも読み取れ、国を隅々までよく知っているという意味が込められています。
テクニック② 擬人法でさらに天皇の偉大さを強調させる
次に、自然を神様からの貢ぎ物と例えて、歌を詠んでいます。
「たたなはる 青垣山 やまつみの 奉る御調(みつき)と」は、「幾重にも連なる山の峰々は 山の神がこれですと差し出す貢ぎ物として」という意味があり、吉野の豊かな自然は山の神様からの貢ぎ物であると例え、「行き沿ふ 川の神も 大御食(おおみけ)に 仕へ奉ると」は、「離宮に流れ沿う川の神も帝にお食事をさし上げようと」」という意味があり、吉野を流れる川の魚も川の神様からの貢ぎ物であると例えています。
これは、対象が神様ではありますが、擬人法を取り入れており、あたかも山や川が人であるかのように例えて、山も川も天皇に仕えていることを表現しています。そうすることで、天皇の権威を歌でますます際立せていることにもつながります。
テクニック③ 対句を用いて長歌のリズムをよくしている
最後に、高等テクニックとして、対句が用いられています。
「やまつみの 奉る御調(みつき)と」⇔「川の神も 大御食(おおみけ)に」(山と川を対比)
「春へには 花かざし持ち」⇔「秋立てば 黄葉(もみじ)かざせり」(春と秋を対比)
「上つ瀬に 鵜川を立ち」⇔「下つ瀬に 小網(さで)さし渡す」(上つ瀬と下つ瀬を対比)
このような対句を用いることで、お互いのフレーズを際立たせることができ、また長歌自体のリズムもよくなるという効果があります。
このように計算をされ尽くした柿本人麻呂の長歌ですが、おそらくはその場で思いついて詠んだのではなく、歌を添削しながら、要所に自身のテクニックをふんだんに取り入れ、詠んだであろうと考えられています。
こうした歌を多く詠んだ柿本人麻呂は、後世において「歌聖」と呼ばれるようになります。
↓「柿本人麻呂」については、こちらもどうぞ。
第三期:平城遷都~山上憶良 没(710年~733年)
【時代背景】
・710年:藤原京から平城京に遷都
・712年:『古事記』成立
・720年:『日本書紀』成立
710年に、藤原京から平城京に遷都し、奈良時代が幕を開けます。
この頃になると、個性的な歌が次々と生み出され、『万葉集』を代表する歌人がぞくぞくと登場します。
山部赤人は、自然の風景を描き出すような叙景歌に優れた歌人として有名な人物です。

(万葉仮名→漢字・ひらがな)
田子の浦ゆ うち出でてみれば 真白にそ
富士の高嶺に 雪は降りける
(現代語訳)
田子の浦を過ぎ、広い海にこぎ出でて眺めてみると、真白に、富士山の山頂に雪が降っていることよ。
この歌の特徴は、空の描写を全く詠んでいないのにもかからず、青空をバックとした富士山の情景が目に浮かぶことにあります。
富士山に積もる雪が真っ白であることを強調することで、空の情景は言わずとも取れるような表現しているところが、 山部赤人のスゴイところですね!
人生を見つめる長歌を詠んだのが、大伴旅人です。

大伴旅人は、実は高千穂にニニギが降り立った「天孫降臨」神話に登場するアメノオシヒを祖神にもつ大伴氏の末裔であり、歌人でありながら、朝廷の軍事を司る役職も担っていました。
↓「天孫降臨」神話については、こちらをどうぞ
そんな大伴旅人ですが、60歳を過ぎてから、大宰府に赴任していたときのこと。都で義理の弟(妹の夫)であった 大伴宿奈麻呂が亡くなったという知らせを受けたときに、このような歌を詠んだとされています。
(万葉仮名→漢字・ひらがな)
世間(よのなか)は 空(むな)しきものと 知る時し
いよよますます 悲しかりけり
(現代語訳)
世の中は空しいものといいますが、このような悲しい知らせをうけて、さらに深い悲しみに暮れていくのです。
実は、この歌を詠む2か月ほど前に、最愛の妻であった 大伴郎女を亡くしていたのでした。
まさに、大伴旅人は、悲痛すぎる心情を、歌として見事に昇華していると言えるかと思います。
そして、この悲痛な大伴旅人を想い、それらを歌にしたためたのが、山上憶良でした。
実は、 山上憶良は、大伴旅人が大宰府に赴任していた当時、朝廷から筑前守(筑前国の国司の長官)に任じられ、同じく九州に赴任をしていました。※筑前国=現在の福岡県西部
こうした背景から、山上憶良は次のような歌を詠んでいます。
(万葉仮名→漢字・ひらがな)
悔(くや)しかも かく知らませば あをによし
国内(くぬち)ことごと 見せましものを
(現代語訳)
悔しいことだなあ、こうなると知っていたなら国中をすべて見せていただろうに。
(万葉仮名→漢字・ひらがな)
妹(いも)が見し 楝(あふち)の花は 散りぬべし
我が泣く涙、いまだ干(ひ)なくにも
(現代語訳)
妻が見た楝(あふち)の花は、もう散ってしまうでしょう。私の涙は、まだかわくことが無いのに。
おわかりいただけたでしょうか。
なんと、山上憶良は、妻や義理の弟を亡くした大伴旅人になりきって歌を詠んでいます。
このような歌から、山上憶良は、他人のことをまるで自分のことのように思いやることができる歌人として、大変評価をされています。
↓「山上憶良」については、こちらをどうぞ。
第四期:山上憶良 没~万葉集最後の歌(733年~759年)
【時代背景】
・735~737年:天然痘が大流行(天平の疫病大流行)
・743年:墾田永年私財法を施行
・752年:東大寺大仏の開眼供養
この頃になって、登場したのは、大伴家持という歌人でした。
大伴家持は、先ほど紹介した大伴旅人の息子であり、『万葉集』の編纂に大きく関わった人物として知られています。
その根拠として、『万葉集』に収録された最後の4巻は、大伴家持の歌を中心に構成がされており、また、約4500首ある『万葉集』の歌のうち、約470首(全体の約1割)が大伴家持の歌ということから見ても、そうではないか?と言われています。

また、大伴家持は「山柿の門にいたらず」という言葉を残しています。
この「山柿」は、先代の歌人のことを指していて、「山」は山部赤人か山上憶良のどちらか、「柿」は柿本人麻呂であると言われており、これか歌人から影響を受けていたことがわかります。
こうした先代の歌人には至らないという思いを見るに、『万葉集』に収録された先人たちの歌をよく読んで学び、また自身も歌を書いては詠み、歌人として高みを極めたものと考えられます(その結果、めっちゃ歌を書くことになる家持…)。
大伴家持が残した歌として、次のようなものがあります。
(万葉仮名→漢字・ひらがな)
春の野に 霞たなびき うら悲し この夕影に うぐひす鳴くも
(現代語訳)
春の野に霞がたなびいて心は悲しみに沈む。この夕光の中に鶯が鳴くよ。
(万葉仮名→漢字・ひらがな)
わが宿の いささ群竹(むらたけ)吹く風の 音のかそけき この夕(ゆうべ)かも
(現代語訳)
わが家のわずかな群竹を過ぎる風の音のかすかな、この夕暮よ。
(万葉仮名→漢字・ひらがな)
うらうらに 照れる春日に ひばり上がり 心悲しも ひとりし思へば
(現代語訳)
うららかに照っている春の日に、雲雀が飛びかけり、心は悲しいことよ。ひとり物を思うと。
これらは『万葉集』屈指の名歌と名高い歌であり、「春愁三首」と呼ばれています。哀愁漂う作風には、父である大伴旅人の影響も感じられます。
しかしながら、これには大伴旅人と同じくワケがあり、大伴家持は、この歌を詠んだ当時は、朝廷から因幡国府(因幡国の国司の長官)に任じられ、都から離れた暮らしをしていました。こうした暮らしをする中で、大伴家持は、寂しさやモヤモヤを感じ、これらの想いを歌に込めて払おうとしたと言います。
また、「春愁三首」に関しては、「うぐひす鳴くも」「吹く風の 音のかそけき」「ひばり上がり」といった、かすかな自然の音や鳥の鳴き声が詠まれているのも特徴で、赴任した因幡国がとても静かな環境であったことが、ここから伺えます。
そして、『万葉集』最後の歌も、大伴家持が書き、こう締めくくっています。
(万葉仮名→漢字・ひらがな)
新(あらた)しき 年の始めの 初春の 今日降る雪の いや重(し)け吉事(よごと)
(現代語訳)
新しい(改まった)年のはじめの、新春の今日を降りしきる雪のように、いっそう重なれ、吉き事よ。
ここで注目すべきは、「新しき」を「あらたしき」と詠んでいることです。
実は、「新しい」の語源は「改める」から来ており、この当時の感覚としては、新しい年を迎えるというよりは、年を改めるといった感覚だったことがわかります。
これは、干支(十干十二支)が影響していて、時間や月日は循環するという考え方が根底にあったため、と考えられています。
↓「干支」に関しては、こちらをどうぞ。
続いて、「初春の」と呼んでいますが、これは『万葉集』冒頭にあった雄略天皇の歌を意識しているものと考えられています。
ちょっと分かりづらいかもですが、最初にあった雄略天皇の歌は、今年の豊作を祈願する歌ということで、春の歌と捉えることができます。
こうした最後の歌も、同じ春の歌にすることによって、春の歌で始まり、春の歌で終わるといった一貫性を持たせていると考えられています。
最後に、「いや重(し)け吉事(よごと)」ですが、これも一貫性であり、言霊で始まり、言霊で終わることを意識して、大伴家持が詠んだものと考えられています。
終わり良ければ、全て良しということですね!
↓「大伴家持」に関しては、こちらをどうぞ。
「万葉集」と令和

(内閣官房内閣広報室 - 首相官邸ホームページ)
2019年5月1日から施行された元号「令和」は、この『万葉集』が典拠となっています。
具体的に典拠となったのは、『万葉集』第五巻に収録された「梅花歌三十二首 并序」の序文です。※なので、歌ではありません。
(原文)
初春令月 気淑風和 梅披鏡前粉 蘭薫珮後之香
(書き下し文)
初春の令月(れいげつ)にして、気淑(きよ)く風和ぎ、梅は鏡前の粉(こ)を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香(こう)を薫らす
(現代語訳)
時あたかも新春の好き月、空気は美しく風はやわらかに、梅は美女の鏡の前に装う白粉のごとく白く咲き、蘭は身を飾った香の如きかおりをただよわせている。
この序文の「令月」と「風和」から一文字ずつとり、元号が「令和」に制定されました。ちなみに、元号の典拠が国書となったのは、実はこれが初めてで、それまでは漢籍(中国において著された書籍)を典拠とするのが、慣例となっていました。

また、この序文のあとに、文字通り「梅の花」をテーマにした歌が続くわけですが、実はこれらの歌は、大宰府の長官であった大伴旅人の邸宅にて開かれた「梅花の宴」で詠まれた歌が収録されています。
この宴で、大伴旅人は、
(万葉仮名→漢字・ひらがな)
わが園(その)に梅の花散るひさかたの天(あめ)より雪の流れ来るかも
(現代語訳)
わが家の庭に梅の花が散る。はるか遠い天より雪が流れて来るよ。
と、なんとも優雅な歌を詠んでいます。
ちなみに、梅の花は、唐から渡来した植物であったため、当時の日本人には珍しい植物だったようです。なので、歌にして残したかったのだと思います。
悲しく切ない歌を詠んでいた大伴旅人でしたが、こうして今開いた宴の話が元号になり、実に良かったなあと、感じました。
おわりに

今回は、『万葉集』について、書いていきました。
いろいろ盛り込んでしまった結果、1万字を超えてしまいました。
最後まで読んでくれた皆様、大変お疲れ様でございました。
ただ、『万葉集』の歌人については、まだまだ書き足りないところがあるので、それはまた追々書いていくことにします。
最後になりますが、「100分 de 名著」に登場された佐佐木幸綱先生が、たいへん興味深いことをおっしゃっていましたので、ここに書きおこしをしておきます。
「勝ったものは歴史を作るけれども、負けたものは文学を作る」
なので、文学作品をこういった目線で読んでみるのも、面白いかもしれませんね!
他にも、歴史上の人物や神話などをベースに、記事を書いていく予定ですので、是非フォローなどしてもらえるとありがたいです!
それでは!
