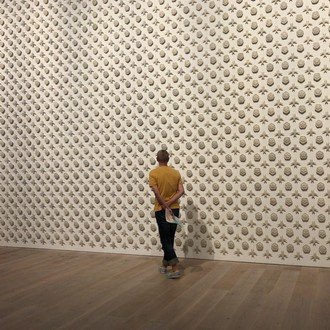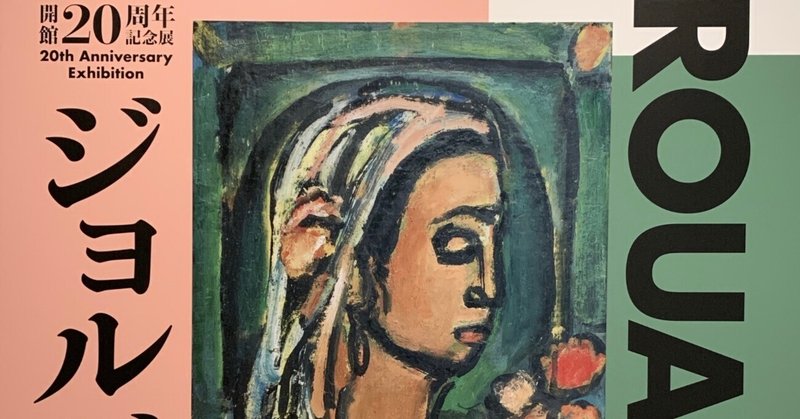記事一覧
やっと、つながるカレー
これまでなんとなく視野に入っていた「カレーキャラバン」プロジェクト。
慶応SFCの加藤文俊先生が行っている活動だ。
街に出かけていき、そこで食材を手に入れカレーをつくる。
提供は無償。先生はそこで生まれるアクシデンタルな出合いやコミュニケーションに価値を置いている。その「カレーキャラバン」、よくよく見ると、加藤先生のソロ活動では「カリーキャラバン」となっている。「カレーキャラバン」は無期休業で、「
映像エスノグラフィーが捉えるもの
久しぶりに映像エスノグラファーである大橋香奈さんと、大橋さんと同じ慶應義塾大学政策・メディア研究科で学んだジョイス・ラムさんの映像を見に、藤沢アートスペースまで出かけた。大橋さんは、私が何度か書いている〝Home in Tokyo〟のナビゲータを務めた、いわば私の先生のような立場の人だ。ジョイスさんとも〝Home in Tokyo〟で出合っている。
今回は、ジョイスさんの展示がメインで、その特別
そこに封じ込められた時代感。
パナソニック汐留美術館 開館二〇周年記念展
「ジョルジュ・ルオー かたち・色・ハーモニー」
汐留にジョルジュ・ルオーを見に行った。
パナソニック汐留美術館は、開館以来、ルオーの作品を継続的に収集し、
二〇二三年三月時点で二六〇点を所蔵しているそうだ。
今回は、フランスや国内の美術館などから、国内初公開作品含む
初期から晩年までの代表作約七〇点が展示される。
〝かたち・色・ハーモニー〟とは、ルオ