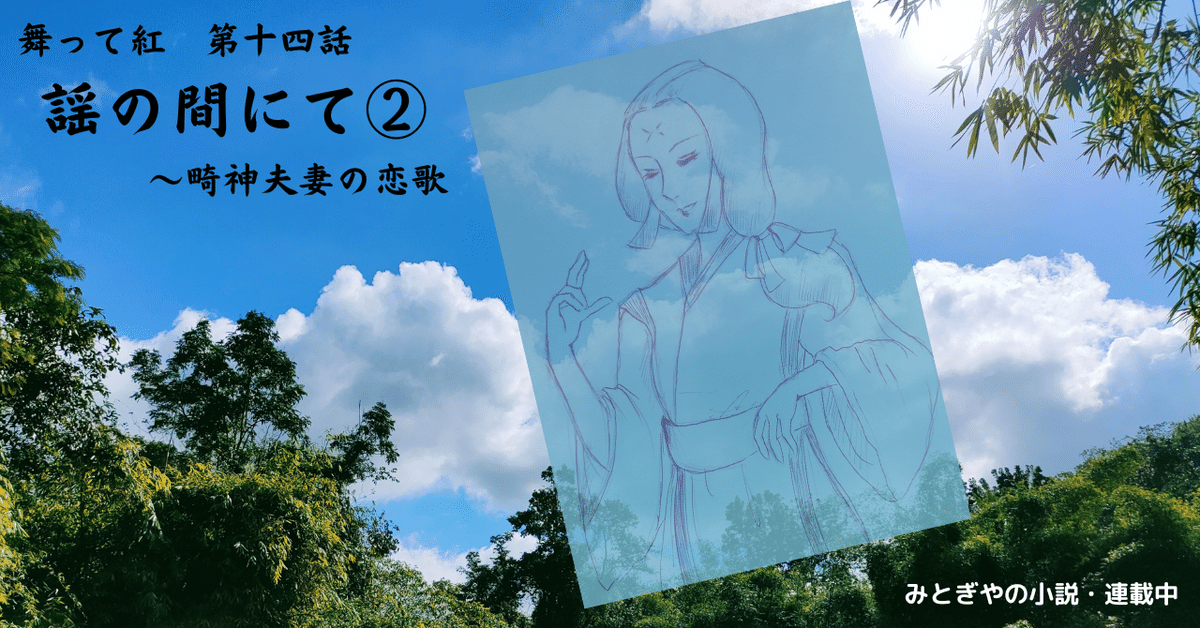
謡の間にて②~畸神夫妻の恋歌 舞って紅 第十四話
「特に好きなのは、クワイを茹でたものだ。口当たりがシャキッとして、飯に合う。醤をつけて、食べる。かぶらも好きだ。汁に入っていると、とろりとして、甘い」
「わかりました。覚えておきます。献立作りの時に、炊屋で、皆さんにお願いしてみますね」
「ああ、無理には、私などの好みなんか、どうでもいい。御師匠のいいように」
「ああ、そう、巣蜜は召し上がったこと、ありますか?」
「いや、ない。ただ、蜂の蜜は、少量を、夏の暑い時に、氷にかけて頂くことがある。氷が氷室から無事に融けずに、ここまで来た時で、蜂の蜜が手元にある時じゃないと頂けない。だから、とても、珍しい」
「まあ、そんな、美味しそう・・・」
「アカは、食べたことないのか?」
「・・・はい」
アカは、心の中で舌を出した。これは、確かに高級品なのだ。その安行の言った通りの理由で、そんな贅沢な代物だ。とすると、その条件を満たすのは、上流の殿上人なのだ。美しい舞姫を侍らせるのと同様に、その高級品が、酒席に並ぶことがある。アカも食べさせてもらったことがある。藤殿の席であった。脂粉にまみれた男の冷たい唇を思いだした。甘い冷たい菓子は美味かったが、残念ながら、その後は、良いものではない。仕方がない。欲しいのは、その男ではない。その貴族のお道具を満たしながら、情報を取ったのだからな、あの夜は・・・。アカは、不本意ながら、そのことを思い出した。甚く、悦んでいたな、あの貴族様は・・・。ふと、安行の声で、我に返る。
「疲れただろう。よかったら、明日から、謡を聞かせてもらいたいのだが」
「いいえ、宵には、よろしいかと」
「今宵で良いのか?」
「その内容によりますが、大概、謡舞いをするのは、夜の酒席が多いですから」
「酒は嗜まない。それに、これは、その謡を遺す為のものじゃから、申し訳ないが、何度もやって頂かなければならないと思う。今日は、休んで、明日からでもいい」
「そうなんですね。わかりました。でも、大丈夫ですよ。安行殿がお疲れなら」
「いや、そんなことはない・・・本当は、一早く、そなたの謡が見たい・・・んだが」
また、言って、真っ赤になられている。
「嫌、違う。そんな意味ではなくて・・・」
「うふふふ・・・」
「違うんだ、アカ」
またまた、何を、否定されてらっしゃるのか・・・。
「いいですよ。じゃあ、すぐにでも、お見せしましょうか?・・・ご準備が必要なのでは?」
「いいのか?もう?」
「はい」
「では、文机を硯と、新しい紙では勿体ないので、紙の背を使わせてもらわなければ・・・」
「御清書は、能福殿にして頂くのですね?」
「まずは、アカ殿の謡を、私が、そのまま、聞き起こし、その後に纏めてから、初めて、新しい紙に、能福殿が清書される・・・手間がかかるが、少しずつ、付き合って頂けるか?」
「はい、勿論、その為に、あたしは、ここに呼ばれて、来たんですから」
「・・・ありがたいことだ。御師匠から、本物の舞巫女の謡が聴けると聞いて、しかも、伝説のアサギ殿の孫娘と聞いて。こんな光栄なことはない」
「まあ、そのように、安行殿に言って頂けるなんて、嬉しゅうございます」
アカは、丁寧に平伏して見せた。顔を上げる、安行は、嬉しそうに頭を掻いている。
「では、よろしく頼む。アカ殿」
「早速、どの辺りから?・・・やはり、『畸神夫妻の恋歌』から、参りましょうか?」
「ああ、それは、存じておるが・・・実際に、謡を聴いたことはないので、是非、聴いてみたい。お願いできるか?」
アカは頷き、そのままのいで立ちで、舞い始めた。アカの動きと共に、その場の雰囲気が変わり、安行は息を飲んで、それを見つめた。これは、書き留める必要はないので、集中して、見聞きすることにした。
『・・・さ蕨の、温もりの・・・緑に舞ひ、息作り・・・雷鳴の轟にも、惹き上がり…渦巻く焔に・・・氷解の果てに・・酔ひ乱れつも、し尽く終ひ・・・』
アカは、謡いながら、舞い踊った。そこには、衣装も小道具も持たぬままだったが、充分に、その意と、雰囲気を伝えるに至る熟しとなった。安行は、短いながらも、それに惹き込まれたようだ。謡い終わり、平伏すアカに、拍手を送った。
「・・・凄い、なんというのか・・・。畸神ご夫妻様方のお心持ちが響くような、空気が変わったようだ。それに、アカが、いずれかの、陽の伽畸神様に見えたようじゃ。・・・美しい謡だった」
うふふ、と笑いながら、アカが顔を上げると、安行は、また、驚いた顔をした。
「ああ、元のアカに戻ったな。・・・しかし、勿体ない。私の為にだけ、謡い、舞ってくれたなんて・・・」
「そんな、お約束ですから・・・」
「それにしても、謡うとあのようになるのか・・・」
「これは、巫女によって、節回しが変わります」
「そうなのか?」
「そうなんですよ。あたしが謡うと、こうなります。母者に似てますが、やはり、違うそうです。アサギのお婆とも違うそうです」
「口伝と聞いたが・・・」
「内容は変わりませんが、その巫女の感じが入るようですから、また、山の民や、南の舟の民、東北の民、それぞれが違うようで、ございますね」
「それは、それは、大変、興味深いことだ・・・しかし、とても、その・・・美しかった。素晴らしい謡だった・・・」
安行は、頬を赤らめ、また、拍手を繰り返した。アカは、にこやかに頷いた。
「ありがとうございます」
「はあ・・・、さて・・・、どうしたものか、・・・ああ、喉が渇いた」
「麦湯をどうぞ」
アカが、予め準備しておいた麦湯を、竹筒から、木製の器に注ぐと、まるで、酒を飲み干すように、安行は、それを飲み干した。
「夜なら、酒となりましょうね」
「いや、だから、嗜まないと」
ついぞ、お酌の気分になる。アカは、つくづく、真面目な安行が、可愛らしく感じられた。しかし、安行は、アカのその感じに飲まれてはならないとし、次へ進まなければと、自らを戒めるように、話を進めた。
「アカのご存知は、どの畸神様の件なのだろうか?」
「あたしたち、海の民の舞巫女が、諳んじているは、二代様と、三代様の件です」
「なるほど、それは、長い部分じゃが、丁度、時代的に、今に近いものだと伺っている。あくまでも、推察であるが・・・」
「そうかもしれませんね・・・ここからは、語りが中心の歌物語のお伝えとなりますが、よろしいでしょうか?」
「あい、わかった。昨夜、今日の為に、墨を擦り溜めておいた。ここからは、書きつけつつ、伺うことにしよう、すまないが、ゆっくり、語りをお願いしたい」
~つづく~
みとぎやの小説・連載中 「謡の間にて②~畸神夫妻の恋歌」
舞って紅 第十四話
お読み頂きまして、ありがとうございます。
アカの謡った歌は、「畸神夫妻の恋歌」という歌です。
さ蕨の 温もりの
緑に舞ひ 息作り
雷鳴の轟にも 惹き上がり
渦巻く焔に 氷解の果てに
酔ひ乱れつも し尽く終ひ
みとぎやのお話には、何度か登場する歌です。
時が移り変わり、どんなことがあっても、変わらぬ愛———
というような意味です。
かつて、畸神という神を信仰していた東国は、これまで、大陸から来たある民族に侵略され、それは、このアカの生きた時代から、先々の未来にまで、その手を伸ばし続け、殲滅を狙い続けていきます。大切な記憶は、その都度、各々の時代に、まるで命からがらという感じで、首の皮一枚の状態で、細い糸で紡がれていきます。繋ぎ、覆い隠し、また、それを掘り起こしながら、後世に伝えてゆく・・・。侵略の目を逃れ、その手に踏みにじられぬように。
本来的に畸神がいたことが、この東国という国に、遍く拡がり、そのことが当たり前のようになるまで、この動きは続いていきます。
次回は、アカが、その畸神伝説の謡の一節を、記録役の安行に披露することとなります。お楽しみになさってくださいね。
「舞って紅」ここまでのお話と、テーマソング(まだ歌詞のみですが)は、こちらから読むことができます。よろしかったら、お立ちよりください。
いいなと思ったら応援しよう!

