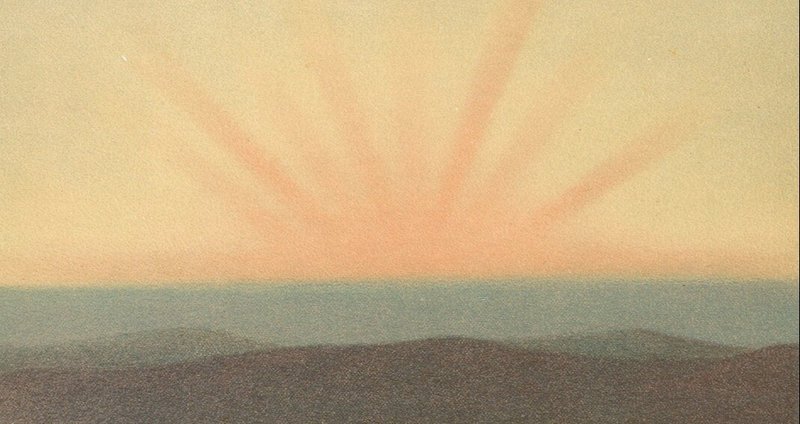
菅原ゼミで読んだ短編小説の書評を順次掲載していきます。書評は全てゼミ生が書いています。授業期間中の毎週末ごろ更新です。
※ネタバレありですので気になる方はお気をつけください。
- 運営しているクリエイター
2021年12月の記事一覧
アーシュラ・K・ル・グィン「オメラスから歩み去る人々」書評(2)(評者:森本和圭子)
アーシュラ・K・ル・グィン「オメラスから歩み去る人々」(『風の十二方位』収録)
評者:森本和圭子
この作品の舞台は「オメラス」という架空の世界である。美しい街並みに、穏やかな気候、明るく、しかし単純ではない人々、またそこに身分の上下はなく、芸術や学問も高みに達しているとされる。かと言って、いわゆる反テクノロジー的な、あるいは禁欲的な世界というわけでもない。オメラスは心やましさのない、読者の
アーシュラ・K・ル・グィン「オメラスから歩み去る人々」書評(1)(評者:平山大晟)
先々週の4回生ゼミではアーシュラ・K・ル・グィン「オメラスから歩み去る人々」を読みました。倫理や人間の幸福のありかたについて活発なディスカッションができました。
アーシュラ・K・ル・グィン「オメラスから歩み去る人々」(『風の十二方位』収録)
評者:平山大晟
暴走したトロッコの線路上に5人の作業員がいる。このまま放っておけば5人全員が死んでしまうが、自分が分岐器を起動し、別の線路にトロッコ












