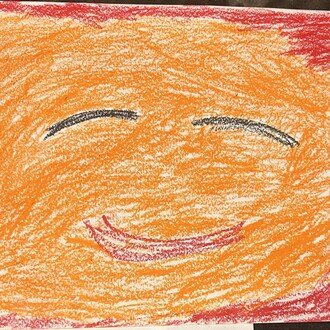「これはテストである」と意識させること。お受験の行動観察をどう捉えるか?
「待ち方が大事!待ち方が汚いと、テストで1点マイナスされちゃうんだよ~」
次男が通う、幼児教室での一コマ。
幼児教室というよりも「お受験塾」である。
授業中に度々「〇〇ができたら2点もらえる」とか、「〇〇したら1点マイナス」とか、点数の話が出てくる。
私はそろそろ「この教室との付き合い方」を考えなければいけない所に来ている。
我が家の立ち位置
2022年秋 長男が小学校受験(単願)をして不合格。
2023年春
長男は公立小学校へ入学。
次男は「小学校入学の練習になれば」という理由で同じ幼児教室へ通い始める(今まで放置しすぎた)。
2023年11月~
次男は幼児教室の「新年長クラス」へ。
毎月、日曜日の「模擬テスト」へ強制参加(月謝に含まれている)。
長時間クラス、季節講習、志望校別授業等への課金誘導が厳しくなる(笑)
お受験塾を中心にした生活が嫌だと思いつつ、私立の柔軟性や自由度の高さに触れると「素敵だな」と感じる。
一方で、お受験教室で習う事は結果的に「主体性を失わせる行為」でもあると感じる。
公立小学校1年生の教室を「動物園」と表現されている人がいたけれど、まさにその通りだと思う。
「動物」にならない為に訓練するのが「小学校受験塾」なのだ。
でも、「動物」を無理やり抑えつける事が正しいの?
私立も公立も、結局「良しとされる子供像」は同じである。
ただ、その訓練を幼児期から開始するのか、1年生になってから開始するのか…の差である。
最近そう感じている。
点数の話が増えた
幼児教室と言うか、小学校受験の入試科目は様々だ。
ペーパー、運動、絵画、制作、ダンス、歌、行動観察、口頭試問など。
毎月の模擬テストでは、入試と同様に沢山の課題に取り組み2週間前後で細かい採点結果が送られてくる。
・自分から挨拶する。
・目を見て話す。
・話している人の方へ体を向ける。
・必要以上にお喋りをしない。
・待機時、姿勢が崩れない。
・最後まで積極的に参加した。
・自分から片付けをした。
・楽しそうに取り組んでいた。
・指示を理解し、覚えていた。
こんな感じで「問題の〇×」ではない部分の評価軸が沢山ある。
特に「必要以上にお喋りをしない」は、ペーパー、運動、行動観察、制作等それぞれの課題に必ずセットで入る項目なので、どの課題でもお喋りをしていたら毎回点が貰えなくなる。
その為、普段の授業中から何かと点数の話をされる事が増えた。
「配られたモノに触ったらマイナス1点だよ」
「ハンカチとティッシュがポケットから出せたら2点貰えるんだよ」
とか。
勿論「入試」という本番があるので、テスト対策が必要だ。
何が採点項目なのか知らなければ対策もできない。
でも、何かしっくりこないモノがある。
子役のオーディション?
特に個人的に耐え難いのが「行動観察」と呼ばれるもの。
〈行動観察とは〉
子供数人でグループ活動をさせるテスト。
パターンの例
・チーム対抗ゲーム(運動、ボールリレー、積み木積み等)
・協力して大きな制作物をつくる等。
行動観察の時、「皆で話し合って決めましょう」とか「皆で協力して〇〇をしましょう」等と言われる。
この時の基準として「ちゃんと話し合いに参加しているか?」がかなり問われる。
ゲームをする時も、勝った時に喜び過ぎる。負けた時に怒り出す等、感情をあらわにする事は減点対象になる。
楽しくなってふざけたり、大きな声を出したり、いわゆる「子供らしい姿」も減点される。
「自由遊びと言われて、本当に遊んじゃう子は×です。自由ではないという事を理解しなければいけません。」とハッキリ言っていた。
入試間近の模擬テストでは、「通塾して場数を踏んでいる子」と「外部生(訓練していない子)」では、行動観察の時に歴然とした差が出るそうだ。
「だから通常授業だけではなく、色々なゼミや講習に参加して、知らないお友達と一緒に行動観察対策をする事が大事なんです!」と熱弁していた。
行動観察の授業の後は、子供達に
「こういう風に話し合って」
「床で作業をする時はお母さん座りをして」
「ふざけてる子がいたら『一緒にやろう』って誘って」
等と「行動観察テスト」の「正解」を徹底的に教え込まれる。
訓練を重ねて、「正しい振舞い」をする様になれば先生は褒めてくれる。
でも、「友達と何かをする時の振舞い方を教え込む」と考えると何だか気持ちが悪くなる。
長男の時も、受験直前期はかなり「正しい振舞い」ができていたけど。
みんな、授業の後は「普通の子供同士」だった。
だから「授業中やテストの中での振舞い」として割り切れば良いんだろうけど。
子供自身に「テストで〇×をつけられるから、こう振舞った方が良い」という意識を付けてしまう事が、本当にその子にとって良い事なのか?
仕上がってくると
「貸して~」「いいよ~」とか。
「〇〇を貸しくれて、有難うございました」
等、お決まりのセリフみたいな言葉を発する様になる。
結局、何を求めているのか
実際の所、入試本番のテストで小学校はどの様な基準で加点・減点がされているのか分からない。
アイドルグループじゃないけど、「エース」ばかり寄せ集めたいわけじゃなくて、色んなタイプの子で構成したいと思っているかもしれない。
行動観察について、どう捉えるか?という問いに対して
老舗の教室「こぐま会」の代表がコラムでこんな風に話していた。
ある学校の願書配布時に配られたパンフレットに「子育ての総決算としての入試を」というメッセージが寄せられ、日常生活の中でさまざまな経験を積むことが大事だと述べられていましたが、まさしくその通りで、特に行動観察のために何か「型」を身につける訓練をすべきではありません。演劇の役者のように振舞うことを学校側は求めていません。その子らしく、臨機応変に問題を解決していく力を普段の生活の中で身につけることが何より大切なことだと思います。
これを読むと週に何日も通塾して訓練するよりも、色々な場所で体験をする事の方が大事だと思うんだけどな。
我が家が通っているのは「こぐま会」ではないので、スタンスが違うのか?(笑)
協調性のない悪ガキにはなってほしくないし、TPOに応じた振舞いも大事だ。
でも、それを「点数化」するってどうなの?
「点数」を意識させるってどうなの?
って話でした。
子育て経験がまだ7年なので、良かったら先輩方コメント下さい。
そして私立・公立問わず学校の先生や、教育関係の方からもコメント頂けたら嬉しいです。
最後までお読み頂き有難うございました。
今日も素敵な一日になりますように☆彡
いいなと思ったら応援しよう!