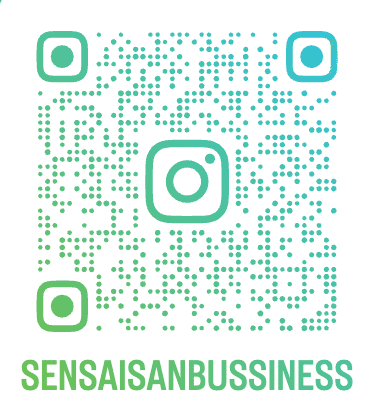Day298 「子どものデジタル脳 完全回復プログラム Reset your children's brain」
著者 ヴィクトリア・L・ダンクリ
米国の精神科医・医学博士、デジタルスクリーン、環境要因、食事療法、投薬が行動に及ぼす影響の研究で受賞多数

■WHAT:デジタル機器が脳に及ぼす影響
デジタルスクリーンは、座りっぱなしで健康を損なう以上有害なもの
(ドラックそのもの:カフェイン、アンフェタミン、コカイン)
デジタルスクリーンの影響で生じる症状のことを、著者は“デジタルスクリーン症候群”という。
■WHAT IF:スティーブ・ジョブス
ハイテク企業のCEOは、子どものデジタル機器の利用を制限している。彼らは、ローテクな教育が集中力や人間関係を構築する能力、創造力を育むことを知っている。
デジタル機器・・
パソコン、テレビ、ゲーム、スマホ、ダブレット、電子書籍
■WHY:デジタルスクリーンの問題点
・刺激が強すぎてストレスになる
・未発達な子どもの脳は耐えきれない
・脳の発達が止まる
・子どもの気分、睡眠、認知に問題を引き起こす。
例えば、小児性肥満症、慢性的なイライラ、集中力の低下、感情を抑制できない、反抗的行動など。
・双極性障害、ADHDと同様の症状を発症(1994年から2003年までの10年間で40倍、2002年から2005年の3年間でADHDの薬の処方が40%増加)
・脳内で覚醒剤と同様の反応を引き起こし、子どもの問題行動の引き金になる
・心身ともに長期的な悪影響の原因になる。
《デジタルスクリーンによる影響》
睡眠の質の低下、日中の機能低下、認知能力の低下、記憶力の低下
注意力や学力の低下、忘れ物の増加、読み書き能力の阻害、読解力と数学の得点にマイナスの影響が持続的に起こる、自分で考える能力の低下
《悪影響を与えるメカニズム》
デジタル機器の強い刺激は、神経系を「戦うか逃げるか」というモードに移行させる。(機能不全、制御不能へ)
精神疾患にそっくりな症状を引き起こす。
高揚力は高まるが、その後、神経系への過剰な刺激により「クラッシュ」が生じる。そして、長く中枢神経に影響を与えることがある。
身体を動かさずに脳だけが興奮させることがよくない。
再調整には身体的エネルギーの放出が必要で、放出のために問題行動を引き起こされる。
未発達な子供は大人より早く影響が出る。
受動より、双方向スクリーンタイムがよくない。
特にゲームは、操作性、即時的という特徴から中毒になりやすい。
関係しているのは、ドーパミン(脳内快感物質)。
「もっと長く遊びたい」
ゲームが始まる合図で、薬物中毒者の脳を全く同じ領域で脳が活性化する。脳が、強い刺激や覚醒に依存するようになる。維持するためにさらに多くの刺激を求める。(覚醒依存症)
刺激レベルが強く、ほどほどにができなくなる。
特に、男の子の方が影響を受けやすい。
ドーパミンは、一気に上昇し、ゲーム後に急降下する血糖値のような特性があるため、精神障害の大きな原因になる。
《特記事項》
脳の発達に最も影響を与える”ネグレクト”
スクリーンタイムが多いと、抱っこされたり、触れられたりする時間が少なく、親からのアイコンタクトも少なくなる。
そのため、絆を深める時間がなくなる。
依存性のある化学物質やスクリーンタイムが乗っ取る報酬経路は、絆を深めるための経路と同じ。子供の頃、絆を深める時間がなくなると、発達に多大な影響を及ぼすので、あまり小さな頃からスクリーンに触れさせない。
■落とし穴
「短時間なら問題ない」「趣味なら問題ない」という考え方
■HOW:デジタルデトックス
デジタルデトックス(デジタル機器と距離を置くこと)により、
80%に顕著な改善(脳全体の統合による)
・・気分や態度が改善
・・よく眠れる
・・集中力の向上
・・成績の向上
・・人間関係の改善
スクリーンを使わず育つことで、脳内化学物質のバランスが整い、過激な刺激が静まり、ストレスホルモンが減り、前頭葉が正常に発達し、心身ともに健やかになる。
デジタルデトックスは厳しく行わなけらばならない。
→一定期間、デジタルを断ち、スクリーンの代わりになるアクティビティ計画を立てる。
例えば、
・屋外で遊ぶ
・家族全員で取り組む
・スクリーンを使ったらその分、子供と遊ぶ
・使わない時間を設ける
・「実験」と言って始める
・デトックス後のことには触れない(次は、いつやるなど)
・最初は3週間
デジタルデトックス期間が終わったら、改善点を書き出す。
■まとめ
現代人、「スクリーンの使用する時間をとっているのに、やるべきことの時間はとっていない」。身体の病気のようにわかりやすい症状が現れないからこそ、定期的な心の体調チェックが必要そうだ。