
ビブリオバトル、やっぱり選書が9割だった。
――ビブリオバトルは本を選ぶ段階から戦いは始まっていて、もはや選書が9割といえるほど、それをないがしろにしてはいけないんですよね。
人生は物語。
どうも横山黎です。
作家として本を書いたり、木の家ゲストハウスのマネージャーをしたり、「Dream Dream Dream」という番組でラジオパーソナリティーとして活動したりしています。
今回は「ビブリオバトル、やっぱり選書が9割だった。」というテーマで話していこうと思います。
🏨母校のビブリオバトルへ
昨日、僕は母校の大学に行ってきました。全国大学ビブリオバトルの予選が開催されるからでした。
ビブリオバトルは、自分のお気に入りの本を5分間で紹介する書評合戦のこと。リスナーは「読みたい!」と思った本に票を入れます。最も多くの票を集めた本がチャンプ本に輝くというわけです。
僕は高校時代から公式戦に参加してきたほど、ビブリオバトルに情熱を捧げてきまして、大学4年生までの7年間で3度、全国大会に進出することができました。人よりは本を紹介する能力に長けているのかなと自負しています。
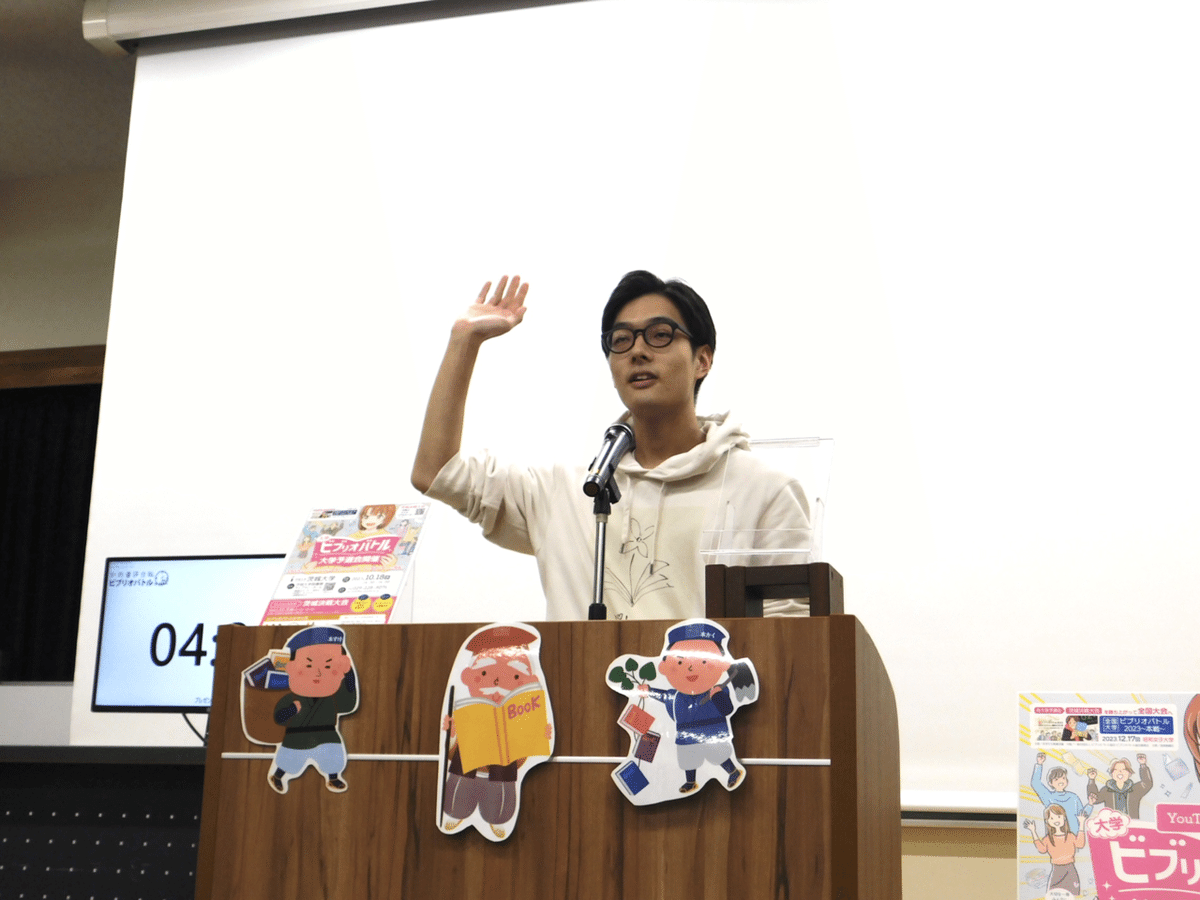
結局全国の頂点に立つことはできなかったけれど、僕なりに本の場づくりに対する答えを見つけることはできたし、僕のまわりの人たちに「ビブリオ」の認知度を高めることができましたし、自分の挑戦を悔いることはしていません。
それを再認識できる機会が、昨日もありました。
僕の挑戦が終わりあれから1年。今年も変わらず全国大学ビブリオバトルが開催されるわけで、観にいかないわけにはいきませんでした。どんな本の戦いが繰り広げられるのか、わくわくしながら参加することにしたんです。
結果、めちゃくちゃ悔しい思いをしました。

🏨実は後輩にレクチャーしていた
実は今回、僕の知り合いの後輩がビブリオバトルに参加するのも、観にいきたかった理由のひとつでした。その後輩には、より魅力的な本の紹介ができるように、僕が最大限レクチャーしていたんです。
彼女は先日、僕の開催した謎解きイベントに声の出演をしてくれた人でしてお世話になったこともあったので、どうにか恩返しをしたいと思い、ビブリオバトルのレクチャーという形でそれを伝えることにしました。
彼女が選んだのは『銀座「四宝堂」文房具店』という本。文房具店の店主さんとそへやってくる訳ありのお客さんたちの関わりを描いた作品です。
ビブリオバトルのレクチャーをするにあたり、本を読んでいないことには相談に乗れませんから、僕もこの本を読むことにしたんです。そしたら、読む前と読んだ後とでイメージががらっと変わったんですよね。
『銀座「四宝堂」文房具店』は、タイトルの通り文房具にまつわるストーリーでありながら、これは手紙を書いて誰かに思いを伝えるストーリーでもあると気付きました。むしろそっちの方が本質に近いんですよね。この本の魅力を伝える上でより焦点を置くのは、「文房具」ではなく「手紙」だと考えました。
……のようなことを、レクチャーをするにあたり伝えにいったんですね。他にも、構成は5段階にするべき、とか、時間配分はどれくらいがいい、とか、導入部分の最後にはリスナーにメリットを提示した方がいい、とか、自分が手にしてきたビブリオバトルにまつわる知見をひとつつずつ伝えにいったんです。
練習をするごとに上達していったし、本番では理想通りのパフォーマンスをしていたので、「レクチャーしてきてよかったな」と思ったし、「きっとこのパフォーマンスなら勝てる」と信じることができたんですが、優勝を飾ることはできませんでした。
彼女の次に紹介したバトラーの紹介する本を目にして、「やられた……」と内心思ってしまいました。案の定、そのバトラーのパフォーマンスは圧巻で、彼が次のステージへと駒を進めました。
🏨やっぱり選書が9割
僕の後輩のパフォーマンスが悪かったわけじゃありません。彼女の発表の順番は3番目だったんですが、前2人を圧倒するくらいには良かったんです。落ち着いていたし、5分ジャストで終わったし、声もスピードも抑揚も強調も良かった。
そもそも彼女の選んだ本が、チャンプ本に輝いた彼の選んだ本よりも劣っていたというしかないんですよね。
誤解を生みそうだから毎回説明しているんですけど、これは本の中身の良し悪しではなくて、ビブリオ向きかどうかの話をしています。紹介しやすいかどうかってことです。僕らビブリオバトラー界隈(?)では「飛び道具」なんて呼び方をしているんですが、誰が紹介しても「え、読みたい!」となるようなマジックブックがあるんです。
例えば、下村敦史さんの『同姓同名』というミステリー小説。登場人物の名前がすべて同じ苗字、同じ名前、まさに同姓同名なんです。だから、犯人の名前だけは最初から判明しているんですよね(笑)
この本はまさにビブリオ向きのマジックブック。ちゃんとわかりやすい結果も出ています。なんと、この『同姓同名』、去年のビブリオバトルの公式戦、中学大会、高校大会、大学大会すべての大会でグランドチャンプ本に輝いているんです。
この実例からお分かりの通り、ビブリオバトルは本を選ぶ段階から戦いは始まっていて、もはや選書が9割といえるほど、それをないがしろにしてはいけないんですよね。
昨日のチャンプ本は、『まず牛を球とします。』という本でした。
人間は牛を食べたいが、動物を殺したくはない。そこで牛を動物でなくすというのが人類のたどりついた解答であり、牛球の技術には五十年ほどの歴史が存在する。
一度聴いたら鼓膜にこびりつくようなタイトル、「牛を球にする」という今までに考えたこともなかったような独特の世界観。紹介されたら心に衝撃を食らうこと間違いなしの1冊いえます。
僕はこの本を読んだことなかったんですが、冒頭1分で心を動かされたし、発表を全部聴いて読みたいと思ってしまったんですよね。
彼の話術や構成の仕方ももちろん最高だったんですが、そもそもどの本を選んで紹介するかによってその後の作業は全部変わってくるので、この本を選んだことが勝利の要因といえるでしょう。
ビブリオバトルに勝つためには、ビブリオ向きの本を選ぶ「慧眼」が必要だというわけです。
▼『まず牛を球とします。』試し読みできます。
今回は後輩から、自分が好きな本を紹介するのでそれをもとにいろいろ教えてください、と頼まれたので、このような形となりましたが、今度レクチャーを担当するときは、そして、勝ちにこだわるなら、やっぱり本を選ぶところから立ち合うべきだなと思い直しました。
僕はやんわりビブリオバトルを卒業したつもりでいたけれど、僕の身体のなかには、ビブリオバトラーの魂がまだ宿っているみたいです(笑)
今後もどんな形だとしても、ビブリオバトルには関わっていくんだと思います。そんな気付きも得られた一日でした。最後まで読んで下さり、ありがとうございました。
20241017 横山黎
