
◆読書日記.《G・K・チェスタトン『ポンド氏の逆説』》
<2023年6月30日>
G・K・チェスタトン『ポンド氏の逆説』(創元推理文庫・中村保男/訳)読了。
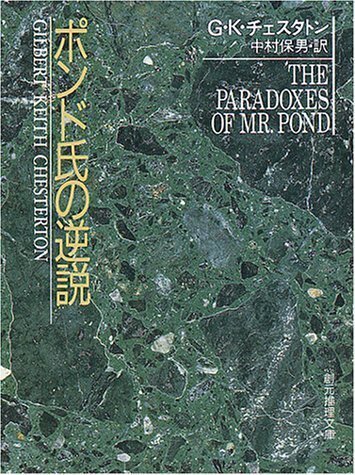
詩人であり、ジャーナリストであり、宗教論争家であり、劇作家であり、文芸批評家、歴史家、伝奇作家、エッセイスト、そして、ぼくのようなミステリ・ファンからすればかの有名な「ブラウン神父シリーズ」で有名な推理作家でもあるギルバート・キース・チェスタトンによる「逆説」をテーマにした連作短編小説集。
「逆説」という、この意表を突くような考え方がぼくは好きである。
そして、その逆説を自由奔放に操って批評から論争、小説にまで応用するチェスタトンの「発想の秘密」というのに、以前から興味を持っている。
このチェスタトンの「謎」については以前ご紹介した山形和美『人と思想172 チェスタトン』の記事では結論までは出なかったので、再びチェスタトンの実作に戻ってその辺りを探ろうと思う訳である。
本作は広義のミステリと言って良い内容の小説集なのだが、「ミステリ」と言って思い浮かべる内容とは若干違っており、素直に「謎‐推理‐解決」といった形式になっていない。
「謎解き物語」である事には違いないのだが、ここで扱われる「謎」というのは、常に冒頭で語られる「ポンド氏が話す事件についての謎めいた総括の言葉」なのである。
そもそも「逆説」というのからして「謎‐推理‐解決」の構造のどこかがおかしいからこそ起こる――という風にも言われている。
ちなみに「逆説」の定義をお馴染みのウィキペディアから引用してみよう。
「パラドックス(paradox)とは、正しそうな前提と、妥当に思える推論から、受け入れがたい結論が得られる事を指す言葉である。逆説、背理、逆理とも言われる。 」

「Aという原因があったためにBという出来事が起こった」という命題が真だとしたら、ポンド氏の話すこの手の逆説は「Aという原因があったためにアンチ・Bという出来事が起こった」といったパターンをとるのである。
本書に出てきた例で言えば「ポンド氏は、「足がありませんでしたから、むろん競歩レースには優勝しました」とか、「酒がありませんでしたのでね、一同たちまち千鳥足ですよ」などと喋っていたらしい(P.68)」といった所である。
この物語の主人公・ポンド氏はイギリスの官吏で、長話をする事で有名な人物という設定なのだが、このポンド氏の何よりも顕著な特徴が、この人物が時々口にする、上に挙げたような奇妙な発言なのである。
そして、それを聞いていたポンド氏の知人が、彼の真意を尋ねると、その奇妙な逆説が見事に成立するような、実際に起こったエピソードを話し始める――本書の各短編は、概ねそんなパターンで成り立っている。
つまりは、ポンド氏が口にする謎めいた逆説の言葉が「謎」であり、その逆説が何を意味しているものなのかというエピソードが語られる事で「解決」がなされる。本作はそんな「謎解き物語」なのである。
本書を読んで、ぼくなどはこれは時事批評やコラムを書いていたチェスタトンらしい小説でもあるのではないかと思った。
この物語のスタイルは「ポンド氏による事件の総括」としての「逆説」が冒頭に出ては来るものの、逆に考えればポンド氏は様々な事件や出来事について、ウィットに富んだ「逆説」によって批評をしている――つまりはチェスタトンが新聞や雑誌に書きまくっていた記事の結論と中身を前後逆に入れ替えただけのストーリーだと言えるのではないか。
本作はチェスタトンのいつものお得意のスタイルで書かれたわけだ。
彼は好きにでっちあげた架空の出来事について、いつものようにウィットに富んだ逆説でコメントすれば良かったのである。
そして、いつもコラムを書いている時は結論として末尾に置く「逆説のコメント」を冒頭に持って行った事で、それがミステリ的な「冒頭の謎」となった。
そう考えると、この物語はどうもぼくには「推理作家・チェスタトン」というよりも「コラムニスト・チェスタトン」としての側面が強く表れた内容になっているのではないかとも思うのだ。
それにしても、何故チェスタトンはしばしば作品上で「逆説」を駆使していたのだろう?
本書に「逆説の定義」として書かれた一文がある。
『人目を引くために逆立ち(※本書の表記では"頭立ち")している真理』というのがパラドックスの定義とされている。
――「人目を引くため」の逆立ち、それが「逆説」であった。
英国ジャーナリズムの一つの方法として「人目を引く」ための「逆説と警句」というやり方をミステリにそのまま持ってきたのが、チェスタトンという、ジャーナリストにして小説家であった人物の方法論だったのではないかとも思う。
◆◆◆
さて、という事で以下からはネタバレも含めて、各短編について簡単にコメントして行こうと思う。ということで――
◆◆◆◆◆以下ネタバレあり◆◆◆◆◆◆◆
《注:以下、チェスタトン『ポンド氏の逆説』の各短編のアイデアに触れるレビューとなっています。本書を未読の方、またネタバレをされたくないと思っている方は、以下文章を読む際はその点をご考慮の上ご覧頂ければと思います》
◆◆◆◆◆以下ネタバレあり◆◆◆◆◆◆◆
●『三人の騎士』
聞くところによればボルヘスが褒めたという一編であり、確かに本集の中では出来も1~2を争う。
本編では「上官に絶対服従したから命令が執行されなかった」という逆説が披露される事となる。
ポーランド侵攻したプロシア軍がポズナンの地を占拠し、その街とは離れた位置に駐屯している将軍直属の白騎兵連隊での話。
「詩人としては国家的存在であり歌手としては国際的であった」という著名な詩人ポール・ペトロウスキーは、その名声を恐れたプロシアに捕らえられ死刑を宣告されていた。
連隊の本拠地からは離れた位置の街で捕らえられ死刑を待つ身であったペトロウスキーの死刑を指示する伝令を連隊の指揮官であったフォン・グロック将軍が送り出した時の話である。
ポンド氏のコメントはこうなる。
「部下があんまり命令に忠実だったものだから、何一つとしてグロック将軍の思いどおりには事が運ばなかったのです(P.11)」
この逆説自体は大した着想だとも思えないのだが、本作の面白さはそのメインとなるエピソードの面白さにあるだろう。
プロシア軍の本拠地とボズナンの街の間に広がる広大な沼地と、その中を一本だけ走る土手が、本格ミステリによく出てくるような限定状況を作り出していて、ラストのどんでん返しの仕掛けがほとんどパズルじみているのである。
寓話的な仕掛けとしても良く出来ているし、最終的に現れる土手から滑り落ちて死んだ騎士を見下ろす将軍という風景も残酷にして美しい。
しかし、チェスタトンが他の本格推理作家と雰囲気が違っている点の一つは、物語の中に本作のように政治的なテーマや軍事的なテーマを入れてくる事だろう。
本作は君主と将軍の確執という状況の裏側に「命令に背く/命令に復する」という事は何を意味しているのか、というテーマが見え隠れしている所が面白い。
将軍は「殿下のためを思って」殿下の意向に真っ向から反対し、良かれて思って君主の命令に背いてしまう。
そして、将軍の意を受けて伝令に飛んだ騎士は、将軍の命を真っ向から守ろうと意を汲みすぎたがゆえに、その命令を守れなかった。
このどちらも、上司の事を思うがために失敗してしまうケースの別ヴァージョンでしかないという事は注目に値しよう。
●『ガーガン大尉の犯罪』
元俳優のフレデリック・フィヴァーシャムが自宅で殺された。 彼はフェンシングの剣で胸を一突きに大地に釘づけにされていたのである。
この殺害事件について弁護士のルークがポンド氏に面会に来た。ポンド氏の友人であるガーガン大尉が、この件については嫌疑があるというのである。
ガーガン大尉はフィヴァーシャム夫人に付きまとっていた事に加え、事件当日の自分の行動について、三人の人物にまったく相反する三通りの話をしていたという。だから、あやしいのだと。
これについてポンド氏はいつもの逆説的な発言でルーク弁護士に反駁する。
「彼は話をあべこべにして、それで同じことを言ったのだ」(P.51)
本編も、逆説自体は大した着想ではないものの、メインとなるエピソード自体は面白い。
しかし、これは本作で言っている通りブロークン・イングリッシュの特徴を事前に理解していないと(事前にフリの話は出てくるのだが)、このオチも驚きが弱まってしまう。
ちなみに、ぼくもそういったものには全く詳しくないのだが、英語の文法と日本語の文法の違いといったものが理解できていると本作の微妙な面白みというものにもピンとくるのではないか。
本編についても前編の「三人の騎士」についても、「逆説」のほうにあまり驚きを感じられないのは、やはりどちらも「謎」としての不可能性を感じないからでもあるだろう。
●『博士の意見が一致すると……』
本編では「わたしは、完全なる意見の一致に達した二人の男を知っていますが、むろん、その一人が相手の男を殺すという結果になりましたよ」(P.71)という逆説が披露される事となる。
ポンド氏が披露した話は、彼がスコットランドにいた際に出席したパーティで出会った、キャンベル博士とその生徒であるアンガスという医学生についてであった。
彼らはある日、議論のすえ遂に意見の一致を見て、その結果、片方が殺される事となるのである。その顛末を書いた一編。
こちらも「意見が一致したから殺された」という状況は確かにパラドキシカルではあるものの、この表現から考えられるシチュエーションは幾つも考えられる。
やはりそういう不可能性の低さがこの逆説の面白さを減じてしまっているのが惜しい。
しかし、このエピソードは寓話としてはなかなかのもので、例えばこれを教訓として国家に当てはめて考える最後のくだりなどは面白い。
「われわれはどうも、ポーランドとかプロシャとかその他の国民のあいだに意見の一致がみられたなどと言って、簡単に安心しすぎるようです。そしてどの点で一致したかは知ろうともしない。しかし、意見の一致というものは、真理との一致ではないかぎり、相当に物騒なものです」(P.92)
●『道化師ポンド』
「赤鉛筆だったとは言いませんよ。だってあんなにまっ黒に書けたんですからね。ウォットン君はあれは青鉛筆みたいだったという意見だが、そうでなくてあれは割合に赤い鉛筆だった。赤鉛筆に似ていた、わたしはこう申したんです。だからこそあんなに黒ぐろと書けたのです」(P.93)――という冒頭のポンド氏の逆説から始まる一編。
この良く分からない話の謎解きとしての諜報戦のような話が展開するのである。
「真赤な鉛筆」というのは謎めいた言葉だが、物語のラストで明かされる、書類の発送先を変更するトリックは、発想としては少々単純で物足りない。
それよりも途中で出てきた「大切な書類を発送するには特別な予防措置を講じないほうが良い」という機転のほうが自分としては発想の逆転としては面白いと思える。
日本では文学は「感情」に注目したドラマが良いものとされているかもしれないが、チェスタトンは人間の「思考」や「判断」や「認識能力」や「理性」といったものに注目する「人間の思考の移り変わりに注目するドラマ」なのではないかと感じる。
●『名指せない名前』
本編は「ある国の政府が好ましい他国者の追放を考慮していたのですが――」(P.125)という逆説から開幕する。
これもロジックから言ってしまえば矛盾だが、表現として見てみればそのような状況もありえなくない。
「好ましい」という形容詞が何にかかってくるかによって条件は違ってくるだろうし「政府」といっても必ずしも一枚岩ではなかろう。様々な意図を持った集団が議会に集まっている事を考えれば、このような逆説も必ずしも不可能という感じはしない。
近代の戦争や革命の内に王政がなくなり共和政が布かれるようになったヨーロッパの某国にポンド氏が滞在していた時の事。
ポンド氏はこの地で三人の知り合いを作る事になる。
典型的なブルジョワの書籍商・フス氏、現政権に信を置く青年官吏・マルクス、そして――この人物がポンド氏の言うくだんの「好ましい他国者」なのだが――カフェテラスでいつも一人コーヒーを飲んでいる「ムッシュー・ルイ」と称する人物である。
特別に変わった容貌でも服装でもない紳士に見えるのに、ムッシュー・ルイは人目を引くこと磁石のようであった。何をするでもなく、彼は絶えず小さな群衆にとりまかれていた。
ムッシュー・ルイとは何者なのか? 何故、何もしていないのに彼は人目を引くのだろうか? そして、何故政府はそんな彼を「好ましい」と思いながらも追放したがっているのか?
本作のメインの謎は、そんな「ムッシュー・ルイ」の正体についての謎なのである。
本作は非常に政治的な色合いの濃い物語だ。
登場人物の書籍商・フスと青年官吏・マルクスは、政治的な考え方から言ってもその境遇からいっても、たいへんに対比的な人物だし、そもそも「ムッシュー・ルイ」という存在そのものが、この物語ではたいへん政治的な「テーマ」になっているというのが面白い。
この紳士の正体が何者であったのか判明した瞬間に、この物語が何を言いたい物語だったのかが分かるという仕掛けが秀逸である。
チェスタトンという作家が、他の本格ミステリを書いている作家と雰囲気が違っている点というのは、ミステリに政治的なテーマを真っ向から入れる所でもあると思う。
ミステリ的なテーマ性と言えば、警察捜査とロジックであったり、男女関係であったり、犯罪であったり……と言ったイメージが強く、チェスタトンのように政治的なテーマだとか宗教思想、国際情勢といったテーマを扱う作家は珍しいと思える。
勿論、この手のテーマというのは、チェスタトンが普段書いている雑誌や新聞の記事にとりあげられているテーマと同じものを扱っているだけ、という事なのだろう。
こういうテーマ面から見てみても、本作は「コラムニスト・チェスタトン」としての側面が強く表れた内容になっているのではないかと思わせられるのだ。
●『愛の指輪』
本短編集にしばしば顔を見せる、ポンド氏の友人であるガーガン大尉が婚約したと仲間に発表する。すると、その事情を知っているポンド氏が「幸福になったから、さて恐ろしい話でもして聞かせようというわけですな」という、例によって謎めいたコメントを漏らす。友人の一人であるウォットンが「それは何のことです?」という事でガーガン大尉が経緯を説明する……という話。
この一編は上に挙げた逆説よりも、次のくだりのほうが本編で語られるエピソードの教訓を指摘していてよほど面白い内容となっている。
「わたしはその区別(事実と小説との区別)というのはこんなものだと思うのです。実生活は部分的には芸術的だが、全体としてはそうではない。芸術作品の破片のよせ集めのようなのが実生活です。だから、万事がきちんとまとまっていて、しっくりしないものが何もないというような時、われわれはそこがこしらえものじゃないかと疑るのです。(略)社交界の何かの出来事がまるで小説のようだとよく申しますが、実際の出来事は、小説のようなけりがつくものじゃありません。――少なくとも小説と同じには終わらないものです」(P.152)
以前にも言ったかもしれないが、人生というものは整然と起承転結の整った「ストーリー」になっているわけではなく、その多くは後々の何にも繋がる事のない散文的なエピソードの寄せ集めに過ぎない。
だが、人間はそれを物語的な因果関係をつけて理解してしまう場合が往々にしてあるものだ。だから「実生活は部分的には芸術的だが、全体としてはそうではない。芸術作品の破片のよせ集めのようなのが実生活です」という意見はよくわかる。
本作ではガーガンがクローム卿という人物がホスト役となって開催した晩餐会に呼ばれて出席した時の事が語られる。
その中でちょっとした事件がおこるのだが、その事件発生直前の「クローム卿の指輪を参加者らが順繰りに回して見ていく」という行為に二重の意味が含まれており、それがラストのどんでん返しに繋がっているのである。
そこには「実際の出来事を、読んだ覚えのある小説の筋道で辿ろうとすると、その筋道が小説のように終始一貫して通っているものと、どうしても思いこんでしまいますからね」(P.162)という罠が仕掛けてあった、というわけである。
提示される教訓の面白さと、小説的な仕掛けと、作品テーマとが有機的に繋がっている、良く出来た一編であった。
●『恐るべきロメオ』
またポンド氏の友人ガーガン大尉が殺人事件の容疑者になる話である。
牧師のホワイトウェイ師の屋敷である晩、月影に照らされてある人物を追いかける人の影法師を見かける。
追いかける方の人物はガーガン大尉だった。追われているほうの人影は、見かけた影法師のどうも姿かたちから、近くに住む画家のアルバート・エアーズではなかったかと牧師は言う。
エアーズと思われる人影が牧師の屋敷のツタを伝って二階のバルコニーに上った時、ガーガンの拳銃が火を噴いて、くだんの人影が射殺されたのだった……というお話。
この事件についてポンド氏は「影法師は見誤りやすいものです。見誤りやすい一番の理由は、影法師というのが実物の姿を寸分の誤りもなく写すことがあるということです」――と、例によって逆説的なコメントを発するのである。
しかし、この逆説の発想も少々凡庸。チェスタトンの文体の描写がもともと映像的ではないため、この極めて「映像的なトリック」を説明されても、ピンとくる読者はあまりいないのではないだろうか。
●『目だたないのっぽ』
欧州大戦中、英国のとある港町に着任し、この町で行われる各国の諜報活動を監視する仕事をしていた時の事件。
事務所の二階に一人でいたはずの職員が、何者かに巨大な刃物で指されて絶命していた。
事務所の一階にはポンド氏を初め複数の職員がおり、二階には探しても他に人は潜んでいなかった。現場は一見、密室のような状態にあったのである。
この事務所の二階にあった機密書類が盗まれていた事を知り、これはスパイの仕業だと健闘をつけるものの、犯人はどこからどうやって逃げたのかが謎であった――というお話。
本短編集の中では最も本格ミステリっぽい内容。
しかし、このエピソードはミステリ・マニアからすれば少々有名過ぎた。
本作に出てくる逆説「犯人はあまりにのっぽ過ぎたんで、われわれには見えなかったのだ」というものも実に有名なトリックだ。
それにしても、この着想は素晴らしい。
何が素晴らしいかと言うと、明かされる真相によって提示される「風景」があまりに幻想的だからだ。本短編集中でも白眉である。
しかし惜しむらくはこのトリック、やはり映像化したほうが分かり易く、読者も想像がつきやすく、このトリックの衝撃も強まるだろう。
この港町がどのような街並みになっているのか。その頃の建築の「玄関口の足場の支柱」とはどのようなスタイルになっていたのか。そして、その町にきていたサーカス一座のスタイルはどのようなものだったのか。――これらが映像として理解できてこそ、ラストの衝撃に繋がるのではないかとも思う。
