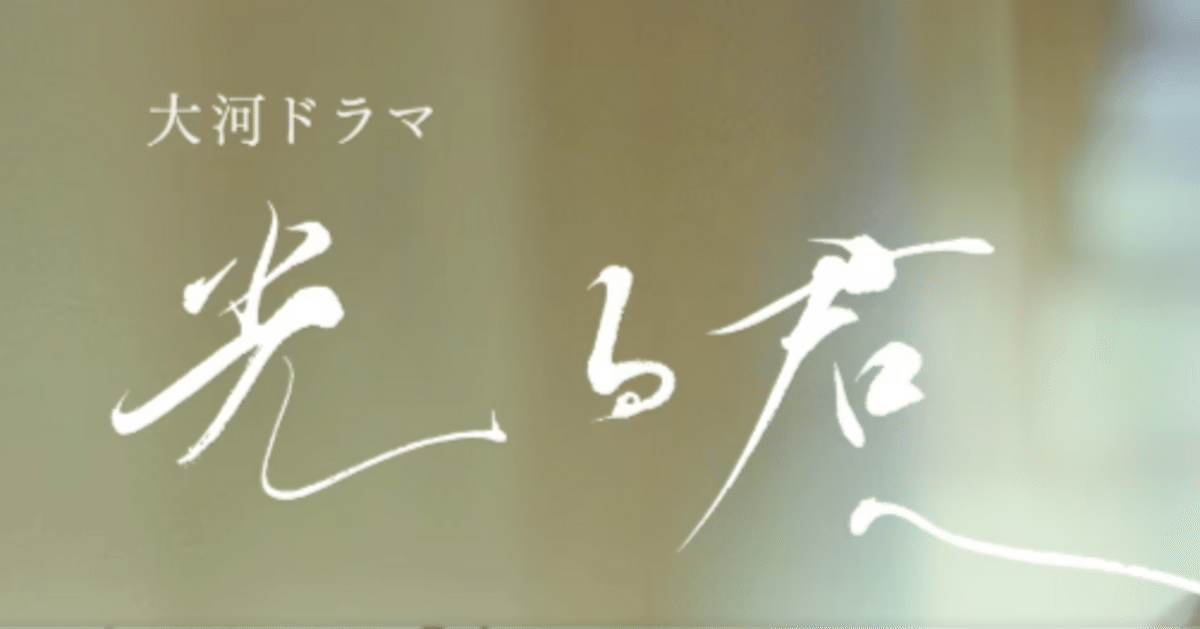
大河ドラマ「光る君へ」を100倍楽しむために【第2話/3話】~蔵人頭と藤原実資
先日、遅ればせながら今年の大河ドラマ「光る君へ」の第1話を見た俺は、その思いのたけが収まらぬまま前回の記事を書き殴った。そうして思いつくままに書き連ねたことで高ぶった気持ちも静まり、俺は改めて録画していた光る君への第2話と第3話を見た。
「第1話こそ楽しめたものの、この先が退屈だったらどうしよう・・・」という俺の愚かな心配も、全くの杞憂に終わった。2話も3話も変わらずに面白かった。あまり馴染みがない平安時代の世界を、映像として見られることが何よりも楽しい。
今回もそんなドラマで描かれる平安時代の世界を、あなた方と共に見ていきたい次第だ。
系図で振り返る藤原氏一族
ひとまず、簡単に作った藤原氏の系図を見て頂きたい。ドラマのサイトを見てみると、登場人物の紹介画像が色々と載っていた。折角なのでこれを見ながら、前回の記事にも書いた藤原氏の一族関係を振り返ってみたい。

まず、系図の一番上に来るのが太政大臣や摂政・関白といった要職を歴任した藤原忠平。そしてその忠平の息子が、藤原実頼と藤原師輔の二人だ。このドラマに登場する上流貴族の藤原氏の大半が、実頼か師輔の子孫という事になる。
忠平の長男だった藤原実頼の一族を小野宮家と呼ぶ。弟の師輔一族に遅れをとるものの、関白となった藤原頼忠がいるように、まだまだ力は衰えてはいない。若い世代にも藤原実資や藤原公任といった有望株がおり、将来も期待が持てる。

兄・実頼の小野宮家に対し、弟・師輔の一族を九条家と呼ぶ。横にズラッと広がる系図の様子からも分かるように、藤原氏の中で主に繁栄を享受したのは、この師輔の子供たちだ。主人公の一人、藤原道長も勿論この九条家の一族に連なる。
師輔の長男だった藤原伊尹は、父の跡を継いで政権を握り、娘の懐子がのちの花山天皇(ドラマ2話時点では皇太子を意味する春宮の地位にある)を産むなど、その権力は確固たるものになるはずだった。だが伊尹は、花山天皇が即位する前に死去し、その後継ぎとなるべき息子たちも相次いで病で亡くなるなど不幸が重なった。この間に権力は兼通・兼家ら伊尹の弟たちのもとに流れていったが、一家を率いる藤原義懐は花山天皇の即位に捲土重来の望みをかける。

師輔の二男・藤原兼通は、弟・兼家と熾烈な出世争いを繰り広げるなど、なかなか強烈な個性の人物だったが、このドラマでは残念ながらすでに故人なので登場しない。ドラマの人物紹介にも息子・藤原顕光の一人しか載っておらず、何とも寂しい状況だ。

兼通の死後、権力の頂点に上りつめたのが、主人公道長も属する藤原兼家の一族だ。一家の繁栄を確かなものにしたい兼家は、娘の詮子が産んだ皇子が玉座に着けるよう画策する。こうして即位した一条天皇は、道長が政権を握る上で重要な役割を果たしていくことになる。

兼家の弟で出世のライバルでもあった藤原為光は、娘婿の藤原義懐と共に花山天皇を支え、娘の忯子を花山天皇の后とするなど権勢を高めた。しかしこの忯子と花山天皇の関係は、のちに大きな悲劇を生むことになる。
そしてもう一人、師輔の子たちの中でも末弟にあたる藤原公季は、長年にわたって大臣の位にあった実力者だ。ただ何となく影が薄い。

藤原氏の一族については前回でも書いたのでここらへんにしておいて、ドラマ本編の話に移る。
平安貴族と和歌
ドラマ2話冒頭では、1話では子供だった主人公まひろが成人の儀式を迎えるところから始まる。母が殺されたことをきっかけとなり、父との関係は冷え切っており、まひろは家を抜け出して和歌の代筆仕事に精を出している。
前回も言った通り、まひろこと紫式部の生涯についての記録などほとんど残っていない。そのため実際の紫式部が若い頃に和歌の代筆仕事をしていたという事実はないが、一方で和歌が上手い人が他人の和歌の代筆をする、という事は現実にあったことだ。
清少納言の「枕草子」には宮廷での様々な出来事が記録されているが、その中には貴族たちが和歌のやり取りをしている場面がいくつもある。貴族たちの知的な遊びといった感じで、その時々の状況にどう上手い事言うのか、相手の歌にどうやって上手い事返すのか、洒落と教養が試されるのが貴族たちの和歌だった。

どんな時代でも機知に富んだ面白い話をする男はモテる。宮廷の女官たちとの会話の中でサラッと和歌を詠んだりしたら、あらあの人は随分風流を理解してるのねと、人気になるのも当然だ。逆に下手な歌を詠んだり興ざめな事をしたりすれば、あいつはダメな奴だと嘲られかねない。
そんな訳で、宮中の社交界に生きる者たちにとって、和歌というのは単なる遊びで終わらない社交の道具だった。後宮の女性の頂点に立つべきお后様ともなれば、和歌が上手に詠めなければ話にもならない。自分の娘を後宮に入れたい貴族たちからすれば、娘が周囲から軽んじられないように、そういった教養を身につけさせる必要があった。そのため、清少納言やのちの紫式部といった教養ある女性が、将来のお后様となる女性に仕え、取り巻きとして主を支えた。
清少納言は藤原道隆の娘・定子に仕えたが、実際に定子の和歌の代作をやったりしている。これは別にズルをしているという訳でなく、むしろ高貴な人間に和歌の代作を頼まれるのは歌人にとっても名誉なことだったようだ。庶民の間でも和歌のやり取りがあったのかどうかは知らないが、ドラマのような和歌の代作業があったとしても不思議ではない気がする。
ちなみに貴族なら誰でも歌が詠めたのかというと、当然そうではなく、苦手な人もいたようだ。有能な事務官で教養も深かった藤原行成は、和歌の初歩的な事を聞かれて「分からない」と答え、周囲に笑われた。また、当代きっての女流歌人である清少納言だが、その夫である橘則光は、清少納言に和歌を詠みかけられるとその場から逃げてしまう、風流のない人間として枕草子に書かれている。清少納言の夫ならいかにも教養ある風流な人物が似合いそうではあるが、平安時代の恋愛も一筋縄ではいかないようだ。
平安貴族のお仕事
さて、ドラマのストーリーでは、まひろが道長と再会したり外出禁止を喰らったりと色々展開が進むが、その一方で朝廷内では大臣たちの策略が渦巻く。右大臣・藤原兼家は自分の娘・詮子が産んだ懐仁親王を皇位につけるべく、円融天皇に様々なプレッシャーをかけていく。

その辺の皇位継承争いは次回の記事で述べるとして、今回注目したいのは、上の画像で緑の着物を着ている、妙に存在感のある人物だ。男の名は藤原実資。権力の道を上りつめる藤原道長の因縁となる相手だ。

藤原実資は先にも述べた通り、藤原氏の中でも小野宮家の一族に連なる存在だ。小野宮家の祖、藤原実頼の孫にあたるが、祖父の養子となる形で小野宮家の正統な跡継ぎとなった。家名の由来ともなっている小野宮邸の屋敷と莫大な財産も受け継いでおり、当時の貴族たちの中でも一等上の存在だった。
実資は道長よりも9歳ほど年長だ。それもあってか、まだ新社会人といった様子の道長たちと違い、道長の父親が出席するような重要な会議の場面にも姿を現している。だが、さすがにこの時の実資は、右大臣である藤原兼家と肩を並べるような地位にはいない。ではなぜそんな大事な場面に実資の姿があるのかというと、彼はこの時蔵人頭という役職についていたからだ。
前回の記事でも述べたことだが、ここで今一度この平安時代の政治体制について触れていきたい。この時代の国家の中心は、天皇をトップとした朝廷と呼ばれる組織だった。その朝廷の上層部、政策を定める意思決定機関となったのが、太政官だ。太政官には名誉職である太政大臣、全貴族の憧れであった左大臣・右大臣・内大臣の三大臣、大臣となる可能性を秘めたエリート集団である大納言・中納言、太政官の登竜門となる参議・・・と続いている。

これを図に表すと上の画像のようになる。図の中にある弁官というのは、太政官の下にあって色々な事務を行い、太政官の命に従い実務を行う各省庁を統轄する役割を担う。政策決定機関の事務を行うのだから、位は太政官の人に劣ると言えど、有能でないとなれない地位なのが弁官だ。
ちなみに、太政官の役職は上記の通りに太政大臣から参議まで分かれているが、その仕事内容はどう違うのだろう?あなた方の中にはそう疑問に思う人もいるかもしれない。実は俺もそれが長年の疑問だった。現代人の感覚から言えば、主任・課長・部長・・・と、それぞれの役職によってその職掌は違うものだ。
この俺の疑問の答えは、極めて簡単だった。太政官に職掌の違いはない。仕事内容の違いはないのだ。太政大臣だろうと参議だろうとやることは同じ。国策会議に出席し、これを議論する。これが全てだ。ただその序列が違うに過ぎない。思うに現代にて内閣総理大臣といえど、国会ではあくまで一議員でしかないのと似ているのかもしれない。
出世街道の登竜門、蔵人頭
さて、朝廷の高官たる太政官は、全ての貴族たちの憧れだった。その太政官の一員になるには、まず参議となることが先決だ。そして参議となるための最有力候補は、蔵人頭という役職だった。
現代の政治家や官僚、一般企業においても、いわゆる出世ルートというものが存在するが、それは平安時代でも変わらない。太政官の仲間入りするためには、まず太政官の最下位である参議を目指すことになる。参議となるためのルートはいくつかあるが、その中でも最も確実で有力だったのが蔵人頭の役職だった。蔵人頭を務めた者はその後ほぼ確実に参議になれる決まりがあったからだ。
そんな貴族の出世の登竜門となる蔵人頭であるが、そもそもどういう仕事の役職なのだろうか。それを説明するには、まず蔵人所について知らなければならない。
蔵人所というのは、蔵人たちが務める役所の名前だ。蔵人という役職は、今でいう秘書のような仕事だ。天皇の身のまわりのお世話から、文書の管理や命令の伝達など、宮中の事務関連を一手に引き受ける、非常に重要な役職だった。そんな蔵人所の実質的な責任者なのが蔵人頭だった。
蔵人は上記の通り重要な役割をこなす職であるが、あくまで雑務をこなす使用人だったので、朝廷の位の上では大したことない存在だった。朝廷の序列を表す位階の事を官位といい、正一位・従一位・正二位・従二位・正三位・従三位・正四位上・正四位下・従四位上・従四位下・・・といった風に30階に分かれていた。

これを図にすると上のようになる。これを見ると、基本的に太政官の官職である大臣や大納言・中納言の役職につけるのは正一位から従三位までの位階であることがわかる。このため、この従三位までの位にある貴族は、公卿とか上達部という風に尊称され、貴族の中でも特別扱いだった。
ちなみに、まひろの父である為時の位階は、たぶん六位ぐらいだと思うが、この時点ですでに若い道長たちに抜かされている。さらにこれからどんどん昇進していくであろう道長たちと違って、為時は恐らくこれ以上昇進することは無く、そのまま生涯を終える可能性が大だ。同じ藤原氏であっても、生まれによってこのような残酷な格差が存在していたことがよくわかる。
同じ藤原でも為時と道長らの格差は上の通りだが、朝廷における身分格差というものは実に様々な形で表れている。その代表的なものが昇殿だろう。朝廷に仕える貴族というのは多数存在するが、天皇の住まいである御所に立ち入ることができるのは、三位以上の公卿たちに限られていた。三位未満の者は、天皇の許可を与えられなけらば御所に入れなかったのだ。そして三位以上の公卿たちや、三位未満で昇殿の許可を得た者の事を総称し、殿上人と呼んだ。
政界のスター、殿上人
天皇のお側で仕える殿上人たちは、朝廷の花形だった。国の高官たちや天皇のお気に入りの臣下たちなのだから当然だ。そんな殿上人たちの仲間入りを目指す貴族たちが求めたのが、蔵人の地位だ。
蔵人の位階はせいぜい六位か五位ぐらいでしかない。本来なら昇殿など許されぬ地位だが、天皇の身のまわりの世話をする人が御所に入れないとなったら本末転倒だ。そういう訳で、蔵人たちは公卿でなくても昇殿が許されている特別な地位だった。
蔵人となれば天皇のお側に近侍することも多いから、自然と顔も覚えられる。低い身分ながら公卿たちの社交の場に出入りすることもできる。権力者に取り入ることで、次の職を得る時に贔屓してもらうことだってできる。下級貴族であっても、蔵人の職を経て地方官の長官となり、たっぷりと私腹を肥やして贅沢な暮らしを送る、なんてことも可能だった。
蔵人の職が下級貴族にとっていかに重要な役だったかは以上の通りだが、一方で上級貴族たちにとっても蔵人の役職が重要なことに変わりはない。ドラマでは道長の兄・道兼が蔵人を務めているが、かつては長兄の道隆も蔵人だったし、道長自身もこのさき蔵人の役を務めることになる。
今をときめく右大臣一家の子息たちがなぜ揃って蔵人を務めるのか。蔵人たちは先に述べた通り、三位未満でも御所に昇殿できる殿上人であり、天皇の秘書として仕え宮中の重要文書を扱う重要な役どころだ。つまり蔵人となれば、若くして朝廷の重要な会議や儀式を身近に経験することができる。
現代においても、政治家を志す人が、有力議員の秘書となって政治の経験を積んで政界に顔を売り、世話になった議員の後押しを受けて華々しく政治家デビュー、なんてことはよくある話だろう。そしてそれは遥か過去である平安時代においても変わりがない。上級貴族の子弟たちは、若くして蔵人となることで政治の経験を積み、将来朝廷の高官となったときに備えるのだ。逆に若い頃に朝廷の作法を学んでいないと、いざ高官になったときに何もできず周囲から無能者と嘲笑されることとなる。
例えば、道長の異母兄である藤原道綱は、他の兄弟たちと違い妾腹だったためか若い頃は大した役職に就くことなく過ごしていた。のちに父・兼家が朝廷のトップに立つと異例の昇進を遂げたが、政界での経験が少ない道綱は満足に政務を行うことができず、実資から「何もできない無能なやつ」と痛烈に罵倒されたりしている。

蔵人の役職がいかに重要な地位だったかという事が、あなた方もよくわかってくれたと思う。そして話はようやく最初に戻るが、藤原実資が務めていた蔵人頭という役職はこの蔵人たちを束ねる責任者だ。天皇の秘書として仕え、朝廷の重要文書を扱い、公卿たちの元に様々な命令を伝える。国家の中枢の庶務を扱う蔵人頭は、有能な人物でなければ務まらない役職だった。そして実資はあまりに有能だったため、普通は蔵人頭を一・二年勤めれば参議に昇進できるところを、実資はその有能さゆえに蔵人頭を辞めさせてもらえず、参議に昇進できないまま結局八年も蔵人頭を勤めることになった。
賢人右府・藤原実資
人材不足の企業の中間管理職みたいな話だが、ともかく実資がいかに有能で天皇から重用されていたかが分かるだろう。実資は仕事ができるだけでなく、小野宮家嫡流の貴族として伝統作法に通じており博覧強記、故実に詳しく、その上かなりの資産家と、字面だけで見るともう完璧すぎる性能だった。実資は最終的に右大臣まで出世するが、右大臣の事を右府と通称したりするので、後世には実資を讃えて賢人右府と称した。
「賢人」とか「賢者」とか言われると、あなた方はどんなイメージを持つだろうか。白ひげを伸ばした厳かなおじいさん、或いは人里離れた秘境に隠れ住む神秘的な仙人か、もしくは勇者パーティーの魔法使い的ポジションの人物を想像するかもしれない。だが現実の賢人はそんなファンタジーで主人公たちに助言をしてくれるようなお助けキャラではない。この賢人右府は礼儀作法がなってない奴にはめちゃくちゃ嫌味を言うし、仕事ができない奴にも容赦ないし、そんな奴に出世を先越されるとめちゃくちゃ文句も言う。

そんな「賢人」と一言でまとめるにはあまりに強烈な個性の持ち主、藤原実資について述べていきたい。
筆まめ貴族・実資
実資を語る上でまず欠かせないのが、彼が残した膨大な日記である「小右記」だろう。当時の貴族たちの多くは日記をつける習慣があり、かの道長自身も「御堂関白記」と呼ばれる日記を残している。しかし勉強嫌いな道長は日記を書くのも不熱心だったのに対し、筆まめな実資は何と50余年分もの日記を現代にまで残した。
当然ながらこの実資の日記は、現代人が平安貴族の生活や政治を知る上でこの上なく貴重な一級史料となるが、この日記の価値はそれだけではない。この時代の重要な史料と言えば、小右記の他には先に上げた御堂関白記と、藤原行成が残した日記の「権記」の三つがまず挙げられる。しかし、権記の著者である藤原行成は道長に近しい貴族だったので、自分や道長にとって都合の悪い出来事は記録に残さない。道長自身が書いた御堂関白記ともなればそんな事はもってのほか、いい出来事しか書き残さない。目を転じてこの時代を描いた歴史物語を見てみると、「栄花物語」や「大鏡」は道長礼賛一色。道長がいかに素晴らしい人物であるか、あの手この手で褒めて褒めて褒めまくっている。
さて一方の小右記だが、実資は多分道長という人物が好きではなかった。いやもしかしたらはっきり嫌いだったのかもしれない。そういう訳でこの実資の日記には、道長に対する批判の記事がたっぷりと残っているのだ。そのおかげで我々は、朝廷での権力者道長の強引な振舞いや、敵対者に対する陰湿な嫌がらせの数々などを知ることができている。現代での道長の評判があまりよろしくないのは、間違いなくこの実資の日記によるところが大きいだろう。道長にとっては意外な誤算だったかもしれない。
ちなみに道長と言えば平安時代の藤原氏の栄華を象徴する、
「この世をば 我が世とぞ思う 望月の 欠けたることもなしと思えば」
という歌が有名だが、この和歌は道長の日記である御堂関白記には書かれていない。ではなぜ現代に伝わっているのかというと、もちろん実資の小右記に残されているからだ。
日記によると、ある日の道長邸での宴の席で、道長から「歌を詠もうと思うんだけど、君もお返しの歌を詠ってね」と言われた実資が、「もちろんですとも」と返すと、道長は「自慢したような歌なんだけど、別に事前に用意してたわけじゃないんだからね!」と言い訳したあと、上記の歌を詠った、という事だ。なんだかほほえましいやり取りだが、まさかこの歌が日記に書かれて千年後の今まで伝わるとは道長は思いもしなかっただろう。自分の日記には書いてないわけだし、道長的には酔っぱらって調子乗っちゃったな~ぐらいの気持ちだったのかもしれない。
しかし実資はしっかりと記録に残し、その結果現代人たちから道長は驕り高ぶった奴だったと思われているのだから、なかなかに鬼のような所業である。ちなみにこのあと実資はお返しの歌を詠うと言って道長に詠わせておきながら、結局自分は返歌をしなかった。やはり鬼の所業である。
信念の人・実資
実資の日記には道長に対する批判の記事が沢山あるが、実資は別に道長だけを殊更に批判していたわけではない。全ての貴族たちをまんべんなく批判している。これは実資が偏屈で気難しい性格だったから・・・というのも一理あるが、決してそれだけが理由ではない。実資という人は、自分の信念を決して曲げず、正しいと思った事は臆せずやり遂げる人物だった。
言葉にすると簡単に思えるが、実際に自分の信念に従って行動できる人間は少ない。上司から理不尽な命令を受けても、大概の人間は何だかんだ文句を言いつつも従ってしまう。逆らったら角が立つし、後々目をつけられても面倒だ。間違った事であっても、その他大勢の人間が従っているなら自分もその集団の一人になる方が遥かに楽な生き方だろう。
平安時代の貴族社会を生きる実資も、権力者の理不尽に直面する場面が多々あった。時には不満に思いつつもその憤りを日記に記すことしかできないこともあったが、いざというときには自分の信じる正義に従って毅然と行動した。
例えばこんなことがあった。道長の娘・彰子が天皇のもとに入内する際、娘の嫁入り道具にと道長は、他の貴族たちに祝いの和歌を詠ませ、それを屏風に書き写したものを娘に持たせようとした。同じ小野宮一族の者や花山上皇なども歌を献じる中、実資は「公卿の仕事はそんな下働きすることではない」とキッパリと断っている。誰が相手だろうと追従したりしない、実資の気性の一面が見て取れる。
さらに実資の性格を窺わせるのが、歴代天皇との関係である。先に述べた通り実資は天皇の最側近の一人である蔵人頭を八年も務めた人物であり、その間仕えた天皇は円融天皇・花山天皇・一条天皇の三代に渡る。そんな歴代天皇から蔵人頭に任じられ頼りにされる実資は、天皇に忠実な人物だった。天皇と言えば朝廷のトップに立つ存在であるが、この時代になるとすでにその権勢は衰えて、大臣たちの権力争いの道具として利用される程だった。

この時代を描いた歴史物語である「大鏡」に次のような話がある。ある時、石清水八幡宮にてお祭りがあり、儀式の差配を終えた実資は円融上皇のもとに参入した。ドラマ2話では天皇の位にあった円融だが、自分の孫を天皇にしたい道長の父・右大臣兼家の思惑からすでに天皇の位を退き、上皇となっていた。権力の中枢から身を引いた円融の周囲はかつての栄華はどこへやら、何とも寂しい状況で、実資が参上した日も周囲に誰もいなかった。

かつての側近が機嫌伺いに来てくれたことを喜ぶ円融であるが、その様子を見た実資は円融に対し、「今から祭りの使者の行列が通ります。見物に行きましょう」と提案する。「そんな急に行っても迷惑かもしれないし・・・」と躊躇する円融だが、実資は「この私がついているから問題ありません。さあいきましょう」と答えてわずかな供回りを従えて円融を連れ出した。
大通りは祭りの見物人でごった返していたが、そこに円融一行がやってくる。見物客たちは最初は誰が来たのかと訝っていたが、実資の姿を見つけると、「上皇様が来たのだ」と騒いで道を開けようとする。折しも見物に来ていた公卿たちもこの騒ぎを見て何事かと思ったが、「上皇様が来た」と聞いてもまさかそんなはずがないと信じなかった。ところが実資が側にいると知った公卿たちは、「それならば本当だ」と慌てて上皇の御前に参上した。右大臣の兼家も上皇の車の横に控え、貴顕を従えて祭りを見物した円融は大いに面目を施した、という話だ。
歴代天皇の側近として仕えた実資の、かつての主人に報いる情義溢れる行動だ。だがこれは単純に円融個人への忠義心という訳ではないだろう。実資かには、かつての主人を権力争いに利用して顧みない他の公卿たちへの憤りがあったのではないか。実資はこういう「筋が通らない」振舞いを何より嫌っていたように思える。
のちのことだが、時の天皇である三条天皇と左大臣になっていた藤原道長が激しく対立していた事があった。自分の孫を皇位につけたい道長と、天皇の位を保ちたい三条の思惑がぶつかり合い、朝廷は混乱に陥っていた。そんな中、三条の妻・娍子を皇后にする立后の儀という重要な儀式が行われたが、道長は何とこれをボイコット。他の公卿たちもみな道長に同調して、儀式に出席した公卿は実資含めてわずかに四人だけという有様だった。これに憤慨する実資は儀式を主宰して何とか無事にやり遂げるが、その日の日記では道長のことを「巨害」呼ばわりして憤りを露わにしている。
社稷の臣・実資
以上の話を見ていると、「天皇の味方・実資」と「天皇を貶める悪の存在・道長」という対立する構図が見えてくるかもしれないが、実はそれは間違いだ。実資は間違いなく道長のことは嫌いだっただろうが朝廷の実力者として一定の評価はしていたし、道長の方も実資に何だかんだと相談したりしている。そもそも「嫌いだから」という理由で自分の行動を変えるなんて、実資の信念からすれば一番許しがたい行為だったに違いない。
実資は道長の痛烈な批判者であったが、決して敵対者ではなかった。この二つは似ているようで全く違う。もし実資が天皇の味方をするのが、自分の欲心のため、道長を退けて自分が朝廷のトップに立とうとしての行動だったなら、道長は容赦なく実資を政敵として排除しただろう。だが実際にはそうしなかったし、できなかった。実資が自分の欲心から行動する人間ではないことは貴族たちはみな知っていた。そんな実資を目障りだからと排除したなら、傷がつくのは道長の威信の方だった。
また、そんなことをする必要が無かったとも言える。実資が自分を蹴落とそうと陰謀をめぐらす人間ではないという事を、道長自身がよく知っていただろう。むしろ自分のことを嫌っていても、間違ったことをしなければ賛同してくれるのだ。多少口うるさくても、道長にとって実資はある意味一番安全な相手だったのかもしれない。
自分の信念を貫くという生き方は、周囲の流れに逆らって敵を作ることになりかねないが、実資のように私心なくやり遂げることができれば、むしろ一つの処世術となる。実資が道長の批判者であったにも関わらず長い間政治の中枢に居続けることができたのは、実資が信念の人であったことと道長がそれを理解していたこと、この二つがしっかりかみ合っていたことが大きい。道長がただ暴虐で馬鹿な男だったら、目障りな実資などさっさと左遷していただろう。そうはならなかったのだから、結局この二人は良いコンビなのかもしれない。実資は嫌な顔をするだろうが。
さて、そんな実資の生き方を見ていると、俺は一人の中国の偉人を思い出す。その名は晏嬰。実資が生きる平安時代からさらに千数百年遡った中国の春秋時代を生きた政治家だ。晏嬰について詳しく語りだすとあまりに長くなりすぎるから今回は省くが、この晏嬰という人はとにかく主君に諫言をしていた。普通、自分の目上の人の間違いを指摘するのは気後れする行為だ。それを絶大な権力を持つ君主にするとなると、機嫌を損ねて殺されかねない危険な行為となるので、誰も恐れて諫言しなくなる。だが晏嬰は例え主君の機嫌を損ねようが、自分の意見を述べることを恐れなかった。それは彼の信念に基づいている。

ある日、君主が側に仕えていた晏嬰を呼んで、食べ物を持ってくるよう命じたが、晏嬰は「自分は食膳係ではありません」と言って断った。それならばと上着を持ってくるよう命じると、今度は「自分は小間使いではありません」とまた断る。さすがに怒った君主が、「じゃあお前の仕事は何なんだ」と問うと、晏嬰は「我は社稷(国家)の臣なり」と答えたという。
晏嬰にとって、自分が仕えるのは国家であって君主個人ではない、という事だ。むしろ君主こそ、第一の社稷の臣でなければならないというのが晏嬰の考えだった。だから君主が間違ったことをすれば直言して諫めることに何のためらいも持たない。そしてそんな信念を持つ晏嬰を、君主は目障りだからと退けることもできず、晏嬰は国中から慕われる大臣としてその生を全うした。
平安時代の日本にはすでに中国の古典が多数入ってきていたから、博識な実資はこの晏嬰の故事も知っていたかもしれない。お上におもねらず、自分の信念を曲げなかった実資は、正に日本の社稷の臣だったと言える。
紫式部と実資
俺が好きな人物だからという事もあって、実資についてかなり長々と述べてきたが、最後にドラマとも関連する紫式部と実資の関係について少し見ていきたい。実資の日記である小右記には、実は紫式部も登場する。紫式部という名前は後世付けられたものなのでその名では呼ばれないが、ある日の記事に、為時の娘という表記でその存在が残されている。
当時、紫式部は道長の娘で天皇の母となっていた皇太后・彰子に仕えていた。実資は養子の資平を彰子のもとに遣わし、当時病気だった皇太子の様子を探らせたのだが、その時様子を知らせてくれたのが彰子の女房(女官の意味)だった紫式部なのだ。しかも日記にはその女房が為時の娘であること、前々から彰子に雑事を申し込む際は彼女に取り次いでもらっていることなどが記されている。
彰子の女房にすぎない紫式部の事をわざわざ日記に注釈して書き残すぐらいだから、紫式部は実資にとってもある程度重要な人物だったようだ。彰子と実資は交流もあり、日記の中に何度か彰子のもとに参上する様子があるが、その時登場する女房も紫式部の可能性が高い。何度も取り次ぎを頼んでいること、内々の知らせを実資に教えていることなどから、紫式部と実資の間にも信頼関係が築かれていたことが見て取れる。
ちなみに紫式部が書いたとされる「紫式部日記」にも実資は登場している。舞台は彰子が皇子を出産して五十日後の祝いの席。父・道長は勿論のこと、右大臣顕光・内大臣公季と三大臣がそろい踏み、今を時めく公卿たちもこぞって参加していた。酔っぱらった藤原顕光が彰子の女房たちにちょっかいをかけ、これに藤原斉信も加わって歌を詠いだすなど騒がしい宴会の様子が描き出される中、紫式部が注目したのは実資だった。
この時、実資は宴会の輪からは外れたところで柱に寄りかかって、一人静かに周りを観察しているようで、「他の人とは違う」と日記に書かれている。実資に興味を持った紫式部は、酒の席だし自分がだれかなんて気づかないだろうと、実資に話しかけに行く。どういう会話をしたかは記されていないが、紫式部は実資の印象を「現代風の洒落た人など比べ物にならないほど立派な人」と好意的に書き残している。
紫式部日記を読んでいると感じることだが、紫式部という人はかなり控えめな性格で、目立つことを嫌う人物だったようだ。宮廷社会に身を置いていることもかなり場違いだと感じており、常に物憂げな雰囲気が日記の中には漂っている。そんな紫式部が、酒の席だからと自分から実資に話しかけに行くというのは、普段の引っ込み思案な様子とは違ってかなり積極的な印象だ。こういう交流があって、のちのち小右記に書かれているように、実資の取り次ぎとして協力するようになるのかもしれない。
ちなみにこの後、実資は祝杯の順番が回ってきて祝いの歌を詠まなければいけないのを嫌がっている様子だったので、一体どうするのだろうと紫式部は観察していたが、結局無難な祝い文句だけ言って済ませてしまった、と日記に書き残されている。先の宴の中心から離れて一人でいる様子といい、正に我々が想像する実資という人物そのままな感じがしてほほえましい。
日記の面白い所は、歴史の教科書を読んでるだけでは分からない、こういう当時の人びとの交流の様子が垣間見える所にあるだろう。そして歴史の面白さと言う面で言えば、このドラマも同じこと。「光る君へ」がこの時代をどう描いていくのか、この先も興味が尽きないものだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
