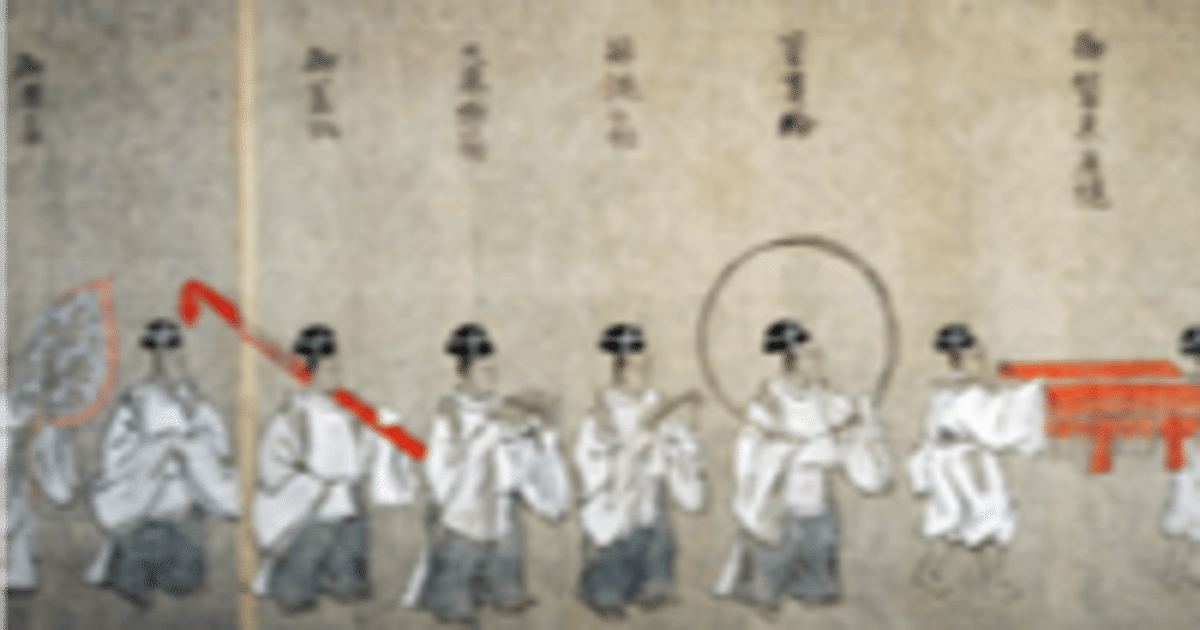
どうして茅の輪をくぐるのか(その1)
【スキ御礼】茅の輪くぐりと夏越の祓
記事「茅の輪くぐりと夏越の祓」の中で、茅の輪くぐりは、夏越の祓いの神事の一つと書いた。
ただ、神田明神の夏越の大祓の神事に参列していながらも、どうしても疑問が残っていた。それは茅の輪くぐりの由来のことである。
各神社の説明でも文献でも、茅の輪くぐりの由来は素戔嗚尊の神話にもとづいていると説明されている。
参列した神田明神の掲示板にもそう書かれていたし、茅の輪神事の発祥の地とされる素戔嗚神社でもそのように説明されている。
備後風土記逸文によれば、昔 北海に坐す武塔神が南海の神女のもとに行かれる途中、日が暮れ一夜の宿を求めて、この地で富み栄えていた巨旦将来の家を訪ねたところ断られました。
次に兄の蘇民将来を訪ねました。貧しいながらも蘇民は快く一夜の宿をお貸ししました。
時を経て尊は八人の王子を連れて蘇民将来の家に立ち寄られ、「吾は速須 佐能雄神なり。後の世に疫病あらば、汝は蘇民将来の子孫と云いて、茅の輪を以って腰に着けけたる人は免れるであろう」と 云われ、巨旦将来を誅滅された伝説が残っています。
尊は温かいもてなしを受けた感謝のしるしとして蘇民将来に「茅の輪」を授けられ、蘇民の一族は疫病から逃れることが 出来ました。
これが今日に伝わっている茅の輪くぐりの神事の起りです。
今では全国的に行われていますが、備後風土記逸文に出てくる疫隈國社は戸手の素盞鳴神社のことで あり、茅の輪神事の発祥の地であります。
しかし、その由来とされる神話からは、現在の茅の輪くぐりが、どうして茅の輪をくぐらなければならないのか、という疑問の答えになっていないのである。
神話のとおり腰につけた茅の輪が疫病退散になるというのなら、現在の茅の輪神事は、お祓いのされた手の平サイズほどの茅の輪を参列者に授けて、腰に付けてもらえばよいはずである。
また、大祓いは過去の半年間の穢れを祓うためのもので、疫病退散の物語の神話と目的が違うのではないか。
さらに、夏の六月末と冬の十二月末に行われる大祓いの時期に行われるのにも違和感がある。
素戔嗚尊の神話だけが由来であれば、どういう変遷を経て神社にあんな大きな茅の輪を建てることになったのか想像ができないのである。
平安時代中期に編纂された『延喜式』(九〇五年)に規定された大祓いの神事の中にも、祝詞の読み上げ、裂布、切麻、人形の神事の四つは記載されているが、五つ目の茅の輪神事は書かれていない。(「茅の輪くぐりと夏越の祓」)
茅の輪くぐりは、どうも大祓の神事と一緒にするのは違う気がしたのである。
この疑問を解決するヒントが、宇佐八幡宮(豊前・今の大分県)で行われていた御祓会の神幸行列の概略を描いた絵巻『宇佐御祓図』(江戸時代画)にあった。
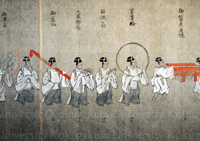
資料の解説によると、この御祓会の行列の図の行列の前方には「菅貫輪」という輪を持っている人が描かれている。
この御祓会は大祓と同様に六月末に行われていたという。
この「菅貫輪」は「茅の輪」と同じものと考えれば、「菅貫」は大祓とは別個の行事だったというのである。
「茅の輪くぐり」は、どうもこの「菅貫」に関係があるようだ。
(つづく)
