
今川泰宏監督 『真マジンガー 衝撃! Z編』 : 今川流ストーリーテリング
作品評:今川泰宏監督『真マジンガー 衝撃! Z編』(2009年・TVシリーズ全26話)
長らく気になりながらも見ることの叶わなかった、今川泰宏版「ジャイアントロボ」「ゲッターロボ」「マジンガーZ」を、ついに見終えることができた。本望である。
本来ならここに「鉄人28号」も加えるべきなのだろうが、劇画調の熱血が好きな私としては、鉄人の丸っこい絵は、好みのものとは言い難く、ぜひ見たいという気にはならなかった。しかしまあ、ここまできたのだから、機会があれば見ても良いとは思っている。
ともあれ、今回は、私的「今川泰宏3部作」のトリを飾る『真マジンガー 衝撃! Z編』だ。

『ジャイアントロボ THE ANIMATION −地球が静止する日』、『真(チェンジ!!)ゲッターロボ 地球最後の日』と見てきて、前者は文句なしの「傑作」、後者は残念ながら第3話で今川監督が降板になってしまったために、いろいろと物足りない「凡作」に堕してしまった「失敗作(挫折作)」というのが私の評価だが、私的「今川泰宏3部作」では最も新しい本作『真マジンガー 衝撃! Z編』は、とにもかくにも今川監督が最後まで作った完成作品であり、足掛け7年で全7話を完結させた、贅沢きわまりない『ジャイアントロボTHE ANIMATION』には及ばないものの、毎週放映のテレビシリーズ作品としては、十分な傑作に仕上がっている。
先の2本については、すでにレビューを書いており、『ジャイアントロボ THE ANIMATION』については同作が如何に傑作なのかを論じ、『真(チェンジ!!)ゲッターロボ』については、どうしてこの作品が、今川監督の降板となり挫折することになったかを論じた。
したがって、今回は、前の2作品を踏まえつつ「今川泰宏的ストーリーテリング」の特徴を論じてみたいと思う。要は「今川泰宏的語りの妙」とは何か、ということである。
○ ○ ○
まず最初に断っておくと、言うまでもなく、今川泰宏版「ジャイアントロボ」「ゲッターロボ」「マジンガーZ」には、それぞれ「原作」があり、その味を「生かしつつも」、今川監督のオリジナルストーリーになっている点だ。つまり、本稿では『真マジンガー 衝撃! Z編』を扱いつつ、前記3部作に共通する「今川らしさ」が、議論の中心となる。
そう断った上で言うなら、今川泰宏の「ストーリーテリング」最大の特徴は、徹底した「騙り(騙し)」にあると、私は考える。
今川泰宏といえば「巨大ロボットアクション」という印象が強い。実際、今川監督は巨大ロボットの見せ方が非常に上手い。



いま流行りの「スピード感」ではなく、「巨大感」や「重量感」を、そのアングルや動きやライティングによって見事に見せており、それでいて単調に堕さないのは、ロボットアクション以外のところでも「回り込み」を使うなど、シークエンス構成にメリハリつけているからで、ロボットが派手に動かなくても、見飽きることはないのである。
(その点、今どきの作品で時々見かけるのだが、3Dモデリングでロボットを描くせいで、無闇にロボットが動き回り、アングルもビュンビュン変わるという絵作りである。だがあれは、中身のないのを口数で誤魔化すのと同様、スピード感で芸のなさを誤魔化しているだけに近く、いささか安直なのではないかと感じられる)
しかしながら以上は、あくまでも「絵作り」の部分であり、今川泰宏監督の「ストーリーテリング」の最大の特徴とは、やはり「騙り(騙し)」だというほかないだろう。
とにかく、今川作品は、視聴者を「騙す」のである。それは、「登場人物の語り」は無論のこと、「ナレーション」や「絵」までのすべてを投入して、視聴者を騙すのだ。
一般には、今川作品の特徴として「大風呂敷」ということがよく指摘されるが、これはもう「大ボラ吹き」とほとんど同じようなものであり、『ジャイアントロボ THE ANIMATION』のサブタイトルは「地球が静止する日」で、『真(チェンジ!!)ゲッターロボ』の方は「地球最後の日」だった。
「そこまで言うか」と言いたくなるような、こうしたサブタイトルのつけ方に象徴される「大胆不敵なハッタリ」性にこそ、今川「ストーリーテリング」の特徴がよく現れていると言って良いだろう。
もちろん、とんでもない超能力者集団だの異星人だのが地球の征服を狙って攻撃を仕掛けてくるのだから、「地球が静止したも同然の日」や「地球最後の日かと思われる日」ならば描かれていて、その意味ではまんざら嘘でもないとは言えるのだろうが、そんなことをいえば、たいがいのSF的活劇ものは「地球静止する日」や「地球最後の日」みたいなものを描いているとも言えるだろう。
だが、地球が「静止したまま人類が滅ぶ」のを描くわけでも、「地球が消滅してしまう日」を描くわけでもないのだから、普通はここまで極端なタイトルはつけないものなのだが、その点で、今川監督には躊躇いがない。どっちにするかと迷った時には「派手な方を選べ」、そして「つじつまは、後でも合わせられる」とそう考えているとしか思えない、「大ボラ吹き」ぶりなのだ。
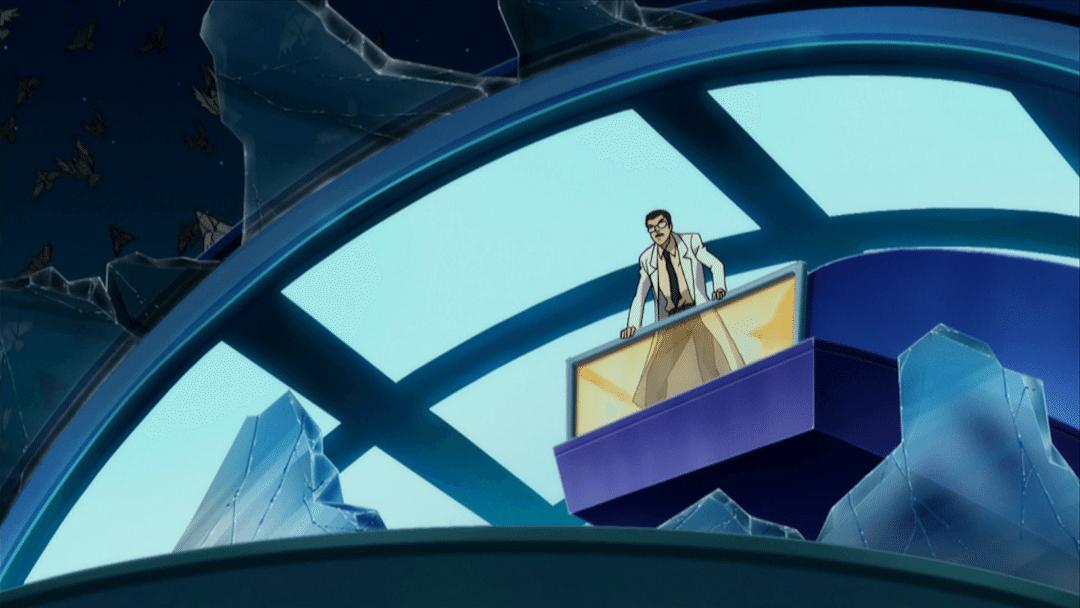
『ジャイアントロボ THE ANIMATION』と『真(チェンジ!!)ゲッターロボ』に共通するのは、物語冒頭の「マッドサイエンティストの開発した超エネルギーによる地球の危機」というものであり、前者のフォーグラー博士にしろ、後者の早乙女博士にしろ、最初は絵に描いたような「マッドサイエンティスト」として登場するし、それを疑い得なくするような「回想シーン」などが、当然のことながら「絵」として示されるから、そうしたものが「すべて嘘」だとは考えにくくなる。
だが、実際には、それが後で、かなりあっさりと撤回されてしまい、フォーグラー博士は本当は良い人だったのであり、早乙女博士にもそれなりの理由があったことが示されて、当初のド派手な「マッドサイエンティスト」のイメージは雲散霧消して、比較的常識的な「人情物語」に落ち着くのである。
しかし、前述のように、私たち視聴者が、当初の「ド派手なイメージ」を真に受けてしまうのは、「回想シーン」などで何度もそのイメージを強化されるからであって、「ここまでやるからには、まさかあれが嘘だっだってことはないよな」と考えるからである。だが、また、今川監督は、そこまで徹底的にやっておいて、最後はあっさり「あれは嘘でした」とやってしまうのであり、言い換えれば、それがヌケヌケとやれるからこそ「並外れたハッタリ」もかますことができるのだとも言えるだろう。
そして、ここで思い出すべきは、私たちが「ロボットアニメ」に期待するのは、基本的に「堅実でリアルな物語」などではなく、少々無理があり辻褄が合わなくても、「ド派手でカタルシスの味わえる物語」だという事実である。だからこそ、あっけなく「あれは嘘でした」とやられても、意外にあっさりと、それを許すこともできるのだ。
そう。「ロボットアニメ」というのは、元来、そうした「ご都合主義」のかたまりのようなジャンルだった。
昔、よく指摘されたように、「どうして、あの少年がロボットのパイロットなの? 他にもっと優秀な大人がいるでしょう」とか「毎週、子供に命懸けの戦いをさせるのは如何なものか」とか「どうして敵は、同時に世界のあちこちに出現して、1体しかない正義のロボットを困らせたりしないの?」とか「絶対的に強いはずの正義のロボットが危機に陥った時、どうして都合よく新兵器が登場するの?」とかいった、そういう「当たり前の疑問」に対し、「いや、そういうものなんだよ」「そういうお約束なの」で済ませてしまうジャンルだったのであり、それで何も問題はなかったのである。

ただ、作り手の方としては、そういう「幼稚」なものを十年一日の如く作るというのは、それはそれで退屈なことだから、そうした「疑問」に答えることのできる、例えば『機動戦士ガンダム』や『装甲騎兵ボトムズ』といった「リアルロボットもの」が作られるようになり、時代はそちらへと大きく流れていったのだ。
つまり、今川泰宏のロボットアニメとは、言うなれば「ロボットアニメが元来持っていた大嘘ぶり」を、あらゆる面において、臆面もなく復活させたものだと言えるだろう。
要は「面白ければ何でもあり」ということなのである。だから「大ボラ」も吹くし「ハッタリ」もかます。それで物語が盛り上がるんなら、それで良いじゃないか、ということなのだ。

ただ、最初に「大ボラ」を吹き、「ハッタリ」をかましたわりには、その「真相」は「意外にショボかった」というのでは、いわゆる「竜頭蛇尾(尻すぼみ)」となってしまい、視聴者をしらけさせてしまう。だが、今川作品に「竜頭蛇尾」という印象が意外に希薄なのは、なぜか?
それは最初にかました「大ボラ」や「ハッタリ」の種明かしがなされる頃には、すでに「次の大ボラやハッタリ」がかまされており、視聴者の興味は、すでにそちらへ移っているからである。
つまり、「真の真相や解決」は、常に「先送りされる」ということなのだ。
最初にかまされた「大ボラやハッタリ」は、「大ボラやハッタリ」のつるべうちによって相対化されてしまい、「当初の謎」は、もはや大きな意味を持たなくなってしまう。つまり、マッドサイエンティストが、本当にマッドサイエンティストであったのか、「じつは良い人」だったのかといったことは、大した問題ではないという物語展開になっているから、最初の「大ボラやハッタリ」をわりあいあっさりと撤回されても「そりゃないよ(真相解明に期待していたのに)」ということにはならないのだ。
しかし、当然のことながら、こうした演出を成功させるためには、「大ボラやハッタリ」の「エスカレーション」が必要になる。つまり、後でつく「嘘」や「大ボラやハッタリ」は、前のそれよりも「大きくて派手なもの」でなければならないということだ。
だが、そのことによって必然的に引き起こされる事態がある。それは、「結末がつけられない」ということである。
実際、『ジャイアントロボ THE ANIMATION』では、最後の最後で、悪の首領であるビッグファイアーが目覚めて、最終作戦である「GR作戦」が発動されるというところで終わるし、『真(チェンジ!!)ゲッターロボ』では、もろに「時空を超えた異空間での、終わりなき戦いは続く」というところで物語は幕を閉じる。
そして本作『真マジンガー 衝撃! Z編』でも、やっと悪の首領ドクターヘルを倒したところ、さらに巨大な真の敵がやってくるというところで、物語は終わる。

『真マジンガー 衝撃! Z編』の場合、このラストは、テレビシリーズ『マジンガーZ』が次シリーズ『グレートマジンガー』へと続く形式を踏襲したもののように見えるのだけれども、たぶんそちらは、「本質」ではない。
つまり、「原作」がどのようなものであろうと、今川監督がオリジナルストーリーにしてしまえば、いずれにしろ最後は「決着がつかない」まま、「戦いは続く」で終わるだろうということだ。そしてこれは、『ジャイアントロボ THE ANIMATION』のレビューで指摘済みのことでもあった。
『この作品においては、「完成」や、その意味での「完全(完璧)性」が目的なのではなく、きっと、先を走る父親が後ろを振り返りながら「息子よ、ついてこい!」と叫び、その後を追う息子が「うん、父さんには負けないぞ!」と追いかけていく、そんな永遠に終わらない、夢物語だったのではないだろうか。』
したがって、物語の決着がつかないというのは、「今川ストーリーテリング」の「弱点」や「問題点」と言うよりも、その「個性」であり、いっそ「美点」だと言っても良いのではないだろうか。
最後に見事に伏線が回収されて、過不足なく物語が完結したら、それは「見事な手際だと感心する」ことはできる。
しかし、それは「物語」として「面白い」ということではなく、「巧みに作られている」ということへの「感心」なのではないだろうか。
例えば、私が好きな「ミステリー小説(推理小説)」の中でも「本格ミステリ」というジャンルは、その本質である「謎と論理の精密機械」としての「完成度」が問題となる。冒頭に示された「大きな謎」が、最後で「過不足なく完璧に解き明かされる」という「首尾一貫性」において、その作品の「出来」が評価されるのだ。
だが、その一方で「本格ミステリ」は、そうした「特性」のゆえに、しばしば「人間が描けていない」という批判を受ける。どういうことかというと、「本格ミステリ」の場合は、作品全体としての「完成度」が問題なのであって、「作品のパーツとしての人間」を描くことには、ほとんど興味がないからだし、「精密機械のパーツ」である以上は、登場人物は皆「機械のネジ」として「正確に作動するもの」でなくてはならず、人間的な「気まぐれさ」や「人間くささ」があってはならないからだ。「この人物はこういう性格だから、必ずこういう動き方をする」というものでなければ、「精密機械として完璧な本格ミステリ」を書くことなどできないからである。
だが、「本格ミステリ」のそうした特性を理解していない、普通の小説読みは、「ミステリー小説」にまで「人間性」を求めてしまう。それが本質的に、異質な要素だというのをわかっていないからなのだ。
そして、そういう人たちに言わせれば「辻褄なんて合わせなくても良い。完璧な説明なんて必要ない。そんなものは、人間の本質から外れた無機質で異様なものだ。しかし、私たちが求めているのは、割り切れない、説明しきれない、そんな人間存在の奥深さなのだ」ということになってしまうのである。

で、ここで議論を「今川泰宏作品」に戻すならば、今川作品とは、まさに「辻褄なんて合わせなくても良い。完璧な説明なんて必要ない。そんなものは、物語の本質から外れた奇妙なこだわりでしかなく、私たちが求めているのは、割り切れない、説明しきれない、人間的欲望の過剰さなのだ」ということになるのである。
つまり、私たちは、つい「作品の完成度」ということを問題にしがちだし、無論それはそれで重要なことなのだけれど、多くの「物語」において求められているのは、実のところ「首尾一貫して完結した物語」などではなく、「ドキドキワクワクさせられ、この先がどうなるのだろうと思いながらも、いつまでも終わらない物語、いつまでも夢を見させてくれる物語」といったものなのではないだろうか。
だとすれば、「今川泰宏のストーリーテリング」というのは、「物語」の王道をいくものなのだとさえ言えるだろう。
例えば、『真マジンガー 衝撃! Z編』を見ていて驚かされるのは、すでに書いたような「物語上のハッタリとしての嘘」ばかりではなく、単純に「死んだはずのキャラクターが、あっさり復活してくる」点である。と言うか、この作品では、メインキャラクターは、敵も味方の、一人も死なないのではないだろうか。
いかにも「死んだ」としか思えないシーンが何度となく描かれるし、作中人物によって「死んだ」と言われもするのだが、「そう見えただけで助かった」とか、さらには「生き返らせてもらった」などということを、ぬけぬけと言うのである。
本作中でも、あしゅら男爵は、何度「この最後の戦い」を口にしたことか。

『ジャイアントロボ THE ANIMATION』や『真(チェンジ!!)ゲッターロボ』では、カッコよく死んでいった作中人物は、少なくとも、最高の死場所を与えられて、死んだままであった。彼や彼女は、死ぬことで、思い出の中で生き続けるキャラクターになった。言うなれば、王道の「死に様」を与えられたのだけれど、本作『真マジンガー 衝撃! Z編』の場合は、カッコよく死んでいったキャラクターも、あるいは物語の展開上「これは流石に、今回は死んだな」というキャラクターでさえ、全員生きて帰ってくるのである。
私たちは、そんな、あっけらかんとした「ご都合主義」に呆れはするのだけれど、しかし、それが作品の「瑕瑾」になっているかといえば、意外にそうではない。「えーっ、あれで生きてたのかよ!」というツッコミ入れつつも、しかし、そのキャラクターが生きていたことに、喜びを感じている自分を否定することもできないのだ。
つまり、ここでも私たちは「論理的一貫性」よりも「感情」を優先してしまっているのである。
そして、これはたぶん、私たちが「物語」というものに求めている本質が、このあたりにある、ということなのであろう。
私たちは「よくできた作品」も結構ではあるけれど、それ以上に「酔わせてくれる作品」を求めているのだ。言い換えれば、「物語」というのは、「酔わせてくれた」上で、「完成度も」高ければ文句はない、ということであり、「完成度」のために「物語の愉楽」を犠牲にするというのは、じつのところ、本末転倒なのである。
そして、そのことをよく知っているからこそ、今川監督は「大ボラやハッタリ」ということを恐れないし、「完結しない」ことも恐れない。
むしろ、私たちが「完結しない物語」を夢想し願望しているというのを知っているからこそ、限りなくそれに近いかたちの物語を、律儀に追求しているのだと、そのように言うこともできるのではないだろうか。
そして本作『真マジンガー 衝撃! Z編』において、メインキャラクターが「死ななくなった」というのは、視聴者に対しては、物語は永遠に終わらないということの、わかりやすい保証であり、監督自身にとっては、その正しさに確信を得たということなのではないだろうか。

キャラクターが死んでいけば、物語はおのずと痩せていってしまう。もちろん、新キャラを出す(補充する)という手もあるけれど、『真(チェンジ!!)ゲッターロボ』がそうであったように、それでは補いきれないものが、たしかにあるのだ(新メンバーは、いつでも旧メンバーの代打でしかない)。
「仮面ライダー」であれ「ウルトラマン」であれ、「昔のキャラクター」が再登場した際に感じるあの「胸の高まり」は、どんなに魅力的な新キャラクターにも生み出し得ないものなのである。
だから、それなら、顔馴染みになったキャラクターたちが「死なない」というのも、わかりやすい「永遠性」の保証であり、「安心」を与えてくれるものなのであろう。
もちろん、キャラクターは死なないかわりに、物語はどんどんエスカレートしていかなくてはならない。その中で、物語は永遠の高みへと駆け昇っていき、ついに、私たちの目の届かないところに去っていってしまうのだ。
今川泰宏の「ストーリーテリング」とは、そのような「永遠性」を幻視させるための、「大ボラ」だった言えるのではないだろうか。

(2024年3月19日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
