
「平均信仰」の社会の中で
「平均思考は捨てなさい」という本を読みました。
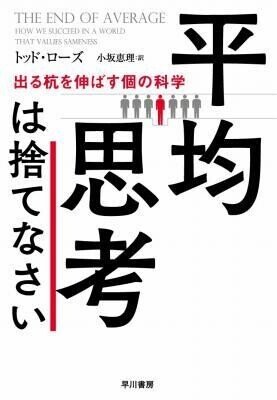
社会のあらゆる場面で「平均」という概念が用いられています。
しかし「平均」は必ずしも実態を表しているわけではない。そのことがこの本では述べられています。
1.「平均的な人」なんていない
この世に「平均的な体の大きさ」の人は、ほぼいないそうです。
例えば「身長」のような単一の物差しであれば、平均身長に等しい人はいます。しかし体の大きさを左右する要素には、様々なものがあります。
身長、体重、肩幅、胸囲、腕の長さ、座高、ウエスト、ヒップ、足の長さ。
これら9つの寸法のうち、4つ以上が平均値に収まる人は、全体の2パーセントに満たず、全てが平均値の人物はほぼいません。
それでも私たちが「平均」を用いるのは、例えば何かを大量生産する時に便利だからです。
洋服を大量生産することで、私たちはある程度の質のものを、安価に入手することができます。少々サイズが合わないところがあっても、それほど気にすることはありません。
2.「平均」と教育
「平均」の概念は、教育の場でも用いられてきました。
「平均」を用いるには、人の能力・資質を測る「物差し」を決めなければいけません。
国が教育を行うのは、「国の競争力強化に資する人材」を輩出するため。そのために様々な「物差し」が設けられ、テストで測定され、「平均」や「偏差値」が算出され、個人が順位付けされることになりました。
そうして皆が順位を争うために切磋琢磨し、それぞれが力を伸ばしていく。この仕組みはとても効果的でした。
しかし問題がなかったわけではありません。
一人ひとりが本来持っている資質に関係なく、あらかじめ決められた種目・ルールの中で競争し、他人より秀でることが求められるようになりました。
3.「平均」への信仰
あくまで一つの手段として用いられてきた「平均」。
これがやがて「当たり前のもの」になり、私たちは色んなことで周りと比較し、「平均」よりも優れているかどうかを気にするようになりました。
赤ちゃんは生後、どれくらいで歩き始め、どれくらいで話し始めるものか。
普通の人はどれくらいで学校に通い始め、そして働き始めるのか。
サラリーマンならサラリーマン、学者なら学者、エンジニアならエンジニア。男性、女性・・・。それぞれの歩むべき平均的な人生、人生モデルがあると考えるようになりました。
私たちは「平均」を信仰している。
そのように著者は主張します。
「平均」があると思うからこそ、自分自身と「平均」とのズレが気になってしまう。神童がもてはやされ、我が子の成長速度が気になってしまう。
しかし、平均より早いから優れているとは限りません。
幼いころに「神童」ともてはやされた子どもの多くが、その後「普通の人」になってしまう。そんな話を耳にした方も多いのではないでしょうか。
そもそも人間の成長は一本道ではありません。
4.人の数だけ「道」がある
赤ちゃんが歩けるようになるまでの道のりも、実は一本道ではありません。
ある研究でたくさんの赤ちゃんの成長を追ってみたところ、歩けるようになるまでのパターンは25通りもあったそうで、赤ちゃんの中には「まず」歩いて、その次にハイハイを始めた子もいたそうです。
その子の親からすれば、いきなり歩き始めたものだから「我が子は天才だ!」と大喜びしたのも束の間、今度はハイハイが始まって「何かまずかったのか?」と悩んでしまったかもしれません。
しかしこれも結局は、それぞれの子どもが「自分の」体の動きの問題について、「自分なりの」ユニークな方法で解決しているに過ぎません。
病気の進行や回復のパターンも一通りではありません。人間の体、精神、職業、いかなる成長も一通りの道はありません。
ゴールへと続く道は複数あり、どの道が最適な経路かは、各人の個性によって決まると言えます。
それを無理やり「この道だけが正常な道だ」として、一本道を歩ませているのが今という時代かもしれません。
5.子どもたちは「花の種」
子どもたちは「花の種」のようなものと言われます。それはスミレの種かもしれないし、ヒマワリの種かもしれない。タンポポかもしれない。
スミレにはスミレの、ヒマワリにはヒマワリの、タンポポにはタンポポの育ち方があり、素晴らしさがあります。
花を咲かせるまでは、何の種かは分かりません。
今後どのような道を歩んでいくのか。いつ、どのような花を咲かせるのか。
それを周りの大人が「あなたはバラになりなさい。何月何日までに茎を何センチ伸ばし、何月何日までに葉を何枚つけて、何月何日までに花を咲かせなさい」と決めることはできません。
今の子どもたちを見ていると、「みんなバラになりなさい」と大人から言われ、それに応えようとして、皆が一生懸命バラになろうとしているようにも見えます。
そうして、大人から与えられた物差しを子どもたちも信じてしまい、その物差しで子どもたち同士で比較し合っているようにも見えます。
本当は、それぞれに自分にしかない素晴らしさがあるのに。
現代の「平均」や「物差し」を用いた教育制度は、あくまで一時的な手段です。この手段は確かによく機能しています。
しかしその物差しでもって、人間の全てを「測れている、分かっている」と思っていたら、そこには傲慢さがあります。
本当は私たち一人ひとりが「測り知れない者」。
今、この「平均信仰」の社会の中において、自分に対しても、相手に対しても、そのような思いを持つことが大切ではないでしょうか。
P.S.
ちなみに私はうつ伏せではなく、仰向けでハイハイしていたそうです。後頭部と背中を接地させ、手は使わず、足で蹴り出してズイズイと。
そのために後頭部がはげてしまっていたようですが。。。
