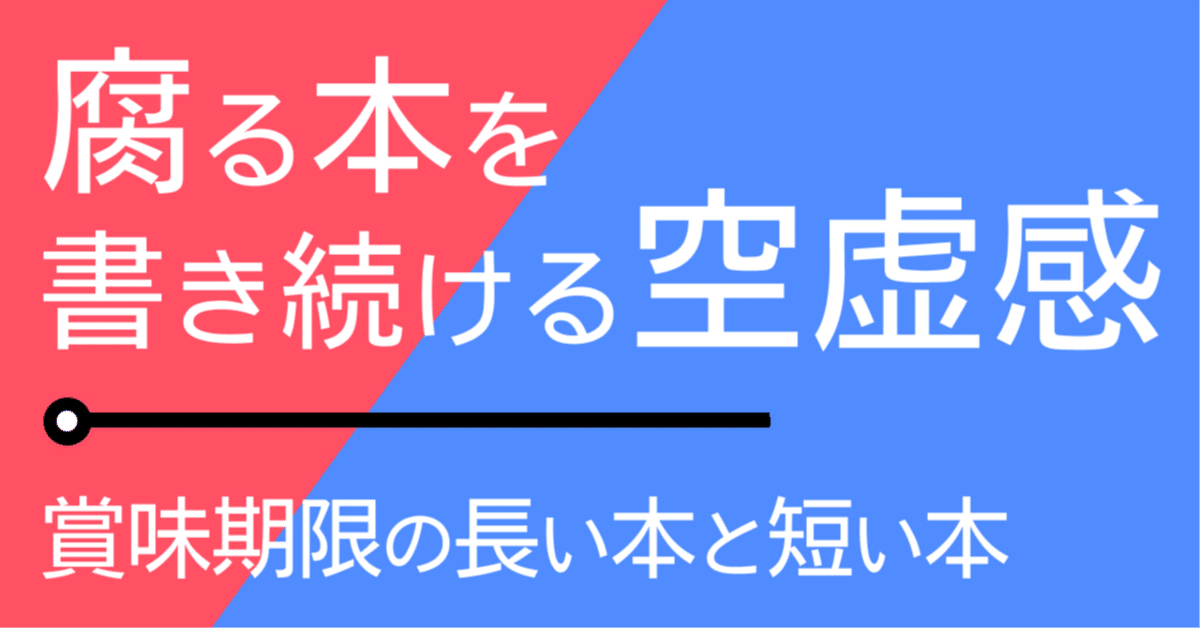
腐る本を書きつづける空虚感 ― 賞味期限の長い本と、賞味期限の短い本
この記事の内容
次のことに触れています。
• 本の「賞味期限」の意味
• 技術書がすぐに腐る理由
• 時間の経過とともに読まれなくなる本の特徴
• 長く生き残る本を書くために必要なこと
• 私自身が本を書きながら感じていた空虚感と、それを乗り越えた方法
それでは以下、本編です。
本の賞味期限
私はこれまでプログラミングの入門書を20冊以上書いてきましたが、その初めの1冊目を3年前に書いていたとき、あることに気がつきました。
本には賞味期限があることです。
賞味期限が短い本
「賞味期限が短い本」とは、すぐに読まれなくなる本、もっと正確にいうと「読めなくなる本」のことです。
技術書はその典型で、時間の経過とともに内容が陳腐化してしまい読めなくなります。
たとえば「Windowsの最新バージョンの使い方」について世界でもっともくわしく書いた書籍を今年出したとしても、来年になって新しいバージョンのWindowsが出たら、その本を読む人はいなくなるでしょう。
つまり書いた時点での価値がもっとも高く、その後は時間の経過とともに猛烈な勢いですり減っていくような本。これが賞味期限の短い本です。
あつかう内容が最先端であればあるほど、実用的であればあるほど、具体的であればあるほど、そして現実に密着していればいるほど、陳腐化のスピードは速まり、賞味期限も短いものになります。
(書籍ではないですが)新聞や週刊誌といったものを考えれば、時間とともに現実との関係性を失っていくような本があることを理解しやすいと思います。
情報提供を目的としたものはもっとも腐りやすいのです。
賞味期限が長い本
一方で賞味期限の長い本、つまり50年、100年、500年、1000年といった時間のあとでも読める本とはどのようなものでしょうか。
それは人間について書いた本、より正確にいえば感情について書いた本です。
小説はその典型でしょう。
1000年前の源氏物語をいまでも面白く読めるのは、この本が当時の最先端の稲作技術だとか、流行していた着物の柄だとか、あるいはおすすめの京都の飲食店の情報だとかについての本ではなく、人間について、人間の感情について書いてあるからです。
小説だけでなく、随筆やエッセー、あるいは哲学書もこの賞味期限の長い本に含まれます。
2000年も読まれているギリシャ哲学の本や、1000年も読まれている源氏物語は例外的といってもいいですが、しかし10年前や20年前といった短いスパンで考えても、今でも読める昔の本というのは小説であったりエッセーであったりで、決して技術書ではないと思います。
外部に依存した本は一緒に腐る
ここまでのことをまとめると、「情報」あるいは「現実」のような「書き手の外部」にあるものについての本は、賞味期限が短く、その対象と一緒に腐ってしまうとわかります。
一方で、「人間」あるいは「感情」のような「書き手の内部」にあるもの、自分の中から養分をくみ取って生み出した自家発電のような書き物は賞味期限が長いのです。
虚無感を感じながらの執筆
冒頭にも書いた通り、このような本の賞味期限の長短について私が気がついたのは3年前、プログラミング入門書(下掲)をはじめて書いていたときでした。
この本がプログラミングの中でも特に変化の激しいフロントエンドと呼ばれる分野の技術についてのものであったことも、このような賞味期限への私の感覚を鋭くしていたのでしょう。
そしてここにある種の空虚感を覚えました。
誰しもそうですが、自分が苦労して作ったものは「できるだけ長く使えるものになってほしい」、本でいえば「できるだけ長く読まれてほしい」と思うからです。
しかし現実には、本の中であつかっている題材ゆえ、その終わりがすぐに来てしまうことは明らかでした。
「これが役に立つのは出版してからせいぜい6ヶ月だけ」「1年後には新しいテクノロジーが出てきて、誰にも読まれないものになっている」という認識を持つこと、つまりすぐに使えなくなるものに人生の時間を費やしている空虚感があったのです。
最初の一冊を書いて以降、かなり長い間このような感覚……自分は使い捨てのものを作っている、うすっぺらいことをしている……という感覚がどこかにありました。
賞味期限の短い本は他にもあった
賞味期限が短い本になってしまうのは、これがプログラミングという変化の激しい分野だからと思い、その分野の本を書かざるを得ないことに、やや自己憐憫を覚えることもありました。
しかしよく考えてみれば、賞味期限が短い本はプログラミング分野だけではなかったのです。
たとえば法律書。
本屋にいけば、立派な装丁の法律専門書がたくさん並んでいます。
プログラミングの本なんかよりもはるかに制作費がかかっていそうなその見た目は重厚で、真面目で、堅牢で、賞味期限も実に長そうです。
しかし法律というものが実は不変ではなく、むしろその時々の社会情勢に応じてすぐに変わっていくことを思えば、法律書も実はとても腐食しやすいことに気がつきます。
同じことは経済の本にも、歴史の本にも、医学の本にも、料理の本にもいえるでしょう。
このことに気がついたとき、私は「腐りやすいのはプログラミングの本だけじゃなかったんだ」とわずかに救われた感覚を覚えましたが、同時にこれが「賞味期限の長い本」についてもう少し深く考えるきっかけのひとつになりました。
3年経っても読まれている
下記記事にも書きましたが、フロントエンド技術をあつかった本が出版から3年経ってもまだ読まれているのは、著者である私にとってまったく予想していないことでした。
先ほど触れたように、半年ほどで時代遅れになると思っていたからです。
実際のところ、この3年のあいだ、電子書籍である特徴を活かして内容のアップデートを重ねていたので、「出して終わり」となってしまう普通の紙の書籍とはやや異なるアプローチが可能だったことは事実でしょう。
しかしまだ腐らずに読まれていることには、もうひとつ理由があるように思います。
ノウハウ系とメンタル系
以前どこかで、「オンライン上のコンテンツにはノウハウ系とメンタル系の2種類しかない」と耳にしました。
この見方を私が面白く感じたのは、書籍も「ノウハウ系」と「メンタル系」に分けられると思ったからです。
ノウハウ系の本とはスキル(技)についての本で、情報提供や技術の伝達を目的とするもの。
メンタル系の本とはマインド(心)についての本で、こころ構えや物の見方・考え方、つまり感情について書いてある本です。
あたりまえですが、情報提供を目的としている本はそもそも書籍というフォーマットである必要もないため、賞味期限は短くなります。
一方で心について、感情について書かれた本は、その内容や書き方にもよりますが、少なくともノウハウ系の本よりも長く読まれる可能性が高いでしょう。
感情をあつかうマインド系の究極の形が小説や随筆、哲学書で、ここまで行けば100年後でも誰かに読んでもらえるかもしれません。
先日、第2版への改訂のため、3年前に書いた本を読み返していました(くわしくは下記記事参照)。
そこで思ったことは、この入門書が3年経っても読まれている理由のひとつは、ここにはスキル系だけなく、メンタル系の内容も書いてあるからではないかということです。
この本では「読者に最新技術を習得してもらう」ということと同時に、「ビギナーに『自分にもできた』という小さな成功体験を作ってもらう」ことにも重点を置いています。
小さな成功体験こそが自信を生み、それが前へと進む推進力となるからです。
それは学習を進める推進力であると同時に自分の人生を進めていく推進力で、より良い方へ、より明るい方へ、より居心地の良い方へと進んでいく力です。
『はじめてつくるReactアプリ』を読み返していて、この本にはこういった「メンタル系」の記述が少なからずあることに気がつきました。
Amazonのレビューを読んでいても、こういったところに気がつき、賛意を示してくれている人は多いようです。
長く読まれる本を書く方法
以上のことを踏まえると、本の賞味期限を延ばし、できるだけ長く読まれるようにするには次のことが有効だとわかります。
つまり情報や知識、テクニックだけなく、読者の感情を少しでも揺さぶるような事柄も書くこと。そしてこの2つが本の中でうまく混ざっていること。
この考え方は、賞味期限が長いものとして上で挙げた随筆やエッセーにも当てはまることかもしれません。
エッセーの難しさは、そもそも読んでもらえないところにあります。
「私はこう感じました」「私はこう思いました」という感情世界の出来事は、本人にとっては一大事でも、他人にとってはどうでもいいことだからです。
一方で芸能人や有名作家の書いたエッセーは読まれます。
読者の側に「あの人は普段どんなことを考えているんだろう?」「この人は物事をどう感じているんだろう?」といった、著者の感情に対する好奇心があるからです。
このような著者の重要度は、プログラミングの本や知識の伝達を目的とした本では下がります。むしろほぼないといってもいいでしょう。
読者は「JavaScriptについて知りたい」「アメリカの経済政策について知りたい」という内容に引かれて本を開くからです。
ここでは「誰が書いたのか」ではなく、「何が書いてあるのか」という点にだけ読み手の関心はあります。
そのため、無名の書き手が自分のエッセーをもっと読んでもらうには、自分の感じたことを書くだけでなく、その中で扱う対象には多くの人が興味をもっている事柄を選ぶのがポイントになるでしょう。
たとえば、佐藤さんという普通の人が『ザンビア滞在記』というエッセーを書いたとき、この本に対する読者の興味の入り口はほぼ存在しないことになります。
ほとんどの日本人はザンビアという国自体知りませんし、佐藤さんの感情の動きなんかにも関心を払っている余裕はないからです。
本への入り口、つまり本を手に取る理由やきっかけが見えにくいのです。
一方、同じ佐藤さんが『フランス滞在記』というエッセーを書いたら、日本人はほぼ全員フランスという国を知っているので、「フランスに対する興味」、つまり「本が扱っているテーマ」に対する興味から手に取る人が出てくるでしょう。
佐藤さんの感情世界の出来事になんかこれぽっちも興味がなくとも、「フランス」というテーマが読者を誘うエサ、つまり本への入り口となり得るのです。
そしてもしこの本がうまく書けているなら、多くの人に読まれ、長く読み継がれることにもなるかもしれません。
「テーマ(本の内容)」だけにフォーカスすると、人に読んでもらえる可能性は高まるが賞味期限は短い。
一方、「感情(本の著者)」にフォーカスすると、賞味期限は長くなるが人に読んでもらえる可能性は低くなる。
そのため、特に有名でもない普通の書き手が賞味期限の長いもの、つまり感情について書きたい場合、本のメインテーマには多くの人が興味のあることを選べばうまくいく可能性が高くなるかもしれません。
文章は形容詞から腐る
三島由紀夫は小説『禁色』で「文章は形容詞から古くなる」と書いています。
本当に形容詞から古くなるのか私にはわかりませんが、しかし言葉自体が古くなったり、意味が変わったり、使われなくなったりすることは誰もが知っていることです。
たとえば現代語で「女房」は「妻」という意味ですが、平安時代は「宮廷で働く女性」のことを指していました。
本が扱う内容だけでなく、本を構成する最小の要素「言葉」というものすらも古びていくのです。
感情だけを上手に扱っても、それが保証する賞味期限はある一定の期間に過ぎない。そしてこの世に腐らないものはない、ということがわかります。
私と読者の二者関係から生まれるもの
さて、ここまで本の賞味期限の長短や、メンタル系の内容を混ぜて腐食を防ぐといった、やや分析的なことを書いてきました。
これらは、賞味期限の短い本を書いているところから来るある種の空虚感を解消するために考え始めたことですが、しかしこれで私の気持ちが晴れたのかというと、そうではありません。
「賞味期限の短い本の執筆に人生の時間を費やしている」という見方を変えられたのは、もっと別のことに気がついたからです。
それは、読者からメールで直接いただいたある感想を読んでいて、ふと思ったことでした。
「……賞味期限が短いとしても、この本で読者の人生が変わったり、何かポジティブな気持ちを得てくれたりしたなら、その読者の未来において私の本は『2024年当時最新とされていた、でも今では誰も使っていないテクノロジーについて書いてある、もはや完全に腐食してしまった本』ではなく、『人生を変える手伝いをしてくれた本』になりえるのかもしれない……」
単なる本という存在を超えた、もっと超越したなにかに読者の中ではなり得るのかもしれない。
私自身をふりかえってみても、そういった本に何度か出会ってきました。
そこに書いてある情報や知識は今では意味を失っているものの、しかし文章の中に見えた作者からのメッセージ、つまり作者の感情は、今でも自分の中で生きていて、時折り思い出してしまうような本です。
私がひとり頭の中で考えていたら空虚でしかないものであっても、読者の存在について考えたとき、つまり私と読者という二者の関係の中にその本を置いたとき、そこからまた別の意味が立ちのぼってくる可能性があることに気がついた瞬間でした。
読者について考える
本というのは書いて終わりではなく、あるいは内容をアップデートし続けてすべてよしでもなく、誰かに読まれることでまた別の命が吹き込まれていくのだと知りました。
読者との関係の中で、まったく新しい、書き手が予想していなかった意味が立ち上がってくることに気がつくと、読者について考える大切さがもう少し深くわかるようになりました。
これまでも「読みやすさ」「わかりやすさ」という点には注意を払って執筆していましたが、そういういわば表面的・技術的なことではなく、「本当に役に立つものを読者に渡したい」という気持ちです。
こんなことに3年経ってようやく気がつきました。
この記事の著者については下記リンクをチェック
◆ Amazon著者ページ:https://www.amazon.co.jp/stores/author/B099Z51QF2
公式サイト:https://monotein.com
X(Twitter):https://x.com/monotein_
◆ React、Next.js、TypeScriptなどのお役立ち情報や実践的コンテンツを、ビギナー向けにかみ砕いて無料配信中。メルマガ登録はこちらから → https://monotein.com/register-newsletter
