
食べて代謝アップを狙うなら絶対に知っておきたい「食事誘発性熱産生」
こんにちは。管理栄養士の河村桃子です。
たんぱく質を食べると代謝が高まり痩せやすい
といった話、最近よく耳にしますよね。
そのため、ここ数年「たんぱく質」が注目されていることからスーパーやコンビニへ行くと「高たんぱく」とパッケージに大きく表示された商品がずらりと並んでいますよね。
また、食事カウンセリングをしていると代謝アップのために毎日プロテインを飲んでいるという方が増えています。以前はプロテインはアスリートやボディービルダー、ハードに鍛えている人など使う方が限られていましたが、今では私たちにとって身近な食品になっていますよね。
話が逸れましたが…
たんぱく質を食べると代謝が高まる理由はいくつかあり、理由のひとつに
たんぱく質は食事誘発性熱産生が高い
ということがあげられます。
【 食事誘発性熱産生 】 聞いたことありますか?
今回は代謝アップを狙うには絶対に知っておきたい食事誘発性熱産生について解説していきます。
食事誘発性熱産生とは?

食事誘発性熱産生とは、私たちの体のなかで起きる代謝のひとつであり、食事をする時に消費するエネルギーのことです。
「食事をするとエネルギーが入ってくるんじゃないの?」
と思うかもしれませんが…
食事をした後に体がぽかぽかと暑くなることありませんか?
このぽかぽかと体が暑くなるのは食事誘発性熱産生によるものなんです。
食事誘発性熱産生とは
食事から摂った栄養素が体内で消化・吸収される際に発生するエネルギー(熱)
のことで、英語で「Diet Induced Thermogenesis 」と表記されることから頭文字をとってDITとも呼ばれています。
たんぱく質の食事誘発性熱産生が断トツに高い
食事誘発性熱産生で消費されるエネルギーは栄養素によって違いがあります。
●糖質のみを摂取した場合 ‥‥ 摂取エネルギーの約6%
●脂質のみを摂取した場合 ‥‥ 摂取エネルギーの約4%
●たんぱく質のみを摂取した場合 ‥‥ 摂取エネルギーの約30%
と、たんぱく質は代謝の過程が複雑なため糖質、脂質よりも食事誘発性熱産生は5〜7倍と断トツで高いため、たんぱく質を食べると代謝が高まりやせやすいと言われています。

しかし、食事では栄養素を単体で摂るわけではなく、糖質・脂質・たんぱく質が混合されているため、通常の食事では1日の消費エネルギーのうち約10%が食事誘発性熱産生によるものとされています。
例えば、1日の消費エネルギーが2000kcalの場合は200kcalが食事誘発清熱産生ということです。
ちなみに、200kcalと同等なのが…
◎ 食パン(5枚切り) 1枚分
◎ コンビニのおにぎり 1個分
◎ ビール 500ml
◎ ランニング 30分
1日の消費エネルギーのうち約10%であっても、身近なものに置き換えてみると、意外と大きな量ですよね。代謝を上げていきたいなら、食事誘発性熱産生をしっかり発生させないともったいないです!
食事誘発性熱産生を発生しやすくするために、たんぱく質を食事に取り入れることは大切なのですが、、、
たんぱく質がメインのプロテインを飲めば効率よく食事誘発性熱産生を高めることが出来るのではないか!?
と思いませんか??
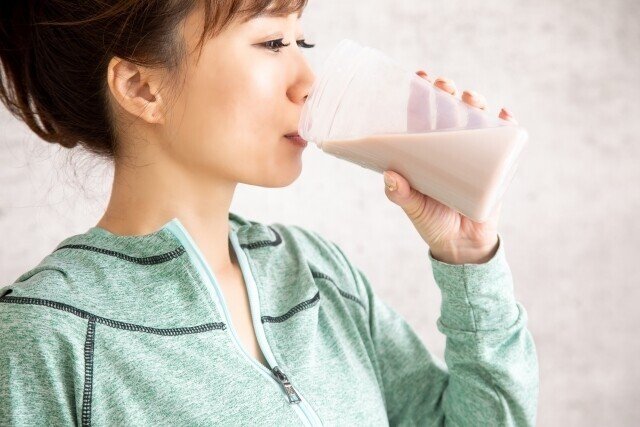
ちょっと待って下さい!!
単にたんぱく質を摂れば消費エネルギーが高くなるというわけではないのです。
食事誘発性熱産生を高めたいならプロテインといった飲料よりも形のある食事を重要視していただくことをおすすめします。
よく噛むことで食事誘発性熱産生が高まる
同じ食事をしてもよく噛まずに早食いをした時と、よく噛んで食べた時とでは食事誘発性熱産生に差があるのです。
食事は口から体内に入り消化管を通って消化され、必要な栄養素が吸収されます。食事誘発性熱産生を高めるには消化管の動きを高め、消化・吸収をスムーズにすることがポイントです。
噛む必要のない液状のものや、固形物であってもよく噛まずに飲み込んでしまうと消化管に負担がかかり、消化不良を起こしてしまうと食事誘発性熱産生の発生量も少なくなってしまいます。

よく噛むことで消化管の動きを高めて、消化・吸収されやすくする
→食事誘発性熱産生をしっかりと起こすことができる!!
また、唾液にはアミラーゼという糖質を分解する酵素が含まれています。
よく噛むことで唾液腺が刺激され唾液の分泌量が増え、消化吸収がスムーズになり、食事誘発性熱産生が起こりやすくなります。
今回は詳しく紹介しませんが、東京工業大学の林直亨教授らが行った研究でも、噛む回数によって食事誘発性熱産生の発生量に違いがあることが明らかになっています。
※詳しい研究内容は下記のサイトに研究論文が掲載されています。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24493207/
「The number of chews and meal duration affect diet-induced thermogenesis and splanchnic circulation」
夜よりも朝のほうが食事誘発性熱産生は高い
「たんぱく質を食事に取り入れる」
「よく噛む」
以外にも、食事誘発性熱産生の発生量に大きく関わることがあります。
それは
食事の時間
です。

同じ食事を同じ量食べても、朝の方が夜よりも食事誘発性熱産生の発生量が高いのです。
日本の女子大学生を対象に食事時刻が食事誘発性熱産生量に与える影響について調べた研究を簡単にご紹介します。
一 律 500kcalの食事を
●朝型:7時、13時、19時に食事を摂取
●夜型:13時、19時、1時に食事を摂取
の2パターンに分け、食事誘発性熱産生の発生量を調べました。
その結果、
朝型のほうが1日を通して食事誘発性熱産生の発生量が高い
ということがわかりました。
また、7時の食事誘発性熱産生が最も高く、1時の食事誘発性熱産生が最も低いという結果となり、7時の食事誘発性熱産生は1時の食事に比べて4倍も高かったのです。
朝食を食べずに夕食をがっつり食べるという生活スタイルだと、食事誘発性熱産生の量も少なく、太りやすいということがこの研究結果からわかりますね。
「朝はしっかり食べて、夜は軽めに」と言われていますが、これは食事誘発性熱産生の面からも言えることです。
まとめ
代謝を高めて太りにくい体を作るうえで抑えておきたい食事誘発性熱産生(DIT)についてお伝えしました。
●食事誘発性熱産生は食事が消化・吸収されるときに発生するエネルギー(熱)
●たんぱく質の食事誘発性熱産生は糖質、脂質の5〜7倍と高い
●1日の消費エネルギーの約10%を占める
●よく噛むことで食事誘発性熱産生が起こりやすい
→飲料(プロテイン)よりも固形物(食事)を
●夜よりも朝のほうが食事誘発性熱産生は高い
→朝はしっかり食べて夜は軽めに
食事誘発性熱産生を高めるためにたんぱく質をしっかり摂ることはとても大切なことですが、その前提は食事から。そして、必要以上にたんぱく質を摂るのではなく、1日3回の食事で不足しないようする。よく噛んで、夜遅くにたくさん食べないようにしていくことが大切です。
「しっかり食べて、しっかり燃やす」が太りにくく、健康な体づくりには欠かせませんね!
※参考文献
・「食事誘発性熱産生 / DIT」,e-ヘルスネット(厚生労働省)
・関野由香、柏絵理子、中村丁次(2010).「食事時刻の変化が若年女子の食事誘発性熱産生に及ぼす影響」日本栄養・食糧学会誌.63 巻 3 号 p. 101-106
閲覧日:2021年10月4日
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+
最後までお読みいただきありがとうございました(^ ^)
