
真のしあわせは、"安定"や"将来の約束"よりも”没頭"できること
おはようございます。美月です。
最近は、LINE登録者限定記事ばかりを公開していました。4月も終わるので「公開記事も書いてよ!」とnoteから通知が来たので久しぶりの公開記事です。
100点満点中105点だった(!?)地理の課題
学生時に受けた授業で今でも鮮明に記憶に残っているのが、高校の地理の授業です。そこでわたしは105点という謎の数値をとった記憶があります。(え、100点満点じゃないの!?と思ったけど理由は思い出せません)
この地理の授業は一風変わったテストの内容でした。ただ世界地図や地形を暗記させてテストで記憶の正確性を測るのではなく、「ある課題」が出されて2人1組でプレゼンテーションし、評価するといったテストです。
その課題が、こちら。
「地球家族」という写真集に掲載されている30か国の写真の中から好きな"発展途上国"について調べ、内容をまとめてプレゼンせよ。
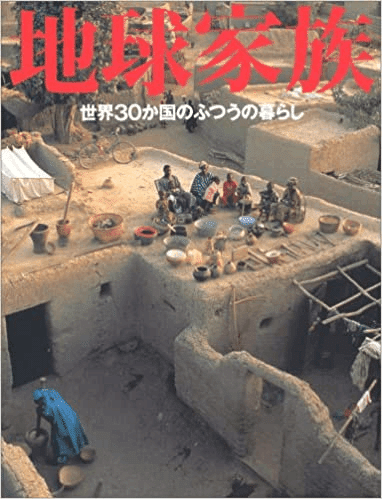
「地球家族」という雑誌の紹介文を引用します。
ドイツ出身の写真家ピーター・メンツェルによる世界30か国、中流階級と呼ばれる人々の暮らしを切り取った写真集。
「申し訳ありませんが、家の中のものを全部、家の前に出して写真を撮らせて下さい」
戦禍のサラエボからモノがあふれる日本まで、世界の平均的家族の持ち物と暮らしを写真で紹介します。





こんな感じで30か国の家と家族、所有物が1枚の写真に並んでいます。
当時は先進国と途上国の定義もよくわからなかったのですが、なんとなく写真を観た直感で、わたしは「サモア」という国を選びました。
(最近ラグビーで有名になりましたね)

サモアを選んだ理由は、写真を観た時にある問いが浮かんだからです。
「なんで、他の国よりも圧倒的にモノがないのにこの家族はしあわせそうで、余裕がある表情をしているんだろう…?」
「サモア」という国はこの写真集で初めて知り、なんの事前知識もありませんでした。ただ明らかに他の国よりもモノが少ないにも関わらずゆったりと、リラックスした在り方で写真に写る彼らに、心が惹かれました。
「先生、わたしたち、サモアにする!」
粋な課題を出してくれた先生に告げ、友人と2人でさっそくサモアという未知の国について調べることになりました。
どんな自分で居ても馴染めるつながりの社会
ネットを中心にサモアについて調べると、サモアにはたくさんの「ファファフィネ」と呼ばれるニューハーフがいることがわかりました。
ですが、他の国と異なりサモアのニューハーフたちには差別や偏見なく当たり前のように公に開示し、暮らしています。
以下、サモアで暮らした体験をブログにしている上妻さんの記事を引用します。
サモアに来て彼らと出逢いたいなら、懸命に探す必要などない。なぜなら銀行、政府省庁、スーパーマーケットの販売員、学校の教師……と、あらゆる職場でごく普通に働いているからだ。ファファフィネは市民権を得て堂々と暮らしており、周囲もファファフィネをごく自然に受け入れている。指をさされたり、もの笑いの種になることはまったくない。だから、ファファフィネたちの表情は至って明るい。

わたしは高校生の時にこのブログを読んで衝撃を受けました。日本だったら、ニューハーフに限らず、少し女性っぽい男性は「おかま」と呼ばれ笑いものにされる。(現在は時代の風潮も変わりつつありますが…)
ましてや、銀行、教員、政府省庁などで公表している方は日本にはほとんどいません。履歴書や面接で「わたしはニューハーフです」なんて公言しても大丈夫な雰囲気はまだまだ日本にはありませんよね。
わたしはこの「指をさされたり、もの笑いの種になることはまったくない。だから、ファファフィネたちの表情は至って明るい。」という一説にひどく感銘を受けました。
人と少し違う自分であっても、笑われたり後ろ指をさされることはない。どんな自分でいても大丈夫という信頼のつながりがサモアの人々にはあるのでしょう。そして、そんなつながりや承認の文化があるからこそ、ファファフィネたちの表情は明るい。
日本はどうでしょうか。
少し人と違ったことをすれば「あの人はおかしい」「あの人は変わっている」などと"私たち"から外されてしまう。
セクシャルマイノリティの当事者たちが「もっとLGBTQを認めよう」と活動しているのは、サモアのように自然に、当たり前のようにはまだ馴染めておらず生きづらさを抱えているからなんだと思います。
でも、LGBTQに限らず、マイノリティ当事者でも「どんな自分でいてもいいという承認の文化があるコミュニティ」につながっている人は表情が明るいように感じます。
つまり、その人が生きづらくなるかどうかは、「どこに所属するか」「誰といるか」といった環境によって変わります。
オープンでかつ、相手への尊重や思いやりをもっている人といることで、「こんなこと言ったらどう思われるかな…」とちょっと不安になることでも正直に伝えあえる。そして自分に対して正直で居られることで、自分のことが好きになってくる。日本であれ、サモアであれ、ともに過ごす人や環境によってそんな循環が生まれるのだと思います。
「持たない=貧しい」は勝手な先入観だった
サモアについて情報収集をしていくうちに、サモアはびっくりするくらい「持たない国」であることがわかりました。
まず、家に壁がない、ドアもない、ドアがないから鍵もない…。
ないない尽くしの生活です。地球家族の写真を観ても一目瞭然。モノもほとんどない。
だからこそ、垣根がありません。
サモアにはお昼寝の習慣があるようで、昼食後にはどこからともなく広いファレ(というサモアの家)に人が集合し、雑魚寝でお昼寝をするそうです。

サモア人の開放性がわかるような記事も発見しました。以下、サモアで海外青年協力隊をした方の体験記です。
サモア人の多くはファレに住み、壁がある家よりファレが大好きだという人が多い。(中略)また、知り合いのサモア人からファレのことについて説明を受けた時に、「壁がないのは、様々な人に対して、いつでも歓迎して待っていることの表れ」と話があった。この言葉に非常に納得したことを覚えている。村を歩くと多くの家族から「一緒にお茶を飲まない?」と誘われたり、食事に招待してもらったりすることが多い。そして、毎回「また明日来なさい」と素敵な笑顔で声をかけてくれる。その度に、サモア人が持つホスピタリティーに感謝を覚える。
壁がない家ファレに住む多くのサモア人は、人と人との間にも壁を作らず、心と心で接しているといえるかも知れない。
サモアを調べ始めた当初、わたしは発展途上国について「貧しい国」だというイメージがありました。
でも、サモアについて知っていくうちにだんだん「豊かさってなんだろう」「しあわせってなんだろう」と疑問を持つようになりました。
何が貧しさなのか、何が豊かさなのかの境界線がわからなくなり混乱していたところにサモアのとある酋長・ツイアビの言葉をまとめた一冊の書籍に出逢いました。
パパラギというのは、サモア人から観た白人のことです。植民地支配の時代に海を渡ってやってきた冒険家や異邦人に対しての呼称です。
この書籍の一説で、サモアの酋長・ツイアビはパパラギについてこう語ります。
物がたくさんなければ暮らしていけないのは、貧しいからだ。大いなる心によって造られたものが乏しいからだ。パパラギは貧しい。だから物に憑かれている。(中略)
少ししか物を持たないパパラギは、自分のことを貧しいと言って悲しがる。私たちならだれでも、食事の鉢のほかは何も持たなくても歌を歌って笑顔でいられるのに、パパラギの中にはそんな人間はひとりもいない。
(第4説「たくさんのものがパパラギを貧しくしている」より)
経済的に豊かで、たくさんのモノを所有する日本。
何もなくても、笑顔で居られるサモア。
調べれば調べるほどに、どちらが豊かなのか、わたしにはわからなくなってしまいました。
でも確かに言えることは、モノを持たない=貧しいという方程式は成り立たないということでした。持たないことが貧しいと決めつけていたのは、日本という国に生まれたわたしの驕りであり、勝手な先入観でした。
お金がないと選択肢が減る、だからお金を稼いで自由を得るんだという話はよく聞きますがお金がなくて得られないという状態=貧しさではないのかもしれません。
むしろ、日本という経済的に豊かな国に生まれたにも関わらず「やりたいことがわからない」と、本来選択できるはずなのにできない、という問題に直面しているわたしたちの方が貧しいのではないか。サモアと比較してそんな風に感じました。
楽しさに、没頭したい
話は少し変わって、最近わたし、人生で初めてマンガで泣きました。いや突然なんだよって思うかもしれませんが、どうしても紹介したいのでお許しを。

この漫画にですね、しあわせの本質、豊かさの本質がすべて描かれていたんですよ。ざっくりあらすじを説明すると、お箏初心者の高校生たちが廃部寸前の筝曲部で音楽に没頭し、全国大会1位を目指す青春ストーリーです。
各キャラの感情や背景のストーリーをこんなに繊細に描けるマンガは他にないのではないかと思うくらいに良いマンガです。わたしの2023年マンガ大賞すでに3冠王の推しマンガです。
主人公の久遠(くどお)は少し前まで喧嘩に明け暮れていた問題児。かつ、箏はまったくの初心者なので最初は「お遊びで音楽をやるんじゃないよ!」と周囲の風当たりが冷たい筝曲部でした。ですが本気でお箏にのめり込む久遠の在り方に少しづつ周囲の人々は心揺さぶられ、巻き込まれていきます。まさにわたしが度々の発信で「純度の高さに人は畏怖を感じ、エネルギーが集まる」と言っていたことはこのことです…!(実際にわたしは課金というエネルギーを久遠に届けました…苦笑)
周囲の反対者たちも認めざるをえないくらい久遠は音楽に没頭し、「全力で没頭する楽しさ」を感じてどんどん変化していきます。
そしてそのエネルギーに周囲の人々も魅せられ、最初は「あの不良が音楽なんて、バッカみたい!」と反対していた人たちがどんどんと久遠の本気さ、真摯さに胸を打たれていく。
この漫画で、ハッとさせられたシーンがあるんですよね。(文脈少し添えておくと、久遠らの筝曲部の舞台を聴いて「いいなあ、わたしも若い頃に何かに没頭したかった~」という女性のセリフの後に発せられた言葉です。)

このマンガを読んで、わたしは「没頭する力(=心を動かし楽しむ力)こそが、真のゆたかさなのかもしれない」と確信を得ました。さらに、どうしてこのマンガが多くの人の心に届くのかという理由も、少し見えてきました。
「やりたいことがわからない」と悩む人は、自分の人生が飽和していることに気が付いているんじゃないかなって思うんです。本当は、自分の強みを知りたいんじゃなくて、やりたいことを見つけたいんじゃなくて、楽しさに没頭し、生きている実感を味わいたい。だからこそこのマンガの内容にも共鳴し、感動する。(わたし含め)
でも、サモアの例からもわかるように、「この音とまれ!」でも描かれているように、全力で楽しむために必要なことは自分の強みを知ることだけじゃない。
自分の内側にある、「きっと否定されるかもしれない感情、衝動、想い」を否定しない仲間の存在が何よりも大事です。
サモアのファファフィネたちが自分に嘘をつかずに堂々と生きられるのは、否定されない、承認のつながりや文化があるからです。
指をさされたり、もの笑いの種になることはまったくない。だから、ファファフィネたちの表情は至って明るい。
みんなと同じことを自分がしたければ、後ろ指をさされることはない。ならば、もう行動しているはずです。それでも飽和状態にあり、「もっと人生に没頭したい」と思うのは自分だからこそ衝動が湧くこと、自分だからこその感情や想いをもっともっと表現し、没頭していきたいからです。
そしてそれは、久遠のように「きっと周囲に否定されること」がタネかもしれません。だって、否定されるかもって感じるということは、みんなと同じではない、あなた独自のものだから。それはきっと、人とは違う感覚なんだと思います。
それこそが、内なる美であり、感性だとわたしは思っています。
真のしあわせは、"安定"や"将来の約束"よりも"没頭"できること
何かに没頭して、毎日汗だくになって取り組んで、自分だからこその役割を全うして生きている感覚。
それが、「この音とまれ!」にはありました。そしてきっと、サモアの人たちがモノを持たなくても笑顔な所以も、「今この瞬間に没頭できる力、全力で楽しむ力」がゆたかなんだろうなと感じます。
わたしはこのような自分だからこそ自然にやってしまう、没頭している状態を「いとなみ」と呼んでいます。
湧いてくる衝動に、正直に在ること。
それを人の眼を気にせずに、ありのまま表現していること。
自分を活かし誰かが喜び、エネルギーが循環していること。
このすべてが満たされている状態こそが、人間にとっての自然のいとなみだと定義しています。
わたしで言えば、こうして言葉を紡ぐこともひとつのいとなみです。累計85回目を迎えたRoom105の活動(ホムパ)もいとなみです。それは誰に頼まれたわけでもなく、ただ、楽しいからやってしまう。noteも、湧き上がるから綴ってしまう。そしてそれが、他者に伝わり誰かの気付きにつながることがある。書いているだけでも楽しいですが、筝曲部の舞台公演のように、それが他者に伝わって喜んでもらえたらなお「もっとやりたい」という気持ちが溢れてきます。


真のしあわせは、今この瞬間の楽しさに没頭できるいとなみにあると私は確信しています。
引用したマンガのワンシーンのように、おとなにだって、全力で楽しみ没頭する自分だからこそのいとなみがきっとある。
誰もが自分だからできるいとなみに出逢ったとき、真の意味でのしあわせや豊かさを味わう人が増えることを信じています。
いいなと思ったら応援しよう!

