
数年ぶりに再会した従姉妹と、ひとつ屋根の下で甘い生活を 第36話(第1部最終回)
*
「手、つないでもいい?」
「えっ?」
「いいから! ほら!」
陽葵が俺の手を取ってきた。
「お、おい……」
「へへん♪ これでカップル成立だね!」
「…………」
「嫌だった?」
「そんなことはないよ。ただ、びっくりしたというか……」
「もう、照れちゃってぇ……」
「別に、照れてないし……」
「はい、ダウト!」
「ぐぬぅ……」
「ふふ……」
「はは……」
俺たちは、お互いに笑い合った。
「ねぇ、蒼生」
「ん?」
「キスしてあげようか?」
「ぶほっ!!」
俺は思わず吹き出してしまった。
「な、なに言ってんの!?」
「だって、わたしたち、元々は、あのときカップルになってたんだよ。それなのに、蒼生の恋人候補がいっぱい現れてさ……。だから、これは、その復讐みたいなもの。大人しく受け入れなさい!」
「ちょ、ちょっと……」
陽葵が俺の顔に迫ってくる。
俺は慌てて後ずさった。
「あれ? どうして逃げるの?」
「逃げて、悪いかよ!?」
「じゃあ、わたしの勝ちだね!」
「勝負じゃないだろ!?」
「蒼生の意気地なし!」
「それは違うと思うぞ!?」
俺が必死に逃げ回っていると、いつの間にか公園にいて、よく落ちている石ころにつまずいて転んでしまった。
「あっ……」
「きゃっ……」
ドサッ!!
どんな運命をたどれば、陽葵を押し倒すような体勢になるのか……俺には意味が理解できない。
とにかく運命の石ころのせいで陽葵を押し倒していた。
「…………」
「…………」
やばい……。
これ、完全にラブコメの展開じゃん……。
ど、どうしよう……。
「…………」
「…………」
陽葵は顔を真っ赤にしながら目を逸らすと、小さな声で、つぶやいた。
「このまま、キス、する?」
……マジで?
「い、いや、それはダメだ……」
「……そうだよね。蒼生は、まだ迷っているもんね。わかってるよ……。だけど、わたしは諦めないからね……」
「陽葵……」
「いつかは振り向かせてみせるんだから……」
陽葵は優しく微笑むと、俺の首に手を回してきた。
「お、おい!?」
「大丈夫。蒼生は、なにもしなくていいの。わたしに全部任せて……」
「えっ!?」
陽葵の吐息が耳にかかってくすぐったい。
彼女の柔らかい身体が密着している。
陽葵の甘い匂いが鼻腔を刺激した。
こんなことをされて普通の男は我慢できないだろう。
心臓の鼓動が加速していく。
「蒼生……大好き……」
陽葵が潤んだ瞳で見つめてきた。
「…………」
俺は無言のまま、ゆっくりと陽葵に近づいていく。
「蒼生……」
そして、唇が触れようとした瞬間―――。
ピタッ……。
俺は動きを止めた。
「……?」
陽葵が不思議そうな顔で首を傾げる。
「……ごめん」
俺は陽葵から離れていく。
「えっ……?」
「俺たちは振り出しに戻った。それに……今じゃない」
「そっか……。うん、わかったよ……。やっぱり、まだ決心はつかないよね……。でも、いつかは、きっと答えを出してね……」
「ああ……」
「待ってるから……」
陽葵は立ち上がると、俺に手を差し伸べてくれた。
「ありがとう」
俺も立ち上がって、彼女と手をつなぐ。
そして、ふたりで歩き出すと、やっとコンビニが見えてきた。
「おっ、ちょうど見えてきたな」
「うん……」
「なんか奢るよ。さっきのお詫び」
「本当? やったぁ~!」
俺と陽葵はアイスクリームを買って、近くの公園のベンチに座って食べることにした。
「はい、アイス」
「ありがと~」
俺はバニラ味で、陽葵はストロベリー味のカップアイスを食べる。
「おいしいね」
「ああ」
「こんな日々が続くといいね……」
「そうだな……」
こうして、俺たちの夜は過ぎていく。
カップアイスを食べ終わった俺たちは、少しだけ散歩することにした。
夜風が気持ちいいし、相変わらず、星空が綺麗だ。
本当に、この平和な日常がいつまでも続けばいいのにな……。
そう思いながら歩いていると、いつの間にか自宅の前に着いていた。
「さて、家に入ろうか……陽葵?」
陽葵が、なにか心惜しいような表情をしていることに気づく。
「ん?」
「あのね……」
陽葵は自分の胸に手を当てていた。
「なんだ?」
「その……やっぱり……」
「えっ?」
「えっと……こっちに来てくれる?」
「えっ、あっ、うん……」
俺は陽葵に近づいたのだが……。
――ちゅっ……!
「……陽葵?」
一瞬のことだった。
俺の口にキスをしたのだ。
「……えへへ」
陽葵は照れくさそうに笑っていた。
「なんだよ、いきなり……」
「わたしは蒼生の恋人になりたいから……」
「だからって……」
「今日の心残りは、これでなくなったし、家に入ろうか」
「あ、ああ……」
「ねぇ、蒼生」
「ん?」
「わたしのこと好き?」
「ああ、好きだよ」
「ふーん……。でも、わたし以外の女の子と付き合うの?」
「えっ? それは、わからないけど……」
「じゃあ、もしもの話をするね。もし、わたし以外に好きな人ができたら、そのときは正直に言ってね。絶対に責めたりしないから……」
「あ、ああ……」
「約束だよ?」
「わ、わかった……」
「ふふっ……」
「なんだよ、その笑い方は……」
「別に。なんでもないよ。ただ、今が、嬉しいなって思っただけだから」
「まあ、俺だって、みんなに幸せになってほしいと思ってるし、そのためにできることなら協力したいとは思うよ」
「……そう」
陽葵は、なにか含みのある表情をしている。
「じゃあ、また明日……だね」
「おう。今日は楽しかったよ」
「うふふ……。ありがと!」
俺と陽葵は自分の部屋に戻っていく。
また、一糸学院での日常が始まろうとしていた。
*
一糸学院の不良生徒たちは、すべて更生された。
もう、この学校で不良生徒たちと、なんらかのトラブルに巻き込まれることはないだろう。
――放課後の生徒会室。
そこには俺と陽葵と葵結と悠人と知世と琴葉さんがいた。
「蒼生くんのおかげで、たった一ヶ月で不良生徒がいなくなってよかったよ」
「いえ、俺は、そんな大したことはしてませんよ。みんなのがんばりがあったからこそです」
「でも、蒼生くんがいなかったら、もっと時間がかかっていたかもしれないし、私たちだけでは解決できなかった問題もあったと思うから……」
「はぁ……」
「それに、また、なにかあったら相談してほしいかな。前みたいに、ひとりで抱えるのは、やめたほうがいいよ」
「……はい。わかりました」
「蒼生くんには、感謝してもしきれないくらい、お世話になっているから……ここでも、家でもね」
「そんなことないですよ。俺は、自分が正しいと思ったことをしているだけですから」
「蒼生くんは、そういう感じで取り繕うところがあるよね……困っちゃうな……」
「…………」
「でも、蒼生くんだけじゃないか。悠人くん、知世さん、葵結、陽葵も、ありがとう」
「いや、俺たちは事後報告をしただけですけどね」
「ほとんどは蒼生が解決しましたからね」
「蒼生がいなかったら、今年の不良生徒問題を解決できなかったと思うよ、お姉ちゃん……」
「でも、本当に、みんな、ありがとね……。これで、ひとまずは安心だね」
琴葉さんは胸を撫で下ろす。
「あの、わたし……今回、なにもできなくて、申し訳ございませんでした」
葵結が深々と頭を下げた。
「いや、葵結がいなかったら、不良生徒たちの問題が浮き彫りにならなかっただろうから……ありがとう」
「……そう、ですかね」
「葵結は、ずっと俺のそばにいてくれて、俺を支えてくれた。それが、なにより嬉しい」
「蒼生……」
「これからも、よろしくな」
「はいっ!」
葵結は満面の笑みを浮かべる。
「青春してるなぁ……」
悠人が口を尖らせた。
「悪いかよ……」
「なんか、蒼生が、たった一ヶ月で遠いところへ来たんじゃないかって思えてきたぜ……」
「なんだよ、それ……」
「蒼生を見ているとさ……なんか、俺たちが普通すぎて違和感があるというか……」
「いや、俺は、ただの……普通の高校生だよ……」
「そうかもしれないけどさ……蒼生は、なんていうか、俺たちとは違う気がするんだ。いずれ、この世界に、なにかを残すんじゃないかっていう確信が俺にはあるんだ。それが、なんなのか、どういう形になるのかは、わからないけど……」
「買いかぶりすぎだよ……」
俺は苦笑いをするしかなかった。
「そういえば、蒼生は陽葵さんと正式に付き合うことになったんだっけ?」
「いや、それは……」
「違うのですか?」
知世が突っ込んだ。
「いや……付き合ってはいない」
「そうなの? えっ、どうして?」
「俺は……今、考え中だ」
「蒼生……」
陽葵が心配そうに見つめてくる。
「まあ、まだ答えは出ていないんだけどな……」
「そっか……。でも、蒼生は、きっと自分の気持ちに気づいているはずだよ。私は、そう思う」
「ああ、俺も同じ意見だ」
「…………」
俺は、どうしたいんだろうか。
でも、その先にある未来に不安を感じているのは確かだった。
だから、俺は宣言する。
「だけど、いずれ答えは出るよ。いや、答えを出してみせるさ……」
『蒼生……』
「だから、もう少しだけ待っていてほしい……」
「うん、わかったよ……」
琴葉さんは優しく微笑んでくれた。
「蒼生の選択を尊重するよ」
「蒼生なら大丈夫ですよ」
悠人と知世は俺を受け入れてくれた。
「はい! わたしも応援していますわ!」
葵結は力強く返事をする。
「蒼生なら、いつか、答えを出せるよ」
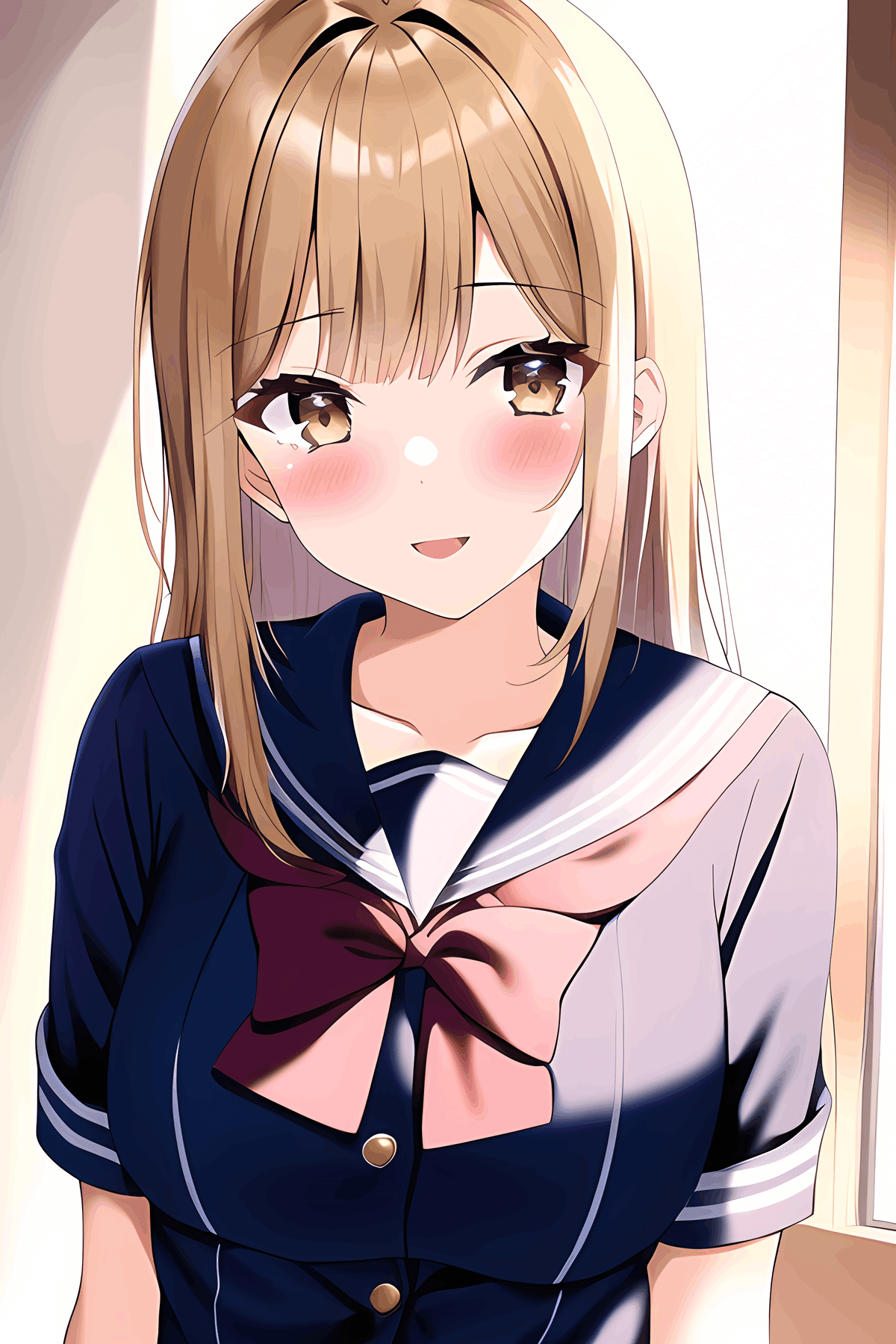
陽葵も信じてくれるようだ。
「ありがとう……みんな」
みんなの優しさに感謝しながら、この平和になった日常が、いつまでも続いてほしいと願った。
みんながいてくれるからこそ、俺は前に進んでいけるような気がするのだ。
こうして、平和になった俺たちの学校生活と、従姉妹たちとの同じ屋根の下での甘い生活が始まろうとしていた。
