
#5 太宰治全部読む |ただ、普通でありたかった
私は、太宰治の作品を全部読むことにした。
太宰治を全部読むと、人はどのような感情を抱くのか。身をもって確かめることにした。
前回読んだ『津軽』は、太宰が生まれ故郷の津軽に帰郷し、産物や自然を享受し、友と語らいながら、生家との長年の断絶に区切りをつける、味わい深い紀行小説であった。
そして、太宰治全部読む、第5回にして真打登場。いよいよ『人間失格』だ。
太宰の代表作を挙げよと言われ、多くの人が答えるであろう『人間失格』。晩年の太宰が心身を削り書き上げたこの作品を、私は真っ向から受け止めることができるのだろうか……。
太宰治|人間失格
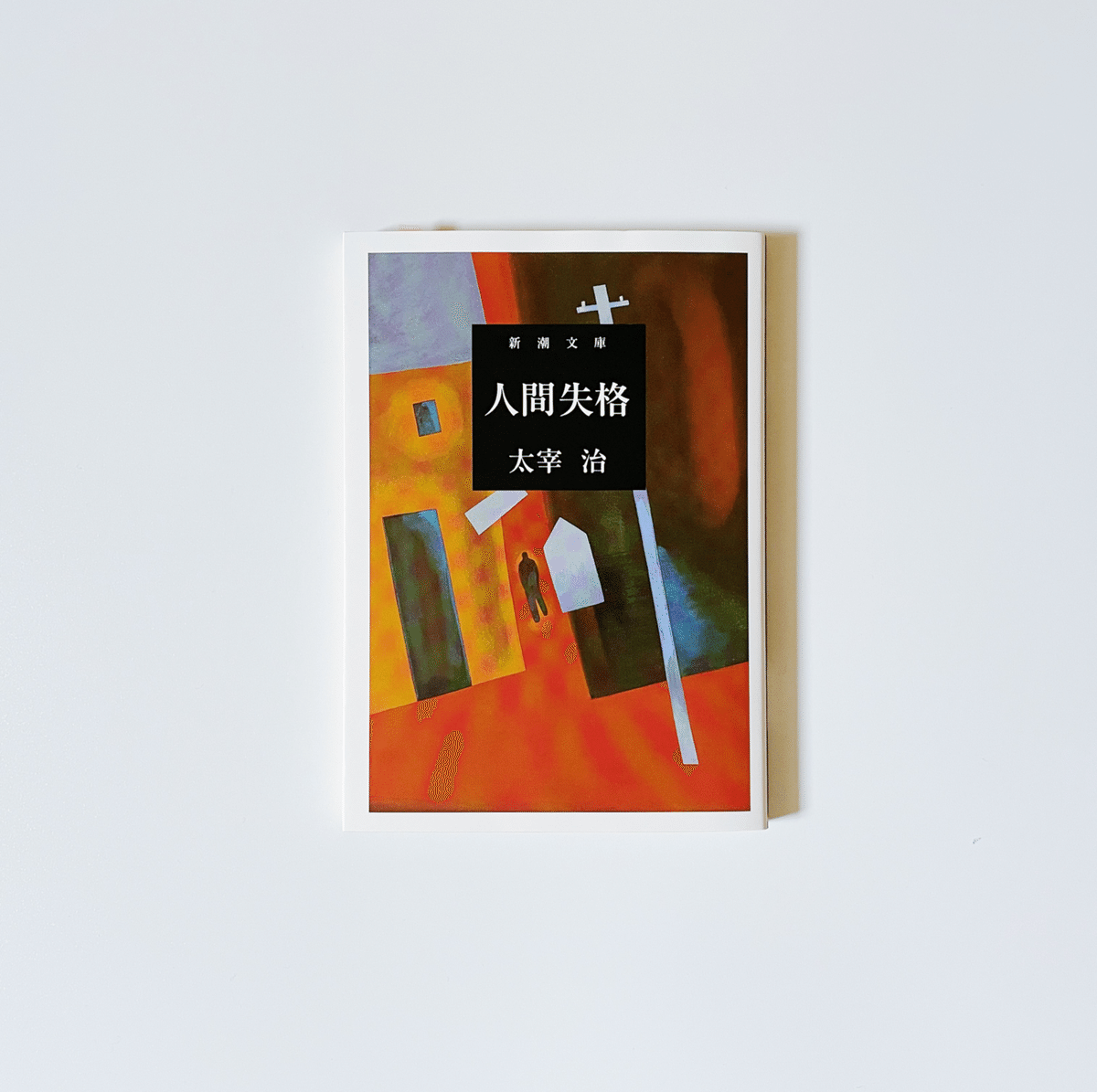
「恥の多い生涯を送って来ました」。そんな身もふたもない告白から男の手記は始まる。男は自分を偽り、ひとを欺き、取り返しようのない過ちを犯し、「失格」の判定を自らにくだす。でも、男が不在になると、彼を懐かしんで、ある女性は語るのだ。「とても素直で、よく気がきいて(中略)神様みたいないい子でした」と。ひとがひととして、ひとと生きる意味を問う、太宰治、捨て身の問題作。
『人間失格』は、太宰自身の内面がひたすらに書き綴られた、自叙伝小説である。死を目前に控えた、心身ともにギリギリの状態の濃密な作品だ。
主人公の男・大庭葉蔵は、言うまでもなく太宰の分身である。書かれていることの全てが事実ではないだろうが、これまで太宰作品を幾分か読んできた身としては、『人間失格』に書かれているのは、まさしく太宰そのものだと感じた。
執筆の経緯
まずは、『人間失格』が執筆されるに至る経緯について、少し書く。
新進気鋭の作家として注目を集める傍ら、自殺未遂・麻薬中毒と、自己破壊の道をひた走る太宰。そんな彼を見かねた周囲の人々は、半ば騙すような形で、太宰を精神病院に入院させる。
信頼していた人たちに裏切られ、「狂人」という烙印を押される形となった太宰は、退院後に『HUMAN LOST』という短編を書く。これが、『人間失格』へ繋がる下地となる。
『人間失格』は、著者が死の直前に書いた作品であるが、構想は長い期間にわたって練られ、太宰の生涯の総決算として書かれた。
精神病院に入れられ、何も信じることができなくなった太宰が、他者を配慮せず、ただ内へ内へと沈み込み、自分のためだけに書き残した文章だ。
それまでの太宰に見られる、読者へのサービス精神やユーモアは、本作には見られない。
淡々と、何か懺悔をするかのように、心の内をすべて吐き出すようにして書かれている。そのため、他の作品にはない、恐ろしい気迫が感じられる。
恥の多い生涯
恥の多い生涯を送って来ました。
本作は、主人公・大庭葉蔵による、3つの手記という体裁を取っている。第一の手記は、上記の一文から始まる。非常によく知られた一節である。
ここから、太宰の長い告白は幕を開ける。「恥の多い生涯」と自ら評する、彼の人生が書き綴られていく。
道化を演じる少年時代。明るさを装い、周囲を偽ることに成功するも、いつか誰かに見破られ、糾弾されることを恐れる日々。
高等学校での放蕩、女遊び。大学進学後の堕落、困窮生活、共産党運動への参加。
やがて共産党運動からも逃亡し、銀座のカフェの女給・ツネ子と入水自殺を試みる。ツネ子は亡くなり、彼は生き残る。
自殺幇助の罪人として捕まると、かえって彼は安心する。「自由」というものを恐れ、何かに束縛されると安堵する。
逮捕されたことよりも、取り調べ検事にわざと大袈裟にした咳を偽と見破られたことのほうが辛かったというエピソードからは、道化でいなければ自分を保てない、彼の生きづらさが伝わってくる。
そして、妻のヨシ子が別の男に汚される事件により、彼曰く「無垢の信頼」が打ち破られ、そこから苦悩に満ちた日々が始まる。
アルコール漬けの日々、服毒自殺未遂、モルヒネ中毒。崩壊した生活の果てに、彼は脳病院行きとなる。
話の大筋は、太宰自身の生涯をなぞっている。時に目を背けたくなるような辛く混沌とした人生であるが、読者は不思議と引き込まれていく。
ただ、普通でありたかった
人間、失格。
もはや、自分は、完全に、人間では無くなりました。
脳病院に入った大庭は、自らを「完全に人間ではなくなった」と評し、絶望する。
太宰にとって「人間」であることの条件は、周囲の人間と同じであること、すなわち「普通」であることだったのかもしれない。他人には普通にできることが、自分にはできない。彼にとって、それは「人間失格」を意味した。
津軽の大地主の家に生まれた太宰は、上流階級としての出自と、堕落した自分の状況とのギャップに、ひどく苦しんだ。道化を演じて仮面を被らなければ、周囲に馴染むことができなかった。
彼は常に、自らをはみ出し者と感じていた。普通の人に溶け込むことのできない、異質な存在。
個性などいらない。ただ普通でありたい。「恥の多い生涯」を送ってきた太宰にとって、それが人生最大の願いだったのかもしれない。
27年間、生死の間を彷徨いながら生きてきた彼は、ひとつの真理にたどり着く。
それは、「自分がいてもいなくても、この世界の一切は何も変わらず過ぎていく」という事実だった。
いまは自分には、幸福も不幸もありません。
ただ、一さいは過ぎて行きます。
長い苦しみの果てに、彼は世界に無感動になる。幸福も不幸もない、無の境地に至ってしまう。自分は世界に必要とされていない。そして恐らく、自分も世界を必要としていない。
生きる意味を失った彼は、必然的に、死へと誘われていく。
「神様みたいにいい子でした」
私たちの知っている葉ちゃんは、とても素直で、よく気がきいて、あれでお酒さえ飲まなければ、いいえ、飲んでも、……神様みたいないい子でした。
『人間失格』は、大庭葉蔵の手記を読んだ小説家が、手記中に登場するマダムが営むバーを訪れる、「あとがき」で幕を閉じる。
そこでマダムに大庭の印象を聞くと、上記引用部分のような答えが返ってくる。
「神様みたいないい子でした」。それまで大庭の手記を読んできた読者は、手記の内容と、マダムの印象とのギャップに驚く。
この一文に、太宰が込めた想いとは、何だったのだろう。
人間失格とまで自分を評した人物でさえ、他人からみれば、良い人だったと映ることもある。
自分の自分に対する評価と、他者の自分に対する評価は、往々にして異なる。そういう意味では、自分の考えを気にしすぎることはないという、一種の希望が込められているのかもしれない。
あるいは、人の記憶は時間の経過とともに美化され、個人の苦悩は何事もなかったかのように忘れ去られてしまうという、メッセージかもしれない。
一時は深く関わった人でも、長く会わないうちに記憶が薄れ、最終的には「良い人だった」という、ぼんやりした印象だけが残る。
自死を選ぶまでに追い詰められていた大庭の苦悩も、大局的な時間の流れの中では非常に小さな悩みで、他者からすれば「良い人だった」という簡素な印象で片付けられてしまう。
このように考えると、人が人として、苦しみながらも生きていく意味とは何なのだろうか——。
様々なことを想像できるが、私がひとつ確信しているのは、マダムの「いい子だった」という言葉は、嘘ではないということだ。
太宰という男はきっと、家族や友人、仕事仲間に多大なる迷惑をかけながらも、皆から愛される人物だったのだと思う。
彼自身は普通でありたいと望んでいたかもしれないが、彼が持つ唯一無二の個性は人を惹きつけ、魅了したはずだ。もっとも、その周囲から注がれる愛ゆえに、太宰は苦しんでいたのかもしれないが……。
小説を読むのと同時に、太宰の人生を読んでいる
長くなってしまったが、私が『人間失格』を読み、考えたことを書いた。
実は数年前、大学時代にも一度、『人間失格』を読んだことがあった。今回はその時よりも、主人公・大庭葉蔵の人物像が、くっきりとした像を持って浮かんできた。
それは、「太宰治全部読む」として太宰作品を読み進める中で、彼の生い立ちや人柄を、より深く知っていたことが理由だろう。
太宰の作品は、読めば読むほど太宰という人物への理解が深まり、それに伴って、作品の面白さも増すという構造になっている。
読者は、小説を読むのと同時に、太宰の人生を読んでいる。この「二層構造」の読書ができる小説家は、世界中探しても稀だろう。
↓「全部読む」シリーズの続きはこちらから!
↓本に関するおすすめ記事をまとめています。
↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。
↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。
