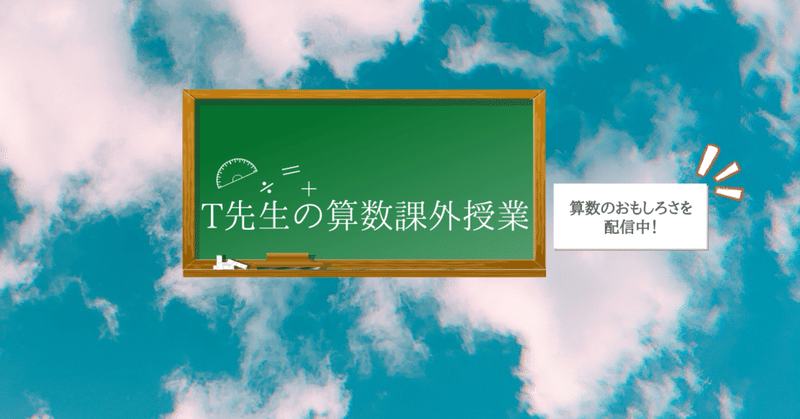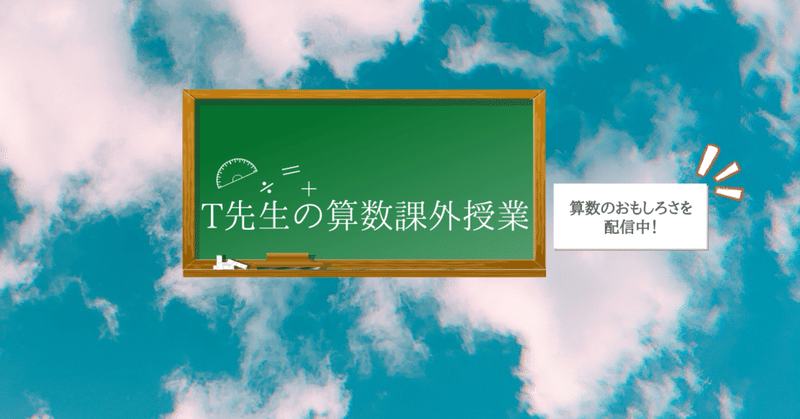【第6話】上下関係に悩んでいる君へ①
こう「あー、月曜日が憂鬱だなぁ。」
T「どうしたん?宿題がまだ終わってないの?」
りん「いつもね、1週間に1回、なかよし会といって1年生から6年生まで20人ぐらいで遊ぶ時間があるんだ。」
こう「でも本当は、僕はいつもサッカーをしたいのに、6年生が鬼ごっこやりたいと言ったら、4年生の意見は通らなくて、6年生の意見ばっかり通ってしまうんだよね。」
T「なるほど、それは大変だね。毎回ではなくても、時々はサッカーやりたいよね。」
りん「算数にも、そうやって年上の人の言うこと