
イランで生まれてインドで広がった「パン」の物語を巡る
インド料理といえば、スパイシーなカレーとふっくらと焼き上げられたナンが定番の組み合わせ。しかし、インドのパンの世界は、ナンだけでは語れないほど奥深く、多種多様な魅力が詰まっている。今回は、そんなインドのパンに焦点を当て、その特徴やインド人にとっての位置付け、そして日本での受け入れられ方などについて書こうと思う。その前にまず、物語のプロローグとして、ローマ帝国のパン文化から。

ローマ帝国のパン文化:食卓を彩り、帝国を支えた多様なパン
ローマ帝国は、壮大な建築物や哲学、そして華やかな食文化で知られる文明だ。その食文化において、パンは重要な役割だった。現在でも、パンといえばヨーロッパのイメージが浮かぶことも多いだろう。イタリア人にとって欠かせないパン文化は、実はローマ帝国から続いている。当時あったものは形も味も今とそこまで変わらず、現代のパンに非常に近いのだ。
パンを焼く技術はどこで生まれたのか。それは、イタリア半島に渡ったギリシャ人によってローマ人に伝えられたと言われている。ローマ帝国は、このパン作り技術をさらに発展させて、帝国の拡大とともにパン文化も広がっていった。後に中世に入ると「小麦は最も重要な食材」という言葉が生まれたが、その遥か以前からパンはローマ人の食生活の中心であり、帝国の繁栄を支える重要な食料だった。
ローマ人たちは、すでに発酵パンと無発酵パンの両方を作り分けていて、小麦だけでなく大麦やライ麦、さらには他の雑穀を使ったパンも楽しんでいたようだ。パンの種類の豊富さは、当時のローマの食文化がいかに洗練されていたかを物語っている。
しかし、パンがローマに伝わる以前、人々は穀物を粉にして粥のようにして食べていた。それは、あまり美味しいものではなかったようだ。「ただ生きるために食べるのではなく、せっかく食べるなら美味しく食べたい」。こうしてパン文化は根付いていった。当時のローマ人にとって、パンは単なる食料以上の存在だったのだ。
ナンの発祥はまさかの紀元前3200年頃!?
「すべての道はローマに通ず」という有名なフレーズがある。ローマが物事の始まりとして中心的な役割を持つことを指す言葉だが、しかし、ナンはこの限りではない。なんと、ナンの発祥は紀元前3200年のメソポタミア文明の頃だと言われている。しかも、インドではなくイランでペルシャ料理として生まれた。そこから東方のインドに渡り、現在に至るまでの文化が広がったそうだ。ローマ帝国の建国が紀元前750年あたりであったことを考えると、ナンにはヨーロッパのパン以上にずっと深い歴史があることが分かる。
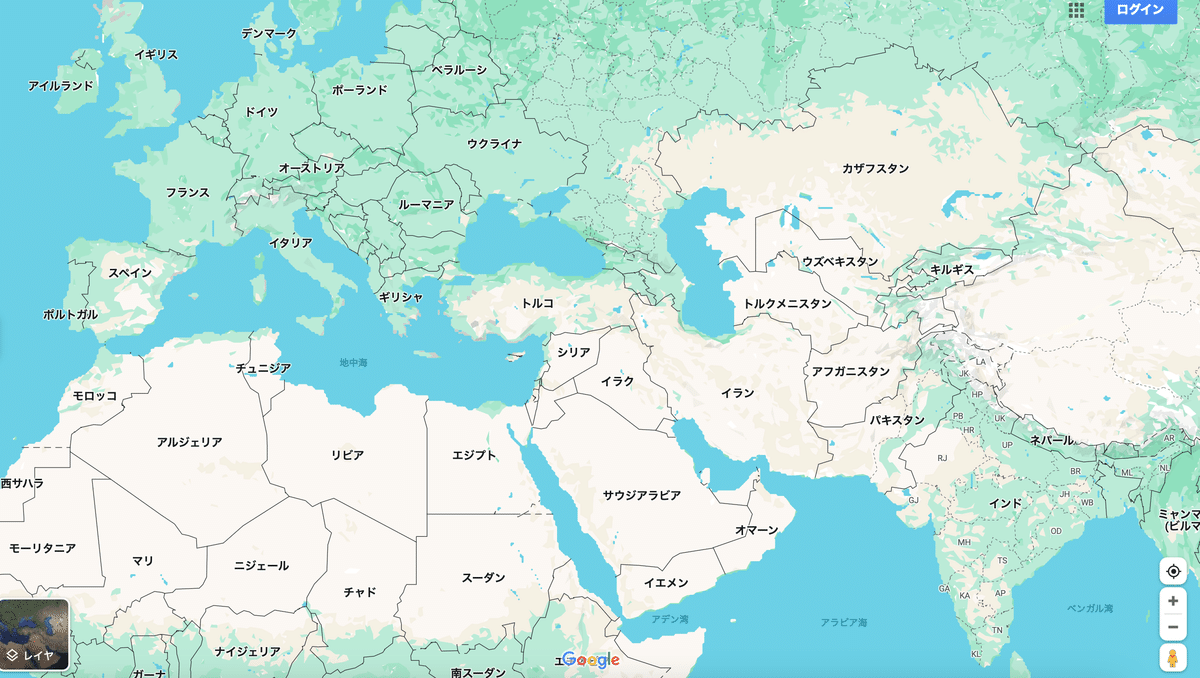
そして現在、ナン以外にも種類が豊富で、様々な調理法や食べ方が見られるのがインドのパン文化だ。一見すると似たような形のものが多いが、調理法や味わいはとても多彩でイタリアに負けない魅力がある。
インドの代表的なパンの種類
ナン:精白した小麦粉にミルクや卵を加えて発酵させた生地をタンドール窯で焼いた柔らかなパン。

チャパティ:全粒粉を水で練った生地を薄く伸ばし、鉄板で焼いた無発酵のパン。
ロティ:チャパティと同様の無発酵生地をタンドール窯で焼いたもので、タンドールロティとも呼ばれる。もともと「ロティ」=「パン」のような意味。
バトゥーラ:発酵させた小麦粉の生地を油で揚げたパン。
プーリ:全粒粉の生地を油で揚げた小さな揚げパン。
パラタ:全粒粉の生地を薄く伸ばし、バターやギーを折り込みながら焼いたレイヤー状のパン。具入りもバリエーションが多い。
クルチャ:発酵生地をタンドール窯やフライパンで焼いたパン。ナンと区別して具入りのものを指すことが多い。
ドーサ:米粉とレンズ豆を発酵させた生地を薄く焼いた南インドのクレープ状のパン。
アッパム:米粉とココナッツミルクを発酵させて焼く。パンケーキ状の南インドのパン。
イドゥリ:米とレンズ豆の発酵生地を専用の型で蒸して作る南インドの蒸しパン。
代表的なものだけでも、これほど種類があるのは驚きだ。パラタやクルチャは中に詰める具材によってバリエーションがかなり豊富にあるし、ナンも表面のトッピングや生地の練り込みによって種類が広がる。世界中で数千種類もあると言われるパンだけど、インドだけを見てもかなりの数になるだろう。
インド料理の日常と様々な食べ方
ここからは、インドの主なパンについて、その特徴や魅力などをさらに深く見ていこう。
ナン:タンドール文化の象徴
ナンは、タンドールと呼ばれる高温の土窯で焼き上げることで、外はカリッと中はふっくらとした独特の食感が生まれる。日本では、バターを塗ったりガーリックをトッピングしたり、チーズが入ったりしたものが定番だが、インドではもっとバリエーションが多い。

店によって大きさも形もまちまちだ
金沢市せせらぎ通りにあるインド料理店「アシルワード」のレシピでは、ミルク、玉子、砂糖などを使用。「バターチキン」や「ダールマカニ(乳製品をたっぷりと使った豆のカレー)」といった、こってりとしたカレーに特によく合うように作られている。表面のトッピングや詰め物の食材、生地に練り込む具材を変えることで多様なアレンジができるのも、ナンの大きな魅力と言えるだろう。
インドの人たちにとっての位置付けを見ると、特に北インドではナンは特別な存在だ。家庭の食卓から離れた非日常の食事やレストランでは、家族や友人が集まる場を彩る一品として楽しまれる。単なる食べ物にとどまらず、インドのタンドール文化や歴史を象徴する存在とも言える。
チャパティ:素朴な味わいで日常の食卓に欠かせない存在
油を含まない全粒粉の生地。薄く伸ばした生地を「タワ」と呼ばれる鉄板に乗せ、ゆっくりと両面を焼く。アシルワードでは、そこからさらに仕上げで直火にかけて、全体がふっくらと膨らんだ状態に仕上げる。日常の主食としてインドで広く人気があり、ナンと比較するとよりヘルシーで、日常的に食される。

インドの家庭では、母親が手作りしたチャパティを食べる光景は、ごく一般的なものだそう。チャパティはシンプルだからこそ、様々な料理に合わせることができる。カレーはもちろん、野菜の炒め物やスープ状の料理にもとても合う。どんな料理と合わせても楽しめるが、こってりとした料理よりはどちらかと言えば軽めの料理と相性が良い。
ロティ(タンドールロティ):チャパティとナンの隙間に存在している
チャパティと同じ全粒粉の生地をタンドール窯で焼き上げたもの。チャパティと比べると、より香ばしさや小麦の力強い味わいを感じられる仕上がりになり、同時に、ナンよりもヘルシーな主食になる。アシルワードのインド人シェフたちの日々の主食がこれ(理由はヘルシーさと、チャパティよりも短時間で調理できること)。

プーリ
全粒粉生地の揚げパン。小さめのサイズで作られることが多く、軽い食感に仕上がることから、朝食や軽食のシーンで人気で、縁起の良い食べ物として特別な食事や祝いの席でも供される。
バトゥーラ
小麦粉生地の揚げパン。プーリーよりも大きめのサイズで作られることが多く、食べ応えのあるしっかりとした食感に仕上がる。チャナマサラ(ひよこ豆)と一緒に食べるのがインド全土で一般的。

パラタ
全粒粉の生地を、バターやインドの精製バターであるギーなどの油をたっぷりと使いながらレイヤー状に仕立てて、それを「タワ(鉄板)」で焼いたもの。油分を多く含む生地がレイヤー状になっているため、仕上がりはクロワッサンのようにサクサクとした食感になる。

様々なカレーと合わせて食べられるプレーンのパラタのほか、中に詰め物をしたパラタもインドでは定番で人気が高い。アシルワードのシェフたちが好きなのは、スパイスで味付けしたじゃが芋(マッシュポテト)を詰めたアルパラタで、シェフたちの故郷(北インド・ビハール州)では、朝食としてヨーグルトと一緒に食べるのが一般的だそう。仕込みにかなりの時間を要するため、アシルワードではパラタは特別メニューとしてのみ過去に何度か提供してきた。

クルチャ:多彩なアレンジ、飽きさせない魅力
クルチャは、インドの北部、特にパンジャーブ地方の代表的なパン。小麦粉にヨーグルト、砂糖、塩、ベーキングパウダーを混ぜた生地が一般的で、タンドール窯で焼かれることが多い。プレーンのクルチャだけでなく、チーズ(カッテージチーズ)やじゃが芋、カリフラワー、ほうれん草を包んだものなど様々な種類がある。インドのパンの中でも特にアレンジが自由な食べ物で、地域や家庭によって様々な種類が存在し、人々の食の好みを反映している。具材の入ったものは、手軽に食べられるストリートフードとしても人気。

日本で愛されるインドのパン
日本では近年、インド料理店が全国で増えたおかげで、ナン以外にチャパティやプーリーなども少しずつ知られるようになってきた。とはいえ、定番のカレーとの組み合わせとして多くの人々に愛されているナンと比べれば、それ以外のパンはまだまだメジャーではない。
圧倒的な一番人気のナンについて言えば、口に入れた時にまず感じるのは、その風味の豊かさだろう。独特の食感も美味しさのポイントで、スパイスの香り豊かなカレーとの相乗効果で食欲が刺激される。しかし、一方で、一緒に食べるカレーによってはナンが少し油っこく感じられることもあるかもしれない。

そんなふうに感じるようになった時は、この記事で紹介したインドのパンの多様性や奥深さを思い出してほしい。チャパティやロティにはナンには異なる魅力があるし、何よりインドの人々の生活に深く根ざしているものだ。インド料理がますます身近になっている日本でも、きっとナン以外のパンもより多くの人々に愛されるようになるだろう。

インドのパンを種類豊富に楽しむことは、僕にとっては単なる食事にとどまらず、インドの雄大な歴史や文化に触れることでもある。皆さんもぜひお気に入りのお店を見つけて、様々な種類のインドのパンを味わってみてはいかがだろうか。
いいなと思ったら応援しよう!

