
フリーランスから起業したデザイナーが50本のnoteを書いて得たこと、実践した5つのこと
皆さんこんにちは。Maslowの安達です。
今月noteアカウントをリニューアルし、これまで私が個人で運用していたものを正式に会社として運用する方針となりました。
そこでこれまでの振り返りをする良い機会だと思い、フリーランスから起業してこれまで50本のnoteを書くまでに、どんな意識や工夫をしてきたのか、具体的な方法や実績含めて、5つにまとめてみました。
誰向けに何を伝えたい記事?
これからnoteでの発信を検討されているクリエイターやフリーランスがこれを読み終わった後に「自分もnote始めるか〜!」とちょっぴりモチベーションが上がってくれたら嬉しいです。

・20人の業務委託メンバーの採用
・13件のプロジェクト受注
・37.6万の全体ビュー数達成
・4200人のnoteフォロワー
・合計8700以上のスキ
・noteに貼っている会社紹介資料の閲覧数合計が9万回再生
結論
自分が欲しいものを書く
具体的に書く
読みやすくデザインする
意外性を盛り込む
楽しみながら書く
1. 自分が欲しいものを書く

「自分が読みたいな」とか「これあったらいいな」と思う記事をなるべく書くようにしました。
結果として、自分が本当に欲しいと思って書いた記事は多くの方に引用リツイートされたり、note公式マガジンにも取り上げてもらえました。
反対になんとなくこれ需要ありそうと思って書いた記事はほぼ読まれませんでした…
また自分が欲しいものなので、内発的モチベーションが働き、記事の更新も苦にならず継続できました。
何をやったか?
インターンを募集するも10人中1人しかポートフォリオを用意してくれなく、聞いてみると「そもそもポートフォリオの作り方が分からない」という声が多かったため、ポートフォリオの必要性と作り方について網羅できるように、良記事をまとめました。
これは結果的に多くの方に見てもらえ、採用にも貢献できました。
▼このnoteきっかけで会社のことを知ってくれ、チームに加わったメンバーがいる
noteで上手く発信するための5つのヒント
過去の自分に読ませてあげたい記事を書く
自分がこれ振り返りたいなと思うテーマを書く
自分がインプットしたいなと思う記事をまとめる
言語化して再現性を持たせたいなと思うテーマを書く
いつも人から聞かれる質問に「これ送ればOK」という内容を書く
2. 具体的に書く

なるべく読者の方が具体的なイメージがしやすいように、数字やそこに至るまでに具体的にどんなアクションをしてきたのか?などをなるべく盛り込むよう意識しました。本記事もかなり具体的に書くように意識しています。
何をやったか?
デザイナーとして成長するためにやってきたこと、月収100万になるまでにやってきたこと、デザイナーから経営者になるためにやってきたことをかなり具体的に書きました。
これは成果を出すために具体的にどんなことをやってきたのか?HOWの部分を知りたいニーズが多いからなのではと思います。
noteで上手く発信するための5つのヒント
読者が一番知りたい部分を数値化して書く
文字だけでなく写真やイメージ図、グラフを盛り込む
実際の画面をスクショして貼る
結果だけでなくその過程やHOWを細かく言語化する
タイトルには数字を入れ具体的に書く
3. 読みやすくデザインする
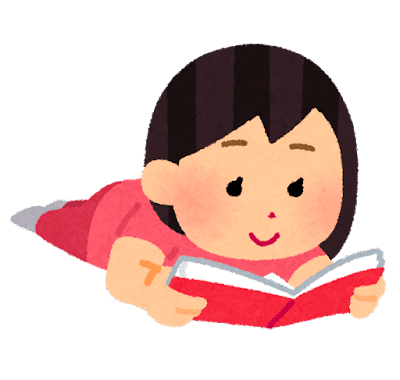
自分が思っている以上にユーザーは文字を読んでくれません。
自分がnoteを読むときも基本、タイトルや太字だけを無意識で目で追ってませんか?ただ良い記事を書くだけでなく、無駄な情報を削ぎ落としたり、文字に強弱をつけてメリハリをつけたり、図やグラフを入れるなどしてとにかくユーザーが読みやすいような工夫をしました。
何をやったか?
ただnoteをまとめるだけでなく、読者が読みやすいようにテーマごとにカテゴライズしました。
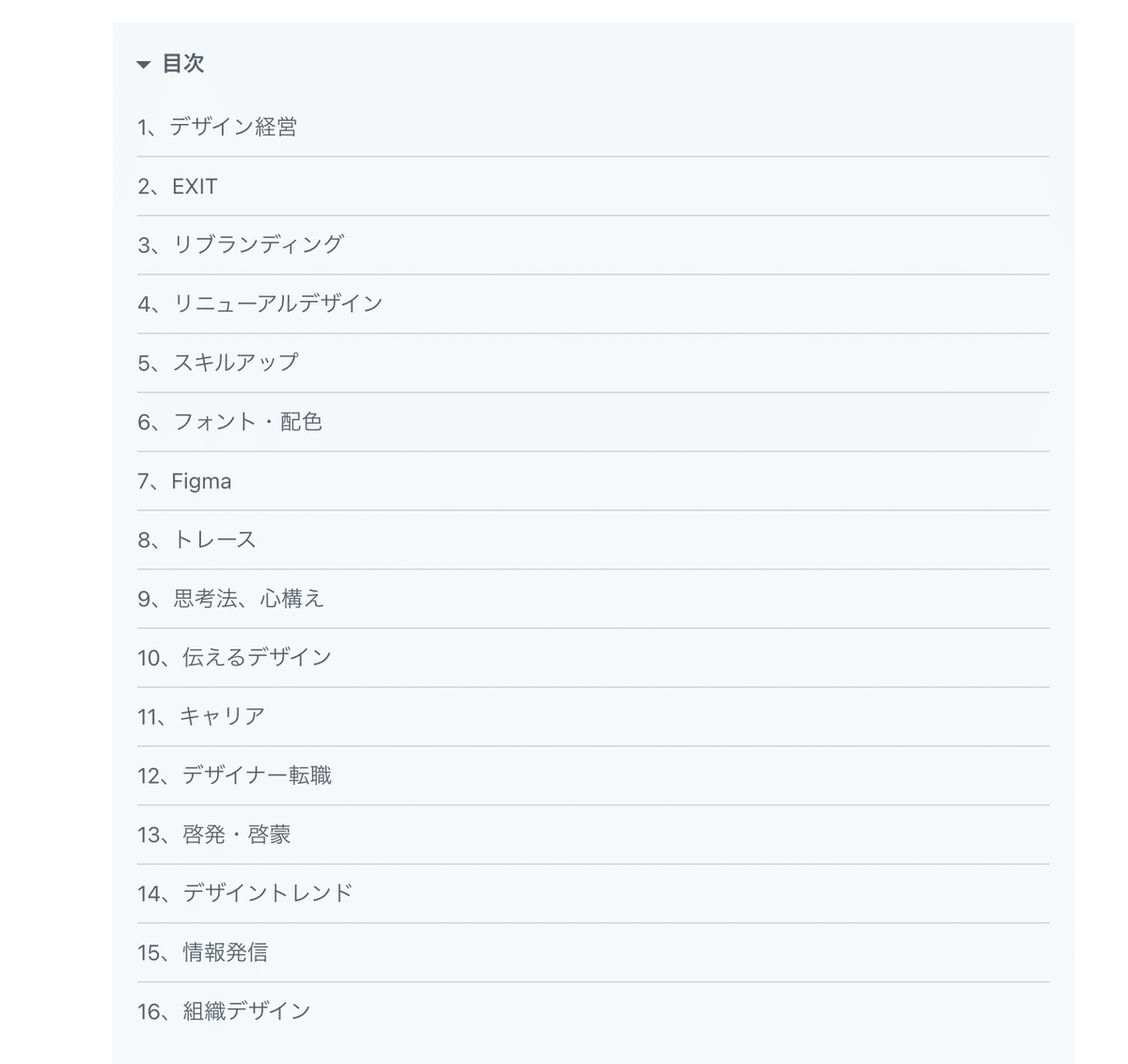
また引用したnoteに飛ばずとも、伝えたい結論や要点がパッとみて分かるように、特に重要だと思った文章を抜粋する工夫をしました。

noteで上手く発信するための5つのヒント
結論から書き、要点は端的にまとめる
目次をつけて、記事まとめはテーマごとにカテゴライズする
グラフやイラストにして直感的に分かりやすく工夫する
重要な箇所は太字にして文章にメリハリをつける
大胆に文章を削ぎ落とす
4. 意外性を盛り込む

ただ有益で具体的な内容を書くだけでなく「意外性」や「新規性」ある要素を盛り込むことで、期待値を超える工夫をしました。
何をやったか?
今でこそ当たり前ですが、2019年当時「noteのキュレーションをする」という使い方は比較的新しかったんじゃないかなと思います。
良いコンテンツが溢れている時代だからこそ「本当に良いコンテンツをサクッと手軽にインプットしたい」というニーズを捉えられたと思います。


また普通は10選ぐらいのところを100選まで思い切って書くことで、ユーザーの予想を超える意外性を生み出しました。
ちなみにこの記事は「車輪の再発明」を無くしたいと思ったことがきっかけで書いた記事なので「自分が欲しいものを書く」にも通じます。
noteで上手く発信するための5つのヒント
バズっている記事を切り口を変えて書いてみる
一次情報を書く
人に話しづらい内容をあえて書く
一般論とは逆説的な内容をロジック持って書く
自分が「意外!」と思ったことをまとめる
5. 楽しんで書く

バズったnoteを振り返るとその全てが楽しんで書いてたなと思います。一方で「書かなきゃ」とか「発信しないと」と義務感持って書いた記事は全く成果が上がってません。これはとても面白い事実だと思います。
noteで上手く発信するための5つのヒント
自分のためじゃなく「人のため」に書く
自分が得意なテーマを一貫して書く
自分の強みを活かした内容をかく
引用してくれた方に感謝のリプライ&コメントをする
noteからくる通知をSNSにシェアして大げさに喜ぶ
楽しむやつが最強
ここまで50本のnoteを書くまでにやってきたことを書いてきましたが、やっぱりなんだかんだ楽しむことが大事なんではないでしょうか。ぜひ「ヒント」を参考にnoteにトライしてみてください。

最後までご覧いただきありがとうございました。
このnoteをフォローしていただくことで、これからフリーランスを目指している方や現役デザイナーの方、起業家の方などにとって、価値ある有益情報を受け取ることができます。
▼今後執筆予定の記事
・3年間デザイン会社を経営してみて、学んだ5つのこと
・ある経営者の1週間の過ごし方
・Twitterでバズってる、デザイナー超有益情報まとめ
・2022年が終わるまでにデザイナーが絶対に読むべきnote20選…
▼フォローして定期的に有益情報を受け取る
記事を書いた人
安達 卓則(あっくん | Maslow)
Maslow株式会社 代表取締役CEO兼CDO。株式会社Branding EngineerにてtoB営業を経験。その後、株式会社Spaceeで営業、カスタマーサポートを通してUI/UXの重要性を認識し、広告代理店にWebデザイナーとして転職。Web制作の上流から下流まで全てを経験。2018年、自身が天職を見つけ、自己実現した原体験から、人の持つ潜在能力を開花させるため、Maslow株式会社を創業。
さいごに
このnoteを運営するMaslowは企業の潜在価値を引き出すコーチングデザインカンパニーです。
デザインとコーチングで、企業が本来持っている価値や魅力を最大化させ、中長期的なブランディングを作っていくための支援を、ベンチャーから上場企業まで幅広いお客様に提供しております。

