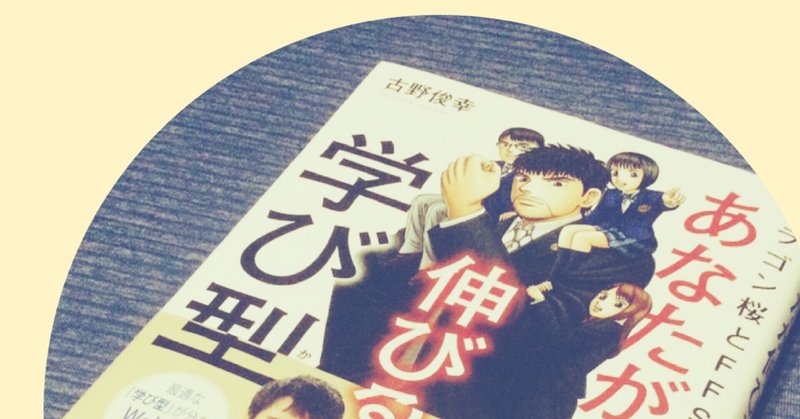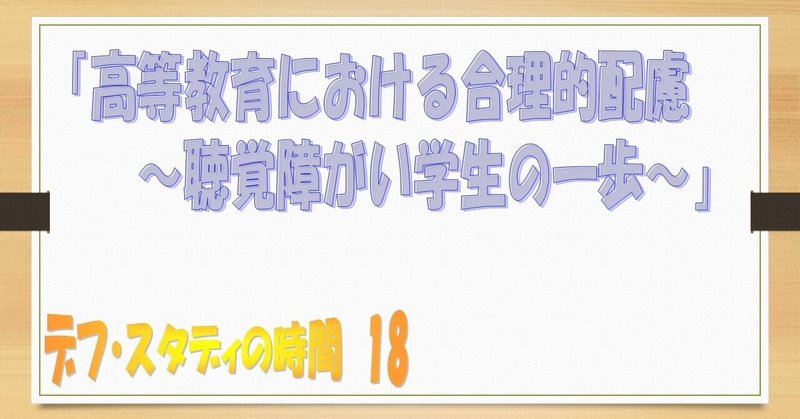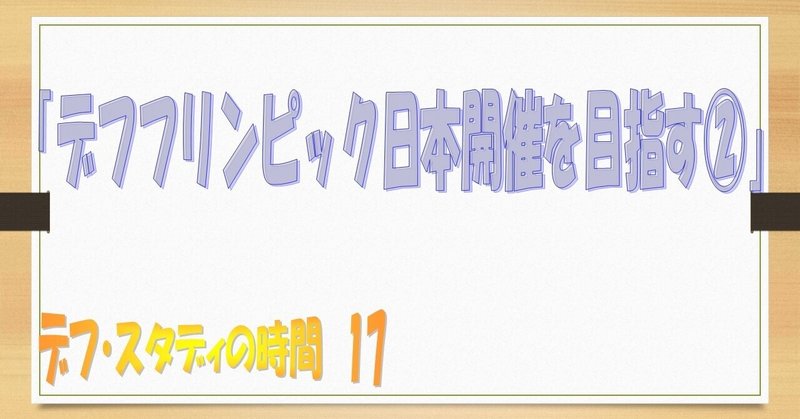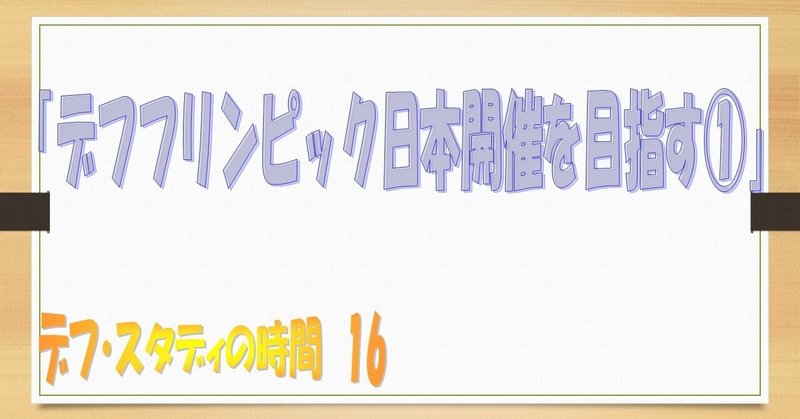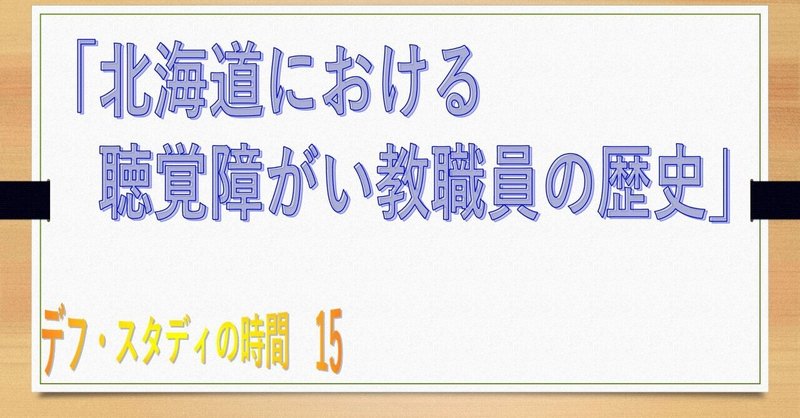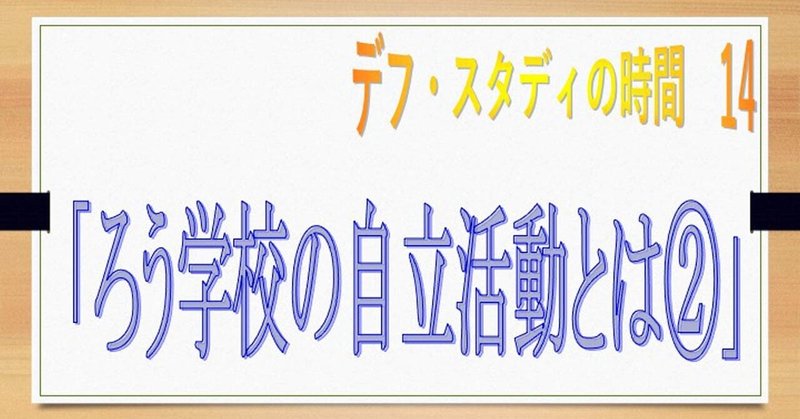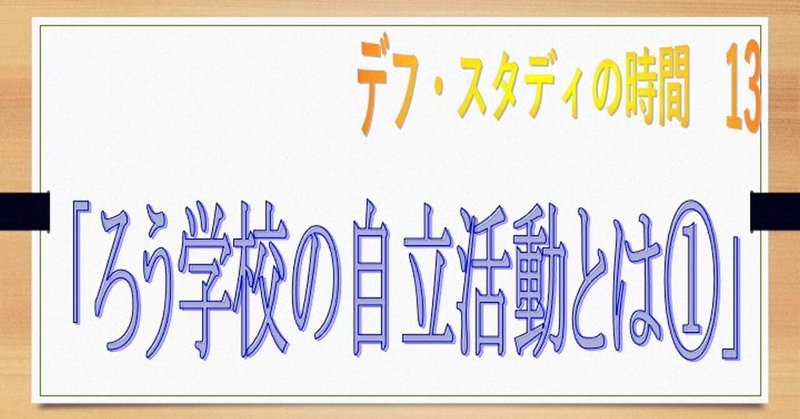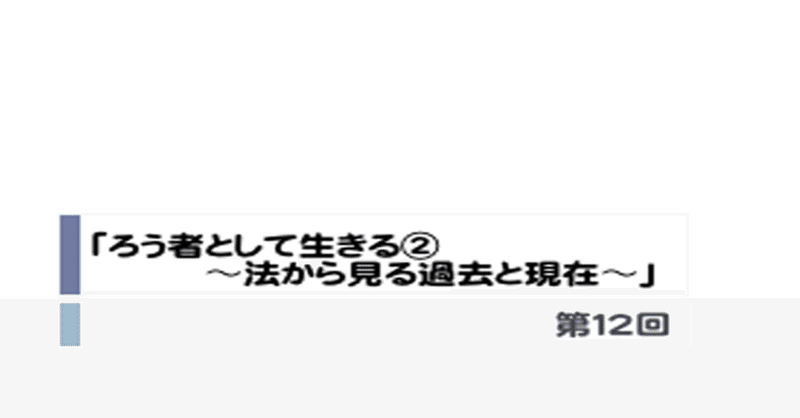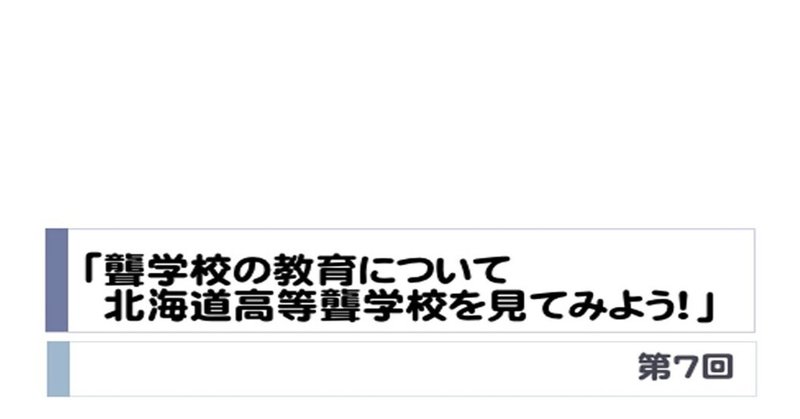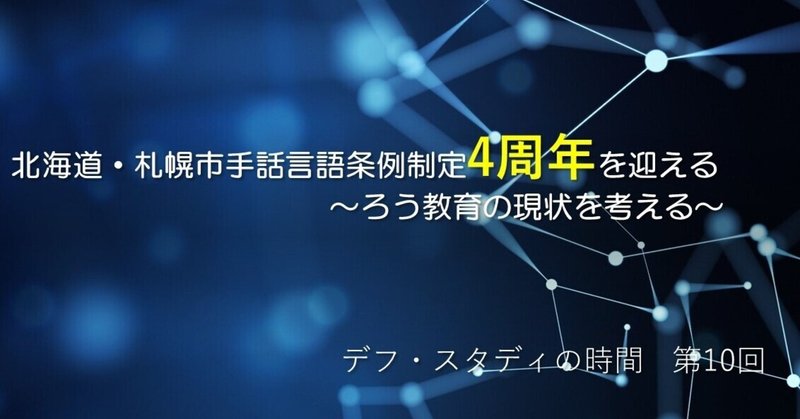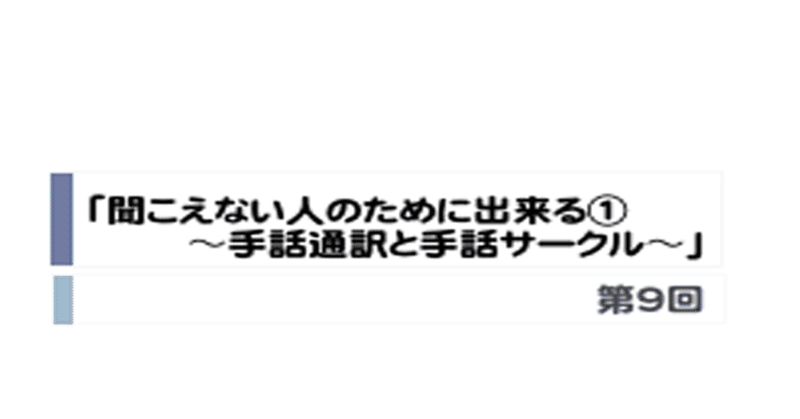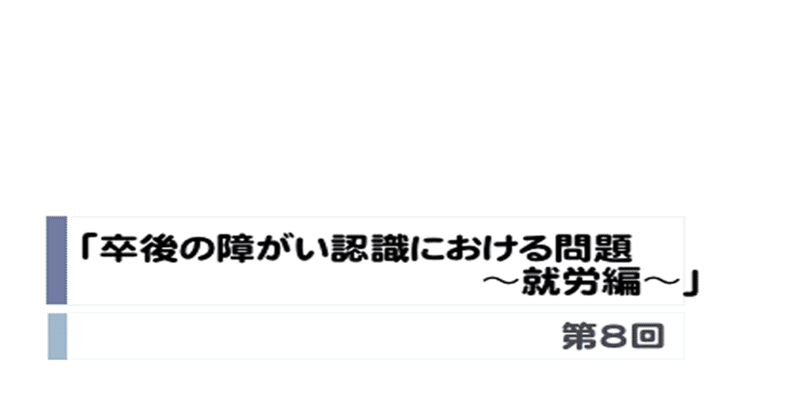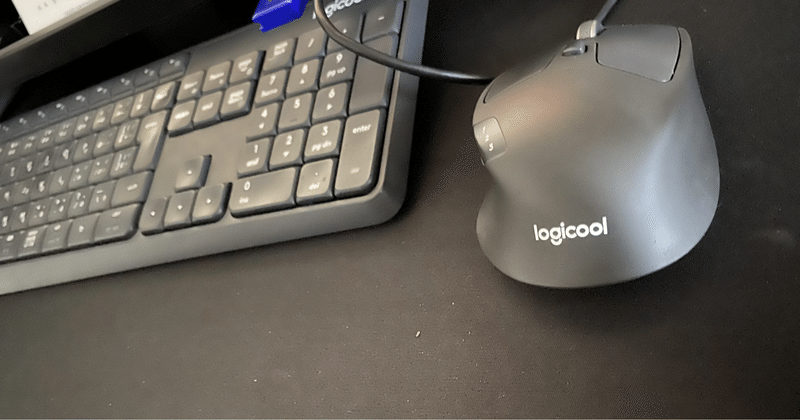
- 運営しているクリエイター
記事一覧
当たり前だと思わないで!
実に高等教育機関に進学する聴覚障がい学生は年々、増加する傾向にある。私が大学時代から分析しても増えているしそれだけではない。教育を受けることで必要な合理的配慮における環境整備も変化していることが伺える。以前だったら、「大学進学って厳しい。」「お前に大学は無理だ」という一方的な否定感という思考がもはや「大学に行ったほうがいい。」「大学でも頑張れることはある。」というように当たり前に変わり、きこえる学
もっとみるデフリンピックについて①
現在、東京オリンピック・パラリンピックが開催される方向でコロナ対策についての審議が行われている。国民の関心は、新型コロナ感染の怖さで意見が真っ二つになっており、招致決定当時の関心度より下がって今は中止するべきであるという声が高まっている。私は、どちらかでいうと中立である。
新型コロナ感染対応をしっかりする上で、無事選手のモチベーションを高く望んでもらいたい。と同時に子どもたちへの夢を与えたり世
聴覚障がい教職員の存在
久し振りに配信するデフ・スタディの時間シリーズ第15回目に触れておく。YouTube動画「北海道における聴覚障がい教職員の歴史」をぜひ視聴して頂ければ幸いである。その上で、今勤務しているきこえない先生方の人数は昔と比べて増加している傾向にあるが実は残念ながら厳しい環境に置かれていることは改善しておらず。転職、または自主退職するなど教職から辞めていくという苦しい気持ちを抱えている方も数人いることを知
もっとみる自立活動について考えた理由
なぜこの時期にこの動画を作って配信しようとしたのか。皆さん、疑問に思うことでしょう。その疑問に素直に伝える機会になればと思い、書きます。実は、ろう学校の教育では一番大事な魅力というのは、「自立活動」という教育課程でどのように取り組むかによってこれが、学校全体の客観的評価になると考えるわけです。
しかしながら残念なことに厳しく現状を伝えておきますと、この自立活動の取り組みを勘違いした学びで満足し
わが指のオーケストラ
この動画で最も見て欲しいのは、「わが指のオーケストラ」という作品で挙げられている内容である。きこえないことを知る上ではもっとも分かりやすいし、面白い物語として楽しめる漫画があることを紹介したい。
きこえない人の歴史を知るというのは、長い日本語で書かれる文庫みたいな書籍が多くあるがこれを読んでいくことは苦手な方が多いだろう。歴史が好きとか、読書が好きでないとあまり関心が少ないかもしれない。でもこ
ろう学校とはどういう場所?
乳幼児から高校卒業までの18年間、学んだのは「ろう学校」である。聞こえる人が通う普通学校での選択も必要だと考えたこともあったが結局ろう学校育ちで、学齢期が終わったのである。卒業式が終わった今頃は、必ず学年末テストが控える時期であり、この期間が私にとっては嫌いな時間だったことを覚えている。
私だけではなく、卒業生の多くは同じ気持ちだろう。そりゃ無理もない笑!一緒に学び、語ったり部活動で汗を流した
声代わりの手話言語に想うこと
目が見えない障がい者や肢体不自由で車椅子の生活をする障がい者など、障がい者のほとんどは普通の人と同じ、聴覚はもっているわけである。そのため、音を聞いたり音を発することで日常生活上では概ね問題がなく、生活できるということがある。
しかし聴覚をもっていない、もしくは著しく困難な課題があるという障がい者。ここでは聴覚障がい者と一括りで表現する。この聴覚障がい者が日常生活をする上で考えなければならない
きこえない苦労をプラスに変える
ここで挙げる動画(第8回「卒後の障がい認識における問題〜就労編〜」)内は、私が非常にとても重要と位置付けているテーマの一つである。卒業が控えている3年生だけではなく、2年生の後輩たちにとっても改めて社会に出ることのキャリア教育の内容として考えて頂きたいと思って取り扱ってみたのである。
ここで挙げる内容は、正直言って聾学校現場においては、授業に全く強く意識されていない。大人の都合によって、生徒