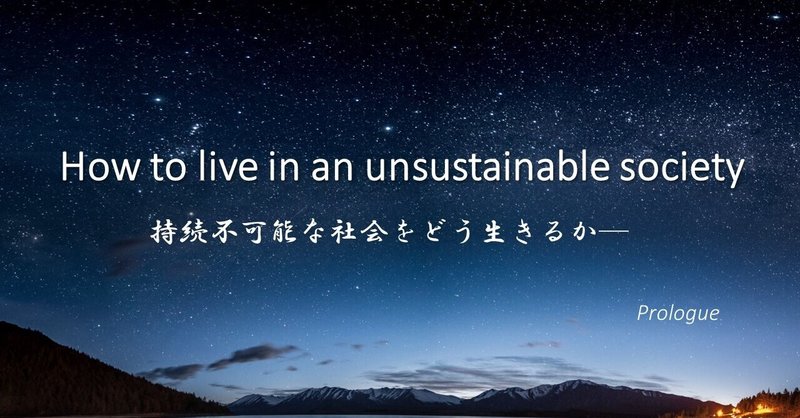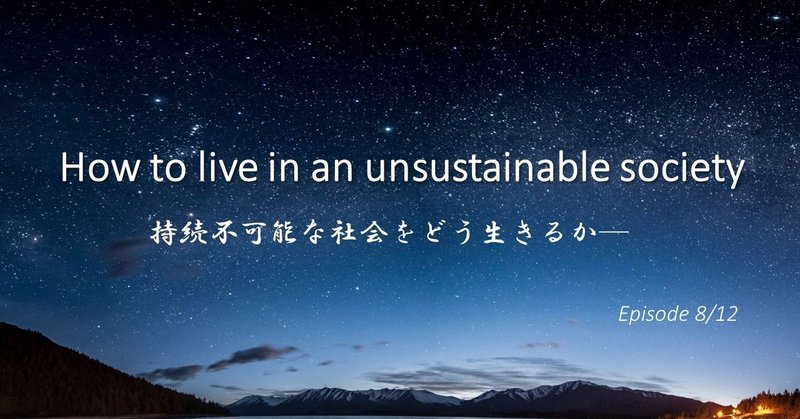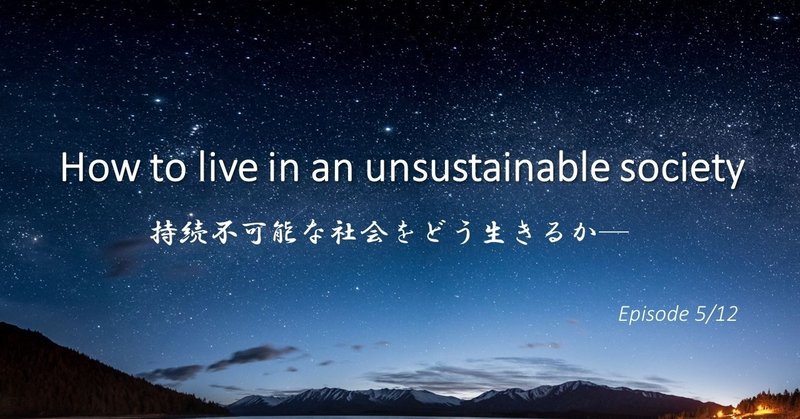「地球はすでに限界を超えている」と叫ばれる中、私たち日本人の意識や社会は驚くほど変わっていない。なぜ意識が変わらないのか、社会はどんな姿を目指すべきなのかについて、環境・経済・哲…
- 運営しているクリエイター
#共有地の悲劇
No.0|『持続不可能な社会をどう生きるか』を書いたワケ
Prologue1972年にローマクラブが『成長の限界』を発表しました。「地球の資源は有限であり、経済は無限に成長することはできない」、そう発表された50年経った後も、私達、特に日本人の意識は恐ろしいほどに楽観的で、関心を持とうとしません。
現在生態系はすさまじい速度で破壊されています。気候変動——最近は気候危機と呼ばれますが、将来の危機は過少化され、事なかれ主義のモラルハザードが起こっています
No.5|私たちはどうして行き過ぎてしまうのか?(暴走・衰弱のメカニズム)
私たちは"宿命的に"、悪い結果が予想できていてもなかなか行動を変えられない生き物である。
経済格差、財政問題、少子高齢化、地球環境問題・・・、様々な問題がクローズアップされている中でも意識が追い付いていない。問題は絶えず後送りされている。
なぜ行動を変えられないのか、その原因のいくつかをシステム的思考に基づいて紹介していきたい。
①競争原理が内在する暴走私たちは、競争を好意的に捉えている。競