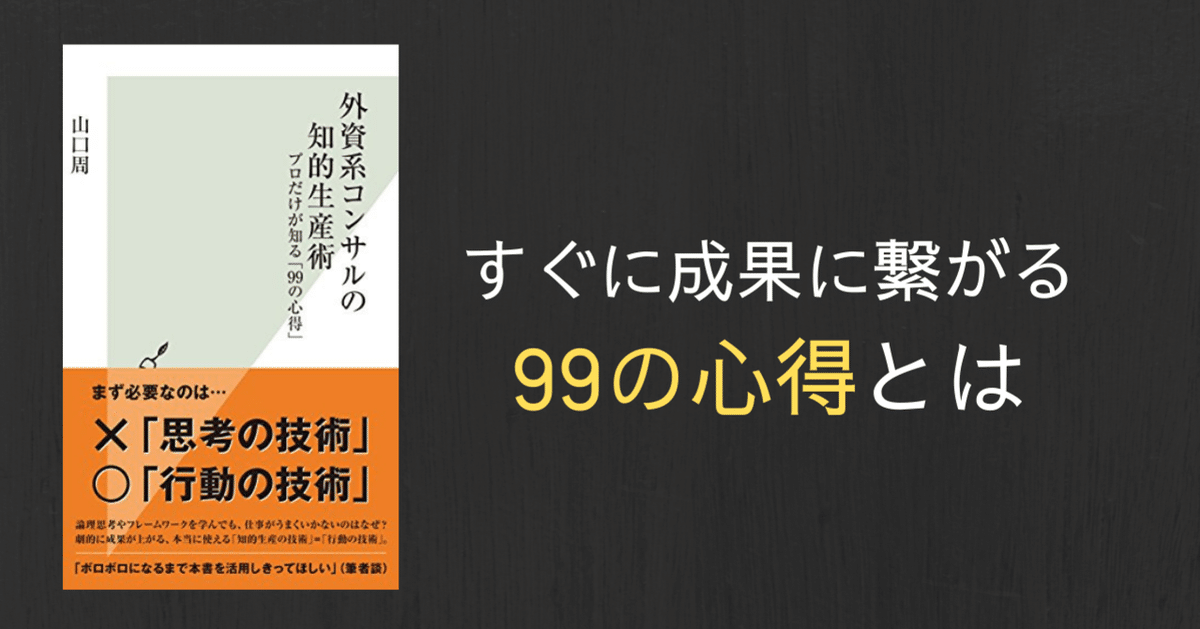
【本要約】外資系コンサルの知的生産術~プロだけが知る「99の心得」
本記事は『外資系コンサルの知的生産術~プロだけが知る「99の心得」』(山口周著・光文社)の要約・解説の記事です。本書では、ベストセラー作家である山口周氏が広告代理店、外資系コンサルの経験で培った「知的生産の心得」を99個紹介しています。アウトプットがクライアントや上司に響かない、良いアイデアが浮かばない、とお悩みの方におすすめの1冊です。
知的生産に必要なのは「思考の技術」ではなく「行動の技術」だ
知的生産性というのは、「思考の技術」そのものよりも、「情報をどう集めるのか」とか「集めた情報をどう処理するか」といった「行動の技術」、いわゆる「心得」によってこそ大きく左右されます。(中略)
どんなに地頭がよく、思考力に優れている人でも、「動き方」を知らなければ実社会で評価されるような知的生産物はまったくといっていいほど生み出せないということです。(本文より)
本記事の想定読者は、ホワイトカラーの仕事につくビジネスマンです。ビジネスマンは、何らかの知的生産物を生み出すことで経済的対価を得ています。
ここでいう「知的生産物」とは、情報を何かしらの知的な処理を行うことで、得られたアウトプットのことです。例えば、クライアントへの提案資料、上司への報告資料、新しい事業企画などが知的生産物にあたります。良い知的生産ができる人はそれだけ市場価値も高くなることは容易に想像できると思います。
そのため、世の中にある多くのビジネス書はこの「知的生産性」を高めるためのノウハウやスキルを提供するものがほとんどです。しかしながら、本を読んだ後は「なるほど、そういうことか!」となるのに、うまく仕事に活用できないと感じることが多いのではないかと思います。かくいう私も一時期ロジカルシンキング系の本を多読して、色々なフレームワークを覚えましたが、結局実際の仕事で活用できたことはわずかでした。
本書では、その原因を「行動の技術」すなわち「心得」が身についてないからと指摘します。どんなに調理方法を知っていても、実際にできるようになるわけではなく、作ることで動作が身につき、作れるようになるのと同じです。
本書では、「戦略」「インプット」「プロセッシング」「アウトプット」においてどのように行動すればいいのか、そのポイントについて解説してくれます。
何をどう行動すればいいのかという具体的な内容と、なぜそうすべきなのかという本質的な内容と両方を解説してくれるので、納得して飲み込めるはずです。
また、後半は中長期的に知的生産性を上げていくために、知的ストックの増やし方についても言及しており、合計99のポイントと盛りだくさんの内容です。
本記事では、本書で解説されている知的生産術の中から「戦略」「インプット」に絞り、重要だと思ったポイントをピックアップして紹介します。
戦略:知的生産とはマーケティングだ
意外に思われるかもしれませんが、情報収集はもっとずっと後回しで構わないのです。では、何をやるべきなのか?
答えは「知的生産の戦略策定」ということになります。どのような知的生産物を生み出せば、この局面で勝てるのか?という点についての見通しをつける。ここが、知的生産全体の成否を分ける前半での大事なポイントになってきます。(引用)
例えば、上司から来期の戦略について資料をまとめてほしいという依頼があったとしましょう。多くの人がとりあえず、今の市場について他社の状況などを調査するところから始めるのではないでしょうか。しかし、本書では情報収集の前に戦略を立てることをファーストステップとしています。
「どんなアウトプットを出せば、最も成果に繋がるのか」
この問いに向き合うことが知的生産の成否を分ける重要なポイントです。
では、どのように戦略を立てればいいのか?
ポイントは「マーケティング的に考える」ことです。
そもそも、ビジネスマンが生み出す知的生産物はある種の商品だと言えます。そこに経済的な価値があるから、サラリーマンであれば給与を貰えるし、フリーランスとかであれば、対価を得ることができるわけです。つまり、知的生産を生み出すということは広義の意味でのマーケティング活動なのだと本書では指摘します。
では、マーケティングで重要なことは何でしょうか。
マーケティングで重要なのは「どうやって他のものと差別化するか」です。
そして、ここでポイントなのが、差別化とは競合との差別化だけでなく、「顧客がすでに持っている知識との差別化」が含まれている点です。
顧客とは、社外の人だけではなく、社内の人間も含まれます。それは上司かもしれないし、管理部から見たときの営業部かもしれません。
アウトプットする相手は具体的に誰なのか(ターゲットを明確化する)
現状どんな知識を持っていて、何を知らないのか(顧客を知る)
知らない中から何をアウトプットすれば価値を生み出せるのか(差別化する)
これらの問いを考えられているかどうかで、どんな情報を集めればいいのか、どのようにその情報を加工すればいいのか、どのような形でアウトプットすればいいのかの方向性が決まります。
インプット:情報収集すべき価値ある情報とは
知的生産の顧客ターゲットが決まり、どのようなアウトプットを出さないといけないか方向性が決まったら、次にやることは情報収集です。
ポイントとなるのが、どのような情報ソースを用いて答えを出すのか大まかな「あたり」をつけておくことです。
そうすることで手当たり次第に調べたりするような非効率を避けることができるのと、色々調べてもアウトプットが定まらない際にどの情報に手をつけていないかが判断できるようになります。
また、本書では情報ソースは幅広に想定して、多面的に情報を集めることが推奨されています。特に求められているアウトプットのうち、そもそも情報を取ることが難しそうなものに関しては、一つの情報リソースに頼るのではなく、初めから二の矢、三の矢までを想定しておくべきでしょう。
では、ホワイトカラーが活用できる情報ソースはどのようなものがあるか?
筆者は大別すると以下の4つのどれかに全て含まれるといいます。

これら4つの情報ソースを、求められるアウトプットに向けて活用します。
本書ではこの中でも特に「社外関係者へのインタビュー」は注意を払うべきとし、インタビュー時のポイントが詳細に解説されていますが、ここではポイントだけ羅列しておきます。
①他者が絡むところは情報収集に最も時間がかかるため、真っ先にやる
②「これだけははっきりさせたい」という問いを明確にしておく
③予めアウトプットのイメージ(スライドやレポート文章など)を持つ
④質問はできる限り具体化する
⑤質問は紙に落とす
⑥分かったふりをせず、疑問や腑に落ちない点は明らかにする
⑦用意してきた質問だけに捉われない
ここまで、情報収集のやり方を見てきましたが、色々と調べても顧客をハッとさせられるような情報が見当たらない場合はどうすればよいのでしょうか。
本書では「一次情報」の重要性を強調しています。一次情報とは、記事や書籍等の「人手を介した情報」ではない情報です。例えば、現場を観察して得られた情報や当事者に直接インタビューして得られた情報などが一次情報にあたります。
そもそも、知的生産においてインパクトのある成果物を生み出すためには大きく2つアプローチがあると本書では解説されています。
一つは、相手が知らないような一次情報を集めて情報の非対称性を生み出すというアプローチです。(中略)
もう一つは、顧客がすでに知っているニ次情報を高度に組み合わせて情報処理し、インサイト=洞察を生み出すというアプローチです。(引用)
このうち後者の二次情報を処理する方法は高度なプロセッシングが必要となるため、スキルや経験が必要です。一方、一次情報を集める方法は、仮に情報処理が拙くても情報そのものの価値が高いため、経験が浅くても、インパクトのある知的アウトプットを生み出すことができます。
このように、一次情報を得ることが良い知的生産を生み出す鍵になります。
一次情報の詳しい収集方法については本書を確認してもらうとして、最後にインプットにおける心構えを紹介したいと思います。
情報収集の成否は「腰の軽さ」で勝負が決まるという側面があります。「腰が軽い」というのは「まず行ってみる」「まず聞いてみる」という態度で、取れる情報をどんどん取りにいくという行動様式のことです。(中略)
結局のところ、集められる情報の質と量というのは、運動量で決まるからです。
本書冒頭でも述べられていたとおり、知的生産において重要なのは行動です。どうしても知的生産と聞くと、我々はその言葉に引っ張られて、何か机の上で全て完結するようなイメージを持ちますが、むしろその逆で動き回ることが求められます。
この点は以前に紹介した「AI分析でわかった トップ5%社員の習慣」でも述べられており、できるビジネスマンは基本席におらず、動き回っているという点が特徴として紹介されていました。
自分があまり思った成果を出せていない、求められているアウトプットが出せていない時は、机の前で悶々とするのではなく、自身の行動量はどうなのかを見つめ直すべきでしょう。
まとめ
今回は知的生産を高める実用書『外資系コンサルの知的生産術~プロだけが知る「99の心得」』について要約、解説して参りました。
この本でも指摘されている通り、自身のスキルやアウトプットを変えるためには、行動することが重要です。「知る」と「できる」には大きな隔たりがあります。
この本も読んで満足だけではもったいなくて、実際に行動に移していくことで、目の前のことを変えていくことができます。本記事では99の心得のうち、厳選した内容だけを絞ってお伝えしましたが、解説したところ以外の内容も全て納得できるものばかりでした。また、どれも具体的な内容なので、読んで1つだけでも実践するだけでも日々のアウトプットを変えていくことができると思います。
すぐに使える実践書となりますので、ぜひご興味のある方は本書をご一読ください。
今回の記事は以上になります。
ご一読いただき、ありがとうございました。
