
匂いの無いオンラインの世界で、「香道」の魅力を伝える【イベント開催レポート】
臘梅の候、いかがお過ごしでしょうか。香人 / 香道研究家のmadokaです。
この記事では、去る2020年10月25日(日)夜にオンラインで開催した、香道イベント「知られざる香道具の魅力 〜伽羅の香りを聞く会・番外編〜」を振り返る開催レポートをお届けいたします。
実は本イベント、オンラインの映像で、和蝋燭の薄明かりの中で見る香道具の魅力を伝えるという「史上初」の試みでした。
「香道」とは?
香道とは、お香を美しい所作で焚き、その香りや場の雰囲気を楽しむ、日本の伝統な遊びの一種です。茶道や華道と共に、三大芸道と呼ばれる事もあります。
匂いの無い「オンライン香道イベント」開催の背景
コロナ禍に見舞われた2020年は、芸術文化の魅力を伝える活動に取り組む人にとって、大きな変化を余儀なくされた年でもありました。
香道では香りを嗅ぐことを「聞く」と表現しますが、この香道で行う「聞香(もんこう)」という遊びは、マスクを外さなければ、体験することができません。
新型コロナウイルスは解明が進みつつあるものの、まだまだ未知の部分も多く、命を奪われる方や、回復後も嗅覚障害や心肺機能等に後遺症が残る報告も出ており、過酷な環境で現場を支え続けている医療従事者の疲弊も、極めて深刻なものです。
主催として参加者やスタッフの皆様の安全を最優先に現状を考えた結果、2020年2月〜2021年現在まで一貫して、リアルな場での香道体験会やお香の会の開催を全て中止・延期しています。
一方で、このような誰にとっても厳しい時期であるからこそ、オンラインの安全な環境で芸術や文化の魅力を楽しめる機会には、とても大きな意味があると改めて実感しました。特に伝統文化や伝統芸能に携わる人は、人間の方が文化や芸術を支える姿が頻繁に描かれますが、(それも間違いでは無いものの)人間の方が文化や芸術に心の豊かさを大いに支えられていると思います。参加者の皆様の安全を確保できる「オンライン」の場で、今だから出来る香道の魅力を伝える活動をもっと増やしたい、と考えました。
そこでまずは、かねてより温めていた国内・海外の美術館コレクションにある香道具を中心に、日本の香りの伝統文化の魅力を伝える活動を、2020年夏からinstagramを使って香道具の魅力を発信するようになりました。そして同年秋、今回のオンライン香道具イベントを開催する事にしました。
Instagramの香道アカウント(@madoka_incense)
国内・海外の美術館の香道具を中心に、日本の香文化の魅力を発信しています。オープンしてまだ数ヶ月のアカウントですが、香道というニッチな分野をわかりやすく解説付きで掲載しています。香りや美術工芸品に興味のある方は是非こちらもフォローして頂けると嬉しいです。
『陰翳礼讃』にも通じる世界、「知られざる香道具の魅力」をオンラインで体験。
実はこのイベント、開催当日まで秘密にしていましたが、実は「史上初」の和蝋燭の薄灯りのもとで行う香道具観賞(オンライン)という、かなり珍しいイベントでした。
ただ、「知らぬ間にそんな試みに巻き込まれていた、と後で気づいたら面白そうだな…」と思ったので、参加者の方々にも敢えて詳細は告知せず、当日びっくりさせる方向で準備を進めました。
そして迎えた開催当日。
まずは、香道の歴史や香道具の基礎的な知識をざっくりと「おさらい」していきます。全く初めての方にも、経験者の方にもお楽しみ頂けるよう、下準備を整えたところで、いよいよメインディッシュの「知られざる香道具の魅力」に迫ります。
現代の私達が香道具を目にする機会は、概ね次の3つに大別されますが、一般的には①か②が多いと思います。
現代の香道具を見る機会と環境
①美術館・博物館などの展覧会、書籍、公式サイトで見る
②香道体験会や香筵(お香の会)で見る
③蒔絵や香道具のコレクターや作家などから作品を見せてもらう
①や②のようなパブリックな場では、鑑賞の為、LEDなどの電灯により、一定の明るさが保たれた場が用意されており、時間帯も概ね朝〜日中が中心です。
これは勿論、多くの方々が細工の妙や技法を見て学ぶ上で、大きな利点がある為に行われている事ではありますが、古の人々が見ていた環境とは異なるが故に、その景色(見え方)は、現代では大きく変わっています。
しかし中には、その本来とは異なる姿をちらっと見ただけで、物の良し悪しを判断してしまい「何だか派手過ぎるなぁ…」と、どこか軽薄な印象を持ってしまう人も居るかもしれません。実に勿体ない事です。
そこで、電灯の普及していない時代の人々が、暗闇の中、たった一つの和蝋燭の薄明かりを頼りに見ていたであろう香道具の姿を、オンライン配信で実際に、電気を消してじっくりとお目にかける鑑賞会を開始する事にしました。
日頃はお目にかけることが難しい、香道具がその本領を発揮する瞬間を、オンラインの動画配信で、視覚的にお伝えする、というものです。
それでは実際に、
鑑賞会の一部を、画像で少しご紹介いたします。
まずは、こちらの電灯の明かりで香道具をご覧ください。

電灯に照らされた明るい場所で見る、金蒔絵の施された香道具は、まさに「豪華絢爛」といった印象を受けます。
一般に、美術館や博物館の展示や、書籍、香道体験会など、多くの方が香道具をご覧になる際には、この様な電灯の明かりに照らされた環境です。
しかし、明るい電気の照明が用いられるようになったのは、近現代のこと。
古の人々が暮らした、和蝋燭の薄明かりの中では、
香道具は、どのような見え方をしていたのでしょうか?
それでは実際に、
電気の照明を消し、部屋を暗くして・・・
蝋燭一つだけの薄明かりの中で、
蒔絵の香道具を見てみましょう。

事実、「闇」を条件に入れなければ漆器の美しさは考えられないと云っていい。
日本を代表する文豪・谷崎潤一郎は、随筆『陰翳礼讃』の中で、漆の魅力は闇を抜きに語ることは出来ない、と断言しています。
谷崎は、漆の道具とは、電灯の無い時代、昔の蒔絵職人達は、きっと薄明かりの中で見ることを前提に、暗闇の中に少しずつ浮かび上がる具合を味わう様に作ったはずであり、明るい太陽や電灯の代わりに、真っ黒な闇の中、たった一つの蝋燭の、乏しい明かりの中で見ることで、暗闇の中に金蒔絵が底深く沈んで、渋く、重々しい、本来の姿を見ることが出来るのだと語ります。

つまり金蒔絵は明るい所で一度にぱっとその全体を見るものではなく、暗い所で色々の部分が時々少しずつ底光りするのを見るように出来ているのであって、豪華絢爛な模様の大半を闇に隠してしまっているのが、云い知れぬ餘情を催すのである。
あのピカピカ光る肌のつやも、暗い所に置いてみると、それがともし火の穂のゆらめきを映し、静かな部屋にも折々風のおとずれのあることを教えて、そぞろに人を瞑想に誘い込む。
引用部分:谷崎潤一郎『陰翳礼讃』
なお、実際のオンライン配信イベントは、『陰翳礼讃』の朗読と共に、この様子を静止画像ではなく、動画で配信しています。
参加者の方々には、「灯火の揺らめきを映し……そぞろに人を瞑想に誘い込む」と、谷崎潤一郎が見て感じたであろうその瞑想的な光景を、蝋燭の火の穂のゆらめきによって、暗闇に浮かぶ蒔絵が煌々と輝く映像を、オンラインの動画配信で、じっくりと体験して頂きました。
参加された方々からも、「貴重な体験が出来た」「ずっと眺めていたかった…」など、非常に大きな反響がありました。
解説と香道具観賞会を終えたところで、香道Q&Aコーナーを実施。
最後に、残り時間の許す限り、リアルタイムで次々飛んでくる質問に、(おそらく一般的な香道関係者では答えにくいであろう突っ込んだ内容も含めて)ビシバシ回答していきます。
「蘭奢待を切り取った信長も、香道を嗜んでいたのですか?」
「日本にも香水のように、液体の香りを楽しむ文化はありますか?また、それはなぜだと思いますか?」
「これから香道を習ってみたいと思ったら、どうすれば良いですか?」
…等々、当日は沢山のご質問やコメントをいただき、それぞれ離れた場所から参加するオンライン開催でありながら、大いに盛り上がりました。
※ちなみに、私は一般的にお香の先生やお茶の先生としてイメージするお教室の運営や、お弟子さん募集をしていません。香道に限らず先生を選ぶ時のポイントをお伝えしました。香道や着物などの和文化系イベントは、参加者にお教室への勧誘や商品購入をゴリゴリ勧める為の催しである事も多いのですが、私のお香のイベントではそういった心配は無いので、安心してご参加いただけます。
ブログ・SNSなど参加者の皆さんから頂いたご感想
ブログやTwitter、当日のチャットやアンケートでも、たくさんの有り難いご感想を頂きましたので、一部を引用してご紹介いたします。
ご感想一覧はこちら:
https://note.com/kaoritobunka/n/nbdcab4847444
SNS
オンライン香道、あの場におられない方には少し信じられないかもしれませんが、
— 白沢達生@新年初登壇は1/5online (@t_shirasawa) October 25, 2020
さながらまさに「香りを聞く」ときの体験そのままでした。
主催の方が現況を考えぬいて、「聞く」を突き詰めるだけでなく、ぼくら聞き手の想像力を信頼してくださったからできたことと思います。
稀有の時間でした… https://t.co/Mtt1GAMWsv
すっごく、よかった。陰翳に浮かぶ香道具。本物の物がもつヴァイブスは映像越しにも伝わってきました。
— +M (@freakscafe) October 25, 2020
常日頃本物に触れている人特有のたたずまいも伝わってきて、本当に上質な時間。始終どきどきしてました。
体験会が開催できるようになったらぜひ参加したい。それまでに予習しておきます。 https://t.co/xY6lcQOq08
送られてきた素敵な文香。香りが消えてゆくのも風情と思いつつ、手に取って香りを愉しむ時以外には、移り香を期待して伊達本の古今和歌集の294番目のあたりにそっと仕舞ってみる。(本当は袋ごと) pic.twitter.com/LTI3x2Gjim
— 水芙蓉 (@suifuyoh) December 1, 2020
先日のオンラインイベント「知られざる香道具の魅力」の特典として、香人madokaさんお手製の文香「唐紅」が届く。天然の伽羅や麝香を中心とした複雑で妖艶な香り。もったいないので時々取り出して楽しむ事にします。写真はあえて薄明かりで。https://t.co/dDbP3PaPnh pic.twitter.com/iZOYAXba0R
— 須藤岳史 (@Artssoy) December 10, 2020
ブログ
フランス在住の俳人・小津夜景さんのブログにて、今回のイベントの感想の記事と、文香の記事と、重ねてのご紹介頂きました。遠方からのご参加、ありがとうございました!

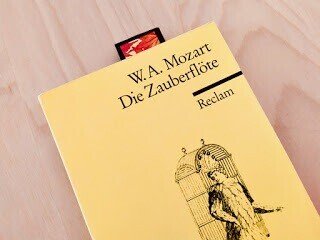
▼イベントの記事「香りのない香りの会」小津夜景日記*フラワーズ・カンフー
https://yakeiozu.blogspot.com/2020/10/blog-post_26.html
▼文香の記事「唐紅のスパイシートーン」小津夜景日記*フラワーズ・カンフー
https://yakeiozu.blogspot.com/2020/12/blog-post_6.html
今回ご参加の皆様には、任意で開催後アンケートへのご協力をお願いしました。
初のオンライン開催、しかも、史上初の試み(真っ暗がりでよく見えない香道具の映像を流すのがメインという、一歩間違えれば放送事故と扱われそうな内容…)ということで、匂いの無いインターネットの世界で香道具の魅力をどこまで伝えることが出来たかを確認すると同時に、香道を含め暫くはコロナ禍で方向転換が求められる伝統文化の今後の活動にも役立てたいと考えた為です。
ご協力頂いた方々にはお礼として、本物の貴重な香木「伽羅」を使用し、沈香や丁子などの天然香料と調合した特製文香を謹呈しました。貴重なお時間を頂きました事、改めてお礼申し上げます。
アンケート結果も、全体的に非常に満足度が高く、オンラインで香りのない香道イベントを開催するという今回の試みは、大いに成功したと言えそうです。
謝辞・あとがき
まず最初に、今回の奇特なイベントにご参加頂いた皆様に、心からお礼を申し上げます。首都圏以外の全国各地の方々や、海外の方々とも、移動距離を気にせず、気軽にご参加いただくことができたのは、とても嬉しいことでした。
コロナ禍における安全性の確保という点が第一ではありますが、(参加者の皆様にお楽しみ頂けるものにする、という宿題をクリアした上で)「この状況を逆手に取って、まだ誰もやったことが無い新しい挑戦をしてみたい」というのも、今回の目標の一つでした。
ご参加の皆様に加え、告知ページの開設が遅れ、僅か2週間ほどの短い募集期間の中で本イベントを拡散してくださった方々のご厚意(おかげさまで追加席まで完売しました)や、文化庁継続支援事業の採択による機材調達費等の補助にも、大いに助けられました。
こうして多くの方々のご協力を頂いたおかげで、匂いのないインターネットの世界で、香道という香りの芸術の持つ高雅な雰囲気を如何にして伝えるか?という難題に、一つの最適解を体現することができたと考えています。
例年の香道体験会では、開催後すぐにイベント開催レポートを書いていましたが……今回のイベントは、当日のライブ配信だけでなく、開催後日の見逃し配信で視聴参加する方も居られた為、当日参加者の方々からSNSやブログでお寄せ頂いた参加者の皆様のご感想を紹介する程度に留め、主催側からのレポート記事はご用意しないようにして居りました。
そうして迎えた2021年1月。何の偶然か、NHKで「谷崎潤一郎の『陰影礼賛』の世界を、ロウソクの薄明かりの中で屏風絵などを撮影し、その光景を映像化して配信する」という趣旨の番組が新春ETV特集として作られた事を知り、思いがけず「ゆく年くる年」を振り返る良い機会が生じましたので、嘗ては新年の始まりとされていたこの立春に、オンライン香道イベントの開催レポートをnoteに公開することに致しました。
本オンライン香道イベントへのご参加が叶わなかった方にも、当日の雰囲気をお楽しみ頂ければ幸いです。
上野の東京国立博物館で、例年は初心者の方にも気軽に正座無しで楽しめる香道体験会を開催(前回のレポートはこちら)して満席のご好評を頂き、次回参加のご希望も多数頂いて居りましたが、今はまだ、少人数に絞っても(同居家族など日常的に会っている方同士を除き)不特定の方々の集まりは、依然リスクが高い状態です。
参加者やスタッフの皆様が安心してリアルな香道体験会を楽しめる時まで、今暫くお待ち頂ければ幸いです。その間、オンライン等で安全に、香道の魅力やお香の楽しみをお伝えできるよう、今後とも精進して参りたいと思います。
皆様どうぞ御健勝にて、素晴らしい一年をお過ごしください。
令和三年 立春 madoka 拝
