
中国古典インターネット講義【第10回】中唐・晩唐の詩~白居易・柳宗元・杜牧・李商隠
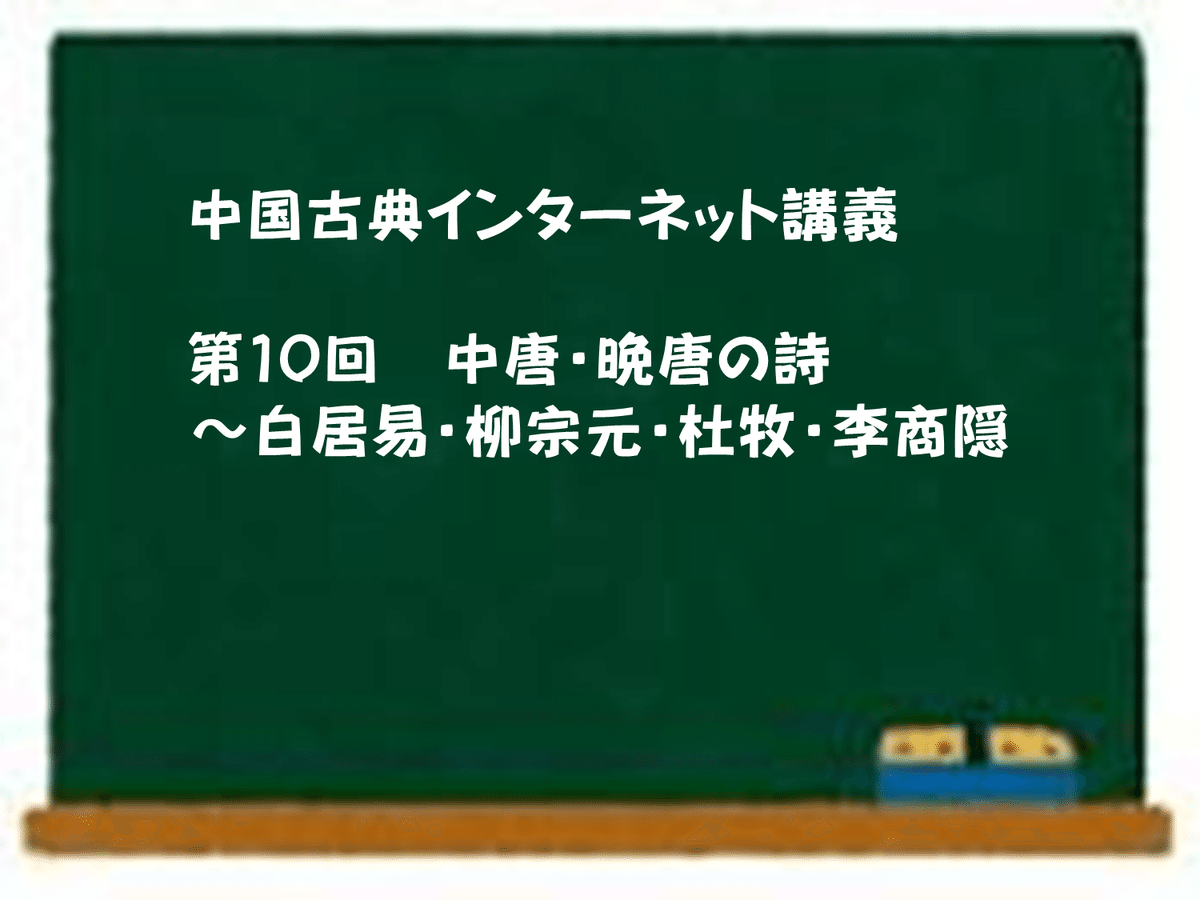
中唐
「中唐」は、安史の乱以後の約70年間を言います。安史の乱は終結しましたが、その後、地方の軍事勢力が新たな動乱の火種となり、また、乱の平定を援助したチベットやウイグルなど異民族の兵士たちが唐朝の国内に出入りをして略奪を繰り返していました。
中央の朝廷では、宦官の横暴や官僚の間での権力闘争が絶えず、社会不安は続いていました。
詩壇では、大暦年間の初め、元結と顧況が激しい調子の社会批判の諷喩詩を作りました。
また、銭起・廬綸・司空曙ら「大暦の十才子」と総称される一群の詩人や、韋応物・劉長卿らの詩人たちが現れました。
これらの詩人たちの詩は、田園の生活や自然の情景を繊細なタッチで描いたものが多く、静寂な自然の中に見出した高雅清逸な境地を歌っています。
韓愈
韓愈(768~824)は、字は退之、散文の大家であり、中唐の古文復興運動の主導者です。
「古文復興運動」とは、六朝以来の形式的、修辞的な美文を排して、漢魏以前の思想内容のある力強い文章に立ち返れという文学主張です。
韓愈は、中国古典文学史の上では、詩人としてよりも、文章家として名を残しています。
文章家としての韓愈については、また後日の講義で詳しくお話しします。

詩人としては、韓愈の詩は「文を以て詩を為す」と評されています。
散文的な風格を持ち、技巧面で型破りの手法を用いて、新しい境地を開いています。
散文の調子で詩を作るので、やや理屈っぽい面がありますが、気勢をもって人に迫る力強さを持っています。
「武骨」(骨張ってごつごつ)で「険怪」(難解で不自然)な詩と評され、
独創的なあまり、奇怪で晦渋な詩句が多く見られます。
白居易
白居易は、字を楽天と言います。中唐を代表する詩人です。29歳で進士に及第し、翰林学士や左拾遺などの官を歴任し、中央のエリート官僚として順調に出世しました。
ところが、元和10年、44歳の時、長安で起きた宰相殺害事件に関して、事件の処理の手ぬるさに不満を抱き、早急な犯人逮捕を要求して上書したことが越権行為と見なされ、江州(江西省)に左遷されます。
その後は、杭州(浙江省)や蘇州(江蘇省)の刺史(州の長官)を歴任し、50代後半に中央に返り咲き、官は刑部尚書(法務大臣)に至っています。

白居易の詩は、平易明快で人々に親しまれ、詩人の生前から大いに流行し、早くから日本にも伝わっています。
白居易は、自らの詩を編集して、「諷諭・閑適・感傷・雑律」の4類に分けています。
「諷諭」は、主に若い頃に、経世済民の儒家的理念を抱いて歌った詩です。社会の現実を諷刺したもので、「新楽府」五十首、「秦中吟」十首など、人道主義の上に立って政治批判の意を込めた作品群です。
「閑適」は、日常の生活を題材とした作品群です。主に、江州に左遷された後のもので、中央の政界から遠ざかり、俗世から離れた心静かな境地を歌っています。
「感傷」は、世間の事物や歴史的事柄によって触発された情感を歌ったもので、「長恨歌」や「琵琶行」などの名作があります。
日本では感傷詩が有名ですが、白居易本人は、感傷詩は遊戯的な作品に過ぎず、自分の詩の本領は、諷諭詩にあると考えていました。
「雑律」は、他の3類がいずれも古体詩であるのに対して、近体詩(絶句・律詩・排律)を集めたものです。
「賣炭翁」
「賣炭翁」(炭を売る翁)は、「新楽府」50首の中の第32首。官吏の横暴と庶民の窮状を活写し、世の不条理を歌った作品です。

賣炭翁 炭を売る翁
伐薪燒炭南山中 薪を伐り 炭を焼く 南山の中
滿面塵灰煙火色 満面の塵灰 煙火の色
兩鬢蒼蒼十指黒 両鬢 蒼蒼 十指黒し
賣炭得錢何所營 炭を売り 銭を得て 何の営む所ぞ
身上衣裳口中食 身上の衣裳 口中の食
可憐身上衣正單 憐れむ可し 身上 衣 正に単なり
心憂炭賤願天寒 心に炭の賤きを憂え 天の寒からんことを願う
――炭売りの爺さん。
南山に入って薪を伐り、炭を焼いている。
顔中にほこりと灰をかぶって、炭焼きの煙ですすけた顔をしている。
左右の耳際の髪の毛は、黒白入り交じり、十本の指は、すすで真っ黒だ。
炭を売って小銭をかせいで、それでいったい何をしようというのか。
それは、身につける着物と、口に入れる食べ物を手に入れるためだ。
ああ、なんと気の毒なことに、身につけているのは、まさに単衣の薄着。
炭が安くなるのを心配して、「天よ、もっと寒くなれ」と祈っている。
夜來城外一尺雪 夜来 城外 一尺の雪
曉駕炭車輾冰轍 暁に炭車に駕して 氷轍を輾らしむ
牛困人飢日已高 牛困れ 人飢えて 日已に高く
市南門外泥中歇 市の南門の外 泥中に歇む
翩翩兩騎來是誰 翩翩たる両騎 来るは是れ誰ぞ
黄衣使者白衫兒 黄衣の使者 白衫の児
手把文書口稱敕 手に文書を把りて 口に勅と称し
廻車叱牛牽向北 車を廻らし牛を叱し 牽きて北に向かわしむ
一車炭 千餘斤 一車の炭 千余斤
宮使驅將惜不得 宮使 駆り将けば 惜しみ得ず
半疋紅紗一丈綾 半疋の紅紗 一丈の綾
繫向牛頭充炭直 牛頭に繫けて 炭の直に充つ
――昨夜は雪が降り、長安の郊外では、一尺の雪が積もった。
明け方、炭を積んだ荷車に牛を繋ぎ、凍った轍の上を車輪を軋らせて行く。
(町に着いた時には)牛は疲れ、爺さんは腹を空かし、日はもう高い。
市場の南門の外で、ぬかるんだ泥道に腰を下ろしてひと休みする。
すると、そこへ馬に乗った二人の者が、飛ぶように軽快にやってきた。
いったい何者かといえば、黄色い服を着た宮市使と白い衣の手下の若者だ。
手には文書を持ち、口では「勅命じゃ!」と叫ぶ。
荷車の向きを変えさせ、牛を叱るように追い立て、北の方へと向かわせる。荷車いっぱいに積んだ炭は、千斤余りの重さがあるのに、
宮中の使者に駆り立てられたら、もう惜しんでもどうしようもない。
わずか半疋の赤い薄絹と一丈のあや絹、
牛の頭に引っ掛けて、これを炭の代金に充てろと言っている。
「黄衣使者」は、「宮市使」(宮中の物資調達役の宦官)を指します。
「文書」は、民からの物資買い上げを認める文書のことです。
荷車を「北に向かわしむ」とありますが、長安の東西の市から見ると、皇宮は北の方角に位置します。つまり、老人の焼いた炭が宮中で買い上げられることになったということです。
老人が真冬に苦労して焼いて、重いのをやっとの思いで運んできた炭です。もし市場で売れば、それなりの銭にはなったはずですが、お上に買い上げられてしまったらタダ同然になってしまいます。
当時、実際に、宮中で使い残した絹の切れ端などが農産物の代金に充てられました。こんな物をもらっても、山村に暮らす貧民には、何の役にも立ちません。

この詩に描かれているのは、当時の「宮市」(お上による売り買い)の制度の実態です。
物資調達役の宦官が、手下の者を従えて都の市場を徘徊し、めぼしい品物を見つけると、宮中で要らなくなったものと物々交換させていました。没収・略奪に等しいやり方です。
「賣炭翁」は、こうした悪政の弊害を諷刺し、批判した作品です。
虐げられても為すすべのない庶民のありさまを淡々とした筆致で描写しています。政策を非難したり譴責したりする言葉は一切用いず、ただ起きている事柄だけを平易な表現で客観的に語っています。
個別の事象を一つの物語に仕立てて歌い、それを社会全体の問題として提示する手法は、まさに楽府の伝統にのっとり、杜甫の社会詩を継承するものと言えるでしょう。
ここから先は
¥ 300
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
