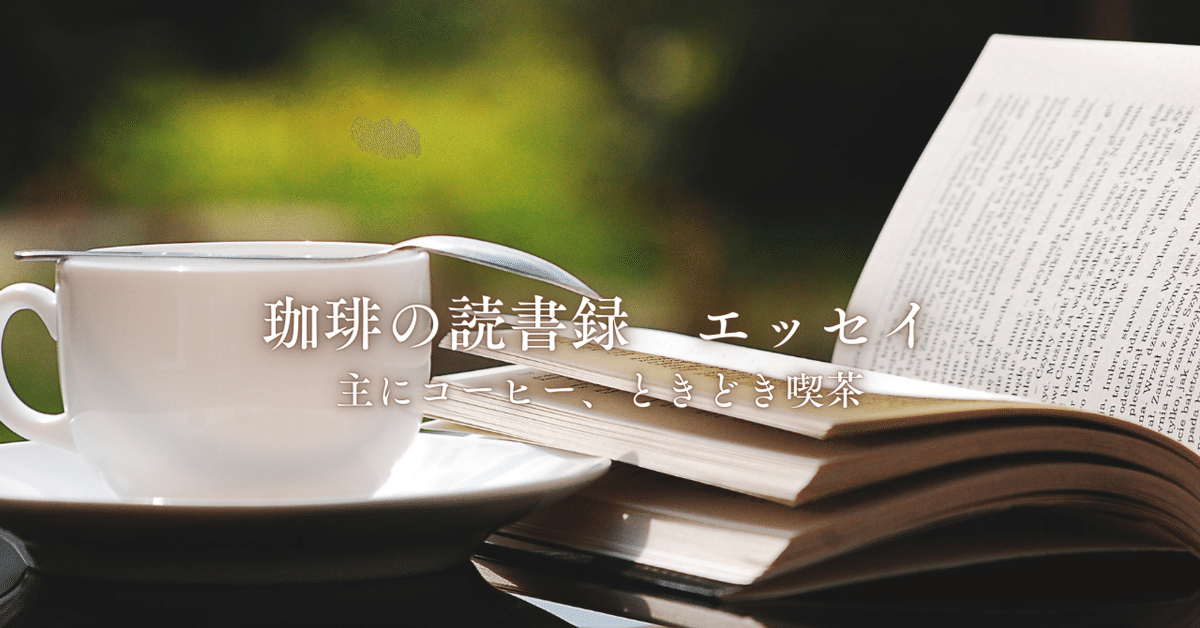
珈琲の読書録『咖啡の旅』標 交紀
旅の楽しみのひとつは、夢を壊すことだと思っている。頭の中だけで描いた身勝手な夢が壊れて、目の前の現実が取って代わる。予め持っていたイメージの正解不正解ではなく、いくらか重なりはするがひと続きではない。失望だけで終わることもある。もし現れてきたものが豊かであれば旅は上々である。
旅人は自家焙煎珈琲店「もか」の店主である標交紀氏とその奥様。22年間続けた店を休んで旅に出た。コーヒーを高貴なものとして研鑽を積み、自らのコーヒーがある種の到達点に達した時、周囲を見渡すと日本のコーヒーはすっかり変わっていたという。少量の豆で効率よく抽出する薄いコーヒーの流行に失望した標氏は、かねてより夢見ていた理想のコーヒーを求めて機上の人となった。
とにかく飛行機が怖かったようで、「はじめに」の後半は飛行機の話で占められている。お守りを握りしめ、奥様に慰められ、トイレのためにシートベルトを外すなんてとんでもないと水も飲まずに過ごした標氏は、呪文のようにこう唱えていたという。
「本物のコーヒーを探しに行くんだ」
標氏は昭和51年から58年の間に5回渡欧した。イギリスをはじめとする11か国の旅行記を国別にまとめたものが本書である。
標氏には「コーヒーの鬼」の異名がある。理想のコーヒーを追い求める厳しさによるものだという。この本を読むだけでも、言外に厳しさと美意識が伝わってくる。構成のどこにも無理がない。はじめにテーマを提示し、旅のエピソードが大きな流れを描いてエピローグに至る、抑制の効いた上品な文章が、そこにしか置き場所がないかのように適切に配置されている。無造作に置かれた言葉はひとつもない。無駄のない建築のように美しい。
標氏は美味いともまずいとも滅多に言わない。憧れていた伝統が失われている国もあり、失望が漂っても、それを悪く言うことはない。冷静に観察し、文化的な背景に思いをはせ、ありのままを受け止める。美味ければ宝石を讃えるような美辞麗句を並べ、喜びを爆発させる。通りすがりの小さな店で、コーヒー豆の煎り具合にドキリとして意気投合し、焙煎士と3時間話し込んだこともあったという。
「あれから六年たった今でも、胸が熱くなる思い出がある。チューテス氏と分かれの握手をした時に、手のひらの或る個所がコツンと当ったのだ。長い間コーヒーの焙煎機を扱っていると、タコができる。彼にも私と同じ場所にタコがあった訳だ」
この鬼は怖くなさそうだ。
標氏は2007年に他界した。「もか」は自家焙煎珈琲店の草分けとして今でも語り継がれている。氏のコーヒー器具コレクションは、国立民族学博物館におさめられた。その一方で著作は絶版となり入手が難しい。嶋中労氏による評伝は売られており、コーヒーに人生を捧げた求道者としての逸話は残っているが、本人の言葉は消えかけている。その姿は伝説の影に隠れてしまった。
標氏がコーヒーのイデアのような理想のコーヒーを追い求めたように、神格化されたシメギコーヒーのイメージを誰かが追っているだろう。今日もどこかで誰かが、一杯のコーヒーに一喜一憂している。
旅はどこまでも続いていく。
標 交紀 (著)『咖啡の旅: 吉祥寺・珈琲店「もか」 』単行本 – 2017/9/1
美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 開館40周年記念新着資料展示「標 交紀(しめぎゆきとし)の咖啡(コーヒー)の世界」国立民族学博物館
国立民族学博物館 標本資料目録
検索ワード: 自家焙煎咖啡専門店「もか」
