
「榎戸」の謎
第1章「えのきどいちろう」
えのきどいちろう(本名・榎戸一朗、65歳)さんという、コラムニスト兼ラジオパーソナリティがいる。
彼が昔、われわれ川崎市民の記憶に残る、以下のような文章を書いている。
僕の実家は川崎市にあるんですよ。川崎市多摩区。小田急線の向ヶ丘遊園というところなんですけど。これが物凄く微妙なところなんですね。(中略)
だけど「東京」との間には川が流れている。意識のうえで、いつも川が流れている。(中略)テレビを見ていて、タレントに「どちらにお住まいですか?」と尋ねられて「小田急線です」と電車の線で答えた女子高生が映った。ははぁ、さてはと思ったが案の定、タレントにもっとつっこまれて川崎市多摩区登戸だと白状していた。(中略)僕は賭けてもいいが八八パーセントくらいの川崎市民は内心、出来たら川崎なんてなくなってくれないかなぁと思っていると思う。
(えのきどいちろう「川崎と東京の間には、深くて暗~い溝がある」杉山康彦『川崎の文学を歩く』=1992、多摩川新聞社=p3の引用による)

東京と横浜にはさまれた、川崎市民の微妙な劣等感を表現した文章だ。
その意味で、神奈川における川崎市民は、関東における埼玉県民と似ている、という記事を、この文章を引用して、私も前に書いたことがある。
この文章を、私が雑誌で最初に読んだのは、30年以上前だ。
えのきどいちろうさんは、ナンシー関さんと親しく、ナンシーさんを文壇デビューさせた人としても知られる。
以前、ナンシー関さんと飲んだことがあると書いたが、その横にはえのきどさんがいた。
そんなこともあって、「へー、えのきどさんの実家は川崎なんだ」という情報とともに、この文章が記憶されていた。
その後、20年ほど前に、私は川崎の登戸に住み始めた。
川崎市民になって、改めてえのきどさんの文章が思い出された。
ある日、登戸の隣の向ヶ丘遊園をぶらぶら歩いていると、津久井道沿いに、「榎戸ビル」があった。
1階が「ホール」で(たしか「榎戸ホール」という表示があった)、社交ダンスの練習場にもなっている立派な建物だった。
(ここが、えのきどさんの実家なのかな。意外に金持ちだな)
と思ったのであった。
と、同時に、「榎戸」という名前の由来が、なんとなく気になっていた。
ちなみに、えのきどさんは、「榎戸」だと「えのど」と間違って呼ばれるから、「えのきど」とひらがな書きを筆名にしているという(wikipedia「えのきどいちろう」より)。
第2章 稲城市の「榎戸」
「榎戸」にまつわる、その20年ほど前の記憶がよみがえったのは、今月の22日だ。
私は、約80年前の1944年(昭和19年)に、民俗学者の柳田国男が歩いた「柿生〜矢野口」というルートを、歩いてみた。
それは、1月24日にnoteに書いた。
その途上、JR南武線の矢野口駅に着くすぐ手前で、「榎戸」という地名表示を見たのである。
私は思わず、それを写真に収めた。↓

(へー、こんなとこにも、「榎戸」があるんだ)
と思って、約20年前の向ヶ丘遊園の「榎戸ビル」の記憶がよみがえったのである。
「榎戸」という名前の由来が、改めて気になった、という次第。
第3章 柳田国男の考察
数日前、図書館で柳田国男の全集をパラパラめくっていたら、柳田が「榎戸」について書いている文章があって、私は興奮した。
柳田は、以下のように書いている。
榎戸の問題は、久しい前から私も考えているが、関東ことに東京の四周には、同じ地名が多く、また現実に古榎も多かった。近年伐ったり枯れたりしているけれども、まだまだその記憶を辿って、昔の交通路を跡づけることは不可能ではなく、それがまたこの方面の旧事を探る上に、有力な手がかりともなるのである。(中略)
一里塚でなくても塚の木は多くは榎であり、また塚のない処にも大きな榎があり、また榎戸という地名がある。つまりこれが大昔以来の路傍の樹だったのである。
(柳田国男「榎戸懐古」『柳田國男全集3』ちくま文庫、p53 初出「初瀬とこれさまと五反田節」昭和二十八年十一月)
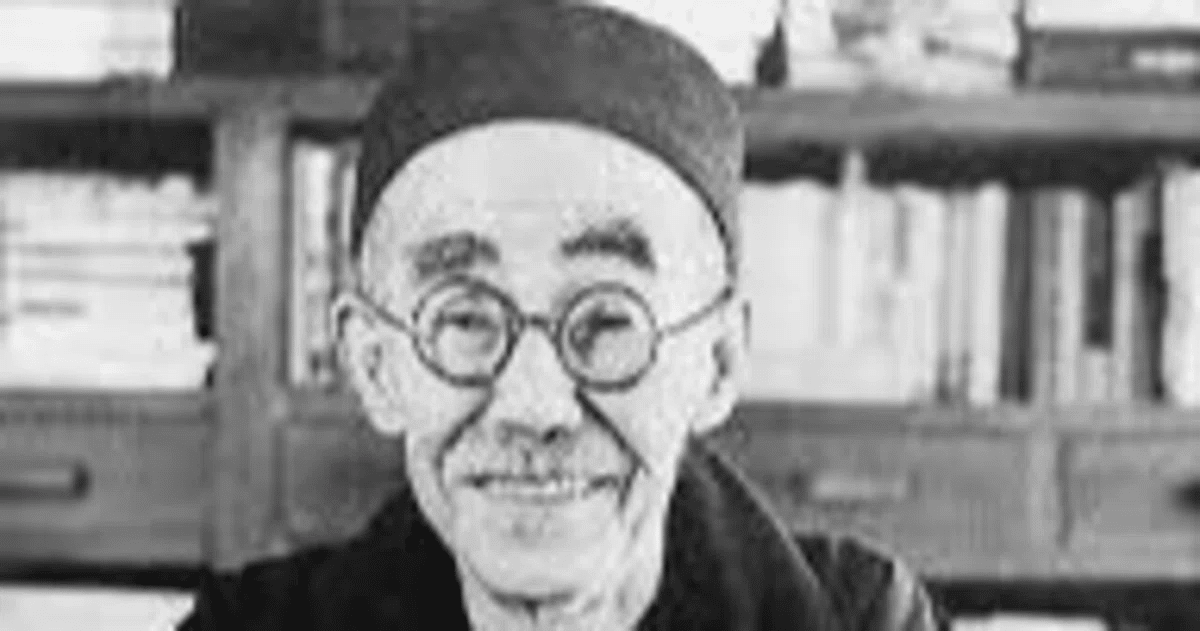
榎は、生育が早く、大きく育つので、かつては道の目印としてよく植えられていた。当時のランドマークである。
その榎のところ(榎戸)に、旅人がひと休みする、旅籠や居酒屋ができて、賑やかな場所を形成したらしい。
柳田が「関東に多い」と書いているとおり、千葉、埼玉、茨城にも「榎戸」があることが、ネットですぐにわかる。
現在の向ヶ丘遊園にあった「榎戸」は、中でも有名な榎戸であったらしい。
柳田がこの文章で考察しているのも、現在の向ヶ丘遊園、かつては「五反田村」と言っていた頃の「榎戸」である。
当時の「榎戸」の、だいたいの位置を地図で示せば、以下のようになる。

そこは、津久井街道と、府中街道が交わる交差点だった。
また、多摩川を渡ってきた西に向かう旅人が、多摩丘陵の「山」を登る前に、準備をととのえるのにふさわしい場所だった。
そういう場所の目印として、榎の巨木がそびえたっていたのだろう。
五反田榎戸の名木の榎なども、話の様子ではよほどの年齢を経ていたらしいから、おそらくはこの界隈随一の故老であり、物こそ言わぬがさまざまな世の中の変化を、じっと見おろして立っていたのであった。
(同p54)
第4章 「榎戸」の賑わいと「五反田節」
当時の榎戸の賑わいについては、図書館の郷土史コーナーにあった『わがまち麻生の歴史三十三話』にも記述があった。
小泉橋を渡ると津久井街道は、川崎と府中を結ぶ府中街道と交わります。この辺りは榎戸と呼ばれ、昔は五反田村でした。いまはそれほどではありませんが、江戸時代には紀伊国屋をはじめ数軒の旅籠と居酒屋などがあり、当時は賑やかな場所でした。
紀伊国屋の前の家に、榎の大木がありました。明治二年(一八六九年)に榎戸の火事で燃えてしまったそうです。
(高橋嘉彦『わがまち麻生の歴史三十三話』日本機関紙印刷所、1992、p207)
この江戸時代の繁華街であった「榎戸」から生まれたのが「五反田節」だ。当時のヒット曲である。
本来は旅人を居酒屋に誘う、少し色っぽい「勧酒歌」であったが、めでたい内容から、この地域の結婚披露宴で祝歌として歌われていたという。
以下のとおり、歌詞に「五反田の境のあの榎」と、榎が歌い込まれている。榎戸はちょうど、五反田川をはさみ、登戸と生田の境でもあった。
これほどの旅の疲れを
五反田の酒屋で忘れたや
忘れても忘れがたなや
五反田の酒屋の小娘子
鳥なれば巣もなかけたや
五反田の境のあの榎
榎にゃ蔦がからまる
娘にゃ御殿がからまる
かわさきの古民謡「五反田節」を歌う(川崎市文化芸術応援チャンネル)
第5章 柳田国男の想像力
50歳を過ぎた柳田国男は、毎週水曜日に、自宅があった成城学園前から、小田急線に乗って下り、今の和泉多摩川や登戸、柿生や鶴川で降りて、武蔵野や多摩丘陵を散策していた。
この「榎戸」と「五反田節」を考察した文章も、その散策の中で生まれたもので、「水曜手帖」としてまとめられ、本になるはずだった(が、柳田の生前に実現せず、原稿のまま「全集」に入った)。
この柳田の文章を読んで、私は感動して涙が出てきた。(老人だから涙腺がゆるく、すぐ涙が出る)
老年になった柳田は、ただ古いものを訪ね歩いていたわけではない。
その古いものが、「若いころにはどうだったか」を想像するために歩いていた、というのが、よくわかるからである。
そこには、自分の心も若返らせたい、という老年の願いがある。そういう心理は、同じ老人だから、よくわかる。
精力的に武蔵野と多摩丘陵を歩き回り、土地の「青春」を想像する老人柳田のたくましい想像力に、私は感動したのであった。
榎戸の榎は古木であったというが、それでも一ぺんは若木であり、人が路傍の神の御しるしに、これを手植した時代はあったろう。私はそれを多摩川の岸がなお近く、ここを川船の船場としていた時代だったかと思っている。それがある年の大水で流されて、村は以前の対岸の地へ移り、その跡は久しく曠野になっていた。榎はその間にもだんだんと成長して、岡を南に超えて行く旅の者が、まだ陸続と去来している頃に、すでに遠くからの目標となり、またその樹陰の居酒屋を有名にし、やがては五反田節というような新たなる勧酒歌を、発生せしめる素地を作ったのではなかろうか。こういう推定の当れりや否やを決するのは、これから芽を吹くべき大川崎市の郷土研究でなければならぬ。
(同p60)
終章 「えのきど」さんと、稲城と川崎
最後に、「えのきどいちろう」さんのことに戻れば、向ヶ丘遊園のあのへん一帯が「榎戸」であったわけだから、私が見た「榎戸ビル」が、えのきどさんの実家だとは限らない。たんに地名をビルの名前にしただけかも知れないからだ。
でも、えのきど(榎戸)さんの名が、旧地名の「榎戸」に由来するのは、ほぼ間違いないだろう。土地の名前を苗字にしたのは、やはりそれなりの名主だったからではないだろうか。
いまは登戸駅周辺が大開発中だが、それだけに、かつての「榎戸」のあたりの賑わいは、忘れられていく一方だろう。
でも、名歌「五反田節」を生んだ榎戸の出身であれば、えのきどさんは、川崎生まれを卑下するのではなく、もう少し誇りを持ってもいいのでは、と思う。
また、私が稲城で見た「榎戸」については、ネットの範囲では詳しい来歴がわからなかった。
向ヶ丘遊園の「榎戸」と、稲城の「榎戸」が、ちょうど1里(約3・9キロ)であれば面白い、と思ったが、google mapで調べたら約5キロであった。

でも、「五反田節」は府中でも歌われていたというから、府中街道を通じて、両「榎戸」に何らかの関連はあったと思う。
川崎市の「登戸ー榎戸」の関係と、稲城市の「矢野口ー榎戸」の関係は、よく似ている。どちらの榎戸も、多摩川を渡ってきた旅人が、榎の大木のもとで、ひと休みする場所だったのではないか。
(登戸=登り口、矢野口=谷の入り口、は、どちらも武蔵野の「横山」の登山口だったことを意味するのだろう)
稲城の「榎戸」については、今後の研究課題である。
<参考>
