
ベトナム人の海外労働の動向について-日本との関係性を考える2024年10月
ベトナム人の海外労働の動向について2024年10月【2,430字】
はじめに
ベトナムの海外労働者は、現在40カ国以上に渡って活躍しています。
ベトナム海外労働局(労働傷病兵社会問題省)の発表によると、2024年9月末時点での海外労働者派遣総数は、年間目標を上回る19万1,502人に達しました。
この数値は、ベトナム経済の国際化と労働力輸出の成功を物語っています。
その中で、日本は依然として最大の派遣先国であり、7万4,301人のベトナム人労働者を受け入れています。
次いで、台湾が6万1,720人となり、これら上位2カ国で派遣先の8割以上を占めています。
その他、韓国、シンガポール、ハンガリーなどが続いています。
ここでは、日本とベトナムの関係について考察し、労働市場の動向を追いながら、その背景や要因について考えていきます。
【1】日本の研修制度と中国人労働者との関係
日本の技能実習制度を理解する上で、中国からの労働者との関係を避けては通れません。
この制度は、発展途上国の労働者に技術を伝えることを目的として始まりましたが、実際には労働力不足を補うための手段として利用されてきました。
初期には中国からの労働者が多数を占めており、「旧:研修制度」時代には、低賃金や長時間労働など、問題の多い環境でした。
特に、時間外労働に対する適切な報酬が支払われないという訴えが相次ぎました。
その結果、制度は改善され、「技能実習制度」として書面による適正な雇用契約と労働基準法の尊守が義務付けられるようになりました。
近年では、ベトナム人労働者の数が増加し、日本国内での重要な労働力として活躍しています。
この背景には、中国と日本の関係の変化や、中国国内の賃金水準の上昇、農村部での所得の増加などがあります。
日本と中国の関係が政治的・経済的に緊張する中で、日本はベトナムからの労働者を積極的に受け入れるようになっています。
【2】ベトナムのドイモイ政策と労働力輸出
ベトナム戦争後、1986年に開始されたドイモイ(革新)政策は、計画経済から市場経済への移行を目指し、国内の経済発展と国際経済への統合を促進するものでした。

この政策により、労働力の輸出が国策として重要視されるようになり、海外での就労がベトナム経済にとって外貨獲得の重要な手段となりました。
日本は、このドイモイ政策の下でベトナムからの労働者を受け入れる主要な国の一つとなりました。
ベトナムにとって、日本での就労は技能や知識を習得する大きな機会であり、日本の労働市場にとっても重要な労働力となっています。
【3】ドイモイ政策の背景と目的
1986年に開始されたドイモイ政策は、ベトナム戦争後の深刻な経済危機に対処するためのものでした。
当時のベトナムは、生産力が低下し、食糧不足やインフレが深刻化していました。
この政策により、計画経済から市場経済への移行が図られ、国内経済の活性化と国際経済への統合が目指されました。
【4】ドイモイ政策と労働力輸出のさらなる詳細
ドイモイ政策により、外国投資が奨励され、農業集団化の緩和、国有企業の民営化などが進められました。これにより、ベトナムの経済は自由化が進み、労働力の輸出も活発化しました。
日本はベトナムからの労働力を受け入れることで、自国の労働力不足、特に介護職や建設業などの分野での需要を満たしています。
また、日本は比較的安全な労働環境を提供していることから、ベトナム人労働者にとって魅力的な就労先となっています。
【5】ベトナムと日本の関係を支える要因
経済的な要因
日本はベトナムへのインフラ投資を積極的に行っており、ハノイの都市鉄道プロジェクトやホーチミン市の水処理プロジェクトなどがその代表例です。
このプロジェクトを代表例に、ベトナムと日本の経済的なつながりは強まりました。
また、日本の労働市場における人材不足は、ベトナム人労働者によって部分的に補われており、これが日本の高齢化社会における重要な対策となっています。
文化的な要因
ベトナムからの留学生の増加により、両国間の文化的理解が深まっています。
特に日本のアニメや音楽などのポップカルチャーは、ベトナムの若者に影響を与えており、日本への親近感を高めています。
政治的・外交的な要因
日本とベトナムは、地域の安全保障においても協力関係にあります。
特に南シナ海問題に関しては共通の懸念を持ち、政治的な信頼関係が築かれています。
また、高官の相互訪問も頻繁に行われ、両国間の政治的なつながりを強化しています。
教育と技能開発
日本の技能実習制度を通じて、ベトナム人労働者は日本で技術や知識を学び、その経験をベトナムに持ち帰ることができます。
また、日本語教育の普及は、ベトナム人が日本での就労に適応するための基盤を提供しています。
【6】日本とベトナムの軍事的・歴史的な交流
歴史的に見ると、日本とベトナムの関係には軍事的な側面も存在します。
第二次世界大戦中、日本はフランス領インドシナに進駐し、ベトナムの独立運動に影響を与えました。
その後、冷戦期を経て、ベトナム戦争後には日本が経済的支援を行い、ベトナムとの関係を改善しました。
現代においても、日本とベトナムは防衛分野での協力を強化しており、南シナ海問題に対する共通の懸念が両国を結びつけています。
日本はベトナムに対して、防衛関連の技術や装備の提供も行っており、地域の安定に寄与しています。
まとめ
ベトナムのドイモイ政策と労働力輸出戦略は、国内経済の成長と国際経済への統合を目指す重要な手段であり続けています。
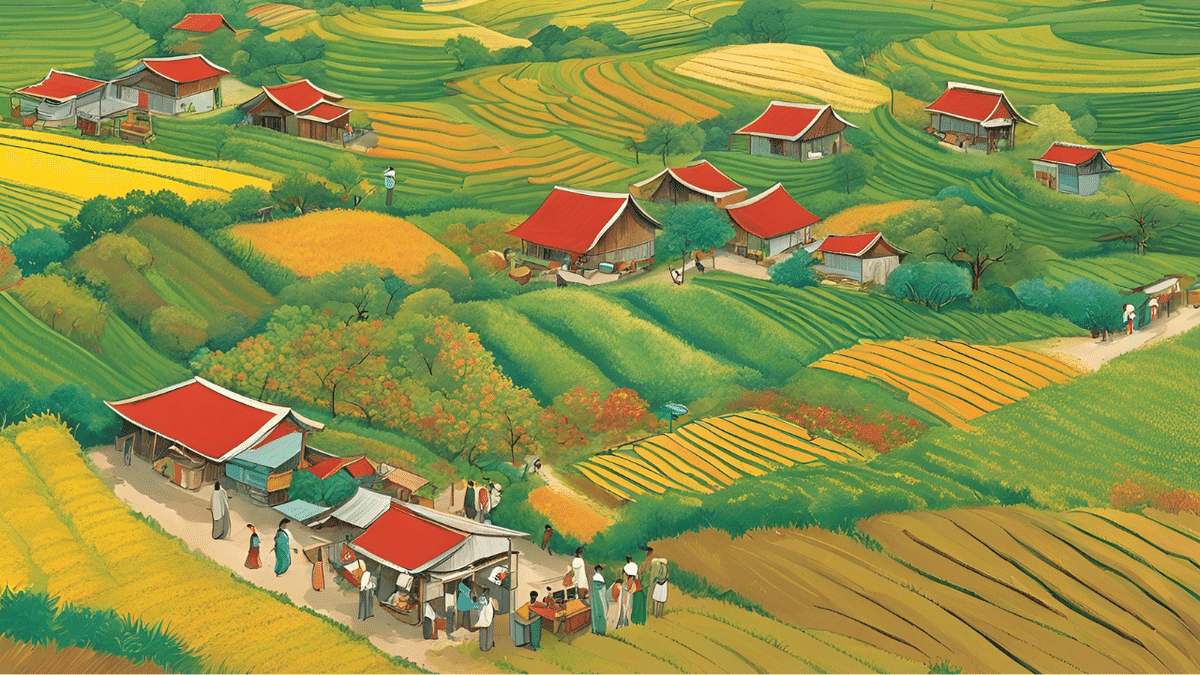
日本はその中で重要な役割を果たしており、両国間の経済的・社会的な関係を強化する基盤となっています。
この関係は、両国にとって相互に利益をもたらすものであり、今後もその発展が期待されます。

日本は将来の社会のために、より良い仕組みを構築していけるはずです。
#最近の学び #ベトナム #ホーチミン #ハノイ #スーダンカァウ #タインホア #ゲアン #ジェンチャウ #ダナン #国内労働市場 #少数民族 #共生社会 #毎日note #外国人就労者 #技能実習生度見直し #特定技能 #ベトナム語 #技能実習 #安全 #安心 #感動 #北海道 #外国人雇用
#雇用センター
