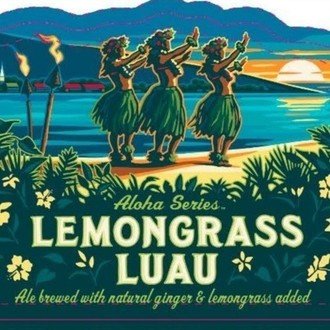読書記録2022 「スーパー猫の日」編
猫好きである。
小説家になりたいと思う気持ちの半分ぐらいは「猫を飼えるから」という願望が占めていると言っても間違いではない。
過去には家の庭に野良が居着いたこともあったのだけれど(この話を語ろうとすると、それはすなわち母への恨み言と繰り言を羅列することになるので割愛するが)、「うちで猫を飼ってます」と胸を張って言えるほどの経験がない。
とはいえ、何から何まで猫ファーストというような —— 猫の置物を飾るとか、猫がデザインされているものをとりあえず選ぶというような —— 猫好きではなく、実際に飼うことになったとしても猫べったりの可愛がり方などはしない、「猫は猫、自分は自分」というような、過剰に干渉することなどない真っ当な猫好きになるんじゃないかと思う。
猫と自分の将来像はさておき、2022年2月22日は2が6つ並ぶ特別な猫の日だそうである。
というわけで猫のスペシャルな日に合わせて、最近読んだ猫にまつわる本で、気に入っているものを挙げることにしました。
(計31冊中の26〜31冊目)
+ + +
『作家と猫』
平凡社・編 夏目漱石、谷崎潤一郎、石井桃子、佐野洋子、中島らも、水木しげる ほか
猫が主人公の小説が多いのは、猫と小説家仕事の相性の良さを表しているのだと思う。
猫が登場する小説——古くは漱石の『我輩は猫である』、ポーの『黒猫』に始まり、赤川次郎の『三毛猫ホームズ』のシリーズ、リリアン・J・ブラウンのシャム猫ココのシリーズ、重松清の『ブランケット・キャッツ』、有川浩の『旅猫リポート』と、パッと思いつくだけでもかなりの数がある。
猫が主人公だったり、重要な役目をする小説を書いた作家は、皆揃って猫好きで、だからこそ猫を小説に登場させたのだろうけれど、個人的には猫好きが書く猫にまつわるエッセイの方が面白いものが多いと感じる。
日本という国は世界的に見ても猫をやたらと可愛がる珍しい国らしい。
それは米作り・養蚕などから鼠の害を防ぐためだったり、鼠が船を齧ることから船を守るという四方を海に囲まれた国らしい理由で、猫が生活と近いところにいる存在だったからなのだそうだ。
それだけ近いところにいれば、生態や習慣も当たり前に目にする。
よく観察できるから余計にエッセイが面白くなる、という好循環なのかもしれない。
もっとも「よし、猫をネタにエッセイを書くぞ」と腕まくりしているというよりは、猫のことを書くこと自体が作家にとってはいい気晴らし、気分転換になるから、というのが真相であるような気がする。
本作は猫好きで知られる作家・漫画家等のエッセイ集成。
内容はもちろんどこを開いても猫、猫、猫だから、難しい顔をして読むことも理解に苦しむこともない。
最初から終わりまで頷いたり、ニヤついたりしながら楽しむことができる(中には猫嫌いのエッセイもあったりして、それがまた面白い)。
今はまだ我が家に猫はいないけれど、猫がいたらなるほどこういうことを書いてしまうのか、と肩の力は抜きっぱなし、日向の縁側の猫みたいになって読んでしまった。
+ + +
『猫ごよみ365日: 今日はニャンの日? 猫といっしょに季節のある暮らし』
トラネコボンボン 中西なちお
「猫が描いてあればとりあえず選ぶ、なんてことはない」と書いた指先も乾かぬうちにこういう本を選ぶのもどうかと思うのだが、この画集ともイラスト集とも分類できない本作は愛すべき一冊になっている。
「こよみ」とあるように、日めくりカレンダーのごとく1ページに1枚、猫が描かれ、毎日が猫の書いた日記のようになっている。
脚注の部分には「今日は何の日」的に二十四節気やこよみ、記念日等の説明が短く加えられているのだが、大半は人間のこよみの中にときどき猫社会における記念日や猫的見解が混ざり込んで、それにまたニヤッとさせられる。
ちなみに、今日、2月22日のページにはこうある。
「スペシャルデイ。猫の日なので新しいねずみを買ってもらった。新しいねずみ、毛がふわふわで最高。それと上等猫缶。アイスクリーム少し、コーヒー少し」
脚注には「日本の猫の日。各国それぞれでロシアは3月1日、アメリカは10月29日。」とある。猫も国それぞれなのだなあ。
著者の中西なちおさんは料理人兼作画家で、店舗を持たずに「トラネコボンボン」というレストランを主催している人なのだそうだ。
「作画」というとアニメーションを思い浮かべる人も少なくないかもしれないが、中西氏の描くのは漫画的な猫のイラストでも、写実的な絵でもなく、猫の特徴を捉えた「絵」である。
水彩やペン、クレヨンなど、アナログな絵画手法で擬人化した猫(椅子に座って足を組んで新聞を読むなど)をワインのラベルや宅配シールの残ったダンボールなど、様々な素材に描いている。
描かれた猫のサマが実に面白くて、ちょっとした時間に数ページ眺めるだけでも気持ちが少しだけ緩む。その時の自分が、まるで猫を眺めてる時の自分のようで、「猫がいたらなあ」という願望が一層強くなる。
作り方、考え方がとてもアート寄りだからかもしれないが、パッと見すごく体裁が良くて、僕のデスクでは国語辞典の隣のポジションを確保している。
猫好きの人にプレゼントしたらさぞかし喜ぶだろうと、バレンタインデーにチョコレートを贈ってくれた猫好きの友人一家へのお返しにクッキーとセットでこの本を送るべく、書棚には包装紙がかかったままのもう一冊が鎮座している。
+ + +
『猫語の教科書』 ポール・ギャリコ
ある日、ポール・ギャリコの元に意味不明の原稿が送られてくる。
暗号めいたその文面を解読してみると、なんと猫の猫による対人間マニュアルだった、という設定の本作。
中身の面白さはぜひ読んで楽しんでいただきたいが、とにかく猫を飼っていたら強く肯くであろうことばかりで、読んでいてもニヤニヤが止まらない。
人間は猫の下僕、地球の支配者は実は猫なのではないかと感じることがあるが、その裏で猫が本作のように巧妙に対人間マニュアルを持って人類を征服しようと目論んでいるのであれば、核保有国などよりはるかに怖い集団である。
冗談はさておき、本作を読むと、ギャリコの猫を観察する細かさと同時に、さすがO・ヘンリー賞を受賞した作家だなあと文章の上手さに感心する。
それにしても『ポセイドン・アドベンチャー』を書いたのと同じ人だとはとても思えない。これもまた猫のなせる技なのかも。
登場する猫がメスだからと、訳者は「〜ですのよ」みたいに女性言葉で訳したのだろうが、それは余計だったように思えて残念。教科書なら教科書らしく書き言葉で訳した方が良かったのに。それだけが残念。
+ + +
『文豪の猫』 アリソン・ナスタシ / 浦谷計子(訳)
小説家と猫の相性の良さは、NHKの『ネコメンタリー』を見てもぼんやりと感じてはいたが、本作を読んでそれが決定的になった。
今のところ猫と作家の相性の良さの要因は、書斎で年がら年中仕事をしていることと、基本的に一人仕事だということぐらいしか思いついていないのだが、可能性としては「作家は猫の相手をするのが精一杯という程度の社会性しかない」という暴論も浮かばないわけではない。
実際のところ、小説家という商売はかなり特殊だと思うし、他の表現者ともまた違う感じがする。それは例えば画家のように頭の中に浮かんだイメージを視覚化するのと、文字で伝え、読者の頭の中で再度イメージ化するという手法・方策の違いなのかもしれないが、小説家が一見すると高度に社会性があるように見えるのは、猫が普段凶暴さを隠しているのと同じようなものなんじゃないのかなと、チラッと思ったりもするのだ。
だとすれば、同類相憐れむ、類は友を呼ぶといった感じで、理屈でもなんでもなく、自然と引き合ってしまうものなのかもしれない。
本作は「文豪」と呼ばれる総勢45人の大作家たちと愛猫の写真に、それぞれの作家の猫にまつわる逸話、エピソードなどが集められている。
羅列すればこの通りだ(コピペで申し訳ないが)。
「アリス・ウォーカー / アレン・ギンズバーグ / アンジェラ・カーター / アン・M・マーティン / アヌージャ・チョーハン / ベリット・エリングセン / ベバリイ・クリアリー / 謝冰心 / カルロス・モンシバイス / チャールズ・ブコウスキー / チェスター・ハイムズ / ドリス・レッシング / イーディス・シットウェル / エリナ・グリン / エリザベス・ビショップ / アーネスト・ヘミングウェイ / ギリアン・フリン / グロリア・スタイネム / 村上春樹 / ヘレン・ガーリー・ブラウン / ハンター・S・トンプソン / アイリス・マードック / 大佛次郎 / ホルヘ・ルイス・ボルヘス/ジュディ・ブルーム / フリオ・コルタサル / カジム・アリ / リリアン・ジャクソン・ブラウン / ルイーズ・アードリック / リディア・デイヴィス / マーガレット・ミッチェル / マーク・トウェイン / マーロン・ジェイムズ / ニール・ゲイマン / パトリシア・ハイスミス / プリーティ・シェノイ / レイ・ブラッドベリ / レイモンド・チャンドラー / サラ・ジョーンズ / スティーヴン・キング / シルヴィア・プラス / トルーマン・カポーティ / アーシュラ・K・ル=グウィン / ゼルダ・フィッツジェラルド」
なんともすごいメンバーである。
これだけの人たちが揃って愛猫家だったのなら、小説家になるための第一歩は猫を飼うことなんじゃないのかと考えたくなる。だとしたら猫と暮らしたいがために小説家を志すのもあながち間違いではなさそうだ。
それにしてもねえ、揃いすぎでしょ、この面々。
+ + +
『ねこまたごよみ』 石黒亜矢子
冬場、冷えた寝室の空気の中、大急ぎでベッドに潜り込んで小説を読むのは毎年の楽しみの一つだった。
読んでも読んでも一向に朝がくる気配はなく、思う存分小説の世界に耽溺できる。小説読みにはたまらない季節なのである。
昔は小説の面白さは常に眠気に負けてしまい、読書灯は点けたまま、ともすれば本の間に栞のように指を突っ込んだまま寝落ちすることもあったのだが、年齢とともに眠りは浅くなり、最近では熱中しすぎると脳の興奮がおさまらなくて眠れなくなるようになってしまった。
とはいえゴロゴロしながら本を読む悦楽を手放すのはあまりに哀しい。
「だったら小説ではなく、写真集や画集にすれば良いではないか」と切り替えを図って見たのだが、写真集や画集はあまりに大きく、重い。仰向けに寝転がって眺めようにも、本の重さで真ん中から折れるわ、折れた真ん中が真っ先に顔に落ちてくるわ。眠る直前にスリルを求めているわけではない。
そんな試行錯誤を繰り返している最中に書店で平積みされているのを見つけたのが本作だった。
絵本は良い。大きいけれど厚くも重くもない。
しかも本作は年中行事を楽しむ擬人化された猫が山ほど描かれている。
ただの猫ではなく、猫又というのも洒落ている。
長生きして、尾が二つに割れた猫又ならば、年中行事を楽しむくらいのことはやってのけるはずだ。とまでは思わないけれど、眠りに落ちる直前に眺めるにはなかなか愉快なのである。
多分作者の石黒さんも意識していたのだと思うが、本作はいわゆる「屏風絵」と似ている。
ページを広げた中が一つの世界で、読者はそれを俯瞰して見ている。
中の猫又たちはページのあっちこっちでてんでバラバラに好き勝手なことをやっているのだ。
目線がページの中を動くたびに、違う猫又の様子を発見することになって、これが実に楽しい(「洛中洛外図屏風」をじっくりと鑑賞しているときの感じに似ている)。
子供じゃないんだから、絵本なんて一度見てしまったら飽きてしまうんじゃないかと思っていたが、本作は年中行事のなんたるかがわかっている大人の方が楽しめるような気がする。
考えてみたら書店の中でも児童書のコーナーではなく、美術書の一群の中においてあった。
我が家にあっては、ベッドサイドから置き場が移動する気配は当分なさそうだ。
+ + +
『猫のいる家に帰りたい』
仁尾 智 / 小泉さよ (イラスト)
短歌+エッセイ+イラストという構成の本作。
不覚にも収録された歌を読んでウルっとしてしまった。
冒頭にも書いたけれど、猫と人間の歴史は古い。
特に日本人には馴染みの深い、付き合いの長い動物だ。
実際に飼っているかどうかはともかく、生活の端々に猫がいてもなんら不思議とも思わず、路地を横切る猫を目にしたところで「ああ、猫がいるなあ」くらいにしか思わない。
すでに猫は人間社会の一部 —— 猫の側からすれば人間が猫の社会のシステムの一つなのかもしれないけれど —— になっている。
猫を「うちの家族」と呼ぶ愛猫家は多い。
僕としてはそこまで人間化してしまうのは猫には迷惑でしかないようにも思うのだけれど、一つ屋根の下で共に暮らしていれば家族の一員と感じるようになるのも当然といえば当然だ(「人ではなく、家につく」と言われる猫がどう思っているかはともかくとして)。
本作には猫と暮らす人間が猫に向ける目線の優しさが溢れる歌が多く収録されている。
著者ご本人の顔を存じ上げなくても、歌を詠む時の目の表情がどんなものだったかが容易に想像できるほど、著者の猫に向ける愛情は深い。
日本で生まれ育った身で、日本に根ざした「七五調」のリズムが無意識に染みているのか、エッセイよりもはるかに少ない文字数の短歌に詠まれた猫飼いの気持ちの方が、強く、ダイレクトに入ってくる感じがある。
時折見せる猫の滑稽さが乗り移ったようなユーモアや、人間よりもはるかに早く生涯を終える猫を見送る優しさまで、「心が温まる」というとあまりに陳腐で、使い古されすぎているのだが、そうとしか言いようのない「歌集」だった。
猫好きではなくても、本作を読んだら猫好きの気持ちはわかる、と言いたいところなのだが、猫嫌いの母に読ませたらと想像してみても、母が猫好きに変わるとは到底思えない。
実に残念である。
いいなと思ったら応援しよう!