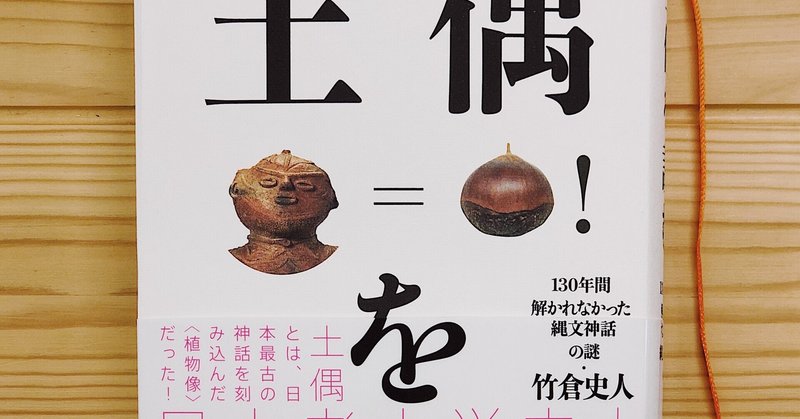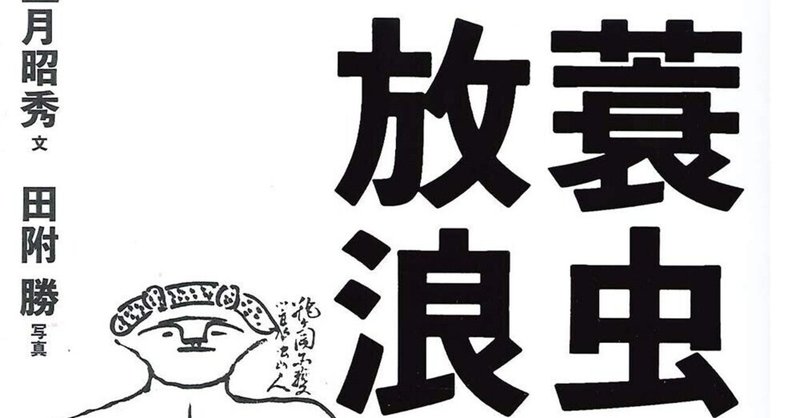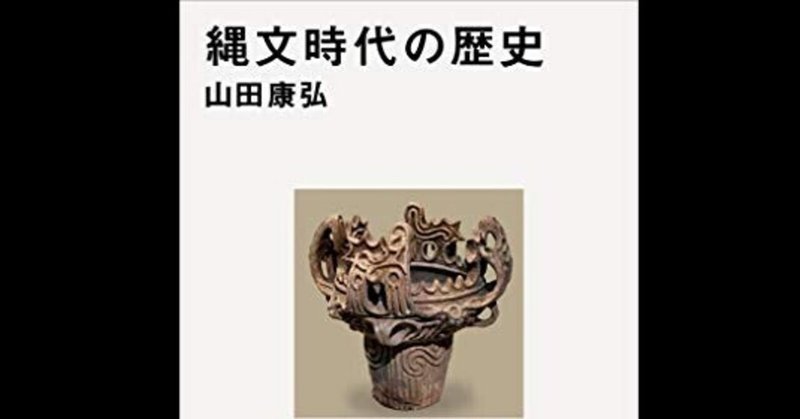記事一覧
「日本」は縄文人がつくった。小林達雄著『縄文文化が日本人の未来を拓く』が文化的遺伝子で解き明かす「日本」の意味
首都圏は非常事態宣言が続いていることもあり、なかなか縄文の異物を眺めに行けない日々が続いています。まあ博物館や郷土資料館は空いてるので、行こうと思えばいけるんですがね。
そんな事もあって、縄文不足を補おうとちょっと本で勉強しようと思い立ちました。ということで、まず読んだのは小林達雄先生の『縄文文化が日本人の未来を拓く』です。
現代から見た縄文文化の意味を200ページあまりに短くわかりやすくまと
縄文土器のマニアックな謎解きでありながら、現代社会を考えるヒントにもなる『縄文のマツリと暮らし』(小杉康著)
縄文が好きな理由は色々あって、第一は縄文の遺物の造形が好きなのですが、縄文社会がどのようなものであったのかという「謎」にも興味があります。農耕以前の社会はどのようなものだったのか、人々はどんな価値観を持っていたのか、それは現代のわたしたちの暮らしのヒントになるのではないか、そんなことを思ったりもするわけです。
そんなこともあって前回は小林達雄先生の『縄文文化が日本人の未来を拓く』を紹介しました。
残存する縄文的社会から贈与社会の平等と平和について考える『縄文の思想』(瀬川拓郎著)
考古学者・アイヌ研究者の瀬川拓郎さんが書いた『縄文の思想』。タイトルは縄文ですが、語られているのは主に弥生以降の時代の話です。縄文ファンとしては、「縄文の思想」と題された第四章を読めば済むと思いますが、三章までを読むと、そこに至る論理がより分かるという感じです。
弥生以降の周縁から縄文に思いを馳せる論を紐解くのは弥生時代から、大陸から弥生文化が流入したあとも縄文文化が本州沿岸部の海民と北海道に残
わたしたちは「縄文のイメージ」に惹かれている。そのイメージの成立と意味を考えれば、いま縄文が重要なことがわかる。ー『縄文ルネサンス』(古谷嘉章著)
「縄文ブーム」と呼ばれることもある昨今の縄文時代への着目。私もその流れに乗っているわけですが、なぜ現代の日本人の少なくない人たちが縄文の惹かれるのか。それは私もたまに考えたりすることではあります。
この本の著者である古谷嘉章さんは文化人類学者で、その視点からこの現象を眺め、これを「縄文ルネサンス」と名付けます。
この本自体がその意味について書いたわけで、詳しくは本を読んでもらいたいですが、簡単
縄文時代とは?定住とは?知ってるようでわかってなかった縄文時代「の」歴史が分かる本『縄文時代の歴史』(山田康弘著)
縄文時代に興味を持って色々見ていると、なんとなく縄文時代というものがわかってくる。草創期から晩期という区分とそれぞれの特色だったり、地域による違いだったりといったものだ。そしてそのバリエーションの豊富さにどんどんハマっていくわけだが、逆に、こんなにバリエーションに富んだものを一つの文化と呼べるのだろうかという疑問が頭をよぎることもある。
そんな疑問に答えてくれるのではないかと手にとったのがこの本
土偶が植物?説にはある程度納得するが、本には納得感がない『土偶を読む』(竹倉史人著)
縄文界隈で話題になった(ている)本『土偶を読む』、簡単に言うと、「土偶は植物(や貝類)を象ったフィギュアだ」という本。著者はこれまでのどの説よりも土偶について整合性のある説明をしていると豪語する。
そんなふうに豪語したもんだから、あらゆる方向から批判が向けられ、でも「新説」としてもてはやされもするという現象が起きた。
というわけなので読まなければはじまらないというわけで読んでみた。
最初に端