
IB教育は人間性を育む
こんな私も、パソコンを持ち込んでスタバであるとか、ドトールコーヒーであるとか、そういう場所で仕事をすることが良くある。
家にデスクがないわけでもないが、適度に雑音がある方が集中できるというのは不思議なものだ。
しかし、昨今、カフェで作業をするのは大人だけではない。
受験勉強的なことをしているであろう学生を良くみかける。我々の時代は外で勉強すると言えば、薄暗い図書館一択だった。
ずいぶんおしゃれになったものだ。
今日など、私の向かいに座っていたのは小学生らしき男の子と真っ白なふりふりのブラウスを着た母親だ。
子どもは防音ヘッドフォンのようなものをつけて鉛筆を走らせている。
IBラーナープロファイルの「バランスのとれた人」というのを思い出す。
休みの日くらい、外で遊ばせてやればいいのにと。(苦笑)
時代は変わったのだ・・・。
さて、IBの本部には、日本担当のIB機構職員経由で、「IBの候補校になりたい」という申請や問い合わせが届く。
どうやら国内も色々な自治体がかなり関心を持ち始めているようだ。
そんな中、先日、こんなニュースが流れた。
福島県の南相馬市が、「復興の担い手を育てたい」というビジョンで、IBに取り組むというニュースだ。
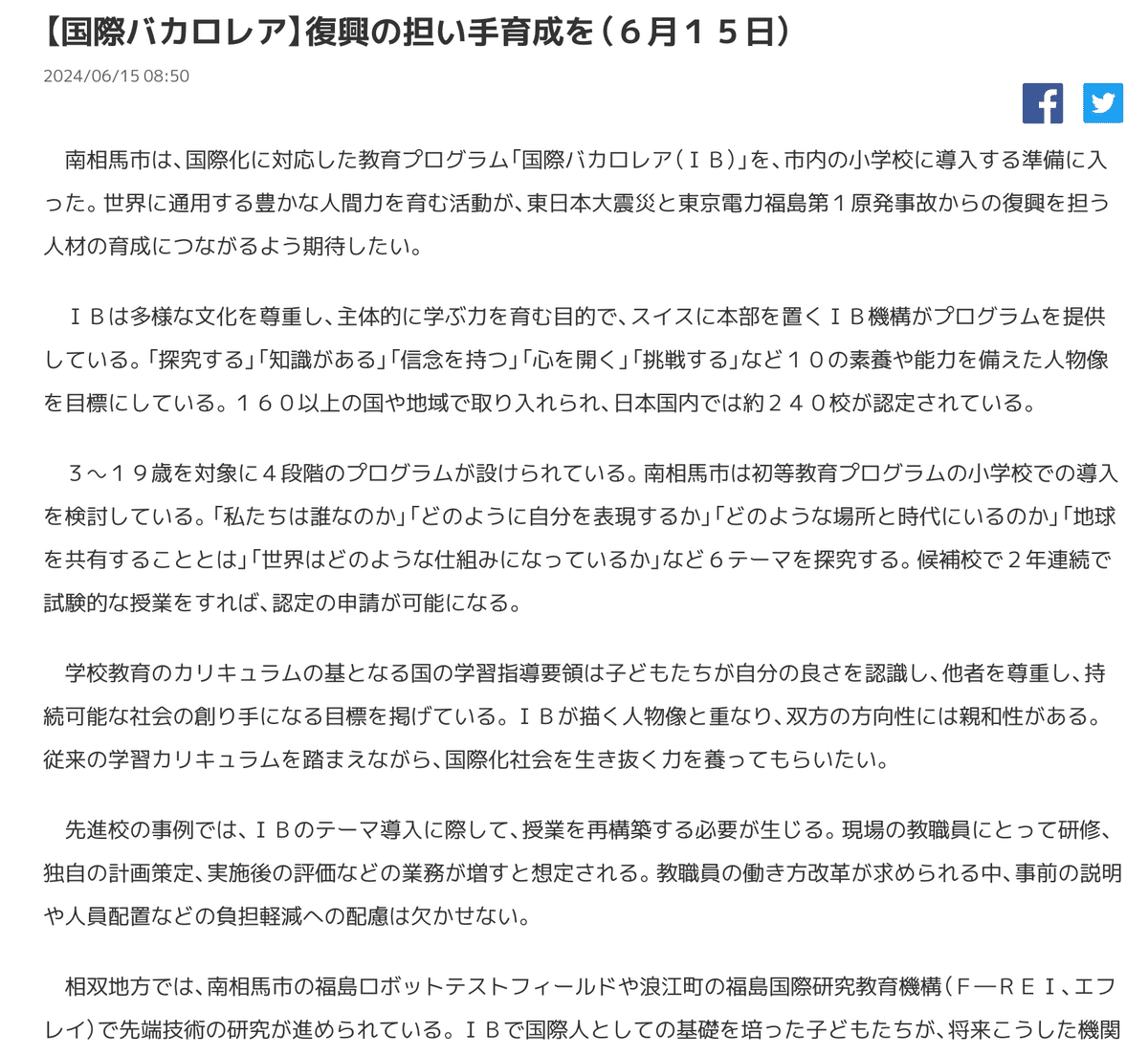
私は早速、総裁に情報共有した。
本部の幹部職員もとても喜んでいた。
IBの卒業生は有名大学に進学する生徒が確かに多いので、IB=アカデミックな成功、という印象を持っている人が多い。
間違っているとは言わないが、IB教育の目的は実はそれではない。
ビジョンにうたわれているのは
”Education for a better world”
教育の内容や質を上げることで、より平和な世界をつくることに貢献できる若者の育成をすることであり、その核は、「人間性の教育」だ。
今回、南相馬市の関係者がそういう視点でIBに取り組もうとしていることは本当に素晴らしい。
私も声がかかれば及ばずながら精一杯お手伝いをしたいと思う。
大人になっていくのに一番大切なことは
「ちゃんとした人間性を育むことだ」、
どうしてそういうことを大人はもっと声高らかに言えないのだろうか。
どうして、受験に合格するとか失敗するとか、偏差値がどうとか、内申点がどうとか、そういうメッセージばかりが優先してしまうのだろう。
先日、うちの3年生の担任が私のところにきて言った。「園長先生、今、子どもの人権についてのユニットをやっているのですが、子どもたちのエージェンシーがすごいんです。どんどん自分たちで調べて自分たちの考えをまとめています。こんな素晴らしい学びを学校の中だけで置いておくのはあまりに残念なので、メディコス(岐阜市のライブラリー)の部屋をかりて、地域の人にも発表できるようにしたいんですが、よろしいでしょうか、ひょっとすると少し会場費がかかってしまうかも知れなくて・・・」
私がダメだというわけはありません。
「いいね、ぜひそれはやるといいよ!」と言いました。
<担任からのメッセージ>
「ユニットで探究した事を地元コミュニティに共有することで、色々な人々に子どもの権利について知ってほしい。私たちのActionです。」
だそうです。笑
私がこのユニットで指導をしたのは、情報の集め方やインタビューの仕方ぐらいで、自分たちでそのスキルを使って色々な方法で探究をまとめている児童の姿にとても感動しています。
最近『探究やりたい!』を通り越して、『え、UOI(探究)の時に全部の教科(国語、算数、社会、理科、アート)について学ぶから、別に何時間目にこの教科をする、って決めなくてもよくない?』などPYP教育者みたいなことを言い出してきました笑

7月4日の午前に岐阜市のメディアコスモスでやるそうです。お近くの方、ぜひみにきてあげてください。
高学年クラスは岐阜出身の外交官、杉原千畝という人物がユダヤ人にビザを発行したという歴史的事実をもとに、それに関係した色々な人物、杉原千畝本人、奥さん、日本の外務省、ヒトラー、ドイツ人などそれぞれの立場で、「もし自分が○○だったら」というロールプレイを行い、意見交換をする授業だ。
IBがミッションステートメントの中で明記している
「人がもつ違いを違いとして理解し、自分と異なる考えの人々にもそれぞれの正しさがあり得ると認めることのできる人」を育てていくために、多面的なものの見方を経験させようとしている教師の意図が伝わってくる。
これらすべては、いわば「人間性の教育」だ。
この先のグローバルな時代を生きる若者に身につけさせるべきことばかりだ。
この先も、IB教育が目指しているものを正しく理解し、そのビジョンに向かっていこうとする教師たち、大人たちが増えていくことを願っている。
教育現場に生成AIを導入するとか、そういうのは今の所、私はまったく興味がない。
