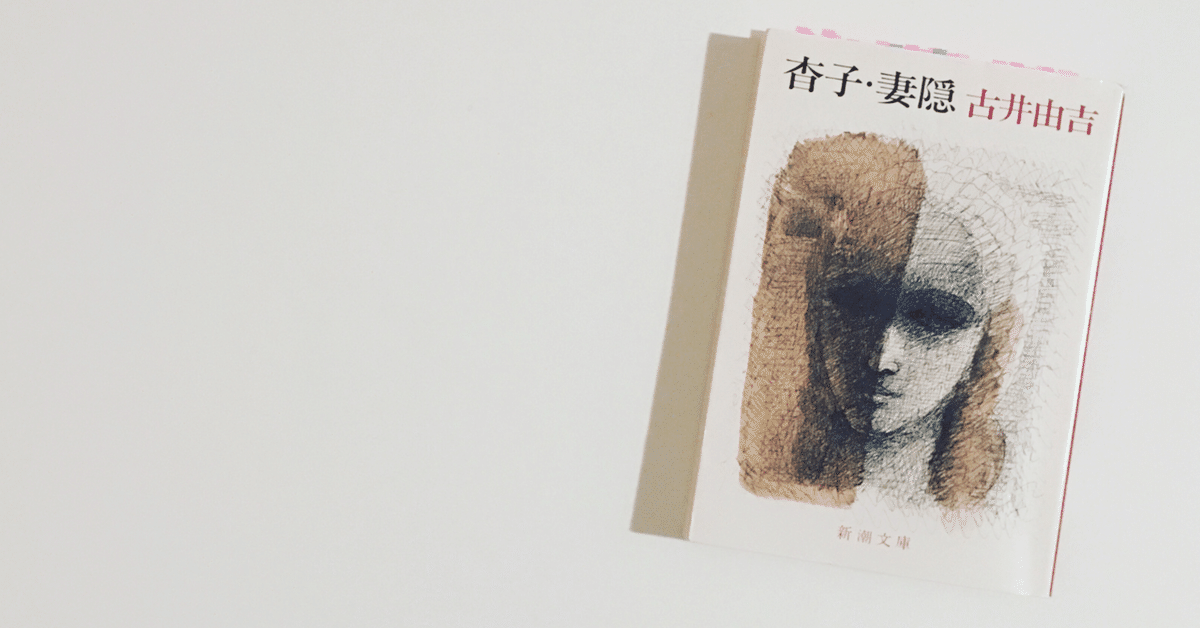
古井由吉/杳子・妻隠
「そうね、あなたの思っている人生というのは、そちらのほうなのね。でも、どんなに外の世界に応じて生きていたって、残る部分はあるでしょう。すこしも変わらない自分自身に押しもどされる時間が、毎日どうしたって残るでしょう。そこでいつも同じことを、大まじめでくりかえしているのよ。あたしの思う人生は、こちらのほうよ」
『杳子』を一読した時、上記の杳子の科白にどうしようもなく共感し、
著者である、内向の世代と称される古井由吉に、心の中で、
「内向の世代最高!内向の世代ありがとう!言葉にできない苦しみを表現してくれてありがとう!純文学ひゃっほい!」
と叫んでいた。(一部脚色、叫んではいない。)
その後、平常心を取り戻し、2回目3回目と読み重ねていくうちに、また違った角度からより深くこの作品を理解することが出来た(気がした)ので筆を取った。
それはもしかすると私自身が杳子の姉の側の人間になったことを意味するのかもしれない。成熟した女の側に。
※内向の世代とは
内向の世代(ないこうのせだい)とは、1930年代に生まれ、1965年から1974年にかけて抬頭した一連の作家を指す、日本文学史上の用語。
「60年代における学生運動の退潮や倦怠、嫌悪感から政治的イデオロギーから距離をおきはじめた(当時の)作家や評論家」と否定的な意味で使われた。主に自らの実存や在り方を内省的に模索したとされる。
代表的な作家は、古井由吉、後藤明生、日野啓三、黒井千次、小川国夫、坂上弘、高井有一、阿部昭、柏原兵三など。
"病気"と"健康"
「健康になるって、どういうこと」
「まわりの人を安心させるっていうことよ。」
古井由吉『杳子』は、"二十歳をすこし越えたばかりの"彼(S君)と同じ歳の杳子が出会い共に過ごした季節について描かれた作品だ。
病名は明らかにされていないが杳子は病気である、と描かれている。
Sと店で待合わせた際以前と同じ席に座る事に偏執的に拘ったり、慣れた道以外の道を一人で歩くことが困難だったり、外食の際ナイフとフォークで食事する事が困難である姿が描かれている。
彼はその様子をしばしば"失調"と表現している。
その病気が何であるのかは明確に描かれていないが、その逆である健康が何であるかについては杳子の科白でこう表現されている。
いいえ、あたしはあの人とは違うわ。あの人は健康なのよ。あの人の一日はそんな繰返しばかりで成り立っているんだわ。廊下の歩きかた、お化粧のしかた、掃除のしかた、御飯の食べかた......、毎日毎日死ぬまで一生......、羞かしげもなく、しかつめらしく守って......。それが健康というものなのよ。それが厭で、あたしはここに閉じこもってるのよ。
いまのあたしは、じつは自分の癖になりきってはいないのよ。あたしは病人だから、中途半端なの。健康になるということは、自分の癖にすっかりなりきってしまって、もう同じ事の繰返しを気味悪がったりしなくなるということなのね。そうなると、癖が病人の場合よりも露わに出てくるんだわ。
自分の癖の露わさで、相手の癖の露わさと釣合いを取っているのね。それが健康ということの凄さね
"少女"と"成熟した女"
先程杳子の科白に出てきた"あの人"とは杳子と九つ歳が離れた30過ぎの杳子の姉である。
この姉もかつては病気だったという。
この物語において"成熟した女"という存在として描かれている。
杳子はこの姉を嫌悪している。
姉を嫌悪しているというより、自身の中に同居している"少女"と"成熟した女"をはっきり自覚した上で、自覚しているからこそ、健康になって病気のことを忘れて"成熟した女"になってしまった姉を嫌悪しているのだ。
"境い目"においての"孤独"と"恍惚"
ここまで書いてきたことを見てはっきり言えるのは、杳子は自身の病気についてきちんと自覚したうえで、後退もしたくなければ前進もしたくない。少女のままでいたくもなければ成熟した女になりたくもない。その境界である今が一番美しいと気づいているという事だ。
《ああ、きれい》
彼の知らぬ間に、病気を内に宿したまま女として成熟していた。
病気の中へ坐りこんでしまいたくないのよ。あたしはいつも境い目にいて、薄い膜みたいなの。薄い膜みたいに顫えて、それで生きていることを感じてるの。
病気の中にうずくまりこむのも、健康になって病気のことを忘れるのも、どちらも同じことよ。あたしは厭よ。
ラストにいたっては、赤みをました秋の夕陽が沈む自然らしさと怪奇さの境い目に立ち静まり返る中細く澄んだ声で
ああ、美しい。今があたしの頂点みたい
と、つぶやくのだ。
これから病院に行くことで恐らく彼女の病気は快方に向かうのだろう。そして彼女自身それを自覚している。自身の美しさの斜陽と秋の斜陽、それぞれの美しさのピークが重なり息を飲んだ描写だ。
そしてまた、彼(S君)も杳子の孤独と恍惚に気付き、魅せられ、惹かれた人間だ。
道の途中で立ちつくす杳子の孤独と恍惚をや彼はつかのま感じ当てたように思う。
杳子の軀は病気を内につつんで、そのまま成熟して落着くことを願っている。
彼はいっそ杳子と一緒に彼女の病気の中へ浸りこむことを願った。
病気が快方に向かうことも、悪化することも、彼は望まなかった。良くなること、悪くなること、それはどちらも杳子を破壊することのように思えた。
"杳子"と"彼(S君)"
これまで杳子と彼女が内包する病気について書いてきたが、ここでは彼(S君)について、また、彼(S君)と杳子の関係について書いていきたい。
まず、彼(S君)についてだが、彼(S君)自身も健康とは言い難い。
あの頃の彼自身も、かならずしも尋常な状態にあったとは言えない。夏休みからもう学校にも出ないで、ほとんど家にひきこもりきりだった。
自分の《子供部屋》に閉じこもって、退屈を知らなかった。言ってみれば、これも自己没頭という病いである。
毎晩、彼は寝床の中で何を考えるわけでもないのに窓の白む頃まで寝つかれなかった。
二人の関係をいよいよ外にむかって閉ざしていくことに、彼は歓びを覚えた。
「入りこんで来るでもなく、距離を取るでもなく、君の病気を抱きしめるでもなく、君を病気から引っ張り出すでもなく......。僕自身が、健康人としても、中途半端なところがあるからね。」
「でも、それだから、ここでこうやって向かいあって一緒に食べていられるのよ。
そう、そんな彼(S君)だからこそ、杳子の、杳子の病気の共犯者になり得たのだ。
杳子を理解し、二人はより深いところで共鳴し合えたのだ。
彼が杳子と同じ歳というところも大きいのかもしれない。
子供から大人への過渡期。
二人は病み上がりの人間どうしのように、心の動きの曖昧さを許しあった。
彼がとまどえば、そのとたんに、杳子の振舞いはあまりにも物狂わしいものになってしまう。
二人の会話についても、きちんと目線は同じで杳子の感じ方を理解した上で返答をしているように感じる。
二人の会話でいっとう好きなシーンがある。
「君の癖なら、僕は耐えられるような気がするよ」
「二人とも、凄くなってしまえばいい」
「どんな癖だろうね。僕は健康人だから、わからない」
杳子も彼の言葉を誤解せずに受け止めた。
今のところ私史上イチの、プロポーズで言われたい言葉である。
二人は精神のところで触れ合っている。
だがしかし、全く同じ人間ではないし、個々の入れ物(軀)があり、境界があり、完全に一致することもなければ、浸ることも溶け合うこともない。
出来ない。
二人は依然として越えられない距離を間に置いて、お互いに沈黙の中からときどき見つめあい、それ以上の触れ合いを知らなかった。この頃から二人は頻繁に最初の谷底の出会いのことを語りあった。二人の話はたえず喰い違って、互いにつかみあえなくなり、長い沈黙をおいてまた最初から細々と出なおした。
"軀"と"輪郭"
この作品を開いてまず驚くのは夥しい数の"軀"という文字だ。
彼自身にとっても、自分の軀をじかに感じることのむしろすくない一時期だった。
杳子の軀はそのとたんに、ただ互いに見つめ合っていた時よりも、かえって彼にとって遠い、表情のつかみがたいものになってしまった。
そして素肌まで触れ合っていながら杳子をつかみ取れないでいる彼自身の軀も、ときどきふっと遠いものに、あわててたぐり寄せなくてはならないもののように感じられることがあった。
彼の軀は内側からの存在感を失って、不安な輪郭の感覚だけに瘠せ細っていった。
自分自身の軀のことを気づかせてやりたい、そして自分自身のありかを確にしてやりたい。
今まで疑ってみたこともない軀というものの現実味への信頼を逆に揺がされた。
彼は自分の軀が重みを失って、うしろへ置き残されていくような奇妙な感じを覚えた。すると、人の流れの中で自分のありかを確めて方向を見定めていくことが、すこしばかり困難に感じられた。
これは二人ともに軀を切り離して考え客観視している、入れ物としての感覚を感じる。
さらに特筆すべきは"軀"という漢字だ。
【からだ】を表す漢字は全部で5種あるそうだ。
【体】【軀】【軆】【躰】【體】
『杳子』にて頻繁に使われているのは【軀】だ。
これは、【むくろ=しかばね】を意味する。
軀と心の釣合いが取れず上手く歩くことが、上手く生きることが出来ない。
"谷底"と"海辺"
二人は深い谷底で出会った。
二人はお互いに途方に暮れると最初に出会ったこの時のことを思い返し、きれぎれな言葉で満たしあう。
谷底とはどんな場所か、二人の出会いとは何だったか。
なぜ二人は繰返し谷底の話をするのか。
沢山の岩がどれもこれも重く頑固に横たわっていて、お互いに不機嫌そうに引っ張りあって釣合いを保っている。
杳子は、その網の目にくりこまれてしまい身動きがとれなくなっていた。
その中で杳子は、
人間であるということは、立って歩くことなんだなぁ、
と思ったとある。
そこに彼(S君)はやって来た。
「麓まで連れて行ってください」
重要なのは"釣合い"というキーワードだ。
ある時、池のほとりで杳子は河原石を積んで塔をこしらえていた。
ここでも"釣合い"について描かれている。
杳子の石の積み方は非常に無造作で危うい釣合いを取っていた。
大小の順も、形の釣合いもかまわずに積まれていた。
それを見た彼(S君)は
塔はひと石ひと石、いまのせられたばかりのように動揺に怯えながら、全体として不安に満ちたなまなましい成長の気配を帯びて、空にむかって伸び上がり、さらに音も立てずに伸び上がっていくよう見えた。彼はふと杳子という存在を感じ当てたような気がして起き上がり、杳子のそばに行って一緒にかがみこんで石の塔をながめた。
その後、
「このままじゃ、だめだね」
と言うのだ。
杳子の病気を守りあいながら、二人は段々にまたあの最初の谷底のような、最初の喫茶店のいつも決まったあの席のような、二人だけの孤立した時間と場所の中へ押しこまれていく。そんな気が彼にはした。
生きることは釣合いを取ることだ。
自分自身の体と精神の釣合い、
周りの人間との関わりにおいての釣合い、
釣合いが取れなければ待っているのは途方もない孤独だ。
そして彼らを結びつけたのはこの孤独だ。
彼らは釣合いが取れないという点で結びつき釣合いを取っている。
二人して同じ反復に耽っていると、軀を合わせている時よりも濃い暗い接触感があった。しかしそれをお互いに見つめあう目が残って、暗がりの中に並んで漂って、お互いのおぞましさをいたわりあった。二度と繰返しのきかない釣合いを彼は感じた。
どうせ続かない釣合いをひと思いに崩してしまおうと、二人は軀を押しつけあい、ときどき息をひそめてはまだ釣合いの保たれているのを訝り、やがて釣合いの崩れ落ちる歓びの中へ奔放に耽りこんだ。
「今日は海辺に行きましょう」
海辺に二人が向かうシーンがある。
そこで杳子は岩の上に立っている。
谷底とは対照的に描かれており、光を感じる生命的なシーンである。
この作品において、1人立って歩くということは釣合いを取るということだ。
この後物語は終盤へ向かう。
この作品を読んで嫌悪する人も中にはいるらしい。
メンヘラな男女のよくわからない物語だと捉える人もいるのかもしれない。
もしかしたら生きていく上では、そちら側の方が良いのかもしれない。
だが、きっと杳子は言うだろう。
「そうね、あなたの思っている人生というのは、そちらのほうなのね。でも、どんなに外の世界に応じて生きていたって、残る部分はあるでしょう。すこしも変わらない自分自身に押しもどされる時間が、毎日どうしたって残るでしょう。
今この作品を平常な心で、こんな時期もあったと、振り返りながら読めている自分の成長に安堵した。
この作品に出会ったのは二十代前半、二人の、二人だけの孤独に泣きたくなるくらい共感した。
二人はこの後離れる予感しかないけれど、それでも彼らが過ごした季節はかけがえのないものであり
生涯忘れがたい輝きの季節だ。
他人同士でも人はここまでは理解し合える。
不可能を嘆くより可能性に手を叩きたい。
