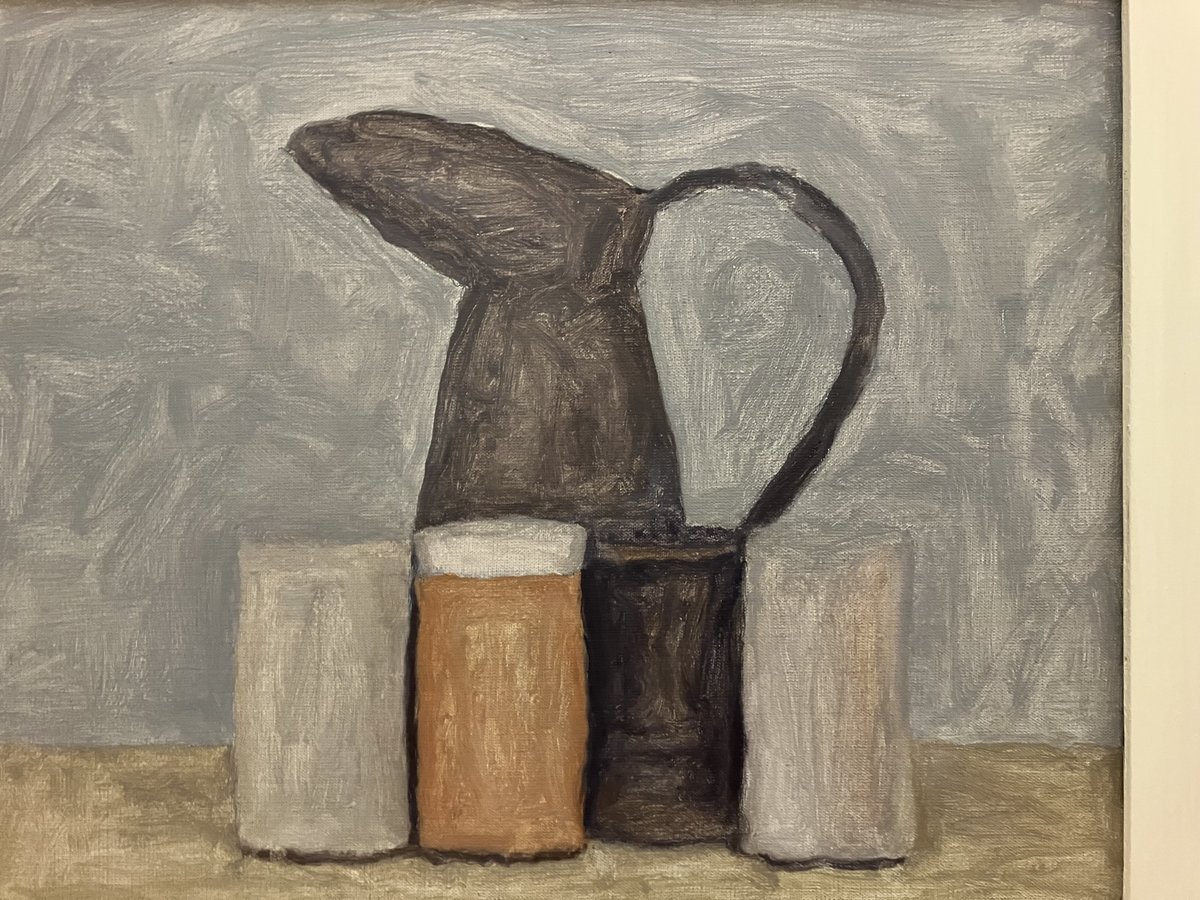聖堂とヴェネチアとモランディ・その1<旅行記シリーズ>
1・建築空間の一部としての絵(デッサン技術)

たとえばこのマンテーニャの天井画なんてどうだろう。埼玉の航空公園と、もう潰れてしまったが、渋谷の宮益坂にあったサイゼリヤでみた覚えがある。天井にあってはじめて効果が引き出される絵なので、画集で眺めてもつまらない。建築空間のなかで首を曲げ、天を仰ぎ見ると、いま自分のいるこの建物がはるか上方へつづき、ついに天空にむかってひらかれた開口部に天使たちがむらがっている。天界の人や鳥の姿もみえる。これがこの絵の主要な仕掛けなわけだから、ファミリーレストランで再現してくれるのはありがたい。
「同じサイズのものでも、遠くから見ると小さく見える」という法則を画面上で再現する方法論を「遠近法」というけれど、まさにこの遠近法によって、画面中央にむかってすべてが小さくなっていくように描かれている。「天上のひとつの点が世界のすべてを眺めている」という構造を身をもってあらわしてもいるから、この絵はつまり、一神教的な世界観と、技法的なからくりとが、造形的に重なっているともとれます。

絵の描き方を工夫する歴史のなかで、あるとき遠近法が開発される。
「芸術とか無駄だしマジメに語る対象にすらならない」といった旨を言い放った哲人(プラトン)の影や、「偶像崇拝はいけません、神の似姿をつくるな」という教条も鳴り響く西洋世界において、遠近法という「ロジカルな技法」が、絵を描くことを権威的にみせてくれた。権威という鎧をまとうことで安心してスタートできたのが美術芸術のアカデミックな歴史なんだとすれば、たとえば美術館学芸員が、だめな展覧会の企画に対して「こんなの見世物だ」と一蹴するのもわかる。見世物は大衆的な娯楽である。大衆は権威にとっちゃ「下」なのだ。
美術や芸術がエラいと考える立場の人ならカチンとくるかもしれないけれども、けれどやっぱり、デッサンというのは結局のところトリックアート技術だと思う。大衆娯楽的な響きではあるが、しかし絵が示す権威性というものが、「権威だぞ!オラ!」と観衆をどやし、上から力業でねじふせるケンカのテクの程度の高さによって観察されているのなら、それってすごく大衆的で、いい意味で野蛮なエネルギーだ。ハデに歌舞いてくれてはじめて、こっちも素直に「すげー!」とため息を漏らして面白がれる。


ローマには相当数の教会があり、僕はそれを不思議に思った。田舎なら、その村にひとつの教会があって、村とはつまり教区であり、村人たちはみんな、「その教会」の教会員だろうけれど、都会はそうではない。聖人ごとに教会があり、為政者ごとに教会が建つ。こんなお祈りはあちらで、あんな告解はこっちでと使い分けられる環境は、まるで多神教みたいだ。権現があって、稲荷があって、あちらにはサルタヒコ、こちらには阿弥陀如来。
相当数の教会があるおかげで、徒歩だけでいろんな聖堂をみてまわれるから楽しい。どの教会も巨大で、天井の高さだけでも神経が昂ぶるのに、さらに装飾は隅から隅までけばけばしい。床の大理石の複雑な組み方ひとつとっても途方もなく、息苦しくなりこそすれ、見飽きるということがない。カラヴァッジョやラファエロ、ベルニーニなど、名匠たちの実際の作品があちこちに顔を出す。しかも無料である。

たとえばこの絵にも遠近法は使われている。近くの人に比べて遠くの人のほうが小さい。柱のサイズも、奥にいくにつれ小さくなっていく。(天井の高さがぐにゃぐにゃした空間にはなぜか見えない。)
しかし冷静にみると変な床である。床の面が手前から奥まで見えすぎている。こんなに奥まで床がみえるなら、相当上から見下ろしていなければ道理が合わないはずだが、人々の体は正面からみているようだし、柱と天井が接するポイントも見える。

サイゼリヤの天井画じゃないが、実際の空間で実物をながめると疑問が解決される。この絵は人の背の高さよりも上に描かれているので、鑑賞するなら見上げないといけない。見上げる視線が、絵の中の床と沿うように描かれているので、画像だけみると変に立ち上がってるようにみえる床も自然にみえる。絵の中の柱と天井の接し方は、実際の体の動かし方を補強する。
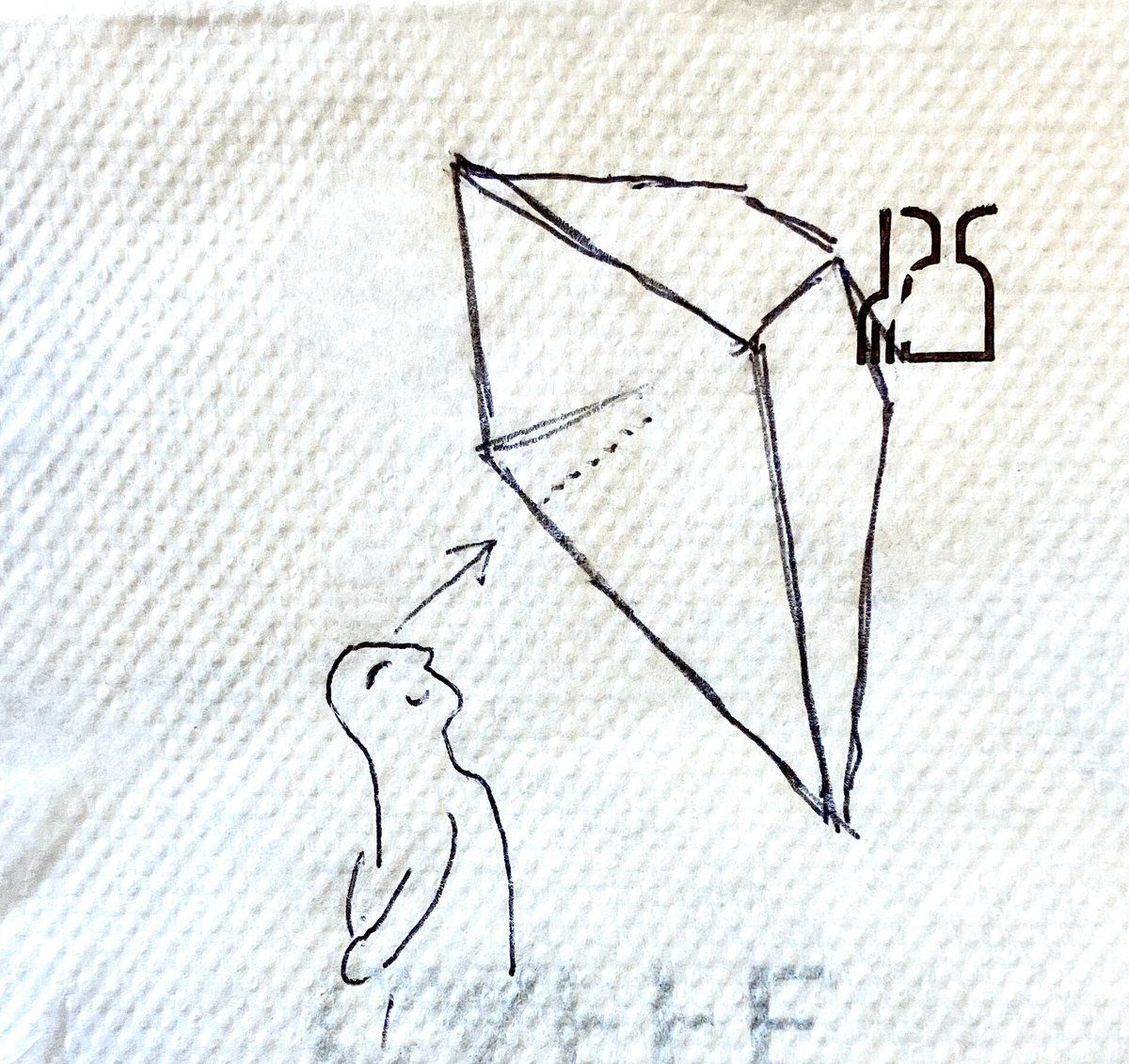
ちなみにこのラファエロの壁画はフレスコ画という種類の絵で、これは壁に塗った漆喰が乾ききらないうちに色の粉を塗り付け、壁材が完全に乾くことで色が定着して絵を完成させる方法でつくられている。まさに建築空間と一体になった絵である。
カラヴァッジョの絵にも建築空間との一体化をみた。


絵の中で設定されている光源の位置が、実際の空間のなかで絵に注ぐ光の供給源である窓の方向と合うように描かれている。
2・デッサン技術を学ぶ
「写真みたいなリアルさ」を指して絵の技術を評定する言葉と出くわすことがあるけれど、ここに至るまでの道のりは案外複雑である。
まず「写真(写真術)」という言葉がはじめて使われたとき、それは西洋的な絵の描き方、つまりデッサン的な技法を意味する用語だった。たしか司馬江漢だった気がする。
さらに、ヨーロッパでいわゆるカメラの技術が発達したころ、(全部が全部ではないにせよ)芸術としての<写真>を追求するために、絵画の構図にならって撮影されてもいたから、カメラのレンズがまず求めたリアリティは「絵画のようなリアルさ」だったともいえる。いろいろねじれている。
もっといえば、古典的な西洋絵画はリアルを目指していない。アイディアルを目指している。現実的なものではなくて、理想的なものを求めている。現実よりも数段うえの、崇高で美しいものを目指している。どの登場人物の肌にも、しみ・しわ・そばかす・ホクロ・傷跡・ムダ毛・キスマークなどはない。まるでSNSでの画像加工修正である。つるつるで大理石のような肌には、なんの汚れもほつれもない、上等な布がかかっている。堂々とした体躯の白人男性と、たおやかな白人女性が優美に絵画を彩る。町では当たり前のように見かけるはずの黒人の姿は登場しないから、歴史を鑑みずに素朴に昔の絵を見れば、ラファエロ時代と奴隷貿易時代が重なっているとは思いづらい。それに、圧倒的な主役「人物と布」、以外は、結構ずさんだったりする。犬も猫もかわいくないし、なんかへん。植物なんかもよくわからない。

つるつるの肌と布こそ、理想的な世界を表象する質感なのだ。昔の絵の表面はすべて物理的に平滑で、ゴッホみたいな絵の具の使い方の人はいない。窓からの光と蝋燭の揺れる炎しか光源のない世界では、筆の跡が荒く残っていると、単に絵がみづらくなるから、きっと喜ばれなかったろうけれど、それよりも、筆跡の消されたつるつるな質感が美しい、という感性も根にあるんだろうと思う。
デッサンでは、モチーフの明るい部分と暗い部分、日向と日陰をはっきり描き分けることが重要である。リンゴを描くなら、それがまず、ちゃんとリンゴっぽい、ごろんとした立体に見えなければいけない。石でできたリンゴなのか、木でできたリンゴなのか、青いリンゴなのか、黒いリンゴなのかは、まずはどうでもよい。色や模様や形状よりも、メガネを外してみるようなぼんやりさでかまわないから、とにかく明暗をとらえて立体感をつかまえる。

ニューヨーク近代美術館MOMAが、壁も床も天井も真っ白くて平らな空間(ホワイトキューブ)に美術作品を展示しはじめてから、それ以降のミュージアムはあとにつづいたけれど、ローマにある聖堂や宮殿はもっとずっと古いからホワイトキューブじゃない。再三繰り返すように、床や柱にもびっしりと意匠は凝らされ、壁に直接描かれた絵画は「絵画」として切り分けて独立させられるものではない。
「作品」としての独立した存在感があるのは、台座の上に置かれた彫刻だ。床の意匠と地続きな台座の上に、急にモノトーンの彫刻が、でん、とある。ミュージアム内あらゆるところに大理石彫刻がある。
白い大理石はつるつるに磨かれて、人物や布をかたどる。背景はない。白いだけだから明暗がくっきり見える。


デッサンを学ぶために、つるつるの大理石でできた単色の彫刻を描きとって修行するなら、明暗のみに集中する訓練にはなるし、人物と布の表現には役立っても、ほかのものを描写する技能は人物と布ほどには磨かれないから絵の中での主役脇役のメリハリが結果として自然にくっきりつくだろう。



大理石彫刻のありようが、西洋美術すべての根っこにかなり大きく影響していて、美しいから大理石を彫るのと、彫られた大理石が美のイメージをつくりあげるのとの両輪で、西洋的な美の感覚や、制作という観念が醸成されていったのなら、CREATEとは、泥が重なり土偶になることではなく、白い石を彫り出したら真実や理想が姿をみせるイメージをその意味の中心に据えていそうだ。
なんとなく、そんなふうに短絡したのだけど、きっかけは次の彫刻をみたことによる。エジプト美術としてしか知らなかったイメージが西洋的なアプローチでつくられているものをみたのだ。この違和感が引き金をひいた。「西洋らしさ」とは、要するに、その地域でとれる石の質感のことなんじゃないかという気がした。


このエッセーに登場するほかの情報と同様だが、こちらもうろ覚えの思い込み。トマス・ピンチョンの小説のなかで、ある登場人物が、こんなようなことを言うシーンがあった、たしか。「便器が白いのはどうしてだと思う? 自分の体内から出てくる黒いものの色を隠すためだ。白人の世界は、なるべく黒いものをみないようにできているんだよ。われわれの生活に実際には奴隷たちが欠かせないという事実にむきあうと気が悪いだろう。個室にこもっているときぐらい、われわれの白い肌の奥に黒いものがあるなんてこと、意識しないで過ごしたいんだ。」(読み返したら全然ちがうニュアンスである可能性が非常に高い。『重力の虹』のたぶん、下巻……)

3・ローマを発つ
この記事に写真が多い理由は、この文章があくまでも旅行記であることを伝えるためでもある。ローマ実地で考えたことを述べているのだから、いかにテキストが考え事の開陳であっても、語り手の心は旅のなかにある。
ローマでさまざまな聖堂へ行き、美術館に行き、圧倒されて疲れます。げっそりしながら食料を買うべく訪れたマーケットで殴り合いの喧嘩があって買い物どころではない。いそいそ退店し、男性器型の容器にいれられた酒をショーウィンドに並べる土産物屋を横切ればホームレスと仲のいい野良犬たちがくつろいでいる。そんな犬らと、どうしてか道にぶちまけられたスイカをついばむ鳩らに気を遣って道をいく。

ローマに留学中のけんちゃんは学問をやる生活なのだから、単に彼のところに泊めてもらうだけの僕とは関係のない時間を過ごすはずだ。忙しいだろう。当たり前にそう考えていたので、けんちゃんが僕と一緒にヴェネチアに行くつもりでいたとは、思いもよらなかった。
「ヴェネチアで超有名で超おおきな現代アートの展覧会をやってるから、それも絶対みようと思ってるんだよね」という心づもりを伝えていたのは、これはただオレの予定を伝えただけ。「一緒に行こうよ」なんて底意はなかった。宿のこともチケットのことも、全部ひとりで手続きしたあとで、「手続き完了したから無事この日は確実にヴェネチアにいる。だからこの期間は安心してローマでの研究生活に専念できますよ」知らせたらぶうたれられた。「え、一緒に行くんちゃうん?」「一緒に行こうやあ」「一緒に行ってくれへんの?」
急にどうした。めちゃくちゃしなだれかかってくる。そんなにさみしい思いをさせるスケジューリングだったか、ごめんごめん。
けどもう宿はとっちゃってる。だから別の宿をけんちゃんはとる。結果、お互い、同じ系列の巨大ホステルの別の部屋となる。都市によってはビジネスホテルが林立するように、旅人が多い地域となるとビルまるごとの規模のホステルが複数棟そろうことがあるらしい。
ローマで学問をやっている複数人が同居している家を出たのは早朝で、外はまだ真っ暗だった。スマホアプリでの操作を経由して動かすことのできるレンタルスクーターが町のそこここに駐車されていて、ターミナル駅までこれを利用すりゃ大丈夫だから!とけんちゃんが太鼓判を押すんで乗ったのに、エラーばっかりでてうまく使えない。足で走ったり二人乗りしたり、旅程にとって最も重要な「出発の便にのる」というタスクをおおあせりで追いかけ、ようやく仲良く駅に着く。ターミナル駅からヴェネチアまでの特急列車の指定席は、車両からしてまったく別々である。だって一緒に予約してない。それぞれ座席でぼんやりうとうとして、朝のヴェネチアにむかう。

ローマは、町じゅうに遺跡があり教会があり、そこには古代の芸術、古代からずっと守られ続けている芸術がある。古代だけでない。美術史の文脈に相当な存在感で君臨するマスターピースたちが豊富で、ここには観光資源・宗教資源としての活躍もみられる。さまざまな国からさまざまな人がきて、よろこんで、経済も動かすし評判を伝播してくれもする。ふらっと散歩した先にある建物にタダで立ち寄ったらカラヴァッジョがある町なのだ。
もしこの町に生まれ育っていたら、自分は絵を志しただろうか。やってらんないんじゃないだろうか。絵への馴染みはつくられるだろうけど、自分自身を「画家」と呼ばれうる立場に持って行こうと発想し、後戻りできない年齢になっても定職につかずに絵を描き続けるような人生を選んだだろうか。やってらんないんじゃないのか。やろうと覚悟するよりだいぶ前に、気持ちで負けちゃうんじゃないだろうか。この文化環境のなか生まれ育って、それなのに絵で戦ってこうと思える人は端的にヤバいし、しかもそれでちゃんと戦績を残せるなら本当にヤバい。ローマ出身じゃなくてよかった。イタリア出身じゃなくてよかった。

……そう思うと、イタリア生まれイタリア育ち、僕の説によりそってあおれば、「美術的環境が荘厳すぎて威圧的すぎて圧倒的すぎて絵で身を立てる発想そのものすらを思い浮かばせないような地域のなかで、しかしそれでも絵の道を選んだ作家」それはものすごいことだ。気合はいってる。