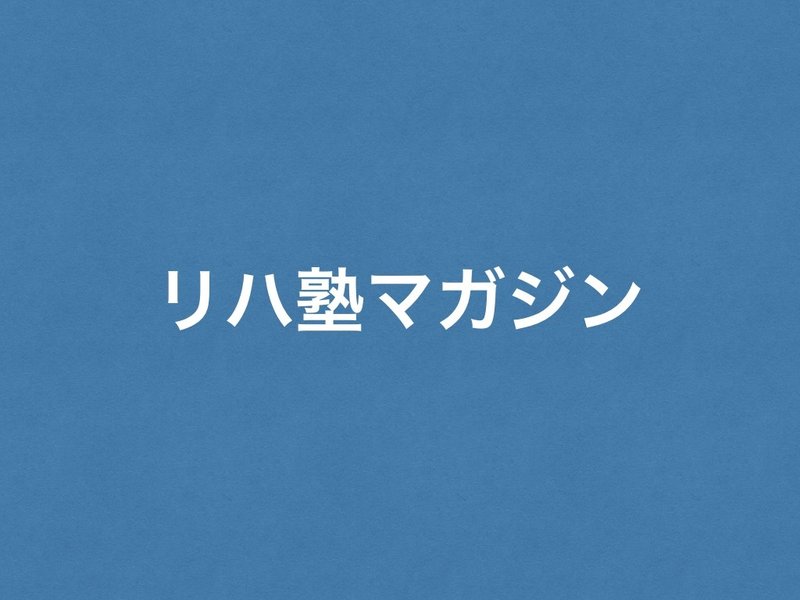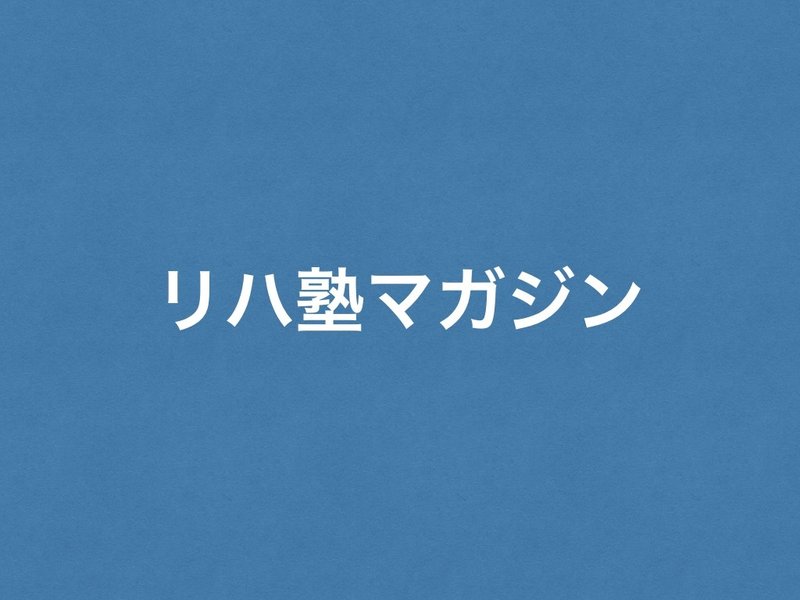頚椎症状に対するフローチャート【頚椎に対する苦手意識をなくそう】
火曜日ライターの松井です!
手指や前腕の痺れや痛み、筋力低下がある場合、自信を持って評価・介入することができていますか?
頚椎由来の症状が考えられる場合はもちろん整形外科テストを実施し、痛みの鑑別をしないといけません。
クリニックや整形外科医がいない施設では、理学療法士が整形外科テストなどの評価結果から必要なら医師へ報告したり、受診を勧めることが必要です。
また、手術をするような大きな病院なんかでは整形外科医がいるので理学療法士が細かく整形外科テストをするようなことは