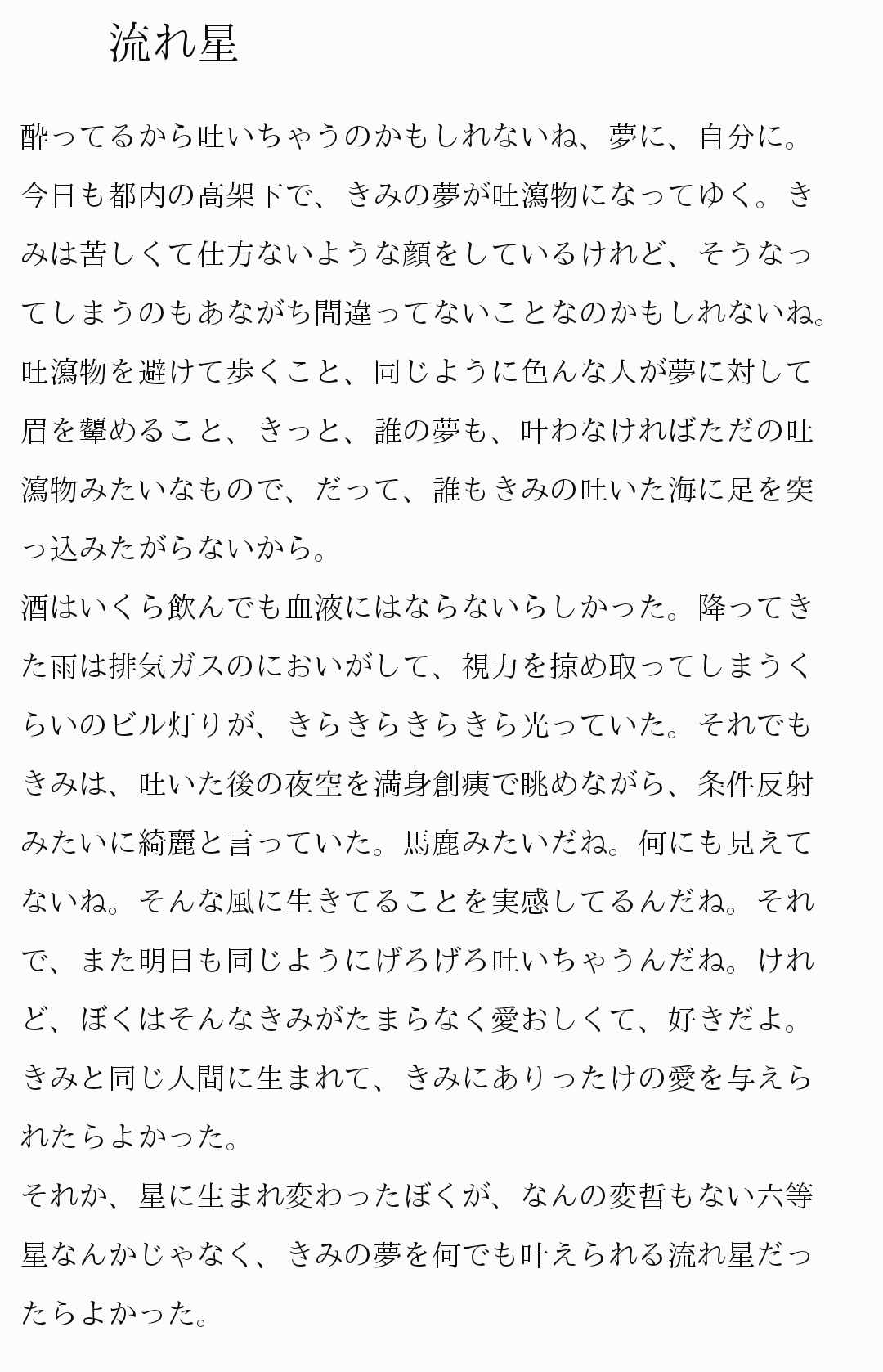【詩】流れ星
酔ってるから吐いちゃうのかもしれないね、夢に、自分に。今日も都内の高架下で、きみの夢が吐瀉物になってゆく。きみは苦しくて仕方ないような顔をしているけれど、そうなってしまうのもあながち間違ってないことなのかもしれないね。吐瀉物を避けて歩くこと、同じように色んな人が夢に対して眉を顰めること、きっと、誰の夢も、叶わなければただの吐瀉物みたいなもので、だって、誰もきみの吐いた海に足を突っ込みたがらないから。
酒はいくら飲んでも血液にはならないらしかった。降ってきた雨は排気ガスのにおいがして、視力を掠め取ってしまうくらいのビル灯りが、きらきらきらきら光っていた。それでもきみは、吐いた後の夜空を満身創痍で眺めながら、条件反射みたいに綺麗と言っていた。馬鹿みたいだね。何にも見えてないね。そんな風に生きてることを実感してるんだね。それで、また明日も同じようにげろげろ吐いちゃうんだね。けれど、ぼくはそんなきみがたまらなく愛おしくて、好きだよ。
きみと同じ人間に生まれて、きみにありったけの愛を与えられたらよかった。
それか、星に生まれ変わったぼくが、なんの変哲もない六等星なんかじゃなく、きみの夢を何でも叶えられる流れ星だったらよかった。