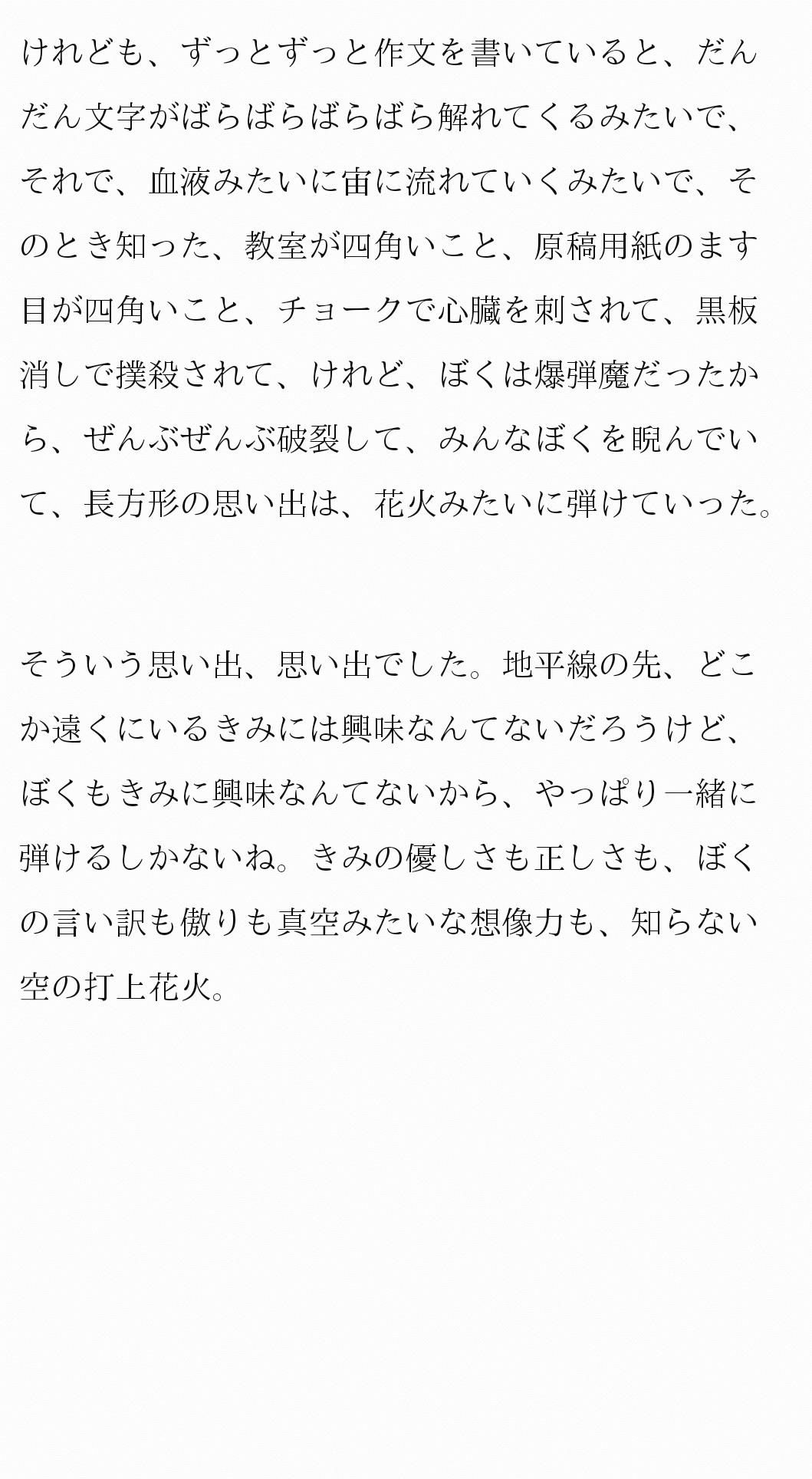【詩】感覚花火
弾けて、弾けて、言い訳さえも弾けて花火になれよ。
正しいものぜんぶが破裂して、すばらしいもの、すばらしくないもの、きっとそれぞれ色は違うけれど、すべて同じように花火だったらいい。どこかの誰かの恋だとか、愛だとか、きみが考えていること、ぼくが考えていること、くだらないことのなにもかも、ぜんぶぜんぶ着火して、閃光を噴いて、儚いだとかありきたりなこと、呟きながら死んでくれ、死んでくれよ。その死んでくれが、そのきもちが、誰にも無視されず、打ち上がること。けれども、なにもかもいつかは収束して、最期には、馬鹿みたいに光っただけのはなびら。
ぼくの認められないもの、ぜんぶ花火になれって思いました。
秋、教室で作文を書いていた。ぼくは、そのときだけ、自分が世界の中心にいるような気がしていた。手の震えが止まらなくて、瞼が熱く湿っていて、それでもなぜか、そのときだけ、みんながぼくのことをほんとうに分かってくれるんじゃないかって、そう思っていたんです。
けれども、ずっとずっと作文を書いていると、だんだん文字がばらばらばらばら解れてくるみたいで、それで、血液みたいに宙に流れていくみたいで、そのとき知った、教室が四角いこと、原稿用紙のます目が四角いこと、チョークで心臓を刺されて、黒板消しで撲殺されて、けれど、ぼくは爆弾魔だったから、ぜんぶぜんぶ破裂して、みんなぼくを睨んでいて、長方形の思い出は、花火みたいに弾けていった。
そういう思い出、思い出でした。地平線の先、どこか遠くにいるきみには興味なんてないだろうけど、ぼくもきみに興味なんてないから、やっぱり一緒に弾けるしかないね。きみの優しさも正しさも、ぼくの言い訳も傲りも真空みたいな想像力も、知らない空の打上花火。