
中小企業の職場改革:パタハラ防止で男性の育児休業を支援する方法
=男性の育児休業取得を阻むパタハラ問題に焦点を当て、中小企業が取り組むべき具体的な対策と、法的リスクを避けながら働きやすい職場環境を整えるためのステップを解説します。=
パタハラをなくし、働き方改革を進める!中小企業ができるパタハラ防止策
日本では、男性の育児参加が推進され、育児休業を取得する男性も増えています。しかし、現実には職場での偏見や育児休業の取得を阻む「パタハラ(パタニティハラスメント)」が、男性の育児参加を妨げる要因となっています。
特に中小企業では、育児休業を取得する男性従業員が少なく、育児休業申請時にプレッシャーがかかるケースも多く見られます。
パタハラは育児・介護休業法に反する可能性があり、企業にとって法的リスクにもなります。そこで、この記事ではパタハラを未然に防ぎ、育児休業を円滑に取得できる職場環境を整えるための具体的な対策を解説します。
効果的な研修の実施方法や職場風土の改善、育児休業を支援するための社内の体制づくりに役立つ情報も盛り込み、中小企業の人事担当者が現場で実践できる内容をお届けします。
パタハラの定義と重要性
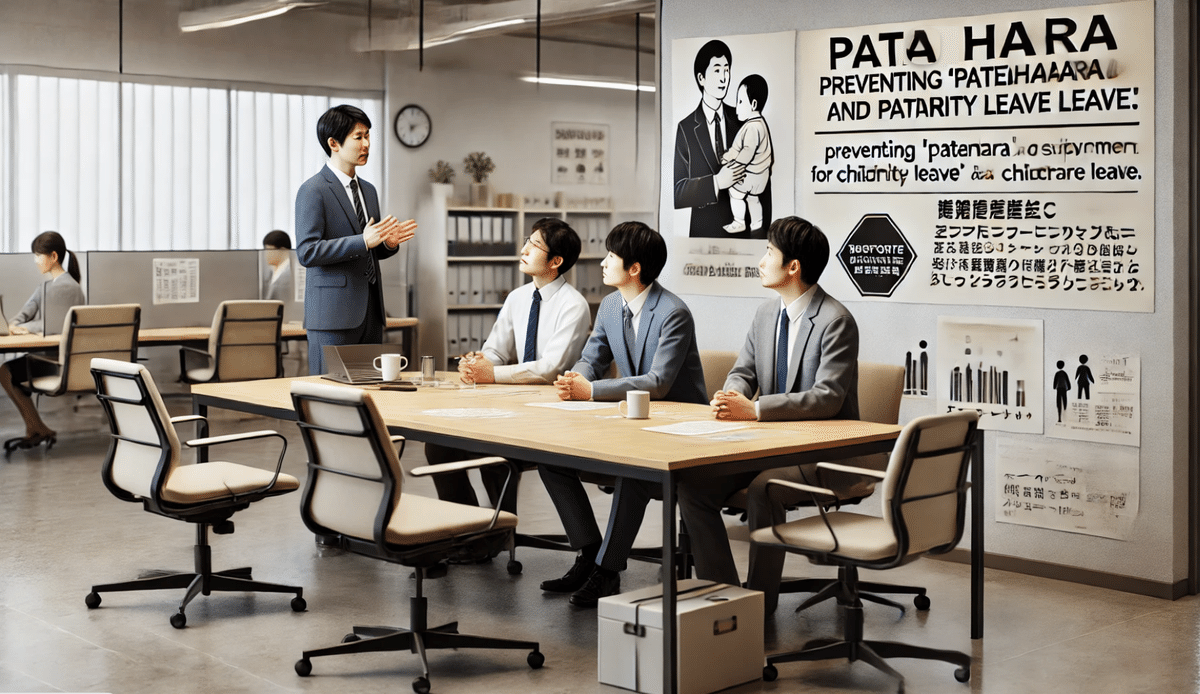
パタハラ(パタニティハラスメント)とは、男性が育児休業や育児に関する休暇を取得する際に、職場で嫌がらせや不当な扱いを受けることを指します。
これは、育児・介護休業法に反する行為であり、労働者の基本的権利を侵害する重大な問題です。日本では男性の育児参加が徐々に進む中、パタハラが男性の育児参加の障害となっている現実があります。
中小企業では、人手不足や業務の属人化が進み、特に男性の育児休業取得に対して「休まれると困る」といった声が上がりやすい状況です。
しかし、企業が積極的に男性の育児休業をサポートし、パタハラを防止することで、職場環境の改善や企業の成長に繋がります。
パタハラの具体的な事例

パタハラの形態には、次のようなものがあります。
1. 育児休業の取得を阻むプレッシャー
男性が育児休業を申請した際、「仕事を優先すべきだ」「男性が育休を取るなんておかしい」という圧力をかけられることがあります。
これは典型的なパタハラです。特に中小企業では、育児休業が業務に支障をきたすという懸念から、育休の申請が阻まれがちです。
2. 職場復帰後の不当な扱い
育児休業から復帰した後に、不当な配置転換や昇進の機会を失うケースもあります。
「育児休業を取るとキャリアに悪影響が出る」という偏見が原因です。結果として、男性従業員が育児休業を取得しづらくなり、家庭と仕事を両立させることが困難になります。
3. 育児参加に対する職場内の偏見
男性が「子どもの世話をするために早退したい」といった発言をすると、「男がそんなことを気にするのか」と揶揄されることがあります。
このような偏見は、男性が育児に積極的に参加しづらい空気を作り、職場の風土を悪化させます。
パタハラが企業に与える影響とリスク

パタハラは、企業に対して以下のような影響やリスクをもたらします。
1. 働き方改革への逆行
働き方改革が進む中、パタハラの存在は企業の働き方改革に逆行します。多様な働き方を認めることで、企業の魅力は高まりますが、パタハラがあると育児休業を取得する従業員が減少し、結果的に企業全体の士気や生産性が低下します。
2. 従業員の士気低下と離職率の上昇
パタハラが蔓延する職場では、男性従業員だけでなく、他の従業員も育児や介護に関する休暇を取得しづらくなります。
これにより、従業員の士気が低下し、長期的には離職率の上昇や新しい人材が集まりにくくなる傾向があります。
3. 法的リスクの増大
パタハラは育児・介護休業法や男女雇用機会均等法に違反する可能性があるため、企業は法的なトラブルのリスクを抱えます。
中小企業でも、法的トラブルは経営に大きな打撃を与えるため、パタハラ防止策を講じることが重要です。
パタハラ防止のための具体的な対策
1. 育児休業取得を奨励する仕組みづくり
企業は、男性従業員が育児休業を取得しやすい環境を整えるために、インセンティブ制度や育休取得者の表彰制度を導入することが有効です。
また、福利厚生制度として浸透しているで慶弔休暇の申請時に人事担当者から育児休業制度の説明をし、取得を奨励することも有効です。
経営層や管理職が積極的に育休取得を支援し、職場全体で育児休業を奨励することで、パタハラを防ぐ風土が生まれます。
2. 社内研修や啓発活動の実施
パタハラ防止には、ハラスメントに関する社内研修が有効です。管理職には、育児休業取得を支援するための研修を行い、職場の意識改革を進めましょう。
また、全従業員を対象に、育児休業の権利やパタハラのリスクについて理解を深めるための研修も実施することが重要です。
3. 相談窓口の設置
パタハラを未然に防ぐため、従業員が気軽に相談できる窓口を設けることが重要です。
特に匿名での相談を可能にすることで、従業員が安心してパタハラの報告や相談ができる環境が整います。また、相談内容に対して迅速かつ公正に対応する仕組みも必要です。
成功事例から学ぶパタハラ対策

ある中小企業では、育児休業取得を奨励し、パタハラを防止する取り組みが実施されました。育児休業を取得した男性従業員にインセンティブを支給し、職場復帰後も評価を維持する仕組みを導入することで、育児と仕事の両立がしやすい職場環境が整いました。
結果として、従業員満足度や企業の信頼度も向上し、離職率の低下や新しい人材の確保に成功しています。
まとめ

パタハラは、男性の育児参加を妨げる深刻な問題です。中小企業においても、パタハラ防止策を講じ、男性が安心して育児休業を取得できる環境を整えることは、企業の競争力向上や従業員満足度の向上にもつながります。
企業全体で育児休業を奨励し、職場のハラスメント防止体制を強化することが、従業員一人ひとりのワークライフバランスを尊重し、持続的な企業成長を支える礎となります。
今後も、パタハラ防止を含む働き方改革を進め、より多様で柔軟な働き方が実現できる職場環境を目指していきましょう。

貴社の未来を切り拓く、さらに深い洞察が必要な方へ。
この記事では触れきれなかった詳細な戦略や、実践に移すための具体的なアドバイスを深掘りしたコンテンツや中小企業の人事担当者に有意義な記事を用意しております。
中小企業の人事担当者として次のステップを踏み出すための貴重な情報を、下記のウェブサイトで詳しくご紹介しています。今すぐアクセスして、あなたとあなたの組織の未来に役立つ知識を手に入れましょう。

この記事を最後までご覧いただき、心から感謝申し上げます。
中小企業の人事担当者として、皆さまが直面する多様な課題に対して、より実践的なアイデアや効果的な戦略を提供できることを願っています。
皆さまの未来への一歩が、より確かなものとなるよう、どうぞこれからも一緒に前進していきましょう。
