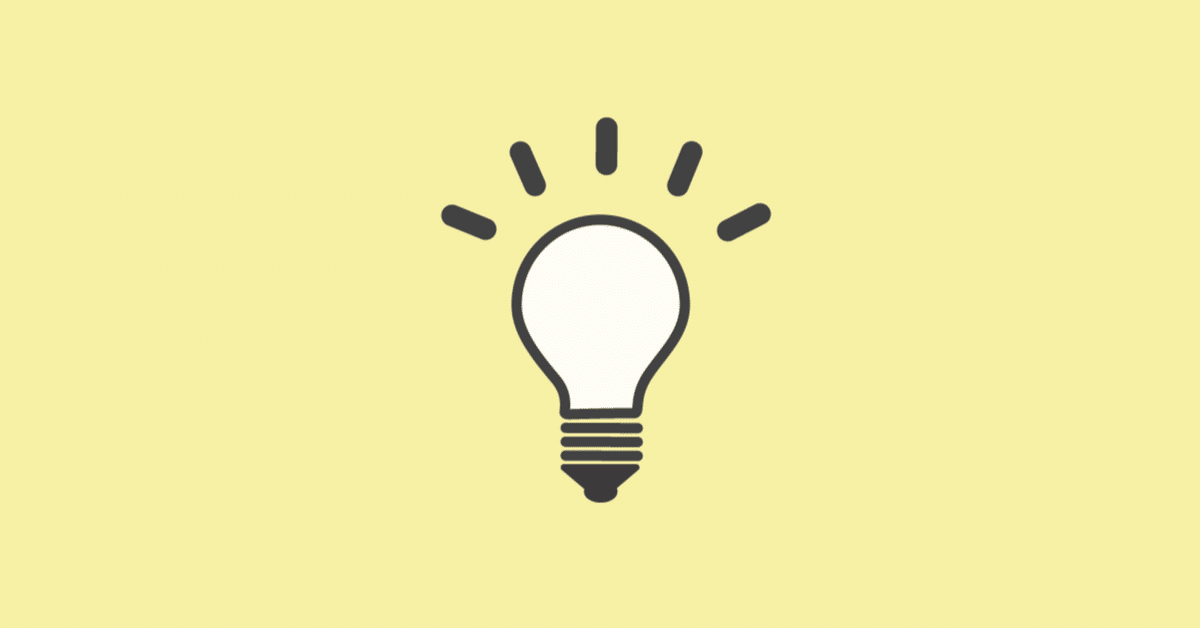
【仕事】ナレッジマネジメントでは検索履歴を活用する
(このnoteは2分で読めます。約2,000文字)
皆さんの会社ではナレッジマネジメントは実施されていますか?商用のナレッジマネジメントを導入している会社もあれば、エクセルなどでナレッジを管理している会社も多いかと思います。
私は前職時代にGoogle spreadsheetとslackを活用したナレッジマネジメントツールを自作していました。自作ツールでは、ナレッジをより多く蓄積する仕組みとして検索履歴の保存と分析をしていました。
このnoteでは、ナレッジマネジメントをする際に検索履歴を活用するという観点について書きます。
✅1、ナレッジマネジメントの必要性
『そもそも、ナレッジマネジメントってなに?』という方もいらっしゃるかと思います。ナレッジマネジメントとは、会社やチーム内の知識・知見を体系的に管理し、活用することができるようにすることです。
例えば、『○○のようにした方が、効率的に運用することができる。』という知見を組織全体に展開することによって、組織全体の生産性が向上します。また、同じことを何度も人に質問せず、ナレッジ管理しているツールで確認することによって、時間の効率化を図ることができます。
私の会社では、チームそれぞれでナレッジマネジメントをしており方法がバラバラでした。そして、どのナレッジマネジメントの施策もなんだかんだうやむやになりいつの間にか自然消滅していました。
✅2、自作のナレッジマネジメントツール
私もナレッジマネジメントの必要性を痛感していたので、チーム内でナレッジマネジメントをするよう提案しました。『じゃあ自分でやってみて。』という上司からのオーダーだったので、どのようにすればメンバーが使いたくなるようなナレッジマネジメントツールになるかを考えました。
ナレッジマネジメントツールが使われなくなってしまう理由はいくつか考えられますが、私が大きな原因だと考えたことはそもそもナレッジマネジメントツールに必要なナレッジがない、という根本的な問題です。
自分が『○○について知りたい』と思った時にナレッジマネジメントツールで検索して探してみます。しかし、欲しいナレッジが見つかりません。そういったことが繰り返されれば、当然そのツールは使われなくなってしまいます。
一方で、ナレッジを作る側は『何がナレッジとして必要かどうか』を調査してからナレッジを作るのではなく『これはナレッジマネジメントツールに入れておいた方が良さそうだ』という感覚で、ナレッジを作る場合が多いと思います。
ここに、ギャップがあると考えました。ツールを使う側が、知りたいと思っているナレッジが収録されていれば、ツールを使わなくなるということは避けられると考えました。では、ツールを使う側が知りたい情報はどう調べたら分かるのでしょうか。
そこで思い出したのが、『誰もが嘘をついている~ビッグデータ分析が暴く人間のヤバい本性~』という本です。
この本は、Googleの検索エンジンに入力する単語は、その人が本当に知りたいと思っている内容であるため、Google の検索エンジンの検索履歴を分析すれば、人々の本当の思考が見えてくるのではないか、というコンセプトで書かれている本です。
✅3、検索履歴こそ重要視すべきもの
ナレッジマネジメントツールで検索する単語こそ、ナレッジとして収録するべき内容のヒントになるのです。
よく、商用のナレッジマネジメントツールには、ナレッジが役に立った場合『いいね』する機能が設けられており、特に『いいね』をもらったナレッジが紹介される機能がついています。
特に参照されたナレッジを紹介する機能も大切ですが、もっと重要なのは、検索したが見つからなかった情報です。それこそが、ナレッジとして追加していくべきものなのです。
そこで、私は自作のナレッジマネジメントツールに検索窓を設け、そこに入力された単語をデータとして蓄積していきました。そして、ナレッジを探しても見つからなかった場合は『見つからなかった』というボタンを設置しました。『見つからなかった』ボタンがクリックされた場合は、その時の検索ワードがメンバーにslack経由で連携され、知っている人が回答するという仕組みを整えました。もちろん、その後ナレッジに追加していきます。
このように、ナレッジマネジメントにおいては、ツールの使い手がどんな情報を欲しているか、情報収集することが大切です。この作業を怠ると、ナレッジは溜まっていっているが、欲しい情報がないツールになりかねません。
✅4、まとめ
ナレッジマネジメントツールにおける検索履歴の重要性について書きました。アイデアは、『誰もが嘘をついている~ビッグデータ分析が暴く人間のヤバい本性~』を参考にしています。面白い本なので機会があれば読んでみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
いいなと思ったら応援しよう!

