
シン十割蕎麦

蕎麦好きが二人揃うと、二八蕎麦と十割蕎麦のどっちがおいしいかという議論になりがちです。そんなことを議論したところで結論がでないことは百も承知ですが、それでも顔を合わせるたびに議論してしまうのが真の蕎麦好きというものです。

二八蕎麦
二八蕎麦は蕎麦粉8割と小麦粉2割の配合だと言われています。それなら八二蕎麦と言うべきだとか、二八は蕎麦粉2割、小麦粉8割だという説もあります。現代の成分表の記載ルールでは、多いものから順に記載することになっているので、そんなことを妄想する気持ちは分かりますが、ニハ蕎麦は江戸時代から使われている名称です。ならばまずは江戸時代の文献を当たりましょう。

守貞謾稿
江戸時代の文化・風俗について調べる時に、研究者が真っ先に調べる文献があります。「守貞謾稿」です。
著者の喜田川守貞は1810年(文化7年)6月、大坂に生まれました。1837年(天保8年)に江戸・深川に移り、上方と江戸の文化・風俗があまりに違うことに驚き、当時の庶民の生活の様子を、江戸と上方の違いを交えながら、30年間にわたり全35巻に書き残しました。その記録は江戸時代には刊行はされず、明治になってから日の目を見ました。1600点にも及ぶ付図と、江戸と上方の違いを詳細な解説しているので、近世風俗史の基本文献として、重宝されています。

値段説
守貞謾稿によると、「二八そばは寛文4年(1664年)に始まり、値段が16文とのことである。慶応になって物価があがったので江戸のそば屋が役人の許可を得て値上げをして20文とし、またついで24文としたので、看板から二八を除いた。京坂も同じであろう。24文になっても三八とはいわない」とあり、ニハは値段であると記しています。うどんにも「二六」があり、「一八そば」や「三四そば」もあったようですから、値段説でいいと思います。
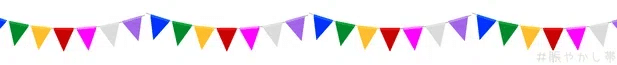
十割は打ちにくい
蕎麦粉八、小麦粉ニの蕎麦と十割蕎麦では、混ぜ物なしの十割がおいしいような気がするのですが、二八の方がおいしいという人はたくさんいます。また、十割では蕎麦職人が打ちにくいから二八がいいんだとか。なぜ十割が打ちにくいのかと調べてみると、蕎麦粉には粘りの素であるグルテンの含有量が少ないので、生地が伸びにくく、ボソボソになりやすいからだそうです。ちなみに、小麦粉を繋ぎに使うようになる前は、ご飯のおねばや、豆腐を繋ぎに使っていたようです。

糯性
生地に弾力がなく、ボソボソなら、弾力があって打ちやすい生地にすればいい。その考えから小麦粉などの繋ぎを混ぜるようになったのですが、繋ぎを混ぜる以外にも方法はあります。弾力があってモチモチのソバ粉を使えばいいのです。簡単なことですね。
イネ科のイネ、トウモロコシ、オオムギ、コムギ、アワ、キビ、ソルガム(タカキビ・モロコシ)、ヒユ科のアマランサスには糯性種があります。もち米は稲の糯性種だということです。✳️ 糯とは、通常種よりも粘り気が多い穀類の総称です。 糯をつくと餅になります。対義種は粳です。
糯性種の特徴はそのモチモチした食感と粘りにあります。その粘りはアミロースという、デンプンに含まれる炭水化物ポリマーに関係しています。そのアミロースが多いほど食感が硬く、粘りが少なくなります。アミロースが多い米が、日本人が主食にしているうるち米です。逆にアミロースが少ないと柔らかく、粘りが出てモチモチになります。

GBSS-I
そのアミロースの量は、米や麦などに含まれる【デンプン粒結合型デンプン合成酵素granule-bound starch synthaseⅠ】略してGBSSの中のⅠ型酵素が機能しているかどうかで決まります。
このGBSS Ⅰ酵素はデンプンを合成する最終段階で働く酵素で、正常に機能するとアミロースを合成します。GBSS-Ⅰが正常に機能しないとアミロースが作られず、モチモチの糯性になります。
米や麦に糯性種があるのだから、「糯性種のソバがあれば十割蕎麦が打ちやすいのではないか」と、ずいぶん前から考えられていました。

糯性ソバ
米や麦をはじめ、イネ科の植物は、そのデンプンの性質上GBSS-Ⅰが機能せずに糯性になることがよくあります。一方、ソバのデンプンは元々ウルチ形質でアミロース含有量が高い上に、糯性種が見つかっていません。
ただ、イネ科の糯性種がそうであったように、突然変異でアミロースが少ない個体が生まれる可能性はあります。イネ科の糯性種は突然変異を人の手で固定したものなので、ソバのGBSS-Ⅰ突然変異体探しは長年続けられてきました。しかし、それはとても難しい作業でした。なぜなら、イネなどの主要穀類が自殖性(自家受精=その個体だけで受精が完結する)なのに対して、ソバは完全他殖性なので、他の個体との受粉でなければ受精しません。
自殖性ならば、突然変異の個体が代々自家受精することで、何代かに亘って突然変異を発現させ続ける可能性があります。つまり、比較的見つけやすいのです。しかし、完全他殖性では例え突然変異が発現しても、次の代には他の個体と交配することで、突然変異が消えてしまうのです。つまり、見つけにくいということです。

ゲノム解析
やはり糯性ソバは夢なのかと思われていたのですが、2023年、京都大学、理化学研究所などの研究チームがソバのゲノムを完全解析し、道が開けました。
ゲノム解析とは、DNAの4種類の塩基(A,T,G,C)の配列を解読して、遺伝情報を総合的に解析することです。その解析で、ソバにはアミロースを生み出すGBSS-I酵素に係わる遺伝子が5つあり、そのうちの2つがソバの実の部分で強く働いていることが分りました。
そこで、種子に化学薬品をかけて様々な変異を起こさせた5801個体から、実の部分のGBSS-I酵素に係わる2つの遺伝子(仮に遺伝子A・Bとします)のうち、遺伝子Aが機能しなくなった個体と、遺伝子Bが機能しなくなった個体を見つけ出しました。そしてその2体を交配させて遺伝子A、遺伝子Bの両方が機能しない個体が生まれました。その個体がつけたソバの実は、狙い通りの糯性でした。尚、同研究グループは自殖性ソバの開発にも成功しています。

ゲノム編集食品
糯性ソバはいわゆるゲノム編集食品で、遺伝子組み換え食品ではありません。日本では、ゲノム編集食品は7種が登録され、そのうち4品種が市販されています。その中でも、GABA(アミノ酸の一種で、神経伝達物質として脳の興奮を鎮める働きがあります)トマトはスーパーで手軽に買え、概ね好評です。
他に、可食部増量マダイ(上の写真)というのもあります。これは、筋肉細胞の増加・成長を止める役割を果たすミスタチオンという遺伝子を壊し、筋肉増加のストッパーを無効にします。その結果、体の厚みが増し、可食部が平均して1.2倍に増加します。

シン十割蕎麦
すでに糯性ソバの特許は申請済みで、京都府木津川市の京大付属農場で何度か収穫しています。ごく近い将来にモチソバが流通する可能性は高いと思います。
モチソバのモチモチ具合によってはモチソバ十割ではモチモチ過ぎるかも知れません。その場合は既存のソバ粉とブレンドすることになります。それでも十割蕎麦に違いありませんが、あるいは既存の蕎麦粉が八、モチ蕎麦粉が二でシン二八蕎麦と呼ぶのかも知れません。
シン十割(シン二八)蕎麦を食べてみたいと思いませんか? それとも、そんなものは食べたくないですか?

「壬生義士伝」の握り飯
《 勝手にご飯映画祭⑤ 》

▶ 武士道の義と勇
▶ 義の握り飯
▶ 自分だけが正しいわけじゃない
▶ 命をかけても護りたいもの


