
先人の心が生んだ言の葉に、現代の職人が形を与える!千年の時を超えて「和歌イメージブローチ」が出来るまで。
和歌が日常的に詠われていた時代に思いをはせて、詠み手と和歌をもっと身近に感じてほしい!
みなさま、こんにちは!
歴史大好き・ミュージアム部プランナーのささのはです。
突然ですが、みなさまに問題です!
政権が確立された時期が史料に残っている奈良時代から先、日本史上でどの時代が一番長く続いたかご存じでしょうか?
正解は……平安時代!
よく長らく続いた政権として語られる江戸時代の約260年に比べて、平安時代はなんと約390年間(桓武天皇の平安京への遷都~鎌倉幕府成立まで)!!約130年長く続きました。

平安時代と言えば、華やかな十二単、平仮名・片仮名の誕生、女流作家たちによって描かれた文学の世界、中期以降に確立した国風文化、末期の治承・寿永の乱(いわゆる源平合戦)などなど、大変興味深い歴史上の出来事・文化が盛りだくさんの時代。
そんな中でも、「和歌」は現代人にとって一番親しみ深い”平安時代を象徴するもの”のように感じます。

懐かしいですね……!
唐歌(漢詩)に対して「やまと歌」「倭歌」とも呼ばれた和歌。
日本最古に詠まれた和歌は、なんと神代、日本神話界での知名度上位を誇るスサノオノミコトによるものと言われているのだとか!
ちなみに彼が詠んだと伝わる歌は、
夜久毛多都 伊豆毛夜幣賀岐 都麻碁微爾 夜幣賀岐都久流 曾能夜幣賀岐袁
と、微妙にヤンデレちっくなものでした……。
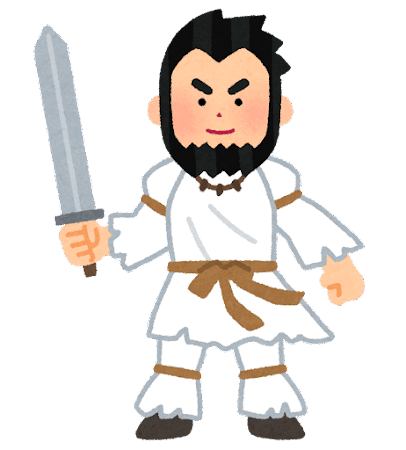
約束通りクシナダヒメを迎え入れることが出来てホクホクなのが目に浮かびます◎
スサノオの情熱的な言葉から始まった「和歌史」に、大変重要な出来事が起こったのは平安時代初期のこと。
天皇・上皇の命によって製作された勅撰和歌集「古今和歌集」の序文のひとつ・通称「仮名序」にて、土佐日記の作者としても有名な紀貫之により
やまと歌は、人の心を種として、
よろづの言の葉とぞなれりける。
から始まる、仮名文字による日本初の文学論が書かれたのです。

人の心が生み出した短い言の葉は、千年の時が流れても色あせず、輝かんばかりに美しい……。子供時代に親しんだ小倉百人一首の思い出の先、大人になった皆さまに、改めて和歌の真価にふれる入り口をご提案したい……!
そんな想いから、歌人たちに畏敬の念を表し、彼らが詠んだ和歌をモチーフに、上品かつ華やかにきらめくブローチを作ってみました。

ミュージアム部
雅を身にまとって 男性歌人が詠んだ和歌イメージブローチの会
月1個 ¥2,900(+10% ¥3,190)
※1個だけ(1ヵ月だけ)の購入も可能です。
※詳しくは「初めての方へ・お買い物ガイド」をご確認ください。
ブローチにすることを思いついたのは「人前で頭髪をさらすことを恥ずかしいこととし、貴族の男性であれば公的な場では冠を、私的な場では烏帽子を被っていた」という平安時代の慣習から。
現代の帽子を彼らが詠んだ和歌で彩ることができたら、絶対素敵だと思ったのです!

早速ではございますが、どんな和歌にインスピレーションを得たブローチが完成したか詳しくご紹介いたします◎
【菅原道真が詠んだ歌より「梅と東風」】

ひとつめのブローチは、学問の神様・菅原道真が詠んだ和歌よりインスピレーションを受けた「梅と東風」。
咲き誇る梅と、優しく東から吹く春風をデザインに落とし込みました。

この歌は時の左大臣・藤原時平による流言や、菅原道真を敵視する有力貴族たちに呼応した醍醐天皇により、大宰府に左遷されることになってしまった道真が詠んだものとして知られています。
歌に詠まれているのは、道真の自宅である紅梅殿に咲いていた梅です。道真は幼いころから梅を大事にしていたようで、伝承によるとわずか5歳の時に梅にちなんだ和歌を詠んだそうな……。
道真の絶筆とされる漢詩「謫居春雪」でも、雪を白梅と見間違えるという描写があり、彼が最期まで梅のことを大事に想っていたことがしみじみと伝わってきます。
ちなみにこのお花にまつわる有名なお話に、道真を慕った梅が空を飛んで後を追いかけ、太宰府にそのまま根付いたという「飛び梅伝説」があります!
道真と梅、完全に両思いですね……!

専用の台紙にセットしてお届けします!
【藤原道長が詠んだ歌より「空に浮かんだ望月」】

ふたつめのブローチは、平安時代を代表する作家・紫式部を重用したことで有名な藤原道長が詠んだ和歌よりインスピレーションを受けた「空に浮かんだ望月」。
かかろうとする雲すら弾くように強い光を放つ満月は、かつて道長が誇った栄光を思わせます。

自らの娘たちを次々に天皇に嫁がせて権力を握った藤原道長。彼の三女・藤原威子が天皇に嫁いだ1018年10月16日に開かれた宴で、空に浮かぶ満月(当時使用していた太陰暦は月の満ち欠けに則っていたため、15日前後=満月の日でした)を見ながら詠んだ和歌として知られています。
この歌は宴に同席した道長の又従妹・藤原実資の日記「小右記」に記されていたことをきっかけに、今日では「権力者の傲慢さがにじんだ歌」として有名になりました。
ただ、病気がちだった道長、同日記をはじめとする当時の文献によると望月の歌を詠んだ頃には病によって視力が低下していたらしく……その日、空に満月が浮かんでいるのをはっきりと認識できていたかは謎だという、切ない伝承もあります。
もしかしたら道長はそこに確かにあるであろう満月に、自らと一族の繁栄の願いを託そうと「望月の歌」を詠んだのかもしれません。

専用の台紙にセットしてお届けします!
【在原業平が詠んだ歌より「杜若と八橋」】

みっつめのブローチは、源氏物語の主人公である光源氏のモデルにもなったとされる稀代のプレイボーイ・在原業平が詠んだとされる和歌よりインスピレーションを受けた「杜若と八橋」。
平安時代に成立した歌物語「伊勢物語」東下りのシーンにも登場する、今も愛知県・知立市で親しまれている伝承・八橋伝説地の風景をモチーフにしました。

住み慣れた京都を離れ、友人と一緒に東に向かって旅をする業平は、三河の国(現在の愛知)の八橋という場所にたどり着きます。
橋が八本渡る沢のほとりで休憩中、そこに咲き誇る杜若を見た友人が「かきつばたという五文字を各句の頭に置いて、旅の思いを詠んでくれ」と業平に投げかけたことをきっかけに詠まれた歌と伝わっています。
友人が業平に投げかけたのは「折句」と呼ばれる技法で、一つの詩歌の中に、まったく別の意味の言葉を織り込む遊びです。
しかし平安時代を代表する歌人「六歌仙」にも名を連ねる歌の名手・業平は、すかさず
からころも
きつつなれにし
つましあれば
はるばるきぬる
たびをしぞおもふ
と、見事な歌を返したといわれています。
なお、実際に業平が東下りをしたという記録は残っておらず、「伊勢物語」には主人公の名前も明記されていません。しかし「伊勢物語」にはプレイボーイ・業平に重なるような恋物語と、「かきつばた」を始めとする彼が詠んだ歌が多く使われているため、その主人公と見られることが多いのだそう。
それにしても、もしも本当に東下りをしないまま、八橋で杜若を見ないままにこの「かきつばた」の和歌を詠んだとすれば……天才歌人・業平の底力を恐ろしいほどに感じてしまいます……!

専用の台紙にセットしてお届けします!
彼らが紡いだ和歌の美しさを、余すことなく美しい形に落とし込みたい。
そんな想いから、ブローチは日本の職人の手でひとつひとつ、ていねいに製作していただきました。時間をかけて1から原型を作り上げた、職人こだわりの造形が光ります。

ストールはもちろん上着の衿もとに着けても素敵な、先人たちの言葉の形。

千年の時を超え形を持った「和歌」を身にまとう贅沢をお楽しみください。
ミュージアム部
雅を身にまとって 男性歌人が詠んだ和歌イメージブローチの会
月1個 ¥2,900(+10% ¥3,190)
※1個だけ(1ヵ月だけ)の購入も可能です。
※詳しくは「初めての方へ・お買い物ガイド」をご確認ください。
ミュージアム部のグッズはこちらでご覧いただけます!
ミュージアム部SNSでは
グッズ情報や部員注目のアート情報を発信中!

