
自然からヒントを得た「新感覚のアイデア」が集結!~『Epson Nature Idea Award』最終審査会レポート~
セイコーエプソンは2023年、大学生・大学院生(以下、学生)の発想力や創造力を発揮する場として、「自然からヒントを得た」アイデアを募集するコンテスト『Epson Nature Idea Award』を初開催しました。
同年12月22日にはコンテストの最終審査会及び授賞式をエプソンスクエア丸の内で実施。会場にはファイナリストとして選出された10組の学生が一堂に介し、プレゼンテーションに臨みました。
今回の記事では最終審査会から授賞式までの模様や受賞者のコメントに加え、本アワードに込められた意義や担当者の想いについてもご紹介します。
まずは、アワードの模様をまとめたダイジェスト動画をご覧ください。
■ 最終審査員紹介/審査基準

デザインストラジスト/太刀川英輔さん

コンテンツクリエイター/藤原麻里菜さん

セイコーエプソン 代表取締役社長 小川恭範

セイコーエプソン 執行役員 技術開発本部長/地球環境戦略推進室長 市川和弘
以上、4名の最終審査員が下記の5項目を基準に審査を行いました。
① テーマとの親和性(テーマを踏まえたアイデアになっているか)
② 独創性(固定観念にとらわれない発想や工夫がされているか)
③ 社会への貢献度(社会課題の解決につながるか)
④ 実現可能性(アイデアの伸びしろや「実現への可能性」を感じさせるものか)
⑤ 表現力(考えたアイデアをわかりやすく伝えられているか ※プレゼンの内容で評価)
最も優れたアイデアにはグランプリ(1点)、最も社会に貢献するポテンシャルのあるアイデアにはエプソン賞(1点)、ゲスト審査員がそれぞれ選定したアイデアには審査員賞(2点)が贈られました。
■ 最終審査会の様子

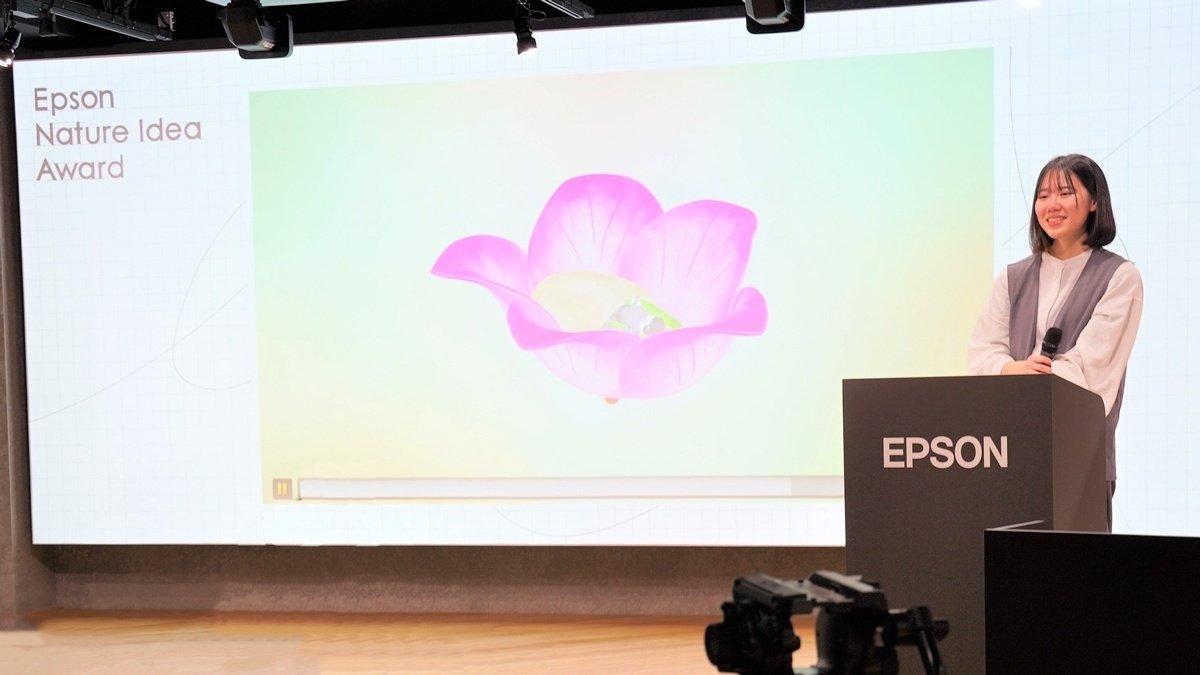


■ 受賞作品の紹介
【グランプリ】
植物の腺鱗(せんりん)を利用した虫除けストラップ/釜田陽光さん(京都大学)

【概要】
植物が持つ、香り成分などを蓄える特別な器官“腺鱗”をヒントに考えた虫よけストラップ。腺鱗はキャビティーと呼ばれる化合物を一時的に蓄積する空間を有し、外部刺激により蓄積された香り成分を外部に散布する機能を備えている。この性質を活かし、身につけた人間の歩行などの振動により、虫除け成分が自動で放出されるストラップを考えた。アイデアの詳細はこちら
【審査員講評】
太刀川さん「アワードの趣旨である“自然界から学ぶ”という観点と、デザインを含むプロダクトとしての観点。そのバランスがすごくよかった」
小川さん「非常にまとまりがいいアイデアという印象。社会貢献という意味でも価値を持っていますし、今回の応募の中では最も商品として世に出せそうな内容だと思いました」
【受賞者インタビュー】

Instagramの広告を見てアワードを知ったという釜田さんは現在、京都大学で植物に関する研究に励んでいます。グランプリ受賞については「率直にうれしいです。普段は植物の基礎研究をしていて、今回のように応用の面でアウトプットすることが少ないので、こうした機会をいただいたことにも感謝しています」と語りました。
審査員から高い評価を得たテーマと実現性のバランスについては「自然を模倣するという部分と、プロダクトとしての実用性、そのベン図がうまく重なる部分を見つけるということは結構意識しました」と、構想の段階から念頭に置いていたとのこと。
大学院へ進学するという釜田さんは「漠然とはしていますが、植物の力を利用して何らかの形で世界を良くしたいという思いを持っています。これからも植物に着目しながら、世の中の役に立つような研究をしていきたいです」と今後の目標を語ってくれました。
【エプソン賞】
見守りコウモリ君/藤原聡実さん(岩手大学)

【概要】
「認知症の高齢者が一人でも安全に過ごせるように」と発案。コウモリが超音波で獲物を認識するように人の行動を探知し、人の生活を見守る装置。自動で人間を検知し飛び立つと、超音波を発しつつ対象の人物の体格や歩行スピードから見守るべき人物かを識別。一定の距離を保ちながら家の中での行動を記録。また、もし見守る対象が屋外に出てしまった場合には、GPSクリップを衣類につける機能もある。アイデアの詳細はこちら
【審査員講評】
小川さん「多くの機能を盛り込んでいるところがエプソンらしいなと。機能を盛り込み過ぎてしまうケースもあるのですが、それは社会貢献に対する気持ちが強いから。このアイデアからも社会課題を何とかしたいという熱い思いを感じました」
市川さん「ご家族との実体験がアイデアの出発点だと聞きました。身近な困りごとを社会課題やアワードのテーマにうまく結びつけたことが、切実でリアリティのある提案につながったと思います」
【受賞者インタビュー】

岩手大学で高圧化学を学ぶ藤原さん、実はエプソンの2024年度内定者なのです(この事実は審査終了まで審査員には伝えられていません)。内定式でアワードの存在を知り「エプソンが多数の特許技術を持っていることを知っていたので、それを生かした装置を提案してみたい」と考えて挑戦を決意。その時、頭に浮かんだのが、離れて暮らしていた御曾祖母様とのご経験だったそう。
まさかファイナリストに選ばれるとは思っていなかったという藤原さんですが「みなさんのプレゼンテーションを聞いて、広く共感を得るための表現力や発表のまとめ方が非常に勉強になりました」と、エプソン賞以外にもアワードへの挑戦を通じて多くの収穫があったようです。
社会人生活に向けては「大学では基礎研究の側に立っていますが、入社後はさまざまな方向に目を向けながら勉強して、明確な強みを持った技術者に成長していきたいです」と意気込みを語りました。
【審査員賞/太刀川英輔 選】
生物を模した物質回収装置/中野和真さん(東京大学)

【概要】
さまざまな生物がそれぞれの方法で餌だけを選別して食していることからヒントを得た物質回収装置。生物の摂食様式を応用することで目的の物質だけ回収・除去することができる。タイワンガザミから着想を得たこのアイデアは、腕のハサミで海底に沈んだ漁網などを切って回収し、ゴースト・フィッシングの解決などを図れる。
アイデアの詳細はこちら
【審査員講評】
太刀川さん「約3000万種ともいわれる生物種。その数だけ物質の回収方法があるのではないか、という考え方はすごいなと思いました。現段階での答えそのものよりも、このような問いを発見したことを高く評価したいです」
【審査員賞/藤原麻里菜 選】
無数の情報から心を守るデザイン−食虫植物より−/樅山大耀さん(芝浦工業大学)

【概要】
食虫植物“ハエトリソウ”が虫を素早く捕まえる光景からヒントを得てデザインした帽子。SNSは便利だが、誹謗中傷やセンシティブな画像、ネタバレなど気持ちがマイナスになる情報も多いように感じる。そういった情報を素早く検知し、0.2秒という人の反応よりも早く閉じることで、装着者がSNS上で見たくないモノから身や心を守り、心の健康を保つ。アイデアの詳細はこちら
【審査員講評】
藤原さん「SNSという身近な問題と食虫植物の動作がリンクする意外性。そして、このマシンがもし出来上がったら色んなことができるんじゃないかという“ワクワク感”で選ばせていただきました」
■担当者が語る、アワードに込められた思い

岡村鞠子
2023年に大学生・大学院生(以下、学生)を対象に行った「ものづくりや発想力に関する意識調査」の結果、約77%がアイデアを生み出すことが好き、約60%がアイデアやスキルを磨く場に参加したいと望んでいることが分かりました。こうした学生の皆さんの気持ちに応え、学生がアイデアを考えたり、ものづくりを楽しんだりすることを応援するために開催したのが今回のアワードです。
エプソンは創業以来、自然環境と向き合い、共生しながら事業を育んできました。これからの社会を担う学生の皆さんにも自然と向き合い、その価値や可能性を見出すような経験をしてほしい。そんな思いから『自然からヒントを得たアイデア』をアワードのテーマに設定しました。実際、ご応募いただいたどのアイデアからも自然が与えてくれる豊かな「気づき」を感じることができ、学生の皆さんの発想力や着眼点に驚かされるばかりでした。
私たちはこれからも、学生の皆さんの想いに寄り添い、サポートできるような取り組みを続けていきますので、今後もエプソンの公式Instagramをはじめ、ホームページや各メディアでの発信にご注目ください。
『受賞作品一覧』
https://corporate.epson/sp/nature-idea-award/winners/
『Epson Nature Idea Award』受賞結果・作品掲載特設サイトURL
https://corporate.epson/sp/nature-idea-award/
※本サイトの構成はスマートフォンの表示に最適化されています。
