
或る読書家が考える 読書について/読み方/読め方/読書法/読書論について妄察
約135億年前のビックバン以降、物質、エネルギー、時間と空間が誕生し・・・更に原子、分子が誕生していきました。
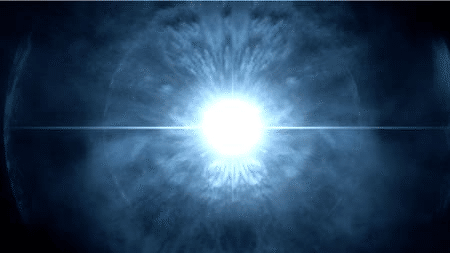
そして・・・約38億年前に有機体が誕生することになり、約20万年前までにホモ属が誕生し進化の過程を辿ることになりました・・・現代人類は農業革命⇒科学革命⇒超ホモ・サピエンス時代を迎えようとしております。

7万年前に認知革命が起こりホモ・サピエンスによる文化がはじまったというのが・・・ユヴァル・ノア・ハラリ先生のサピエンス全史の冒頭です・・・
余談ですが、ハラリ先生は有機体はアルゴリズムの集積物であるとしていて、その活動状態を計測し、継続的にモニタリングすることで、その背後にある法則やアノマリーを炙り出す事が可能だとも言っております。

※ユヴァル・ノア・ハラリ/サピエンス全史(上/下巻)
そして・・・世界最古の書籍と言われている(諸説ありますが)易経が約5,000年前に誕生しました。孔子や孫子や荀子など諸子百家の先生方も愛読していたんだそうです。
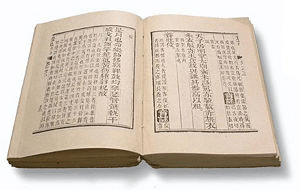
※画像:wikipediaより
◯易経とは?
少し、易経について補足を加えて参ります。
易経の易という字はかわると読むことができます。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、実は易経は英語訳では『book of changes』なんですね。
変化の書という大変、興味深く魔術的な響きのある書籍ではありますが、易という字には光の変化によって日に十二回、体の色を変えるという意味が含まれているんだそうです。
ですので、この書物は「変化」について説かれた書物だと捉えて良いと思っています。また占いの書とも言われております。
ただ・・・存在は知っていても、日常生活で易経に触れる機会はほぼ、ないと思われます。先程述べました通り、占いの書と言われておりますが、実は易経を理解出来ていれば占う必要がないとも言われており、パラドクスを内包した不思議な書物でもあります。
そして、この変化の法則をわかりやすくあらわした「易の三義」というものがあります。
易の三義とは易という字に含まれる変易・不易・簡易の三つの意味のこと。
①変易:かわるものが更にかわっていくことを意味しており、あらゆる事物は常に創造変化であるということなんですね~
②不易:かわるものだがかわらないということを意味しており、万物の創造変化には必ず一定の理、法則性、根源が存在するということなんです。
③簡易:かわるものが、楽にかわる事を意味しており、その変化と一定の理を明らかにすれば、変易へと導くことができるということを現しており、この3つを合わせて易の三義と言うそうです。
易経はもともとは帝王学、すなわち王の書だったわけです。以前のstandfmで配信をしております通り、長らく書物というものは一般大衆のものではなく、一部の特権階級、権力者、聖職者のものであり、時の権力者の意向を反映させたものであり今のように自由にビジネス書や自己啓発書でお勉強が出来たということがない時代も長く続いておりました。
また、識字率や教養としての読み書きが出来るのもそれなりに裕福な家庭の出身やエリートたちが勉強して身につけている以外は読み書きも出来ない人もたくさんいたんですよね。
◯易経の 六十四種類の卦とは?
この六十四卦ですが、易で、八卦を二つずつ組み合わせてできる64の卦の事を指すそうです。
易経では、この六十四卦を占いの語や解釈として記しているわけです。私もまだまだ勉強中ですが、どうも乾為天という卦が最も重要だと言われております。
乾という字は天を意味しています。
乾為天は、2つの天が重なってできている卦という構成の様です。
強力な天のパワーにみちみちており、運気の上昇や飛躍・成功が暗示されているとも言われていますね。これは物事の理であり、表があれば裏があり、ペアコンセプトの様な感覚もございますがが・・・よい運気を表しているだけではなく大成功を掴むにはそれなりに、険しい山道、つまり試練が訪れるわけです。どうしても、気を抜く瞬間は人間にはありますが、油断・慢心をしてはならないという教えも秘められているんですね。
これは私のstandfmの配信や様々な読書体験から感じるところではございますが、思っていても行動に起こさなければ得られる果実も半減するな~といつも思います。読書の話で恐縮ですが、例えば、司馬遷は史記列伝で「知ることが難しいのではなく、如何に知っていることに身を処するかが大切だし、それが非常に難しことなんですよ」と教えてくれてますし、
或いは、MITのメディア・ラボの創設者で計算機学者のニコラス・ネグロポンテは「知ることは時代遅れだ」とも言っています。
日々、読書体験を積んでたくさん知ることができても、如何に知ったことを私の文脈で言えば、子育てやビジネスの現場で活かして行くかを、よくよく考えておりますが、知っただけでは意味がないとまでは言いませんが、威力は半減するのだと感じます。
折角、自分の人生の貴重な時間というリソースを割いて、読書という創造性の高い行為をするのであれば得られたものを・・・例えば私であれば、standfmでリスナーさんのどなたかの気付きになるような配信に仕立てたり、日々の文脈で心穏やかに立ち振る舞えるかを何度と無く試行錯誤をすることで、段々、何者かに成っていく、そんな感覚をいつも感じております。
お話を乾為天に戻しますが・・・実は乾為天は・・・ 龍伝説のメタファーとして書かれているんですね。。地に潜んでいた潜龍が力をつけて、今度は飛龍になって勢いよく天に昇って行き、そして降り龍になるという龍の成長になぞらえて、人の人生、会社組織などあらゆるものごとに通じる時の変遷過程の原則を示しています。
個人的には、万物流転の法則を想起させれれます。
全ては変化し続けるのです。自然界だけでなくて、動物も、植物も鉱物も人間もですね。しかも、絶え間なく無間に変化し続けていますね。これは逆張り思考で言えば、万物は変化する様に予定説的に創られているとも捉えられますね。
ですので、読書体験でいえば、絶えず読書を続けて学び続けることが大切かと思っております。学ぶことや真似ることで自分自身が毎日変化をしている感覚がありますね。
これは少し言い過ぎですが、変化を止めることは万物流転の法則に逆らうことになるし、自分への学びも止めてしますので、変化出来ないんですね。
このエピソードはかなり有名ですが・・・
本田技研を世界のホンダに育てあげた本田宗一郎の共同創業者でもある藤沢武夫さんは、「万物は流転する」と語っておられましたし・・・
私の以前のヨシタケシンスケさんのりんごかもしれないの2回目の配信でも語りましたが、古代ギリシアの哲学者、ヘラクレイトスも「万物の根源はみずである」そして、「万物は流れ去る」と言ったわけですね。
自然界は常に変化していて、人は同じ川の水に二度と入ることはないとも言っていますが、万物流転説の考え方では、この世界には永遠不変な存在などはなくて、全て形あるものはいつかは壊れてしまい、その形を変化させて流れ去ってゆくということになりますね。
ちなみに、パルメニデスは存在は決して変化しない何かであると言ってヘラクレイトスの主張と対立したとも言われておりますが、個人的には変化することも変化しないことも存在する様に思えてなりませんが、人間は常に生理学的にも自然科学的にも哲学的に考えても変化する動物の様な気もしますし、時代は間違いなく流れているような感覚がバイアスなのかもしれませんが常にあるので、自分自身がどう変わっていきたいのか?
何が変わって、何が変わらなかったのかを見定めていきたいですよね。
さて、古代における書籍は主に巻物が形式で、パピルスが使用されていたようです。※パピルスとは・・・
パピルスは、カヤツリグサ科の植物の1種、カミガヤツリの地上茎の内部組織から作られる、古代エジプトで使用された文字の筆記媒体のこと。
プトレマイオス朝時代には、エジプトの輸出品として各地に拡散した様です。このパピルスを切断して今の様な書籍の形式を提唱したのが、ユリウス・カエサルとも言われております。
ヨーロッパでは、紀元前6世紀には既にに書籍というものが流通していた様です。当時のヨーロッパでは哲学書、化学書などのアカデミックな領域の学問書が主に流通をする一方で、中国や日本では宗教=仏教に関する書籍も流通という言い方で良いのか分かりませんが登場していたようです。ご存知の方も多いと思いますが、まだ、グーテンベルクの活版印刷の発明よりだいぶ前ですので、まだまだ、手書きのものやその模写だったりと、全て手書きだった様です。
書籍が当時の人々の身近な存在であったことは間違い無いようです。これは、様々な書籍が語っておりますが、やはり識字率の向上は大きいですよね。大衆、民衆が文字を読める様になってきた訳ですし、読むのが楽しくなる。15世紀の前半には知的想像力の大爆発が起きたことが分かりますよね。
これは余談ですが、パーソナル・コンピューターの生みの親でもあるアラン・ケイは活版印刷技術を発明したグーテンベルクがタイトルにもある、マーシャル・マクルーハン著、「グーテンベルクの銀河系」を読んでパーソナル・コンピューターの概念を構想したとも言われております。

1450年にドイツの金細工師をしていた、グーテンベルグは活字と活版印刷を考案し発明したと言われております。現代の印刷技術への影響も非常に大きいとされるイノベーションが起こった訳ですね。正に、グーテンベルグが印刷の父とも言われております。
これは歴史が語るところですが、過去のヨーロッパの歴史を見ても貴族やブルジョアが周囲の人々に自慢したいが為に、わざわざ屋敷に豪華な製本をした書物を陳列する本棚を据えた応接間をつくるとう贅沢極まりない本の扱いをしていた本目線で言えば黒歴史がありました。書物達から言わせればは鎖で繋がれていて身動きができない状態でして、人に読まれることもなく気の毒な状態です。そして、書物は長らくかんたんには民衆が持ち出せないという時代が続きました。本は当時は知識を保存しておくための貴重品という位置づけでだったので、現代の人の本への考え方、パラダイムとは全く違うものだったということですね
これまで膨大な書籍がこの世に生まれてきて、更に今も現在進行系で様々な書籍が日々発刊する世の中において・・・何を読んで、何を読まないのか?という読書に対するマインドセットが必須のリテラシーになりつつあります。そもそもこの世に書籍がある意味とは何なのか?我々は何故、書籍を読むのか?また書籍が何故、膨大に発刊されるのか?
書籍を読む前にこの様な抽象度の高くレイヤーを上げた問いに向き合う事で、日々のインプットが格段に良質なものに成ることは日々、実感をしております・・・
イントロはこの辺りで終わりにして・・・
みなさま如何お過ごしでしょうか?
みなさまは日々、どのように読書に向き合っていらっしゃいますか?
日々、領域を横断し越境しながら乱読をしております。それには明確な目的が3点あります。
①読書体験の中で「子育て」、「ビジネス」、「人間関係」に活かす読書体験をするには、どうしたら良いのか?
②娘たちに書籍から得られて示唆をどの様に与えられるか?
③書籍から抽出した洞察をどうビジネスの現場に落とし込んで行くか?
他者が出せない洞察をどう出して行くのか?
この読書の効用は読書全般について書いております。また下記の様に、2020年4月からstandfmで子育てパパ×読書体験ラジオをはじめて書籍に関する配信をしております。
【読書の効用/standfm配信中】
直近ではこのnoteの記事をベースにタイトルに【マガジン】と冠を付けて
小出しにして配信を試みております↓
たとえば・・・こんな感じです。
第318回【マガジン】読書の効用Day5 読書の種類とは?
この様な形式でコメント欄に配信の要点をまとめたりしております。
今回は下記の3点について語りました。
1_目的と無目的の価値の転覆とは?
・目的を持つ=良い事
・無目的である事=良くない事
※ビジネスの現場ではこの様なパラダイムが当然、存在すると思います。この良いと悪いという価値の転覆が読書体験で可能になると思います。
2_読書の種類とは?
・早い読書→即効性の高い読書体験
・遅い読書→即効性は低いが然るべきタイミングで効果を発揮する読書体験
3_書籍から抽出可能なフレームとは?
言葉からフレーム化して自分独自の思考法に昇華させる事が可能。例えば、正反合でも心技体でも自画像、献身、尺度でも守破離や序破急など。
上記の様に日々、私の読書についてのマインドセットや向き合い方もアップデートされておりますので、日々の配信で肉付けて行っております。
第57回目~第59回目全3回の配信はまだstandfmを立ち上げて3ヶ月目くらいでの配信ですが、宜しければご視聴下さい。
早速ですが・・・
読書のマインドセット編
子育てをしていますので、子育てという文脈にどの様に活かして行こうか?また、ビジネスや人間関係にどう活かせるのか?という問いはずっと持ち続けてきました・・・どのように?という問いから(HOW思考)、1段レイヤーを上げた抽象度の高い問いに向き合うことも大切にしています。
読書を続けていると、時々、何の為に読書をしているのか?とか、一体自分はどうなりたいのか?とか、読書体験を通じて得られた洞察をどの様にすれば自分のより良い生に活かせるのか?など色々考えることがあります。
この記事を読んで頂いている方にはビジネスパーソンも多いのだと思いますが、ビジネスへの示唆を得るにはどのような読書の方法が効果的なのでしょうか?そもそも・・・読書をするということは、どんな意味があるのか?
よく聞かれる読書についての質問は・・・読書をするとどんな良い事があるのですか?ビジネスに役に立つ本は何ですか?本は何冊くらい読んだ方が良いのですか?などです・・・。
読書には・・・2種類あると考えております
①早い読書(即効性のある読書体験)
→流行りの新刊のビジネス書がこれに当てはまります。
例えばここ数年のビジネス書の流れを見ていくと、newspicksと幻冬社のレーベル、newspicks bookがあり堀江貴文さんの多動力や前田祐二さんのメモの魔力、田端慎太郎さんのブランド人になれなど、敏腕編集者の箕輪厚介さんプロデュースで非常に当たりの良く、キャッチーな内容で売れましたよね。さらにNEWSPICKS PUBLISHINGから安宅和人さんのシンニホンや近内悠太さんの世界は贈与でできているなど、少し骨太ではありますが、上手なマーケティングにより売れてますね。
②遅い読書とは(今すぐ即効性はないが、人生の然るべきタイミングで効いてくる様な読書体験)
→いわゆる、古典・原典と呼ばれる本物の書籍です。数千年のヤスリに掛けられた書籍、風雪に耐えてきた理論や法則などが書いてある書籍。例えば諸子百家の先生方の書籍も、論語でも良いですし或いはダニエル・カーネマンのファスト&スローやチクセントミハイのフロー喜びの現象学、ジャレド・ダイアモンドの銃・病原菌・鉄など本質を突く書籍です。
結論から言ってしまうと、その人の置かれている文脈・状況によって変わってくるというのが、私の今のところ到達している答えです(読書体験が更に進めばまた、問に対する自分なりの答えも変わるのだと思います)。この先、数十年読書を進めて行くと違ったステージに進むことができるのかもしれません。
また、自分以外の人間の人生や気づきに触れることで、今ここにいる自分以外の人間の経験を知ることによって、自身のより良い生に活かしたり、書籍の登場人物と自分の現在の文脈とを比較したりするなど、抽象と具体の往復運動にも一役買うのではないでしょか!?
※余談ですが、前田裕二さんの「メモの魔力にはノートを活用した抽象から具体的なアクション⇒実装へのフレームが書かれております」。汎用性、再現性が高いフレームだと思います。
・元中国大使、伊藤忠の元会長を歴任した丹羽宇一郎さんも著書「死ぬほど読書」で読書についての本質を語られていますが、結局は、読みたい本を読む。という事に集約されているのかもしれません。
書籍との出会うタイミングも非常に重要でその時々で感じる文章やページすら変わってくるので不思議なものですよね。
丹羽宇一郎さんは下記の様な本質を突く事をおっしゃっております。
あなたがよりよく生きたいと望むなら、「世の中には知らないことが無数にある」と自覚することだ。すると知的好奇心が芽生え、人生は俄然、面白くなる。自分の無知に気づくには、本がうってつけだ。ただし、読み方にはコツがある。「これは重要だ」と思った箇所は、線を引くなり付箋を貼るなりして、最後にノートに書き写す。ここまで実践して、はじめて本が自分の血肉となる。

・幻冬舎/死ぬほど読書/丹羽宇一郎著
それでは・・・まず、ビジネス書とビジネス書以外の読み方について書いてみたいと思います。
【マガジン-読書の効用DAY6/standfm/第160回で収録致しました↓】
◯地図とコンパスのメタファー

VUCA時代と言われて久しいですが、本当に先行きが不透明で不確実性で暗闇を進んでいたり或いは霧の中を手探りに進む感覚が何となくありますよね。
VUCAとは・・・
変動性を意味する言葉、Volatility
不確実性を意味する言葉、Uncertainty
複雑性を意味する言葉、Complexity
曖昧性を意味する言葉、Ambiguity
の頭文字を取りましてVUCAと呼ばれておりますが、もともとは軍事用語として生まれました。
トピック冒頭に地図とコンパスの画像を持ってきておりますが、現代は地図が読みにくい時代だと言われております。今まで通っていた道が通行止めになっていたり、新しい道が出来ていたり、或いは道そのものがなくなっていたりと・・・地図が読みにくい時代となりました。
一方で地図ではなくコンパスというものを活用する事がサピエンスには可能です。コンパスの使い方や針の指し示す方向を的確に捉えるフューチャーズ・リテラシーが必須スキルとなって参りました。
そしてこの針が示す方向に歩みを進める事がリーダーに求められる事になってきている様にも思います。
野田先生、金井先生の共著でもある「リーダーシップの旅」は過去のstandfmでも収録して参りましたが、桃太郎のメタファーが秀逸です。

桃太郎が鬼ヶ島に誰に言われる事もなく、本人の内発的動機に駆動され熱を帯びて出発します。途中で猿、犬、キジを仲間にして鬼退治に向かいますが、この時・・・猿、犬、キジは桃太郎の何か得体のしれない熱量を感じていたはずで熱に巻き取られる事で徐々に沼地へと歩みを進めて行くことになるんですね。最後は鬼を退治しておじいさんと、おばあさんの元に帰還をした所までがお話ですが・・・この「帰還」というキーワードも重要ですので、ご興味あれば過去のstandfmをご視聴下さい。
さて・・このVUCA時代に何を残して行くのか?先日、内村鑑三の後世への最大遺物をsrtandfmで収録しました、内村先生は下記の4点について触れております(箱根で青年諸君に向けて熱い語り・・・)。
①金
②事業
③思想
④高尚な生き様
個人的には③④は非常に刺さりますね。特に④はリベラル・アーツとも言い換えられますし、③も自分なりのロジックを構築出来て自分の大切にしている尺度や判断軸があるという事になると思いますので内村鑑三先生が最後に持って来ているのも分かるような気も致します。
先行きが不透明だからこそ、大局観や時代を読む選球眼が必要だし、大局観や選球眼を養う一つの方法として読書体験は有効ではないでしょうか?
【第116回/内村鑑三著/後世の最大遺物↓】
◯80:20の法則/パレート分析×読書
ヴィルフレド・パレートという人をご存知でしょうか?イタリアの経済学者です。この人が提唱している80:20の法則を読書術に当てはめるとどんな事が言えるのか?
私も以前はそうでしたが、購入した書籍は一字一句最初から最後まで読んでいました。読んでいる途中に気分が乗らなく止めてしまうことも多々ありました。しかしながら、パレートの法則を読書体験に当てはめると何が言えるのか?20%の読書で80%果実をもぎ取る事が出来るとも言い換える事が出来ると思います。
読書量が増えて来ると新刊のビジネス書などは全て読まなくてもある程度の事までは理解出来るようになりました。この場合の書籍は私が勝手に読んでいる「早い読書」に分類されるような書籍ばかりです。
遅い読書は20%の読書体験で80%の果実をもぎ取ることは出来ない場合の方が多く感じます。数千年のヤスリに掛けられた書籍も多い為、20%以上の読書体験は必要になる事が多く感じます。
◯働かなアリに意義がある/長谷川英祐著
蟻塚の中に70:30の様な法則が実は隠れています。
アリの生存戦略における遺伝子のプログラムではありますが、蟻塚には一定のさぼりアリ(人間が認識しているに過ぎない)と働きアリがいます。
・働きアリ:さぼりアリ:70:30です。
これを100%真面目な働きアリの蟻塚と、上記の通常構成比の蟻塚と比較をした場合何が分かるのか?
この比較は生存率についての比較です・・・

サボりアリがいる蟻塚の方が、なんと・・・生存確率が高いという研究結果が出ています。ビジネスの現場でも一定数さぼっている人はいるでしょうが、さぼっている人が3割り程度いる組織の方がバッファーがあるので、生存率は高い?と言い放っても良いのでしょうか・・・謎ではありますが、ロジックとしてはサボっているおじさん達がいる方が良いのかもしれませんね。。。。
◯書籍の選び方
個人的な書籍決定方法の順番です。
①テーマ(スタンス)を決める
②ジャンル(ファクト)を丁寧に吟味する
はい。以上、①⇒②です。
シンプルですが・・・このテーマを決めたりジャンルを決めたりは非常に楽しい作業であり、この部分の思考を回すだけでも読書に対する戦闘力がアップ致します。そもそも、僕、私はどんなテーマを掲げているんだっけ?どうなりたいのか?どうなることがゴールなのか?何が自分に必要なのか?どんな事を知りたいのか?などとにかく深く掘る。掘る。掘る。
たまたま、ジャンルを・・・「よし!歴史だぁ・・・」と決めたとして・・・何で歴史なのとか?歴史を勉強するとなりたい自分に近づけるの?とか歴史ってどの時代のこと?とか・・・人類史では?とか・・・進化生物学のジャンルは読まなくていいの?・・・みたいな問がどんどん沸いてきて・・・再び自分との対話が始まるんですね・・・
これは妄想にも近い、読書前の儀式のようなものですが、たしか・・・GRITやり抜く力という書籍だったと思いますが、お勉強が出来る方やアスリートなど何かずば抜けて成果を出している方は物事をスタートする前に儀式的なルーティンを行っているんだそうです。
儀式を言えば・・・君主論で有名なニッコロ・マキャベリさんは書籍を読む前に正装して、わざわざ書籍を読むための机にわざわざ座って神聖な気持ちで読書をしたとも言われております。
【第20回/ニッコロ・マキャベリ著/君主論↓】
例えば・・・勉強をする前に・・・机の上を毎回同じ位置に鉛筆はここ・・・消しゴムはここ・・・などポジションを決めていて、その通りに整理整頓する・・・みたいにルーティンをすることで、脳に信号を送るんだそうです。信号を送ることで、脳も今から勉強するんだぞ~!!というスイッチ?が入るんだという話を読んだ記憶があります。
論点ズレましたが・・・テーマとジャンルを決めた後はメタファー的に横展開するも良し!メトニミー的に縦構造を形成するも良し!必要に応じてポートフォリオ組めば良いんだと思います。。。
◯RPM(リーディング・ポートフォリオ・マネジメン)による戦略読書とは?
元BCGや、アクセンチュアでもコンサルタントとしてご活躍された三谷宏治さんの戦略読書(増補版)が最近発刊になりました。2015年に一度発刊していますが、大幅に加筆修正をして今回パワーアップしています。
・読書をポートフォリオマトリックスで資源配分せよ!!
PPMフレームを三谷さんはビジネス系と非ビジネス系、基礎と応用・新奇の2×2のマトリクスにしているのが秀逸ですね。
そして下記の4つを提唱しています。
①ビジネス基礎→てってい攻略(左下)・カメ②ビジネス応用→ファクト集中(左上)・ウサギ③非ビジネス基礎→楽しく雑学(右下)・リュウ④非ビジネス新奇→流行チェック(右上)・トリ
三谷さんが提唱したのがリーディング・ポートフォリオマトリクスRPM理論です。

※画像参照:ダイアモンド・オンライン
【standfm/第159回で収録致しました↓】
【standfm/第163回で収録致しました↓】
【読む前のお作法】
読む前のお作法としてスタンスを決めたり、RPM理論を駆使してポートフォリオを組んでします・・・読むべき書籍と始めから読まない書籍を線引してしまう(状況や置かれている文脈で柔軟に変更、または、ライフステージやキャリアトランジションでトランスフォームしていく)。
また個人的には書籍を購入したら、下記の順番でとにかく想像力を働かせる・・・・
①書棚に入れる→カテゴライズされた書棚に購入してきた書籍を入れてみる
②以前から並んている書籍と書籍の間にのお顔を見てみる→背表紙やタイトルから何か連関出来ないか思考を巡らす
③右隣、左隣の書籍と購入した書籍の装丁を眺めてみる→何が書かれているのか読んで見る、推薦文や文字から逸脱的思考と求心的思考をフルスロットルで回し続けてみる
④適切な問いの設定→書籍を買うにも選書の技法を駆使して購入したはずの書籍たち・・・この書籍にはこんな事が書いてあるんじゃないのか?或いは自分の立てた問いに答えてくれるのか?この言葉は何を意味しているのか?
様々な問いに向き合いつつ・・・ようやく書籍を開きます。。。◯ビジネス書とビジネス書以外の読み方
ビジネス書の新刊は毎月膨大に発刊され、ここ数年のトレンドだとNewsPicks と幻冬舎のレーベル、NewsPicks Bookから発売になっている堀江貴文氏の「多動力」、前田裕二氏の「メモの魔力」、田端信太郎氏の「ブランド人になれ」などがあり、私も一通り目を通してきました。
流石、幻冬舎の敏腕編集者の箕輪厚介氏が携わっているだけあり、読みやすいし、当たりの良い文章が散りばめられていて、楽しく読むことができました。足元のビジネスですぐにでも活用できる内容もたくさんあるし、これからの働き方のヒントになる話題も盛り込まれていました。
この手の流行の新刊は当然目を通す事は大切ですが、流行の新刊に書いてあることの全てとは言いませんが、その核心を突くような本質的な内容は実は、元となる本が既に何十年?古いものだと数百年?も前に発刊されて長年読み伝えられている書籍があることをご存知でしょうか?薄々、みなさんもお気づきでしょうけど、ソースが必ずあります。
現在活躍されている著名な方や有名経営者も必ず、元となるソースから学びやヒントを得て自分の経験値と掛け合わせているはずです。またご自身のご経験を元に、事例を分かりやすく紐解いて、書籍にして世に問う事も出来ると思います。
読書法や読書術については多数の書籍が出ており諸説あるので正しい読み方があるとは言えないと思いますが、私が年間300冊以上読み進めて行く中で実践している方法をまとめてみました。
◯自身で実践している読書法
様々な知見を統合する読書法
人それぞれ、置かれている文脈や状況がそれぞれ違うので、必ずハマるという訳ではありませんが・・・流行りの新刊には全て目を通している人、活字は漫画しか読まない人、本は月に1冊程度、本屋さんのビジネス書コーナーで目に付いた本を購入するという人・・・読み方は人それぞれ、様々・・・千差万別。
年間300冊(絵本を入れると500冊くらいになると思います)の書籍と対峙している私としては、流行のビジネス書も読まない訳ではないですが、割合としては10%程度でしょうか。ほとんどが、ビジネスに直結しそうにない、文学や哲学書、人類史、歴史などは良く読むジャンルです。複数の書籍を同時に併読して行くと結構な頻度で共通の人が登場します。
例えば・・・ソクラテスが・・・とか、プラトンがとか良く見かけます。他にも書籍の名前で良く見かけるのが、「影響力の武器」とか「フロー体験・喜びの現象学」、「銃・病原菌・鉄」などなど・・・良く見る書籍は結構共通していたりします。

・誠信書房/影響力の武器第三版/ロバート・チャルディーニ著

世界思想社/チクセントミハイ/フロー体験喜びの現象学

草思社/ジャレド・ダイアモンド/銃・病原菌・鉄
この様々な領域を越境していく越境型読書は後ほど語りますが、メタファー的読書、メトニミー的読書という読書法でもあります。様々な領域から得られた洞察と自身の今置かれている文脈と掛け合わせる事で対者とは違う洞察を出すことが出来る様になります。
この領域越境型読書法を後々、出てきますが人生のある一定期間、無目的に取り組むことが後々の人生に間違いなく効いて来ると考えています。様々な領域に行き交うので経営の文脈でも歴史でも心理学でも、どんな話題にもそのメカニズを応用出来るのが特徴です。東大読書の西岡壱成さんの提唱されているクロス読みに近いのかもしれませんが、人生は短距離ではなくて、長距離マラソンだと仮定すると、質の良いインプットを一定期間続ける事が間違いなく持久力獲得へと繋がると考えています。

・東洋経済新報社/東大読書/西岡壱成著
○古典・原典に当たるとは、どういうことなのか?
各分野でそれぞれ脈々と読み継がれてきた書籍。長いものだと数千年のヤスリに掛けられた書籍もありますよね。
みんなが読んでいるから他の人とは違うインプットをするという方もいると思いますが、ここでは、そのフレームは一旦外しまして、古典・原典を読み込むという事にフォーカスしたいと思います。
ここで注意が必要なのですが、よく「ポーター入門」や「1分でわかるドラッガー」などの様にエッセンシャル版という書籍が存在すると思います。
エッセンシャル版は読みやすく、すぐに理解したような気分になりますが、私は、古典・原典を読むことを強くおすすめ致します。
古典・原典に当たるという事は著者と同じ思考を辿るということですので、間違いなく深い(狭い)読み方になります。すぐに理解する事が難しいことが多いので何度も読み込むことが大切です。実際には理解するのが難しい場合にはしばらく時間を置いてから読んで見ると新しい発見などもあります。
時間を置く、余白を取ることで、自分自身の文脈もまた変化したりするので、数年前に読んだ時には難解過ぎて読み進める事が出来なかった様な書籍が、例えば、結婚して子供が出来るなどのライフステージが変わるような変化が自身に起きた場合など、改めて読み返すと理解出来たり、転職などの転機により、スキルや心境の変化などでも読書体験は変わって来るという話はよく聞きます。
繰り返しになりますが、何度も読み込み事が重要だと感じます。
結構、大変ですけどね・・・
◯何を読むべきかも重要だが、同じくらい何を読まないかも重要
読むべき本はもちろん読むべきですが、何を読まないかを考える事も重要です。不要なインプットをしても返って不要な知識が増えるだけです。本当に必要な良質な知識をインプットした方がアウトプットも良くなるはずです。
これは、スティーブ・ジョブズも言ってますが、何をやるのかを考える事と、何をやらないかを考えることはどちらも検討していく話だと思います。
物事は二律背反やペアコンセプトという必ず対になる概念が存在する訳で、物事は多面的に見るべきで、片側だけを見て判断するのは危険な思考だと考えざるを得ません。
またガ-べジ-イン、ガ-べジーアウトというシステム系の言葉がありますが、ゴミ(=ここでは不必要な情報)をインプットすれば出てくるアウトプットもそれなりの質という事になりますので、何をインプットして、何をインプットしないのか?を予め考えておく必要がありますね。
◯関連分野の固め打ち読書法
自分の置かれている文脈や興味のある分野の本を徹底的に読み込むといのも一つの手法だと感じます。よく聞くのはその分野の書籍を10冊読んでみよう!というものです。結構10冊読み込もうと思うと、それなりに覚悟が必要だと思います。10冊の中には内容が重複するものもあるでしょうし、10冊読めばある程度、記憶が定着につながると思います。
◯人間の幅を広げる書籍とは
ビジネスに役立つ書籍について書いてきましたが、即効性はありませんが、後々、大きな財産となるのが人間力を高めてくれるような書籍ですね。
ここ数年聞いたことがある方もいるかもしれませんが、リベラル・アーツに関する書籍は読むに値すると思います。
以前にリベラル・アーツについて書きましたが一言で教養ですが・・・一言で言ってしまうのは簡単ですが、結構、奥は深いと感じています。人によって目的も選ぶジャンルも異なる(日々、ライフステージの変化により等)と思います。
個人的には少し抽象度の高い話になりますが、知的戦闘力を上げることで自身が日々選択している意思決定の品質の向上に役に立つと思います。具体的には過去の歴史的な事象から、自身が置かれているビジネスの現場へ置き換えて考えてみたり、洞察を引き出してみたりという具体と抽象の往復運動をすることが可能になって来ると思います。
日々、選択の連続の中で生きているわけなので、成功も失敗もあるわけですが、出来る限り後悔の無い選択をしたいものです。失敗から得られる教訓はたくさんあるので失敗が駄目と言っているわけではなく、自分で下した決断が後悔の無い内容である事が自己肯定感にも繋がるわけですし、大切ではないかと考えています。
◯目的を持つ事と無目的な読書
何事にも目的を持っておくことはブレずに先へ進めるという事もあるので重要な事だと思います。目的を持っておけば仮設を立てて検証する精度も高くなるし、読書に於いてもどんな目的で本を選ぶのか?などの問も立ってくると思います。なんとなく・・・人にすすめられて・・・など、時にはそのような場面もあるのかもしれませんが、自分のスタンスを決めてからジャンルを決めた方が良いと思っています。
一方で無目的な読書というのも重要なケースがあります。無目的に様々なジャンルの書籍と格闘する。これも一つの読書の醍醐味かもしれません。
直ちにビジネスでの成果につながることがない読書体験や一定期間、無目的に読書を続けることの意味は一体、何なのでしょうか?
書籍を毎年、何冊も出している様な、博覧強記の方々は間違いなくこの、一定期間の無目的な読書体験があるのでは?思われるくらいのアウトプットを質、量共に兼ね備えていると言えます。関連分野の固め打ちという読書の仕方と複数のジャンルを無目的に行うというのは一見、別物の様に思えますが、実は読み進めて行くと本質の部分で繋がりを発見出来るなど、驚きの体験があるので、是非、読み方やスタンスを固めるなどしてから読書をした方が効果的かと思います。
◯メタファー的読書とメトニミー的読書
山口周さんの読書法と千葉雅也さんの「勉強の哲学 来るべきバカのために」の思考法を掛け合わせてレバレッジを効かせようと思います。
メタファーとメトニミーはご存知でしょうか?
・隠喩(metaphor)⇒いんゆ・メタファー
比喩法の一つです。「・・・のようだ」「・・・のごとし」の様に物事を表現する方法の一つですね。たとえのことですね。
例)雪の肌=白い肌(雪の様に白い肌という意を含む)
彼女は太陽のようだ(太陽ではないが太陽の様に明るい性格だの意を含む)
彼女は花のように美しい(花ではないが花の様にきれいに美しいの意を含む)
・換喩(metonymy)⇒かんゆ・メトニミー
比喩法の一つです。物事を表現するときに、それと深い関係のある物事で置き換える方法ですね。
例)青い目=西洋人/金バッジ=国会議員
白バイ=白いバイクに乗る警察官(スピード違反で捕まるなどの意を含む)
テーブルを片付ける(テーブルの上にある食器やカトラリーを片付けるの意を含む)
黒板を消す(黒板に書かれて文字を消すの意を含む)
このメタファーやメトニミーという表現方法を使いこなすのはVUCA時代のリーダーには必須スキルではありますが・・・このメタファーとメトニミーが読書とどの様に関係があるのでしょうか?
例えば・・・イタリアの都市・・・ベネチア。
ベネチアと聞いてみなさんはどんなイメージを持たれますか?
美しいアドリア海の女王!!水の都!!など異名を持ちますね。英語ではベニスとも呼びます。水上都市ですが・・・このベネチアをメタファーとメトニミーで表現すると・・・
・ベネチアをメタファーで表現すると・・・アドリア海の宝石!!
・ベネチアをメトニミーで表現すると・・・ゴンドラの街!!
ということになります。
ではメタファー的な読書とは?
例えばですが、組織論やリーダーシップの書籍を読んでアムンゼンの南極探検記やコロンブスの伝記などを読む・・・というように横展開する読み方です。
一方でメトニミー的読書とは?
上記のベネチアの事例を借りますと・・・
ベネチア⇒ゴンドラについての書籍を読む⇒さらに第4回十字軍についての書籍を読む⇒インノケンティウス3世についての書籍を読む⇒オスマン帝国についての書籍を読む・・・
と・・・縦に構造化する読み方です。
これは千葉雅也さんの書籍「勉強の哲学 来るべきバカのために」の中に出てくるボケ型の勉強方法(横展開/メタファー的読書)とツッコミ型の勉強法(縦に構造化/メトニミー的読書)にも当てはまる非常に奥の深い読書法です。
これは正直、読む方の性質によると思います。物事を深く深く掘りたい方はメトニミー的読書になると思いますし、一方で色々な領域に好奇心が沸く人はメタファー的読書になるのだと思います。
どちらの読書法が良いとか悪いとかというレイヤーの話ではなく、読む人の性質にもよりますので、読み方を追求しても面白いかもしれません。
状況に寄ってはメタファー的読書とメトニミー読書を使い分け或いは、掛け合わせて知見の獲得を目指しても良いのではないでしょうか!?
◯軸ずらし読書法/ペアコンセプトの応用
これは自分が調べたいキーワードや掘りたいジャンルなどの反対の言葉や概念、思想について知ることで、自分か調べたい内容を多面的に掘る読書法です。あくまでも対に成る言葉や実際に対になっていなくても対に成るであろう言葉や概念でもOKです。
例題としては・・・
・天皇(ローマ教皇)と征夷大将軍(ローマ皇帝)
・月と太陽
・営業と開発部門(マーケティング部門など)
この例題から何が言えるのか?
天皇について調べたい人がいたと仮定しますね。天皇について書籍を調べたりネットを駆使して情報を集める訳ですね。その中に征夷大将軍という言葉を発見したとします。この征夷大将軍とはなんぞや?をもちろん調べますが、この征夷大将軍から見た(視点をずらす)ことで改めて天皇に対する見方を検討していくという読書法です。
あくまでも天皇(一面的解釈)ではなく他のステークホルダーから見た天皇という存在がどうであるかを探るためのある種のメタファーだと捉えて頂いても良いのかもしれません。
営業部門の話ですが、営業はこんな商品があれば販売実績も伸びるなど、常に顧客と折衝している訳で自身があるわけです(根拠有り、根拠なしなど両側面がありますよね)。一方で開発部門はコストや納期、ロット、製造部門との調整などもあり、営業からの提案を全て言われた通りに段取り組むことはなかなか難しい面もあると思われます。またマーケティング部門の立場ではマーケット分析や営業が持ち込んだ案件のエビデンスを探ったり定量と定性の両側面で語り始める訳ですよね。
つまり・・・物事は多面的でもあるので、一側面だけを即物的に判断しては危険ではないか?この文脈での危険とは、判断を誤ったり意志決定の品質が担保出来ていない事を意味しています。
視点をずらす読書法をする事で、自分の掘りたい内容やお題を多面的に見ることが出来ますので、是非、対になる言葉や概念から深堀りをして読書体験を多面的に進めてみては如何でしょうか?
○その他
・西岡壱成さんの東大読書で推奨されている、記者読み+仮設読み。書籍の装丁や帯、表紙や裏表紙に書かれている文言からその書籍に何が書かれているかを推測したり自分なりの仮説を構築したりと、書籍自体を読む前にそれなりの準備や装備をして書籍に対峙するという読書法。
・Voicyでお馴染みの荒木博行さんのコンテンツ×コンテキストリーディング。自身の置かれている状況にレバレッジを掛ける読書法。
私事ですが、先日、知人が亡くなりました。お世話になった方でしたので結構ショックでした。娘さんと奥さんを残して先立たれましたが、その時に手が伸びた書籍は、セネカの「人生の短さ」についてでした。
【standfm/第12回で収録致しました↓】
これをチクセントミハイ並み?にフローの状態で読み進めた訳ですが、人生に誠実に向き合うのは結局、自分が現在の状態に深くコミットする事で人生が長くもあり短くもある、という事がよく理解できました。
ちなみに荒木さんはお子さんの受験の面接前の待合室で他の親御さんがドキドキ面接前に待っている最中・・・内村鑑三先生の「後世への最大遺物/デンマルク国の話」を読んでいたんだそうです・・・メンタル強い方ですね・・・汗
以上が私が日々、ケースバイケースで使い分けをしている読書法です。
ご興味ある方は是非、試してみてください・・・
次は・・・私がオススメする書籍です.
※ただ、これは私の現在の文脈や知的戦闘力での推薦図書でございます。
参考になれば幸いです・・・以下・・・参考程度におすすめする書籍をご紹介をさせて頂きます。
◯出口治明さんの読書に対するマインドセット_本物の教養とは?
・人・本・旅
出口治明さんは人:本:旅=50:25:25の配分だそうですが、私も近いものを感じました。リスナーさんの配分はどうでしょうか?
人:人は交われば朱くなりますし、影響は絶大です
旅:その土地のものを食べたり、空気を吸ったり、
・面白いが大切
丹羽宇一郎さんも同様ですが、好きな本を楽しく読む!これに尽きるかなと思っています。他者から強要される読書体験ほど辛いものはないのでないでしょうか?
社長の推薦図書とか上司から渡されたなどと言う話はよく聞きますが、選書は自分で自発的に自律的に選ぶべきだと感じます。
・読み返す
一読して書籍を閉じてしまうのは勿体無いですね。他の書籍を読んでいる時に、たまたま以前読んだ書籍のある箇所を思い出すことがあります。そのときには書棚から本を持ってきて読み返したりすることがあります。
読んだ内容を記憶する事を目的にしてしまうのは、少しスタンスとしては違うかなと思いますが、一方で読んだ書籍を自分の血と肉とするためには、ある程度記憶しておくことも大切です。
・ベストセラーを読む事とは?
ベストセラーを読むのはラーメン屋の行列に並ぶようなものだと例えています。或いは三谷宏治さんはみんなと同じ本を読むと同じアウトプットになると言っています。ベストセラーは必ずしもクオリティーを反映していないので購入する際はよく調べる必要が時にはありますよね。
・古典は無条件に良い
未開拓な自分の領域とは遠い領域の書籍は分厚い書籍から入った方が良いとおっしゃっております。分厚い書籍とは古典・原典をさしているかと思われます。数千年のヤスリや風雪に耐えてきた100年以上前の書籍は無条件に読んだ方が良いと指摘されております。
アレクサドロス大王のエピソードとしてダレイオス1世が作った王の道を整復しさらに自身のスキームである情報の伝達手段として活用したという話は有名ですね。アレキサンドロス大王は連戦連勝だったことは有名ですが、この様な駅伝制度を利用したことも自分の支持を的確に伝える事で闘いにを有利に進めたと思われます。
→歴史の裏側のメカニズムを紐解くと
毎日14~15時間読書をしていて学校の勉強より楽しかった。最初の5分から10分で面白いと思ったら最後まで読みなさいとおっしゃっております。序文に力を入れる著者の方も多いので、私も同感です。
◯楠木健さんの読書法とは?
一橋ビジネススクール教授でいらっしゃって有名な先生ですよね。「ストーリーとしての競争戦略」「好き嫌いと経営」は私も過去読んできましたが、そこにはセンスという言葉やイメージが常に浮かんできます。特に好き嫌いと経営の中の日本電産の永盛さんとの対話は絶妙ですので、経営者その人の性質にご興味あればご一読ください。
○楠木さんの読書に対するマインドセット
非常に素晴らしいマインドセットをされています。そもそも考えることが大好きなようです。読書が無類に好きな理由として・・・それが考えるための日常的手段としてもっとも効率的で効果的だからだとおっしゃっております。読めば考えることがありますし、それを文章にしてたくさんにの人に読んでもらうという仕事とご自身の専門である経営や競争戦略とが借りに関係がないにしても、考えるという行為としては本業と共通しているとおっしゃっておりまして、この知的態度が素晴らしいと思います。
また楠木さんは、センスがいい人のそばにいても、その本質を見破らなければ相対化できず、自分のセンスを磨くこともできない」と言っておりますが、センスがいい人と思われる人のの書籍からそのセンスを相対化し、自分のセンスを磨いていくというアプローチも可能ですよね。
また読書をするときには姿勢も素晴らしいと思います。本をあまり目に近づけないように、といった物理的姿勢にも配慮しつつ、マインドセットはもっと大切だと言っています。
著者や登場人物と対話するように読むことを推奨されていますし、対話をすることによって自分との相対化が進むことになるので、この対話、ダイアローグがポイントになりますね。これまで他の方の読書法をご紹介して参りましたが、その言葉や定義こそ違いますが、著者や登場人物との対話を楽しんでいる方が多く見受けられます。
読書の絶対的な強みとして、生身の人間との対話が物理的に離れて出来ないことや、すでに過去の人となりこの世に存在しない場合もありますが、読書体験を通じていつでも、どこでも時空を超えた対話が可能になっている事が強みと言えそうです。
孫正義、柳井正やキケロ、セネカと対話も可能でありますし、投資金額としては1,000円や2,000円で、その人の思考力や行動力、専門性を勉強できるので、読書は投資対効果が非常に高い行為だと言えますよね。
また偉人の伝記の回でもお伝えしましたが、例えば、名だたる経営者の自伝を読むことで、経営者との対話を何度も重ねることができますし、この日々の積み上げこそが、戦略や経営のセンスを磨くことにも通じるのだと個人的に誤読をしております。
楠木さんらしいメタファーとして・・・戦略のセンスを磨くためのいくつかのアプローチの中でも読書を次の様に表現しております。
・早い
・安い
・美味い
です。本格的なフランス料理のフルコースには及ばないが、相対的に低コストで、時間をかけずに、いつでもどこでも日常のルーティンとして生活に取り込めるというのが読書の素晴らしいところだと語っておられますが、自分のタイミングや置かれている状況・文脈でいつでも読書が開始できますので、言い得て妙な訳です。
→ 読書は経営センスを磨き、戦略ストーリーを考えるための筋トレなのです。
本書に書かれている楠木氏の多くの書評から私たちは戦略ストーリーの組み立て方やセンスの磨き方を学べます。楠木氏の思考に大きな影響を与えた内田和成氏や吉原英樹氏などの幅広い書評を読むことでスキルではなく、センスを鍛えることの重要性を学べます。コンテキストのないネットの文章やノウハウ本をいくら読んでも私たちは戦略思考やセンスは育めません。
○読書とは?
読書とは、アスリートにとっての基礎練習だと表現されています。室内で寝ながらできる走り込み、汗をかかない筋トレ、体を動かさないストレッチという秀逸なメタファーで表現されておりますね。個人的に読書は飲み物で表現しておりますが、読書と考えることの関係性を紐解くと脳トレや筋トレとも言い換える事ができますし、日々の具体と抽象の往復運動によって少しずつ鍛えれる感覚が確かにありますね。ローマは1日にしてならずなわけですね。
また楠木さんは、読書は経営のセンスを磨き、戦略ストーリーを構想するための筋トレであり、走り込みである。即効性はない。しかし、じわじわ効いてくる。三年、五年とやり続ければ、火を見るより明らかな違いが出てくるはずだとも言っていますが、この予測ではなく構想としているところが素晴らしいですね。構想するリテラシーはVUCA時代には必須の能力ですし、非常に素晴らしい考え方ですよね。
読書とは考えるための日常的手段であり、読書の醍醐味は、そこから何を読み取り何を得るかにありますが、何を入手して何を入手しないのか?を考えながら読んでいます。常に自分の古い武器や思想をアンラーンしながら、とにかく使えないなと思ったらどんどん捨てるようにしています。
過去の知見や経験値に捉われていても時代の濁流に流されるばかりなので、流されない体幹を鍛えておくためにも使えなそうな知見はどんどん個人的には捨てる事にしています。
楠木さんの独特な分類として脳への負荷別に次の3つに書籍を分けています
①重量
②中量
③軽量
それぞれを三冊ぐらいを並行して読む提案していますね。私もこの考え方はとても良いと思いますし、振り替えると各重さ別に各15冊程度は併読していることに改めて気づきになりました。古典・原典の中でも良書と呼ばれるものを自ら選書して著者や経営者との対話の粘り強く何度も繰り返すことで体幹は鍛えられ、結果として引き出しの数を増やすことも可能です。
読書体験から、我々は経験の量と質、幅と深さを生み出す事も可能になってきますが、一方で・・・そのためのセンスを養うための近道は残念ながらなさそうです。引き出しの獲得を目的とした読書体験は本末転倒ですが、私が度々、ご紹介しております、領域越境型読書法を駆使することで横断出来に様々な知見の獲得が可能になりますし、結果として引き出しの多さを獲得することが可能になります。
○裏をとる読書とは?
裏をとる読書。これは中々秀逸な表現なんですが、例えばナポレオン1世を例にとりますね。ある著者はものすごく肯定的に書くし、ある人はものすごく否定的に描いている。
こんなことはよくありますよね。
複数の評伝を読むと、ナポレオン1世に対する理解が多面的に立体的に浮かび上がります。
。これが裏をとっていくみたいな感覚ですごく面白いと楠木さんもおっしゃっております。ひとつのテーマや人物、歴史的な出来事について興味・関心があれば、違った角度やアプローチをしている書籍を読むことで例えば第一次世界大戦について考察している人がだいたい何人くらいいて、どんな考察が何通りくらい有るのかをざっくり把握しておくことが大切かと感じます。
○そもそもセンスとは?
センスと聞いてリスナーさんはどんな印象でしょうか?
あの人はセンスが良いとかセンスがある!という文脈で使用されるフレーズではありますが・・・
センスとは「文脈に埋め込まれた、その人に固有の因果論理の総体」を意味している。平たくいえば、「引き出しの多さ」。優れた経営者はあらゆる文脈に対応した因果のロジックの引き出しを持っている。しかもいつ、どの引き出しを開けて、どのロジックを使うかという判断が的確、これもまたセンスである。経験の量と質、幅と深さが「引き出し能力」を形成すると語っていることからも、あらゆる球を打ち返すには繰り返しの著者との対話が必要になってきますし、センスを磨く道には近道がないと改めて肝に銘じるべき一文ですね。
○具体と抽象の往復運動に本質が宿る
戦略ストーリーを構築する経営者の能力は、どれだけ大きな幅で、どれだけ高頻度で、どれだけ速いスピードで具体と抽象を行き来できるかで決まる。具体的な問題や案件の表面を撫でているだけでは、優れた戦略ストーリーは生まれない。最終的な意思決定は常に具体的でなければならない。しかし、その一方で抽象度の高い原理原則がなければ、しかもそうした原理原則がきちんと言語化され、言葉で意識的に考え、伝えられるようになっていなければ、筋のよい戦略ストーリーはできないとしておられますが、
個人的にはこの具体と抽象の往復運動にこそ本質が宿ると個人的は考えています。そして、読書は田坂広志さん的に言えば、知性を磨く方法だと言うことです。楠木さんの書籍はどれも、抽象的な話は具体レベルで、具体的な話は抽象レベルで解釈されていますし、楠木さんの書籍はまさに練習問題の様な感覚を受けますね。
○出口治明さんについて
出口治明を尊敬されている様でして、出口さんの知的インプット方法として「本」と「旅」と「人」を引用されております。この読書の効用でも何度となく語らせて頂いております、秀逸な考え方です。
余談ですが、ギリシア神話に「プロクルステスのベッド」の話があります。プロクルステスは強盗でして、旅人を自分のベッドに寝かせるとき、身長がベッドより長いと体を切り落とし、短いと体を引っ張ってのばそうとする恐ろしい強盗です。以前出口さんお「直球勝負の会社」(ダイヤモンド社)を読みましたが、この書籍の中で日本生命を「プロクルステスのベッド」にしてはいけないと決めたと語っていたのが印象的dす。。ベッドのほうを伸縮自在にしておいて体を切り落とされないようにする為だということだと思います。。ちなみに出口さんの愛読書はユルスナールの『ハドリアヌス帝の回想』だそうで、超名著です。

直球勝負の会社―日本初!ベンチャー生保起業物語 /ダイヤモンド社
◯永田希さんの読書法とは?
現代社会を見渡したみると、大量の情報が洪水の様に襲ってくる訳ですが、書籍におきましても毎月膨大な新刊が出てくることはご承知かと思われます。書籍をお手にとる方もたくさんいらっしゃると思いますが、放置していてもある種、未読・積読が溜まっていくのではないでしょうか?読むために購入したが何となく気分がのらず、最初の数ページだけ読んでお蔵入りなんて方もいるかもしれないですね。
永田さんの大きな問いが一つあって・・・それは、どうしたら「その本を読んだ」と言えるのか?というものです。自分で選書して購入した書籍ではありますが、何を持ってその本を読んだことになるのか?
個人的には結構、深い問いだと思います。
一字一句、漏らさず読んだことなのか?荒読みや斜め読み、速読をしてオーバービューを理解した状態でも読んだ!と言えるのか?人それぞれ置かれている状況や文脈が違うので必ずしも○○したので読んだこととしますとはならないですよね?
いつも思いますが、読書は人生と同様に正解がないので、自分でスタンスをどんどん決めて行ってしまって宜しいかと思います。もちろん決めたスタンスは状況次第で修正しながらですが。
そして今回ご紹介する読書法はある意味では最上位の読書体験なのかもしれませんが・・・日々の情報の濁流に抗って生きるため、自発的、自主的且つ、積極的に本を積んで自らの砦、拠り所とするべしと主張されております。もう一度言いますね。タイトルにもある通り積読すべしと言っています。
そして本を溜め込みすぎてゴミ屋敷の中、暮らしたこともあるという著者のインサイトを掘り下げてみると、そこには積読に対するある種の罪悪感の様なものも垣間見ることができて非常にジレンマと格闘しながら積読する様子が分かります。
○一冊の本を例えどんなに深く読み込んだとしても、そこに込められた著者の想いを完全に理解することは不可能
たしかに、読み手は書き手の思いを完全に理解することは不可能でしょう。全くの同じ人間になら可能でしょうが、我々一人一人違うマインドや思想を持つ人間なので。
そして、自分で読んだと思う本であっても数ヶ月も経てばその内容はすっかり忘れてしまい、「本を読んだつもり」になっているだけなのかもしれない知れないという自分への問いを投げかけることも可能になります。
個人的には記憶するために読書をするのは少し違うかなと思います。様々な書籍を読む中で結果として身について、記憶してしまっているという状態が良いかと思っております。
以前の読書に効用で語りましたが、私は購入した本はすぐに読まず、次の順番でようやく読み始めます。
①購入後は放置
②購入した書籍ジャンル確認し、自宅の同じジャンルがカテゴライズされている書棚に差し込む、陳列する
③隣同士のお顔(タイトル)を観察する
④装丁を確認してその書籍に何が書かれているのか逸脱的思考と求心的思考を回して仮説読みを始める
⑤自分の立てた問いに答えてくれるか?やこの書籍はこんな事が書いてあるのでは?
こんな主張をしたいのでは?など仮説をいくつかつくり・・・ようやく読み始めます。この仮説読書法の考え方は以前に読書の効用の中で語りましたので割愛しますが。読む前にもそれなりに時間がかかります。
いよいよ本を開いていく訳ですが、タイトルと前書きと目次と後書きを読んだだけでも、その本を読んだとも言えますよね。私の様に読む前に書籍に書いてあることを予測して読むことで、「積読」に対するうしろめたさ、罪悪感はなくなりますし、むしろ、著者のススメル様に積極的に「積読」をしようという主張も受け入れやすくなりますね。永田さんは「積極的な積読」をビオトープの構築だと秀逸な表現をしております。
ビオトープとは生物の生息空間を意味しますが、一言で言えば、積読の本たちをしっかりメンテナンスせよ!と言っているんですね。そのプロセスにおいては積まれていない本と積んでいる本の境界線をしっかり引くことで、自らのテーマ、文脈が形成されていくイメージです。これが著者の言う完全な読書術に値すると個人的には誤読致しました。
然るべき、読まれ方・積まれ方・分類のされ方などはそれぞれの課題感や日々の置かれている状況や文脈があるため、人それぞれ千差万別かと思われます。
ビオトープ的積読環境設計をしておくことは、過去への清算と未来への投手というある意味でのパラドクスを内包しているように感じます。
本書で紹介されている草森伸一らの床が抜けそうなビオトープを作り上げている方の話を伺うと我が家の書籍の整理の仕方やビオトープの設定の仕方の改めて考えてみる必要があるな〜と感じます。限られたスペースなので書籍を吟味して独自のエコシステムを形成していこうと思いました。
そして著者は世界には「読んでいない本について語りたい」人より「積んでいる本、どうしよう?」と思っている人の方が多いので?という問いを投げかけてきます。視点が非常に素晴らしいですね。
○完全な読書は存在しない?
そもそも一冊の本を読んですべての内容を未来永劫覚えていることは不可能ですよね。ここから言えることは「完全な読書は存在しない」ということです。逆説的に言えば・・・一度読んだ本も含めてすべての本積ん=積んである未読の本とも言えますよね。
すべての本は積読本であるというのが著者の究極的な積読論に行く着く訳ですね。
これは歴史が語るところですが、過去のヨーロッパの歴史を見ても貴族やブルジョアが周囲の人々に自慢したいが為に、わざわざ屋敷に豪華な製本をした書物を陳列する本棚を据えた応接間をつくるとう贅沢極まりない本の扱いをしていた本目線で言えば黒歴史がありました。書物達から言わせればは鎖で繋がれていて身動きができない状態でして、人に読まれることもなく気の毒な状態です。そして、書物は長らくかんたんには民衆が持ち出せないという時代が続きました。本は当時は知識を保存しておくための貴重品という位置づけでだったので、現代の人の本への考え方、パラダイムとは全く違うものだったということですね。
著者は大胆な仮説を2つ構築しています。
仮説①
産業革命と前後して、大規模な機械の導入が遅れることもあったでしょう。そんな時は、機械ではなく人間が働くことで遅れを取り戻そうと勤勉さが奨励される様になったのでは?
昼夜を問わず長時間働く事で1日あたりの生産性を爆発的に向上したわけです。
この時のパラダイムとしては、「怠け者はダメで勤勉な人ほど素晴らしい」というパラダイムが普及して、働きながらしっかり読書に向き合い、そこで得た知見を自身の日々の日常の文脈に落とし込むことでアップデートしたのでは?
という仮説です。
→ 本は勉強のために読むもの。購入した書籍を読まない人は怠惰であり出世できないという結論を導いた訳ですね。
以前にご紹介した読書をすることは無条件に良いというテーゼに対して、偉人の金言を4度配信してきた通りですが、読書をするとアホになるというアンチテーゼの設定も可能にあんりますしね。
そして、読書しない事が悪であり、そこから転じて読まない本があるのはよくない=積読状態は良くないと拡大解釈をされたという事も容易に想像できますよね。
仮説②
書籍は個人の一生を超えたアーカイブとして継承されていくものでは?
たとえば図書館は最近では「無料で本を借りられる場所」みたいに思われているが、もともとは知をアーカイブする場所という位置づけでした。ある共同体が積み立ててきた蔵書を受け継いで研究し、そして後世の子や弟子に伝えていくという蔵書観がずっとあった訳で、積んである本は無用としてしまうのは、この蔵書の連鎖を断ち切ることにもなりますよね。
著者の言葉を借りるならば・・・
「勤勉革命」と「アーカイブとしての蔵書観の衰退」が重なって「置いてあるだけの本に価値はない。本は読んで役立てないといけない」というパラダイムに落ち着いたといも言える訳ですね。
【最終的なメッセージ】
書籍を読む事で自分の血と肉にしていくものだ!という実用性重視のパラダイム自体が歴史的な産物であり、別にそれに従う必要はないという事なんですね。
「たくさん読んでいる人が偉い」「全部読んでいる方が偉い」「古典を読んでいる方が偉い」「仕事に役立つ読書の仕方ができる方が偉い」という考え方そのものをアップデートしないといけないと個人的にも思います。
丹羽宇一郎さんの書籍をご紹介した時にに語りました、好き本を好きなタイミングで読めば良い訳ですし、この書籍の様に読まない美学もあるわけです。
自分の自主研究テーマや執筆されている方であれば関係するところ以外は読み飛ばす、或いはざっと荒読みや斜め読みをすることは、「ちゃんと読んでいない」ことにはならないですし、改めて読書体験は深いと感じます。

積読コールガ完全な読書術である/イースト・プレス
◯佐藤優さんの読書法
・佐藤優さんの読書術とは?
⇒作家・元外務省主任分析官。1960年、東京都生まれということですが、佐藤さんの書籍は書店に行くと至るところで見かけます。領域も広くジャンルも多岐に渡る執筆活動をした支えしているのが、月300冊を読みこなす読書術でしょうね。
○佐藤さんの読書の技法
この読書の技法という本の中で語られている読み方が大きく3つあります
超速読、普通の速読、熟読のです。
①超速読は一冊を5分で読むという読書法です
→ これは基礎知識が無ければ速読はできないとも言っています。
例えば、本屋でパラパラ立ち読みして買うべき本を見定めるのは・・・超速読を実践している状態ということです。言葉の定義としたは、超速読は熟読するに値する本を見分けるために使うものであり、十分に内容を理解するためのものではないということなんです
②普通の速読は一冊を30分で読む読書法です。
※時間制限を設けた読書とも言えますね
→ 例えば、試験問題を制限時間内で解くために意識して速く読む場合は普通の速読を実践していることになります。
③熟読は時間制限なく丁寧に読むという定義です。
→ 速読は内容理解度という側面では熟読には勝てないということになりますね。佐藤さんは速読は決して超能力的なものではなく、誰でも自然にできるようになるおっしゃっております。そして、これらの能力を高めるためには何よりも知識が必要であり、その知識を得るために地道に熟読で本を読むことが最も大切だということなんですね。
最後に聴く、話す、書くという三つの力が読む力を超えることは絶対にないと佐藤さんはおっしゃっております。読む力が天井だとも言っていて佐藤さんらしい言い回しだとも言えますね。
○人を作る読書術
人を作る読書術で語られているのは・・・間違った読書の一つとして、いきなり専門的で難しい本を読み、理解できないままに時間を浪費してしまうことがあります。これはいきなり古典・原典を読む事を意味しているのかもしれないですが、この文脈で想像するに予備知識ゼロの状態で学術論文を読む様な事をおっしゃっているような気も致します。
出口治明さんは無条件に古典・原典は読むべしと言っていますので、それぞれの著者で言葉の定義が若干異なりますね。
私の読書の法で考えるならビジネスの現場で明確な課題感を持っている場合には・・・エッセンシャル版5冊程度と古典・原典を5冊程度まずは2、3回読み込んでみることをオススメしております。冊数は目安ではありますが、さらに理解を深めたい方は冊数を増やして頂いて結構ですし、エッセンシャル版も5冊だはなく3冊くらいでも良い場合もありますしね。ご自身のの経験や状況から理解できるのであればですが。
また古典・原典もエッセンシャル版を読まなても既にある特定分野の領域にある程度精通しているのであれば、いきなり古典・原典を読み込んで、たまにエッセンシャル版に戻っても良いかな〜とも思います。
やはり読書も人生を同じでして、読み方は千差万別、置かれているご自身の状況、文脈次第になりますね。
佐藤さん独特の言葉に通俗本という言葉が出てきます。
→入門書としておすすめするのが通俗本です。通俗本というと何か言葉は悪いのですが、実際は非常に重要なジャンルだと考えています。通俗本とは専門家が一般の人たちにその知識を広めるべく、やさしく平易な言葉で解説したものだとも語っておりす。
→私の読書術の定義では早い読書に分類されるいわゆるエッセンシャル版と遅い読書に分類される古典・原典の中間の様な書籍を通俗本と定義することも出来ると思われます。
例としてフェラデーのロウソクの科学について興味深い記述があります↓
イギリスの科学者で物理学者でもあったマイケル・ファラデーの「ロウソクの科学」はご存知でしょうか?ファラデーは電磁誘導や電気分解の法則を発見した科学者ですが、この本は世界各国のロウソクやそのつくり方、利用の仕方などを紹介しつつ、科学の本質に触れていく書籍です。
ロンドンの王立研究所が主催した講演をまとめたものがロウソクの科学です。本当に専門分野について理解していて、なおかつ幅広い知識と教養がなければ、やさしく人に教えたり伝えたりすることは容易ではないと思います。佐藤さんは通俗本こそ知識と知恵の結晶化されたものだと主張されていて、誠に本質を突いた一文だと感じます。
ということで・・・
通俗本には2種類あり・・・
①ファラデーの書籍の様に専門家が書いた書籍と言えますし、
②門外漢の人物が書いた書籍(何が重要で何が重要でないかを理解しないで書いているケースもある)
①を読むべしと言ってますが、②に当たらない為には著者を確認して書籍の内容の領域の専門家か確認をするという1ステップ踏むという行動が必要になりますね。
○ 読書は、専門書4割・エンタメ本6割でちょうどいい
幅広い知識や柔軟な思考を保つには、通俗本はもちろん、さまざまなジャンルの本をバランスよく読む必要があると語っております。
→これは私の読書法で言えば領域越境型読書法に値する読書に対するマインドセットかと感じます。
ミステリーの分野についても興味深い考察をされていて・・・ミステリーは思考力や推理力をつけるうえでよい分野でしょう。たとえば、ジャーナリストの池上彰さんは鋭い分析と洞察に基づくニュース解説などでおなじみですが、ミステリーを読むことで分析力や洞察力を身につけること可能です。
さらに・・・
文系の人が理数系の知識や論理的な思考を学ぶうえではSF小説も有効です。古典と呼ばれるくらいの良質な名作は、科学理論を基礎としながら、その可能性を豊かな想像力でさらに膨らませています。一見すると飛躍があるようなストーリーでも、しっかり科学的根拠や科学理論を踏まえているのです。
→私も同感でしてSF小説を読むことの効用は絶大だと感じます。
例えばディストピア小説・・・オルダス・ハクスリーのすばらしい新世界やジョージ・オーウェルの1984年などの小説に触れることで逸脱的思考と求心的思考をフル回転して読む事になるので、分析力や洞察力を身につけることができると思っております。
○読書のリソース・マネジメント
一般のビジネスパーソンの場合は仕事に関する専門書を読む時間が3割から4割として、通俗本や小説などエンターテイメント性の高い本を6割から7割くらいでちょうどいいのではないでしょうか。
→私も新刊ビジネス書はほとんど読まなくなり、自身の置かれている領域からなるべく遠い書籍や古典原典ばかりの日々です。
本題とは少しずれますが、興味深いことが語られております。逃げることの効用です。逃げるとは?何となく無条件に負けた?みたいなイメージで
少しネガティブさを漂わす言葉ですが・・逃げるが勝ちという言葉があります。
戦いにおいては突撃より退却が正解のときもあります。何だかクラウゼヴィッツの戦争論を想起しましたが・・・

岩波文庫/クラウゼヴィッツ/戦争論
逃げることが出来なかった悲惨な例として第二次大戦中の日本軍で、ガダルカナルの戦いを例に取っていますね。アメリカの力を過小評価し、圧倒的な火力を誇る敵に対して戦力の逐次投入でごまかそうとする日本軍でしたが・・・勝ち目のない状況であるにもかかわらず退却という断を下すことなく、進軍と突撃を繰り返すことでさらに大きな損害を自ら被る・・・退却や後退は次の反攻を考える上でも必要不可欠な戦術です。それを理解せず、勇ましく突撃して戦うことだけが戦術だとするのはあまりにも稚拙だと喝破しておられます。たしかに、日本人には、この様な状況下での冷徹な見極めが苦手な気も致します。体裁や格好、世間体というものに拘り過ぎているんですね。
美学や感情論がさらに入り込んでしまいどうにもこうにも突撃!しか選択肢がなくなる。自ら醸成した空気に巻き取られていくイメージです。これって日常生活にもよくあることでして、頑張ること、努力することがとかく推奨されますが、では頑張ること、努力することが正しくて頑張らないこと、努力しないことが悪と決め込んでしまうのは如何なものでしょうか?
状況次第では頑張らずにエグジットしたほうが妥当な場面もありますよね。会社の例も出ています。これはデイビット・グレーバーのブルッシト・ジョブズ、クソどうでもいい仕事の理論にも通じますが・・・
たとえば会社でこなしきれないほどの仕事を押しつけられる。
あたかも自分の責任のように追いつめられますが、そこでの頑張りは必ずしも報われませんよね。。特に、社員をいかに効率的に働かせられるかを追求しているようなブラックな組織であればなおさらです。そんなとき、どんなに周りから無責任だ、仕事ができないなどと罵られようが、ちゃっかり手を抜いたり上手にサボったりすることが大事になってくる。同調圧力に屈しない、あるいは空気を読まない、山本七平の空気んも研究的に言えば水を刺すことが大切になりわけですね。
これはジル・ドゥルーズ的に言えばパラノとスキゾで説明がつきます。
パラノイアは偏執型を意味していますが、自分のアイデンティティーに巻き取られているんですね。世間体や世間の価値観に固執すると言いますか、大企業に入れば一生安泰みたいな。
一方、スキゾフレニアは分裂型ですが、嫌ならさっさと逃げればいいんです。このあたりは曲面を見定める大局観が必要ですが、状況がやばそうならさっさと逃げることも大切ですよね。
◯偉人の金言編
金言や格言、偉人の伝記、絵本には自身の凝り固まったアンコンシャス・バイアスやパラダイムに揺さぶりを掛ける効用があります。
昔の人は良いことを言ったもんだな・・・だと思考が浅いですので、自身の置かれている状況・文脈に照らし合わせて考えてみることが大切だと感じます。

以前にテーゼが読書は無条件に良い行為だ!に対するアンチテーゼとして
読書をするとアホになるを設定しました。その時にご紹介したニーチェやショーペンハウアー以外にやばい偉人=ヤバ偉人読書の怪物の如き、リベラル・アーツを自身の血・肉にしているような偉人たちの至極の一文をお届け致します。
それぞれがアフォリズムを利かせた強烈な一発をどうぞ~
1_フリードリヒ・ニーチェ
ドイツ連邦、プロイセン共和国の哲学者ですね。ツゥラトゥストラはかくかたりきは有名ですね~
アフォリズムの名手と読んでも良いですね
・万人受けする書物は常に悪臭を放つ書物である
・古い本をよむことで、新しい視点を持ち新しい仕方でアプローチ出来るようになる
2_アルトゥル・ショーペンハウアー
→ドイツの哲学者です。
・読書は他人にものを考えてもらうことである、本を読むわれわれは他人の考えを反復的に辿るにすぎない
他に読書についてではないですが・・・・人間のもっとも大きな罪は、彼が生まれてきたことにあるのだから・・と悲劇の真の意味を体現している一文です。
3_ルネ・デカルト
→フランスの哲学者。私の以前のstandfmでも方法序説を語りましたが・・・あらゆる学問を学んだ末・・・我思う故に我ありはとても有名な一言ですね。
・良き書物を読むことは過去の最も優れた人々と会話をするようなものである
4_セオドア・ルーズベルト大統領
→ご存知、アメリカの第26代目の大統領です。
ポーツマス条約の和平交渉に尽力して1906年ノーベル平和賞受賞
・私は自分がこれまでに読んだすべてのものの一部である
5_フランツ・カフカ
→不条理文学の代表選手ですね。カミュとならんで・・・
私の以前のstandfmでも変身を収録致しましたが、
非常に性格の良い人だったようですね。
・書物は我々のうちなる凍った海のための斧なのだ
6_トーマス・ジェファーソン
→第三代アメリカ大統領/アメリカ独立宣言の起草者のひとり
・本がなければ生きられない
7_塩野七生
→日本の小説家、歴史作家・・・ローマ人の物語はあまりにも有名ですね。
・私は時間がなくて本も読めませんという弁解を絶対に信じないようにしています
8_ベンジャミン・ディズレーリ
→イギリスの政治家、貴族
・たった一冊の本しか読んだことのないものを警戒せよ
9_ソクラテス
→古代ギリシアの哲学者、釈迦、キリスト、孔子と並び四聖(しせい)に数えられる。
・本を読むことで自分を成長させていきなさい。本は著者がとても苦労して身につけたことをたやすく手に入れさせれくれるのだ
10_丹羽宇一郎
→元伊藤忠会長、社長、元中国大使
・好きな本を読みなさい
11_フランシス・ベーコン
→イギリスの哲学者、神学者、帰納法や4つのイドラでも有名ですね。
・ある本はその味を試み、ある本は飲み込み。少数のある本はよく噛んで消化すべきである
信じて丸呑みするためにも読むな。話題や議論をみつける為にも読むな。しかし、熟考し熟慮するために読むが良い
12_手塚治虫
→日本の漫画家、映画監督。鉄腕アトム、ブラック・ジャックなど数々の作品を世に送り出してますね。
・漫画ばかりではなく、文学や科学書、紀行、評論集などの本に親しんで知識を広めることだ
・君たち、漫画から漫画の勉強をするのはやめなさい。一流の映画をみろ、一流の音楽を聞け、一流の芝居を見ろ、一流の本を読め。そして、それから自分の世界を作れ。
13_吉田松陰
→長州藩士、思想家、私塾である松下村塾(しょうかそんじゅく)を開所。伊藤博文、山県有朋、
・今日の読書こそ、真の学問である。
14_モンテスキュー
→フランスの哲学者、著書の法の精神の中で三権分立を説いた事でも有名ですね。
・一時間の読書をもってしても和らげることのできない悩みの種に、私はお目にかかったことがない。
15_ゲーテ
→ドイツの詩人、劇作家、小説家、ファウストもご一読をオススメ致します。
・気のいい人たちは、読むことを学ぶのにどのくらい時間と骨折りがいるものか、知らない。私はそれに80年を費やしたが、今でもまだ目指すところに達したとは言えない。
16_M・J・アドラー
→コロンビア大学教授。以前のstandfmで収録しましたが、本を読む本の著者・アドラーによる金言です。
・すぐれた読書とはわれわれを励まし、どこまでも成長させてくれるものなのである。
17_三谷宏治
→虎ノ門大学院教授、元BCG、アクセンチュアのコンサルタントであり、経営戦略全史や新しい経営学、直近で私が収録した戦略読書の著者でいらっしゃいます。
・ひとは読んだ本で出来ている
18_国木田独歩
→小説家・詩人・ジャーナリスト/自然主義文学の代表選手ですね~
・読書を廃す、これ自殺なり。
19_キケロ
→古代共和制ローマの政治家、弁護士哲学者です。
・本のない部屋は、魂のない肉体のようなものだ。
20_司馬遼太郎
→小説家、ノンフィクション作家/梟の城や関ケ原/竜馬がゆくなどその書籍に影響を受けた人は膨大な数になると思われますが・・・
私も司馬先生の小説はたくさん読みますし、歴史的な背景を紐解くのにもとても参考になります。
・青春の思い出といえば、ふつう友人との間の思い出だから、図書館で友人もなく孤独でした。いま、自分の十代の間に何ごとかがプラスになったかも知れないということを考えてみると、いくら考えても図書館しかない
21_ナポレオン・ボナパルト
→ナポレオン1世として皇帝になったことでも有名ですが、戦争の天才ですね。時代の要請により登場したとしか言いようがありませんが、一時期はヨーロッパの大半を勢力下においたほどでした。ブリアサヴァランの美味礼讃で語りましたが、食事はわりとせっかちに何でも食べる方だったみたいですよね。
・読書家の一族は、世界を動かす者たちなのだ。
22_ドストエフスキー
→ロシアの小説家、思想家。罪と罰、カラマーゾフ兄弟など非常に人間心理に到達した重たい内容の書籍が多く
人間を理解にするには必読の書籍ばかりだと感じます。
・本を読むことを止めることは、思索することを止めることである。
23_オノレ・ド・バルザック
→19世紀のフランスの小説家。ゴリオ爺さんが有名ですよね。
・すばらしい書物とは、あらゆる思考の戦場で勝利を収めるものなのだ。
24_ジョン・ミルトン
→イギリスの詩人。失楽園が代表作ですね。ルネサンス期の長編叙事詩の代表作だと言えますね。
・良書を破壊する者は、知性を殺しているのだ。
25_トルストイ
→帝政ロシアの小説家、思想家、ドストエフスキーと並んでロシア文学を代表する文豪。
・すべての書を完璧に読む必要はない。心にわき起こる疑問に答えられるように読チェーホフまねばならない。
26_アントン・チェーホフ
→ロシアを代表する劇作家の一人です。かもめ、三人姉妹などの戯曲がありますね。
・書物の新しいページを1ページ、1ページ読むごとに、私はより豊かに、より強く、より高くなっていく。
27_ヘルマン・ヘッセ
→以前のstandfmで車輪の下を収録しておりますので、ご興味あればご視聴下さい。ドイツ文学を代表する文学者ですね。ノーベル文学賞を受賞してますよね。
・書物そのものは、君に幸福をもたらすわけではない。ただ書物は、君が君自身の中へ帰るのを助けてくれる。
28_ビル・ゲイツ
→ご存知マイクロソフト共同創業者です。。。ビル・ゲイツも相当な多読家でよく書籍を初回してますしね。
・子どものころからたくさん本を読んで自分でものを考えろと言われて育った。両親は、本や政治や、その他いろいろなことについて、子どもたちを交えて話し合った。
29_福沢諭吉
→啓蒙思想家、教育者、著述家・・など肩書が多いですが・・・慶應義塾の創設者でもありますが・・・
・知識・見聞を広げるためには、他人の意見を聞き、自分の考えを深め、書物も読まなければならない。
30_ブレーズ・パスカル
→フランス哲学者、自然哲学、思想家。神童としても有名ですね。
・自然な文体に出会うと、人はすっかり驚いて、夢中になる。なぜなら、一人の著者を見ると思っていたところで、一人の人間と出会ったからだ。
31_ルキウス・アンナエウス・セネカ
⇒ユリウス・クラウディウス朝時代のローマ帝国の政治家、哲学者、詩人。
私の以前のstandfmでも収録しましたが、人生の短さについては名著中の名著だと思います。
・気まぐれな読書は喜びを与えてくれるが、有益なものとするには注意深い指導が必要だ
⇒気まぐれ・・・これは私が言う所の無目的型読書法を意味しているのかもしれませんね。喜びは大きいですね。無目的ですので様々な分野を楽しくよめるので。ただ有益なもにするには注意深い指導が必要だと言っていますね
つまり何をインプットして残すのか?そしてアウトプットからアウトカムまでの射程の長いマラソンをどうリソース配分して読書体験を読み切るのか?を考えることが大切かと個人的に誤読致しました。
32_ジョセフ・マーフィー
⇒米国で活動したアイルランド出身の宗教家、著述家
潜在意識を利用・操作することで自らや周りの人さえも成功、幸福へと導く積極思考(ポジティブシンキング)「潜在意識の法則」を提唱した。
・読書の時間を大切にしなさい!1冊の本との出会いがあなたの生き方を
変えてくれることだってあるのだから
⇒書籍に書いてあることが全てではありませんが、人生を変えてしまうかもしれないスゴ本に出会う可能性もまだまだあると考えております
33_司馬遼太郎
⇒日本の小説家、ノンフィクション作家
『竜馬がゆく』『燃えよ剣』『関ヶ原』『坂の上の雲』など多くがあり語りつくせないですよね。戦国・幕末・明治を扱った作品が多いですし、歴史的拝見を勉強するのに教科書的なポジションを個人的に取っているように思えます。背景への洞察が素晴らしいといつも思います。
・自分には学校というものは一切存在理由がなかった。自分にとって、図書館と古本屋さんさえあればそれで十分であった
34_フランシス・ベーコン
⇒イギリスの哲学者、神学者、法学者、貴族である「知識は力なり」の名言は有名ですが・・・
先日4つのイドラでもご紹介しましたが・・・
1 種族のイドラ/人間という種族に基づく思い込みのこと
2 洞窟のイドラ/「個人の思い込み」のこと
3 市場のイドラ/、市場で聞いた話によって作られる思い込み/噂はなしで嫌な思いをするような事。
4 劇場のイドラ/両親の言っていることや、権威のある学者の言っていることをすぐ信じ込んでしまう。ミルグラム実験を想起しますよね、権威者への服従と言いますか。
・読書は充実した人間を作り、会話は機転の利く人間を作り。執筆は緻密な人間を作る
35_ヘルマン・ヘッセ
⇒ドイツの作家。主に詩と小説によって知られる20世紀前半のドイツ文学を代表する文学者である。私も以前、車輪の下を収録シましたが、非常に情景描写が美しい文学作品ですよね。
・この世のあらゆる書物も、お前に幸福をもたらしはしない。だが、書物は密かにおまえ自身の中にだが、お前を立ち帰らせる
⇒密かにというのがいいですね。結局読んだ物がどの様に自分の中に浸透したかは、ある課題に立ち向かうときの姿勢やマインドセットの中に宿るわけで、目に見えるわけでもないですしね。しかにナポレオンも言うように、読書家は世界を制するわけで、読書体験もわるいものではないですよね。
36_マーク・トウェイン
⇒アメリカ合衆国の作家、小説家、トム・ソーヤーの冒険』の著者として知られ、数多くの小説やエッセーを発表していますね。
・良い本を読まない人間は本を読めない人間と同じだ
⇒良書とは・・・この良書の定義は不明ですが、スゴ本だったり、古典・原典のことですかね。そして本を読めない人間と同じと言っていますので、良書の読み方、読め方次第で、本もだんだんと本質的な意味において読める、飲み込めるということなのかと誤読致しました。
37_小林秀雄
⇒日本の文芸評論家、編集者、作家。私も文章が難解過ぎて飲み込むことができない書籍もたくさんあります。読書については好きですね。
・私は、沢山売れる本は読みません。沢山売れる本を決して軽蔑しているわけではないのでして、私は本は勉強以外には読まぬ覚悟をしているだけです。遊びたい時には外の事をして遊びます。およそ、本を読むなどというとぼけた、愚劣な遊びは御免なのであります。
⇒売れる本・・・ニーチェのいう万人受けする書物を差すわけですが。。。
本を勉強以外に読まないというスタンスを決め込んでいるのが素晴らしいですね。何を読んで何を読まないかを考えることは同じくらい重要ですしね。
本を読むという行為は愚劣極まりない・・・と。ここまで来るとマキャベリが正装をして書籍と対峙するのに近いある種の神聖さを帯びてしまってますよね。
38_アルトゥル・ショーペンハウアー
⇒ドイツの哲学者。フリードリヒ・ニーチェへの影響は有名で先日の収録でも語りましたが、ニーチェはショーペンハウアーの書いた書籍を古本屋で手にして人生の難曲を乗り切ったというエピソードは有名です。
・読書しているときは、我々の脳はすでに自分の活動場所ではない。それは他人の思想の戦場である
⇒そうですね。読書をしているときはある種、他者の思想の中で著者とつかみ合って喧嘩をしている気分になりますね。格闘読書とは以前にもお話しましたが・・・ショーペンハウアーの読書については名著ですので、おすすめ致します。
39_サマセット・モーム
⇒イギリスの小説家、劇作家
月と六ペンスは名著ですよね。毎日自分の嫌いなことを2つ行うことは魂によいことだ・・・という名言もありますが、ストイックな方だと思います。
・読書は人に教養を与えてくれる。ただし、それだけでは聡明な人間にはなれない
⇒そうなんです。教養はたしかに身につきますが、聡明にはなれないでしょうね・・・それは自身の置かれている状況や文脈に落とし込んで日々の振る舞い、生き様ま落とし込まないと読書をはじめて飲み込んだことにもならないと感じます。まさに、リベラル・アーツを体現し続ける読書体験を積むことが大切かと個人的に誤読をしております。
40_ジョン・ロック
⇒イギリスの哲学者。哲学者としては、イギリス経験論の父と呼ばれますね。社会契約や抵抗権についての考えはアメリカ独立宣言、フランス人権宣言に大きな影響を与えましたよね。
・読書は単に知識の材料を提供するだけである。それを自分のものにするのは思案の力である。
⇒たしかに材料だけですね。読んでみて、ふむふむ。以上終了なんてこともあるでしょうが、やはり、思案や思索の旅に一人で出かける必要がありますよね。
41_フランシス・ベーコン
⇒イギリスの哲学者、神学者、法学者、貴族である「知識は力なり」の名言は有名ですが・・・
先日4つのイドラでもご紹介しましたが・・・
1 種族のイドラ/人間という種族に基づく思い込みのこと
2 洞窟のイドラ/「個人の思い込み」のこと
3 市場のイドラ/、市場で聞いた話によって作られる思い込み/噂はなしで嫌な思いをするような事。
4 劇場のイドラ/両親の言っていることや、権威のある学者の言っていることをすぐ信じ込んでしまう。
ミルグラム実験を想起しますよね、権威者への服従と言いますか。
・読書は心豊かな人を作る
⇒まさにそうですね。様々な著者の価値観にふれるので受容できる振れ幅が広くなるんですね。自身の尺度や判断軸もだんだん付いてくるので、ぶれないし動じなくなりますよね。
42_ヴォルテール
⇒フランスの哲学者、文学者、歴史家である。歴史的には、イギリスの哲学者である。ジョン・ロックなどと共に啓蒙主義を代表する人物有名な書作に哲学書簡 またはイギリス便りがありますね。
・読書は魂を広やかにする
⇒フランシス・ベーコン同様に受容出来る幅が読書体験を積むことで広くなるので、仮に突然のトラブルが起きてもカバリングできるように思考が回せるんですね。魂は常に穏やかに保てますし、多様な価値観に触れているので
日々様々起きる事柄にも臨機応変に対応することができるわけですね。
43_ヘンリー・デイヴィッド・ソロー
⇒アメリカの思想家。個人的な誤読ですが、エリック・ホッファーの様な生き様を感じます。自給自足の生活を送るなど、時代のフォーマットには、はまらないで自分の信じているものや美しい審美眼で世界を知覚しているような人かと感じます。
・物は、それが書かれた時と同じように思慮深く、また注意深く読まれなくてはならない
書いたのは著者で読むのが読者という事になると、著者と同じ思考や視座、視野、視点で読み解いていくという
まさに著者と対話をする様に読むことを示唆しているのだと個人的に誤読致しました。
44_エドワード・ブルワー=リットン
⇒初代リットン男爵、諸説「ポンペイ最後の日」は有名ですね。
戯曲「リシュリュー」の中の文句に「ペンは剣より強し」という直接的な暴力よりも独立したメディアの方が影響力が強いことのたとえで表現しているようです。
・目的のない読書は遊戯であって、読書ではない
⇒目的を持てと言っていますね。私の読書法で言えば早い読書に分類されるような、ビジネスや実務で即効性を求める様なスタンスを指しているのかと思いました。明確な目的を持つことは確かに大切ですよね。
45_サミュエル・スマイルズ
⇒イギリスの作家・医者です。天は自らを助くる者を助くで有名な自助論の著者ですね。
・人の品性は、その読む書物によって判ずることができる
⇒これは・・・三谷宏治さんの人は読んだ本で出来ていると同義の様なきも致しますが、ブリア・サヴァランも君がどんなもの食べたか言いたまえ、君がどんな人か言い当てて見よう!のような事も言っております。読んだ書籍からその人の思考を辿ることでどんな人物か判ずることも可能になってくるのだと思います。
46_ジョン・コリア
⇒イギリスの作家・・・不思議な話、不気味な話の数々。それでも、その中になんとなくユーモラスな雰囲気が漂っているのが作品の特徴ですね。
・書物は青年時代における道案内であり、成人になってからは娯楽である
道案内というメタファーが秀逸ですね。さらに成人になるころまでに精通していれば、成人を超えるころには道案内なしに一人、読書道へ思索の旅へ出かけられるということですね。
47_デーヴィッド・ハーバート・ローレンス
⇒イギリスの小説家・詩人。チャタレー婦人の恋人でも有名ですね。
・書物のほんとうの喜びは、なんどもそれを読み返すことにある。
出口治明さんもおっしゃっておりますが、読み返す事は非常に読書体験としては必要不可欠ですし、読み返すことで読書が完成へと少しずつ近づくような気も致します。
48_アルトゥル・ショーペンハウアー
ドイツの哲学者です。こだわりの人一倍強い哲学者だった様です。前回は⇒読書は他人にものを考えてもらうことである、本を読むわれわれは他人の考えを反復的に辿るにすぎない
・読書で生涯をすごし、さまざまな本から知恵をくみとった人は、旅行案内書をいく冊も読んで、ある土地に精通した人のようなものである
読書体験が増えてくると様々な領域、分野に精通してくるので、確かに旅行案内書を読み込んでいる様な感覚がありますね。秀逸なメタファーですよね~その領域=土地に詳しくなりますしね。
⑨洪自誠
⇒中国明王朝の著作家。主として前集は人の交わりを説き、菜根譚でも有名ですね。後集では自然と閑居の楽しみを説いた書物である
・書物を読んでも聖者や賢人の精神に触れなければ、文字の奴隷になる。学問を論じても、実践が伴わなければ、口先だけの修行にすぎない
⇒非常に本質を付いた洞察の鋭い一文ですよね。本を読んだだけではあまり効果は実感出来ないとおもます。良いこと書いてあるな~と思い数日後には少しずつ忘れているみたいな・・・小林秀雄さん的な読書になるのだと思いますし、岸見一郎さんもおっしゃっておりまが文体の先に人間がありありと
立ち上がるまで読み込むことが大切ですし、著者と対話しながら時には格闘しながら読んでいくことで、自身の状況や・文脈にレバレッジ掛かって少しずつ血となり肉となるのだと思います。
50_M・J・アドラー
→コロンビア大学教授。以前のstandfmで収録しましたが、本を読む本の著者・アドラーによる金言です。
・読む事はすなはち発見することであり、自然や外界を読み取る技術であり、教わることは本を読む技術、ないし話し手から学ぶ技術である
⇒技術であると言っていますね・・・エーリッヒ・フロムも愛するということは技術だとも言っていますが、自分の内なる世界の外側の世界を理解するためのスキルだと喝破している訳ですね。話してからは傾聴のスタンスを取り、吸収するつもりで一字一句漏らさず聞き取るという気迫が読み取れる
文章ですね。
51_エドワード・ギボン
⇒イギリスの歴史学者です。著書にローマ帝国衰亡史があります。
オックスフォード大学在学中にカトリックに改宗したが、当時のカトリックからの立身出世は難しいと父親が判断して、退学させられて、ローザンヌの父親の知人のプロテスタントの牧師に身を委ねられて、そこでプロテスタントに再改宗したそうです。
・インドの全財宝をあげても、読書の楽しみには換え難い・・
⇒これはムガル帝国の栄枯盛衰と読書の楽しみを比較したのだと思いますが、当時のムガル帝国の凄まじい財力と引き換えにしても読書の方が楽しいというまさに読書家であったギボンを象徴する名言ですね。。
52_フリードリヒ・ニーチェ
⇒ドイツの哲学者で実存主義の代表選手としても知られていまうよね。アフォリズムをきかせた文章は短い一文にもかかわらず読み手の心をえぐります。
・他人の自我に絶えず耳を貸さねばならぬこと、それこそまさに読書ということなのだ
⇒この人を見よの中で語られて一文です。ニーチェは読書を他人の自我と自分の自我がお互いに共鳴し合って、自然に耳を明け渡す現象の様なものだと捉えていたそうです。非常に深い一文だと感じます。
53_ハインリヒ・ハイネ
⇒19世紀ドイツの詩人・作家、文芸評論家。1797~1856年までを生きた人の様です。ベルリン大学在学中にはヘーゲルの教えも受けたそうです。またマルクスとも親交があったようです。
・退屈な本を読んでいてうとうとしたら、その本を読み続けている夢を見て、退屈のあまり目を覚ましてしまった。
⇒独特な表現ですが、退屈な本に出くわしたら、すぐに本を閉じて別の本へと移動をしたいところですが、あまりにも退屈すぎて夢まで見てしまったんですね。さらに退屈すぎて
目を覚ますという、退屈本への痛烈な批判が込められている様なきみしますし、ハイネのいう退屈とは文字通りの退屈ではないよう気も致します。
54_マルティン・ルター
⇒ドイツの神学者、作家。先日のプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神でも触れましたが、宗教改革の中心人物。信仰心もあり、神学者であったルター贖罪府について見過ごすわけにはいかなったようです。またマインツ大司教のアルブレヒトの野望を紐解くと
・権力ち地位を手に入れたい人の心の弱さを見てとれますね。いつの時代も変わらない欲望です。
・学力を増進するのは、多読ではなくして良書の精読だ
⇒多読とはたくさんの書籍を読むことであり、良書はこの時代から遡っての古典・原典や当時出回っていた骨太書籍のことをいうのだと思いますが、良書を読み漁っていて結果とし多読に行き着くのが個人的にはよろしいかと思います。
55_勝海舟
⇒江戸末期から明治初期の幕臣、政治家で初代、海軍卿です。江戸城無血会場でも有名ですが・・・
・人間の精魂には限りがある。多くの読書や学問に力を用いると、いきおい実務の方にはうとくなるはずた。
⇒精神のリソースの配分について語っているんですね。限りがあるから、読書や学問ばかりではなく他のことにも思考を振り向けよ!と言っているようですし、学問領域にばかり囚われて実戦経験が乏しいと実務がうまく回せないことを表現していますね。
56_寺山修司
⇒劇作家、演劇家ですね。青森県のご出身ですが、スキャンダルもありましたが・・・ 一方で多読家の側面を持っているアーティスティックな人でした。
・つまらない書物というのはないが、つまらない読書というものはある
⇒これも非常に深い一文です。書物自体ではなく自分自身の読書に対するマインドセットについて語っていますね。つまならくしているのは自分自身ですので。向き合い方ひとつで面白い、面白くない両方に極が触れますしね。
57_日下部四郎太
⇒天才物理学者です。特に地震学を中心に磁気歪み、岩石の弾性などを研究したことでも有名ですよね。
・少なく読み、多くを考えよ
・無批判的な多読が人間の頭を空虚にする
⇒エッセンシャル思考を回していたんだと推測できますが、より少なく、より良くということですね。樺沢紫苑さんもインプット3 アウトプット7という比率を提唱されておりますが、まさによくよく考えるアウトプットとアウトカムの関係を考えることにも通じますよね。無批判はやはりハンナ・アーレントも言うように悪なわけですし、頭を空虚にするわけですね・
58_格言
・論語読みの論語知らず
⇒論語を読み、論語についての知識があるにも関わらず、その教えを実践できない人がいることや表面上の言葉だけは理解できても、それを実行に移せないことのたとえですね。たしかに、いくら本をたくさん読んで知識が豊富でも、その知識を実践に活かすことができなければ意味が無い。司馬遷も史記列伝の中で知ることが難しいのではない、知ったことに如何に身を処せるかが難しいと言っているし、ニコラス・ネグロ・ポンテも知ることは時代遅れだとも指摘してますしね。
59_寺田寅彦
⇒戦前の日本の物理学者、随筆家です。一流の物理学者として、日本の物理学の黎明期を支えた人でもあります。科学者でありながら文筆家でもあり、寺田寅彦は文豪・夏目漱石を「師」とあおいでいました。漱石も彼に目をかけていました。漱石の作品「吾輩は猫である」や「三四郎」には、寺田寅彦をモデルにしたと言われる人物も登場しましね。
⇒天才は忘れたころにやってくるという名言でも有名
・読みたくない本を無理して最後まで読まなくてい
・興味なかった本が時を違えて興味をもつ
⇒これは私も日々、実戦していますが、自分の置かれている状況や文脈に合わせた読書体験が良いとおもいます。一字一句よむ必要がないと感じたら読まない。というスタンスを決め込むことが大切ですね。
60_太宰治
⇒本名はつしましゅうじですが、自殺未遂や薬物中毒をしたことでも有名ですね。坂口安吾もヒロポン中毒だったことを思いだしました。太宰治のなりたい自分やヒーロー像は芥川龍之介と言われていますね。父は貴族院議員も務めていて、邸宅には30人もの使用人がいたそうです。
・本を読まないということは、そのひとが孤独でないという証拠である。
⇒この一文も太宰らしい文章ですが、本を読んでいる人は孤独であると言いたいということですね。著者との対話や格闘はある種の孤独感や虚無感、脱力感を埋め合わせてくれる活動でもありますね。
【参考書籍】
1_歴史⇒発展的に螺旋状に原典回帰するという裏側の構造のメカニズムを理解するのに役に立ちます。
・ジャレド•ダイアモンド著
「銃・病原菌・鉄」
「文明崩壊 」
「危機と人類」
・ユヴァル・ノア・ハラリ
「サピエンス全史(上・下)」
「ホモデウス(上・下)」
「21Lessons」
・フェンルナン・ブローデル
「地中海」
・ヘロドトス
「歴史」
・司馬遷
「史記列伝」
・ホイジンガ
「中世の秋」
・ニッコロ・マキャベリ
「君主論」
・頼山陽
日本外史
・出口治明先生の書籍全般
2_心理学⇒人間の不合理性を理解し、日々の自身の意思決定に改めて向き直る為に必読だと思います。
・ロバート・B・チャルディーニ
「影響力の武器」
・ダニエル・カーネマン
「ファスト&スロー(上・下)」
・ミハイ・チクセントミハイ
「フロー体験 喜びの現象学」
・シーナ・アイエンガー
「選択の科学」
・岸見一郎
「嫌われる勇気」
3_経済学⇒人間の手で生み出した市場という生き物のようなものが規定するルールに縛られている状態をどうファクト認識するのか?
・マックス・ウェーバー
「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」・
N・グレゴリー・マンキュー
「マンキュー経済学」
・マルクス・エンゲルス
「共産党宣言」
・坂井豊貴
「多数決を疑う」
・ダン・アリエリー
「予想どおりに不合理」
「幸せをつかむ戦略」
・アマルティア・セン
「貧困と飢餓」
・スティーブン・ピンカー
21世紀の啓蒙
・カール・マルクス
資本論
・トマ・ピケティ-
21世紀の資本
・長沼伸一郎
現代経済学の直感的方法
4_経営学
・マイケル・E・ポーター
「競争優位の戦略」
・ジェイ・B・バーニー
「企業戦略論」
・クレイトン・クリステンセン
「イノベーションのジレンマ」
・クレイトン・クリステンセン
「イノベーションの解」
・クレイトン・クリステンセン
「ジョブ理論」
・エベレット・ロジャーズ
「イノベーションの普及」
・リチャード・A・ブリーリ他
「コーポレートファイナンス」
・ジェフリー・ムーア
「キャズム」
「キャズム2」
・スティーブン・P・ロビンス
「組織行動のマネジメント」
・デイビット・ベサンコ他
「戦略の経済学」
・フリップ・コトラー他
「コトラー&ケーラーのマーケティング・マネジメント」
5_脳科学
・ダニエル・ゴールマン著
「EQこころの知能指数」
・池谷裕二
「進化しすぎた脳 中高生と語る大脳生理学の最前線」
・エリエザー・スタンバーグ
「わたしは脳に操られているのか」
・アントニオ・R・ダマシオ
「デカルトの誤り 情動、理性、人間の脳」
・マイケル・S・ガザニガ
「わたしはどこにあるのか ガザニガ脳科学講義」
6_文学
・ドフトエスキー
「罪と罰」
・フローベール
「ボヴァリー夫人」
・フランツ・カフカ
「変身」
・シェークスピア
「リア王」
「マクベス」
「ベニスの商人」
・ヘルマン・ヘッセ
「車輪の下」
・ブリア・サヴァラン
美味礼讃
7_自然科学
・リチャード・ドーキンス
「利己的な遺伝子」
・長谷川英祐
「働かないアリに意義がある」
・福岡伸一
「動的平衡」
「動的平衡2」
・シュレーディンガー
「生命とは何か」
・スティーブン・ワインバーグ
「科学の発見」
8_哲学
・トゥキュディデス
「歴史」
・ユルゲン・ハーバマス
「人間の将来とバイオエシックス」
・ジョン・R・サール
「MiND マインド 心の哲学」
・ウィトゲンシュタイン
「論理哲学論考
・ニーチェ
「道徳の系譜学」
・パスカル
「パンセ」
・デカルト
「方法序説」
・プラトン
「ソクラテスの弁明」
・エーリッヒ・フロム
「自由からの逃走」
・内田樹
「寝ながら学べる構造主義」
・大井正
「世界十五大哲学」
・田坂広志
「使える弁証法」
「直感を磨く」
・セネカ
「人生の短さについて」
・マルクス・ガブリエル
「なぜ世界は存在しないのか」
・東浩紀
「哲学の誤配」
9_テクノロジー/物理学
・ケヴィン・ケリー
「インターネットの次に来るもの」
・カルロ・ロヴェッリ
「時間は存在しない」
・サリム・イスマイル
「シンギュラリティ大学が教えるシリコンバレー式イノベーション・ワークブック
10_組織論/リーダーシップ
・フレデリック・ラルー
「ティール組織」
・野田智義、金井壽宏
「リーダーシップの旅」
・ロバート・キーガン
「なぜ人と組織は変われないのか」
・ピーター・センゲ
「学習する組織」
・ジェイムズ・コリンズ
「ビジョナリー・カンパニー」シリーズ
・ジョン・P・コッター
「企業変革力」
・クレイトン・クリステンセン
「イノベーション・オブ・ライフ」
・内村鑑三
「代表的日本人」
「後世への最大遺物」
・ラズロ・ボック
「ワーク・ルールズ」
・リンダ・グラットン
「ライフ・シフト」
C・オットー・シャーマー
「U理論」
佐宗邦威
「ひとりの妄想で未来は変わるVISION DRIVEN INNOVATION」
11_その他(個人カテゴリー/自主研究テーマ)
ここからは・・・
【ビジネスモデル研究】
ビジネスモデル・ジェネレーション(SE Book)
世界「倒産」図鑑(日経BP)
ビジネスモデル2.0(中経出版)
【人間への洞察】
⇒人間を理解せずに例えば、組織を変革しようとしても組織を構成する最小単位である人間への理解を
・愛するということ(紀伊国屋書店)
・insight(英治出版)
・ツァラトゥストラ(光文社)
・司馬遼太郎作品
・塩野七生作品
・エルサレムのアイヒマン
・服従の心理
【思考/Thinking】
⇒いわゆるシンキング系書籍です。考え方や思考法をまずは学んでみて真似してみて、自分の思考の癖みたいなものを感じられればと思います。学んだ上で、自分自身の思考を俯瞰して見る。取り入れるフレームや思考法を絶えず頭の中で回し続ける。
・エッセンシャル思考(かんき出版)
・Think Smart(サンマーク出版)
・Think Clearly(サンマーク出版)
・仮設思考(東洋経済新報社)
・右脳思考(東洋経済新報社)
・直感と論理をつなぐ思考法 VISION DRIVEN(ダイヤモンド社)
・考える技術・書く技術(ダイヤモンド社)
・ロジカル・シンキング(東洋経済新報社)
・21世紀のビジネスにデザイン思考が必要な理由
【コロナ時代のマインドセット】
⇒アフターコロナだからと言う訳でもないですが、下記の書籍は現状に刺さる内容、マインドセットをするのに活用出来る書籍かと思います。
・世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか?(光文社新書)
・人生を面白くする本物の教養(幻冬者新書)
・ニュータイプの時代 新時代を生き抜く24の思考・行動様式(ダイヤモンド社)
・D2C 「世界観」と「テクノロジー」で勝つブランド戦略(NewsPicksパブリッシング)
・消費社会の神話と構造(紀伊国屋書店)
・経営者の条件(ダイヤモンド社)
・世界は贈与でできている(NewsPicksPublishing)
・ペスト/カミュ
・ハーモニー/伊藤計劃
・1984年/ジョージ・オーウェル
・すばらしい新世界/オルダス・ハクスリー
・夜が明けたら他/小松左京作品
・菊と刀/ルース/ベネディクト
・史上最悪のインフルエンザ/アルフレッド・クロスビー
上記のジャンル分けは個人的に分けたものです。ご意見によってはこっちのジャンルじゃないのか?という向きもあるのかもしれませんが、あくまでも私の私見ですのでご了承ください。
このジャンル選びとテーマ選びも重要な考え方です。テーマ-が主でジャンルは従だと思っています。これはスタンスとファクトの関係でも説明できると思います。
ビジネスでも日常の意思決定の場面でもスタンスを決めてからファクトを固めて行くのか?ファクトを丁寧に見定めてからスタンスを決めて行くのか?という思考法でもあります。
正直、置かれている文脈にもよりますが、ケースバイケースだと思います。
どちらが良いとか悪いとかというレイヤーの話ではなくまずは自分の尺度を決めてポジションを取ることが大切ではないでしょうか?
ちなみに個人的な読書法で言えば下記の様に書籍を選んでいます。
◯偉人の伝記から学ぶ
様々な書籍をご紹介して参りましたが、偉人の伝記からその人をありありとありのまま見てくことで人間への洞察やリーダーシップや生き様を抽出する事が可能ですし、偉人の生き様に触れることでリベラル・アーツに磨きを掛ける事が可能かと思います。この場合のリベラル・アーツも同様の意味でして自身の生き様です。決して、サラリーマンに必須の教養やコロナ時代を生き抜く必須の教養などという安っぽいキャッチコピーを意味しているのではない点を補足しておきますね。
・コロンブス(少年少女伝記文学館)

・リンカーン[新装世界の伝記]

・アムンゼン[新装世界の伝記]

これ以外にも吉田松陰、西郷隆盛、坂本龍馬、源頼朝など日本の偉人からも洞察の抽出も可能ですし諸説ありますが、ご自身の判断軸で早い読書と遅い読書、ファストなのかスローなのか、二項対立で課題に向き合うのか、一方で止揚ですね・・・アウフヘーベンして新たな提案を自分自身に問いとして投げ掛けるのか?自身の判断軸で決めていく時代についになってきましたよね。
◯Dainさんの読書についての考え方
スゴ本という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
このわたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいるの著者であり日本最高峰の書評ブロガーでいらっしゃいますが、その読書に対するしなやかなマインドセットが大変参考になります。
私がこの書籍で参考になった視点は書籍の選び方なんですが、そもそも我々書籍を選ぶ際、本の事ばかり考えていませんか?という問いがこの書籍にありました。テーマやジャンルももちろん大切ですが、Dainさんは別の示唆を与えてくれました。
・好きな作家の好きな本は恐らく自分も好きの法則
好きな作家の好きな書籍を探すには下記のWEBサイトを推薦してくれています。この作家の読書道は様々な作家の読書体験や読書に対する姿勢や本の書き方について語られている非常に読書好きにはたまらないサイトです。
作家の読書道(WEB本の雑誌 編/本の雑誌社)
このサイトを活用しながらでも良いと思いますが、Dainさんは下記の様な書籍の選び方を提唱されております。
①あなたの好きな作家が読んでいる、あなたの知らない書籍を見つける
②あなたの書籍を読んでいる、あなたの知らない作家を読んでいる。
自分の好きな作家がすすめている書籍は・・・あらたが好きな書籍である可能性が高いですよね!ここは無条件に読んで見ても良いと個人的には思っています。
そして、あなたが好きな書籍を推している、あなたの知らない作家がいたら趣味があう可能性が大きいと言っています。
人や自分の好きな書籍を軸に2軸で運命の1冊を手繰り寄せる!こんな読書に対するお作法もあるんですね。大変興味深いです。
【書評/stanfm/第113回で収録致しました↓】
◯松岡正剛先生の読書(本の棚の見方)についての考え方/千夜千冊752夜
ご存知、松岡正剛先生の千夜千冊です。このブログ読むだけでも読書に対する体幹を鍛えることができると感じます。
752夜の「棚の思想」に書いてありましたが・・・松岡正剛先生は本をお手に取るときに1冊を見るのでは無く、塊として見るんだそうです・・・
752夜では棚を観るポイントや注意点やが語られております。
1_文庫本の棚は勉強にならない?
最近はアイウエオ順に並んでいるため、何の工夫もない・・・ただの電話帳だとおっしゃっております。汗
2_本の並べ方には2種類ある
①平積み:手元の台に平積みしている書籍=売セン
②棚指し:棚に並んでいる書籍=平積みではなく棚指しを吟味せよ
3_棚のスキャニングとは?
本の棚を見る(スキャニング)ときには出来る限り3冊ずつ目をずらして見ていく・・・これは凄い。塊、まとまりとして見ていく。
我々の通常のパラダイムでは書籍は1冊手に取り、ふむふむと吟味するのが常だと思っておりましたが、両隣の書籍を見ることで3冊をスキャニングできるという考え方です。
4_財布との闘い・・・書籍は複数冊購入せよ!
図書館で書籍を閲覧室に持って移動する事と同じ様に1冊だけ取って来るにはあまりにも非効率だと仰っております。小説以外は単品で読まない。複数の書籍を読むこと右脳思考が回り、ひらめきや直感などイノベーションの源泉に成りうるソースを獲得出来る可能性もありますよね。
あとはお財布との闘い・・・汗
5_本を買わずに帰宅する場合にも買わなかった本に思いを馳せる・・・
近くにカフェがあれば一度入ってその本について、あれこれ考える。コーヒーを飲みながらあれこれ耽れば・・・思わぬひらめきがあるかもしれないですよね。これも新しい発見でした。
検討するとは?ここまで深く行動をして初めて検討をしたという事に成るのだと改めて気付かされました。
改めて読書とは飲み物であり、食べ物でる様に感じました。
ブリア・サヴァランの明言に・・・

「禽獣はくらい、人間は食べる。教養ある人にして初めて食べ方を知る」
「どんな食べ物を食べているのか言ってみたまえ。君がどんな人であるか言い当ててみせよう」
読書や書籍選び(食材選び)のお作法/食べ方(読み方)は改めて非常に深い人間にとっての根源的な事柄だと感じます。
★★★
──── ここからは毎度の宣伝でございます(※2024年10月13日更新)
読書術研究家の日々の活動👇
【stand.fm 子育て×読書体験ラジオ】
→ 2020年4月5日~配信をスタートしており本日(2024/10/13時点)で1,953本の音声コンテンツを配信しております。
番組開始からもう時期、55か月、4年半を迎えております。
リアルの場ではお会い出来ない方とも、弱くてゆるいフラジャイルな繋がりが持てて、毎日刺激的な日々を過ごしております💡
【Spotify】
【X】
リアルの場ではお会い出来ない方とも、弱くてゆるいフラジャイルな繋がりが持てて、毎日刺激的な日々を過ごしております💡
ここまで読んで頂きまして、感謝申し上げます。
有り難うございました。
#読書 #読書術 #子育てパパ #子育てママ #経営戦略 #リベラル・アーツ #経済学 #心理学 #哲学 #文学 #詩 #音楽 #進化生物学 #歴史 #人類史 #テクノロジー #物理学 #脳科学 #ビジネススキル #ビジネスパーソン
