
【7通目】生と死のあわいにある声——ジャン=ポール・ディディエローラン『6時27分発の電車に乗って、僕は本を読む』【書評】
拝啓
一年で最も昼が短い日、冬至を迎えました。夏が好きなので、子どもの頃は最も嫌いな日でした。しかし、この日を境にして、これから少しずつ日が長くなっていくのだと考えると、ちょっとだけ元気が出てきます。
本当は、前回の手紙でフランスものは一区切りつけるはずでした。しかし、何気なく手に取った一冊の文庫本が、じわりじわりと後から胸にしみ込んできたのです。

その本は、ジャン=ポール・ディディエローラン『6時27分発の電車に乗って、僕は本を読む』です。タイトルからして、あなたのような読書家を思い浮かべるでしょう? しかし、主人公のギレンが読書する場面は一切ありません。
冴えない中年男ギレンが勤めているのは、廃棄される本を裁断する工場で、彼はその大型機械のオペレーター。ただし、大型トラックで毎日運ばれてくる大量の書籍を切り刻み、溶かし、液状ペーストになるまで処理する工程を「大量虐殺だ」とも感じていて、ちょっと心を病んでいるようです。
そんなギレンの慰めは、裁断機のすきまにはさまれて九死に一生を得た書物のページ紙片を、毎朝の通勤電車内で朗読することです。生き残った紙片は、小説かもしれないし、実用書かもしれないし、事典かもしれない。しかし、そんな書物の「最期の生」をまっとうすべく声に出して読む。
もし日本でそんなことをしたら、迷惑がられるでしょう。何よりも狂っている。ただし、物語の舞台はフランス。電車内で毎朝ギレンが朗読するのを心待ちにしている人たちがいて、ときに拍手喝采もおこる。小説のなかのエキセントリックな出来事ではなく、パリでは本当にそんな人がいるかもしれない。ギレンと、乗り合わせた他の客たちとの小さな、そして、どこか温かい結びつきに、自分も飛び込んでいきたくなります。
ギレンの前任者であるジュゼッペのためにつく優しい嘘や、電車内の出会いがきっかけになり、老人ホームでも朗読ボランティアをすることになるエピソードも、胸にじんじん響いてきます。極めつきは、見知らぬ女性ジュリーの日記を電車内で拾ったことをきっかけに、モノクロームのような日々に、ひとつ、またひとつと色彩を帯びていく様子がいい。
かつて写真を撮っていたと、あなたにお話ししたことがありますよね。
モノクローム写真というのは、とても抽象的・観念的です。余計なものを削ぎ落とし、形や姿を浮き立たせる。実際にはどうだったのか、想像させたり、情感や余韻を抱かせたりするのは得意なのですが、まさに非日常であり、生々しさや現実感がない。究極的に、死を想起させます。
それに対してカラー写真は具体的であり、日常的。現実性があり、生々しい。いまを生きている。その瞬間を写したものといえます。
書物の終末を見届けるギレンの生活は、まさにモノクローム。書物の言葉は、いわば死者の声です。生きた証を文字に、言葉に託した書物を、さらに裁断する。大虐殺だと感じるのも当然です。
そんな日々に、ジュリーの日記が現れます。自分とはまったく違う生活の記録であり、包み隠されることのない心の声ほど生々しいものはありません。日記の文面から、ジュリーの人物像を思い描き、日記を返却するための手がかりを得ていくプロセスは、モノクロームの生活に、一つずつ色付けしていくことなのです。何かを夢中で追い求めているとき、人は生きていると実感できるものです。
タイトルにある「読む」は、読書ではなく朗読、readではなくspeakです。これも、死者の言葉を読むだけでなく、実際に声を出すことによって、言葉の「生」を再現しているといえないでしょうか。裁断された書籍のページ紙片を声に出して読むのも、ジュリーの日記を老人ホームで朗読する(!)のも、言葉に「生」または「いのち」を与えているのです。
この物語の結末で、ギレンがジュリーに宛てた手紙が出てきます。ギレンは日記から、まだ見たことのないジュリーを思い浮かべていたように、ジュリーは手紙から、まだ見ぬギレンを思い浮かべます。ギレンの手紙は、手書きでした。メールやSMSではありません。胸が高鳴るなかでしたためる手紙に、自分を重ね合わせました。
書物っていいなあ。声を出して読むっていいなあ。そして手紙って、やっぱりいいなあと感じました。手紙の先には、あなたがいる。それも幸せだなあと強く想いました。
冬至は、一年で最も夜が長い日だといえます。ドアノーや高田美の写真集をながめながら、遠いパリの冬を思い浮かべてみます。ずいぶん寒くなりましたが、あなたも風邪などひかないように。
あなたからの手紙、待っています。
既視の海
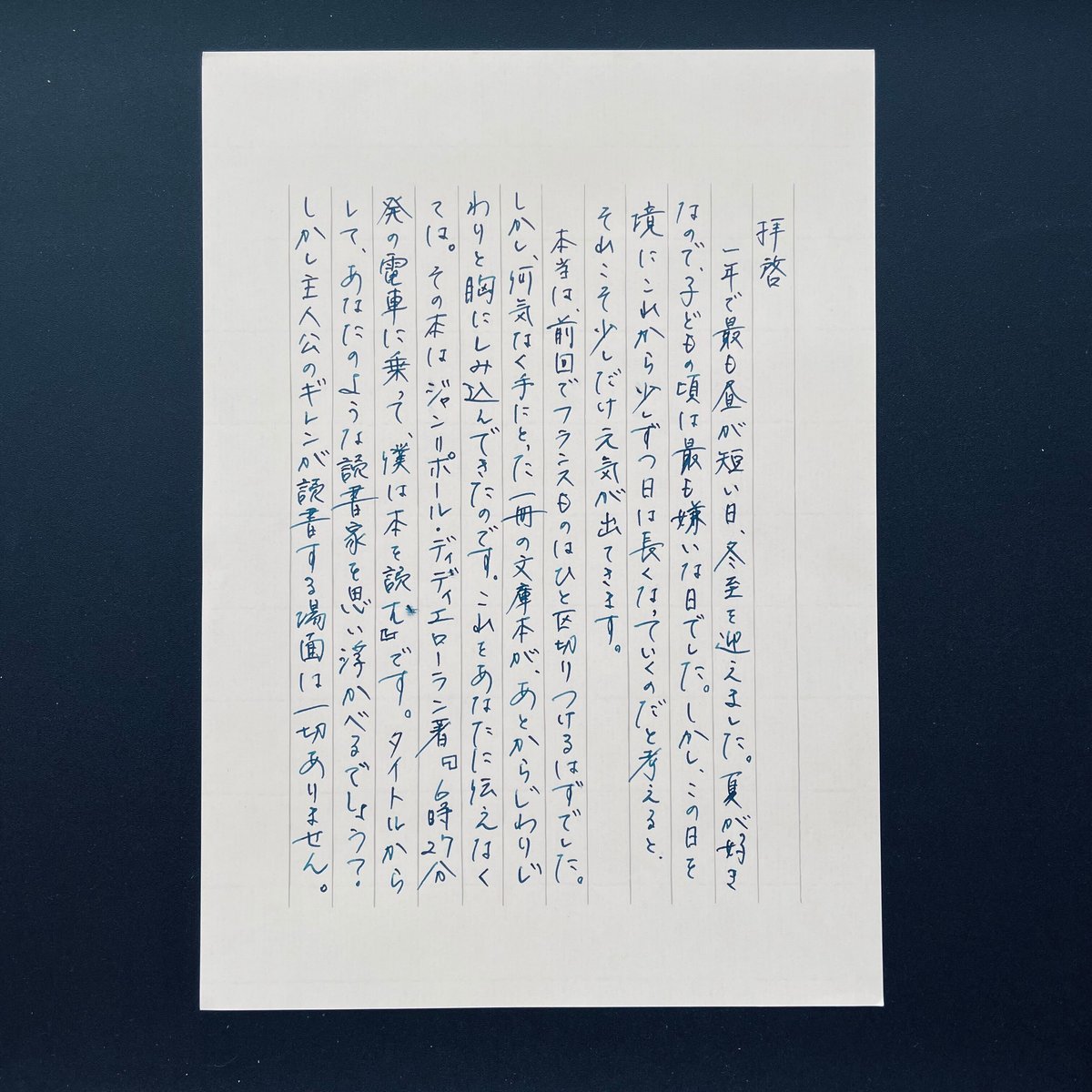


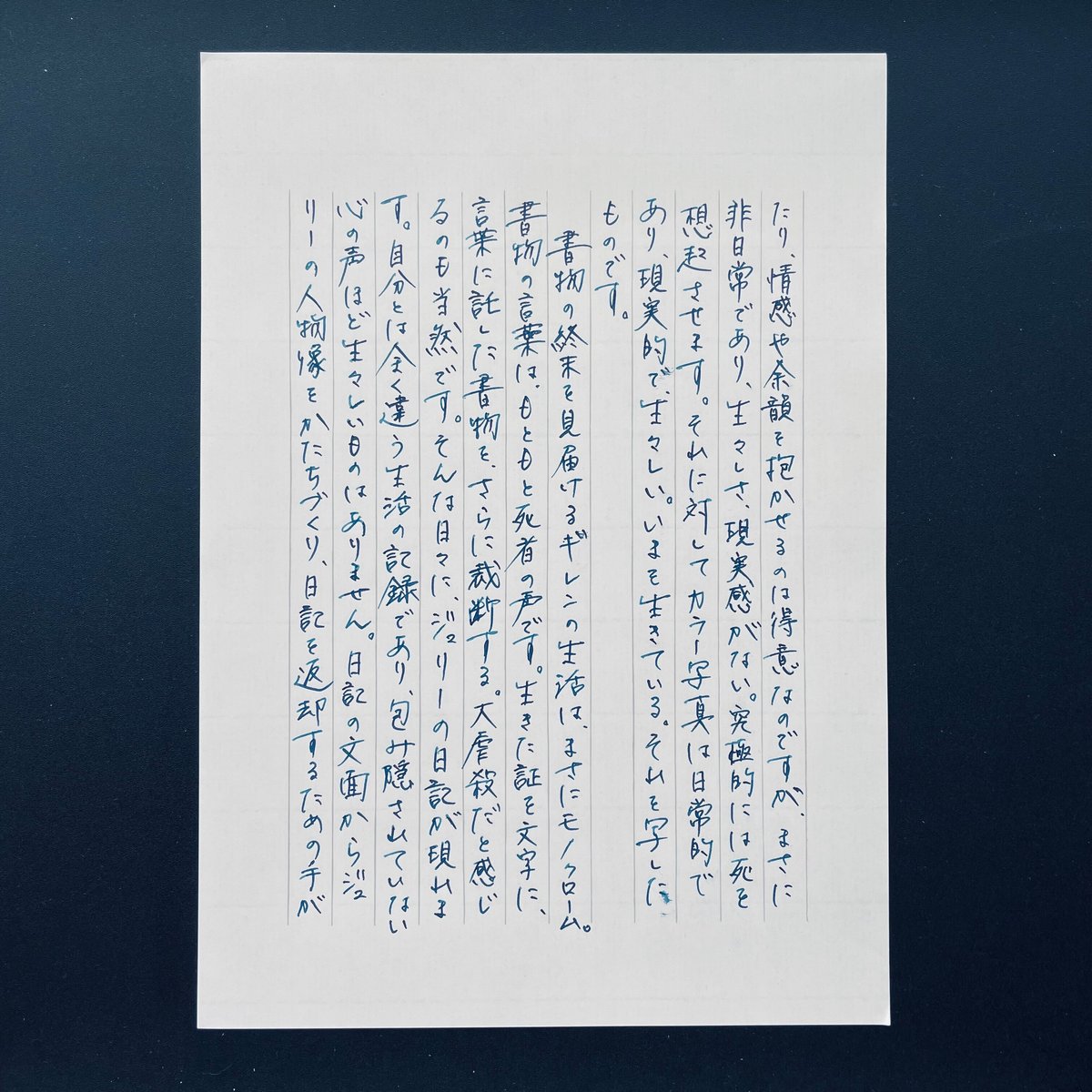



いいなと思ったら応援しよう!

