
日常こそすべて──小説家・庄野潤三の魅力
昨年、2023年、色々と小説を読みましたが、
「この作家さんの本を読めて心からよかったな」と、心底思ったのが、庄野潤三さん(以下、敬称略)。
文壇では有名な方だと思うのですが、まだ読んだことがなかった。
知らない、未読――そういう方も多くいるではないかと思い、noteに書き留めることにしました。
すでにお亡くなりになられているのですが、庄野潤三の小説は、今の私の“感覚”にドンピシャにハマった。
今の私の“感覚”というのは、『暇と退屈の倫理学』に書かれている考えをもとにしている。
「暇と退屈とどのように向き合うか?」
ハイデガーなどを引用して、解き明かしていく、非常におもしろい一冊でした。
私はこの本に、とても影響を受けた。ここに書かれていることを実践したいなと思った。
そんな中で出会ったのが、庄野潤三の小説。
「まさにこれだ」、と思った。
読み終えた2冊の感想をのせておきます。
少しでも紹介になれば幸い。
『夕べの雲』
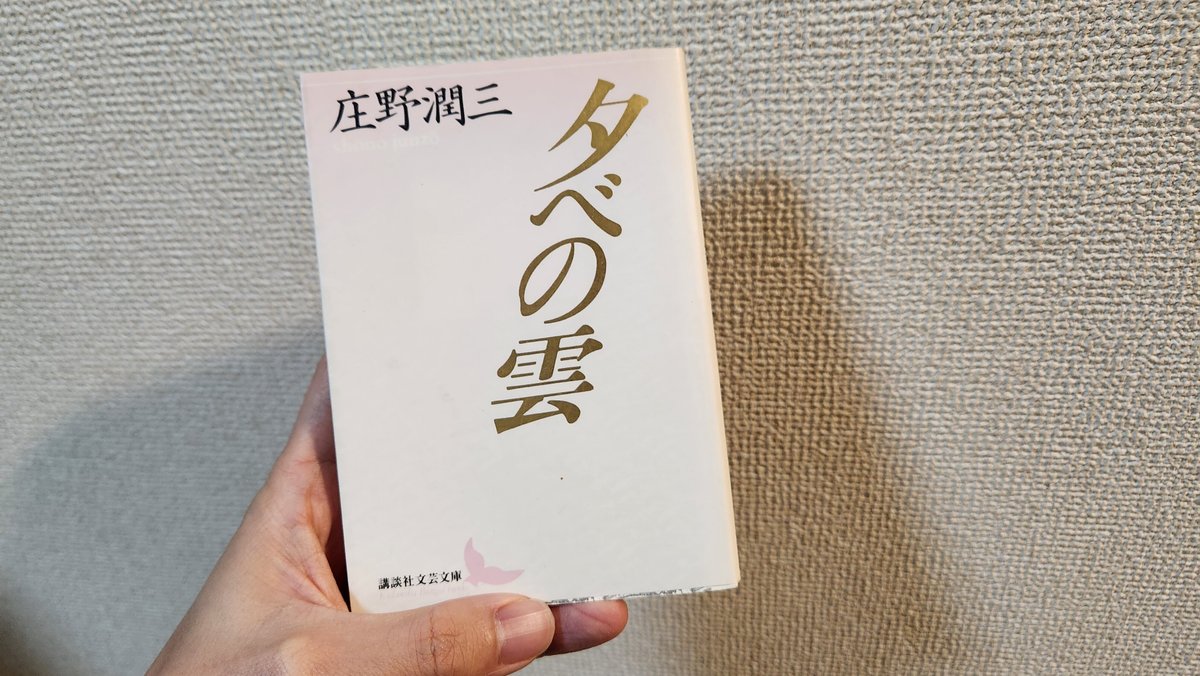
何もさえぎるものない丘の上の新しい家。主人公はまず“風よけの木”のことを考える。家の団欒を深く静かに支えようとする意志。季節季節の自然との交流を詩情豊に描く、読売文学賞受賞の名作。
まず前提として、本書は“純文学”であるということを分かっていなければならない。
決してエンタメ小説ではない。
基本、“退屈でつまらない”、それが純文学である。人を楽しませるために書かれた本ではない。
前情報なく、本書を読み始めると、「何だこの退屈な小説は」と思い、途中で投げ出してしまうかもしれない。なので、巻末の解説を最初に読むことをおすすめする。
「幸せとは何でもない日常にこそあるのだ」
確かにそうだろう。そう思って読んでいた。
退屈を愛でること、それこそが幸福であると。
しかし、どうやらそんな単純な話ではないことに途中気づいた。
当たり前の日常は、当たり前“だけ”ではない。
退屈な日常は、実は、退屈ばかりではない。
そこには必ず、“危うさ”が潜んでいる。
当たり前も、退屈も、いつそれが消えてなくなってもおかしくない。実はとても不安定で、危ういものである。
夕べの雲のように、いまの形は次の瞬間には変わっている、言い換えれば、いまの形は次の瞬間には“消えている”のである。
そう考えると、いまの平凡な日常が、“いま”であるはずなのに、どこか懐かしく思われてくる。
ただただ退屈を愛でるだけでは、退屈な日常を真に理解しているとはいえない。
「幸せとは何でもない日常にこそある」
確かにそうであるが、その裏側に潜む“危うさ”もセットにして日常を捉えること。
「懐かしい」には、「哀しい」が含まれている。
懐かしいと思うとき、そこにはどこか哀しい気持ちも含まれている。
そのような、懐かしくて哀しい気持ちをもって、今を、日常を、見つめる。
ありふれた日常がまた違って見えてくる。私は退屈を愛でるだろう。
私の幸福は、不幸と表裏一体であることで存在している。常にそういった気持ちでありたい。
『プールサイド小景・静物』

大金を使い込み、突然会社をクビになった夫。妻が問いただすと、つらい勤めの苦痛や不安を癒すため毎晩のようにバーに通いつめていたという。平凡な中年サラリーマンの家庭に生じた愛の亀裂――日常生活のスケッチを通し、ささやかな幸福がいかに脆く崩れやすいものかを描いた芥川賞受賞作『プールサイド小景』、家庭の風景を陰影ある描写で綴った日本文学史上屈指の名作『静物』等、全7編を収録
一年後、どんな内容の本だったか思い出せるか。
もしかすると、すっかり忘れてしまっているかもしれない。
それはそうで、これはあまりにも“日常”である。
三日前の晩ご飯を思い出せないように、“日常”とは過ぎ去っていくもの、忘れ去られていくものである。
そのような“日常”を克明に描写している。
一つ一つの出来事を丁寧に、ありのまま描くことで、些細な“日常”の裏に深刻な何かが見え隠れする。急に、“日常”が重大に思われてくる。
その深刻な何か、日常の裏にある“危うさ”みたいなもの、それは一体何なのか、どういうことなのか、はっきりと書かれてはいない。しかしそれが結果的に、読後の絶妙な余韻へと繋がっている。
本書収録の中では、『舞踏』が最も私の好みで、冒頭からやられてしまった。
“家庭の危機というものは、台所の天窓にへばりついている守宮(やもり)のようなものだ”
庄野潤三の作品を読んで。
以上、簡単ではありますが、感想を書いてみました。
ここまで書いたように、ありふれた“日常”が主なテーマとなっている。
しかし、そのありふれた“日常”の深さを、私はどれだけ知っているだろうか。
庄野潤三の作品には、私が知っている“日常”の表と、私が見過ごしている“日常”の裏が描かれている。
“日常”。それは決して“ありふれた”ものではなく、大げさにいえば、奇跡の連続なのかもしれない。
いや、それはやはり大げさすぎるか――。
しかし、私は思う。
日常こそ人生のすべてなのではないか。
初めて庄野潤三の小説を読んで。
この衝撃は、初めて志賀直哉を読んだときのそれと似ていた。
小説なのだが、どこか詩的な感じ。詩を読んでいるような気持ちになった。
また、読んでる途中で、「梶井基次郎の作品っぽいな」とも思った。『夕べの雲』の巻末の作家案内にもあったように、影響を受けているのかなと思った。
なので、志賀直哉や梶井基次郎が好きな方は、きっと庄野潤三の作品を楽しめると思う。
少しでも気になった方は、『プールサイドの小景』から読むことを個人的にはおすすめします。
以上です。
