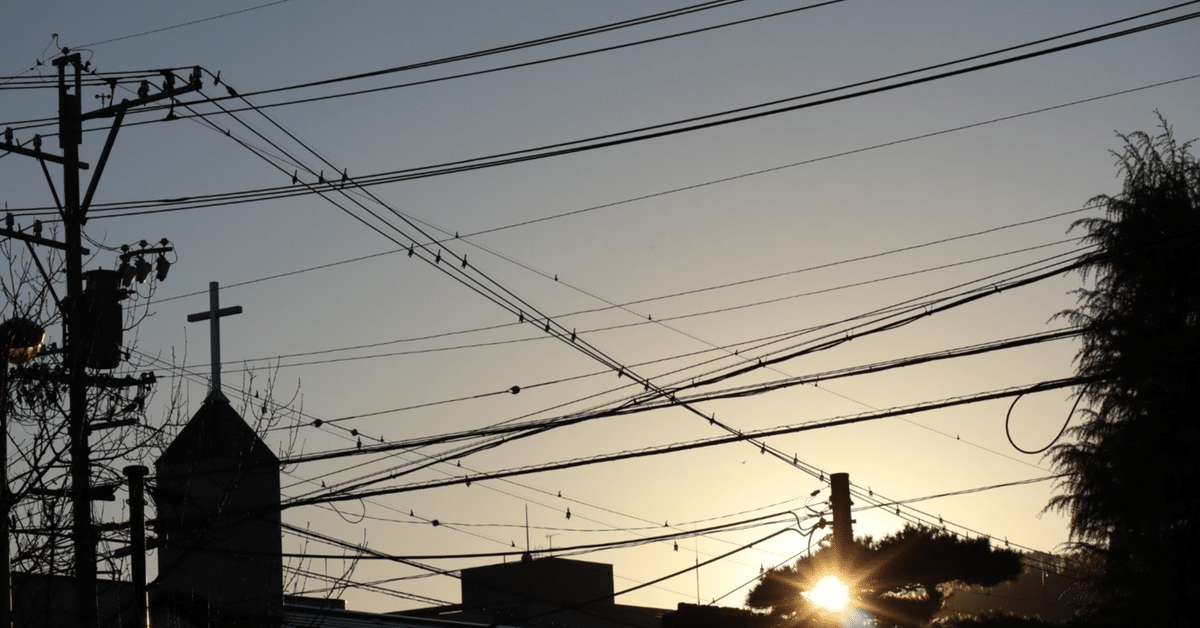
過去を赦すために書く #29
連休中、丸一日自由に過ごせる日ができ、本の読める店フヅクエへ行く。
昼の開店から日没頃まで居られそうで、滞在時間と、自分の読書速度とを勘案して、どうせ行くならその日のうちに読み切ってしまえる一冊を、と積読の山を眺め、どれにしようかな、と思案する(いちばん愉しい)。
そうやって手に取られたのが、ジョルジュ・シムノン(伊禮規与美訳)『サン=フォリアン教会の首吊り男』(ハヤカワ・ミステリ文庫)であった。
フヅクエでは何となく文学を、それも海外文学を読みたくなる。店の雰囲気がそうさせるのかもしれない。
雰囲気、といえばシムノンは雰囲気を作るのがめちゃくちゃ巧い。小説の雰囲気。息遣いというか。
天才だな、と読むたび惚れ惚れする。
先に読んだ『メグレと若い女の死』のほうが、無駄のない文章で、切れ味は鋭く好みではあった。簡潔にして明快。
それに比べたら本作は初期のメグレということもあって、ずっと若書きだが、そのぶんエネルギーは迸っている。
この手の事件化されていない事件を追う話は大好物で、妖しげな雰囲気に誘われて街を彷徨うかんじがとても良い。
瀬名秀明の解説(こちらも素晴らしい)にもあるが、パリの地理的な関係に錯誤があるらしく、実在のパリというよりはメグレ的パリ、シムノン的パリといった趣きで、それがまた物語の雰囲気とよくあっている。結果オーライ。
まあ、物語の中心はリエージュだったりブレーメンだったりするのだけど。
街を活写しているのに実在とはズレている。
森見登美彦『シャーロック・ホームズの凱旋』で、ヴィクトリア朝京都てのが出てきて何じゃそりゃ、とおもいつつ、めちゃいい雰囲気だったのだが、メグレのパリもその感覚に近い。
海外ミステリの古典は、時間と空間のズレに伴う異世界感がある。この異世界へ誘う雰囲気こそ読書の醍醐味といってよく、またフヅクエにはそういう空間と時間が流れている。ガイブンへ誘われるのも、そのあたりの時間的空間的な雰囲気とよく合うから、といえるかもしれない。
以下はあるいはネタバレであるかもしれない。
上にシムノンの若書き、と書いたが、この小説にはある種の若さが描かれている。
それはメグレの失敗であり、真犯人たちの若気の至りであり、また彼らに対するメグレの赦しにも顕れる。
或いは作者は、書くことで自らの過去を葬り去り、且つまたは赦そうとしたのやもしれぬ。
書くことは救いでありまた祈りでもある。
青春はよき思い出としてノスタルジックに描かれることもあるが、少なくとも僕にとっては圧倒的に苦い記憶だ。
思い出したくもないし、まかり間違って思い出してしまえば、消え去りたいほど恥ずかしく、なぜあんなことを、と悔やまれる。ましてやあの頃へ帰りたいなんて露ほどもおもわない。
だから過去を美化する輩は信用していないし、そういうダサい大人がさいきんは多すぎるようにかんじる。
戻ってやり直したいとはあまり思わないが、書くことでやり直すことならできるかもしれない。
やり直す、というよりは、シムノンみたいに赦したり葬ったり、書くことで過去を精算する。小説の役割のひとつ、とでもいおうか。
書かれる動機って、案外そんなところにあるのかもしれない。
さいきんは新書ばかり読んでいて、小説は久しぶりに読んだが、やっぱり小説っていいな、とおもった。
これからは一冊ずつ交互に、或いは小説2、それ以外1、くらいの割合で読んでいくのがいいかもしれない。
僕はやっぱり小説が読みたいのだ。
Amazonで見る👇
